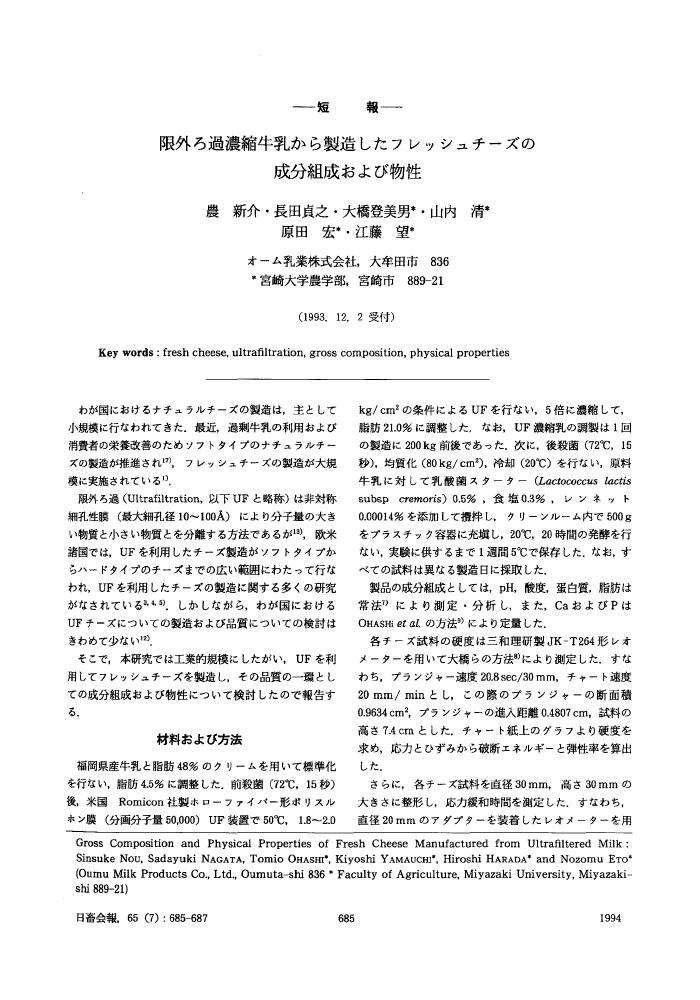1 0 0 0 OA 木曽駒ケ岳における植物調査
- 著者
- 林 武生
- 出版者
- 名古屋文化短期大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09148353)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.9-16, 2009-03-05 (Released:2016-12-20)
1 0 0 0 OA 10Be露出年代法を用いた氷成堆積物の形成年代の測定
- 著者
- 青木 賢人
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.189-198, 2000-06-01 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 4 10
木曽山脈北部の千畳敷カールおよび濃ヶ池カールのカール底に分布するターミナルモレーン上に露出する複数の巨礫に対し,宇宙線生成核種の一つである10Beを用いた露出年代測定法を適用し,モレーン構成礫の生産年代を測定した.AMSによる10Be測定から得られた露出年代値の多くが17~19kaを示し,両モレーンは最終氷期極相期に形成されたことが示された.また,両モレーンは構成礫の風化皮膜の厚さが等しく,モレーン構成礫の風化皮膜の厚さを用いた相対年代法(WRT年代法)による年代推定結果と矛盾がないことが確認された.
1 0 0 0 OA 日本語無意味音節の連想價
- 著者
- 梅本 堯夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.23-28, 1951 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2 7
In this study the writer has determined the association values of 1016 Japanese two syllable nonsense words. These syllables were divided into four groups, and each group was read to two classes of Ss in reversed order. Ss were 404 high school students. After giving sufficient information on the nature of the association performance, the E reads the syllables at the rate of one syllable per five seconds. Ss were instructed to write down any associated word, while attending to the experimenter's reading. When there was no time to write down any, Ss had to mark a circle on the syllable. When they found the word impressive, though not meaningful, Ss had to mark a triangle. The association values ranged from 82% (o-pe) to 3% (pu-nu), the average was 26.02%. The reliability was tested by caliculating the coefficients of correlation between the results of two classes of Ss, performed on the same list, and between boys and girls in the same class. These values were r=0.49 and r=0.76 respectively.
1 0 0 0 OA 形状記憶樹脂
- 著者
- 入江 正浩
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.353-359, 1990-06-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA SiC長繊維の機械的特性に及ぼすBNコーティングの影響
- 著者
- 伊藤 義康 亀田 常治 西田 勝利 梅澤 正信 今井 義一 市川 宏
- 出版者
- 社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (日本セラミックス協会学術論文誌) (ISSN:09145400)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.1236, pp.830-834, 1998-08-01 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 2
Toughness of ceramic-matrix composites can be optimized through coatings the reinforcing fibers. Chemical vapor deposition (CVD) process is a key technology for fiber coatings. The mechanical properties of continuous silicon carbide fibers (Hi-Nicalon) have been studied as a function of the thickness of the pyrolytic boron nitride (P-BN) coating by CVD process. The compressive residual stress at the P-BN coating layer decreases slightly with increasing the coating thickness. It is considered that, with including the residual stress effect, cracking of the P-BN coating layer occurs first in a monotonic tensile fracture test. In addition no degradation of the silicon carbide-fiber in ultimate tensile strength is observed regardless of the P-BN coating thickness.
- 著者
- 土屋 正彦 栗田 繕彰 深谷 晴彦 大河内 正一
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.12, pp.1087-1093, 2013-12-05 (Released:2013-12-28)
- 参考文献数
- 24
水は種々の特異性をもつことが知られており,液体中にもクラスターが存在することが推定されているが,その大きさやサイズ分布は確認されていない.液体イオン化質量分析法は液体表面及び気相中のクラスターを区別して測定できるので,室温(23~25℃),大気圧下での水のクラスター(H2O)nの測定,解析を行った.液体表面には,水の分子数nが30前後までのクラスターが連続的に存在し,その水分子数の平均値(N)は15~17であった.気相中にもクラスターが存在するが,液体表面よりは小さくなり,液面から遠ざかるほどクラスターは分解して小さくなる.これはArガスが逆方向に流れているので,単位空間中の水の絶対量が減るためである.試料流量を増加すると,イオン量は若干減るが相対的に大きなクラスターが少し増える.また,第2質量分析計(Q3)でさらに大きなクラスター(N=27)が観測された.クラスターは水素結合により生成するので,大気圧下では水はクラスターとして蒸発し,水量が多くなれば湯気や霧のような水分子の集合体になり,減れば分解すると考えられる.このクラスターの存在が水の特異性の主な原因の一つといえよう.
1 0 0 0 OA わらび澱粉の糊化特性と糊液のレオロジー的性質
- 著者
- 足立 里美 阿久澤 さゆり 玉木 有子 松森 慎悟 中村 雅英 澤山 茂
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.136, 2004 (Released:2005-04-02)
【目的】 わらび澱粉はわらびの地下茎から抽出され「わらび粉」として流通しており、わらび餅などに珍重されている。しかし、生産量が少なく高価なため、さつまいも澱粉が代替品として使用されている。演者らは、数種類の澱粉の理化学的性質およびレオロジー的性質について報告してきたが、わらび澱粉に関する報告はあまり見られない。そこで本研究では、わらび澱粉の糊化特性と糊液のレオロジー的性質を検討した結果を報告する。【方法】 わらび澱粉は、広八堂(鹿児島県)で製造された粗澱粉を、常法に従って精製して試料澱粉として用いた。対照としてさつまいも澱粉およびくず澱粉を用いた。アミロペクチンの鎖長分布はHPAEC-PAD法 (Dionex社製DX-500) で測定し、DSCにより糊化特性を測定した。また、SEC-MALLS (昭和電工社製:Wyatt Tecnology社製) により重量平均分子量および慣性半径を測定した。糊液の動的粘弾性測定はRheoStress1 (Haake社製) を用いた。【結果】 DSCによる糊化終了温度は、わらび澱粉が70.8℃と最も低く、次いでくず澱粉78.5℃、さつまいも澱粉83.8℃であり、アミロペクチンのDP6-12の短鎖長の割合が多いほど糊化ピーク温度が低い傾向であった。また、糊液を遠心分離後、上澄み中に溶解した糖量を比較すると、わらび>さつまいも>くずの順で糖量が多く、さらに溶液中の重量平均分子量および慣性半径を測定したところ、わらび澱粉糊液は著しく大きかった。動的粘弾性からみたゲル化濃度はわらび澱粉が最も低く、貯蔵弾性率の濃度依存性より3種のゲル構造の違いが示唆された。
1 0 0 0 OA オオムギとイネのケイ酸吸収機構の違いに関する研究
- 著者
- 三谷 奈見季 山地 直樹 馬 建鋒
- 出版者
- 日本植物生理学会
- 雑誌
- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 第51回日本植物生理学会年会要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.0886, 2010 (Released:2010-11-22)
これまでに我々は典型的なケイ酸集積植物であるイネから内向きケイ酸輸送体Lsi1と外向きケイ酸輸送体Lsi2を同定し、これらの輸送体が根からのケイ酸の積極的吸収に重要であることを明らかにしてきた。またオオムギやトウモロコシからもそれらの相同遺伝子を単離し、イネのケイ酸輸送体と同じケイ酸輸送機能を有することがわかった。しかしその一方でオオムギやトウモロコシはイネに比べてケイ酸の吸収量が低く、植物の種類によってケイ酸吸収能力が異なる機構についてはまだ明らかにされていない。そこで本研究ではオオムギおよびイネ由来のケイ酸輸送体の発現量や局在性などを検討した。根での発現量をReal time PCR絶対定量法で比較した結果、Lsi1、Lsi2ともにオオムギよりイネで数倍高く発現していることが明らかになった。次に組織局在性の影響を検討するため、HvLsi1 promoter制御下でOsLsi1 およびHvLsi1をイネのlsi1変異体に導入した形質転換体を作成した。その結果OsLsi1、HvLsi1共に内皮細胞と外皮細胞に極性をもって局在し、イネ本来の輸送体と同じ局在性を示した。これらの形質転換体を用いてケイ酸吸収量を比較した結果、ケイ酸吸収量はOsLsi1を導入した株がHvLsi1を導入した株に比べ高い傾向が見られた。これらの結果はイネ由来の輸送体は強い輸送活性を有していることを示唆している。
- 著者
- Tomomi Saito Junji Okuno Arthur Anker
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- Crustacean Research (ISSN:02873478)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.25-55, 2017 (Released:2017-03-10)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
Two new species of the stenopodid shrimp genus Odontozona Holthuis, 1946 are described and illustrated based on material from several Indo-West Pacific localities, including Japan, Indonesia, Australia and Madagascar. Odontozona arbur sp. nov. is described on the basis of numerous specimens collected in Australia (Queensland, Western Australia), Indonesia, Japan and Madagascar. Odontozona stigmatica sp. nov. is described on the basis of a single specimen from Ishigaki Island, Ryukyu Archipelago, southern Japan. Odontozona arbur sp. nov. and O. stigmatica sp. nov. differ from all other species of the genus by a combination of morphological characters, mainly involving spination on the carapace and third pereopod, as well as sculpture of the pleon. This study increases the total number of species described in the genus Odontozona to 19, eight of them occurring in the Indo-West Pacific. An identification key to all species presently assigned to Odontozona is also presented.
1 0 0 0 OA わかめの消化吸収率とエネルギー利用率に関する研究
- 著者
- 山田 勇樹 三好 保 棚田 成紀 今木 雅英
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.788-794, 1991-08-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4 9
日本人が日常よく摂取している藻類であるわかめについて,日本人を対象とした消化吸収率及びエネルギー利用率に関するデータが殆どないので,これらの値を算出した。対象者は,日本人青年4名である。最初5日間に基礎食,それに続いてわかめ10g:5日間,20g:5日間,40g:5日間とした実験期間中に排泄された糞と尿は全量採取した分析に供した。基礎食期とテスト食期の成分の差によって,消化吸収率及びエネルギー利用率を算出した。しかしながら,各栄養素の消化吸収率にばらつきが大きかったので算出した数値のみ列記する。以下はその結果である。1) 蛋白質の消化吸収率は,70.1±14.0%である。2) 脂質の消化吸収率は,97.5±59.0%である。3) 炭水化物の消化吸収率は,55.8±14.6%である。4) エネルギー吸収率は,60.6±15.9%であった。又正味エネルギー利用率62.4±19.4%であった。
1 0 0 0 OA 初期札幌農学校における地理学教育
- 著者
- 応地 利明
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.410-428, 1982-10-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
One of the characteristics of the history of Japanese geography in the modern period is the fact that the establishment of chairs was rather late compared with other sciences. It was not until 1907 that the chair of geography was founded at Kyoto Imperial University, the first one at any Japanese University. Before 1907, a few geographical books were written by non-specialists of geography and they received a warm welcome. Eminent among them were “Jimbun Chirigaku Kogi (Lecture on Human Geography)” (1888) and “Nihon Fukei Ron (On the Beauties of Natural Scenery of Japan and their Implications)” (1894) by S. Shiga, “Chirigaku Ko (Consideration of Geography, The Earth and Man)” (1894) by K. Uchimura, and “Jinsei Chirigaku (Geography of Life)” (1903) by T. Makiguchi.Shiga and Uchimura were graduates of Sapporo Agricultural College, predecessor of the present Hokkaido University. Makiguchi, who was not a graduate of S.A.C., was a teacher at a normal school in Sapporo at the time he wrote his book, from 1897 to 1901. In addition to the above, I. Nitobe, who was a classmate of Uchimura's at S.A.C., introduced Meitzen's concept of the morphology of rural settlements for the first time in Japan in his book “Nogyo Honron (Main Discourse on Agriculture)” (1898). He was one of the promoters of The Research Society for Study of the Native Land, which exerted a considerable influence on the rise of human geographical studies in the 1910's and 20's.We can safely say that Sapporo is one of the birthplaces of modern Japanese geography. However, Sapporo Agricultural College had no department of geography. Geography was not taught even as a separate subject, though S.A.C. had unique characteristics of a liberal art college compared with the other higher educational institutions at that time.At the Library of Hokkaido University, there are collected various notebooks of the lectures delivered by American professors and recorded by Japanese students. Among them, there is found a notebook under the title of “Lecture on the Geography of Europe by Dr. J.C. Cutter, M.D., Notes by S. Ibuki, 1881”. Dr. Cutter was invited as a professor of physiology, comparative anatomy and English literature. In the introductory part of his lecture on English literature, he taught the geography of Europe, which is considered to be one of the earliest lectures on geography delivered at a higher educational institution in modern Japan.In the present article, the Japanese translation of Prof. Cutter's lecture is made with explanatory remarks of the author. The lecture is composed of two parts, chapters 1 to 8, and 9 to 16. The former part contains physical geography of Europe, with an introduction entitled “Physical geography in relation to social conditions and pursuits” in the first chapter. The second part deals with the appearence and diffusion of races and languages in the Eurasian Continent with special reference to Aryan problems.His lecture is highly characterized by the Euro-centric viewpoint which was prevalent in the 19th century. For example, he taught: “Semitic and Aryan languages were for a long time confined to the continent of Asia in which they occupied only small parts. They are now universally distributed. This group of languages have attained the highest degree of perfection. These types of languages are spoken by majority of the white type of the human species. They were introduced into Europe from India by the Aryan invasions or infiltration. From the Aryan mother tongue have sprung all the European languages. They are now used by peoples occupying about 3/15th of the earth's surface. It is the people using these languages who have been the leaders in civilization in historic periods”. This quoted opinion is typical of Europeans in the mid-19th century. It was accepted by some students at S.A.C., and rejected by others.
1 0 0 0 OA 限外ろ過濃縮牛乳から製造したフレッシュチーズの成分組成および物性
- 著者
- 農 新介 長田 貞之 大橋 登美男 山内 清 原田 宏 江藤 望
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.685-687, 1994-07-25 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 湯田温泉ニ就テ
- 著者
- 北村 大藏 添田 漸
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候学会雑誌 (ISSN:03694240)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.257-264, 1942-04-25 (Released:2010-08-06)
1 0 0 0 OA 高温超伝導磁気マルチバイブレータによる位相記憶論理素子
- 著者
- 内山 剛 牧野 正義 毛利 佳年雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本磁気学会
- 雑誌
- 日本応用磁気学会誌 (ISSN:02850192)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.556-559, 1992-06-01 (Released:2013-01-11)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 2
A transistor logic memory module based on the Royer oscillator type magnetic multivibrator is presented, in which a HTcSC thin disk core having six coils tightly set around it is connected with two switching transistors. The oscillation of this module is initiated by applying a pulse current to a coil and the phase of oscillation is controlled by the sign of the trigger pulse. That is, this module is a phase memory type logic device such as Parametron. Moreover, oscillation is terminated by applying a pulse current to a small transistor which shorts another coil of the HTcSC. We can assign two oscillating states with different phases to the numerical values ±1 and the non-oscillating state to 0. This logic is decided by a majority of multi-input, so that this module has applications in the field of neural network system.
1 0 0 0 OA イネーブリング概念を用いた管理会計研究の動向
- 著者
- 西居 豪 近藤 隆史
- 出版者
- 公益財団法人 メルコ学術振興財団
- 雑誌
- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.47-60, 2015 (Released:2015-11-27)
- 参考文献数
- 39
本稿はイネーブリング(enabling)概念を分析枠組みに適用した管理会計領域の経験的研究の動向を紹介したものである。具体的には,同概念を用いて解明の試みられている現象と得られている知見を整理するとともに,今後の検討課題を試論的にまとめている。
1 0 0 0 OA ポリウォーター
- 著者
- 水口 純 相沢 益男
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.231-235, 1970-03-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
ソビエトのDeryaginらは低圧水蒸気を毛細管中に凝結させて得た水は,通常の水とは著しく物性が異なる,いわゆる“anomalous water” であることを報告していた.その後二三の追試が行なわれていたが,最近アメリカ・メリーランド大学のLippincottらは“anomalous water” は水のポリマーであることをIRおよびラマンスペクトル測定によって見出し,この水を“polywater”と名づけた.“polywater” はF-H-F水素結合と同程度のきわめて強い水素結合によって水分子どうしが結合していて,密度は約1.4g/cm3であるという.“polywater” の存在が事実であるとすれば,水に対する概念の根本的変革が必要であり,その影響は生物化学,地球化学のみならず高分子合成など数多くの分野に及ぶものと考えられる.著者らは生体における水と生体機能との関連性を究明しているが, “polywater” の存在はこの研究に対してもきわめて多くの示唆を与えるものである.
1 0 0 0 OA 放射光が拓く新しい水の分光
- 著者
- 原田 慈久
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.8, pp.8_62-8_66, 2010-08-01 (Released:2010-09-17)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA テキストマイニングによる原価企画の構成要素に関する検討
- 著者
- 趙 婷婷
- 出版者
- 日本原価計算研究学会
- 雑誌
- 原価計算研究 (ISSN:13496530)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.133-143, 2016 (Released:2017-04-14)
原価企画の定義や体系は,論者によって微妙に異なり,多様に存在している。本論文では,原価企画の定義に着目して,多様かつ膨大な先行研究を,網羅的かつ客観的に分析する。原価企画に関する大量な文献から原価企画の定義を取り出し,それらに対して,テキストマイニングという手法を適用することで,原価企画の「基本モデル」を明らかにする。
1 0 0 0 OA エイコ&コマのDelicious Movement Workshopの検討 2
- 著者
- 相原 朋枝 酒向 治子
- 出版者
- 日本体育・スポーツ哲学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.103-116, 2016 (Released:2017-04-10)
- 参考文献数
- 26
A dance unit called “Eiko&Koma” by Eiko Otake and Takashi Otake has been an extremely highly-admired artist in American dance community for more than 40 years. Eiko&Koma has been creating their own workshop style called “Delicious Movement Workshop” (DMW). By using the qualitative research approach (GTA), this paper aims to grasp the basic characteristics of Eiko’s instructional words toward the students in the two basic programs (called “scores”) of DMW, “Sleeping” and “Sleeping Together”, which will intensify and deepen the understanding of DMW structures, and also provides the knowledge related to the instructional words which the physical expression educators can refer to. In the result, through the case studies, we extracted 4 core categories such as [Time(successive)], [Relationship between Oneself and Others], [Image of Nature ], [Consciousness toward Body] and 8 concepts and we linked them into a theoretical mode (Eiko’s words’structure model). From these results, it became apparent that Eiko’s “instructional words” functions as an important tool to induce the creative and expressive movements from the students. The words dissolves the students’ daily senses toward the body and lead them to the unusual, non-daily life world.
1 0 0 0 OA LC/MSによるフグ毒テトロドトキシンの分析
- 著者
- 堀江 正一 石井 里枝 小林 進 中澤 裕之
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.234-238, 2002-08-25 (Released:2009-04-30)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3 4
LC/MSによるフグ毒テトロドトキシン(TTX)の分析法を検討した.TTXは高極性物質であることから,イオン化にはエレクトロスプレーイオン化法(ESI)を採用し,ポジティブモードとした.LC条件は,カラムにTSKgel ODS 80Ts (25 cm×2 mm i.d.),移動相には5 mmol/L HFBA-メタノール(99 : 1)を用い,流速は毎分0.2 mLとした.検出には,プロトン化分子[M+H]+を用い,結果をより確かなものとするために水脱離イオン(m/z 302.1)も同時にモニターした.本法の検出限界は1 μg/gであり,無毒とされる10 MU/g (2.2 μg/g)レベルの分析が可能であった.