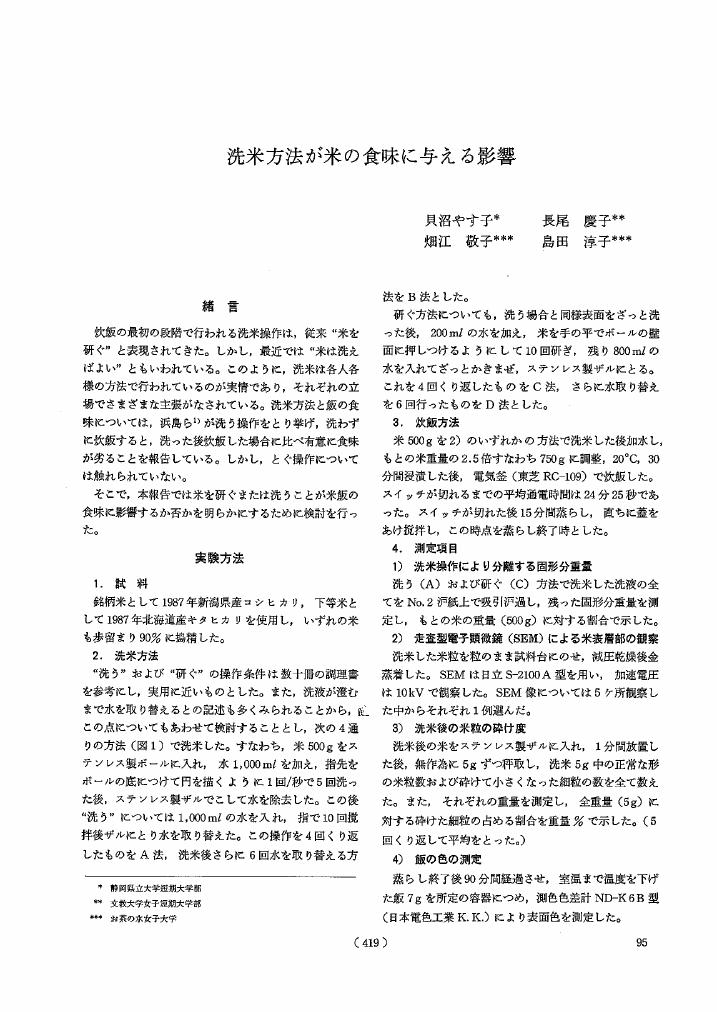- 著者
- 藤田 久雄 安藤 友継 藤岡 博文 島田 昭博
- 出版者
- 香川県環境保健研究センター
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.60-66, 2009 (Released:2013-08-20)
UASB槽(300L)と接触バッキ槽(200L)を組合せた実用規模の排水処理実験装置を試作し,ゆで汁を一日200~300玉製造しているうどん店から週5日全量採取して,7カ月間処理実験を行った。その結果,処理水のpH,BOD,COD,SSは,装置立ち上げ及びトラブル時を除いて,全て排水基準の一律基準以下であった。BODの平均値は容積負荷量が3.1g/L/日,原水濃度が4,000mg/L,UASB処理水濃度が150mg/L,接触バッキ槽処理水濃度が19mg/L,除去率が95%以上であった。BOD負荷量に対する汚泥発生量は5.2%,平均メタン生成量は370L/日,月平均電力使用量は289kWh/月であった。うどんゆで汁排水は,UASBを用いた小型高速メタン発酵装置で処理できることが確認できた。実用化には低コスト化・メンテナンスフリー化技術等が課題となる。
2 0 0 0 OA 大建中湯による周術期管理のサポート
- 著者
- 西 正暁 島田 光生 森根 裕二 吉川 幸造 徳永 卓哉 中尾 寿宏 柏原 秀也 高須 千絵 良元 俊昭 和田 佑馬
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.59-61, 2022-04-15 (Released:2022-05-15)
- 参考文献数
- 10
近年では漢方の分子生物学的な作用機序の解明が進み, 臨床においても質の高いランダム化比較試験により漢方の有用性が明らかになってきた. 現在では大建中湯を含む多くの漢方製剤が広く臨床の現場で用いられている. 大建中湯は乾姜, 人参, 山椒の3つの生薬に膠飴を加えた漢方で, 外科領域においては癒着性イレウスや麻痺性イレウス, 過敏性腸症候群, クローン病などを適応とし, 消化管運動促進作用, 腸管血流増加作用,抗炎症作用などが報告されている. 近年では, 食道・胃・大腸・肝臓・膵臓・肝移植外科それぞれの領域でランダム化試験が実施され, 大建中湯の周術期管理における有効性が証明されている. また分子生物学的なメカニズムについても解明がすすみ, 現在, 大建中湯は消化管外科・肝胆膵外科の分野を問わず消化器外科全般における周術期管理のkey drugとして位置付けられている. 本稿では消化器外科領域における大建中湯による周術期管理のサポートについて概説する.
2 0 0 0 OA 焼酎白麹の各種酵素の諸性質について
- 著者
- 岩野 君夫 三上 重明 福田 清治 椎木 敏 島田 豊明
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.7, pp.490-494, 1986-07-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 19 20
焼酎白麹の各種酵素の諸性質が清酒麹および泡盛麹と較べてどのような差異があるか調べたところ次の結果を得た。1. 焼酎白麹および泡盛麹のα-amylaseは焼酎醪のpH範囲であるpH3~4において相対活性が80%以上と高く, かつpH安定性もこのpH範囲において残存活性が90%以上と高いことが認められた。2. α-Amylaseの熱安定性は焼酎白麹が60℃, 泡盛麹が50QC, 清酒麹が40QCで, 最適反応温度は焼酎白麹が70℃, 泡盛麹が60℃, 清酒麹が50℃ で, 焼酎白麹のα-amylaseの耐熱性が最も高かった。3. 3種類の麹のglucoamylaseは焼酎醪のpH範囲3~4においては相対活性やpH安定性がほぼ同一で高い値を示した。4. Glucoamylaseの熱安定性は焼酌白麹は60℃, 泡盛麹と清酒麹が50℃ であり, 最適反応温度は焼酎白麹が70℃, 泡盛麹と清酒麹は60℃で, 焼酎白麹のGlucoamylaseの耐熱性が高いことが知られた。5. 蛋白分解酵素のacidprotease, acidcarboxypeptidaseは3種類は麹ともほとんど同一の諸性質を示した。6. 3種類の麹の諸酵素の最適反応pH, pH安定性および熱安定性の結果から, 実験方法に示した各種酵素活性の測定条件で, 3種類の麹の酵素活性が測定できることが裏づけられた。最後に臨み, 本研究の遂行に当り御指導を腸わりました当試験所中村欽一所長に深謝致します。
- 著者
- 島田 瑞穂 土井 寛大 川端 寛樹 山内 健生 安藤 秀二 小林 由美江 廣瀬 芳江 周藤 史憲 藤原 由佳子 齊藤 美穂 菊池 広子 小松本 悟 室久 俊光 島野 智之
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.53-56, 2023-06-25 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 18
During the 3-year period (2020–2022), 49 cases of tick bites were presented to the Japanese Red Cross Ashikaga Hospital in Tochigi Prefecture, Japan. More than 60% of all tick bites between March and September occurred within two months (May and June). Amblyomma testudinarium was responsible for 40 cases among all the tick bite cases. Specifically, 41 individuals of this species (39 nymphs/2 adult females) were linked (The point estimate was 0.79 with a 95% confidence interval of 0.67–1.00). There were 38 cases of tick bites in Ashikaga City, and 23 of which occurred in the vicinity of the patients’ houses (gardens and fields). Suspected cases of Tick-associated rash illness (TARI) were first recorded in the Japanese Red Cross Ashikaga Hospital in May 2020, in a total of five cases ( i.e., the patients were aged 50 years or older). TARI is indicative of repeated tick bites, which points to the permanent settlement of the A. testudinarium in and around Ashikaga City. Therefore, we believe that greater efforts should be implemented towards the detection of tick-associated infections in this area, including Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus for which A. testudinarium is considered as a major vector.
2 0 0 0 OA On Two Point Taylor Expansion
2 0 0 0 OA <臨床に有用な基礎知識>痛みと開口障害を伴わない顎関節(雑)音に対する患者説明
- 著者
- 島田 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 雑誌
- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.3-8, 2021-04-20 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 23
顎関節(雑)音は,顎関節症の主要症候の一つである。しかし症状が,顎関節(雑)音のみの場合には,日常生活に支障がでることはほとんどなく,自然経過は良好な場合が多いとされ,治療による顎関節(雑)音の改善,消失は困難であり,再発することも少なくない。痛みや開口障害を伴わない顎関節(雑)音を生ずる病態は,主に顎関節円板障害と変形性顎関節症であり,そのほとんどに関節円板転位が関与している。しかし顎関節(雑)音の病態はさまざまであるため,診察・検査により病態を診断する必要がある。「痛みと開口障害を伴わない顎関節(雑)音」の多くは自然経過が良好である。治療を行ってもその効果は不確実で,副作用として咬合が変化する可能性があり,咬合治療や矯正が必要となる場合がある。しかし症状が悪化しないためには,病態に対する理解とセルフケアが必要である。歯科医師は診察・検査で得られた患者の病態を基に経過観察を含めた治療に対する合理的な選択肢とそれらの利益やリスクに関するエビデンス,さらには患者の価値観を共有し,患者にとって最善の治療方針を患者と一緒に決定することを目的とした説明を行うことが求められる。
2 0 0 0 OA コロッケの破裂の機構
- 著者
- 長尾 慶子 加藤 由美子 畑江 敬子 島田 淳子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.677-682, 1988-07-05 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
コロッケの破裂の機購および破裂を防ぐ揚げ条件を設定することを目的とし, 乾燥マッシュポテトを用いて加水量を変えたコロッケを調製, 実験し以下の結果を得た.1) コロッケの破裂は水分量および揚げ温度, 依存し, 水分が少ないほど, また揚げ温度が高いほど破裂しなかった.2) 油温200℃で揚げたときの, コロッケ破裂時の表層部 (1 mm 内側) 温度, 2 mm, 5 mm 内側および中心部温度は 118, 70, 40 および 22 ℃ であり中心部はほとんど変化がなかった.3) 破裂はコロッケの外皮付近で起きており, いずれの試料も表層部温度は100℃ 以上で破裂した.4) コロッケ外皮の破断強度は, 高水分試料のほうが小さく, また油温が高いほうが大となる傾向にあった.5) 破裂しやすい高水分試料の表層部を, 破裂の起きにくい低水分試料でおきかえると破裂は防止できた.6) 破裂は表層部の蒸気圧と皮の強度が関与している.
2 0 0 0 OA 伝統的薬用芍薬の資源探査:大和薬種のルーツと篤農技術解析
- 著者
- 髙橋 京子 髙浦(島田) 佳代子 後藤 一寿
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.422-433, 2022 (Released:2023-07-01)
- 参考文献数
- 72
- 被引用文献数
- 1
本研究は,日本古来の篤農技術や品種・系統および形態の史的検証と現況調査に基づき,医薬品原料品質の担保と採算性が見込める暗黙知発掘を目的とした。特に,中山間地域活性化を図る候補として期待されるシャクヤク(Paeonia lactiflora Pallas)について,江戸享保期,徳川吉宗が展開した薬草政策以降,国内で育種された大和芍薬のルーツとして,実地臨床で良品とされる「梵天(白花重弁)」と異なる複数の系統基原種を確認した。その中に,幕府保護下の私設薬園(現森野旧薬園)を創始した森野藤助賽郭真写「松山本草」に描かれた赤花単弁の品種も存在した。森野家所蔵文書群から,大和の薬種特産性を示す初出史料を発見し,国内生産地動向や品質系統の管理・栽培技術を考察した。近現代の薬用栽培法では摘蕾・摘花が散見するが,地域文化および薬種専門家の現地取材から,観賞や切り花利用など営利性向上の可能性を示唆した。
2 0 0 0 OA 津波に対する水門・陸閘の有効活用とその効果に関する考察
- 著者
- 杉本 卓司 村上 仁士 島田 富美男 上月 康則 倉田 健悟 志方 建仁
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.306-310, 2002-10-10 (Released:2010-03-17)
- 参考文献数
- 7
2050年までに80%の確率で起こるとされるM8.4級の南海地震津波に対し, 防災施設の新設は困難との立場から, 既存の水門や陸閘の津波浸水防止効果を高知県のU町を対象とした津波数値計算により検討した. その結果, これらの門扉が津波到達までに閉門できれば浸水範囲の低減や津波浸水開始時間を遅らせる効果があることが証明された. 一方, 多くの集落で門扉操作者の安全が確保できない場合があり, 操作を含めた門扉の管理・運用方法の改善が必要との結果が得られ, さらにこれらの門扉を有効に活用した具体的な防災対策について提示した.
2 0 0 0 マグネシウムの鎮痛効果に関する研究
マグネシウムは多くの酵素活性や細胞内伝達系において重要な役割を担う生体内で4番目に多い陽イオンである。本研究の目的は、マグネシウムの鎮痛効果とその機序を明らかにすることである。1.種々の予定手術患者を対象に、周術期の血清イオン化マグネシウム濃度を測定し、術式、手術時間、輸液量、出血量、尿量との関連を検討した。血清イオン化マグネシウム濃度は手術時間の経過とともに減少し、手術終了後徐々に回復した。血清イオン化マグネシウム濃度の減少は、体表手術や開頭術に比べて開腹術で大きかった。また、長時間手術、輸液・出血・尿量の多い手術で減少の程度が大きかった。2.帝王切開術後患者と婦人科手術患者を対象に、マグネシウム投与の有無による術後鎮痛薬の必要量の差を検討した。いずれの群においてもマグネシウム投与患者は、非投与患者に比べて、術後鎮痛薬の必要量が少なかった。3.雄性Wistar系ラットを用い、Neurometer CPT/Cによる疼痛閾値に及ぼすマグネシウムの影響を検討した。C線維を介する疼痛閾値はモルヒネ2mg/kgの腹腔内投与によって上昇したが、マグネシウム2mM/kg及び4nM/kg単独投与では変化せず、モルヒネとマグネシウムの相互作用も認められなかった。4.雄性Wistar系ラットを用い、ヒスタミン刺激に腰髄後角のc-fos発現を指標として、マグネシウムの鎮痛機構を検討した。c-fos陽性細胞は、ヒスタミン刺激と同側の脊髄後角側部に多く、I、IIそしてX層に主に観察された。ヒスタミン刺激側脊髄でのc-fos陽性細胞数は、マグネシウム150及び300mg/kg投与によって減少した。以上の結果から、周術期にマグネシウムを投与することは臨床的に鎮痛効果があり、この鎮痛効果は脊髄後角の二次求心性神経の反応抑制によることが示唆された。
2 0 0 0 OA 「統計的に有意」で満足していませんか?― 統計的帰無仮説検定の問題と対応 ―
- 著者
- 島田 英昭 井関 龍太
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.82-90, 2019-06-15 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 高齢者を対象とした地域保健活動におけるTimed Up & Go Testの有用性
- 著者
- 島田 裕之 古名 丈人 大渕 修一 杉浦 美穂 吉田 英世 金 憲経 吉田 祐子 西澤 哲 鈴木 隆雄
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.105-111, 2006-06-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 50
本研究では,地域在住の高齢者を対象としてTimed Up & Go Testを実施し,性差と加齢変化を調べた。また,転倒,活動性,健康感との関係を調べ,高齢者の地域保健活動におけるTimed Up & Go Testの有用性を検討した。対象は地域在住高齢者959名であり,平均年齢74.8歳(65-95歳),男性396名,女性563名であった。検査および調査項目は,身体機能検査としてTimed Up & Go Test,歩行速度,握力,膝伸展筋力,Functional Reach Testを実施した。質問紙調査は過去1年間の転倒状況,外出頻度,運動習慣,趣味,社会活動,主観的な健康感を聴取した。Timed Up & Go Testを5歳の年齢階級別に男女差を調べた結果,すべての年代において男性が有意に速い値を示した。加齢変化をみると男女とも70歳末満と以上の各年代に有意差を認めた。男性においては他の年齢階級間に有意差は認められなかった。一方,女性では70-74歳と80-84歳,85歳以上,および75-79歳と80-84歳の間,80-84歳と85歳以上の年代間において有意差を認めた。転倒,活動性,健康感との関係では,転倒状況,外出頻度,運動習慣とTimed Up & Go Testの有意な関係が認められた。以上の結果から,高齢者におけるTimed up & Go Testは性差と加齢による低下が明らかとなった。また,転倒,外出頻度,運動習慣と密接な関係が示され,地域保健活動の評価指標としての有用性が確認された。
2 0 0 0 OA 洗米方法が米の食味に与える影響
- 著者
- 貝沼 やす子 長尾 慶子 畑江 敬子 島田 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.419-423, 1990-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 11
2 0 0 0 OA ホエイパウダーおよび各種オリゴ糖がin vitroにおいて腸内発酵に与える影響について
- 著者
- 門 利恵 椎原 啓太 島田 謙一郎 韓 圭鎬 福島 道広 長田 正宏
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.5-17, 2018-03-31 (Released:2018-04-16)
- 参考文献数
- 35
プレバイオティクス効果を有する難消化性オリゴ糖(ガラクトオリゴ糖,ラフィノース,フラクトオリゴ糖)と,チーズホエイパウダーの発酵特性について,発酵培養装置(ジャーファーメンター)を使用し,それぞれ比較検討を行った。難消化性オリゴ糖とチーズホエイパウダーは,善玉菌および有益物質の増加を促進し,悪玉菌および有害物質の生成を抑制することが示唆された。各種オリゴ糖による発酵特性は,全てにおいて類似した傾向が認められ,その効果は難消化性の炭素源によるものと考えられる。また,チーズホエイパウダーに関しても腸内環境に良好な影響をもたらすことが確認された。これらの結果は,副産物とされるチーズホエイについて機能性食品としての新たな有効性を見出す可能性が期待できる。様々な生活習慣病を日常の食生活で予防することの重要性が広く知られてきているが,今後in vivo試験での検討が必要と思われる。
2 0 0 0 OA 小雀浄水場における有機フッ素化合物による汚染事例及び対応報告
- 著者
- 千澤 馨平 水野 信輝 渡辺 太郎 関口 恵美 原田 未来 下田 穣史 島田 大地 齋藤 智幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本水道協会
- 雑誌
- 全国会議(水道研究発表会)講演集 令和3年度全国会議(水道研究発表会)講演集 (ISSN:24361496)
- 巻号頁・発行日
- pp.668-669, 2021 (Released:2022-12-31)
2 0 0 0 ヒトの「生理的早産」
アドルフ・ポルトマン(Adolf Portmann)というスイス人の生物学者がいました。先生は多くの生物の妊娠・分娩に関する研究からヒトを含めて,生物における各種族の位置づけなどを考案されて,現代の生物学とドイツの哲学とを結びつけた学者といわれています。牛や馬の赤ちゃんは生まれてくると,すぐに立ち上がり歩くことができます。これに比べてヒトの赤ちゃん(新生児)は,歩けるようになるには1年近くもかかります。また,鳥の赤ちゃんは卵の殻を破って出てきますが,生まれてすぐにお母さんから固形の食べものを口うつしでもらって,それを食べて,しかも消化吸収することができます。ヒトの赤ちゃん(新生児)は生まれてすぐに固形物を食べて消化する能力はありません。 こうしてヒトの赤ちゃん(胎児,新生児)と他の動物の赤ちゃんを比較してみると,ヒトの赤ちゃんは生まれて来たときには大変に未熟だといえるのではないでしょうか。ヒトは生物の中でもっとも進化した種族です。したがって頭部(脳)の占める体積が大きく,ヒトの赤ちゃんは頭でっかちです。本質的にヒトの胎児は未熟なので,できるだけ子宮の中で発育させておこうということから頭部は脳の発育のために産道を通過できるギリギリの大きさまで発育して大きくなってから生まれてきます。これに対して,母体の産道,つまり骨盤の大きさはどうでしょう。猿や類人猿の時代の4つ足の生活はもうなくなり,立位の生活を送るようになると,体位のために母体の骨盤は圧迫を受け,4つ足時代より狭く変形されてきました。その内腔が狭くなった産道に大きくなってしまった脳を入れた胎児の頭部が通るのはとても大変で,ギリギリだというのです。ですから,ヒトの分娩は他の動物からみると赤ちゃんは未熟で早産のように受けとめられるのですが,実は発達した脳(頭部)と骨盤の変形によって生物のなかではもっとも難産になっていると考えられます。だからヒトの分娩はその途中で低酸素症(胎児仮死)にもなりやすいし,分娩停止や遷延分娩にもなりやすいといえます。この事実を私たち,産科周産期医療従事者はどう考えたらよいのでしょうか。ヒトのお産というのは,ただ放っておけば生まれてくるとか,元気に「オギャー」と泣いて生まれてくるのが100%当たり前とかいった安易なものではないということを再認識しなければなりません。私たちは全生物のなかでもっとも難しいお産を取り扱い,管理する専門職なのです。このことを自覚することはもとより,世間一般の方々に,「お産て難しいことがいっぱいあるんですよ」と教育しなければならないでしょう。なぜなら,産科周産期医療は大いに発展,進歩しました。しかし,それは胎児情報や診断学,治療に関することで,人類が始まって以来,胎児は産道を通って出てくるという分娩現象については全然変わっていないのです。帝王切開術が上昇しているということも少しはうなずけます。時代とともに,文明の進歩とともに,ヒトのお産は「生理的早産」でありながら難産傾向になることは予測できます。たとえば,硬膜外麻酔を応用した分娩などは分娩を楽に終わらせる一方法として脚光を浴びています。ヒトのお産は正期産といえど「生理的早産」であることを忘れないで,今日からまた取り組んで下さい。
2 0 0 0 OA 安全な医薬品の開発及び適正使用に関する性差医療研究
- 著者
- 佐藤 洋美 島田 万里江 佐藤 友美 シディグ サーナ 関根 祐子 山浦 克典 上野 光一
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第40回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.150526, 2013 (Released:2013-08-14)
【目的】医薬品の中には、対象疾病の受療率に男女差があり、男女のどちらかに偏って使用されるものが少なからず存在する。また、薬物動態や薬効・副作用の発現に性差の存在する薬物も多々存在することが報告されている。そこで、安全な医薬品の開発及び個々人に対する医薬品の適正使用に還元されることを目的として、本検討においては、申請資料概要が提出済みの既承認医薬品の中で、女性が組み込まれている臨床試験を実施したものがどの程度存在するかを調査し、解析を行った。【方法】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA)のホームページから検索を行った。2001年4月から2011年12月に承認審査された医薬品のうち、申請資料概要が入手可能な医薬品を対象に調査し、臨床試験における各相の女性の組み込み等について解析を行った。【結果】承認審査された医薬品のうち、国内または海外における第Ⅰ相~Ⅲ相試験及び臨床薬理試験のいずれかには女性は非常に高い割合で組み込まれていた。しかし、第Ⅰ相試験や臨床薬理試験に関しては、女性の組み込み率が低かった。女性を組み込んでいても男女別のデータを区別している医薬品はさらに少なかった。一方、女性が組み込まれ、データを区別している医薬品の添付文書において、性差に関する記述が記載されている医薬品は極めて少なかった。【考察】第Ⅰ相試験や臨床薬理試験の女性の組み込み率が低いことより、薬物動態や薬力学的作用における性差の概念が浸透していないことが考えられた。また、男女のデータを区別している医薬品において、性差に臨床的意義がない場合は添付文書にその旨を記載していないことが多いが、臨床効果に性差がなかったことを記載することは医療現場における安全な医薬品適正使用に貢献すると思われる。
2 0 0 0 OA 大正末期から昭和初期におけるじゃがいもの調理(5)炒め物 調理科学の視点から
- 著者
- 関本 美貴 島田 淳子 Sekimoto Miki Shimada Atsuko
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.863, pp.22-23, 2012-09-01
2 0 0 0 OA 遺伝子医療の倫理的課題
- 著者
- 島田 隆
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.430-434, 2001 (Released:2001-12-28)
- 著者
- 島田 美小妃
- 雑誌
- 流経法學 = Journal of the Faculty of Law, Ryutsu Keizai University
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.37-93, 2020-02-10