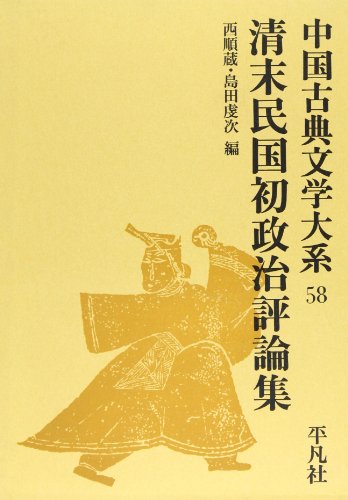3 0 0 0 OA 第一(国立)銀行の朝鮮進出と渋沢栄一
- 著者
- 島田昌和
- 出版者
- 文京学院大学
- 雑誌
- 文京女子大学経営論集
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, 1999
3 0 0 0 OA 誰のための予防理学療法なのか
- 著者
- 島田 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本予防理学療法学会
- 雑誌
- 日本予防理学療法学会雑誌 (ISSN:24369950)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1, 2022 (Released:2022-03-22)
3 0 0 0 IR ディズニーのフェミニズム プリンセスの女性学と男性学
- 著者
- 島田 英子
- 出版者
- 立命館大学映像学会
- 雑誌
- 立命館映像学 (ISSN:18829074)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.93-107, 2022
- 著者
- 金堀 哲也 山田 幸雄 會田 宏 島田 一志 川村 卓
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.133-147, 2014 (Released:2014-06-13)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 6 2
The purpose of this study was to clarify the viewpoint of a well-experienced baseball coach when evaluating batting skills using kinematics indices. Method: First, three baseball coaches evaluated sixteen baseball players in their own teams. The players were divided subjectively into a first superior (FG) group and a second superior (SG) group according to batting ability. Next, the hitting motion of all sixteen players was captured using a VICON system (9 cameras, 250 Hz). We measured the speed of the batted and pitched ball, or the timing of release by the pitcher, using three synchronized high-speed cameras (250 Hz). From these kinematics data, we calculated several kinematics indices for each batter, focusing especially on the indices for motion of the lower extremities and trunk. In contrast, a well-experienced expert coach who had never met these players evaluated the hitting motion of each player using only motion films without the above kinematics indices, and similarly divided them into FG and SG. The evaluation of fourteen players agreed between the team coaches and the expert coach. The FG and the SG each comprised seven players. We analyzed these fourteen players using the kinematics indices, and clarified objectively the differences in hitting motion between the two groups. Results & Conclusions: The speed of swing, batted ball speed and physical index were approximately the same in the two groups. However, players in the FG group showed a significantly longer distance of center of gravity migration in step than those in the SG group. This might have been attributable to the hip abduction movement on the pivot side on the basis of kinematics indices (p<0.05). Moreover, players in the FG group took more time in step, and swung in a shorter time after landing on the stepped foot, relative to the players in the SG group (p<0.05). These results suggest that the well-experienced expert coaches paid particular attention to the above hitting motion rather than the speed of swing, batted ball speed and physical index as coaching points.
3 0 0 0 清末民国初政治評論集
3 0 0 0 IR 英ソ関係をどうするのか : ミュンヒェン会議以降のイギリスの対ソ外交政策
- 著者
- 島田 顕
- 出版者
- 法政大学小金井論集編集委員会
- 雑誌
- 法政大学小金井論集
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.95-103, 2011-12
3 0 0 0 OA 5-303形マイクロテレビの設計概要
- 著者
- 安田 順一 島田 聰
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.7, pp.387-400, 1963-07-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 2
全トランジスタ化で初めて可能な超小形受像機であり, 従来の据置式大形受像機を中心とした生活様式を変える力をもった商品として, SONY. 5-303形マイクロテンビが企画され市場化されたわけであるが, そのためには超小形受像機ないしトランジスタテレビに特有の新たな技術的問題点をいろいろ解決する必要があった.本稿ではそれらを重点的に論じている.
3 0 0 0 OA 教師のレジリエンス形成を促す研修プログラムの開発と試行
- 著者
- 深見 俊崇 木原 俊行 小柳 和喜雄 島田 希
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Suppl., pp.177-180, 2020-02-20 (Released:2020-03-23)
- 参考文献数
- 8
本研究では,レジリエンスの形成に関して先駆的に取り組まれているオーストラリアのBRiTEフレームワークを援用した中堅・ベテラン教師向け研修プログラムを構想・試行した.受講者のコメントからは,180分間という限られた時間にも関わらず,BRiTE の5つの視点を学ぶことで自身が取り組めていない点や自覚していなかった点に気づくことができ,レジリエンスを発揮するための実践につなげる可能性が認められた.
3 0 0 0 OA 高等専門学校の現状と課題:苫小牧高専を事例とする調査報告
3 0 0 0 OA 宮沢賢治の作品に描かれたカラマツ林の景観 : 北原白秋の詩との比較
- 著者
- 島田 直明 米地 文夫
- 出版者
- 岩手県立大学
- 雑誌
- 総合政策 (ISSN:13446347)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.119-131, 2006-03-01
カラマツは宮沢賢治作品への登場頻度の高い樹木である。そのカラマツ林やその周辺の景観について賢治の描写を分析するとともに、同時代の代表的詩人北原白秋の作品と比較検討を行った。本論文では特に心象スケッチ『春と修羅』のなかの作品群に描かれたカラマツに着目した。それらの多くは岩手山麓の牧草地や放牧地の防風林としてのカラマツ林であった。賢治の作品から1920年代の岩手山麓は、草地や草地から遷移が進んだ森林、カシワ林などさまざまな植生タイプがみられ、また草地を囲むようにカラマツ林が列状に連なる景観であったと読み取れた。旧版地形図や岩手県統計書などの資料から判読した当時の景観も同様であり、賢治が『春と修羅』の作品群において正確に景観を描写していたことが検証できた。一方、北原白秋の有名な詩「落葉松」は、カラマツ林の中に歩み入り、また歩み去る己れを抒情的に詠いあげた。この詩人の絶唱ともいうべき作品ではあるが、カラマツ林の景観そのものについては全く描写していない。これに対して、賢治はカラマツ林の景観をナチュラリストの眼で観察し、心象スケッチという形で具体的に描写・記録した。彼はのち,カラマツを用いて景観を造る「装景」をも考えていたのであった。
- 著者
- 島田 昇 丸岡 紀子 佐藤 京子
- 出版者
- 日本ヘルスサポート学会
- 雑誌
- 日本ヘルスサポート学会年報 (ISSN:21882924)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.45-53, 2016 (Released:2016-09-05)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA スピリチュアリティの概念の構造に関する研究 —「スピリチュアリティの覚醒」の概念分析—
- 著者
- 中谷 啓子 島田 凉子 大東 俊一
- 出版者
- 日本心身健康科学会
- 雑誌
- 心身健康科学 (ISSN:18826881)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.37-47, 2013-02-10 (Released:2013-02-18)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 2
本研究は,日本におけるスピリチュアリティの概念を明らかにするための先行的研究である.スピリチュアリティが人間の内面に本来備わる目に見えないものという前提に立ち,「スピリチュアリティの覚醒」,すなわち,スピリチュアリティが顕在化する契機に着目し,その概念を明らかにすることを目的とする.研究デザインは,文献研究である.国内の学術論文を網羅するため3種類の検索データベースを用いた.キーワードを「スピリチュアリティ」「スピリチュアル」「覚醒」「危機」「クライシス」「概念」「グリーフ」「悲嘆」「日本人」に設定し文献を抽出し,その記述内容を分析フォームに整理しデータ化した.このうち,「スピリチュアリティの覚醒」の概念が抽出されたデータを,Walker & Avantの概念分析の手法を用い分析した.その結果,「スピリチュアリティの覚醒」の先行要件12種類,属性5種類,帰結9種類が明らかになった.また,考察の結果,スピリチュアリティの覚醒は,快・不快といった様々な出来事を契機に発生し,その結果として,自己の意識を拡張したり心身の回復,さらには大いなるものへの感謝と慈しみといった自己の成長をもたらすことが示唆された.さらに,このような機会は,生涯を通して,誰にでも起こり得ること,内的自己と超越的存在との関係といった2つの方向性のある探求であることを示唆した.さらに,人間は,「スピリチュアリティの覚醒」によって,生涯にわたり成長や変化の機会を得ることができ,こころとからだの相関の中でQOLを高めていくことが可能であることが示唆された.
3 0 0 0 OA 救急外来システムの時間記録を用いた救急外来混雑状況・待ち時間の定量化
- 著者
- 園生 智弘 白川 透 藤森 遼 島田 敦 奈良場 啓 高橋 雄治 橋本 英樹 中村 謙介
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.151-155, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 16
目的:救急外来(ER)における患者動態の把握は,業務の評価および患者予後改善の観点から重要であるが,測定が困難である。本研究では,システムログを用いてER混雑度と患者待ち時間の定量化を行った。対象:2019年6月1日〜2019年6月30日に当院ERをwalk-in受診した患者を対象とした。ERシステムNext Stage ERの記録を解析することで,ERにおける待ち時間およびER滞在時間・滞在人数を算出した。結果:観察期間中のwalk-in受診患者857名のうちトリアージ時間のデータのある者691名を解析対象とした。トリアージ待ち時間の中央値は10分36秒であった。急なwalk-in患者の増加に対して,待ち時間の延長を認めた。結語:日常診療において自動的に収集されるシステムログを活用することで,ERの業務評価,および診療の質評価と改善につながる可能性が示唆された。
3 0 0 0 OA 近世以前の道路遺産(道標・町石・常夜灯)の本質的価値判断に関わる評価基準
- 著者
- 馬場 俊介 樋口 輝久 山元 亮 島田 裕介 横井 康佑 木田 将浩
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.107-122, 2012 (Released:2012-10-19)
- 参考文献数
- 4
著者らが2007年から実施してきた「近世以前の日本の土木遺産の総合調査」では,データ蓄積と現地調査,ならびに,WEB公開を同時並行で進める中,残存遺構の価値を,(1)保存状態と(2)本質的価値に分け,後者については試行的に判断・公開してきた.保存状態の評価基準の作成に比べて本質的価値の評価基準の作成が遅れたのは,基準作成にあたって相当数のデータ蓄積が必要であり,かつ,文献上の確認も数多く必要となったからである.この度,調査開始5年目にしてようやく基準を作成できる水準に達したと判断したことから,遺構の中で最もデータ数の多い道路遺産(道標・町石・常夜灯)について,本質的価値の基本的概念を,その背景となったバックデータとともに示す.また,各評価対象項目の1位に相当するものを個別に紹介する.
- 著者
- 山下 大地 島田 結依 増田 雄太
- 出版者
- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会
- 雑誌
- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.133-139, 2021-04-30 (Released:2021-08-19)
- 参考文献数
- 13
ハイパフォーマンス・ジム(HPG)ではトップアスリートを対象にアセスメントを行っている.2020年の緊急事態宣言中は,臨時特設サイトにてプログラムで用いているエクササイズの一部を動画で発信した.コロナ禍でのHPGの運営は,様々な競技団体の共用利用に配慮して工夫を凝らしている.選手サポートの要望も変化しており,個別化され,日々のトレーニングパフォーマンスを評価できるエネルギー代謝系の測定およびトレーニングが増えている.
- 著者
- 西来 邦章 石毛 康介 島田 駿二郎 中川 光弘
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.83-94, 2017-06-30 (Released:2017-07-25)
- 参考文献数
- 39
Zircon fission-track (FT) and uranium-lead (U-Pb) dating were carried out to determine the ages of the Biei, Tokachi, and Sounkyo pyroclastic flow deposits in the Biei and Kamikawa areas of central Hokkaido, northern Japan. We collected pumiceous tuff samples of the Biei pyroclastic flow deposits from two sites in the middle and lower reaches of the Biei River, and Tokachi pyroclastic flow deposits from one site to the west of Tokachi caldera. A sample of welded tuff from the Sounkyo pyroclastic flow deposits was obtained from one site in the lower reaches of the Antaroma River. The FT ages of the Biei pyroclastic flow deposits are 0.81±0.08 Ma and 0.72±0.08 Ma, identical to each other within 1σ error. However, they differ from an age of 1.91±0.06 Ma reported previously from the upper reaches of the Biei River. Based on the present data and previous results on the ages and petrographical characteristics of the deposits, they can be divided at least two geological units with different eruption ages. A FT age of 0.058±0.018 Ma (1σ) was obtained from the Sounkyo pyroclastic flow deposits. On the basis of previous studies concerning the distribution and petrographical characteristics of the deposits, this age was obtained from Hb-type pyroclastic flow deposit among the Hb- and Py-type flows of the Sounkyo pyroclastic flow deposits. The Tokachi pyroclastic flow deposits yielded a U-Pb age of 1.24±0.02 Ma (2σ), which falls within the wide range of ages reported in previous studies. Because the Tokachi pyroclastic flow deposits have a wide distribution and a wide range of ages, they can be divided into several geological units with different eruption ages, as with the Biei pyroclastic flow deposits.
3 0 0 0 風力発電事業における鳥類衝突リスク管理モデル
- 著者
- 島田 泰夫 松田 裕之
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.126-142, 2007-11-30
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
風力発電事業を進める上で、鳥衝突(バードストライク)問題の解決が求められる。本稿では、順応的管理を取り入れた鳥衝突リスク管理モデル(AMUSE:Adaptive Management model for Uncertain Strike Estimate of birds)を提案する。このモデルは、個体群サイズと衝突数をモニタリングし、結果に応じて風力発電の稼動率を調整して衝突率を低減し、保護増殖施策を導入して個体群の成長率を増加させ、個体群の管理を目指すものである。オジロワシは、2004年2月〜2007年1月の間に7個体の衝突死が報告されており、本種を対象とし個体群パラメタを定めた。あらかじめ自然条件下での個体群計算を行い、エンドポイントを定めておく。その後、2通りの成長率シナリオと管理シナリオを用いて、管理モデルの計算機実験を行った。死骸は5日間で消失、死骸発見のための踏査間隔を30日間隔と仮定し、発見数を補正して推定衝突数とした。計算期間は、計画段階5ヶ年、稼働期間17ヶ年の合計22年間とし、3年毎に稼働管理計画を見直して、稼動率と保護増殖措置の有無、管理下における個体群サイズを得た。設備利用率は、北海道における2003〜2005年の実績値から推定し、計算機実験で得られた稼動率を乗じて管理対策による設備利用率とした。あらかじめ損益分岐点となる設備利用率の限界点を求めておき、これを割り込む程度を管理の事業破綻率とした。その結果、エンドポイント(個体群サイズ自然変動幅99.9%区間下限値)達成率を99%以上、なおかつ事業破綻率を10%以下とする条件は以下の通りであった。楽観的シナリオにおいては、2種類の管理シナリオと保護増殖措置の導入条件に左右されなかった。これに対して、悲観的シナリオにおいては、必要に応じて稼働率をゼロにし、なおかつ保護増殖措置の開始を稼働率90%もしくは99%の時点で導入する管理シナリオでのみ達成された。管理を実行していく上で残された課題は、死骸消失実験による消失日数の把握、発見率向上のための衝突自動監視装置等の開発、定期的な死骸踏査、個体群モニタリングによる成長率と個体群サイズ推定、道内営巣つがいによる繁殖成績の把握、事業破綻に備えたリスクヘッジである。
3 0 0 0 IR 日本土木会社の研究 : 明治時代の巨大ゼネコンの突如の消滅の原因について
- 著者
- 島田 裕司 SHIMADA Yuji
- 出版者
- 駒沢女子大学
- 雑誌
- 駒沢女子大学研究紀要 (ISSN:13408631)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.201-218, 2014-12
- 著者
- 島田 徳子 古川 嘉子 麦谷 真理子
- 出版者
- 独立行政法人国際交流基金
- 雑誌
- 日本語国際センター紀要 (ISSN:09172939)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.1-18, 2003-03-15
- 被引用文献数
- 1
国際交流基金日本語国際センターでは、海外の日本語教育支援事業の一環として、2001年4月より海外の日本語教材制作を支援するためのウェブサイト「みんなの教材サイト」の構築に着手し、2002年5月に第一次開発を終了し運用を開始した。本サイトの趣旨および目的は、(1)世界のいかなる地域の日本語教師でも活用できること、(2)著作権許諾の手続きを必要とせず、自由に活用できる日本語教育用素材を提供すること、(3)利用者が素材・情報を受容するだけでなく発信もできる双方向性を確保すること、(4)教材に関する日本語教師間の相互交流を促進させ、教師の専門性発達に寄与すること、の四つにまとめることができる。本サイトのデザインおよび開発においては、コンピュータによる協調学習支援(Computer Supported Collaborative Learning:CSCL)研究の知見を理論的枠組みとし、教材制作を通しての教師の専門性発達を支援するために、教師教育における内省アプローチの考え方を取り入れた。開発段階においては、利用者にとって使いやすいウェブデザインをどのように実現するか(ウェブユーザビリティ)を重視した。まず、「みんなの教材サイト」の開発背景とそれに基づく機能概要について述べ、次に、第一次開発の実際とそこで行われた「状況に埋め込まれた評価」の試みを報告する。さらに、サイトの継続性を保つことを旨とした運用の実際と運用に関する評価について述べる。それらの結果をふまえ第二次開発では、(1)コンテンツの拡充、(2)利用者検索の充実、(3)利用者同士の双方向的やりとり機能の追加を行っている。最後に、今後の課題として、非母語話者利用者への支援のありかた、そして海外の日本語センターとの連携、さらに内外の教師支援サイトとの連携を考えていく必要がある。
- 著者
- 村山 英晶 影山 和郎 成瀬 央 島田 明佳
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.7, pp.883-886, 2002-07-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 6
構造の状態を正確に把握することができれば,構造物の安全性を保証することが可能になる.さまざまな環境下で使用される実構造物のひずみや振動をモニタリングするためには,正確な測定ができるだけではなく,耐久性にも優れたセンサーが必要となる.酎久性に優れる光ファイバーセンサーは,近年,発展が著しく,既存のセンサーにはない優れた特駐を兼ね備えている.本稿では,世界的なヨットレースに出場した笈さ25mの競技用ヨットに光ファイバーを張り巡らせ,船体のひずみを測定した結果を示す.これにより,船体が設計どおりの剛性をもつことが確認され,また経時的な剛性の変化を評価することが可能となった.