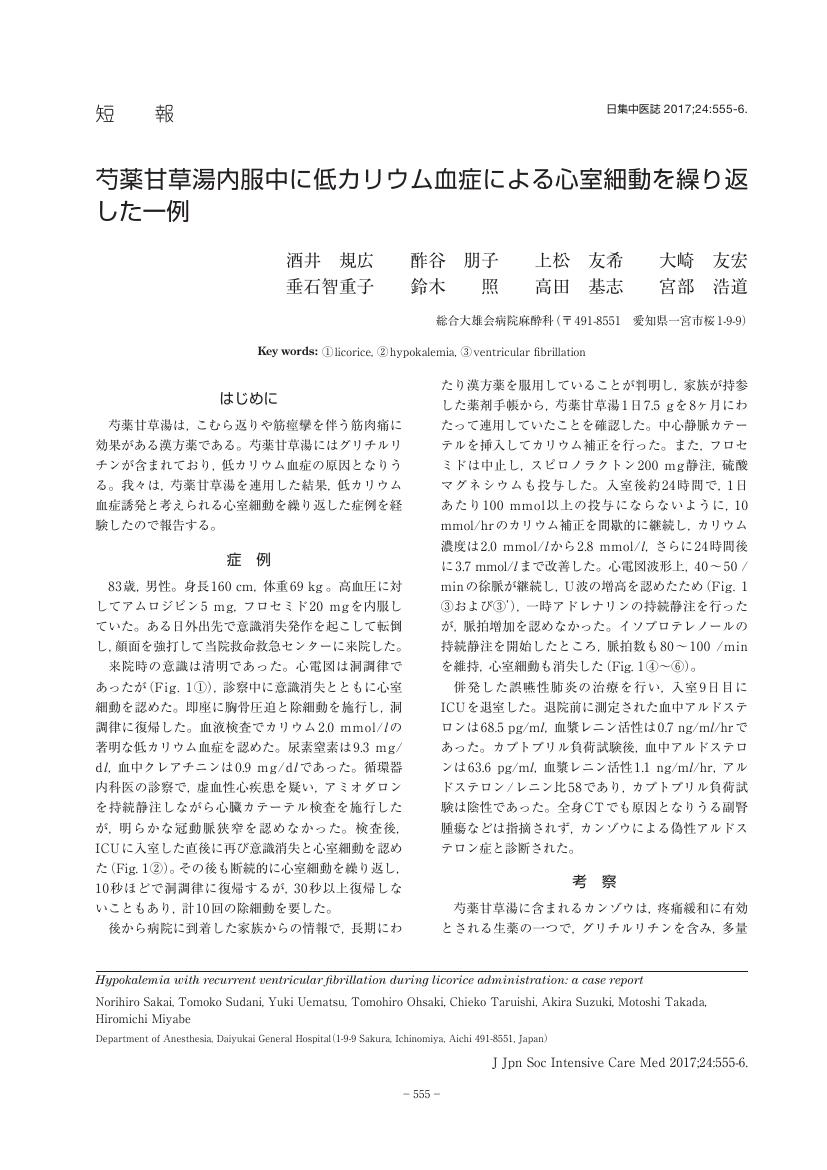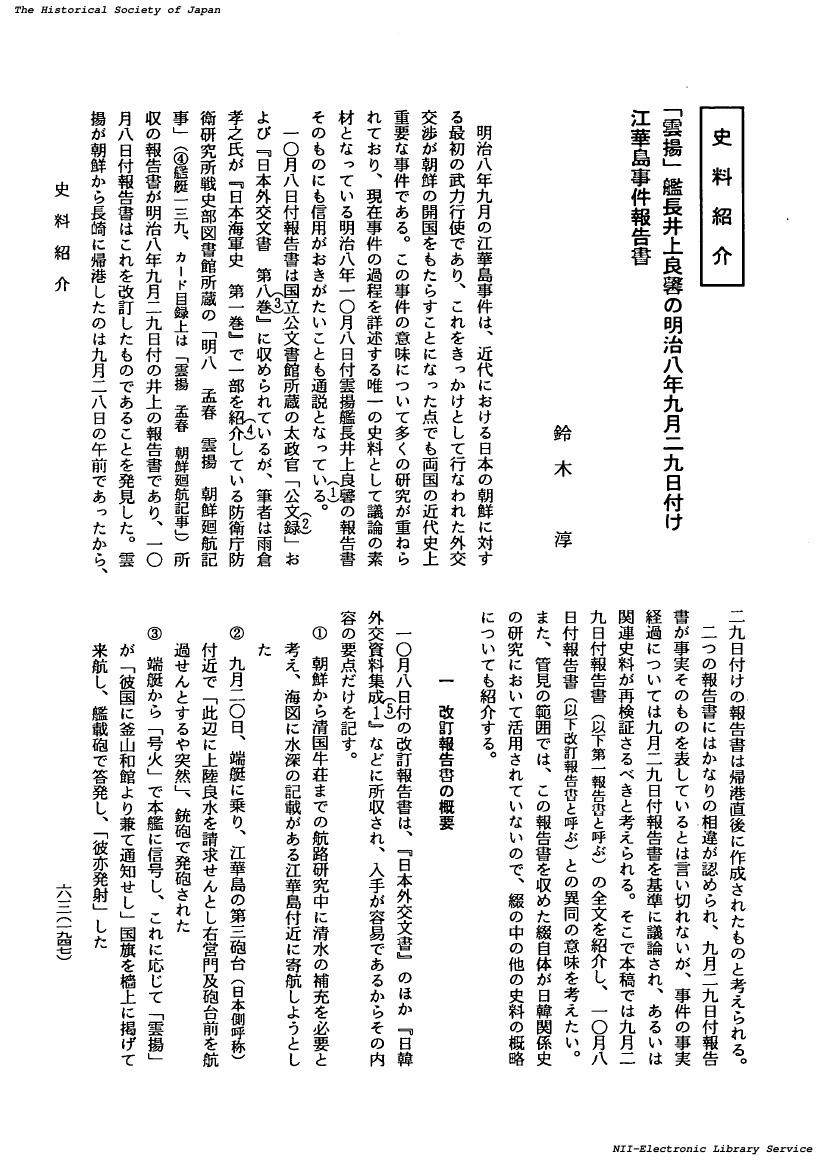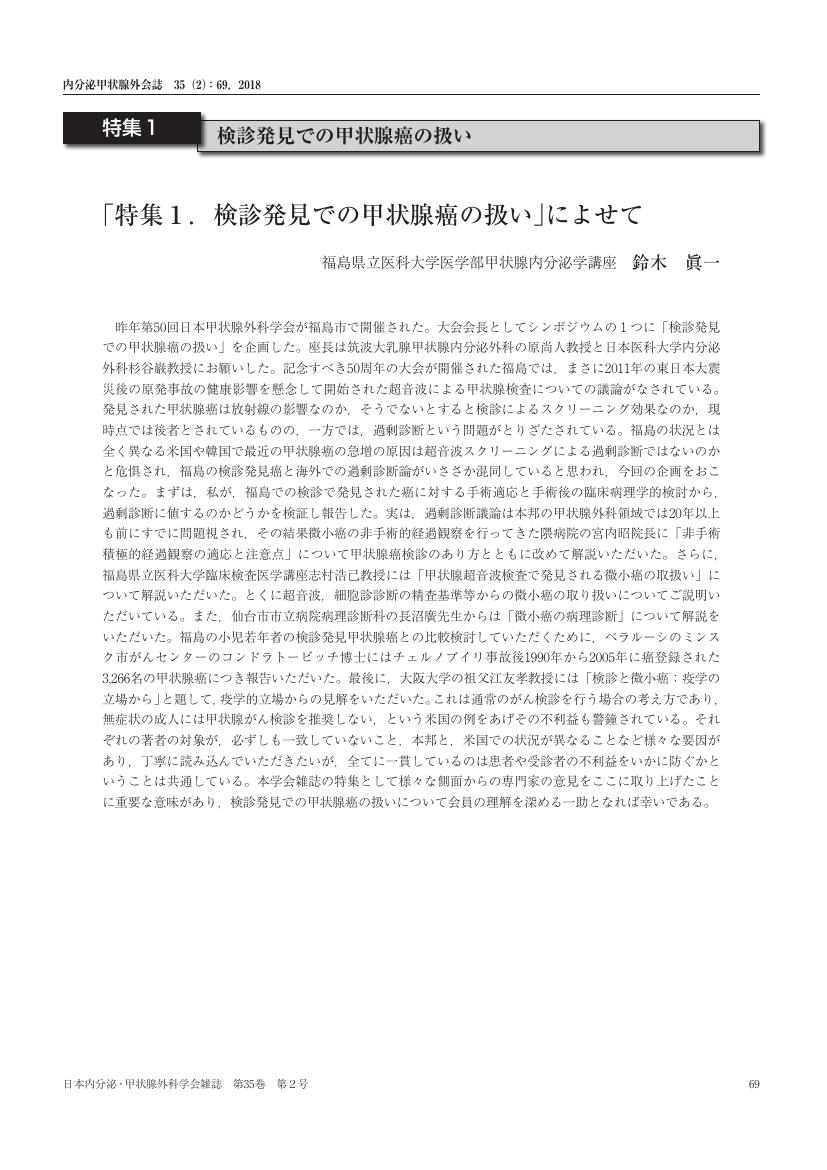65 0 0 0 OA 破壊された魂の行方 : 鈴木大拙を読むシモーヌ・ヴェイユ(研究論文)
- 著者
- 鈴木 順子
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.239-253, 2012-03-14 (Released:2017-03-31)
Que Simone Weil soit l'une des premieres lectrices de Daisetz Suzuki en France est un fait peu connu. Cet article tentera de mettre en lumiere les caracteristiques de la lecture weilienne de Daisetz et l'influence que le bouddhisme zen a exercee sur Weil dans ses dernieres annees. Weil a lu en 1942 Essays in zen bouddhism 2^<nd> series de Daisetz, et a tout de suite copie tous les poemes bouddhistes dans ses essais. Elle en a ensuite traduit plusieurs en francais. Apres deux mois d'etude, elle a finalement ecrit ses reflexions sur les notions zen-bouddhistes et etabli des comparaisons avec la philosophie occidentale et les autres religions. Ainsi, son etude sur cette oeuvre a ete tres progressive, soigneuse et dense. Dans cette etude, Weil remarque particulierement la technique du <<Koan>>, et surtout sa force de destruction de la partie discursive et intelligente de Fame. Cette partie, d'apres Weil, n'est detruite que par une joie intense de pure contemplation (Mystere, experiences mystiques) ou par une douleur et un malheur extremes (Passion du Christ, Exercices Koan de bonzes). Apres cette destruction, dit-elle, les capacites intuitives sont acquises. Depuis 1938, Weil etudiait plusieurs religions, mythes et folklores et tentait de leur trouver un fondement commun. La rencontre avec Daisetz en 1942 a renforce sa conviction que c'est veritablement Dieu (personnel et aussi impersonnel) qui donne les souffrances et les malheurs aux hommes pour que cette destruction soit accomplie. Mais ii y a une grande divergence entre Weil et Daisetz. Alors que ce dernier souligne que cette destruction introduit le Satori (l'illumination) et amene les hommes au Jodo (la terre pure), la philosophe neglige ce theme. Tout en pensant que l'invocation au Bouddha est aussi efficace que l'invocation au Christ, Weil nie l'importance du Jodo. Cette lecture originale est fortement liee a l' indifference de Well envers la resurrection du Christ et la vie eternelle.
- 著者
- 鈴木 亘
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策学会誌 (ISSN:24331384)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.118-129, 2005-09-30 (Released:2018-04-01)
This study focused on the anti-economic measures of the Osaka welfare allowance program and calculated its effect and influence on the local economy. Using the example of Osaka, I performed calculations with concrete data of Osaka. As a result, I determined that in 2003, the welfare allowance of 206.0 billion yen finally caused demand increase in the local economy of 345.3 billion yen. On the other hand, a reduction of income taxes only had an economic influence of 241.7 billion yen, and also, public construction spending was only 337.3 billion yen. Therefore, welfare allowances are understood to be a superior policy for stimulating the economy. Furthermore, when calculating the effect upon creating employment, only 25,474 employment positions were created by public constructing spending, and 19,560 employment positions were created by a reduction of income taxes, whereas the welfare allowance program created 27,685 employment positions.
64 0 0 0 OA 再生核ヒルベルト空間の理論によるガウス過程回帰の汎化誤差解析
- 著者
- 鈴木 大慈
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.10, pp.396-404, 2018-10-15 (Released:2019-04-15)
- 参考文献数
- 19
64 0 0 0 OA 芍薬甘草湯内服中に低カリウム血症による心室細動を繰り返した一例
- 著者
- 酒井 規広 酢谷 朋子 上松 友希 大崎 友宏 垂石 智重子 鈴木 照 高田 基志 宮部 浩道
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.555-556, 2017-09-01 (Released:2017-09-21)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
63 0 0 0 OA ジャワしょうがバングレ
- 著者
- 鈴木 信孝 許 鳳浩 上馬塲 和夫
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-6, 2019-03-31 (Released:2019-04-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
ジャワしょうがのエキス食品であるジャワしょうがバングレの成分,安全性や健康機能性,とくに脳機能賦活作用についての最新知見を紹介した.ジャワしょうがバングレは,in vitroにおいてNGF非存在下でも神経細胞の新生ならびに突起伸展作用を有することが徐々に明らかとなってきた.また,動物実験で,主成分バングレンが血液脳関門を通過することや空間学習能力と記憶力の改善作用をもたらすことなどが報告されている.さらに,ヒトにおいて軽度認知障害(MCI)に対する効果の検討も始まった.以上,ジャワしょうがバングレは,認知症に対する機能性食品として有望なものの一つであると思われた.
- 著者
- 鈴木 和歌奈
- 出版者
- 科学社会学会
- 雑誌
- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.3-29, 2020 (Released:2021-07-01)
62 0 0 0 OA リサーチ・クエスチョンの理論化
- 著者
- チャップマン クリス 鈴木 寛之
- 出版者
- 公益財団法人 牧誠財団
- 雑誌
- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.63-79, 2021 (Released:2022-09-22)
- 参考文献数
- 13
本講演録は,2019年から毎年開催されている「定性研究のためのワークショップ」におけるクリス・チャップマン教授の講演を,鈴木寛之氏の協力を得て訳出したものである。今回は,クリス・チャップマン教授による講演の一つである「リサーチ・クエスチョンの理論化(Theorising research questions)」と質疑応答をお届けする。
61 0 0 0 OA 「雲揚」艦長井上良馨の明治八年九月二九日付け江華島事件報告書
- 著者
- 鈴木 淳
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.12, pp.1947-1957, 2002-12-20 (Released:2017-12-01)
61 0 0 0 OA 医学における因果推論 第一部 ―研究と実践での議論を明瞭にするための反事実モデル―
- 著者
- 鈴木 越治 小松 裕和 頼藤 貴志 山本 英二 土居 弘幸 津田 敏秀
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.786-795, 2009 (Released:2009-10-02)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 2 1
A central problem in natural science is identifying general laws of cause and effect. Medical science is devoted to revealing causal relationships in humans. The framework for causal inference applied in epidemiology can contribute substantially to clearly specifying and testing causal hypotheses in many other areas of biomedical research. In this article, we review the importance of defining explicit research hypotheses to make valid causal inferences in medical studies. In the counterfactual model, a causal effect is defined as the contrast between an observed outcome and an outcome that would have been observed in a situation that did not actually happen. The fundamental problem of causal inference should be clear; individual causal effects are not directly observable, and we need to find general causal relationships, using population data. Under an “ideal” randomized trial, the assumption of exchangeability between the exposed and the unexposed groups is met; consequently, population-level causal effects can be estimated. In observational studies, however, there is a greater risk that the assumption of conditional exchangeability may be violated. In summary, in this article, we highlight the following points: (1) individual causal effects cannot be inferred because counterfactual outcomes cannot, by definition, be observed; (2) the distinction between concepts of association and concepts of causation and the basis for the definition of confounding; (3) the importance of elaborating specific research hypotheses in order to evaluate the assumption of conditional exchangeability between the exposed and unexposed groups; (4) the advantages of defining research hypotheses at the population level, including specification of a hypothetical intervention, consistent with the counterfactual model. In addition, we show how understanding the counterfactual model can lay the foundation for correct interpretation of epidemiologic evidence.
58 0 0 0 OA 「特集1.検診発見での甲状腺癌の扱い」によせて
- 著者
- 鈴木 眞一
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.69, 2018 (Released:2018-08-24)
- 著者
- 今野 秀洋 田嶋 敦 矢田 昌太郎 平崎 真由子 鈴木 千賀子 加藤 英二 後藤 俊二 南 宏次郎 野島 美知夫 吉田 幸洋 KOIZUMI Akari HIRAYAMA Takashi
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 = Journal of Japan Society of Perinatal and Neonatal Medicine (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.595-600, 2012-08-30
57 0 0 0 深層学習を用いた新物質探索に関するサーベイ
- 著者
- 奥野 智也 佐々木 勇和 鈴木 雄太
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.22-31, 2020-07-16
所望の物理化学的な性質を持つ新たな物質の探索は化学,創薬,物質・材料科学などの分野において重要な課題である.従来のアプローチは研究者の勘や経験に大きく依存し,また時間的なコストが高いという問題がある.そのため,探索の効率化を目的として,機械学習やデータマイニングなどの情報科学の技術を取り入れた研究がさかんに行われている.近年では深層学習技術を用いた高精度化が進んでいる.そこで,本稿では新物質探索における深層学習技術を網羅的に調査し体系的にまとめることを目的とする.新物質の探索技術を(1)物質構造からその性質を識別する分類と回帰技術,および(2)性質から物質を導出する生成技術に大別し,それぞれの技術の適用分野,データの分類,および深層学習のモデルについて述べる.さらに,既存技術の制約や問題点を述べ,今後の課題を明確にする.
56 0 0 0 OA 福祉国家に対する態度決定要因としての普遍的社会保障と逆進課税 ―消費増税に関するサーヴェイ実験
- 著者
- 安中 進 鈴木 淳平 加藤 言人
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.1_212-1_235, 2022 (Released:2023-06-16)
- 参考文献数
- 29
本稿では、日本の有権者の間で消費税をめぐる政治対立がどのように展開しているかを明らかにする。先行研究では、受益者の幅を広げた普遍主義的給付と、消費税を中心とした逆進的な課税構造を持つ福祉国家が、中・高所得者や右派からの支持を獲得し、高い平等を達成するとされる。しかしこの主張には、低所得者や左派は一様に福祉国家の拡大を支持する、という暗黙の前提がある。この前提を検証するため、消費増税に注目し、増税によって実現され得る福祉給付の性質と消費税の逆進的性質が有権者の態度形成に影響を与えるか、その影響が所得・イデオロギーによって条件付けられるかを、サーヴェイ実験を用いて検討した。結果は、福祉の普遍的な給付、または税の逆進的性質を強調すると、高所得者の間では高率な消費税がより許容される一方、低所得者の間では低率な税がより志向される傾向を示した。ただし、普遍主義と逆進性を同時に強調しても、これらの傾向は増幅されなかった。また、所得に対してイデオロギーは、実験刺激効果に対して明確な条件付け効果を持たなかった。これらの知見は、福祉・増税政策をめぐる政治対立の理解に有権者の態度形成の側面から重要な示唆を与えるものである。
56 0 0 0 OA 有限単純群の分類
- 著者
- 鈴木 通夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.193-210, 1982-07-26 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 55
55 0 0 0 OA 奄美大島における自動撮影カメラによるアマミノクロウサギの離乳期幼獣個体へのイエネコ捕獲の事例
- 著者
- 鈴木 真理子 大海 昌平
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.241-247, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
イエネコFelis catusによる在来種の捕食は,日本においても特に島嶼部において深刻な問題である.鹿児島県奄美大島と徳之島にのみ生息する遺存固有種アマミノクロウサギPentalagus furnessiの養育行動を2017年1月から3月にかけて調査していたところ,繁殖穴で離乳間近の幼獣がイエネコに捕獲される動画を自動撮影カメラによって撮影したので報告する.繁殖穴における出産は2017年1月14日~15日の夜に行われたが,幼獣(35日齢)がイエネコに捕獲されたのは2月19日1時ごろで,この前日は繁殖穴を母獣が埋め戻さずに入り口が開いたままになった初めての日であった.この動画の撮影後,幼獣は巣穴に戻っていないことから,捕食あるいは受傷等の原因で死亡した可能性が高い.イエネコは幼獣の捕獲から約30分後,および1日後と4日後に巣穴の前に出現し,一方アマミノクロウサギの母獣は1日後に巣穴を訪問していた.幼獣の捕食は,本種の個体群動態に大きな影響を与えうる.本研究により,アマミノクロウサギに対するイエネコの脅威があらためて明らかとなった.山間部で野生化したイエネコによるアマミノクロウサギ個体群への負の影響を早急に取り除く必要がある.
55 0 0 0 サッカーのペナルティキックの最適戦略
- 著者
- 太田 雄大 鈴木 敦夫
- 出版者
- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会
- 雑誌
- オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch (ISSN:00303674)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.328-333, 2006-06-01
- 参考文献数
- 6
サッカーのペナルティキック(PK)の最適戦略をゲーム理論の基礎的な手法を用いて求める.キッカーとゴールキーパーの利得行列をPKが成功する確率として,混合戦略とゲームの値を線形計画法を用いて計算する.利得行列の計算には,Jリーグ,日本代表の試合中のPKのデータと,ワールドカップなどの試合でのPK戦のデータを用いた.混合戦略は,キッカーは,試合中のPKでは,ゴールの右下方,左下方(キッカーが右利きの場合),PK戦では,それに加えて,ゴール中央を加えたコースをある確率で狙うこととなった.
53 0 0 0 OA 小学校における運動部活動の分布 : 市区町村別実施状況マップの作成
- 著者
- 青柳 健隆 鈴木 郁弥 荒井 弘和 岡 浩一朗
- 出版者
- 日本スポーツ産業学会
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.265-273, 2018 (Released:2018-08-02)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
School-based extracurricular sports activity (SBECSA) has widely spread in Japan as a means for youth to play sports or exercise. Especially in junior high school and high school, SBECSA is actively conducted with a high participation rate of students. There have also been reports that elementary schools in some Japanese municipalities also have SBECSA. However, there has been little information about which municipalities conducted SBECSA in elementary schools. Therefore, the present study aimed to clarify the existence of SBECSA in elementary schools in each municipality, and to create a municipal map of implementation status. A complete enumeration questionnaire survey was conducted with all 1741 municipalities’ educational boards. Question items were in regard to the existence of elementary schools’ SBECSA in their municipalities. Answerers were requested to choose one response from the items; “almost all elementary schools have SBECSA”, “some elementary schools have SBECSA”, “there were SBECSA (about 10 years ago), but now there is no SBECSA”, “there weren’ t any SBECSA before 10 years ago”, “we don’ t know”, and “we don’ t answer” . To increase the response rate, a second survey was conducted with Sports Associations or similar sports related organizations in each municipality. Additionally, a third survey was conducted with educational boards again at the same time as the feedback of results was given. As results, 88.0% of all municipalities’ implementation status was identified (response rate = 92.5%). And 23.0% of all municipalities were shown to have SBECSA in elementary schools, although 64.9% did not have it. More than half of the municipalities in Aomori prefecture, Chiba prefecture, Aichi prefecture, and Kumamoto prefecture have SBECSA in elementary school. Based on the results of the present study, it is suggested that further development of the youth sport environment should be discussed. In addition, means to decrease the burdens on teachers who coach and manage SBECSA must be considered.
53 0 0 0 OA トランプ政権の発足とイラン・米国関係の今後
- 著者
- 鈴木 均
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.35-41, 2017 (Released:2019-11-12)
The result of the November election of the US president has crucial importance for the future of several countries including Israel, Saudi Arabia, and Iran, with different nuances pertaining to each country. In the case of Iran, contrary to the other two countries, the result of Donald Trump’s victory is disgusting, as he has openly denied the profits of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) from the outset of his election campaign.If Hillary Clinton were elected, she would have followed Barack Obama’s political legacy in many ways, including the policies that brought about his breakthrough in US–Iranian relations after the 1979 revolution. We could refer to many pieces of evidence, especially from M. Landler’s convincing work entitled Alter Egos (2016). President Obama’s unprecedented challenge in this regard was to change relations with Iran such that there is less emnity. Nowadays it seems very difficult to expect that this rare historical chance at a stronger US-Iran relationship will eventually materialize.In this very difficult situation, Japan should not hesitate to make every effort to convince the Trump Administration that it is crucial for the US to maintain diplomatic relations with Iran to keep the Middle East from entering a more catastrophic situation characterised by greater warfare. Japan is an important player in this situation given its uniqueness in having an alliance with the US while at the same time being trusted by Iran.
51 0 0 0 OA 「特集1.震災後10年を経た福島での甲状腺検査について」によせて
- 著者
- 鈴木 眞一
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1, 2022 (Released:2022-05-24)
<p> 本稿の目的は,大手の結婚相談サービス事業者であるX社の会員を対象にした調査から,学歴・収入・容姿が「成婚の可否」「異性からの選好されやすさ」「結婚相手のより好み」に与える影響を明らかにすることである.分析の結果,以下の三点が明らかになった.第一に,高学歴,高収入,高身長・低肥満といった客観的条件の多くは,男性の高収入を除き,成婚の確率を高めるとは言えない.第二に,男性では,高学歴,高収入,高身長・低肥満であるほど女性から選好の対象とされやすく,女性では,非大学院卒,高収入,低肥満であるほど男性から選好の対象とされやすい.第三に,男性では,高学歴,高収入,高身長・低肥満であるほどより好みしており,女性では,高収入,低肥満であるほどより好みをしている.つまり,結婚相談サービスを利用した婚活では,一般的な結婚とは異なり,学歴・収入・容姿で有利な条件を備えていることが成婚の可否へほとんど影響を与えておらず,これは,男女とも婚活市場における自身の価値に対応したより好みを行うというメカニズムが存在するためだと考えられる.</p>