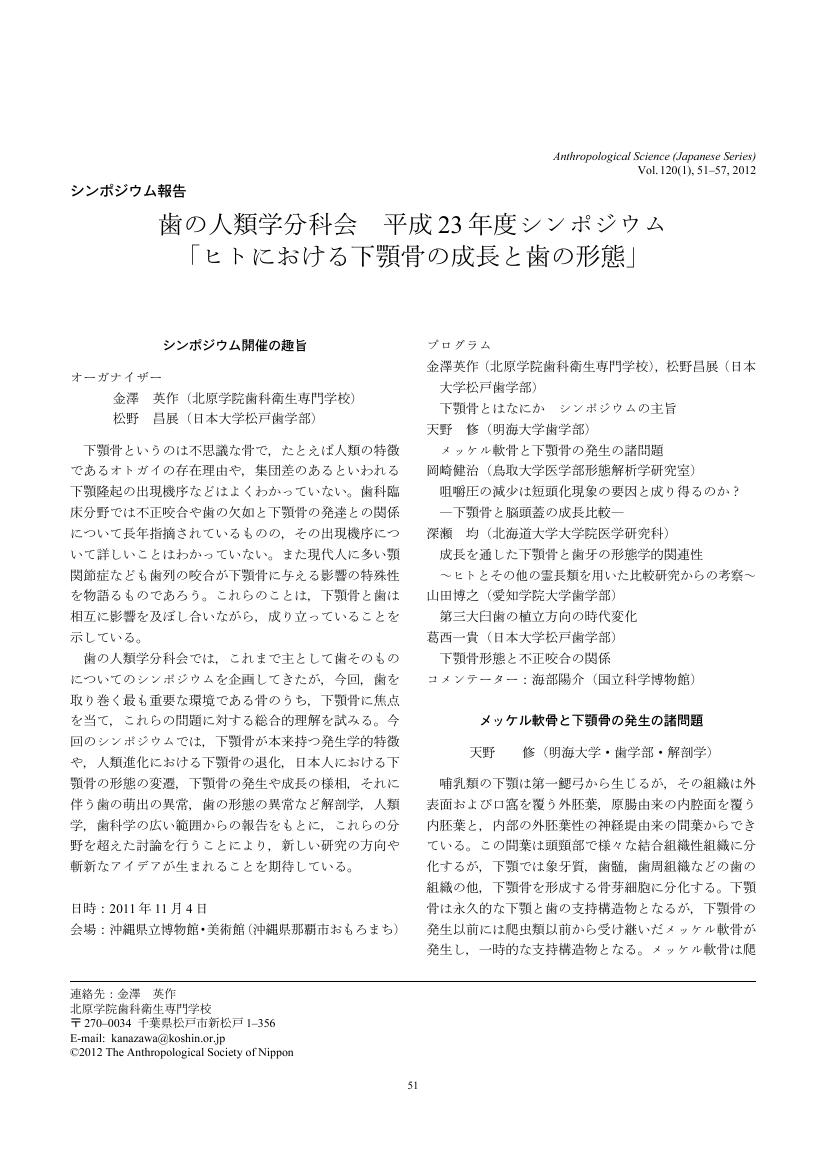1 0 0 0 OA ぺた語義:第14回全国高等学校情報教育研究会全国大会(大阪大会)
2021年8月10日~11日の2日間,第14回全国高等学校情報教育研究会全国大会(大阪大会)がオンラインで開催された.全国高等学校情報教育研究会は,その発足以来,全国の高等学校における情報教育の研究推進ならびに会員相互の研鑽を図ることを目的とし,毎年8月に全国大会を開催し,教科「情報」並びに情報教育の発展に寄与してきている.本稿では,第14回大会(大阪大会)におけるオンラインの特性を活かした新しい取り組みや,口頭発表(リアルタイム発表)と動画発表(オンデマンド発表)を合わせた全35件の発表内容の傾向などについて解説する.
1 0 0 0 2001年(平成13年)の日本の気候の特徴
- 著者
- 向井 利明
- 出版者
- 養賢堂
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.157-164, 2002-09-10
*平均気温は東・西日本と南西諸島で高く、北日本で平均並 *北日本の冬の低温 *春の少雨 *夏は東日本以西で高温 *早い梅雨明け(東日本、東北南部)、7月の記録的な高温と少雨、8月は北冷西暑 *秋は東・西日本太平洋側などで多雨 冬には北日本は1987/88年冬以来13年ぶりの低温となり、北日本日本海側の降雪量も多くなった。春は気温の変動が大きかったが、南西諸島を除き高温となった。また、北・東・西日本では高気圧におおわれることが多く、少雨となった。南西諸島では多雨・寡照だった。夏の気温は北日本で平年並、東日本以西で高くなった。梅雨明けは東日本と東北南部で平年より2週間以上早く、7月は東日本などで記録的な高温と少雨になった。8月にはオホーツク海高気圧などの影響で北日本で低温となる一方、西日本・南西諸島では高温が続いた。秋には台風や低気圧の影響で東日本以西で多雨となった。年平均気温は北海道や東北の一部で平年を下回り、そのほかの地方では平年を上回った。東日本以西では平年を0.5℃以上、上回るところがあった。年降水量は南西諸島と西日本、関東甲信、北海道の一部で平年を上回り、そのほかの地方では平年を下回るところが多かった。年日照時間は東日本と西日本では平年を上回り、北日本と南西諸島では平均を下回るところが多かった。
1 0 0 0 OA 機能性便秘症を伴う下部尿路障害を有する小児における腸内細菌叢の検討
- 著者
- 石川 琢也 池田 裕一 布山 正貴 小川 玲 藤本 陽子
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.6, pp.564-570, 2022 (Released:2022-03-23)
- 参考文献数
- 22
ヒトの腸管内には多くの細菌が生息しており腸内細菌叢を形成している.近年,腸内細菌叢の変化とさまざまな疾患との関係性が報告されている.今回,われわれは機能性便秘症を伴う下部尿路障害の児における腸内細菌叢の分布を調査することとした.機能性便秘症を伴う下部尿路障害の児10名(男児8例女児2例,平均年齢8.1歳)と健常児10名(男児10名,平均年齢7.1歳)の腸内細菌を検索した.検索は培養法で行い,4菌種を評価項目とした.その結果,機能性便秘症を伴う下部尿路障害の児ではClostridium属とLactobacillus属が有意に増加しており(p<0.05),その他の菌種や総菌数では有意差は認めなかった.腸内細菌叢の変化が排尿排便機能に何らかの影響を及ぼしている可能性が示唆され,プロバイオティクスによって基礎疾患とともに下部尿路障害の改善に期待がもたれる.
1 0 0 0 OA ペアプログラミングを取り入れた小学校プログラミング教育の実施方法の提案と評価
- 著者
- 中山 舞祐 森本 康彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.Suppl., pp.149-152, 2021-02-20 (Released:2021-03-08)
- 参考文献数
- 6
協働的に開発作業を行うプログラミングスタイルの一つにペアプログラミングがある.しかしながら,小学校プログラミング教育において,児童がペアプログラミングの仕組みを理解して取り組むことは難しいと考えられる.そこで,本研究では,ペアプログラミングを取り入れた小学校プログラミング教育の実施方法を提案することを目的に,児童がペアプログラミングに取り組む際のルールを定め,それに則り実践を行った.児童への提案方法の効果を聞く質問紙調査の結果,児童は,ペアプログラミングにおける役割を意識し,ねばり強く,2人で教え合いながら取り組めることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 歯の人類学分科会 平成23年度シンポジウム「ヒトにおける下顎骨の成長と歯の形態」
- 著者
- 金澤 英作 松野 昌展 天野 修 岡崎 健治 深瀬 均 山田 博之 葛西 一貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.51-57, 2012 (Released:2012-08-22)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 IR 味覚センサと近赤外分光分析法を用いたトレハロースの計測
- 著者
- 都甲 潔 Chibvongodze Hardwell 永守 知見
- 出版者
- 九州大学大学院システム情報科学研究院
- 雑誌
- 九州大学大学院システム情報科学研究科報告 (ISSN:13423819)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.179-184, 1999-09
- 被引用文献数
- 1
Trehalose is a sweet disaccharide composed of two glucose molecules, and is drawn attention to from the viewpoint of the physiological function. In this paper, we studied the suppression of bitterness by trehalose using a multichannel taste sensor, and the intermolecular interaction between sugar and water with a near infrared radiation (NIR) apparatus. A multichannel taste sensor whose transducer is composed of several kinds of lipid/polymer membranes with different characteristics can detect taste in a manner similar to human gustatory sensation. The NIR spectroscopy is a suitable method for the food analysis of the need for detailed quality specifications in food and beverage industries. The suppression of bitterness by trehalose was quantified by applying a principal component analysis to data on response electric potential. Moreover we found an intimate relationship between NIR spectra and the number of OH radical of sugars.
1 0 0 0 OA 琉球列島に於ける地名の分布
- 著者
- 鏡味 完二
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.11, pp.886-902, 1942-11-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 東京都心居住地域における地価構造をふまえた住宅供給方策に関する研究
- 著者
- 藤村 浩之
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.145-150, 1993-10-25 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 5
THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO PRESENT A NEW METHOD OF MAKING HOUSING-SUPPLY STRATEGIES. RECENTLY,ESPECLALLY AROUND THE CBD OF TOKYO METROPOLITAN AREA, LAND-VALUE HAS A GREAT INFLUENCE ON THE PRICES OF NEWLY-SUPPLLED HOUSINGS. THEREFORE, IN PLANNING THE STRATEGY THERE ,LA ND-VALUE STRUCTURE SHOULD BE CONSIDERED. THIS PAPER INVESTIGATES THE POSSIBILITY OF HOUSING SUPPLY, BY ESTIMATING THE TREND OF ACTUAL HOUSING SUPPLY IN URBAN RENEWAL AND SIMULATING THE PROFITABILITY OF HOUSING PROJECTS.
1 0 0 0 ラスプーチン文学に現れた母子像
- 著者
- 大木 昭男
- 出版者
- Japanese Society for Slavic and East European Studies
- 雑誌
- Japanese Slavic and East European studies
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.83-101, 2007
ロシアの「母子像」と言えば、まず思い浮かべるのはイコンに描かれた「聖母子像」であろう。それは慈愛のシンボルであり、キリスト教的「救い」のイメージと結びついている。ロシア文学に描かれた代表的な母子像としては、ゴーリキイの長編『母』(1906-07)があり、これは社会主義革命のイメージと結びついている。本論文においては、ワレンチン・ラスプーチンの最新作『イワンの娘、イワンの母』(2003)に現れた母子像に注目して、その意味を考えてみた。1993年の「10月騒乱事件」後に書かれた短編『病院にて』(1995)のラストシーンに、修道僧ロマーンの作詞した『聖なるルーシが呼んでいる』という歌の次のような一節が引用されている。「ボン、ボン、ボーン--一体何処、君らロシアの息子たち ボン、ボン、ボーン--なぜに母をば忘れしか? ボン、ボン、ボーン--この響きに合わせ、行進の歩調で ボン、ボン、ボーン--死に歩みしは、君らでなかりしか?!」この歌詞の中の「ロシアの息子たち」と「母」が、中篇『イワンの娘、イワンの母』に21世紀の現代ロシアにおける新しい独特な文学的形象となって登場している。『イワンの娘、イワンの母』に描かれている時代は、ソ連崩壊後の現代、舞台はイルクーツクの町とその近郊。営林署に林務官として長年のあいだ働き、今は年金生活者としてイルクーツク近郊の集落で、菜園を営みながらつましく暮らしているイワン・サヴューリエヴィチ・ラッチコフと、その子供たちと孫たちの三世代にわたる物語であるが、小説のヒロインは、イワン・ラッチコフの長女タマーラ・イワーノヴナであり、彼女は16歳の娘スヴェートカと14歳の息子イワンの母である。「イワン」という極めてポピュラーなロシア人名を小説の題名に反復して使っていることからしても、新たな典型的ロシア人像を描き出そうとする作者の意図が感じられる。小説は5月末にスヴュートカの身にふりかかった災厄から始まり、母親タマーラ・イワーノヴナによる制裁的殺人、そして裁判を経てラーゲリから釈放されて彼女が帰還するまでの4年半の時間的幅をもって描かれている。ラスプーチンは1997年、『我が宣言』という文書を発表し、「ロシアの作家にとって、再びナロードのこだまとなるべき時節が到来した。痛みも、愛も、洞察力も、苦悩の中で刷新された人間も、未曾有の力をもって表現すべき時節が。我々は、我が国が以前には知らなかった諸々の法律の残忍な世界に押し込まれていることが判明した。数百年にわたって、文学は、良心、清廉、善良な心を教えてきた。これなしにはロシアはロシアではなく、文学は文学でない。」と述べ、今、文学に不可欠なものは、「充電池の要素としての意志強固な要素である。」として、「ナロードの意志」を体現する「意志強固な個性」を描くことをロシア人作家たちに呼びかけた。その創作実践のラスーチン自身による最新の成果として、『イワンの娘、イワンの母』は注目すべき作品である。
1 0 0 0 IR 村上春樹「ドライブ・マイ・カー」論 : 「生きる姿勢」、家福の盲点を生み出すもの
- 著者
- 山本 千尋 ヤマモト チヒロ
- 出版者
- 立教大学日本文学会
- 雑誌
- 立教大学日本文学 (ISSN:0546031X)
- 巻号頁・発行日
- no.117, pp.122-134, 2017-01
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2022年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.25, 2022 (Released:2022-03-28)
スポーツの国際大会において,出場選手は地理的環境の異なる場での競技パフォーマンスを高めるために事前合宿を行う。東京2020五輪大会では,政府が事前合宿の場を全国から募り,ホストタウン政策を実施した。共生社会ホストタウンはパラリンピック選手の事前合宿を受け入れるもので,競技施設や宿泊施設,また交流事業を行う公共施設などのバリアフリー化が事業計画に含まれる。 日本の障害者政策には2006年のバリアフリー新法があるが,東京2020大会は施設整備を推し進める契機として期待された。共生社会ホストタウンの事業計画には,地方自治体にとって福祉のまちづくりの推進への期待が読み取れる。全105の登録自治体の事業計画を整理すると,直接パラリンピックに言及するものよりも当該自治体の福祉政策を反映しているものが多い。スポーツ施設だけでなく,教育施設や交通インフラ,観光施設,防災関係の計画も少なくない。ソフト面ではバリアフリーマップや啓発用パンフレットの作成,障害者関連条例に関する記述などもある。自治体のウェブサイトでは事前合宿の様子が報告されているが,具体的な施設整備の状況は確認できない。そこで,自治体の予算書から五輪関連予算の内訳を確認した。4市の事例から,施設整備とその財源,地方都市におけるスポーツ・イベントの存在,ツーリズムとの関連と新型コロナウイルス感染症対策,オリンピックを契機としたまちづくり計画の加速化が明らかにされた。諸施設のバリアフリー化の詳細や,政府の財政支援の詳細については明らかにできなかった。ホストタウン政策を通じて全国に分配しようとした五輪大会の効果は限定的なものとなったが,各自治体の取り組みは福祉のまちづくりをある程度推進したといえよう。
- 著者
- 岩本 裕子 イワモト ヒロコ Hiroko Iwamoto
- 出版者
- 浦和大学・浦和大学短期大学部
- 雑誌
- 浦和論叢 (ISSN:0915132X)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-29, 2015-02
アメリカ演劇における黒人女優の歴史は、アメリカ黒人史同様、白人主体のアメリカ演劇界で苦難の道であった。その業界で成功者となり得た先達たちの代表、マヤ・アンジェロウとルビー・ディーが、2014年5月末と6月半ばに死去した。2人の逝去に挟まれる時期、6月8日に開催されたトニー賞授賞式で、黒人女優の歴史でも記念すべき出来事が起こった。オードラ・マクドナルドが、演劇部門で主演女優賞を獲得したのである。オードラはすでに、ミュージカル部門での助演女優賞と主演女優賞を3回、演劇部門で助演女優賞を2回、実に5回の受賞を果たしていた。ビリー・ホリデイの役を演じた「レディ・デイ」によって、最優秀主演女優賞を獲得したのだった。アメリカ演劇界の人種を超えた女優の世界で、前人未踏の快挙である。マヤとルビーを見送ったアメリカ黒人演劇界は、オードラたち後進が引き継ぎ、先達たちの語り継ぎは、その演技に生き続けていくのである。The history of African American actresses in Broadway dramas has been marked by countless hardships. Two of the pioneers in the theatrical world passed away on May 28 and June 11, 2014. The former was MAYA ANGELOU, the Presidential inaugural ceremony poet in 1993, and the latter was RUBY DEE, a main civil rights activist. Between their deaths, the 68th Tony Awards Ceremony was held on June 8 at Radio City Music Hall. A milestone in African American history was reached in that ceremony. Broadway star AUDRA MCDONALD made history at the Tony Awards on June 8 night, when she became the most decorated actress on the Broadway stage. Audra picked up her sixth Tony for portraying jazz and blues legend Billie Holiday in Lady Day at Emerson's Bar & Grill. The Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Play win also gave her the first Tony Awards grand slam. She had previously won gold as a best featured actress in an play(A Raisin in the Sun & Master Class),a best lead actress in a musical(Porgy and Bess)and a best featured actress in a musical(Carousel & Ragtime).
- 著者
- 本間 亮平 若杉 貴志 小高 賢二
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.127-132, 2017
レベル3自動運転において,システム機能限界に伴う権限委譲時のドライバ対応行動を調べた.運転以外の作業として,ラジオ聴き取りタスクとテキスト入力タスクを設け,DS実験を実施した.テキスト入力条件下では,他の条件より対応の遅れる傾向がみられたものの,本実験設定において,ほとんどのドライバが対応できた.
1 0 0 0 IR 古代アンデス文明と日本人 : 放送大学特別講義と展示会
- 著者
- 稲村 哲也 大貫 良夫 森下 矢須之 野内 セサル良郎 阪根 博 尾塩 尚 Tetsuya Inamura Yoshio Onuki Yasuyuki Morishita Cesar Yoshiro Nouchi Hiroshi Sakane Hisashi Oshio
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 放送大学研究年報 = Journal of The Open University of Japan (ISSN:09114505)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.79-95, 2015
1898年に秋田で生まれた天野芳太郎は、30歳のときに中南米にわたって実業家として成功し、後にペルーのリマ市に考古学博物館を創設した人物である。 天野は少年時代から考古学に関心をもっていたが、その関心を決定づけたのは、1935年のマチュピチュ訪問であった。天野はマチュピチュで、そこに住んでいた野内与吉という日本人に出会い、彼の案内で一週間ほどマチュピチュを踏査した。 しかし、第二次世界大戦が始まると、天野は総てを失い、北米の収容所に入れられたあと、日本に送還された。戦後の1951年に再び南米に向かい、ペルーで事業を再開し成功するが、後半生は古代アンデス文明の研究と土器、織物などの考古遺物のコレクションに身を投じ、1964年リマに博物館を設立したのである。 それに先立つ1956年、当時東京大学助教授であった泉靖一がリマで天野芳太郎と出会った。泉はすぐにアンデス研究を始め、調査団を組織し発掘を始めた。最初のコトシュ遺跡の発掘で、アメリカ大陸最古の神殿を発掘した。東京大学はそれ以来アンデスの研究で大きな実績を重ねてきた。 岡山出身の実業家森下精一は、1969年リマで天野芳太郎の博物館を訪問し、古代アンデスの土器や織物のすばらしさに衝撃を受け、中南米の考古遺物を蒐集し、1975年自らも岡山県に博物館を開設した。 筆者らは、放送大学のTV特別講義「古代アンデス文明と日本人」を制作し、2015年秋田でそのテーマの展示会を企画し実現した。本稿では、それらの内容を中心に、日本人による古代アンデス文明研究、その背景としての先人たちの「運命的」な出会い、そして秋田で開催した展示会について論じる。
- 著者
- 梅本 麻規子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- no.1996, pp.431-432, 1996-07-30
1 0 0 0 OA ドップラーレーダーによる風の場の観測と解析
- 著者
- 中津川 誠 山田 正
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 水工学論文集 (ISSN:09167374)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.1-8, 1993-02-20 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
The present study deals with the investigation of wind velocity observed by the Doppler radar. The first phase of paper is the observation of wind using the Doppler radar. Observations have been carried out by using the Doppler radar which is installed in the suburb of Sapporo, Hokkaido, Japan. Horizontal and vertical wind components are estimated by applying the VAD (Velocity Azimuth Display) method to the Doppler data. We make sure that the VAD method can precisely estimate the wind components. The second phase is the utilization of wind data for investigation of rainfall field. The geostrophic wind observed by the Doppler radar is incorporated into the Kao model so that three dimensional wind components are estimated in the planetary boundary layer. The rainfall field is simulated by applying such wind distribution to the Kessler parameterization. The above methodorogy offers considerable promise for the progress of physics-based rainfall models and forecast methods.
- 著者
- Monir Hossain MONI
- 出版者
- The Japan Society for International Development
- 雑誌
- 国際開発研究 (ISSN:13423045)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.117-130, 2006-06-15 (Released:2020-01-29)
- 参考文献数
- 32
During more than three decades, Japan has strenuously and consistently been upholding its status as the “single largest donor” in Bangladesh, one of the Least Developed Countries (LDCs) located in South Asia. Japan has distinctly proved itself to be a “tested, trusted and dignified” development partner to the country as well. It is an irrefutable fact that several contributions of Japan's official development assistance (ODA) loan programs to Bangladesh, in dealing predominantly with the infrastructure development sectors, have already been identified as “milestone successes.” Nonetheless, it can fairly be asked whether the magnitude of its aid had significantly been efficacious in fostering Bangladesh's sustainable livelihood efforts. On the one hand, while poverty eradication is given a supreme priority with an expanded focus being put on “quality of aid,” Japan's ODA policy considerations regarding Bangladesh are oftentimes being called into question in the reasonableness that its foreign aid is rather too “gigantic” and “radical.” One the other, despite abundant donations from Japan and other major bilateral donors, Bangladesh has still sizeable shortfalls in the key areas like poverty alleviation, environmental hazards, healthcare and nutrition, and basic education. In practice, development cooperation scenario in Bangladesh has seriously been hindered by an absence of renovated “implementation and management efficiency,” a lack of strong “ownership and self-help effort strategies,” as well as a need for effective “partnership and aid coordination” among the multilateral aid agencies, national and local governments, and non-state actors. Hence, in order to reap the fullest benefit from Japanese foreign aid to Bangladesh in the years ahead, its ODA strategies need a new thinking. To make ODA more praiseworthy of public trust and support, it is very urgent to hear the voices of the beneficiaries of public goods Japan provides. Against this crux, while the study critically analyzes the impact of Japan's ODA to Bangladesh, this unique research article endeavors to concretely suggest about how Japanese generous foreign aid efforts to Bangladesh could strive to assist the nation, from the “lessons learned,” toward addressing the UN Millennium Development Goals (MDGs) as well as making it as one of the “stable, poverty-free and prosperous” Asian nations in the most challenging epoch of globalization.
1 0 0 0 OA 運動療法としてのPilates効果の追究 第二報
- 著者
- 清水 英里 長尾 知香
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.CbPI2230, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】我々は変形性膝関節症に対する運動療法として、ピラティス専用器具リフォーマーを使用している。その際、自重で行う場合よりリフォーマーを使用した後の方が、歩容改善や患者の自己効力感が得られるケースが多い。そこで今回、実際に自重で行う場合とピラティス専用器具リフォーマーを使用して行った場合、どのような効果の違いがあるか検証する。【方法】対象は変形性膝関節症を有する患者で、本研究の概要を説明し同意が得られた患者16名(女性14名男性2名、平均年齢74.8±8.1歳)。除外基準は、急性症状を有する者、観血的治療の既往、圧迫骨折、重度の骨粗鬆症を有する者とした。評価項目は基本属性(性別、年齢、身長、体重)、日本版膝関節症機能尺度(以下JKOM)、徒手筋力計にて大腿四頭筋・ハムストリングス・中殿筋・腸腰筋の筋力、体幹MMT、5m歩行速度、フットプリントとした。くじ引きでピラティス群とコントロール群の2群に分類し、週2~3回来院時に以下の運動を約3ヶ月間実施した。コントロール群:ハーフスクワット,片脚ハーフスクワット,ランジ,段差使用での足関節底背屈運動。ピラティス群:タワーバー、リフォーマーにてフットワーク,フットワークシングルレッグ,ランジ,ローワーアンドリフト,ランニング【説明と同意】被験者には書面にて研究内容を十分に説明し、ヘルシンキ宣言に基づき了承と同意サインを得た。【結果】各評価項目を介入前後で測定し、得られた結果についてt検定もしくはWilcoxon符号付順位和検定を行ない、有意水準は5%未満とした。介入前後において、ピラティス群のJKOM、VAS、中殿筋疼痛側・非疼痛側、5m歩行速度、コントロール群の中殿筋疼痛側、5m歩行速度に有意差を認めた。【考察】筋力の有意差が認められたのは、ピラティス群の疼痛側・非疼痛側中殿筋、コントロール群の中殿筋疼痛側のみであった。全て立位で行う運動であったコントロール群の支持基底面が足部であったのに対し、主にsupineで行うピラティス群は体幹が支持基底面となっていたため、骨盤の傾斜や回旋などの代償運動がおこりづらかったこと、目からのfeedbackにより自ら修正できた点が大きな要因となったと考える。また、70歳前後の高齢者では、最大努力筋収縮の50%でのトレーニングの方が筋力増強率が高いという報告もあり、ピラティス群はコントロール群に比べ低負荷であった為、運動制御がしやすかったという点も、ピラティス群のみ両側共に有意差が認められた理由と考える。中殿筋は立位時において膝関節の内側負荷を減少させる為、除痛効果につながるとされている。その為、今回大腿四頭筋やハムストリングスには有意差がみられなかったが、中殿筋の筋力upによって膝の痛みが軽減したと思われる。また、コントロール群においても中殿筋は疼痛側のみ有意差が認められたが、中殿筋によって歩行時の立脚期の安定化が得られ、5m歩行速度は両群ともに改善がみられたと考える。一方で、5m歩行速度は両群共に有意差が認められたにも関わらず、JKOMスコアはピラティス群のみに有意差がみられた点だが、第1報でも述べた通り、ピラティス・エクササイズは自己効力感が高く、心と体のコントロールを可能にする為、身体機能面のみならず心理面においても改善が図れたものと考える。また、ピラティス・エクササイズでは筋出力の量的な改善は中殿筋のみであったが、下肢・体幹の動きの中での筋出力、筋間協調性の質的な面での改善が得られ、それがADL、QOLの向上に繋がったのではないかと考える。【理学療法学研究としての意義】高齢化の進む中、ますますクリニックでの予防的リハが重要となるであろうが、その中でもより加速的・効果的な運動療法の展開が、外来通院患者のモチベーション向上も含めて必要であると思われる。単に減量や関節内注射、筋力トレーニングだけでなく、運動様式の違いによって、より目的とする部分へ加速的に効果を出していくために、今回はCKCでも支持基底面、関節固定部位、姿勢と抵抗量の異なる様式での差を検証した。得られた結果から強調されるべきことは、厳密な条件設定で行えるピラティス・エクササイズの方が有意に機能面の変化をもたらし、更にADLや心理面にも波及するということである。筋力増強という観点だけにこだわらず、筋の機能をいかに引き出し、それをいかにADL,QOLの向上に繋げていくかという点では、変形性膝関節症に対し、CKCで行う運動療法の手段としては、ピラティス・エクササイズの方がより効果的であったことが、本研究により実証されたといえる.