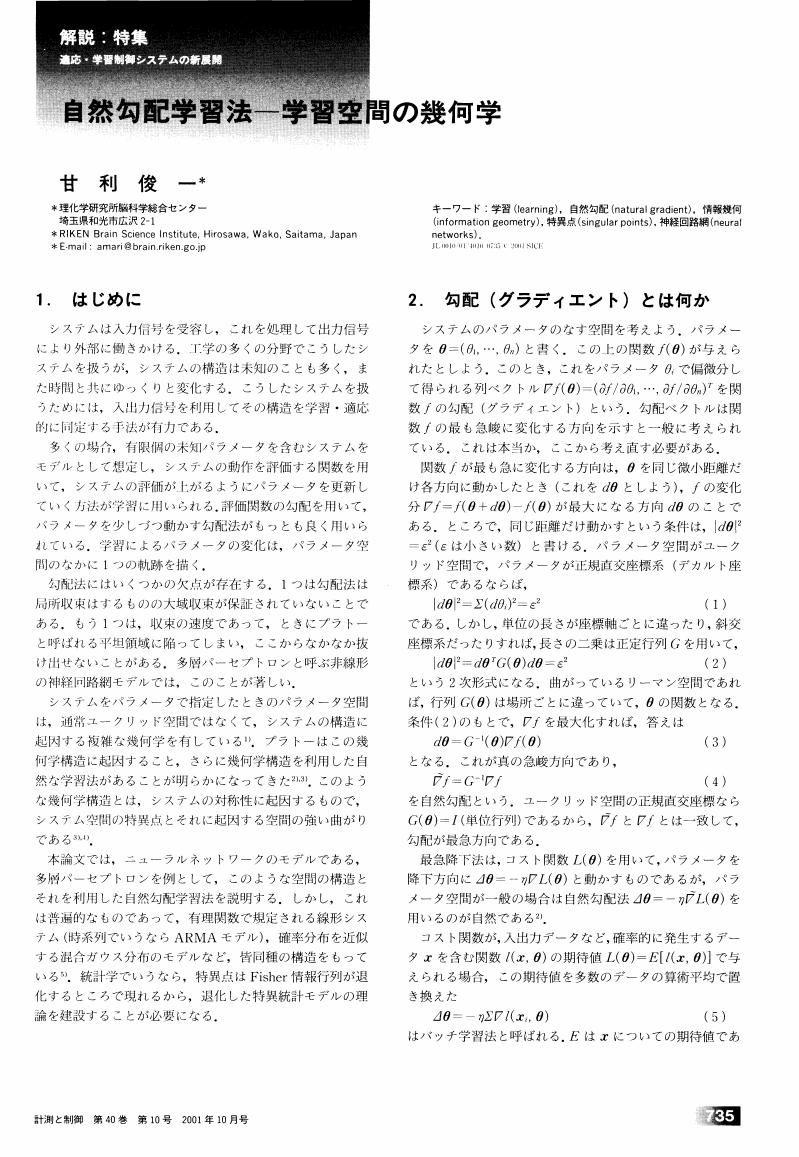46 0 0 0 OA 冬季における日本人と韓国人の20代女性の素肌ならびに化粧肌の比較
- 著者
- 李 吉英 島上 和則 宮崎 良文 佐藤 方彦
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.119-125, 2003-08-25 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 17
The purpose of the present study was to investigate the difference in skin color between 50 Japanese women and 50 Korean women aged in their twenties. We measured the color of bare skin and foundation-applied skin by the Munsell System. Moreover we checked their preference for skin color with "skin color sample board" . The results were analyzed by using a three-factor (nationality, site, make-up) analysis of variance (3-way ANOVA). The results of this study are as follows. l)There was a significant difference between the Japanese and Korean women. The Japanese women had more reddish and brighter skin color than the Korean women. Moreover, the Japanese women showed a low Munsell value. 2) There were no differences in make-up tendencies to between the Japanese and Korean women. Both the Japanese and Korean women had yellowish make-up on their bare skin. In particular, they had darker make-up on their sides of their cheeks. It is a common method of make-up of Japanese and Korean women in their 20's.
46 0 0 0 OA Hans Bergerの夢 —How did EEG become the EEG?— その1
- 著者
- 宮内 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.20-27, 2016-02-01 (Released:2017-03-01)
- 参考文献数
- 24
Hans Bergerがヒトの脳波の発見者であり, α波とβ波の名付け親であることはよく知られている。しかしそれ以上のことを知っている人は少ない。Bergerは脳と心の関連を解明するために脳血流を計測し, 脳温を計測し, そしてついに脳波を発見した。しかしそれは同時に, 脳波がアーチファクトかもしれないというBerger自身の, そして他の研究者からの疑念を晴らすための長くて困難な道への入口にすぎなかった。そして当時のドイツを席巻していたナチスとの関係に苦しみながら, ようやく栄光を掴んだにもかかわらず, 意に反して脳波研究をやめなくてはならなかった。Bergerの研究と生涯, 当時の社会や脳研究の実態を調べれば調べるほど, 単に脳波を発見した精神科医ではなく, まともな増幅器や記録装置がなかった時代に, 脳と心の関連を脳活動計測によって研究しようと苦闘した20世紀初頭の生理心理学者としての姿が浮かび上がってくる。その姿を三回に分けて紹介する。その1では, 脳波の研究を始める前にBergerが行った研究, それらの研究と脳波の研究との関連について述べる。その2では, Bergerが行った脳波の研究の詳細と, 脳波が当時の神経生理学に受け入れられなかった理由について考察する。その3では, 脳波が神経生理学や臨床医学に受け入れられていった過程と, その後のBerger, 特にナチスとの関係, 自殺の原因などについて述べる。
46 0 0 0 1.動物と経皮感作型食物アレルギー
- 著者
- 猪又 直子
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.3, pp.491-497, 2021-03-20 (Released:2021-03-20)
- 参考文献数
- 26
近年,食物アレルギーの発症機序において経皮感作の重要性が認識されてきた.これまでに報告された経皮感作型食物アレルギーは5つに大別することができる.すなわち,(1)アトピー性皮膚炎乳児に発症する食物アレルギー,(2)美容性,(3)職業性,(4)動物刺咬傷によるもの,(5)動物飼育によるものである.前3者の感作源は食品やその成分であるのに対し,後2者は生きた動物由来の成分であり,食品との交差反応によって食物アレルギーが誘発される.
46 0 0 0 OA 『枕草子』初段考
- 著者
- 東 望歩
- 出版者
- 全国大学国語国文学会
- 雑誌
- 文学・語学 (ISSN:05251850)
- 巻号頁・発行日
- vol.230, pp.75-87, 2020 (Released:2021-12-30)
46 0 0 0 OA タヌキが利用する果実の特徴―総説
- 著者
- 高槻 成紀
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.237-246, 2018 (Released:2019-01-30)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 3
タヌキNyctereutes procionoidesが利用する果実の特徴を理解するために,タヌキの食性に関する15編の論文を通覧したところ,タヌキの糞から103の植物種の種子が検出されていた.これら種子を含む「果実」のうち,針葉樹2種の種子を含む68種は広義の多肉果であった.ただしケンポナシHovenia dulcisの果実は核果で多肉質ではないが,果柄が肥厚し甘くなるので,実質的に多肉果状である.また,乾果は30種あり,蒴果6種,堅果4種,穎果4種,痩果4種などであった.このほかジャノヒゲOphiopogon japonicusなどの外見が多肉果に見える種子が3種あった.果実サイズは小型(直径<10 mm)が57種(55.3%)であり,色は目立つものが70種(68.0%)で,小型で目立つ鳥類散布果実がタヌキによく食べられていることがわかった.「大型で目立つ」果実は15種あり,カキノキDiospyros kakiはとくに頻度が高かった.鳥類散布に典型的な「小型で目立つ」果実と対照的な「大型で目立たない」果実は10種あり,イチョウGinkgo bilobaは検討した15編の論文のうちの出現頻度も10と高かった.生育地にはとくに特徴はなかったが,栽培種が21種も含まれていたことは特徴的であった.こうしたことを総合すると,タヌキが利用する果実には鳥類散布の多肉果とともに,イチョウ,カキノキなどの大型の「多肉果」も多いことがわかった.テンと比較すると栽培植物が多いことと大きい果実が多いことが特徴的であった.
46 0 0 0 OA 戦争の衝撃と国鉄の人的運用
- 著者
- 林 采成
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.46-62, 2010-10-30 (Released:2017-08-30)
- 参考文献数
- 62
The purpose of this paper is to analyze the personnel management of Japanese National Railways (JNR) during the wartime period and clarify the postwar implications of that policy. When the Sino-Japanese War broke out, JNR faced great instability of railroad labor and a concomitant attenuation of skills. In response, JNR reinforced its internal training system and adjusted the disposition of its limited human resources. Through the expansion of incentives including allowances, bonuses and fringe benefits, the decline of real wages was halted. Programs for the ideological reinforcement of laborers' spirit and lifestyle were implemented as well. However, as the war escalated to become the Pacific War, labor supply was further restricted, finally running short, and the quality of labor consequently deteriorated. As a countermeasure, JNR implemented administrative streamlining and established a personnel maintenance committee, focusing human resources allocation within the organization according to importance. Female workers and students were employed as a new source of labor. In particular, to compensate for a marked decline in living standards, chances of promotion were expanded. Railroad operational efficiency was achieved through this personnel management style and in 1943 JNR reached the highest level of productivity since its foundation. Nonetheless, in the face of a transportation crisis and with a mainland battle seeming imminent, JNR could not avoid conversion to a military organization. For this conversion, a new rank of Vice Associate Railroad Officer was established as a temporary measure and more than 100,000 personnel were promoted to this rank and the existing Associate Railroad Officer. At the same time, the lowest rank of employee was abolished. These wartime measures and the military organization of JNR were reformed during the radical postwar reorganization of Japanese National Railways under the Allied occupation of Japan.
- 著者
- H. M. EL-HINDI H. A. AMER
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.505-510, 1989 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 6 7
Six variable supplementations of thiamine magnesium, and sulfates were given to 30 male adult rats in their diets. After 3 weeks, the concentrations of thiamine in the blood and liver and those of cholesterol, phospholipids, and triglycerides in the serum were determined. Blood thiamine level did not reflect the vitamin content in liver. Sufficient and/or excessive intake of the 3 supplementations caused an increase in liver thiamine content and body weight gain; it also caused a reduction in serum cholesterol level without a change in the levels of serum triglycerides and phospholipids. Deficiency of both magnesium and sufate salts in thiamine-supplemented groups decreased body weight gain and liver thiamine content with a significant elevation of serum triglycerides.
46 0 0 0 OA 薬剤師のジャーナルクラブ
- 著者
- 青島 周一 桑原 秀徳 山本 雅洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.10, pp.948-950, 2016 (Released:2016-10-01)
- 参考文献数
- 5
前景疑問に対する問題解決に、Evidence-based Medicine(EBM)の実践は必要不可欠である。しかしながら我が国では、EBMに対する薬剤師の認知度は高いとは言えない。「薬剤師のジャーナルクラブ」は論文抄読会をインターネット上で開催することで、EBM学習の場を提供する取り組みである。取り組み当初より、視聴者数は徐々に増え、現在ではコメント投稿機能を用いた活発な議論が展開されている。論文から深い考察や新鮮な驚きを得たことを示唆するコメントも多く、当取り組みは、EBM学習の場を提供するという点において、一定の役割を果たせるものと思われる。
- 著者
- Masahiko Takeda Naoki Ishio Toshihiro Shoji Naoto Mori Moe Matsumoto Nobuaki Shikama
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.6, pp.1020, 2022-05-25 (Released:2022-05-25)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 9
46 0 0 0 OA パンデミック下におけるインフォデミックとアカデミアの関わり
46 0 0 0 OA 水の酸化分子触媒の新展開
- 著者
- 八木 政行
- 出版者
- Japan Society of Coordination Chemistry
- 雑誌
- Bulletin of Japan Society of Coordination Chemistry (ISSN:18826954)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.67-74, 2011-05-31 (Released:2011-08-31)
- 参考文献数
- 84
Artificial photosynthesis is expected as one of promising clean energy-providing systems in future. Development of an efficient catalyst for water oxidation to evolve O2 is a key task to yield a breakthrough for construction of an artificial photosynthetic device. Recently, significant progress has been reported in development of the molecular catalysts for water oxidation based on manganese, ruthenium and iridium complexes. The molecular aspects of the catalysts in chemical, electrochemical, and photo- or photoelectro-driven water oxidation were reviewed to provide hints to design an efficient catalyst. This review will mainly cover the related progress in the last 5 or 6 years.
46 0 0 0 OA 列車内販売の「かにめし弁当」によるブドウ球菌食中毒
- 著者
- 高橋 広夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.467-468, 1989-10-05 (Released:2009-12-11)
46 0 0 0 OA 学力・政策・責任
- 著者
- 矢野 眞和
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.65-81, 2012-06-15 (Released:2013-06-17)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
本稿では,「政策」という補助線を設けることによって,学力と責任の関係を考察する。はじめに,学力政策の基本的枠組みに基づいて,学力政策の特質を二つ指摘し,この特質と責任の関係を述べた。一つに,学力は,生徒と教師の相互行為から生産される共同生産物であり,製品のような製造物責任を問うことが難しい。いま一つの特質として,教育に投入される資源の性質に着目する必要があり,法的責任とは別に教育費の経済的責任が重要になる。 第二に,学力の生産関数を測定する困難性を整理した。この困難に早急な解決を図ろうとする政治勢力が重なると「もっともらしいけれども,危うい」政治ショーが起きやすくなる。 第三に,困難な学力問題を広く理解するためには,国民の意識ないし世論の動きを視野に入れる必要性があることを指摘し,私たちが実施した「教育と社会保障の意識調査」結果を報告した。わが国の生涯政策への関心・選好・税負担の意識には,強いシルバーポリティクス(年齢格差)が働いており,教育政策への関心は二次的,三次的な優先順位になっている。「教育劣位社会」とでもいうべき日本の現状を明らかにした。 最後に,わが国の生涯政策の経済的責任がねじれていることを踏まえて,学力政策とトータルの教育政策を議論する一つの道筋を提示した。
46 0 0 0 OA 喫煙の気管支喘息への影響
- 著者
- 小田嶋 博
- 出版者
- 日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.237-246, 2005-08-01 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 60
46 0 0 0 OA 自然言語処理技術をサービスの現場へ導入する際のちょっとしたポイント
- 著者
- 山下 達雄
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1-2, 2019-03-15 (Released:2019-06-15)
46 0 0 0 OA 水田生態系におけるアメリカザリガニのタガメへの影響
- 著者
- 大庭 伸也
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Entomology and Zoology
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.93-98, 2011 (Released:2016-10-22)
46 0 0 0 OA ニューヨーク市SoHo地区における芸術家街を契機としたジェントリフィケーション
- 著者
- 笹島 秀晃
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.106-121, 2016 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
都心衰退地区に形成される芸術家街は, ジェントリフィケーションの契機となることが知られてきた. 芸術家の存在は, 不動産開発や飲食業・文化産業の集積を促し, その過程において地価は高騰し居住者階層は移り変わる. 先行研究では, ジェントリフィケーションのメカニズムを分析するにあたって, おもに不動産業者や消費者としての中産階級に注目してきた. ところが, 重要なアクターであるはずの美術作品の展示・売買を行う画廊については十分な分析がなされてこなかった. 本稿の目的は, 芸術家街を契機とするジェントリフィケーションのメカニズムを, 画廊の集積過程に着目して分析することである. 具体的な検討事例は, 1965年から71年の間に芸術家街から画廊街へと転換した, アメリカ合衆国ニューヨーク市SoHo地区である. 芸術家街であるSoHo地区に画廊が集積した要因は, 安価な地価や広い室内空間を備えた未利用の工場建築物の存在だけではなかった. むしろ, ニューヨーク市における美術業界の構造変動の中で, 画廊経営者が自身の美術的立場を明確にする際に準拠した, 芸術家街の表象という文化的要因が重要であったことを明らかにする.
46 0 0 0 OA 自然勾配学習法-学習空間の幾何学
- 著者
- 甘利 俊一
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.735-739, 2001-10-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 21
46 0 0 0 OA 保健物理学会が見えない!
- 著者
- 田中 俊一
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.133-134, 2018 (Released:2018-11-27)
- 被引用文献数
- 1