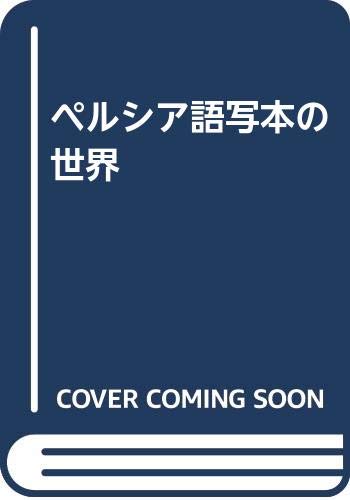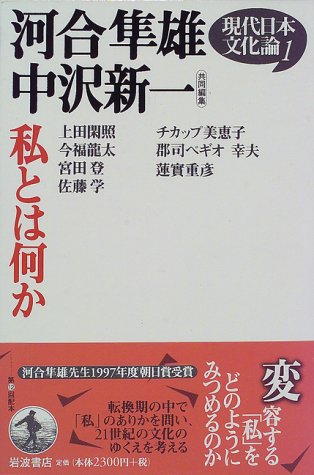1 0 0 0 OA 知識形成における多様性と客観性の認識論的基盤の研究
科学的知識の客観性=「価値自由」という見方は、近年科学哲学上でも影響力を失いつつある。科学は、社会のなかの一事業として、様々な諸価値や状況からの影響をうけざるをえない。しかし、同時にそれは、特定の個人や立場のみに占有されるのではなく、社会全体に共有される公共知でもあるべきだ。こうした新しいいみでの「客観性」概念を担保するひとつの要素として、近年、科学者共同体内部の価値観、信念背景、立場、観点などの「多様性」を重要視する見方が、提起されている。さまざまな観点をもつものによる共同体部の相互批判により、科学知のステイタスを確保するという見解だ。本研究は、このような見解の是非と意義を理論的に検討する。
1 0 0 0 モデル誤差抑制補償器を用いた既存制御系のロバスト化
- 著者
- 岡島 寛
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.168-175, 2023-03-10 (Released:2023-03-21)
- 参考文献数
- 32
- 著者
- 鷲谷 里美
- 雑誌
- 女子美術大学研究紀要 = Bulletin, Joshibi University of Art and Design (ISSN:13477188)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.46-52, 2022-03-31
1 0 0 0 OA 『ワインズバーグ・オハイオ』 -新しい現実
- 著者
- 東山 嘉一 Higashiyama Yoshikazu
- 出版者
- 神奈川大学大学院 外国語学研究科
- 雑誌
- 神奈川大学大学院言語と文化論集 (ISSN:1341612X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.71-85, 1999-12-05
1 0 0 0 ペルシア語写本の世界 = جهان نسخههای خطی فارسی : نمونههائی از دستنوشتههای ایرانی, ماوراء النهری و هندی
- 著者
- 羽田亨一 近藤信彰共編
- 出版者
- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 IR ヒンドゥスターニー音楽の成立 : ペルシャ語音楽書からみる北インド音楽文化の変容
1 0 0 0 OA 「新感覚派」は「感覚」的だったのか? : 同時代の表現思想と関連して
- 著者
- 島村 輝
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 = 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.109-118, 2011-03
- 著者
- 中釜 英里佳 吉村 匠平
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護学教育学会
- 雑誌
- 日本看護学教育学会誌 (ISSN:09167536)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3-2, pp.103-114, 2023 (Released:2023-03-17)
- 参考文献数
- 26
〔目的〕ディプロマ・ポリシー(DP)及び教養教育カリキュラムに着目し、看護系大学における教養教育の違いを検討した。〔方法〕大学設置基準大綱化以前設立の2学部以上ある(以下、前複)10大学と大綱化以後設立の単科(以下、後単)13大学のDP及び教養教育科目の内容を分析し検討した。〔結果〕DP内で前複大学が多かった語は、『解決』、『多様』、『情報』、後単大学が多かった語は、『看護』、『身につける』、『地域』、『態度』だった。教養教育科目の内容は、前複大学が『情報』科目や「外国語」科目で選択の機会が保証されており、後単大学は「英語」科目において専門教育の教養教育への侵入性が高かった。〔考察〕前複大学では、言語能力や情報活用能力など学習の基盤となる資質・能力育成のための科目を含む教養教育カリキュラムが編成されていた。一方後単大学では、教養教育を専門教育である看護学の学習の基礎として位置づけている傾向が見られた。
1 0 0 0 OA 日本の看護系大学におけるInstitutional Research活動・業務の実態
- 著者
- 丹治 史也 南部 泰士 柿崎 真沙子 嶋谷 圭一 西本 大策 黒澤 昌洋
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.69-79, 2023-02-25 (Released:2023-03-16)
- 参考文献数
- 22
背景 : 看護系大学のIR活動・業務の実態, IR組織の担当項目と他の看護系大学と比較したい項目の差を検討した. 方法 : 看護系大学48校・424名を調査対象とした. 結果 : 回答者116名のうち51名 (44.0%) が「IRの名称・役割ともに知っている」, 82名 (70.7%) が「IR組織がある」に該当した. IR組織の担当項目と比較したい項目ともに教学関連が多く, 入学志願者・卒業生調査では比較したい項目での割合が高かった (p<0.05). 考察 : 看護系大学ではIR組織の設置が先行し認知度が低く, また現状の分析項目と他大学と比較したい項目にはギャップがあるため, 各大学でIRの共通理解を図ることが課題である.
1 0 0 0 OA 脊髄損傷に対する再生医療
- 著者
- 堀 桂子 中村 雅也 岡野 栄之
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.53-59, 2013 (Released:2013-04-11)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
脊髄損傷とは, 外傷などによる脊髄実質の損傷を契機に, 損傷部以下の知覚・運動・自律神経系の麻痺を呈する病態である. 本邦の患者数は10万人以上おり, 加えて毎年約5,000人の患者が発生しているにもかかわらず, いまだに有効な治療法は確立されていない.しかし, 近年基礎研究が進歩し, 中枢神経系も適切な環境が整えば再生することが明らかになった. 脊髄損傷に関する研究も著しく進み, すでに世界中でさまざまな治療法が臨床試験に入りつつある. わが国でも, 神経幹細胞, 嗅神経鞘細胞, 骨髄細胞などを用いた細胞移植療法のほか, 顆粒球コロニー刺激因子 (granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) や肝細胞増殖因子 (hepatocyte growth factor, HGF) などの薬剤が臨床応用される可能性がある.本稿では, 脊髄再生に関する基礎研究を, 細胞移植療法とそれ以外に分けて述べ, さらに現在世界で行われている臨床試験について概説する.
1 0 0 0 志賀直哉の自己と超越者--「城の崎にて」の静謐
- 著者
- 富沢 成実
- 出版者
- 立命館大学人文学会
- 雑誌
- 立命館文學 (ISSN:02877015)
- 巻号頁・発行日
- no.515, pp.p235-249, 1990-03
1 0 0 0 松下圭一政治理論による「社会科学と社会」への影響の包括的研究
本研究は、2015年5月に85歳で逝去した政治学者・松下圭一の政治理論が社会科学と社会に与えた影響を可視化し、包括的に把握することを目的とする。松下の政治理論は社会科学にも社会にも大きな影響を与えた。地方自治、行政学、政治学の分野での活動は、革新自治体、2000年地方分権改革の理論的支柱となった。松下は、丸山眞男と並び「その理論が社会を動かした」研究者だが、影響が広範なために分野ごと時代ごとで分断され、体系的・包括的な把握や評価がなされていない。本研究で、関係者のヒアリングや資料を用い、松下圭一の「社会科学と社会に与えた影響」を、高度成長期以降の現代史的視角とともに進め、明らかにしていく。
1 0 0 0 私とは何か
- 著者
- 河合隼雄 中沢新一共同編集
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 レトリックとしてのスキ-マ--樋口一葉「十三夜」の場合
- 著者
- 山本 雅子
- 出版者
- 日本文体論学会
- 雑誌
- 文体論研究 (ISSN:13425498)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.39-50, 1997-03
1 0 0 0 多径間連続斜張橋の軽量合成端2箱桁の構造提案とその特性
- 著者
- 杉山 裕樹 川崎 雅和 金治 英貞 八木 知己
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.A1-0719, 2023 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 37
本研究では主径間650mを3径間有する多径間連続斜張橋の主桁構造に対して,一般的な扁平六角形鋼床版1箱桁断面に代わり,維持管理性および構造合理性の向上を目的に超高強度繊維補強コンクリート床版を用いた端2箱桁断面を提案する.提案構造に対して,耐荷性能の観点から,扁平六角形鋼床版1箱桁との構造特性の違いを明らかにし実現性を確認する.さらに,端2箱桁を実現する上での重要な課題である耐風安定性について,風洞試験による種々の断面形状に対する検討を行い,実現性のある主桁形状を提案する.活荷重および温度荷重に対して構造設計し,扁平六角形鋼床版1箱桁との比較により,提案構造は実現可能な構造であることを確認した.また,バネ支持試験およびフラッター解析により,フラッターに対する耐風安定性を確保可能な断面形状を示した.
- 著者
- 西田 千夏 合田 友美
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.4_771-4_781, 2022-10-20 (Released:2022-10-20)
- 参考文献数
- 20
目的:発達障害特性が感じられる看護師への合理的配慮を含めた現任教育に関する実態調査から,その現状と課題を明らかにする。方法:看護師長等の看護管理者へ,無記名自記式質問紙による調査を実施した。調査内容は,発達障害の診断を受けていることを申告,または「発達障害特性があるのではないか」と看護管理者が感じる看護師の特性や教育上の配慮,合理的配慮に関する考え,等である。結果:看護管理者の認識する課題には,コミュニケーションの取りづらさ,本人が特性を自覚する必要性,他の看護スタッフとの関係,および合理的配慮の周知が存在した。結論:合理的配慮を申告しやすいシステム作りと,感情に焦点を当てすぎない面接により本人の自覚を促すことが必要である。発達障害特性について学びを深め,他のスタッフと一緒に解決方法を探り,到達目標の具体化と業務・環境調整の重要性が示唆された。
- 著者
- やまだ りよこ
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.91-101, 2022 (Released:2023-02-27)
日本笑い学会の研究企画の一環として取り組んでいる「聞き書き」。長く「笑い」に携わり表からは見えない側面や裏面を知る、そんな現場にいた方の体験談を記録に残す<拾遺録>第二弾です。 今回は、上方漫才のレジェンドー夢路いとし・喜味こいしのマネージャーとしてお二人を長く支え続け、それ以前からも裏方として関西の笑芸界を間近で見つめてきた津田愼一さんの歩みを一人語りの形でまとめました。コロナ禍のため長い休止をはさんで2回計7時間におよんだインタビューは昭和の上方笑芸史を物語る貴重な回想録ともなり、そのため特別に「その1」「その2」にわけて構成。「その2」は次号に掲載します。
1 0 0 0 OA 《研究ノート》「ユーモアとは何か」とは何か ユーモアの定義をめぐるRuchの問題
- 著者
- 鵜子 修司 成瀬 翔
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.53-69, 2022 (Released:2023-02-27)
現状、研究者たちがユーモアを明晰に定義できていないことは、批判されるべきである。この事実は、研究者たちが「ユーモアとは何か」について、非専門家の期待に応える知識を示せないというだけでなく、ユーモアを研究するための基本的な道具を持たないことをも意味している。これは約四半世紀前にWillibald Ruchが既に提起していた問題である(Ruch, 1998)。彼はこの問題を二つに改めている。すなわち、「これまで我々はどのようにユーモアを用いてきたか」および「我々はどのような科学概念としてユーモアを理解したいか」である。本稿では、これらを「Ruchの問題」と総称し、特に後者の問題に答えるため必要な議論のロード・マップを提示した。これはユーモアを定義するために、「どのような型を採るべきか」および「どのような要素を含めるべきか」という、二つの問いに大別された。これらは問題に対処するトップ・ダウン/ボトム・アップな方針に、それぞれ対応する。
1 0 0 0 OA 近赤外分光法による体脂肪測定
- 著者
- 沢井 史穂 白山 正人 武藤 芳照 宮下 充正
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.155-163, 1990-06-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 5 3
近赤外分光法は, 従来, 食品成分の非破壊分析法として用いられてきたが, 近年アメリカにおいてこの方法をヒトの体脂肪率の推定に応用する試みがなされ, 携帯用小型測定器が開発された.本研究は, この測定法を日本においても汎用可能とするための日本人用体脂肪率推定式を決定しようとするものである.年齢, 体格, 身体活動量の異なる18~58歳の健常な男性69名, 女性52名を対象に, 身長, 体重, 体脂肪率を測定した.体脂肪率は, 水中体重法, 皮脂厚法, 近赤外分光法の3方法を用いて推定した.近赤外分光法の測定部位は, 予備実験の結果, アメリカにおける先行研究と同様, 他の測定法による体脂肪率との相関が最も高かった上腕二頭筋中央部とし, 947mmの近赤外線を照射して光吸収スペクトルを得た.被検者の1/2について, それぞれの近赤外スペクトルの値を水中体重法による体脂肪率に回帰させ, 体脂肪率推定式を算出した.残り1/2の被検者の近赤外スペクトルをその式に代入して得た体脂肪率と水中体重法によって求めた体脂肪率の値とを比較したところ, r=0.89 (SEE=2.9) の高い相関が認められた.これは, 水中体重法と皮脂厚法との間の相関係数とほぼ同様の値であった.アメリカ人用の推定式の決定には, 近赤外分光法スペクトルの他に身長, 体重, 年齢の変数を加えた方が, 相関係数の値が高くなったと報告されているが, 日本人の場合, 他の変数を加えても相関係数の値はほとんど変わらなかった.また, 測定部位における左右差はなかった.したがって, 近赤外分光法による日本人用体脂肪率の推定式は, 体脂肪率=54.14-29.47× (947nmにおける近赤外スペクトル値) 〔r=0.88 (p<0.01) , SEE=3.2〕と決定された.