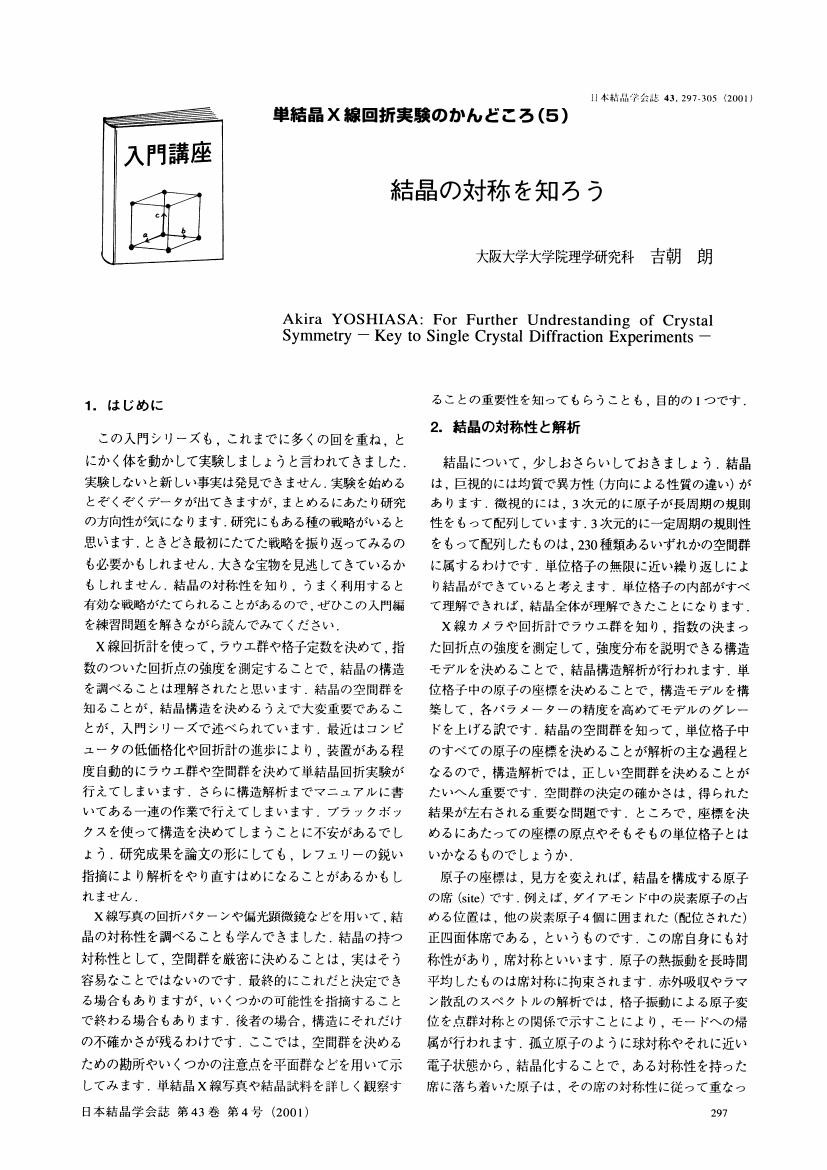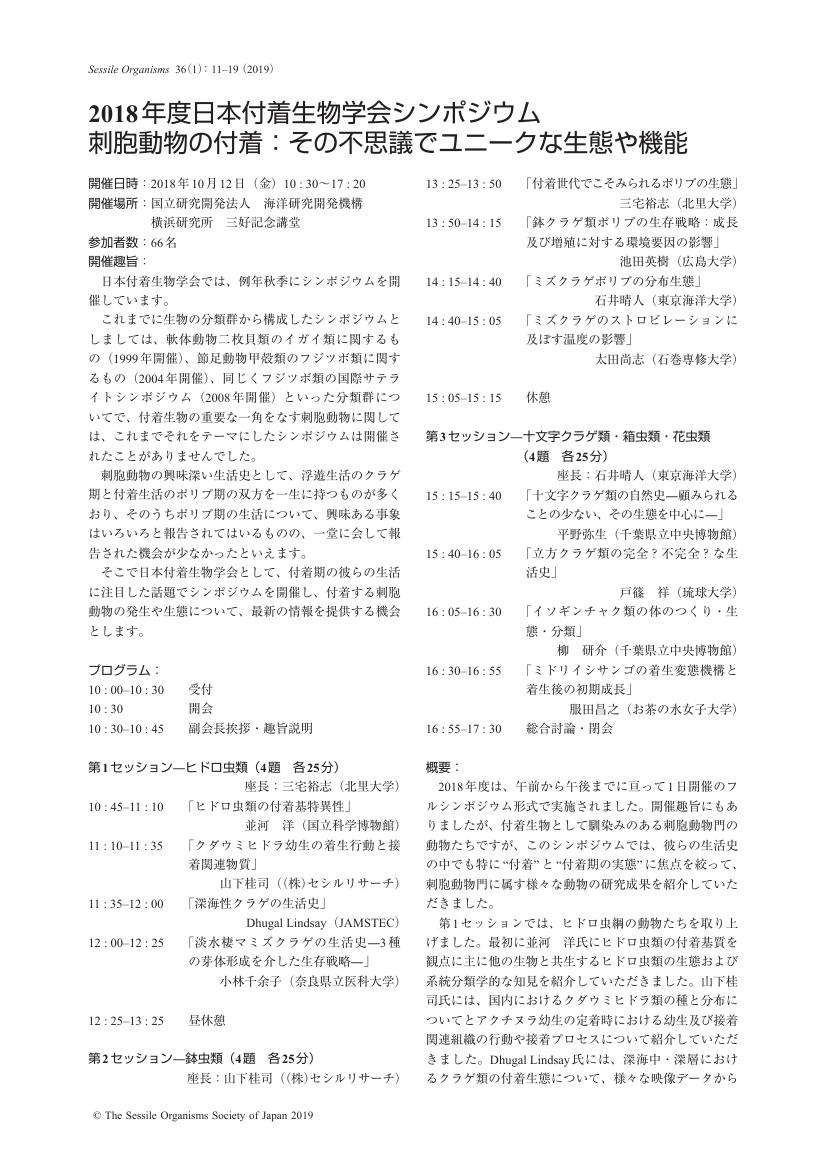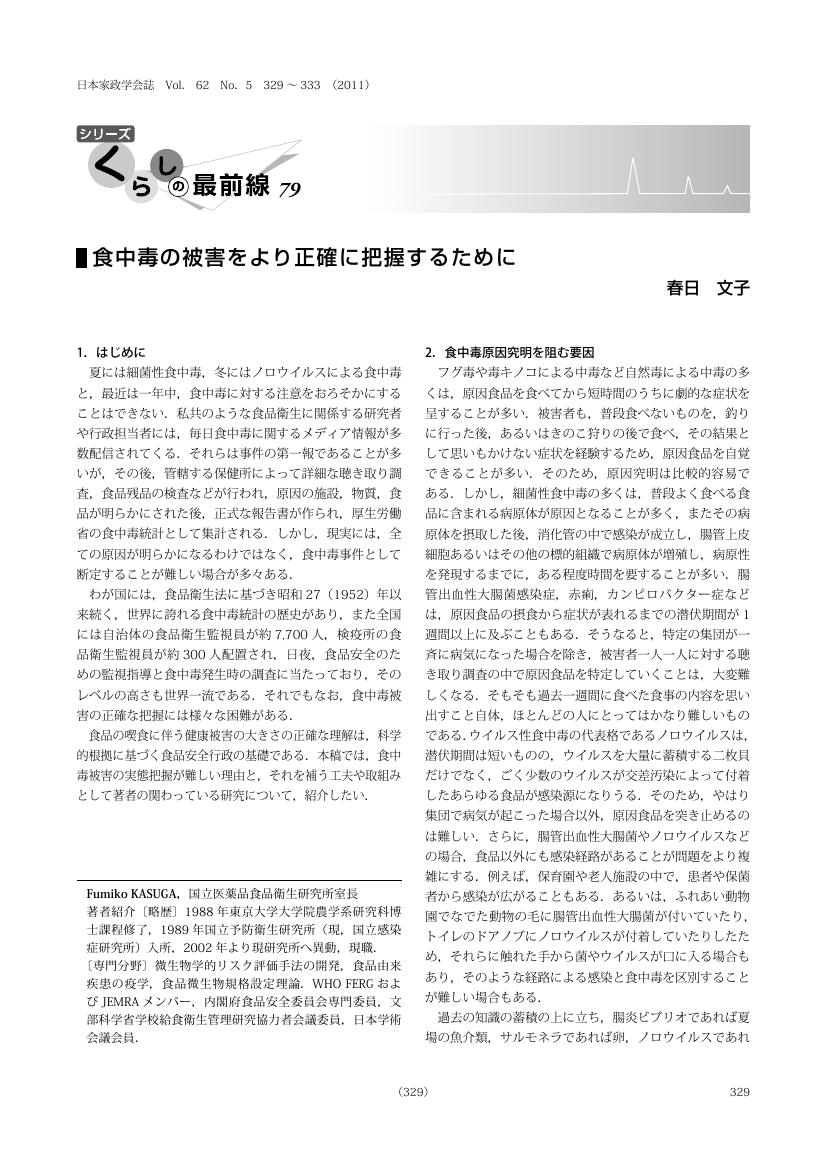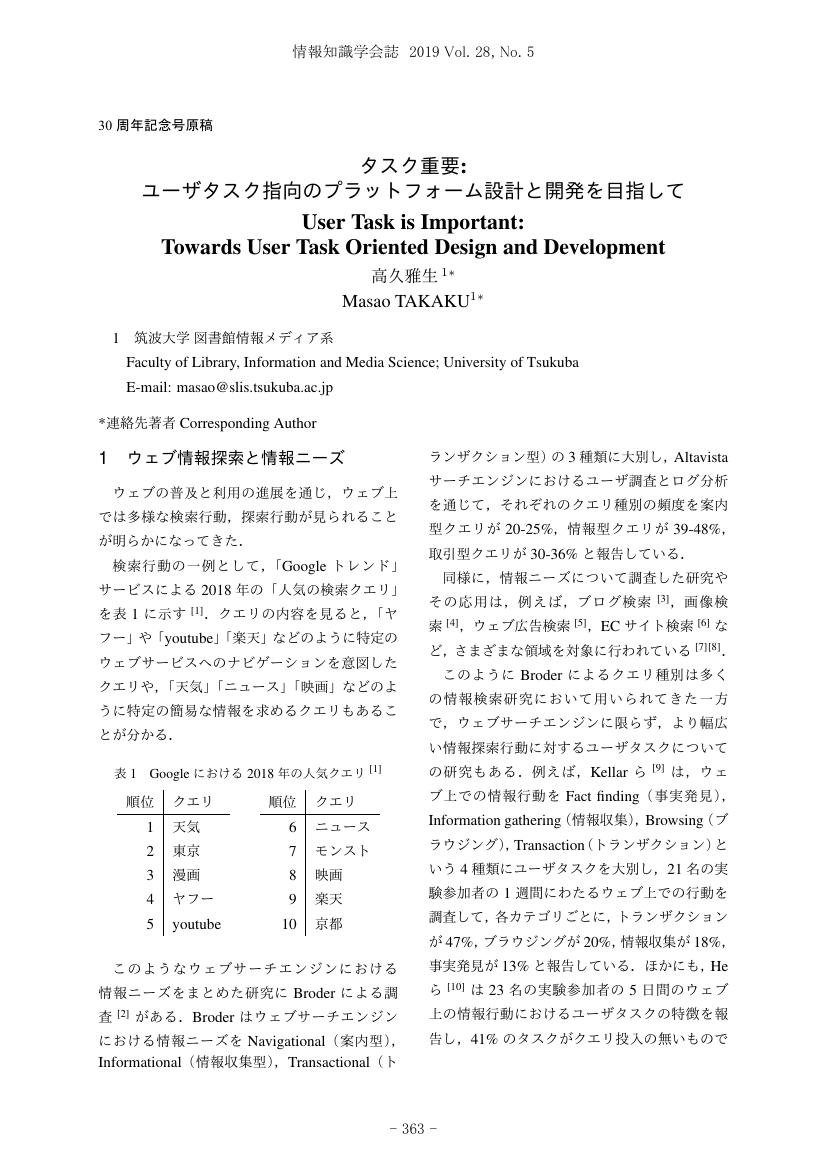3 0 0 0 OA ルールに基づきカメラワークを設定するシステムと「小津ルール」のシミュレーション
- 著者
- 立花 卓 小方 孝
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第23回全国大会(2009)
- 巻号頁・発行日
- pp.1J1OS211, 2009 (Released:2018-07-30)
物語の表現方法としての映像表現カメラワークを対象とした研究を行っている。ルールに基づきカメラワークを適用するシステムを試作し、そのルールを小津の『東京物語』の分析から「小津ルール」として得た。『東京物語』を再現した映像に試作を適用し、実際の映像をどの程度表現できるかシミュレーションした結果、約60%表現可能であった。芸術作品において何処までルール化が可能なのかを問うことが本研究の意義である。
3 0 0 0 OA 結晶の対称を知ろう
- 著者
- 吉朝 朗
- 出版者
- The Crystallographic Society of Japan
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.297-305, 2001-08-31 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 1
- 著者
- 宗藤 伸治 刑部 有紀 山外 啓太 岩永 純平 三浦 秀士 古君 修
- 出版者
- 一般社団法人 粉体粉末冶金協会
- 雑誌
- 粉体および粉末冶金 (ISSN:05328799)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.8, pp.471-474, 2017-08-15 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 9
Poly-crystalline Ba8AuxSi46−x clathrate with p-n junction was synthesized for electric power generation from heat under no temperature difference. The n-type Ba8Au4.5Si41.5 and the p-type Ba8Au5.5Si40.5 powder were stacked in the graphite die and sintered by a Spark Plasma Sintering (SPS) method at 1073 K for 5 min with pressure of 50 MPa. The Au composition of Ba8Au4.5Si41.5 and Ba8Au5.5Si40.5 side in the sintered sample were Ba7.8Au4.2Si41.8 and Ba7.8Au5.2Si40.8, respectively. It was found that the Au composition was gradually changed near the interface with thickness of around 500 micrometers. Electric power generation test under no temperature difference was performed by using the sample cut to contain the interface of two layers. The electric power increased by only heating and the maximum voltage can be observed around 2 mV at 773 K. These results suggested that electron excitation occurred near the n/p interface and generated electrons and holes diffuse to n-type and p-type semiconductor side, respectively.
3 0 0 0 OA 有機リン化合物の反応
- 著者
- 稲本 直樹 秋葉 欣哉 山田 紘一
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.105-128, 1970-02-01 (Released:2010-01-28)
- 参考文献数
- 166
- 被引用文献数
- 1 1
3 0 0 0 OA カンボジアと日本の中学校および高等学校教科書の比較-ウイルスはどう取り上げられているか
- 著者
- 都築 功 松田 良一
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.635-636, 2020 (Released:2020-11-27)
- 参考文献数
- 3
カンボジアの公立中学校理科および高等学校生物の教科書では健康や衛生,食物,農業,ヒトの生殖と発生など生活に関連した内容が多く扱われている.ウイルスに関しては,カンボジアの教科書では中学校第3学年と高等学校第1学年で感染症および生物の分類と関連させそれぞれ3~4ページにわたり扱っている,韓国,中国,台湾の教科書においてもカンボジアと同様,ウイルスを数ページにわたって扱っている.一方,日本の理科や生物の教科書では生活と関連の深い内容の扱いが少なく感染症も扱わない.日本の教科書ではウイルスは本文外で参考として1ページ以下の扱いであり,他の国々と大きく異なっている.日本の生物教育で生活や健康に関連した内容をもっと多く扱うこと,ウイルスに関しては本文で扱うよう見直すことが必要と考える.
3 0 0 0 OA 材料化学における実利用へ向けたグラフ生成アルゴリズムを基礎とする分子生成モデル
- 著者
- 武田 征士 濱 利行 徐 祥瀚 岸本 章宏 中野 大樹 古郷 誠 本江 巧 藤枝 久美子
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)
- 巻号頁・発行日
- pp.4F4GS10o04, 2021 (Released:2021-06-14)
AIやデータなどを駆使して材料開発を加速させるマテリアルズ・インフォマティクスが世界的な注目を集めている。中でもAIによる分子構造デザインは、ポリマーなど様々な材料分野への応用が可能であるのみならず、生成モデルの文脈で近年数多くの報告がなされている。しかしながら、これらの技術のほとんどがディープ生成モデルであるため、膨大なデータや複雑なハイパーパラメータ調整、長時間にわたる事前学習を必要とする。さらに、得られたモデルも化学者には解釈ができず、構造生成の細かいチューニングも行えなため、材料化学の実利用に即しているとは言い難い。我々が開発した手法およびツールは、化学構造のエンコードおよびデコード部がグラフ理論を基礎とするアルゴリズムにより構築済みであるため、事前学習が不要かつ、特徴ベクトルや構造生成過程の詳細を理解可能であり、原子単位での細かい調整が可能である。本ツールにより、人間の専門家と比較した場合に数10~100倍程度の構造生成のスピードが確認された。本発表では、基本的な方法論に加え、ツールの実装内容、各材料分野における事例などを紹介する。
3 0 0 0 OA ポリ乳酸の屋外劣化に及ぼす日照および降水の影響
- 著者
- 大澤 敏 城殿 威生 小川 俊夫 附木 貴行
- 出版者
- MATERIALS LIFE SOCIETY, JAPAN
- 雑誌
- マテリアルライフ学会誌 (ISSN:13460633)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.73-78, 2001-04-30 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
生分解性プラスチックであるポリ乳酸は, 高い力学的性質と透明性を兼ね備えており, 近年農業用シートなど屋外での用途が期待されている.実用的な視点から見ると使用中の耐候性の評価や分解予測が必要である.本研究では, ポリ乳酸 (PLA) フィルムを屋外暴露試験し, 試料の破断強度に与える日照量 (光分解) と降水量 (加水分解) の影響を重回帰分析した.その結果, 破断強度は, 降水量Wと加水分解の反応速度定数kを掛け合わせた変数雁7と, 日照時間Uと光分解の反応速度定数k'を掛け合わせた変数k'Uの関数で表すことができた.また, PLAの分解に及ぼす影響を重回帰式の標準偏回帰係数で比較したところ加水分解と光分解で約2: 3であり, 光分解の影響がかなり大きいことが明らかになった.またこの結果は実験室内で加水分解速度と光分解速度を別々に測定した結果と一致した.
3 0 0 0 OA <場所>と<あいだ>:知の統合への哲学的アプローチ
- 著者
- 野家 啓一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
- 雑誌
- 横幹 (ISSN:18817610)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.81-88, 2010 (Released:2016-03-21)
- 参考文献数
- 21
Modern science developed its methodology through the Scientific Revolution in 17th century and established its social institution through the second Scientific Revolution in 19th century. In the latter period, science was specialized from science to sciences, and lost its unity as “natural philosophy.” The mainstream of scientific thought consists of atomism, analytic method and local optimization. To overcome the specialization of science and to realize the integration of knowledge, it may be stimulating to consult the intellectual heritage of Japanese thought which includes the unique concepts of “place (basho),” “scene (bamen)” and “between-ness (aida).”
3 0 0 0 OA 免疫機構におよぼす針灸の効果
- 著者
- 五十嵐 宏 丹野 恭夫 光藤 英彦 代田 文彦
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.117-121, 1975-12-30 (Released:2010-10-21)
- 参考文献数
- 7
- 出版者
- 日本付着生物学会
- 雑誌
- Sessile Organisms (ISSN:13424181)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.11-19, 2019-01-01 (Released:2019-06-11)
3 0 0 0 OA 大学生アスリートの注意欠如・多動症状と脳震盪の関連
- 著者
- 金澤 潤一郎 榎本 恭介 鈴木 郁弥 荒井 弘和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.47-51, 2019 (Released:2019-01-01)
- 参考文献数
- 9
大学生アスリートを対象としてADHD症状と海外で最も研究が進んでいる脳震盪経験との関連について検討した. その結果, 第一にADHD症状が陽性となった大学生アスリートは27.9%であった. 第二にADHD症状がスクリーニング調査によって陽性となった場合, 脳震盪経験が高まることが示された (β=0.25, p<0.05). これらの結果から, スポーツ領域においても脳震盪の予防や対応の観点からコーチやアスリート支援をしている心理士などに対してADHDについての知識の普及が必要となる. さらに大学生アスリートは学生であることから, 脳震盪からの復帰の際には, 競技面と学業面の両側面からの段階的復帰を考慮する必要がある.
3 0 0 0 OA 100 m走後半の速度低下に対する下肢関節のキネティクス的要因の影響
- 著者
- 遠藤 俊典 宮下 憲 尾縣 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.477-490, 2008-12-10 (Released:2009-02-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 8
The purpose of the present study was to clarify the factors involved in deceleration in the last phase of a 100 m sprint by comparing the kinetics of the lower limb joints between the maximal running velocity phase (Max) and the deceleration phase (Dec). Five male collegiate sprinters, running 60 m and 100 m at maximal effort, were videotaped with high-speed cameras (250 fps) and the ground reaction force (1000 Hz) was measured at the 50-m and 85-m points. The kinematics and kinetics of the lower limb joints were then calculated. The results were as follows: 1) The deceleration of running velocity was due to a decrease of stride frequency. 2) In the Dec, braking impulse increased, but propulsion impulse decreased significantly. 3) Significant decreases were found in joint torque and negative power exerted by ankle plantar flexors. 4) Hip negative work exerted by hip joint torque in the late support phase tended to decrease, and it is thought that this decrease affected the delay of hip-flex movement during the early recovery phase. These results reveal that the function of the ankle has a direct influence on deceleration, and suggest that the negative work exerted by hip joint torque during the support phase may help to maintain hip-flex movement during the early recovery phase in the final phase of the 100-m sprint.
3 0 0 0 OA 戦前国鉄における現業委員会の構成と運営
- 著者
- 林 采成
- 出版者
- Business History Society of Japan
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.3_27-3_50, 2013 (Released:2016-03-18)
- 参考文献数
- 41
This paper examines the constitution of JNR Workplace Committee and its administration from the prewar to the wartime periods and analyzes the process and the reality of JNR labor movement that subsumed into the Familism. The Workplace Committee attempted to internalize the labor movement by letting the laborers display their dissatisfaction as well as the demand as a part of adaptation mechanism within the internal organization, sometimes offering the opportunities for fringe benefits and promotion. This was the reality of the labormanagement relations that subsumed into the JNR’s Familism. Even though the Workplace Committee functioned as the passage to obtain better working environment during the 1920s, in the 1930s, it became to be a defensive mechanism that dealt with delayed follow-ups for the issues brought up by the pay raise and the promotion. In the background of such transformation, there was the existence of the antagonistic labor union that pressured the authorities to consider the demand of the Workplace Committee, as well as the JNR’s economic foundation that enabled its realization. The adaptation of the Workplace Committee to the JNR system deepened in the 1930s and it transformed into ‘the Service Society’ during the wartime period. The price of “service” was the improvement of labor treatment and the stability of livelihood. The postwar JNR labor-management relations began on the basis of these factors.
- 著者
- Hiroki Okada Masahiro Mimura Shunsuke Tomita Ryoji Kurita
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- pp.20SCP23, (Released:2021-01-29)
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 今野 颯人
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.721-725, 2021 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA アーケードの原型としての日覆いに関する研究
- 著者
- 辻原 万規彦 藤岡 里圭
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.596, pp.85-92, 2005-10-30 (Released:2017-02-11)
- 参考文献数
- 176
- 被引用文献数
- 5 4
The purpose of this paper is to analyze "Hi-oho-i" (awning for street) as the origin of Arcades in Japan in detail. First, according to the nation-wide research of the Japan Chamber of Commerce and Industry in 1935, "Hi-oho-i" was distributed all over the country. Next, it was confirmed to use the word "Hi-oho-i" at Edo era, to exist old photograph and dairy on the "Hi-oho-i" at Meiji era (1890s), and to be declining the "Hi-oho-i" about 1950s. Finally, the relation between the construction of the "Hi-oho-i" and the formation of the community and urban space in shopping streets was examined.
3 0 0 0 OA 高等教育研究・私史
- 著者
- 天野 郁夫
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.157-176, 2017-07-31 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 13
この度日本高等教育学会から,学会創立20周年行事の一環として学会設立当時の状況や設立の背景や学会の現状について,初代学会会長として一文を寄稿するような依頼があった.学会設立の事情を語るには,高等教育研究の制度化の源流に遡って見ていく必要がある. 私が高等教育研究に関心を持ったのは,1960年代の初め,東京大学大学院の教育社会学専攻に在籍していた頃からである.当時,高等教育研究は,細々とやられていたにすぎなかった. 学会創設以前の高等教育研究に大きな役割を果たしたのは,大学史研究会,IDE文献研究会,広島大学・大学教育研究センター(現高等教育研究開発センター)などである.特に1972年のセンターの創設は,エポックメイキングな出来事であった. その後,マス化の進展とともに顕在化し始めた,高等教育の新しい政策課題に対応するため,文部省は国立教育研究所に高等教育研究室を置いたほか,大学入試センター(1976),放送教育開発センター(1978),学位授与機構(1991),国立学校財務センター(1992)など,次々に大学関連のサービスセンターを開設し,そこに調査研究関連の部局を置いた.さらに国立大学に大学教育関連のセンターが順次設置され,私立セクターでも,同様のセンターを設ける大学が現れ始めた.また1980年代の後半になると,玉川大学出版部が高等教育関連の本を,積極的に刊行し始めた. 東京大学教育学部にようやくわが国最初の「高等教育論講座」の新設が認められたのは1992年,私が初代の教授に就任した. このように高等教育学会の創設に至る,私が体験してきた高等教育研究の流れと時代状況の変化をたどってみると,1990年代半ばという時代が,その機が熟したというべきか,様々な条件と環境が,学会の設置に向けて整い始めた時代であったことがわかる. 1997年9月には東京大学で発会式を迎えることになった.私たちからみれば新世代の高等教育研究者たちの熱意と努力の賜物である.教育社会学の関係者が多いとはいえ,多様な専門分野から理事が選出され,他の教育関連諸学との関係が深まった.高等教育研究者の集まる「アゴラ(広場)」の出現である. その後,2010年から11年にかけての『リーディングス 日本の高等教育』の刊行は時代の「激流」に巻き込まれ,「あわただしく」対応を迫られてきた高等教育研究に対する「批判的反省と学問的な問い直し」の試みという点で,重要な意味を持っている. 今世紀に入ってからの新自由主義的な政策誘導の高等教育改革という高等教育研究を取り巻く状況の激変は,研究者に期待される専門性の内容が大きく変化し,その幅が著しく拡大したことを示唆している.改革は具体的な実践の問題になった.そのことが例えば学会の年次大会における研究発表の,また会員の出身専門分野のどのような変化をもたらしているのか.20周年を迎えた学会が,「批判的自省」を踏まえた「さらなる発展と飛躍」をはかるためにも,改めて検証する必要があるだろう.教育社会学以外のどのような学問的・理論的よりどころをもとに知識と理解を深めていくのか,学会は今それを問われているといってよい. 世代交替の進んだ学会が主導的に,研究の新しいフロンティアを切り開いていくことを期待している.
- 著者
- 森永 輝樹
- 出版者
- 公益財団法人 損害保険事業総合研究所
- 雑誌
- 損害保険研究 (ISSN:02876337)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.135-161, 2011-11-25 (Released:2020-06-21)
3 0 0 0 OA 食中毒の被害をより正確に把握するために
- 著者
- 春日 文子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.329-333, 2011-05-15 (Released:2013-08-12)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA タスク重要: ユーザタスク指向のプラットフォーム設計と開発を目指して
- 著者
- 高久 雅生
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.363-366, 2019-03-31 (Released:2019-04-12)
- 参考文献数
- 28