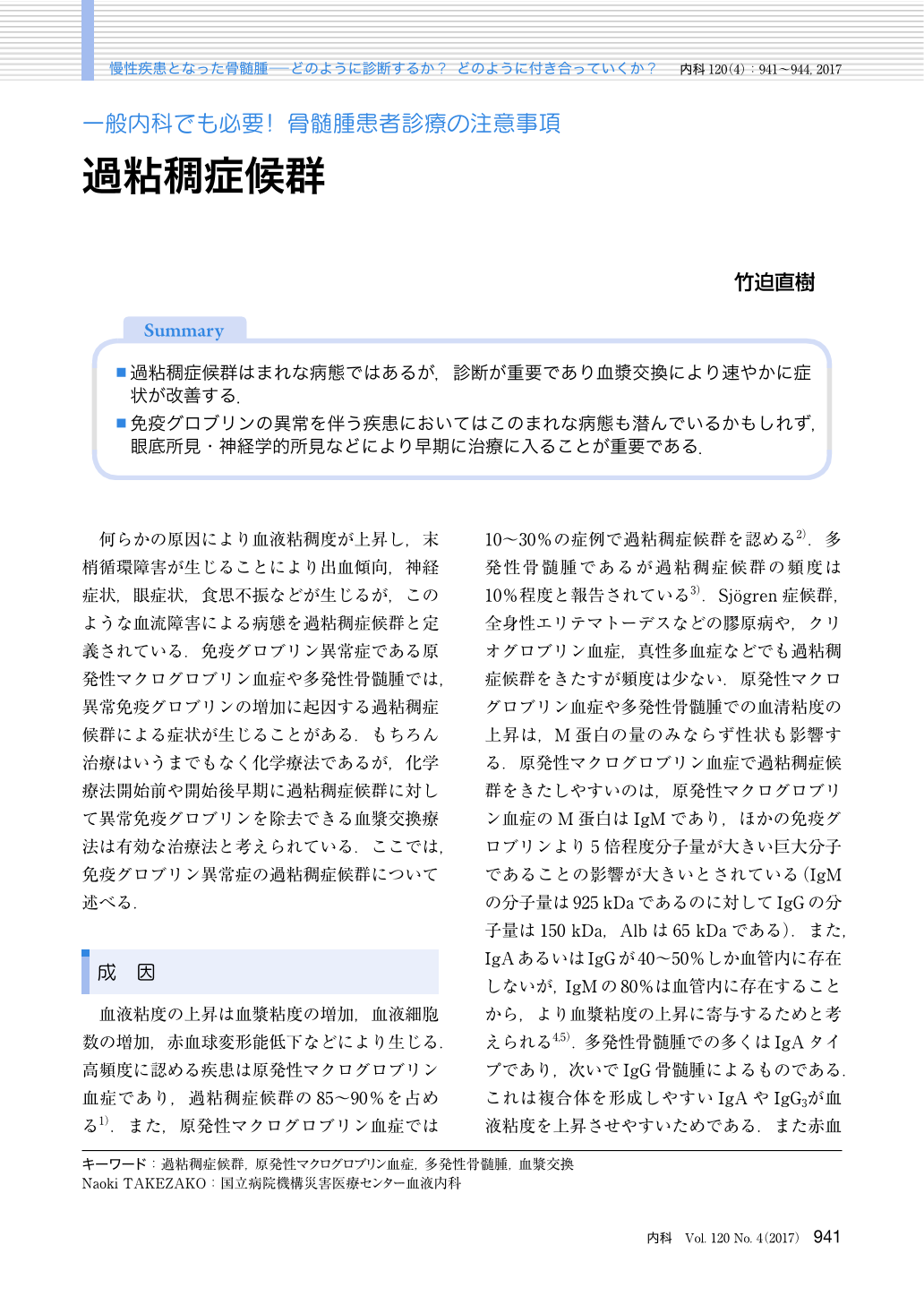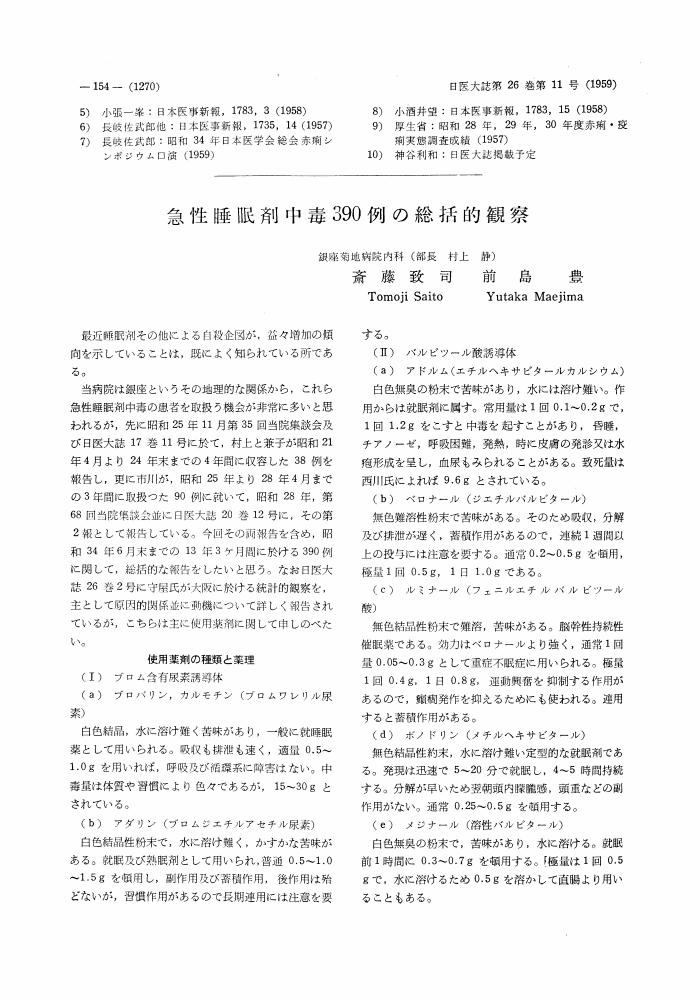1 0 0 0 IR 今村紫紅における琳派受容について : 『伊勢物語』を題材とした作品を中心に
- 著者
- 原田 礼帆 Harada Ayaho
- 出版者
- 名古屋大学大学院人文学研究科図書・論集委員会
- 雑誌
- 名古屋大学人文学フォーラム (ISSN:24332321)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-17, 2020-03-31
図1-図8は都合により掲載しておりません
1 0 0 0 OA 足趾エクササイズが足内側縦アーチに及ぼす影響について
- 著者
- 城下 貴司 福林 徹
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.397-400, 2012 (Released:2012-09-07)
- 参考文献数
- 22
〔目的〕足趾機能は重要とされているが未知な部分も多い.我々は足趾機能の臨床研究や筋電図解析を行ってきた.しかしながら足趾機能と足内側縦アーチ(MLA)の関係はわかっていない.本研究の目的は足趾エクササイズとMLAの関係を検討することである.〔対象〕健常者20名,20足,平均年齢22.5±3.6歳とした.〔方法〕被験者にはタオルギャザリングエクササイズ(TGE)と3種類の足趾エクササイズ(母趾底屈エクササイズ,2から5趾底屈エクササイズ,3から5趾底屈エクササイズ)をランダムに行い,各々の足趾エクササイズ前後にNavicular Drop (ND)を計測し比較した.〔結果〕介入前NDは4.34 mmであった,TGE後NDは4.94 mmで有意差を示さなかったが,母趾底屈エクササイズ後NDは5.25 mmで有意に低下した.2から5趾底屈エクササイズ後NDは3.07 mm,3から5趾底屈エクササイズ後NDは3.32 mmとなり各々有意にNDは低下しなかった.〔結語〕母趾底屈エクササイズはMLAを低下させた.TGEは特に変化を示さなかった.しかしながらその変化は母趾底屈エクササイズに類似した.一方で2から5趾底屈エクササイズ,3から5趾底屈エクササイズはMLAを高くする効果を示しMLAとの関係性を示した.
1 0 0 0 雨と植物反応に関する研究:(VI) 降雨後の萎凋現象
- 著者
- 木村 和義
- 出版者
- 養賢堂
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.271-279, 1984
降雨後, インゲンマメ葉が萎凋する現象がみられた。降雨後の萎凋現象について解明するため, 人工降雨実験装置を使って, その萎凋現象の実態と原因について実験的に検討を行った。<br>1) 雨の日, 鉢植したインゲンマメを屋外におき, 降雨を21時間受けた後に葉が萎する現象がみられた。萎凋の状態は, 葉縁が上方に曲り, 葉全体がいくらか杯状を呈し, 極端な場合は葉縁付近の裏面が表面から見える程度にまき上る状態になった。<br>2) 雨の日を想定した人工降雨装置を使って, 降雨処理後の萎凋現象の実態を詳細に検討した。降雨処理した植物の葉は, 処理終了後15分位から萎れ始め, 1時間目に最高の萎凋程度に達し, その後数時間かけて回復した。萎凋程度は処理期間が長い程強く現われ, またその回復も遅くなる傾向がみられた。またサツマイモ葉でもほぼ類似の萎凋現象がみられた。インゲンマメ葉の場合, 1~2日間の降雨処理では, 程度の弱い萎凋がみられ, 3~4時間後にはほとんど回復したが, 3日以上の処理では強い萎凋現象がみられ, 処理後24時間目でも葉縁に多少の異常が残った。また若令葉ほど, 老令葉と比して, 萎凋の程度が大きい傾向がみられた。<br>3) 降雨処理後の萎凋現象は, 地下部への雨の浸入が遮断された場合, 逆に地下部を浸水状態にして降雨処理した場合でも, あるいはイオン交換水で降雨処理した場合でも, 同じ程度に起こることから, 地下部の状態や水道水中の諸成分に関係なく, 雨水が地上部 (葉) を濡らすことによって起こると考えられた。<br>4) 降雨処理後における葉の蒸散量は急激に増大した。処理後1時間目の蒸散量は11.5mg/cm<sup>2</sup>であり, 無処理区の4mg/cm<sup>2</sup>の約3倍の値を示した。この1時間における降雨区の根による吸水量は5.2mg/cm<sup>2</sup>であり, 蒸散による水の排出は根による水の吸収の約2倍の値であった。<br>5) 降雨処理された植物から切離された葉の乾燥速度は無処理区のものよりも著しく大きい値を示した。無処理区の植物からの切葉は1日後, 切断時の生鮮重の約50%まで減少した程度であったが, 降雨処理した場合は約10%まで減少した。<br>6) 上述のような結果から, 降雨後の萎凋現象の原因は, 地上部の雨水接触によって, 葉の表面構造に障害をうけ, 水の透水性を増し, その結果, 蒸散作用が急激に増大したことによると推察された。
1 0 0 0 OA 膝関節,足関節,第一中足趾節関節の肢位に伴う足底腱膜の形状変化
- 著者
- 中島 明子 山路 雄彦 大橋 賢人 七五三木 好晴 渡邊 秀臣
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C3O3051, 2010 (Released:2010-05-25)
【目的】 内側縦アーチは足底に加わる体重負荷を分散して支え,着地時の衝撃を吸収し,効率のよい歩行を遂行する上で重要である.内側縦アーチの支持機能の一つとして足底腱膜があげられ,足趾背屈や荷重などの動作に合わせて伸縮を繰り返している.足底腱膜の伸張ストレスはウインドラス機構やアキレス腱足底腱膜連動機構により増大すると報告されているものの,客観的に足底腱膜の形状変化を検証した報告は極めて少ない.そこで,本研究は動態の観察が可能である超音波画像診断装置を用いて,足底腱膜の解剖学的特徴を明らかにし,膝関節,足関節,第一中足趾節関節(以下,母趾)の肢位の違いによる足底腱膜の形状変化について検討することを目的とした.【方法】 対象は健常成人16名(男性8名,女性8名,年齢25.6±4.6歳,身長166.8±7.1cm,体重58.9±7.5kg)とし,測定肢は全例左側とした.計測には超音波画像診断装置(GE社製LOGIQ BookXP Series,Bモード,8MHz)を用い,超音波プローブを踵骨隆起と第一中足骨頭を結ぶ線に平行に当て,長軸方向にて足底腱膜内側部を抽出した.測定部位は踵骨より1cm末梢部(以下,踵骨部)とし,背臥位にて計測した.測定肢位の条件として,膝関節は屈曲位(股関節膝関節90度屈曲位)・伸展位(股関節中間位膝関節完全伸展位)の2肢位,足関節は45°底屈位・中間位・最大背屈位の3肢位,母趾は中間位・最大背屈位の2肢位を定め,3関節の肢位を組み合わせて,計12肢位にて足底腱膜の厚さを計測した.各肢位3回ずつ計測し,平均値を求めた.なお,基本肢位は股関節中間位,膝関節伸展位,足関節中間位,足趾中間位と定義した.また,各肢位は安楽姿勢とし,関節運動は全て他動運動にて行った.統計学的分析では,信頼性の検討に級内相関係数(以下,ICC)を用い,膝関節および母趾の肢位別の比較に対して対応のあるT検定を用いた.さらに,足関節の肢位別の比較に対して一元配置の分散分析後Tukeyの多重比較を用いた.なお,有意水準は5%未満とした.【説明と同意】 対象者全員に研究の趣旨及び方法を説明後,同意を得た上で計測を行った.【結果】 踵骨部の足底腱膜は表層で高エコー,深層で低エコーとして描出された.ICC(1,1)は0.902であり,基本肢位での足底腱膜の厚さは2.41±0.39mmであった.母趾背屈により足底腱膜の厚さは0.11±0.18mm薄くなり,いずれの測定肢位においても有意に薄くなった(p<0.05).一方,膝関節や足関節の肢位変化に伴う足底腱膜の厚さには有意な差は認められなかった.【考察】 足底腱膜は踵骨隆起に起始し,第1-5趾基節骨に停止する強靭な腱組織である.踵骨部の足底腱膜は組織学的に表層の線維配向性が張力方向であるのに対し,深層は網目状であることから,本研究において足底腱膜の表層は高エコーとして描出されたと考えられる.また,足底腱膜の境界線が鮮明に描出されたことで同肢位,同部位での計測で高い信頼性が認められたと考えられる.母趾背屈による足底腱膜の形状変化は,ウインドラス機構が働き,足底腱膜の停止部が遠位上方に巻き上げられ,長軸方向への伸張ストレスを有するために生じたと考えられる.一方,膝関節や足関節の角度と足底腱膜の厚さに関連がみられなかったことの理由としては,膝関節伸展,足関節背屈により下腿三頭筋が伸張され,距骨に対して踵骨が底屈方向に動くものの,足底腱膜の厚さが変動するまでの長軸方向の伸張ストレスはかからなかったと推察される.【理学療法学研究としての意義】 超音波画像診断装置を用いて足底腱膜を鮮明に描出することが可能であった.Javier Pascual Huertaらによると,足底腱膜の厚さは踵骨部にて2.70±0.69mmであったと報告しており,本研究の結果とほぼ一致する値であった.本研究にて高い信頼性を得られたことからも,超音波検査法は足底腱膜の評価ツールとして臨床的有用性が高いと判断できる.このため足底腱膜炎などの踵骨部の足底腱膜の厚さに異常をきたす疾患の評価に,超音波装置を用いて経時的な変化をみることが可能であると考えられる.また,足底腱膜の形状変化は主に母趾背屈により生じ,足関節や膝関節の評価肢位には影響されないことが示された.
1 0 0 0 OA 人体通信を使用したウェアラブル機器の開発とヘルスケアシステムへの試適用
- 著者
- 山本 恵理 佐々木 良一
- 雑誌
- 研究報告コンシューマ・デバイス&システム(CDS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-CDS-12, no.26, pp.1-8, 2015-01-19
近年,自分で自分の健康を管理するヘルスケアへの関心が高まっている.ヘルスケアを目的とするデバイスとして用いられるウェアラブルデバイスは,WBAN(Wireless Body Area Network) とよばれる人体を中心とした無線通信により,ハブ端末であるスマートフォンやタブレットとの通信が行われている.この WBAN は,IEEE 802.15.6 によって規格が策定されており,物理層として UHF 帯狭帯域通信,超広帯域通信 (UWB),人体通信 (電界方式) の三種類が技術仕様として定められている.我々はこの中でも,ウェアラブルデバイスへの搭載が期待されている,消費電力の少ない人体通信について着目した.人体通信機能がウェアラブルデバイスへ実際に搭載された事例は ID カードと玩具の数例しかなく,その通信の安定性については,まだいくつかの課題が残されている.そこで著者らは,ハブ端末とウェアラブルデバイス間の通信を,人体通信を用いて行う場合の人体上の伝搬特性と周波数特性について,21MHz と 455kHz の搬送波周波数を用いて測定を行った.この結果,21MHz に比べ 455kHz の搬送波周波数を使用した場合,安定した通信が行えることを確認した.この結果を用い,455kHz の搬送波周波数を使用し,人体通信で情報を送信または受信するウェアラブルデバイスの製作と,受信した情報をスマートフォンで可視化するためのアプリケーションの開発を行い,さらに,人体通信の実用化のため,通信の安全性を考慮し,AES を用いて通信傍受対策を行った.これにより,雑音にそれほど強くない符号化 ASK でも,手先や顔の周辺では人体通信でウェアラブル機器同士の通信が十分行えることを確認したが,足付近では雑音によって情報が誤って受信されるという課題が残った.今後、雑音対策として FEC の実装を行い,消費電力に考慮した対策を行っていく予定である.
1 0 0 0 OA 世界遺産候補「百舌鳥・古市古墳群」の天皇陵古墳の意味をめぐる葛藤
- 著者
- 藤村 健一
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2019年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.146, 2019 (Released:2019-03-30)
百舌鳥・古市古墳群は大阪府堺市・藤井寺市・羽曳野市に位置する。2017年、これに含まれる45件49基の古墳が文化審議会によって世界文化遺産の推薦候補に選ばれた。早ければ2019年にも正式に登録される可能性がある。 推薦候補に選ばれた古墳には、仁徳、履中、反正、応神、仲哀、允恭の各天皇陵古墳が含まれる。このうち、堺市の仁徳天皇陵古墳は国内最大、羽曳野市の応神天皇陵古墳は国内2番目の規模の古墳である。天皇陵は皇室祭祀の場所であり、現在でも宮内庁が管理している。 発表者は2016年、京都の拝観寺院(観光寺院)の意味や性格について報告した。これらの寺院に対しては、主に宗教空間、観光施設、文化財(文化遺産)という3種類の意味が付与されている。これらは互いに異なる立場から意味づけられており、対立する可能性をはらむ。1980年代の古都税紛争は、このことが一因であったと考えられる。 天皇陵古墳に対しても、様々な立場から異なる意味づけがなされ、そのことが摩擦を生んでいる。本研究では百舌鳥・古市古墳群の天皇陵古墳を事例として、そこに付与された様々な意味を整理・分析するとともに、意味づけを行っている人々についても調査し、摩擦の要因を解明する。 百舌鳥・古市古墳群の天皇陵古墳に付与された意味は、①聖域、②文化財、③観光地・観光資源、④世界文化遺産の4つに集約できる。①の見方をとるのは主に宮内庁と皇室、神道界の人々や、皇室崇敬者・皇陵巡拝者である。②の見方をとるのは、主に古墳を研究する歴史(考古)学者である。③は地元の経済界や観光業者・観光客を中心とした見方である。④は、主に世界遺産登録運動の推進役である地元自治体や文化庁の見方である。 ①~④の意味には重複する部分もあるが、これらは一致しておらず齟齬もある。とりわけ、①の見方をとる立場と②の見方をとる立場の間では対立が顕著である。天皇陵古墳を②とみなす歴史学者は、宮内庁を批判してきた。 ①の立場をとるのは宮内庁・皇室関係者だけでない。神道界や皇室崇敬者、皇陵巡拝者には、天皇や皇室に対する尊崇の念をもって天皇陵を聖域視する人々が少なくない。 こうした人々の中には、天皇陵古墳をもっぱら文化財とみなす歴史学界や、世界遺産登録を推進する行政、観光資源としての利用を図る業者を非難する人もいる。ただし、現代の皇陵巡拝者は必ずしも皇室崇敬者に限らない。彼らは「陵印」収集など多様な動機をもって巡拝している。
- 著者
- 前川 玲子
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.67-71, 2003-09-30 (Released:2017-04-10)
1 0 0 0 過粘稠症候群
1 0 0 0 OA 幼児・児童における分配の公正さに関する研究
- 著者
- 渡辺 弥生 Watanabe Yayoi
- 巻号頁・発行日
- 1989
思えば、筆記用具片手に、幼稚園へ観察に通ったのが、本研究のはじまりだった。運動場で戯れる子どもたちを終日追いかけて、何か興味の湧く研究テーマに出会わないかと漠然と期待しながら、観察していた。砂場、ブランコ、すべり台、体育館、いたるところで、たくさんの子が夢中で遊んでいる姿は、半ば戦場のように騒然としていた。まったく、無秩序で、混沌たる世界のようであり、時にはケンカする場面も見かけられたが、ふっと不思議に思えたことがあった。それは、もうすでに子供達なりの世界ができあがっているんだなあ!といった印象であった。 ・・・
ニューロプシンの海馬機能における役割を検討する目的でニューロプシンノックアウト(KO)マウスの学習・記憶障害を行動学的に検討した.KOマウスはwildのlittermateに比較し,オープンフィールドテストではより高い活動性を示し,Auditory Startle Reflexでは驚愕反射の増大と延長を,そして水迷路テストでは反応潜時の明らかな延長を認めた.一方,放射状迷路テストと受動的回避学習テストでは両群間で有意差は認められなかった(Obata K,et al.4th World Stroke Congress,Melbourne,Australia,2000).KOマウス脳は病理組織学的にはwildのそれと比較し、シナプスに形態異常のあることが判明した(Hirata A,et al.Mol Cell Neurosci,in press,2001).さらにニューロプシンは海馬LTPに重要な役割を果たしていることが明かとなった(Komai S,et al.Eur J Neurosci 12:1479-1486,2000).従ってニューロプシン欠損は高次脳機能のうち情動障害と空間認知機能障害をはじめとする学習・記憶障害をきたすことが明らかとなった.マウスの一過性前脳虚血モデルを用い,脳虚血負荷後の海馬機能を行動学的に検討した.虚血負荷後CA1錐体細胞死のみられたマウスではすべての行動テストに異常を認めた.一方,細胞死のみられない動物ではオープンフィールドテストや回避学習テストではsham群に比し差異を認めなかったが,水迷路では反応潜時の明らかな延長を認めた.放射状迷路学習での誤反応数は細胞死の有無にかかわらず虚血群とsham群間に差異は認めなかったが,虚血群では空間配置の確認作業や遂行の順序だての欠落を示すと考えられる行動異常,痴呆症にみられる徘徊行動を説明する現象を認めた.従って,脳虚血は明らかな海馬神経障害の有無にかかわらず空間認知機能障害をはじめとする学習・記憶障害をきたすことが明らかとなった(Matsuyama T,et al.J Cereb Blood Flow Metab 17(Suppl 1):S638,1997).以上の所見より,脳虚血に伴う海馬ニューロプシンの低下は学習・記憶障害を引き起こす可能性のあることが明らかとなった.これらの結果は今後の神経行動科学研究に有用であると思われる.
1 0 0 0 OA “電磁場と、その変動・伝播”を小学生に! : 「場」概念から“電磁石”教材に接近
- 著者
- 倉賀野 志郎 有元 恭志
- 出版者
- 北海道大学教育学部教育方法学研究室
- 雑誌
- 教授学の探究 (ISSN:02883511)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.41-63, 1989-03-25
1 0 0 0 OA カルトグラムの作成手法と応用可能性
- 著者
- 清水 英範 井上 亮
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-15, 2008-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
本論文は、統計GISの発展と利活用には統計データの視覚化手法の進展も必要であるとの問題意識の下、地図を敢えて変形させることによって統計データの空間分布の特徴を視覚化する、カルトグラムという視覚化手法の潜在的な魅力と可能性に着目し、その合理的かっ実用性の高い作成手法を構築した。手法構築の基本的方針は、(1) 作成手法の全体像を単純かつ明快にするため、作成問題を最小二乗法で記述すること、(2) 不必要な地図変形を抑制するため、カルトグラム上の地点間の座北方位角を地理的地図上の方位角に可能な限り近づけるという正則化条件を導入すること、の2点であり、この方針に基づいて三種類のカルトグラムの作成手法を提案した。また、幾つかの事例分析を通して、統計データの視覚化手法としての提案手法の有効性を例示した。
1 0 0 0 OA 呼吸筋麻痺をきたしたホタテ稚貝中毒の1例
- 著者
- 井上 卓也 清水 幸雄 鍛治 徹 高崎 眞弓
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.556-558, 1992-07-20 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 7
麻痺性貝毒による呼吸筋麻痺の1例を経験した. 59歳の男性. ホタテ稚貝を知人よりもらい受け, 30~40個食べた. 1時間後より口唇, 両手足のしびれ感が現われ, 2時間後には呼吸が停止した. ただちに気管内挿管を行い, 人工呼吸管理を行った. 6時間後より徐々に筋力が回復し, 15時間後には自発呼吸が回復した. 2日後には四肢の麻痺は完全に消失した. 後遺症もなく退院した.
1 0 0 0 OA 自動車用ターボチャージャ
- 著者
- 岡崎 洋一郎 松平 伸康
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.9, pp.547-552, 1987-09-10 (Released:2011-07-11)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 急性睡眠剤中毒390例の総括的観察
- 著者
- 斎藤 致司 前島 豊
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.1270-1272, 1959-11-15 (Released:2010-10-14)
- 著者
- 生井 達也
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 = Annual review of the institute for advanced social research (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.187-194, 2017-03-31
1 0 0 0 OA 南部フォッサマグナに関連する地形とその成立過程
- 著者
- 貝塚 爽平
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.55-70_1, 1984-07-31 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 98
- 被引用文献数
- 19 18
Landforms in and around the South Fossa Magna, which are shown in Figs. 2 and 3, and the history of their growth during the late Cenozoic are described. The pattern of the tectonic landforms and the history of their growth are explained by a tectonic model shown in Fig. 5.The South Fossa Magna consists mainly of strongly folded and thrust Neogene and Quaternary strata along the subduction and collision zone between the overriding Eurasian plate (or the Eurasian and North American plates) and the subducting Philippine Sea plate. The collision occurred on the north of the Izu Peninsula during the past 1-0.5 Ma. The characteristic landform in the folded zone is flights of elongated domes or ridges, called outer ridges.There are three areas with different topography and tectonic history in central Honshu to the north of the plate boundary; they are, from west to east, 1) the Akaishi Mts-Tokai lowland and offshore area, 2) the Kanto Mts-Misaka Mts-Tanzawa Mts area, and 3) the Kanto Plain-Miura-Boso Hills and their offshore area. To the south of the plate boundary, there are three different belts in the northeastern part of the Philippine Sea (PHS) plate; they are, from west to east, i) the Shikoku Basin, ii) the inner volcanic arc (Izu Inner Bar), and iii) the outer non-volcanic arc (Izu Outer Bar) of the Izu-Bonin arc.The PHS plate moved to the north after the spreading of the Shikoku Basin (30-15 Ma BP), and different physical property and somewhat different speed of movement of the three belts gave different tectonic features to the three areas in central Honshu as is shown in Fig. 5 (A). Then the PHS plate collided with Honshu on the northern side of the Izu Peninsula, and changed the direction of movement to the northwest in 1-0.5 Ma BP. Quaternary uplift of the Akaishi, Tenshu, Misaka, and Tanzawa Mts thus started, while the processes of making the outer ridges ceased under a rather extensional stress field in the Miura-Boso Hills and their offshore area of southern Kanto as shown in Fig. 5 (B). Collision between the northeast Japan arc (on the North American plate) and the Southwest Japan arc (on the Eurasian plate) may have occurred along the Fossa Magna in the Quaternary Period.
1 0 0 0 OA 世界最高齢でエベレスト登頂を成し遂げた日本人登山家の除脂肪量および骨密度
- 著者
- 藤田 英二 赤嶺 卓哉 高井 洋平 川西 正志 Dennis R. Taaffe 柳沼 悠 山本 正嘉
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.18083, (Released:2019-08-07)
- 参考文献数
- 26
Here, in comparison with community-dwelling middle-aged and older men, we investigated the skeletal muscle mass and bone mineral density of a Japanese alpinist (Mr. A) who, at the age of 80 years, is to date the oldest person to have climbed to the summit of Mount Everest (8,848 m). Using dual X-ray absorptiometry, we determined the appendicular skeletal muscle mass index (SMI), total bone mineral density (tBMD), whole body fat-free mass index (FFMI) and fat mass index (FMI) of Mr. A (84.6 yr) and 209 community-dwelling middle-aged and older men (50-79 yr, mean age: 68.1 yr). The SMI, tBMD, FFMI and FMI were 8.79 kg/m2, 1.075 g/cm2, 22.3 kg/m2 and 9.8 kg/m2, respectively, in Mr. A and 7.46 ± 0.81 kg/m2, 1.020 ± 0.100 g/cm2, 18.1 ± 1.9 kg/m2 and 5.5 ± 1.7 kg/m2, respectively, in the community-dwelling middle-aged and older men. The values in Mr. A were higher than those in the community-dwelling middle-aged and older men, with z-scores for the SMI and tBMD of 1.63 and 0.55, respectively. Mr. A maintained a high skeletal muscle mass and bone mineral density even at the age of 84 years, which may have been attributable in part to his long-term training for mountain climbing.
1 0 0 0 OA 添い寝中の死亡事故からみた育児と授乳 : 新聞記事と育児書を中心に
- 著者
- 宮内 貴久
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.207, pp.347-389, 2018-02-28
本論は『朝日新聞』,『読売新聞』の記事から,添い寝中に子どもが死亡する事故について,なぜ発生するのか,死因,住環境,授乳姿勢,死亡年齢を検証することにより,添い寝と授乳の実態と変化を明らかにした。さらに育児書の検討から添い寝がどう捉えられていたのか,適当とされる授乳期間はどの程度だったのか明らかにした。添い寝で死亡する事故は明治期から発生しており,時代によって死因は異なった。1870~1910年代は80%以上が乳房で圧死していた。1920年代になると乳房で圧死は67%,布団と夜具での死亡事故が20%となる。1930年代には乳房での圧死が50%まで減少し,布団と夜具での死亡事故が26%となる。こうした事故は職業には関係なくあるゆる住宅地で発生していた。1940~1960年代前半には深刻な住宅不足問題を背景に,スラムなど極めて劣悪な住環境に居住するブルーカラーの家で事故が発生した。1960年代後半にも住宅の狭小が原因による圧死事故が発生するが,高度経済成長による所得の増加による家電製品の普及とともに,タンス,学習机などの物があふれて部屋が狭小化し,そのため圧死するという事故が発生した。1970年代にはアメリカの育児法が紹介され,うつぶせによる乳児の死が問題視され,さらに死の多様化が進んだ。18冊の育児書の検討から11冊の育児書が添い寝を否定,5冊が注意すべきこととされたこと,また添い寝中の授乳により乳房で窒息死する危険性を指摘する育児書が12冊あったことからも,添い寝の危険性を喚起する新聞記事と一致し,社会問題となっていた。20冊の育児書の検討から,適当とされた離乳開始時期は5ヶ月頃からが3冊,10~12ヶ月が4冊,もっとも遅いのは2~3年だった。時代による離乳期の特徴は特にみられなかった。離乳時期は遅く4~5歳児への授乳,特に末子は5~6歳まで授乳するケースもあった。授乳は母親にとって休息がとれる貴重な時間であり,それが遅い離乳の要因の一つだった。母子健康手帳では添い寝が否定されたが,現実には多くの母親は添い寝をしていた。育児における民俗知と文字知にはズレがみられる。1985年に『育児読本』が大幅改訂され,これまで否定されていた添い寝が,親子のスキンシップとして奨励されるように変化した。