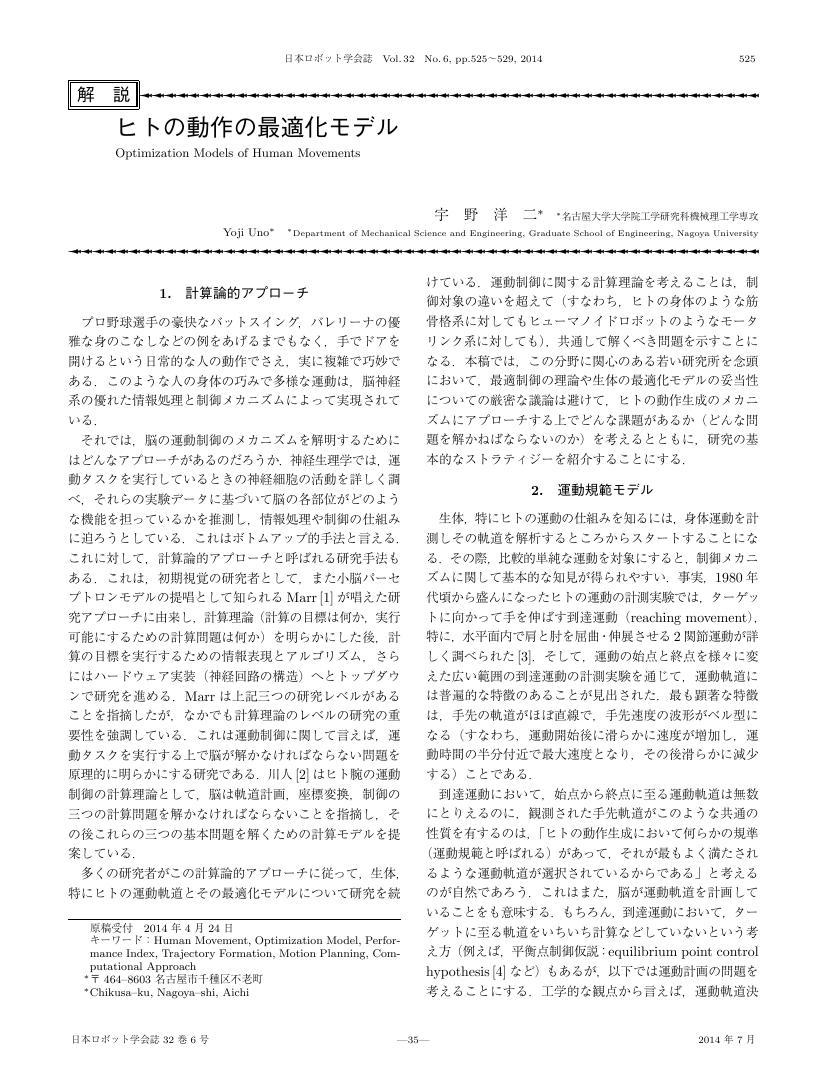- 著者
- 中上 晨介
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.115-158, 2019 (Released:2019-06-11)
- 参考文献数
- 5
本稿では,不平等回避モデルを拡張し,ネットワーク上のcontribution gameにおけるプレイヤーの利得関数に不満と罪悪感のパラメータを用いて新たなモデルを構築し,ナッシュ均衡とabsorbing setを導出した.ネットワーク上でcontribution gameを行った研究では,プレイヤーは隣り合う2人のプレイヤーとつながりを持つサークルの形をした社会的ネットワーク上で公共財への拠出にContributionするかDefectするかの戦略の決定を行う.また,プレイヤーの利得関数はつながりを持つ周囲のプレイヤーの戦略に基づいて決まる.本稿では,不満と罪悪感のパラメータの範囲によっては,多くの人が貢献する状態もナッシュ均衡,absorbing setとして実現することを示した.結果の解釈としては,ある条件下で,人々が持つ罪悪感が不満よりも大きいとき,多くの人がネットワーク上のcontribution gameにおいて協力的行動をとるということである.
- 著者
- Tsukasa Waki Satoshi Shimano Takahiro Asami
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.11-15, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
The parasitic mite Riccardoella (Proriccardoella) triodopsis Fain and Klompen, 1990 was sampled from two localities in Chiba prefecture, Japan. The sampled mites were identified based on palps and leg chaetotaxy and structure of famulus on tibia I. This study is represented by the second record of R. triodopsis inhabiting the pulmonate snail and the first discovery in Japan.
- 著者
- 小川 真実 森貞 亜紀子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.6, pp.398-408, 2002 (Released:2003-01-28)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
リバビリン(レベトール®)はC型慢性肝炎の治療にインターフェロンα-2b(IFNα-2b)と併用して使用される抗ウイルス薬である.本薬は主にRNAウイルスに対して幅広い抗ウイルス作用を示すことが報告されており,C型肝炎ウイルス(HCV)の代替ウイルスとしてウシウイルス性下痢症ウイルスを用いた感染細胞系において,IFNα-2bと併用することにより増強作用が認められた.本薬の作用機序として,宿主のイノシン一リン酸脱水素酵素の阻害作用,RNAウイルスのRNA依存性RNAポリメラーゼ(RdRp)の阻害作用等が報告されていた.最近,リバビリンがHCVと同じRNAウイルスであるポリオウイルスのRdRpによりRNAに取り込まれ,新生RNAの鋳型となり,突然変異を誘導することが明らかにされた.更に,リバビリンにより誘導される突然変異のわずかな増加により,ウイルスの感染能が激減することが証明された.このRNAウイルスに対する変異原としての作用は本薬の新規機序であり,本薬は新しいクラスの抗ウイルス薬として分類されるものと考えられる.
- 著者
- Makoto Hasegawa Michio Murakami Shuhei Nomura Yoshitake Takebayashi Masaharu Tsubokura
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.248, no.2, pp.115-123, 2019 (Released:2019-06-26)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 8
After Fukushima disaster in 2011, the health status of the region’s residents deteriorated. We analyzed the health status, care needs, and access to health services among evacuees and non-evacuees using healthcare expenditure (for self-employed and unemployed individuals aged < 75 years) and long-term care expenditure (mainly for individuals aged ≥ 65 years). Fukushima Prefecture was divided into four areas according to their evacuation status: non-EOAs (municipalities that did not include evacuation order areas (EOAs)); EOAs/non-EOAs (municipalities that included both EOAs and non-EOAs); short-term EOAs (municipalities where the EOA designation was lifted in most areas by fiscal year (FY) 2011); and long-term EOAs (municipalities where most EOA designations remained in place until the end of FY 2015). Increases in expenditure on healthcare and long-term care per capita in short-term and long-term EOAs were greater in FY 2015 than the average values in FYs 2008-2010. The increases in expenditure were higher in short-term and long-term EOAs than those in non-EOAs and EOAs/non-EOAs. The increases in dental health expenditure were attributed to enhanced accessibility to dental health facilities. Furthermore, the evacuations contributed to increases in healthcare and long-term care expenditure, independent of aging and improved accessibly to health facilities. Possible explanations for these increases include the poor health status of the evacuees following the evacuations, reduced availability of informal care provided by family members and neighbors, and reduced patient copayments. The findings highlight the necessity of health promotion among evacuees.
3 0 0 0 OA 側頸部後方より口角への貫通銃創の1例
- 著者
- 清水 正嗣 水城 春美 福山 義邦 松本 有史 河村 哲夫 柳沢 繁孝
- 出版者
- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.1380-1384, 1991-07-20 (Released:2011-07-25)
- 参考文献数
- 10
A case with fresh gunshot wound penetrating from the left lateral neck to the mouth angle, which was caused by pistol shooting during a conflict between gangs, was reported and discussed by us.The patient, a 41-year-old male, was shot probably with a 38-caliber revolver from behind. Its entrance was on the left rear of the neck, and the exit hole at the left mouth angle. The route through the body: the bullet passed inside of the mandible, where it caused a crashing fracture of the body in the molar region while breaking the lower prosthesis. But, he was very lucky that the important blood vessels and nerve bundles were not injured, although the route was very close to them. He was transported to our Dept. that same day and operated on under general anesthesia for removing foreign bodies, uniting and fixing the jaw fracture, and also for reconstructing the mouth angle, while we sanitized the wound and sutured the soft tissues at each place. At last, a tracheotomy was performed, to prevent suffocation from postoperative swelling. The progress after the operation was good, and he was discharged three weeks later. After 3 years he is now healthy and in prison.
- 著者
- 尹 聖鎮 大山卞 圭吾 岡田 英孝 高松 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.510-521, 1999-11-10 (Released:2017-09-27)
- 被引用文献数
- 2
A study was conducted to investigate the effect of gastrocnemius muscle stiffness on achilles tendon force in rebound jumps on slanted contact surfaces. Five trained college jumpers and throwers, and six active males executed five continuous repetition rebound jumps under three surface gradient conditions. The surface gradients were 8 degrees uphill type (U8), 8 degrees downhill type (D8), and level type (L) conditions. Force plate and limb position data were recorded simultaneously during all jumps. The changes in length of the achilles tendon (L_<AT>), m. gastrocnemius (L_<GAS>) and gastrocnemius muscle-achilles tendon complex (L_<MTC>) during the eccentric phase were calculated according to the mode1 of Voigt et al. (1995) and Grieve et al. (1978). The main results were as follows; 1. Jumping height in U8 and L was higher than in D8. There was also a tendency for a higher achilles tendon force at the midpoint (ATF_<MID>) in U8. On the other hand, in U8 and D8, L_<MTC> was lower, and L_<AT>/L_<GAS> was higher than in L. 2. There was significant positive correlations between the ground reaction force at the midpoint (GRF_<MID>) and jumping height, and ATF_<MID> and jumping height in U8, D8 and L. 3. There were significant positive correlations between GRF_<MID> and ATF_<MID>, and L_<AT>/L_<GAS> and ATF_<MID> in U8 and L. However, L_lt:MTC> and ATF_<MID> showed a significant negative correlation. These results indicate that the stretch length of the gastrocnemius muscle-achilles tendon complex is lower, and ATF_<MID> higher under uphill-type conditions than under level conditions because L_<AT/L_<GAS> becomes higher as gastrocnemius muscle stiffness increases.
- 著者
- 尹 聖鎮 田内 健二 高松 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.15-25, 2003-01-10 (Released:2017-09-27)
本研究の目的は,傾斜面でのリバウンドドロップジャンプにおける腓腹筋-アキレス腱複合体の神経筋活動を、跳躍トレーニング経験の相違に着目して検討することであった。9名の競技者および健常者に、30cmの台高からのリバウンド型ドロップジャンプ(RDJ30)を行わせた。着地面の傾斜角度は、上向き斜面8度(U8)、平地面(L)およぴ下向き斜面8度(D8)の3種類であった。その結果、競技者においては、上向き斜面での試技は下向き斜面および平地面と比較して、伸張局面における腓腹筋-アキレス腱複合体の長さ変化に対する踏切中点のアキレス腱張力の比(ATF_<MID>/L_<MTC>)、および腓腹筋-アキレス腱複合体の平均仲張速度(V_<MTC>)は大きいことが認められた。これに対して、健常者においては、上向き斜面および下向き斜面での試技は平地面と比較して、ATF_<MID>/L_<MTC>およびV_<MTC>が低いことが認められた。また、競技者は健常者と比較して、ATF_<MID>/L_<MTC>およびV_<MTC>は,いずれの傾斜面においても大きいことが認められた。上述の結果は、プライオメトリックス手段の一つとして傾斜而でのRDJを用いる際には、傾斜方向や跳躍トレーニング経験の相違によってMTCにかかる負荷特性が異なることを考慮する必要があることを示唆するものである
3 0 0 0 OA 国際関係論と地域研究の狭間
- 著者
- 浅羽 祐樹
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.151, pp.156-169, 2008-03-15 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 41
3 0 0 0 OA 飼育下ニホンザルにおけるα個体の推移
- 著者
- 青木 孝平 辻 大和 川口 幸男
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.137-145, 2014-06-20 (Released:2014-08-02)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
Using long-term behavioral data recorded between1950 and 2010, we studied cases of change in the alpha individual and its social background in a captive troop of Japanese macaques (Macaca fuscata) housed in Ueno Zoological Gardens, Tokyo, Japan. During this period, nine alpha males and four alpha females were recorded. Among the alpha males, three were juveniles. All alpha males except for one continued to keep their position until they died or were removed from the group. Alpha females, on the other hand, lost their position when they were in estrus/pregnant/nursing, after which time they continued to stay in the group. Unlike cases in free-ranging populations, captive male Japanese macaques are included in the social hierarchy of their natal group, and dominance relationship between males and females were unclear. Under such conditions, dominant females and their juveniles can become alpha individual when the former alpha disappears and/or there are no dominant male(s) present. Appearance of female/juvenile alpha individuals in the Ueno Zoo troop seems to be one of the bi-products of a captive environment and in order to keep social relationships of captive animals similar to those of free-ranging populations, artificial transfer (removal/introduction) of adult males should be considered.
3 0 0 0 OA 大学進学率の都道府県間格差の要因構造とその変容
- 著者
- 上山 浩次郎
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.207-227, 2011-06-10 (Released:2014-06-03)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2 1
本稿では大学進学率における都道府県間格差の要因構造を時点間の変容を考慮しながら明らかにする。そのことを通して,近年の都道府県間格差がどのようなメカニズムによって生じているのか,その特質を浮かび上がらせる。 そこで1976から2006年の4時点マクロデータに基づき,共分散構造分析の下位モデルである多母集団パス解析を行った。 結果,(1)1976年には「所得」と「職業」によって格差が生じていたものの,(2)1986年には「地方分散化政策」(供給側要因の格差是正)の効果もあり「所得」と「職業」の影響力が弱まった。だが(3)1996年に入ると,男子で「所得」の影響力が,女子で「大学収容率」の影響力が増し始め,さらに(4)2006年には,男女ともに「所得」と「大学収容率」が影響力を持ち始めただけでなく,男子のみではあるが「学歴」も大きな影響力を持っている。加えて,「大学収容率」を介した「所得」の間接効果ももっとも大きい。 以上から,こんにちの大学進学率の都道府県間格差のメカニズムには,社会経済的条件が持つ影響力の大きさ,供給側要因の「実質化」と「機能変容」,両者の「相乗効果」の増大という特徴があることが浮き彫りとなった。
3 0 0 0 OA ウェーブレット変換,特異値分解,フーリエ変換を用いた樹木画の画像解析
- 著者
- 川杉 桂太 竹村 和久 岩滿 優美 菅原 ひとみ 西澤 さくら 塚本 康之 延藤 麻子 小平 明子 轟 純一 轟 慶子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.90.18219, (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 24
In this study, we proposed three image analysis methods (wavelet transform, singular value decomposition, and Fourier transform) to evaluate drawings of the tree test quantitatively, and demonstrated the analyses to three images of the tree test drawn by schizophrenic patients. Wavelet analysis suggested that information about the position of drawn trees (direction, depth and width of drawn lines) can be captured. Fourier analysis suggested that information about the direction and depth of drawn lines can be captured. Singular value decomposition suggested that information about the position and direction of drawn lines can be captured. Further research is needed to consider the features of mathematical image analysis in detail, and apply them to analysis of the tree test.
3 0 0 0 OA TGF-β1による血管内皮細胞メタロチオネイン遺伝子の転写誘導
- 著者
- 土田 翼 藤江 智也 吉田 映子 山本 千夏 鍜冶 利幸
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第43回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.O-41, 2016 (Released:2016-08-08)
【背景・目的】内皮細胞は種々の増殖因子・サイトカインを産生・分泌することで, 血管機能を調節している。TGF-β1は,内皮細胞の増殖を抑制的に制御し,動脈硬化などの血管病変の進展に関与する。一方,メタロチオネイン(MT)は重金属の毒性軽減や細胞内の亜鉛代謝などに寄与する多機能な生体防御タンパク質であるが,細胞機能調節因子によるMTの誘導に関する報告は少ない。本研究では,TGF-β1による血管内皮細胞のMT遺伝子の転写誘導とそのメカニズムについて解析した。【方法】培養ウシ大動脈内皮細胞をTGF-β1で処理し,MTアイソフォーム(MT-1A,MT-1EおよびMT-2A)mRNAの発現をreal-time RT-PCR法により解析した。Smad2/3,ERK,p38 MAPKおよびJNKのリン酸化はWestern Blot法で検出した。siRNAはリポフェクション法により導入した。【結果・考察】血管内皮細胞において,TGF-β1の濃度および時間に依存してMT-1A/2A mRNAレベルが上昇したが,この上昇はTGF-β1中和抗体の同時処理により消失した。TGF-β受容体ALK1またはALK5 siRNAを導入した内皮細胞では,ALK5の発現抑制によりMT-1A/2A mRNAの発現の上昇が抑制された。ALK5下流のSmad2およびSmad3のsiRNAをそれぞれ導入したところ,Smad2 siRNAによりMT-1A/2A mRNAの発現上昇が抑制された。またnon-Smad経路としてMAPK経路を検討したところ,TGF-β1により全てのMAPKsが活性化したが,p38 MAPKおよびJNK阻害剤によりTGF-β1によるMT-1A mRNAの発現上昇のみが抑制された。以上の結果より,TGF-β1は内皮細胞のMT-1A/2A遺伝子を転写誘導すること,この誘導はALK5を介したSmad2シグナルの活性化に介在されること,およびp38 MAPKおよびJNKの活性化はMT-1Aの転写誘導を選択的に介在することが明らかになった。
3 0 0 0 OA MRミエログラフィーが漏出部位推定に有用であった特発性低髄液圧症候群の1例
- 著者
- 上野 卓教 吉澤 利弘 町野 毅 庄司 進一 阿武 泉
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.11, pp.2382-2384, 2005-11-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
特発性低髄液圧(Spontaneous intracranial hypotesion: SIH)症候群とは誘因なく髄液圧の低下をきたすことにより起立性頭痛・悪心・嘔吐・めまいなどを呈する症候群である.症例は24歳女性.突然,座位・立位時の嘔気・頭痛が出現した.髄液検査にて圧が0mm水柱であり,ガドリニウム造影脳MRIでは硬膜の肥厚と著明なガドリニウム増強効果,さらに両大脳半球の下垂を認めたため,特発性低髄圧症候群と診断した. MRミエログラフィーにて上部胸椎レベルに髄液と同等の液体貯留を認め,同部位近傍からの髄液漏出が推定された.
3 0 0 0 OA 繊維源の違いがウサギの血漿中コレステロール濃度に及ぼす影響
- 著者
- 鈴木 麻実 岡部 愛子 清水 玲子 松本 力 宮原 晃義 武石 勝 石川 信幸 堀 弘義 小牧 弘
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.113-120, 2003-10-10 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 26
本実験は,異なる繊維源がコレステロールの吸収阻害効果に及ぼす影響をウサギで調べた。異なる繊維源であるビートパルプ,大豆皮,アルファルファー,サフラワー粕の4試験飼料に各々0.5%コレステロールを添加した供試飼料を給与し,消化試験を実施するとともに血漿コレステロール値を測定した。血漿中総コレステロール・遊離コレステロール値の経時的変化では,ビートパルプが他の繊維源に比して最も低い値で推移し,コレステロールの吸収阻害効果が高いことを示唆した。大豆皮,アルファルファミールの血漿中総コレステロール値は同程度に推移した。大豆皮を給与したウサギの糞中コレステロール排泄率が他の飼料区に比して高いことから,大豆皮はコレステロール排泄に有効であると推察した。以上の結果,ビートパルプと大豆皮は肥満予防効果が同様に期待できるものと考えられた。
3 0 0 0 OA リポソームの機能と医薬への応用
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.328-335, 2009 (Released:2015-06-14)
- 被引用文献数
- 1 3
It was previously considered that the practical application of liposomal medicines was very difficult. The pharmaceutical technologies for mass production, long term stability during storage, encapsulation efficiency of the drug, etc. were seemed big problems to be solved, and it was well known that the liposomal particles are apt to be entrapped in vivo by the reticuloendothelial system (RES) such as liver, spleen, etc. Fortunately, owing to the progress of science, about 10 liposomal medicines containing the anticancer agents, the antifungal agents, etc. were launched out and are now contributed to medical treatment in the world. Recently liposomes are expected to be useful as the vectors for in vivo nucleic acid (plasmid DNA, siRNA, etc.) therapy and as the tools for target validation in the area of drug discovery. There are already many liposomal reagents for transfection, and some clinical trials are performed using liposomes. It is considered that liposomes, the membrane–structure particles, have unlimited potential in the medical field.
3 0 0 0 OA ヒトの動作の最適化モデル
- 著者
- 宇野 洋二
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.525-529, 2014 (Released:2014-08-15)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 5
3 0 0 0 OA 宇宙線の研究から「秩序-無秩序現象」の計算機実験へ
- 著者
- 上田 顕
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.97-110, 2013-04-30 (Released:2014-04-30)
- 参考文献数
- 28
3 0 0 0 OA 岡山市周辺の吉備高原に分布する古第三系「山砂利層」と海成中新統
- 著者
- 鈴木 茂之 松原 尚志 松浦 浩久 檀原 徹 岩野 英樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.Supplement, pp.S139-S151, 2009 (Released:2012-01-26)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 4
吉備層群(いわゆる「山砂利層」)は,ほとんど中~大礫サイズの亜円礫からなる,谷埋め成の地層である.時代決定に有効な化石は得られず,更新統とされていたが,稀に挟まれる凝灰岩層を対象とするフィッション・トラック年代測定によって,地層の定義や対比が行えるようになってきた.いくつかの堆積期があることが分かってきたが,岩相では区別しがたく,地層区分は高密度の踏査による地層の追跡が必要である.各層の基底は,地層を構成する礫を運んだ当時の河の谷地形を示す.この復元された古地形は,底からの比高が150m以上に達する深い谷地形である.これは一般的な沈降を続ける堆積盆に形成された地形より,むしろ後背地側の地形である.すなわち吉備層群には,一般的な沈降する堆積盆の地層に対する区分や定義の方法とは異なる,新しい取り組みが必要であり,堆積の要因についても考えなくてはならない.これらは案内者一同を悩ませ続けている課題であり,見学旅行を通じて議論をいただきたい.
3 0 0 0 OA 最先端赤外線サーモグラフィで探る動物の情動
- 著者
- 佐藤 侑太郎 狩野 文浩 平田 聡
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- pp.68.1.7, (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 3
Emotion is understudied in nonhuman animals despite broad interests in the topic. This is partly due to the difficulty in measuring subtle emotional reactions, such as physiological changes, under ecologically-valid situations. It is particularly challenging because the majority of traditional physiological measurements require animal participants to wear electrodes and head/body restraints in a laboratory. Recent advances in infrared thermography (IRT), and its use in measuring changes in animals' skin-temperature, offer suitable solutions for these challenges. This article reviews a growing body of research employing IRT in the study of animal emotions and identify both merits and shortcomings of IRT which need to be considered when designing experiments and observations. Also, we introduce our recent efforts to facilitate the use of IRT for the study of large-body animals, such as chimpanzees. Finally, we illustrate some of the critical future directions of IRT for the study of nonhuman animals. In conclusion, the study of animal emotion is more possible than ever before with this novel technology.
- 著者
- 上野 雄己 平野 真理 小塩 真司
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- pp.28.1.10, (Released:2019-06-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
This study aimed to reinvestigate age differences in resilience in a large cross-sectional Japanese sample (N=18,843; 9,657 men, 9,156 women; meanage=47.74 years, SDage=14.89, rangeage=15–99 years). The data were obtained from a large cross-sectional study by NTT DATA Institute of Management Consulting, Inc. The results of hierarchical multiple regression indicated that age and squared term of age were significantly positively associated with resilience. These results reconfirm that resilience in Japanese individuals increases with age, corroborating the findings of previous studies.