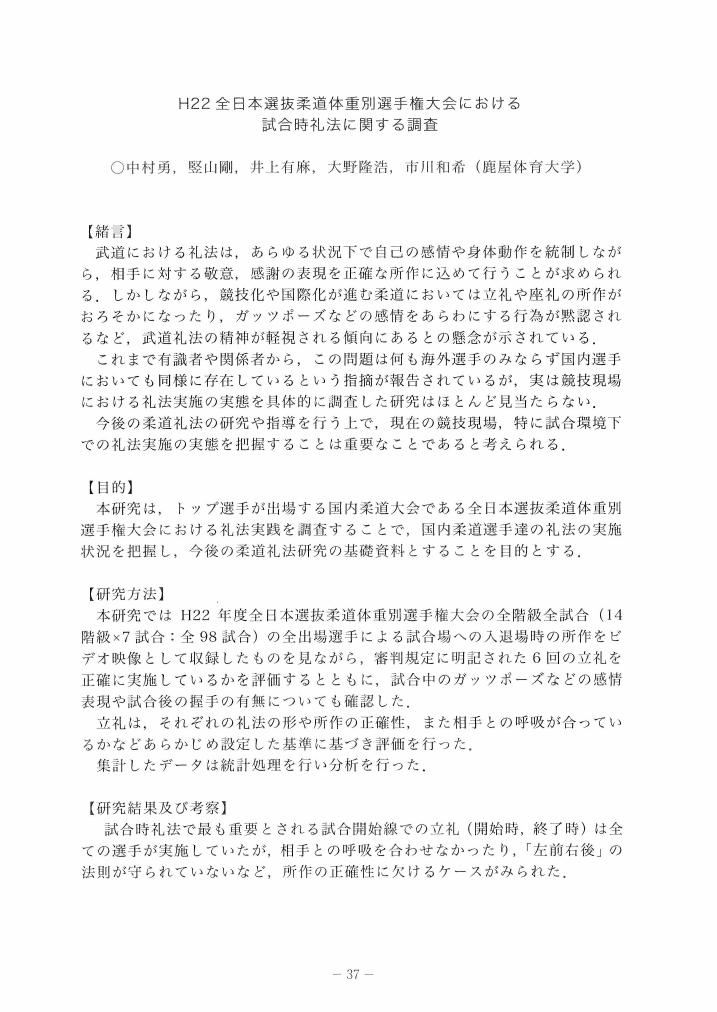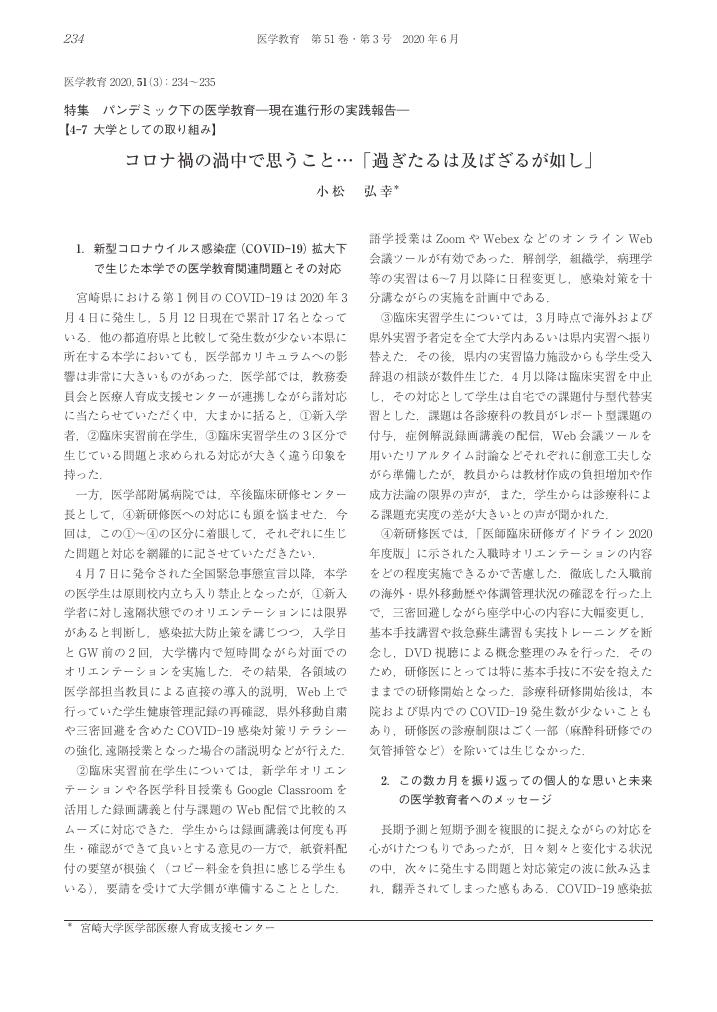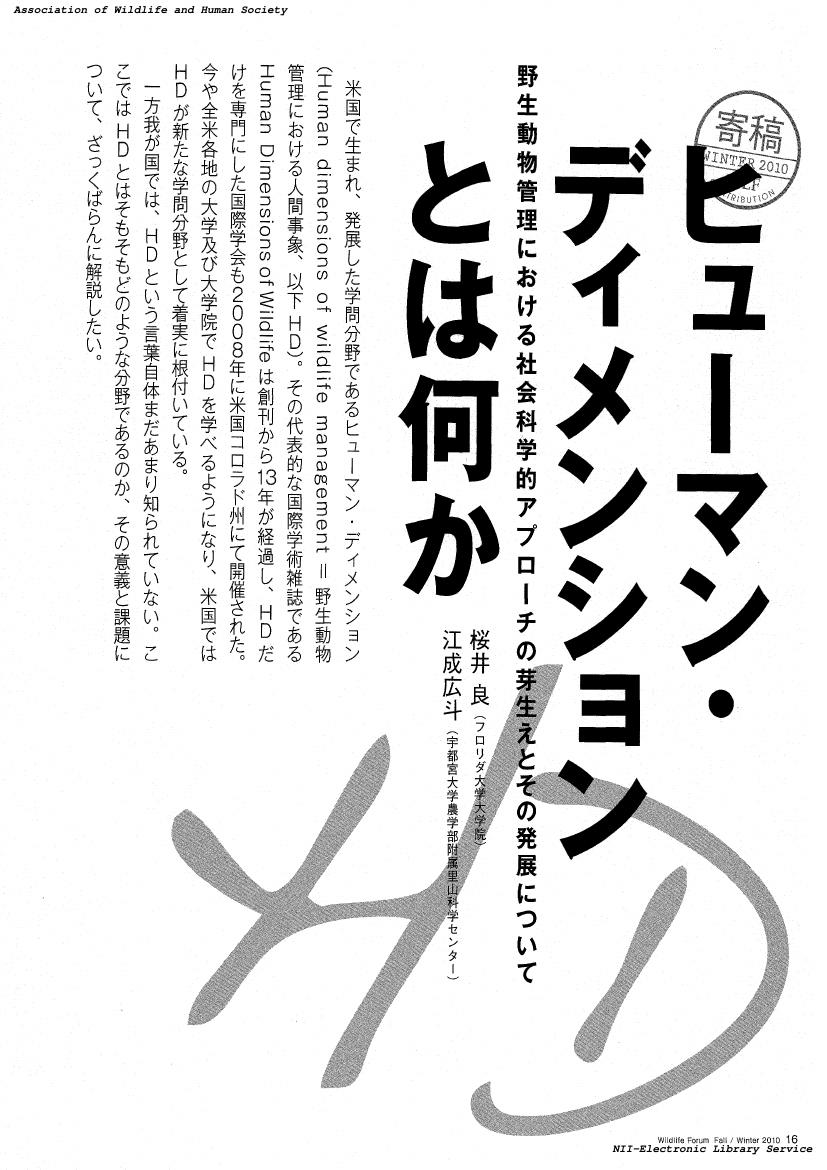2 0 0 0 OA パンの発酵による旨味物質イノシン酸およびグルタミン酸の生成と変動
- 著者
- 藤沢 和恵 吉野 昌孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.494-497, 1995-12-10 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
パン生地および発酵前後のイノシン酸, グルタミン酸を定量し, 両者の増減の機構とパンの旨味との関連を考察した。1) イノシン酸, グルタミン酸とも, パン生地として用いた小麦粉の中で強力粉に最も大量に含まれ, ついで中力粉, 薄力粉の順であった。2) 発酵によりパン中のイノシン酸は約2倍に増加する一方, グルタミン酸は1/2以下に減少した。3) パンの旨味物質としてはイノシン酸が発酵により増加しており, その蓄積はパン酵母のAMPデアミナーゼの高い活性とイノシン酸分解酵素 (5′-ヌクレオチダーゼ) の低い活性に起因すると結論された。
2 0 0 0 OA プライバシー意識と自己愛傾向の関連1)
- 著者
- 太幡 直也 佐藤 広英
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.69-71, 2023-07-24 (Released:2023-07-24)
- 参考文献数
- 11
Researchers have defined privacy consciousness as the extent of awareness regarding privacy for the self and others. This study investigated the relationship between privacy consciousness and narcissistic personality—an exaggerated sense of self-importance. University students (N=155) responded to scales assessing privacy consciousness for the self and others. Additionally, scales were employed to assesses narcissistic tendencies, including hypervigilance and obliviousness. The results indicated that participants who scored higher on hypervigilance tended to report taking actions to preserve their privacy. Moreover, those who scored higher for both obliviousness and hypervigilance were less likely to act to maintain others’ privacy.
2 0 0 0 OA 発達障害への接触経験が大学生の発達障害に対する態度に与える影響
- 著者
- 岡田 有司
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.96-98, 2023-10-04 (Released:2023-10-04)
- 参考文献数
- 6
This study examined the impact of direct and indirect contact experiences with developmental disabilities on college students’ attitudes toward such conditions. A total of 185 students participated in this study, responding to a questionnaire and paper-format implicit association test. Multiple regression analyses revealed that direct contact with conditions such as social and institutional support, acquaintance potential, equal status, and cooperation, as suggested by the contact hypothesis, positively affected attitudes toward developmental disabilities. Conversely, direct contact without meeting those conditions negatively impacted these attitudes. Furthermore, the study revealed that certain indirect contact experiences positively influenced attitudes toward developmental disabilities.
2 0 0 0 自由エネルギー原理と認知発達ロボティクス
- 著者
- 長井 志江
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.826-832, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)
2 0 0 0 OA H22全日本選抜柔道体重別選手権大会における試合時礼法に関する調査
- 著者
- 松浦 弘幸 根本 哲也 久保田 怜
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 (ISSN:13451537)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.89-96, 2012-05-30 (Released:2017-09-02)
- 参考文献数
- 9
神経軸索で興奮伝導や量子干渉を伝える媒体として,準粒子・ポラリトンの存在を考えた.ポラリトンは神経軸索膜で活動電位に伴って発生する分極が量子的波動として,軸索上や軸索間に伝搬して行く状態を分極ベクトルの回転として量子モデル化したものである.量子的分極波がエファプスやシナプス干渉,興奮の伝導の媒介等,ミクロな視点からの神経電気現象を担い,この分極ベクトルの変動の伝播・ポラリトンが神経的電磁気現象を伝える情報担体である.準粒子としてのポラリトン質量は約10^<-25>Kg,スピン1の質量を持つ光子として表現される.裸のポラリトンの質量は,電子質量の1〜10倍程度(6.7×10^<-30>Kg)である.通常は,熱ノイズの擾乱に耐えるために,水和した状態で存在する.高々,10個程度の水分子が,裸のポラリトンに引き寄せられて準粒子を形成する.神経伝導のポラリトンが持つ基底状態の波長は1μmを中心に10μ〜0.6μmに存在する.ポラリトンは,シュレディンガー方程式やクライン・ゴルドン方程式に従う.Na+,K+の膜の内外への流入・流出が伝導原因のカレントを形成し,その効果を軸索方向や軸索外に伝搬するのが,媒介粒子ポラリトンの役割である.
2 0 0 0 OA 動的で, 構成的な類似判断 ―思考の基盤としての類似が持つべき条件―
- 著者
- 鈴木 宏昭
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.4_6-4_18, 1997-12-01 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 52
Recent research has shown that similarity plays crucial roles not only in lower-level cognition, but also in higher-level ones such as problem-solving and learning including analogy. At the same time, these findings have made clear the insufficiency of the traditional model of similarity that assumes a flat representation of a fixed set of properties of an object. This paper explores the possibility of extending similarity to the variety of cognitive activities. For this purpose, by reviewing recent studies on similairty judgment, we examined whether human similarity judgment could reflect a.) structural information, b.) task goals, and c.) knolwedge relevant to achieving the task. The review revealed that human mechanisms of similarity judgments incorporate structural and goal-related information in computing similarity.
2 0 0 0 OA ミトコンドリアから放出されるアポトーシス誘導物質
- 著者
- 平野 哲男
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.324-325, 1999-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 全国の街路樹における種類と本数の現況と推移
2 0 0 0 OA 古代インドにおける植物病害と菌類について
- 著者
- 山本 昌木
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.249-251, 1985-07-25 (Released:2009-02-19)
2 0 0 0 OA ハスの観照の歴史的変遷について
- 著者
- 渡辺 達三
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.19-24, 1993-03-31 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
わが国前近代のハスの観照の歴史的な変遷をみ, 1) 上代では, ハスへの観照がみられるが, 中国からの影響の大きい, 女性, 恋愛などの寓意性をもった人事中心のものであること, 2) 中古では, ハスの植物や生態などの特性がよく観察され, それを基礎にした植物や, 釈教, 人事上の事柄について観照されていること, 3) 中世では現実的, 実践的な性格を強め, ハスは環境との連係を強め, 空間, 時間, 音響などの再構成された, 複合的な事象の中で, それらとの連関において観照されていること, 4) 近世では, 前代の現実的指向, 環境との連係の傾向をいっそう強め, その植物や生態等の特性に即したものとなり, 釈教的な観照はほとんどみられなくなっていること等をみた。
2 0 0 0 OA 多孔質成形板で構成した有孔板の吸音性能と応用例
- 著者
- 日高 孝之 中川 武彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.9, pp.551-561, 2016-09-01 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 33
板状に成形加工された多孔質材で構成した有孔板の吸音特性について報告する。このタイプの材料は通常, 吸音性能を得るため塗装表面には細孔が設けられるが, その吸音メカニズムは通常の孔あき吸音板とは若干異なっている。本報告では細孔の設けられた塗装面と多孔質材を対象として, 材料表面から見た音響インピーダンスの計算式を求める。既存の多孔質成形板の音響性能の実測結果に基づき, 2種のモデル試験体の垂直入射吸音率の測定値と計算値の比較を行い, 当該音響モデルの妥当性について検討する。最後に, 若干の垂直入射吸音率の数値計算例を示し, 材料パラメータが及ぼす影響, 及びこのタイプの吸音材料の性質について述べる。
2 0 0 0 OA コロナ禍の渦中で思うこと…「過ぎたるは及ばざるが如し」
- 著者
- 小松 弘幸
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.234-235, 2020-06-25 (Released:2020-07-15)
2 0 0 0 OA 都道府県における身体活動促進を目的とした行動計画の策定およびその実施状況―量的記述―
- 著者
- 武田 典子 種田 行男 井上 茂 宮地 元彦 Fiona Bull
- 出版者
- 日本運動疫学会
- 雑誌
- 運動疫学研究 (ISSN:13475827)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.113-135, 2019-09-30 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
目的:全国の都道府県を対象として,身体活動促進を目的とした行動計画の策定とその実施状況を明らかにすること。方法:Bullらが開発した「健康増進のための身体活動に関する国の政策を監査するためのツール(Health-Enhancing Physical Activity Policy Audit Tool; HEPA PAT)」を改変し,地方自治体向けの新たな政策監査ツール(Local PAT; L-PAT)を作成した。内容は,「身体活動促進に関する行動計画の策定」,「行動計画の策定における部門・組織間の連携」,「実際に行われた事業や活動」など11項目とした。研究期間は2015年8月から2016年3月であった。対象は全国47都道府県の保健,スポーツ,教育,都市計画,交通,環境の6つの部門で,合計282(47都道府県×6部門)であった。結果:全対象282のうち202から回答が得られ,回答率は71.6%であった。保健部門とスポーツ部門は,行動計画の策定率(それぞれ100%,97.6%)および実施率(それぞれ93.6%,100%)が他の部門よりも高かった。環境整備に携わる都市計画部門と交通部門においても行動計画が策定されていたが(それぞれ55%,30%),実施率は低かった(それぞれ13.6%,22.2%)。保健,スポーツ,教育の部門間には連携が認められたが,その他の部門との連携は不十分だった。結論:都道府県レベルの身体活動促進に関する行動計画の策定・実施は,保健部門とスポーツ部門を中心に行われていた。都市計画部門や交通部門においても関連する計画がみられた。今後は策定や実施の具体的内容および活動の効果など質的な検討が求められる。
2 0 0 0 OA 日本新産種のUsnea fragilescens Lynge(ウメノキゴケ科,地衣類)
- 著者
- 大村嘉人 文光喜 柏谷博之
- 出版者
- 植物研究雑誌編集委員会
- 雑誌
- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.303-307, 2000-10-20 (Released:2022-10-21)
ウメノキゴケ科サルオガセ属地衣類の Usnea fragilescens (アッケシサルオガセ 新称)が北海道霧多布湿原周辺で発見された. 本種は西ヨーロッパおよび北米から報告されているが, これまで日本からの報告はなかった.本種の特徴は次の通りである. 地衣体は直立半懸垂性, 不同長二叉分岐, 地衣体基部は黒炭色, 分枝の髄層は厚く軸が細いため膨らんだようになる(%C/%M/%A = 5.1/33/23). 枝の幅ほどの円形の粉芽塊を持ち, その表面はやや凹み, 顆粒状の粉芽を生じる.粉芽塊の縁の皮層は反り返らない. 今回採集された全ての標本は, バルバチン酸, 4-O-デメチルバルバチン酸, プロトセトラール酸を主成分として含む.この化学変異株は本種では初めての報告である.
2 0 0 0 OA 初期イギリス福祉国家におけるキリスト教社会主義 ―R・H・トーニーを中心として
- 著者
- 林 昌子
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1-10, 2023-08-30 (Released:2023-09-15)
- 参考文献数
- 24
戦間期、R・H・トーニーは福祉社会実現に向けて中心的役割を果たした一人である。彼は社会が世俗化に向かうことを理解し、それに適合する社会思想の構築を試みた。20世紀後半には福祉国家の限界が唱えられるとともに、その現代化が模索された。ネオリベラリズムが限界を迎えようとしている今、トーニーの社会思想への注目が、再び高まってきている。本研究はイギリス福祉国家の成立を支えた理念に焦点を当て、キリスト教社会主義がその土台としての役割を果たしてきたことを示す。
2 0 0 0 OA 特定健診未受診に関連する要因の検討:千葉県海匝地区国民健康保険加入者に対する調査
- 著者
- 原田 亜紀子 吉岡 みどり 芦澤 英一 木下 寿美 佐藤 眞一
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.201-209, 2019-04-15 (Released:2019-04-26)
- 参考文献数
- 18
目的 本研究は,特定健康診査(特定健診)を受診しなかった者に対し,未受診の理由や健診受診に対する意識を調査し,未受診に影響する要因と現状の問題点を明らかにすることを目的とした。方法 千葉県海匝地域にある三市の各国民健康保険(国保)で実施した特定健診の未受診者を対象とし,健診を受けなかった理由,新しい健診制度と国保保険料との関係,健診に対する要望,次年度の健診受診の希望などを調査した。調査対象については,翌年の健診受診の状況も合わせて調査した。各調査項目について,市別,性別,年齢階級別に集計を行い,項目間の関連についてはχ2検定を行った。次年度の健診受診の意向の有無,次年度に実際に受診したかどうかをそれぞれ従属変数とし,関連する要因の検討にロジスティック回帰分析を用いた。さらに,次年度の健診意向と翌年の受診状況を組み合わせ(意向あり・実際に受診,意向あり・実際に受診なし,意向なし・実際に受診なし)を従属変数とし,関連する要因につき名義ロジスティック回帰分析を用い検討した。結果 次年度の健診を希望せず,実際に受診しない傾向は,会社員,「通院中・経過観察中」などを未受診の理由にあげた者でみられた。一方で,健診受診の意向がありながら,実際に健診を受診しない傾向は,自営業の者,メタボに該当する者,未受診理由で「健診が日中だった」,と回答した者においてみられた。また,これらの要因とは別に,健診受診率と後期高齢者医療制度への支援金の関連を知らなかった者において,健診受診の意向と実際の健診受診の割合が高かった。結論 健診受診の意向と実際の受診行動を組み合わせて,受診に関連する要因を検討することで,未受診者の特徴を分類することが可能であった。未受診者をひとくくりに考えることなく,特徴に応じて切り分け,各々に対し効果的なアプローチを考えていく必要がある。
- 著者
- 桜井 良 江成 広斗
- 出版者
- 「野生生物と社会」学会
- 雑誌
- ワイルドライフ・フォーラム (ISSN:13418785)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.34, pp.16-21, 2010-02-10 (Released:2017-11-03)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 古川 敏明 ハウザー エリック 大野 光子
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.197-212, 2023-09-30 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 14
日本の保育所は共感の社会化を主要な目的とし,従来に比べ,保育士が子どもたちの間で生じた揉め事に介入するようになったと指摘されている.本稿は東京都区部にある保育所の2歳児クラスを対象として,大人と子ども間の相互行為をマルチモーダルに会話分析する.特に,遊びの最中に生じた子ども間の揉め事に養育者が介入する場面において,2人の養育者が発話と身体資源を用いて「行なっていること」にどのような核心的相違があるかを記述する.また,養育者たちの発話や身体資源をモラル性の社会化におけるどのような志向の違いとして記述できるかも探究する.養育者が子どもを自らの行為に責任を負う主体として扱う発話を行ない,かつ,視線,身体の配置,道具の使用を含むマルチモーダルな働きかけを行った介入では,子どもから望ましい応答を引き出し,モラル性の社会化が達成されている.
2 0 0 0 OA 冬期におけるスズメの住宅地利用と営巣場所への執着
- 著者
- 三上 かつら 三上 修
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.227-236, 2015 (Released:2015-12-13)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
都市の生物多様性に対する関心は高まってきており,都市化を測る生き物として,鳥類はしばしば注目される.鳥類が都市の中のある場所において,どこをどのように使っているかという情報は,都市における生物多様性の創出や維持管理のために役立つだろう.都市には多様な環境が含まれており,特に小鳥類にとっては,数m離れた場所は,別の環境を意味することがあると考えられる.しかしながら,都市環境でそういった小さいスケールで特定の鳥類の環境利用を調べた研究例はほとんどない.そこで本研究では,岩手県内の住宅地において,冬期のスズメを対象に,住宅地にどのくらいいて,どのような場所を利用しているのかを調査した.特にスズメがなぜその環境を選んだか,に関わる要因として,季節性と営巣場所に着目した.群れの観察は2012年10月から2013年4月にかけて,営巣場所の探索は2012年と2013年の繁殖期に行った.厳冬期には,スズメの個体数が減り,群れは大きくなった.これはシーズンの進行がスズメの行動に影響することを示している.冬期のスズメの群れは,大部分が古巣または新巣から半径40 m以内でみられた.これは古巣をねぐらとして利用していることと,古巣の近くにまた翌年の巣をつくることが多いことから,スズメが営巣場所周辺に強い執着を持っているものと考えられる.また,餌がとれそうな未舗装の場所をよく利用していた.ただし,地形や構造物など他の要因もかかわっている可能性があり,採餌場所の選択については今後,検証が必要だと思われる.営巣場所への執着が強いことは間違いないと考えられるため,衛生や管理上の目的で,スズメが高頻度に利用する場所をコントロールしたいとき,巣箱の設置が有効である可能性がある.