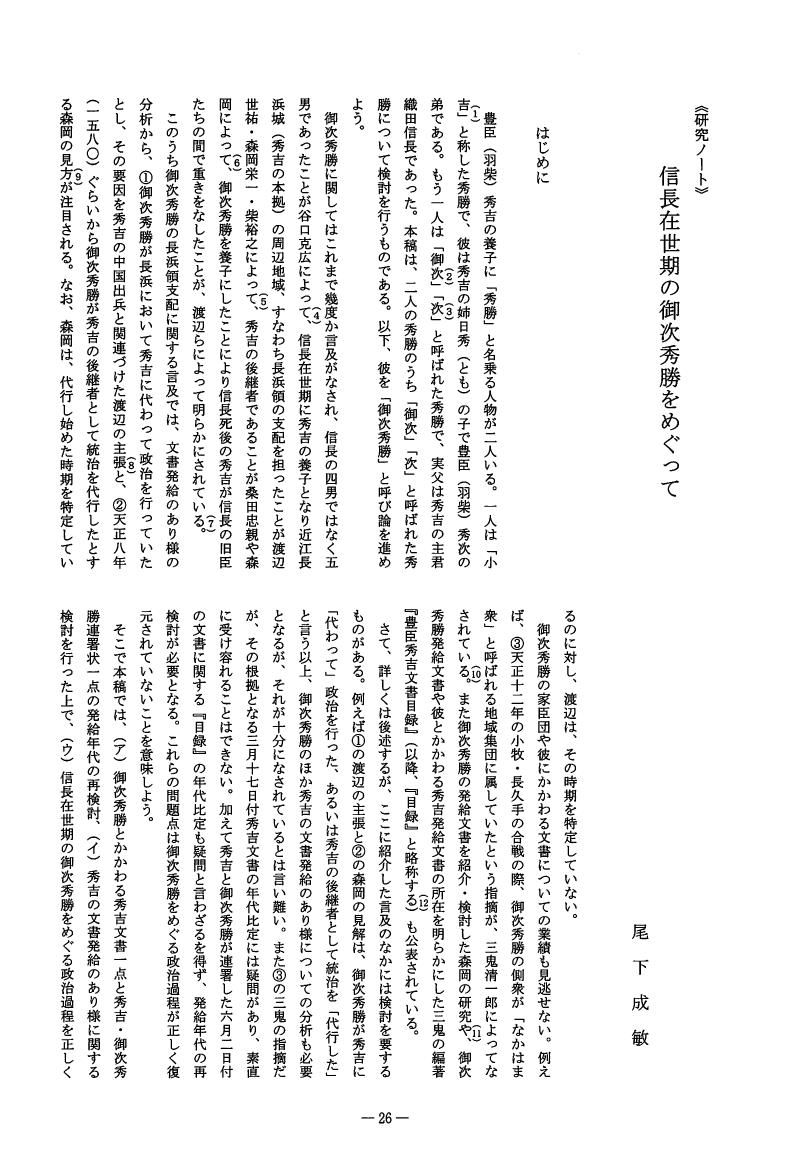2 0 0 0 OA Defining “The Definition of the Situation”
- 著者
- Ikuya Sato
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- Japanese Sociological Review (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.346-359, 1991-03-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 47
本論文は、もっぱらトマスとズナニエツキのテクストに沿って、状況の定義概念の初期の定式化とその後の変遷をあとづけ、この概念が、行為主体と「構造」の関連を明らかにする上でもつ「感受概念」としての潜在力を明らかにする。社会学におけるスタンダードな用語の一つである「状況の定義」は、これまで主に社会的行為の主意主義的な側面を表現する代表的な概念として取り扱われてきた。しかしながら、この概念の初期の定式化の歴史をたどってみると、「状況の定義」は、行為に対する社会文化的な構造の規定性を示す際にも使われていることがわかる。とりわけトマスは「状況の定義」を多義的に使用しているが、これは、様々な行為主体と多様な状況との関連を実証研究を通して明らかにしていく上で彼が用いた効果的な戦略の一つであると考えられる.この「状況の定義」の一見相矛盾する多義的な用法の解明は、現在さまざまな形で試みられているマイクロ社会学とマクロ社会学の統合を進める上で、一つの有力な手がかりを与えてくれる。
2 0 0 0 OA ガソリンエンジンのリーン限界に及ぼす燃料化学種の影響
- 著者
- 内木 武虎 小畠 健 渡邊 学 横尾 望 宮元 敬範 中田 浩一
- 出版者
- The Japan Petroleum Institute
- 雑誌
- Journal of the Japan Petroleum Institute (ISSN:13468804)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.303-308, 2019-11-01 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 11
スーパーリーンバーンにおいては,タンブル比を上げるなどエンジン技術による燃焼限界(リーン限界)の拡大が図られているが,さらなるリーン限界拡大のためには新しい燃料技術と組み合わせることが重要であると考えられる。本研究では,タンブル比を変更した2種類のエンジンを用い,燃料化学種がリーン限界(IMEP変動率3 %になる空気過剰率)に及ぼす影響を評価した。その結果,燃料組成変更により,リーン限界をさらに拡大することが可能であることを確認した。また,燃料組成変更によるリーン限界拡大効果は,エンジン変更(タンブル比の違い)によるリーン限界拡大効果とほぼ独立していることを確認した。さらに,燃料の層流燃焼速度とリーン限界は良い相関を示した。
2 0 0 0 OA 予測可/ 否条件における異なる距離ステップ動作が予測的姿勢制御反応に与える影響
- 著者
- 大塚 健太 冷水 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本基礎理学療法学会
- 雑誌
- 基礎理学療法学 (ISSN:24366382)
- 巻号頁・発行日
- pp.JJPTF_2023-04, (Released:2023-09-09)
- 参考文献数
- 25
【目的】健常若年者を対象とし,ステップ動作におけるステップ距離の予測可否およびステップ距離の違いが予測的姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustments:以下,APA)反応に与える影響を検証することを目的とした。【方法】健常若年者20 名を対象に,身長に応じた3 つの距離でのステップ動作を事前に距離を教示する条件およびステップ直前に提示する条件にて実施し,各種条件におけるAPA 時間,下肢筋活動時間および筋電図間のコヒーレンスを算出し比較した。【結果】筋活動時間においては予測可否によってステップ側前脛骨筋・支持側ヒラメ筋,ステップ距離によってステップ側前脛骨筋・腓腹筋外側頭に有意差を認めたものの,APA 時間およびコヒーレンスにおける有意差は認められなかった。【結論】健常若年者においては,ステップ距離の予測可否およびステップ距離の違いがAPA 反応に及ぼす影響が少ない可能性が示唆された。
- 著者
- Takuma Noda Hanseul Kim Kenta Watanabe Kota Suzuki Naoki Matsui Ryoji Kanno Masaaki Hirayama
- 出版者
- The Ceramic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (ISSN:18820743)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.10, pp.651-658, 2023-10-01 (Released:2023-10-01)
- 参考文献数
- 27
The reaction distribution in the composite cathode of an all-solid-state battery (ASSB) was directly tracked by in situ scanning electron microscopy (SEM) combined with energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Contact between an electrode active material and a solid electrolyte is important for improving the properties of ASSBs as a promising next-generation battery. An in situ analysis is significant for establishing strategies to obtain sufficient contact areas between the active material and solid electrolyte particles. SEM-EDX has the advantages of in-situ measurement in spatial/time resolution, non-destruction, and versatility. We investigated the sensitivity of EDX to the Na signal and distinguishable distance to ensure sufficient spatial/time resolution. The acceleration voltage of 5 kV for the electron beam provided the highest sensitivity to the Na signal among all acceleration voltages. The distinguishable distance decreased with increasing magnification owing to the decrease in pixel size. Cross-sectional SEM-EDX images of the TiS2–Na3PS4/Na3PS4/Na–Sn cell were collected during charge/discharge. The time variation of Na signal intensity confirms the deintercalation of Na+ in the TiS2–Na3PS4 cathode layer. Moreover, intercalation on the solid electrolyte side proceeded faster than that on the current collector side. This was because the rate-determining step was ionic conductivity rather than electronic conductivity based on the difference between ionic and electronic conductivities. Ex situ observations detected only a uniform distribution in the composite after Na+ diffusion had relaxed. Operando SEM-EDX is a new tool to directly explore the intermediate conditions of electrode materials under ASSB operation.
2 0 0 0 OA 有熱時痙攣後に川崎病と診断し可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎/脳症を合併した女児例
- 著者
- 塚本 由紀 真島 久和 犬飼 幸子
- 出版者
- 日本小児放射線学会
- 雑誌
- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.113-118, 2021 (Released:2021-03-27)
- 参考文献数
- 18
1歳10か月女児.発熱2日目(第2病日)に痙攣し,単純型熱性痙攣と診断された.第3病日,川崎病主要症状全てを認め川崎病の診断で当院に入院し,免疫グロブリン療法(IVIG)を開始した.同日夜に痙攣を2回認めた.第4病日,発熱が続きJapan Coma Scale 30の進行性の意識障害があり,脳MRIを施行したところ拡散強調画像において,脳梁膨大部,および前頭葉から半卵円中心に対称性の高信号域を認め,拡散係数は低下し,mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion(MERS)2型の画像所見に合致した.進行性の意識障害を認めたためIVIG追加とステロイドパルス療法を行ったところ,意識障害は改善し,後遺症なく経過した.本症例のように熱性痙攣と考えられた場合でも,脳炎・脳症の可能性があるので慎重な経過観察が必要である.
- 著者
- 岩谷 幸雄 岡本 拓磨 トレビーニョ ホルヘ 鈴木 陽一
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.544-549, 2011-11-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 22
2 0 0 0 OA 明石博高旧蔵ヒポクラテス像について
- 著者
- 勝盛 典子
- 出版者
- 近世京都学会
- 雑誌
- 近世京都 (ISSN:21886709)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-99, 2023-09-20 (Released:2023-10-02)
In the collection “Materials related to Akashi Hiroakira donated by Mr. Akashi Hiro’omi, ” in the Kyoto Institute, Library and Archives, there is a hanging scroll of the “Portrait of Hippocrates” (Frontispiece 1) for which the Dutch scholar Udagawa Yōan (1798-1846) wrote a Dutch inscription. It is based on the copperplate illustration of Historische kronyck (Leiden 1698) by Johann Ludwig Gottfried (1584-1633), and is similar to the copperplate portrait of Hippocrates held by Waseda University Library, which was introduced in Ogata Tomio’s The Praise of Hippocrates in Japan (1971). However, in the case of this work, the painting is by ink on paper, and Udagawa’s inscription is written in pen. Akashi Hiroakira (1839-1910), the former owner of the scroll, was a bureaucrat in Kyoto Prefecture for about 10 years from 1870, devoting himself to scientific and technological education and the development of the medical system. This article discusses the “Portrait of Hippocrates” owned by Akashi. A description of the work (hereafter, “Akashi version”) is given here:
2 0 0 0 OA 炎症性腸疾患患者の大腸内視鏡検査に伴う苦痛の体験
- 著者
- 布谷 麻耶 髙橋 美宝
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.295-304, 2023 (Released:2023-10-03)
- 参考文献数
- 24
目的:炎症性腸疾患患者が大腸内視鏡検査に伴いどのような苦痛を体験しているかを明らかにする.方法:発症後に大腸内視鏡検査を1回以上受けた経験がある寛解期の患者10名に半構造化面接を行い,質的記述的に分析した.結果:患者は大腸内視鏡検査に伴い,【前処置による心身の負担】【検査中の痛み】【検査への恐怖】【異性の医療者に対する抵抗感】【検査後の疲労と病状悪化】【検査結果への不安】【時間と費用の負担】という苦痛を体験していた.【検査中の痛み】には『炎症時の内視鏡操作に伴う痛み』『内視鏡挿入時や体位変換時の合併症による痛み』『腸管屈曲部に内視鏡が当たる痛み』『送気による腹部の張りと痛み』があった.結論:大腸内視鏡検査に伴い炎症性腸疾患患者は,腸管の炎症や合併症によって疾患特有の苦痛を体験していた.
2 0 0 0 OA 三種混合ワクチン(DPT)接種およびBCG接種がアトピー性疾患におよぼす影響
- 著者
- 米山 宏 鈴木 まゆみ 藤井 浩一 小田島 安平
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.7, pp.585-592, 2000-07-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 14
三種混合ワクチン(DPT)接種とBCG接種によるアトピー性疾患発現効果と抑制効果について検討するために, 東京都神津島村在住の0歳から3歳の全小児82名, 小学1年生全生徒31名および中学1年生全生徒30名, 合計143名を対象として調査を行った.0歳から3歳児では, DPT接種群におけるアトピー性疾患(22/39人, 56.4%), 気管支喘息(10/39人, 25.6%)の各頻度は非接種群におけるそれぞれの頻度(4/43人, 9.3%, 1/43人, 2.3%)に比して有意に高率であった(p<0.01).またアトピー性皮膚炎の頻度(7/39人, 18.0%)も非接種群(1/43人、2.3%)に比して有意に高率であった(p<0.05).小学1年生では, ツベルクリン反応陽性者にアトピー性疾患を有するものはなかった.しかし, 中学1年生では関連はみられなかった.以上より, DPT接種はアトピー性疾患の発現に促進的に作用する可能性を持ち, BCG接種はアトピー性疾患の発現を抑制するが, その抑制効果はかならずしも持続的なものではない可能性があると考えられる.
2 0 0 0 OA 信長在世期の御次秀勝をめぐって
- 著者
- 尾下 成敏
- 出版者
- 愛知県
- 雑誌
- 愛知県史研究 (ISSN:18833799)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.26-36, 2015 (Released:2020-02-27)
2 0 0 0 OA 炎症型歯周疾患の急性発作期に対する黄連解毒湯と排膿散及湯の効果
- 著者
- 神谷 浩
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.191-195, 1993-10-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 1
歯肉の発赤, 腫脹, 疹痛, 出血, 排膿などの炎症症状が著明に認められる炎症型 (実熱証型) 歯周疾患の急性発作期に対し, 清熱作用を持つ黄連解毒湯と排膿散及湯の投薬目標 (証) を想定し投薬を行った。黄連解毒湯の証は, 歯肉が腫脹し発赤の程度が強い歯周炎, あるいは歯肉発赤と出血が認められる歯周炎と想定した。排膿散及湯の証は, 歯肉が腫脹しているが発赤の程度が弱い歯周炎, あるいは排膿が認められる歯周炎と想定した。黄連解毒湯, 排膿散及湯とも各10症例に投与し, 良好な結果が得られた。炎症型 (実熱証型) 歯周疾患の急性発作期において, 想定した投薬目標 (証) で, 黄連解毒湯と排膿散及湯のエキス剤が有効であると考えられた。
- 著者
- 安部 昌宏 前田 泰宏 本田 隆文 安川 久美 武藤 順子 髙梨 潤一
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.275-278, 2017 (Released:2017-07-12)
- 参考文献数
- 10
臨床経過および特徴的なMRI所見から可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症 (clinically mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion; MERS) と診断した2症例に対し, 急性期および回復期に脳梁膨大部をMR spectroscopyにて解析した. 2例ともにcholine/creatine比が回復期に比して急性期に高値となり, 髄鞘代謝に何らかの変化が生じていることが示された. みかけの拡散係数の低下が一過性であることと合わせ, MERSの病態として髄鞘浮腫が示唆された.
- 著者
- 飯島 茂子 沼田 充 佐々木 和実
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.8, pp.669-677, 2020 (Released:2020-09-18)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
【背景】ニトリルゴム手袋によるアレルギー性接触皮膚炎の抗原決定基については,いまだ完全には明らかにされていない.【対象】ニトリルゴム手袋によるアレルギー性接触皮膚炎と診断した36 歳女性.【方法】使用していたゴム手袋,ジャパニーズスタンダードアレルゲンおよびその成分,および手袋の化学分析にて検出された物質を用いてパッチテストを行った.【結果】ニトリルゴム手袋,チウラムミックス,ジチオカルバメートミックス,テトラメチルチウラムジスルフィド,ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛が陽性,テトラメチルチウラムモノスルフィド,ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛が疑陽性であった.手袋の化学分析でエチルイソチオシアネートおよびブチルイソチオシアネートが検出され,これらのパッチテストもともに陽性であった.【結語】自験例をエチルイソチオシアネートおよびブチルイソチオシアネートによって感作された接触皮膚炎と診断し,これらアルカリイソチアネートが原因抗原となりうると考えた.加硫促進剤不使用のニトリル手袋は,代替として推奨できる.
2 0 0 0 OA 粘塑性有限要素法によるフレッシュコンクリートの流動解析
- 著者
- 森 博嗣 谷川 恭雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文報告集 (ISSN:09108025)
- 巻号頁・発行日
- vol.374, pp.1-9, 1987-04-30 (Released:2017-12-25)
- 被引用文献数
- 3 2
The purpose of the present paper is to establish a simulation method of the behavior of fresh concrete at its mixing, placing, consolidating, etc. As one of the method to estimate the flow and deformation of fresh concrete, a method of visco-plastic finite element analysis is proposed, and some analytical results are shown in this paper. In the analysis, slip resistance force between boundary surface and fresh concrete can be considered, and the dynamic behavior can be analyzed by calculation of the retardation of velocity change. The results of simulations are in good agreement with those calculated by simple theoretical equations about some examples such as flowing in pipe, parallel-plates plastometer, slump test, and the adequacy of the proposed analytical method is confirmed.
2 0 0 0 OA 日本の消費者団体のシステム
- 著者
- 井上 拓也
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.2_19-2_41, 2012 (Released:2016-02-24)
- 参考文献数
- 22
Types of consumer groups can be classified as customer consumer groups or citizen consumer groups. The former pursues the consumers' economic interests and rights, and generally has a mass - based membership, whereas the latter pursues the social and political interests of the public and stresses consumers' social responsibility. Major consumer groups in most advanced countries were formed as customer consumer groups based on the model of the U.S. Consumers Union in the 1950s and 60s. By contrast, in Japan, major groups were rather organized as a hybrid of both types without a mass - based membership, and have slowly moved between them. This seems to be the main character of the contemporary Japanese consumer group system. The purpose of this article is to analyze how this system was established in the 1960s and why it has been maintained. The article points out three historical conditions that affected the way the CU model was imported to Japan. It also explains how non material selective incentives have employed in maintaining the above mentioned consumer groups in the system.
2 0 0 0 OA 発声・発語障害の評価と対応
- 著者
- 司会:田村 悦代 梅野 博仁 シンポジスト:森 浩一 益田 慎 阪本 浩一 永井 知代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.4, pp.388-392, 2019-04-20 (Released:2019-05-22)
2 0 0 0 OA 隠すことの心理生理学:隠匿情報検査からわかったこと
- 著者
- 松田 いづみ
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.162-181, 2016 (Released:2018-04-13)
- 参考文献数
- 113
- 被引用文献数
- 12
Deception, especially unexpressed deception, concealment, is difficult to detect from words and behavior. Thus, psychophysiological approaches are used to detect deception. One such approach is the Concealed Information Test (CIT). The CIT is used in criminal investigations to examine a subject’s concealing of a memory through autonomic and/or central nervous activities. In contrast, psychophysiologists generally infer cognitive processes from physiological responses. This study aimed to reveal the cognitive processes of concealing the memory by reviewing physiological responses during the CIT. We demonstrated that the intent to conceal memory (or withdrawal motivation) would increase the significance of the memory and recruit controlled processes, such as monitoring and inhibition of physiological responses.
2 0 0 0 OA 遷音速機設計の具体例
- 著者
- 平木 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.311, pp.667-671, 1979-12-05 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 各種製茶の煎出条件とカフェイン・タンニン溶出量及び味との関係
- 著者
- 米田 泰子 加藤 佐千子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.31-38, 1994-02-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 4
In order to discover the correlation between the concentration of caffeine and tannin released by brewing tea and the result of the palatability, as for gyokuro, sencha, mizudasisencha, hojicha, bancha, oolong-tea, we brewed each tea three times and measured the amounts of caffeine and tannin in each different brewing period.1. Gyokuro; The second infusion exuded more caffeine and tannin when it was steeped for 0.5,1,2,3 minutes. And the first infusion exuded more when it was steeped 4 minutes. But in the palatability of each brewing tea there were little differences on the degree of bitterness and astringency. The total taste of the first infusion was the strongest and most preferred.2. Sencha; The second infusion exuded the most caffeine and tannin when it was steeped for 0.5,1 minute. The first infusion exuded them most when it was steeped for 3 or 4 minutes. The bitterness and astringency in the first infusion were as mush as the second infusion and in the third infusion were weaker. The more the tea was rebrewed the weaker the taste got.3. Hojicha, bancha; The first infusion exuded more caffeine and tannin (except 0.5,1 minutes steeped one), and the bitterness and astringency were stronger.4. Oolong-tea; As for the concentration of caffeine and tannin the result was the same as hojicha, bancha. The first infusion with the strongest total taste was not preferred. The second one seemed to be favoured.5. The lower quality teas have a positive correlation between the concentration of caffeine and tannin and bitterness, astringency, umami and popularity. Their tastes seem to be more affected by the concentration of caffeine and tannin. Oolong-tea has a negative correlation between the popularity and the concentration of caffeine and tannin.
- 著者
- 吉見 俊哉
- 出版者
- 日本コミュニケーション学会
- 雑誌
- ヒューマン・コミュニケーション研究 (ISSN:09137041)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.5-17, 2010-03-31 (Released:2017-11-30)