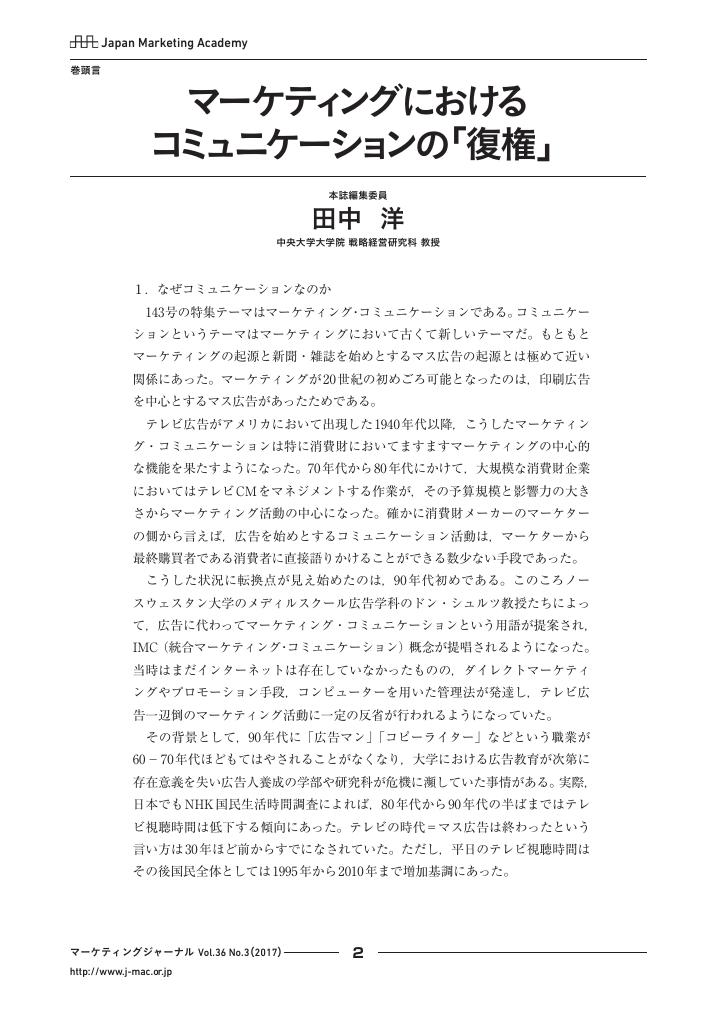- 著者
- 戸崎 敬子 清水 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.39-49, 1987-09-14 (Released:2017-07-28)
大正期における特別学級の実態とその性格を解明するために文部省普通学務局『全国特殊教育状況』(1924年、1927年発行)に記載された「特殊教育」実施校名を手がかりに、現在の学校名と住所を調査した上で該当校に対してアンケート調査を実施した(回収率70.7%)。その結果、60例の特別な取組事例(うち25例が特別学級の事例)を得た。調査結果から次の諸点が判明し、大正期特別学級の全国的実態とそれらの性格の一端を明らかにすることができた。すなわち、1.該当校は学校規模の大きい、伝統のある学校が多い。2.回答事例の特別学級のうち、開設時期の判明した学級のすべてが大正期に開設され、その多くが短期間で消滅している。また学級は多様な呼称を持っている。3.特別学級の対象児童のほとんどが学業成績不良児である。しかし、大正末期には知能検査の普及に伴う変化も生じている。さらに学校沿革誌の史料的価値についても明らかにできた。
2 0 0 0 OA くも膜下モルヒネに高用量のブピバカインを併用し良好な鎮痛が得られた2 症例
- 著者
- 工藤 尚子 三浦 耕資 周東 千緒 村上 敏史 齊藤 理 的場 元弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- pp.13-0014, (Released:2013-09-30)
- 参考文献数
- 9
オピオイドの全身投与で十分な鎮痛が得られなかった2 例のがん性痛患者に対して,くも膜下モルヒネに高用量のブピバカインを併用し良好な鎮痛を得たので報告する.症例1:72 歳の男性で,肺がんの腸腰筋・大腿筋群転移による下肢の痛みに対し,くも膜下鎮痛法を施行した.モルヒネ単独で十分な鎮痛が得られずブピバカインを最大94 mg/日で併用し,痛みはverbal rating scale で4 から1~2 へ軽減した.症例2:64 歳の女性で,直腸がんの皮膚転移による陰部,大腿の痛みに対し,くも膜下鎮痛法を施行した.モルヒネ単独で十分な鎮痛が得られずブピバカインを最大66 mg/日で併用した.レスキュードーズ使用時に下肢のしびれ,低血圧を認めたが,レスキュードーズの調整で軽減し,痛みはnumerical rating scale で10 から2~5 へ軽減した.くも膜下モルヒネの効果が不十分ながん性痛の患者において,ブピバカインを加え,副作用や合併症に注意しながら高用量まで漸増することで,患者満足度の高い優れた鎮痛が得られた.
- 著者
- 畔上 恭彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.154-164, 1996-08-15 (Released:2017-06-28)
臨床において、コミュニケーション場面での子どもの行動の変化を捉えると同時に、その行動の意図、例えば、人に視線を向けたという行動だけなく、子どもの視線の奥の「まなざし」の意図を理解するということが重要な意味を持つ。このような観点からINREALでは、コミュニケーション分析を行い、これを通して、話し手・聞き手はどのように『会話の原則』に従ったかを検討する。今回、自閉的傾向のある発達遅滞児とのプレイ場面において、INREALの『会話の原則』に従ったコミュニケーション指導を行ったところ固執と思われていた行動が、人との関わりの接点となり、大人と子どもとのやり取りへと変化していった。大人が意味のあるコミュニケーションを行うために『会話の原則』を守ることの重要性が示唆された。この『会話の原則』を守っているかどうかは、臨床場面の録画ビデオを検討することで確認できる。
2 0 0 0 OA We-modeサイエンスの構築に向けて
2 0 0 0 OA グラフェンの電気伝導の現状と可能性
- 著者
- 神田 晶申 田中 翔 後藤 秀徳 友利 ひかり 塚越 一仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本真空学会
- 雑誌
- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.85-93, 2010 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 43
Present understanding of electric transport in graphene, a crystalline layer of carbon, is reviewed. In the first part, emphasis is placed on the gap between the ideal and reality of electron transport, which is mostly caused by disorder (charged impurities) in the experimental samples. Disorder which affects the graphene transport originates mainly from charged impurities in the substrate, comtaminants on the graphene surface due to, e.g., resists and sticky tapes, and absorbed gas molecules. The amount of charged impurities and the methods to remove them are discussed. In the second part, the characteristic phenomena in multilayer graphene are explained for spins and Cooper-pair transport, which are relevant to the nonuniform distribution of the carrier density under nonzero gate voltages.
2 0 0 0 OA 日本人地域在住高齢者の呼吸機能は筋力,移動能力,認知機能と関連する
- 著者
- 前田 拓也 上出 直人 戸﨑 精 柴 喜崇 坂本 美喜
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.29-36, 2021 (Released:2021-02-19)
- 参考文献数
- 46
【目的】本研究は地域在住高齢者の呼吸機能に対する運動機能,認知機能,体組成との関連性について検討した。【方法】対象は要介護認定のない65 歳以上の地域在住高齢者347 名とした。呼吸機能として努力性肺活量および1 秒量,運動機能として握力,下肢筋力,Chair Stand Test,Timed Up and Go Test(以下,TUGT),5 m 快適・最速歩行時間,認知機能としてTrail Making Test part A(以下,TMT-A),体組成として骨格筋指数および体脂肪率を評価した。呼吸機能と運動機能,認知機能,体組成との関連を重回帰分析にて分析した。【結果】年齢,性別,体格,喫煙などの交絡因子で調整しても,努力性肺活量は握力,TUGT,TMT-A と有意な関連を示した。同様に,1 秒量は握力,TMT-A と有意な関連を示した。【結論】地域在住高齢者の呼吸機能は運動機能,認知機能が関連することが示唆された。
2 0 0 0 OA 若年女性の味覚感受性と月経周期との関連
- 著者
- 小林 三智子 岡田 幸雄 戸田 一雄
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会
- 巻号頁・発行日
- pp.11, 2007 (Released:2007-08-30)
【目的】 味覚感受性と月経周期との明確な関連性の報告は少ない。我々は、規則的な月経周期の場合には、月経期には電気味覚感受性が有意に低くなることを報告した(1)。本研究では、不規則な月経周期の場合の電気味覚閾値と、認知閾値の変化について検討した。【方法】 19~23歳の健康な女性25名を対象とし、婦人体温計を用いて3ヶ月間基礎体温を記録させた。そのうち、不規則な月経周期をもつ者12名について報告する。味覚感受性の測定には、電気味覚計とろ紙ディスク法を用いた。測定時期は、月経期(月経期間中)・黄体期(月経開始前1週間)・卵胞期(月経終了後1週間)の3期とし、それぞれの期に各1日測定を実施し、3回の平均値を閾値とした。5基本味は、甘味(スクロース)、塩味(塩化ナトリウム)、酸味(酒石酸)、苦味(硫酸キニーネ)及びうま味(グルタミン酸ナトリウム)を用いた。【結果】 電気味覚閾値では、舌尖部の茸状乳頭刺激、舌縁後方の葉状乳頭刺激ともに、月経期は黄体期と卵胞期に比べ高い値となり、月経期には電気味覚感受性が低いことが認められた。一方、ろ紙ディスク法により求めた認知閾値は、甘味・塩味及び苦味では月経周期による有意差は認められなかった。しかし、酸味では茸状乳頭において、月経期 (19.6mM)は黄体期(10.4mM)・卵胞期(14.2mM)に比べ有意に高い値を示し、味覚感受性が低いことが認められた。また、うま味では茸状乳頭において、月経期には黄体期に比べ有意に味覚感受性が高いことが認められた。 (1)小林三智子、岡田幸雄、戸田一雄:日本家政学会第59回大会研究発表要旨集(2007)
- 著者
- 高取 克彦 岡田 洋平 梛野 浩司 徳久 謙太郎 生野 公貴 鶴田 佳世
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.382-389, 2011-08-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
【目的】日本語版STRATIFYおよびMorse Fall Scale(MFS)の作成とリハビリテーション専門病院における有用性を検討すること。【方法】2008年8月からA病院回復期リハビリテーション病棟に新規入院した患者120名を対象とした。日本語版STRATIFYおよびMFSの作成は開発者の許可を得て完成させた。STRATIFYおよびMFSは入院時に評価し,3ヵ月間の転倒発生を前向きに調査した。データ解析には転倒発生日をエンドポイントとした生存分析(Kaplan-Meier法)を用い,また比例ハザード解析にて転倒発生の危険因子を抽出した。【結果】累積生存率ではSTRATIFYを用いた場合,ハイリスク群で生存率の有意な低下が認められたが,MFSではその差は有意ではなかった。また比例ハザード解析においては,2点以上のSTRATIFYスコアが有意な転倒危険因子として抽出された。【結論】STRATIFYは,本邦リハビリテーション病棟においても転倒ハイリスク者を良好に判別できる簡便なアセスメントツールである。
- 著者
- SUZUKI Yasuhiro ISHII Shoko INAMURA Tetsuya NARA Yumiko TAKAHASHI Hirofumi BATTULGA Sukhee ENKHTAIVAN Dangaa NARANGEREL Serd-Yanjiv ARIUNAA Chadraabal SERJMYADAG Dalai ALTANBADRALT Batsukh BADRAL Tuvshin
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.1, pp.1-9, 2019-12-27 (Released:2019-12-27)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
As emphasized in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR) 2015–2030, an important key for enhancing citizens’ resilience is cooperation, in which universities and academic organizations may bear the burden of connecting people. Recently, some universities have conducted various DRR education programs together with local governments and citizens in Japan. In this report, we introduce the progress of our three international cooperative projects between Japan and Mongolia conducted between 2014 and 2018: 1) establishment of the Cooperative Center for Resilience Research (CCRR) by the National University of Mongolia and Nagoya University; 2) the Public Symposium for Earthquake DRR with the Mongolian Government; and 3) the Grass-Roots Joint Project of the Japan International Cooperation Agency (JICA) for disaster awareness in Khovd Province (Aimag), Mongolia. Through these transdisciplinary research projects, we intended to identify the essential conditions for an effective enhancement of citizens’ resilience. As a result, we found the following key aspects to be considered in international DRR cooperation flamework: 1) transfer the spirit of DRR rather than simply its components, 2) customize DRR to match the climate and residents’ temperament in the target area, 3) consider whether the project is consistent with the public policy of the target area, and 4) involve regional organizations and residents to ensure continuity for DRR activity.
2 0 0 0 OA 胆嚢摘出後症候群についての検討
- 著者
- 森田 章夫 小野山 裕彦 宮崎 直之 斎藤 洋一
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.1560-1565, 1992-07-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 19
胆嚢摘出術の功罪について検討する目的で,最近10年間に経験した胆石症例で胆嚢摘出術のみを施行した276例を対象として,術後合併症およびアンケート調査に基づいた遠隔成績より胆嚢摘出後症候群について検討した.術前の症状や併存疾患の有無と,術後合併症および遠隔時愁訴との間に関連性は認めなかった.術後合併症は37例(13.4%)にみられたがほとんどが一過性の軽度なものであった.アンケートは229例(82.8%)について回収し26例(11.4%)に遠隔時愁訴を認めた. 26例のうち18例に対し追跡調査を行い,慢性肝炎2例を除く16例の画像診断および血液検査上異常は認めなかった.遠隔時愁訴で最多の腹痛は14例(6.1%)に認められたが,術後5年以上経過した症例には認めなかった.以上より,胆嚢摘出術は術後合併症,遠隔成績ともに極めて満足すべきものであり,その根治性や癌合併の危険性を考慮すると手術療法が治療の原則であると思われた.
2 0 0 0 OA 置鍼刺激が網膜感度とその測定に与える影響
- 著者
- 福野 梓 鶴 浩幸 生島 美紀 山田 潤
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.628-635, 2006-08-01 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 15
【目的】置鍼刺激は仮性近視や眼精疲労の改善に有用であり、毛様体筋緊張低下、縮瞳、脈絡膜血流増加などの作用を有する。今回、置鍼刺激が網膜感度閾値に及ぼす影響について検討した。【方法】屈折異常以外に眼科的疾患を有しない健康成人11例11眼 (平均年齢27.8歳±7.1、平均±標準偏差) を対象とした。鍼刺激は仰臥位にて両側の合谷、太陽、上晴明穴に10分間の置鍼術を行った。鍼刺激前後における網膜感度閾値をハンフリー視野計のBlue on Yellow視野プログラムを用いて測定し、感度低下の際に指標となるMean deviation (MD) 値と中心窩閾値とについて比較検討した。また、視野測定時間の変化を評価した。同一症例における10分間の安静仰臥位を対照とし同検討を行った。【結果】鍼刺激前後、安静前後におけるMD値や中心窩閾値に変化はなく、両群間にも有意な差は検出できなかった。しかし、安静仰臥位後の視野測定時間は有意に延長したが (14.9±20.1秒, p<0.05) 、鍼刺激後では有意な変化がみられず、逆に3.6±56.9秒短縮した。測定時間が5秒以上短縮した被験者は鍼刺激群に有意に多かった (p<0.05) 。【考察】健康成人に対する鍼刺激ではハンフリー視野計で検出できる程度の網膜感度閾値変化はみられなかった。測定時間延長には感度測定時のばらつきに対する閾値再測定や固視不良が密接に関連しており、鍼刺激による網膜感度の維持、眼精疲労の減少、集中力の持続などが示唆された。
2 0 0 0 OA 食飼料素材中の有害物質
- 著者
- 葛西 隆則
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.S61-S68, 1993-05-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 医療デバイスの進歩~糖尿病治療用注射製剤のペン型注入デバイスの変遷と療養指導の関係~
- 著者
- 朝倉 俊成
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.408-422, 2016-12-25 (Released:2017-02-25)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 1
日常生活において厳格に血糖をコントロールするために、インスリン療法の基本として、生理的インスリン分泌に近いbasal-bolus療法が行われている。インスリン療法には頻回インスリン療法(MDI)と持続皮下インスリン注入療法(CSII)があり、MDIではペン型注入デバイス、CSIIではポンプ式注入デバイスによって行われる。インスリンを皮下に適正に注入するには高精度で高品質な注入デバイスが必要で、同時に患者にとって操作性や認知性、快適性、そして信頼性などが得られるものでなければならない。注入デバイスの開発は、長い期間と段階を経てこれらの項目について改良が加えられてきたが、今後は患者の手技においてもより適正性が確保できるような補助機能の追加や今まで以上の携帯性の向上、患者個々の糖尿病療養生活の細部に対応したプログラム機能を有するなど、「個」に対応可能なデバイスの開発が期待される。
2 0 0 0 OA マーケティングにおけるコミュニケーションの「復権」
- 著者
- 田中 洋
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.2-5, 2017-01-10 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- Eri Kamon Chihiro Noda Takumi Higaki Taku Demura Misato Ohtani
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.331-337, 2021-09-25 (Released:2021-09-25)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 4
Secondary cell walls (SCWs) accumulate in specific cell types of vascular plants, notably xylem vessel cells. Previous work has shown that calcium ions (Ca2+) participate in xylem vessel cell differentiation, but whether they function in SCW deposition remains unclear. In this study, we examined the role of Ca2+ in SCW deposition during xylem vessel cell differentiation using Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells carrying the VND7-inducible system, in which VND7 activity can be post-translationally upregulated to induce transdifferentiation into protoxylem-type vessel cells. We observed that extracellular Ca2+ concentration was a crucial determinant of differentiation, although it did not have consistent effects on the transcription of VND7-downstream genes as a whole. Increasing the Ca2+ concentration reduced differentiation but the cells could generate the spiral patterning of SCWs. Exposure to a calcium-channel inhibitor partly restored differentiation but resulted in abnormal branched and net-like SCW patterning. These data suggest that Ca2+ signaling participates in xylem vessel cell differentiation via post-transcriptional regulation of VND7-downstream events, such as patterning of SCW deposition.
2 0 0 0 OA 熟練訪問看護者の意思決定の構造 : 在宅療養者の自己決定への支援
- 著者
- 松村 ちづか 川越 博美
- 出版者
- 一般社団法人 日本地域看護学会
- 雑誌
- 日本地域看護学会誌 (ISSN:13469657)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.19-25, 2001-03-01 (Released:2017-04-20)
本研究の目的は,在宅療養者の自己決定と家族の意向が不一致な状況において,熟練訪問看護者がその不一致を解決し,療養者の自己決定を実現するためにどのような意思決定をしているのか,構成要素および構造を明確にし,療養者の自己決定を支えるための訪問看護者の意思決定のあり方の示唆を得ることである.対象は5名の熟練訪問看護者で,継続的な家庭訪問での参加観察とインタビューを用いた質的記述研究を行った.その結果,熟練訪問看護者が認識した療養者の自己決定と家族の意向が不一致である内容としては,療養者の日常のケア,治療,生き方に関するものがあった.また,不一致の根底にある療養者と家族の関係性として,家族が療養者を大切に思うがゆえに不一致が生じているものと過去からの関係性の困難さから不一致が生じているものがあった.熟練訪問看護者の意思決定の構成要素として,訪問看護者としてのあり方を意味する2コアカテゴリー【訪問看護者としての生き方】【個人としての生き方】,意思決定のプロセスを意味する10コアカテゴリー【役割認識をもつこと】【了解すること】【自己関与させること】【自己と対話すること】【支援目標をもつこと】【見通すこと】【決断すること】【働きかけのタイミングを掴むこと】【働きかけ方の選定をすること】【支援について省みること】が抽出された.これらのコアカテゴリーを各熟練訪問看護者の意思決定の経時的プロセスに当てはめてみた結果,熟練訪問看護者の意思決定の全体を構造化することができた.以上の結果から,訪問看護者が在宅療養者の自己決定と家族の意向が不一致な状況を解決し療養者の自己決定を支えるためには,療養者と家族が共に納得できるような方向性の家族ケアを提供する必要性が示唆された.そして,訪問看護者の意思決定のあり方として,療養者の自己決定する権利を認識し,療養者の心身の利益の優先という倫理的,かつ自己のあり方を問う自律的な意思決定をしていく重要性が示唆された.
2 0 0 0 OA 昭和恐慌後における佐々木要右衛門家事業の展開 -広島県備後織物業史の研究-
- 著者
- 山崎 広明
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.3-26,95, 2006-09-25 (Released:2009-11-06)
The purpose of this article is to analyze the development of entrepreneurial activities of the Youemon Sasaki family at Shin'ichi in Bingo region which is located in the eastern part of Hiroshima Prefecture during the period after the Showa panic (1930-31) until the wartime (July, 1937-August, 1945). The author utilized such various materials as the oral history, the printed matters and the Sasaki archives to accomplish the above purpose.Youemon Sasaki, successful local wholesale merchant, were seriously hit by the Showa panic, and thereafter, the restructuring by the young leader, Gi'ichi Sasaki, became unavoidable. Gi'ichi closed the weaving factories established in 1915, began sewing business, came to sell new commodities such as wide cloths and garments to the local areas and continued seeking such gains as dividends and rents of land and houses.At the wartime Gi'ichi greatly committed himself to sewing business and kept the wealthy local businessman by becoming a salaried manager in Bingo Tokumen Kasuri Moto Haikyu Kabusiki Kaisha (Bingo Kasuri Distribution Company) and Huhaku Seihin Chuo Seizo Haikyu Tosei Kabushiki Kaisha (Cloth Goods Central Manufacturing Distribution Company). He also earned lots of money through dividends of shares during wartime.In recent years many economic and business historians in Japan are making great efforts to describe the local entrepreneurial activities in the prewar years, and this article is also included in such an academic trend.
2 0 0 0 OA 運動部活動における生徒の体罰受容の問題性:エーリッヒ・フロムの権威論を手掛かりとして
- 著者
- 大峰 光博
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.15109, (Released:2016-09-29)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to analyze problems related to the mechanism whereby students can accept corporal punishment during extracurricular sports activities with reference to the books Escape from Freedom and Man for Himself that were central to Erich Fromm's authority theory. Specifically, the author focused on the concepts of “authoritarian character,” “authoritarian ethics,” and “authoritarian conscience.” Fromm pointed out that anxiety prompted Germany's citizens to give up their freedom in order to obey authoritarian powers such as Hitler and the Nazis. Students taking part in extracurricular sports activities were considered from the viewpoint of Fromm's authority theory. It was revealed that students comply with a leader's authority in order to relieve anxiety, and have positive thoughts about corporal punishment. Furthermore, it was found that such acceptance of corporal punishment succeeded in eliminating conspicuous suffering, but not in removing any underlying conflicts. Fromm pointed that fear of anxiety was relieved by spontaneous activity. To achieve spontaneous activity by students, it was suggested that some form of measure that does not create the type of partnership that occurred between Germany's citizens and Hitler would be desirable for any relationship between the leader of extracurricular sports activities and the students.
- 著者
- Tomoko Maekawa Kouhei Kamiya Katsutoshi Murata Thorsten Feiweier Masaaki Hori Shigeki Aoki
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.227-230, 2021 (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 5
The microstructural underpinnings of reduced diffusivity in transient splenial lesion remain unclear. Here, we report findings from oscillating gradient spin-echo (OGSE) diffusion imaging in a case of transient splenial lesion. Compared with normal-appearing white matter, the splenial lesion exhibited greater differences between diffusion time t = 6.5 and 35.2 ms, indicating microstructural changes occurring within the corresponding length scale. We also conducted 2D Monte-Carlo simulation. The results suggested that emergence of small and non-exchanging compartment, as often imagined in intramyelinic edema, does not fit well with the in vivo observation. Simulations with axonal swelling and microglial infiltration yielded results closer to the in vivo observations. The present report exemplifies the importance of controlling t for more specific radiological image interpretations.