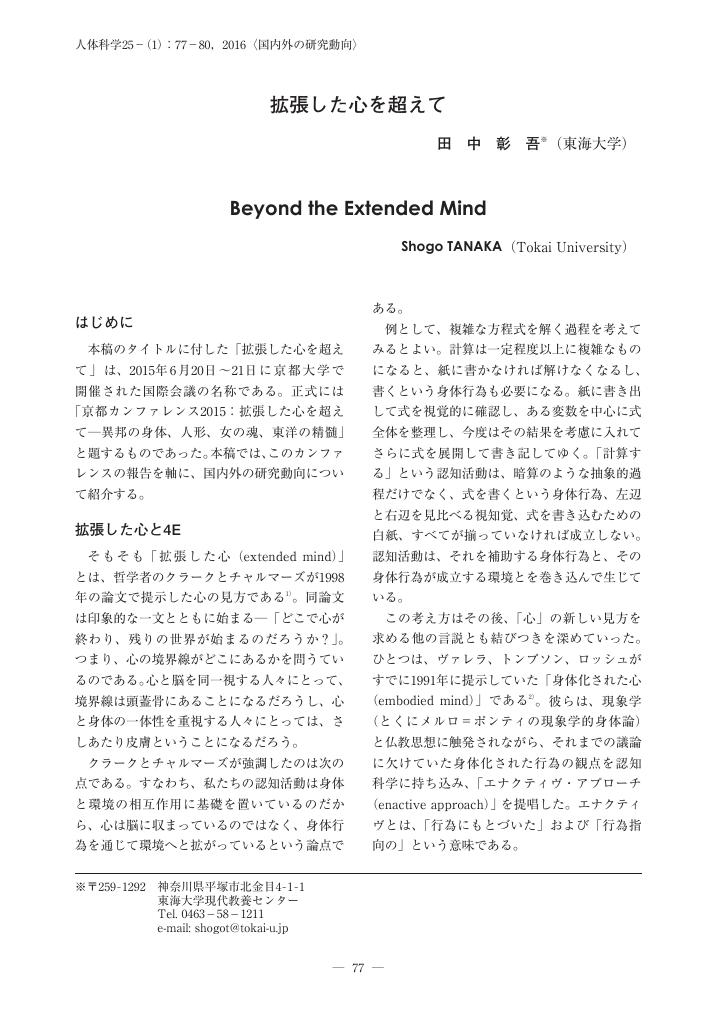2 0 0 0 OA 掌蹠膿疱症
- 著者
- 上出 良一
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.355-364, 1994-06-15 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
掌蹠膿庖症は手掌, 足底に限局する再発性の膿疱形成と, それに続く落屑性紅斑性皮疹を特徴とする疾患である。本症の10-15%に胸肋鎖骨異常骨化症を伴うが, 骨シンチグラムを行うと更に高頻度に潜在性の骨関節炎が見出される。大多数の患者では扁桃や歯肉などの細菌感染を基盤とした病巣感染が病因として考えられ, また扁桃上皮と掌蹠皮膚の角層で交差反応を示す抗ケラチン抗体が検出されている。少数の患者では歯科金属除去により軽快する。今後スーパー抗原の関与やサイトカインネットワークの乱れなどについて検討すべきである。治療の第一選択としてステロイド剤の外用が最も行われているが, PUVA単独あるいはレチノイドとPUVAの併用 (Re-PUVA) も用いられる。シクロスポリン内服 (5mg/kg日以下) は極めて有効で難治例に試みてよいであろう。完治には基盤となる病巣感染を扁桃摘出, 歯科処置などで除去することが推奨されているが, 信頼性のある術前の評価法が未だ確立されていない。皮膚科, 耳鼻咽喉科, 歯科, 整形外科その他関連科の密接な連携が本症患者にとって診療上大切である。
2 0 0 0 OA 救援物資輸送の地理学
- 著者
- 荒木 一視 岩間 信之 楮原 京子 田中 耕市 中村 努 松多 信尚
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.100001, 2015 (Released:2015-10-05)
災害に対する地理学からの貢献は少なくない。災害発生のメカニズムの解明や被災後の復旧・復興支援にも多くの地理学者が関わっている。そうした中で報告者らが着目したのは被災後の救援物資の輸送に関わる地理学的な貢献の可能性である。 救援物資の迅速かつ効果的な輸送は被害の拡大を食い止めるとともに,速やかな復旧・復興の上でも重要な意味を持っている。逆に物資の遅滞は被害の拡大を招く。たとえば,食料や医薬品の不足は被災者の抵抗力をそぎ,冬期の被災地の燃料や毛布の欠乏は深刻な打撃となる。また,夏期には食料の腐敗が早いなど,様々な問題が想定される。 ただし,被災地が局地的なスケールにとどまる場合には大きな問題として取り上げられることはなかった。物資は常に潤沢に提供され,逆に被災地の迷惑になるほどの救援物資の集中が,「第2の災害」と呼ばれることさえある。しかしながら,今般の東日本大震災は広域災害と救援物資輸送に関わる大きな問題点をさらすことになった。各地で寸断された輸送網は広域流通に依存する現代社会の弱点を露わにしたといってもよい。被災地で物資の受け取りに並ぶ被災者の長い列は記憶に新しいし,被災地でなくともサプライチェーンが断たれることによって長期間に渡って減産を余儀なくされた企業も少なくない。先の震災時に整然と列に並ぶ被災者を称えることよりも,その列をいかに短くするのかという取り組みが重要ではないか。広域災害時における被災地への救援物資輸送は,現代社会の抱える課題である。それは同時に今日ほど物資が広域に流通する中で初めて経験する大規模災害でもある。 遠からぬ将来に予想される南海トラフ地震もまた広い範囲に被害をもたらす広域災害となることが懸念される。東海から紀伊半島,四国南部から九州東部に甚大な被害が想定されているが,これら地域への救援物資の輸送に関わっては東日本大震災以上の困難が存在している。第1には交通網であり,第2には高齢化である。 交通網に関してであるが,東北地方の主要幹線(東北自動車道や東北本線)は内陸部を通っており,太平洋岸を襲った津波被害をおおむね回避しえた。この輸送ルート,あるいは日本海側からの迂回路が物資輸送上で大きな役割を果たしたといえる。しかしながら,南海トラフ地震の被災想定地域では,高速道路や鉄道の整備は東北地方に比べて貧弱である。また,現下の主要国道や鉄道もほとんどが海岸沿いのルートをとっている。昭和南海地震でも紀勢本線が寸断されたように,これらのルートが大きな被害を受ける可能性がある。また,瀬戸内海で山陽の幹線と切り離され,西南日本外帯の険しい山々をぬうルートも土砂災害などに対して脆弱である。こうした中で紀伊半島や四国南部への救援物資輸送は問題が無いといえるだろうか。 同時に西日本の高齢化は東日本・東北のそれよりも高い水準にある。それは被災者の災害に対する抵抗力の問題だけでなく,救援物資輸送にも少なからぬ影響を与える。過去の災害史をひもとくと,救援物資輸送で肩力輸送が大きな役割を果たしたことが読み取れる。こうした物資輸送に携われる労働力の供給においてもこれらの地域は脆弱性を有している。 以上のような状況を想定した時,南海トラフ地震をはじめ将来発生が予想される広域災害に対して,準備しなければならない対応策はまだまだ多いと考える。耐震工事や防波堤,避難路などの災害そのものに対する対策だけではなく,被災直後から始まる救援活動をいかに迅速かつ効率よく実施できるかということについてである。その際,被災地における必要な救援物資の種類と量を想定すること,救援物資輸送ルートの災害に対する脆弱性を評価し,適切な迂回路を設定すること,それに応じて集積した物資を被災地へ送付する前線拠点や後方支援拠点を適切な場所に設置すること等々,自然地理学,人文地理学の枠組みを超えて,地理学がこれまでの成果を踏まえた貢献ができる余地は大きいのではないか。議論を喚起したい。
- 著者
- 室井 尚
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.140, 2011-12-31 (Released:2017-05-22)
2 0 0 0 OA 子どもの本とアンチ・メルヘン
- 著者
- 吉原 高志
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.74-84, 1999-03-15 (Released:2018-03-31)
2 0 0 0 OA 振動・音響信号を利用した建築物のシロアリ防除に関する研究
- 著者
- 富来 礼次 大鶴 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.100-107, 2017 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA イギリス産業革命と労務管理
- 著者
- 鈴木 良隆
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.23-45,ii, 1971-03-25 (Released:2010-11-18)
This thesis deals with two aspects of labour management of the Lancashire cotton industry during the first half of the 1830's; 1) organization within workshops and 2) the efficient use of labour. The main difficulties of these two aspects as faced by mill-owners during the Industrial Revolution Era has been repeatedly pointed out by Andrew Ure.1) As regards organization within workshops: as a conclusion of the author's study of that “Indirect Employment by the Master”, the intervention by the mill-owner in the matter of the management is clearly seen in several points. On the other hand, under “Direct Employment by the Masters”, the centralized management by mill-owners can be seen but even in that case there was no completed organization of management from the first. The work of the overseer was differenciated because of the division of processes, due to the expansion of the mills, and the regulation of the organization of operation.2) As regards the efficient use of labour: though attention was paid to the appropriate placement of the labour and the skill, the maintenance of factory discipline was the most significant. For the maintaining of discipline the use of fines and threat importance was attached to educating for the purpose of moral improvement.
2 0 0 0 OA 気候変動が九州および南西諸島地域における果樹生産に及ぼす影響
- 著者
- 山本 雅史
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業研究 (ISSN:18828434)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.46-48, 2020 (Released:2021-04-23)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 脳機能の解析方法
- 著者
- 福山 秀直
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3+4, pp.149-155, 2010 (Released:2012-01-01)
- 参考文献数
- 10
【要旨】脳機能画像の解析において、問題となることを中心に、間違いやすい点や、初期からの進展について、まとめてみた。問題は、いろいろあるが、多くの場合、初期のころと異なり、コンピュータが速くなったため、簡単に結果を得ることができ、その解析のプロセスを理解しない研究が散見される。解析方法、統計学は、統計画像の基礎であり、それらについて概説し、画像解析法の問題点について述べた。最近の話題として、default mode networkについても触れた。
2 0 0 0 OA 本みりんのジャガイモ煮熟時における機能性成分におよぼす影響
- 著者
- 木下 枝穂 久保倉 寛子 石田 丈博 津田 淑江
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.146-155, 2007-06-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 27
本研究では,煮加熱におけるジャガイモの機能性成分の変化におよぼす本みりんの影響を検討した。アスコルビン酸量および風味形成に関与するアミノ酸分析を行った。また,DPPHラジカル消去活性を測定し,抗酸化活性の検討を行った。その結果,本みりんは,加熱によるアスコルビン酸の減少を抑制していることが明らかとなった。この効果は,本みりん中に含まれるエタノールによるものではないことが明らかとなった。アミノ酸分析の結果,みりん溶液およびエタノール溶液でジャガイモを加熱することにより,ジャガイモの構成アミノ酸は減少し,遊離型のアミノ酸量は増加した。このことより,本みりんおよびエタノール溶液で加熱することにより,ジャガイモに含まれるタンパク質やペプチド内の結合の加水分解が促進されたと考えられた。また,少量の煮汁で加熱した場合,本みりんによるラジカル消去活性は大きく増加した。
- 著者
- 内藤 景 谷川 聡
- 出版者
- The Japan Journal of Coaching Studies
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.225-229, 2014-03-20 (Released:2019-09-02)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 犯罪被害者支援に携わる精神科医の2 つの「専門性」
- 著者
- 岡村 逸郎
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.132-153, 2016-05-31 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 53
本稿の目的は,小西聖子が犯罪被害者支援に携わる精神科医としての「専門性」をいかにして形成したのかを,精神的被害の管轄権とケアの非対称性に注目して明らかにすることである. 小西は,第1 に,法学者や法律の実務家というほかの領域の専門職が2 次被害を予防するために精神的被害を理解する必要があるとしたうえで,法的な枠組みにおいてとりこぼされる精神的被害を測定することによって,「専門性」を担保しようとした.第2 に,精神科医―クライエント間の関係の非対称性が露呈することによって生じる2 次被害を予防しながらも同時に治療効果のある,有効な治療法を洗練することによって,「専門性」を担保しようとした. 以上の2 つの「専門性」は,誰に対する「専門性」なのかという点と,精神科医の加害者性が問題になるか否かという点において,異なる水準のものだった.しかしそれらが組み合わさることによってこそ,カウンセリングの実務に従事しつつも法制定を求めるかたちで犯罪被害者支援に携わる,精神科医の「専門性」が形成された. 本稿は,これらの2 つの「専門性」に注目することで,犯罪被害者支援の基盤をつくった精神科医の活動がいかにして可能になったのか明らかにした.そのことによって,先行研究によって十分に検討されてこなかった,犯罪被害者を対象にする福祉実践の基盤の歴史的な形成過程を明らかにした.
- 著者
- Michael H. Walter Jens Dreyhaupt Torsten Mundt Ralf Kohal Matthias Kern Angelika Rauch Frank Nothdurft Sinsa Hartmann Klaus Böning Julian Boldt Helmut Stark Daniel Edelhoff Bernd Wöstmann Ralph Gunnar Luthardt Wolfgang Hannak Stefan Wolfart Guido Heydecke Florentine Jahn Peter Pospiech Birgit Marré
- 出版者
- Japan Prosthodontic Society
- 雑誌
- Journal of Prosthodontic Research (ISSN:18831958)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.498-505, 2020 (Released:2020-08-08)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 8
Purpose: This analysis focused on periodontal health in shortened dental arches (SDAs). Methods: In a randomized controlled clinical trial, patients with missing molars in one jaw and at least one premo-lar and canine on both sides were eligible for participation. In the partial removable dental prosthesis (PRDP) group ( n = 79), molars were replaced with a precision attachment retained PRDP. In the SDA group ( n == 71), the SDA up to the second premolars was either left as is or restored with fixed den- tal prostheses. Outcome variables were vertical clinical attachment loss (CAL-V), pocket probing depth (PPD), bleeding on probing (BOP) and plaque index (PLI). For CAL-V and PPD, the changes at six mea- suring points per tooth were analyzed. For BOP and PLI, patient related rates were calculated for each point in time. Statistical methods included linear regression analyses. Results: In the intention-to-treat (ITT) analysis for CAL-V in the study jaw, the 10 year patient related mean changes were 0.66 mm in the PRDP group and −0.13 mm in the SDA group. The resulting mean patient related group difference of 0.79 mm (95% CI: 0.20 mm–1.38 mm) was significant ( p = 0.01). There were no significant differences in the ITT analyses for PPD. For BOP and PLI, significant group differences with more favorable results for the SDA group were found. Conclusions: In view of lacking substantial differences for CAL-V and PPD, the overall differences were considered of minor clinical relevance. The results add confirmatory evidence to the shortened dental arch concept and its clinical viability (controlled-trials.com ISRCTN97265367).
2 0 0 0 OA 政策の連続と変容 -日本医療制度の構造-
- 著者
- 衛藤 幹子
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.135-153, 1997-12-10 (Released:2009-12-21)
- 被引用文献数
- 2 2
2 0 0 0 OA 自招危難について
- 著者
- 小名木 明宏
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.142-159, 2005-02-15 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA 戦災復興における瓦礫処理の実態
- 著者
- 太刀川 宏志 大沢 昌玄 岸井 隆幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.687-692, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
災害後には瓦礫が発生し、まず復旧復興に先駆け、瓦礫処理を行う必要がある。第二次世界大戦では全国215都市が被害を受け、戦災復興においても、広範囲で一度に一気に行う必要がある瓦礫処理は大きな課題であり、戦災地応急対策として最初に清掃事業(瓦礫処理)が実施された。東日本大震災の被害は非常に広範囲に及んでおり、広範囲で一度に一気に発生した災害における瓦礫の処理方策を学ぶ上で、戦災復興の瓦礫処理を解明して今後に活かす必要がある。あわせて、災害時における瓦礫処理についての備えを考えていく上でも、過去の災害復興を振り返り今後に生かしていくことは意義があると考える。そこで本研究は、戦災復興誌より戦災復興における瓦礫処理の方針を把握した上で、実際の戦災瓦礫処理を都市別に抽出し、処理内容毎にまとめる。さらに、特徴的な戦災瓦礫の処理方策を見出す。戦災瓦礫処理は、制度として戦災復興土地区画整理事業区域を対象としたことが本研究を通じて確認できたことから、見直しにより土地区画整理区域外となった地区を多く抱えた東京の戦災瓦礫処理について具体事例として述べることとする。
2 0 0 0 OA GISとインターネット情報による江戸期以降の歴史空間データの迅速作成
- 著者
- 貞広 幸雄
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.100003, 2012 (Released:2013-03-08)
本論文では,GISとインターネット情報を用いて,江戸末期~明治初期の歴史空間データを簡便に作成する方法を提案する.ここでは初等中等教育や地域情報のインターネット上での発信などでの利用を念頭に置き,情報の厳密さよりも作成の簡便さを重視した方法を採用する.対象地域は現在の千葉県全域であり,主として江戸末期~明治初期の以下4種の空間データを整備した.1) 地形,2) 人口分布,3) 交通網,4) 行政区.
2 0 0 0 OA 「硬さ」「重さ」の感覚と消費者の意思決定 ─ 身体化認知理論に基づく考察 ─
- 著者
- 外川 拓 石井 裕明 朴 宰佑
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.72-89, 2016-03-31 (Released:2020-04-21)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 1
近年の研究では,本来,消費者の判断と直接的に関連していない触覚情報,すなわち非診断的触覚情報が,意思決定に無意識のうちに影響を及ぼすことが明らかにされている。本稿では,非診断的触覚情報のなかでも特に硬さと重さに注目し,これらが消費者の意思決定に及ぼす影響について,身体化認知理論をもとに考察した。硬さに注目した実験1と実験2では,硬さの経験が本来関連のない製品に対する知覚品質を向上させたり,サービスの失敗に対する金銭的補償の要求水準を高めたりすることが明らかになった。重さに注目した実験3と実験4では,重さの経験が本来関連のない製品に対する信頼性や製品情報に関する記憶想起を高めることが明らかになった。最後に,これらの結果を踏まえ,本研究の意義と課題について議論を行った。
2 0 0 0 OA 7. フィルム録音技術
- 著者
- 竹下 彊一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.307-315, 1971-04-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA 拡張した心を超えて
- 著者
- 田中 彰吾
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.77-80, 2016 (Released:2018-03-01)
- 著者
- Hiroshi Ueda Sakiko Orui Sakaguchi
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.29-38, 2019-02-27 (Released:2019-03-12)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3
The brackish-water calanoid copepod known as Pseudodiaptomus inopinus in the mainland of Japan consists of two genetically separate species. One is P. japonicus, which was once synonymized with P. inopinus but was recently revived. This paper describes the other species as Pseudodiaptomus yamato n. sp., which is confirmed to have morphological differences from P. inopinus s.s. based on specimens from the type locality (Lake Taihu, China) of the latter. We also redescribe P. japonicus and P. inopinus s.s. for comparative purposes. The three species are distinguishable by the combination of the following morphologies: 1) weak or prominent posterior round projections of the female last pediger; 2) relative length of posterior processes of the female genital operculum; 3) presence or absence of medial spinules on the first exopodal segment of the female leg 5; and 4) the size of spinules at the center of the ventral surface of the male second urosomite. Significant inter-population variation is observed in some spinules of P. japonicus. The past and present records indicate that Pseudodiaptomus yamato n. sp. is endemic to Japan and confined to the coasts affected by the warm Kuroshio Current from western Kyushu to the middle of Honshu, while P. japonicus is widespread in northern East Asia without overlapping the range of P. yamato n. sp. The range of Pseudodiaptomus inopinus s.s. most certainly does not extend to those of P. yamato n. sp. and P. japonicus.