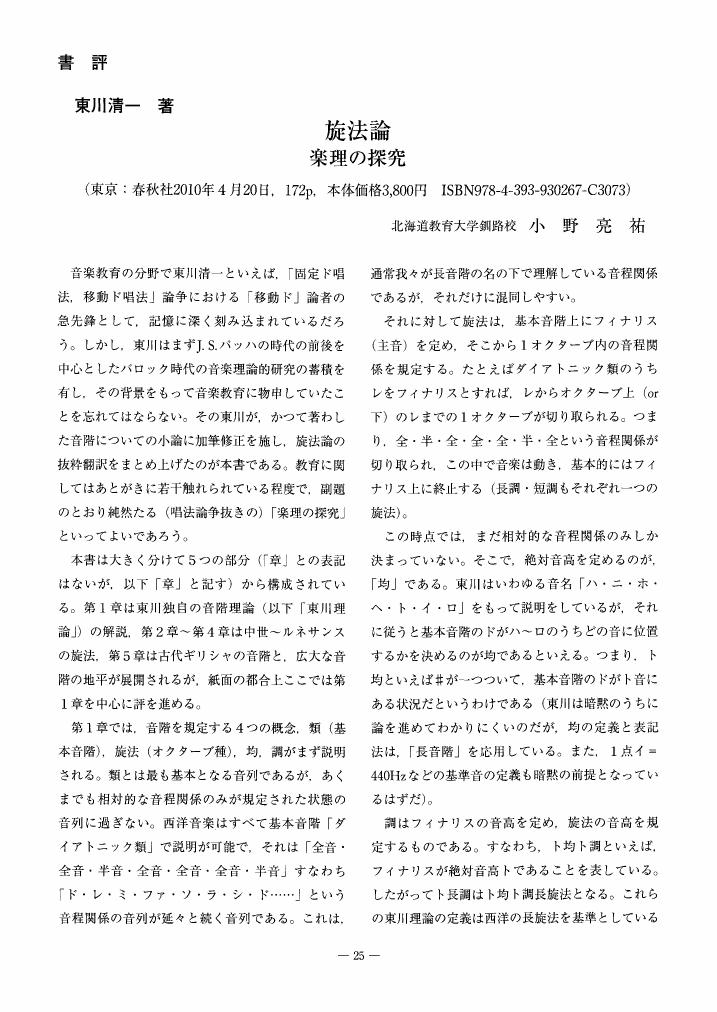2 0 0 0 OA 日本産クモ毒腺中の生物活性アミンの定量および液体クロマトグラフィーによる毒成分の比較
- 著者
- 萩原 健一 鴾田 明子 三輪 昭子 川合 述史 村田 義彦 内田 明彦 中嶋 暉躬
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.77-84, 1991-06-15 (Released:2016-08-26)
- 被引用文献数
- 2 3
野外にて採集した9種類の日本産クモの毒腺中の化学成分のうちカテコラミン, ポリアミン等の生物活性アミンに着目し, これらの含有量を定量し比較した。その結果, クモ毒腺はカテコラミン類の含量は低いがポリアミンの含量が高いことが示された。ただし, 刺咬時の痛みが激しいことで知られているカバキコマチグモだけは例外的に, 毒腺にカテコラミン類およびセロトニンが検出され, これらが低分子の発痛物質として作用していると考えられた。毒腺抽出物を逆相高速液体クロマトグラフィー(逆相HPLC)により分離分析したところ, 各クモに固有のクロマトグラムパターンが得られ, クモ毒成分の多様性が示された。さらに, 逆相HPLCで分画した毒成分について, イセエビ歩脚の神経-筋標本を用いて神経伝達阻害作用をもつ物質のスクリーニングをおこなったところ, クサグモ(Agelena)の毒分画中に新たな神経毒を見いだした。
2 0 0 0 OA 蜘蛛刺咬症の 1 例
2 0 0 0 OA 深泥池におけるミズグモの生息場所の水質条件
- 著者
- 桝元 敏也 桝元 智子 吉田 真 西川 喜朗
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.121-124, 1998 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 4
ミズグモ (Argyroneta aquatica) は水中で生活を行う唯一のクモであるが, 日本では生息環境の分断化と悪化から限られた水域にしか生息しておらず, 早急に保全の対策が必要とされている. ところが, ミズグモの生息環境に関する情報はこれまで報告されていなかった. ミズグモを保全するための研究として, 我々は1996年の5月に京都府深泥池において, ミズグモの生息水域と生息しない水域の水の温度, pH, 溶存酸素 (DO) を比較した. その結果, ミズグモの生息する水域は pH と DO が共に低かった. 特に DO は魚の生息のできないほどの低い値であり, このことによってミズグモは天敵である魚から逃れることができるとみられる. また, この低 pH と DO は深泥池に分布するミズゴケによる環境形成作用によって維持されており, ミズグモの保全にはこのミズゴケ群落を維持することが重要である.
- 著者
- 北本 遼太 茂呂 雄二
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.44-62, 2020-03-01 (Released:2020-03-15)
- 参考文献数
- 32
The purpose of this article is to advance the situated approach through adopting the concepts of performance. Ueno,Sawyer, and Moro (2014) hybridized Actor Network Theory and Activity Theory and proposed analytical viewpoint of “modes of exchange”. For succession of the proposition, we advanced the viewpoint of exchange in emotional aspect. We introduced the viewpoint of “performative exchanges”, which focus to dominant pattern of giving-getting on learning practices and transformation of the pattern, for this purpose. Data were collected through semi-structured interviews with members of welfare service associations and analyzed by two steps as follow. In step 1, we described the entrepreneurial process of welfare serves from two viewpoints of “translation of interest” and “modes of exchange”. Through the comparison of two viewpoints, we found that dominant pattern of giving-getting on this practice is “providing service-receiving reward”, which is characterized by “working for equation”. In step 2, we focused to imagination and emotionality in order to analyze the transformation of “providing service-receiving reward”. The result showed that mechanism of transformation is playful imaginative exchanges with “the most peripheral participants” and re-construction of the exchange of commodities. In general discussion, we pointed out that difference among three viewpoints is approach to emotion.
- 著者
- 田中 輝和 田中 恭子 高原 二郎 藤岡 譲 田村 敬博 山ノ井 康弘 北条 聰子 高橋 敏也 三木 茂裕 中村 之信
- 出版者
- 公益財団法人 日本感染症医薬品協会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Antibiotics (ISSN:03682781)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.790-797, 1994-06-25 (Released:2013-05-17)
- 参考文献数
- 13
MRSAとその複数菌感染症に対し, Arbekacin (ABK), Fosfomycin (FOM) 投与30分後に Ceftazidime (CAZ) を投与する時間差併用療法を設定し, 基礎的, 臨床的検討を行い以下の成績を得た。臨床分離のMRSA 1727及びPseudomonas aeruginosa KIに対し, 1/4~1/8MICのABK, FOM, CAZの同時及び時間差処理を行い, 殺菌効果を比較したところ, 時間差処理群により優れた相乗的殺菌効果が認められた。両菌による複数菌感染にマクロファージを用いた系では, 三薬剤の時間差併用により, マクロファージによる著しい殺菌効果の増強が認められた。MRSA感染症を呈した15症例に対する臨床的検討では, 有効率は80.0%であった。MRSAに対する除菌率は60.0%であった。ABK, FOM, CAZを用いた時間差併用療法は, MRSAを含む複数菌感染症に対し, 非常に有効な治療法であると考えられる。
2 0 0 0 OA 学会事務の改革により発見したこと: 事務効率化とIT 化の課題
- 著者
- 長尾 慎一郎
- 出版者
- 日本セキュリティ・マネジメント学会
- 雑誌
- 日本セキュリティ・マネジメント学会誌 (ISSN:13436619)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.1-2, 2020 (Released:2020-03-15)
2 0 0 0 OA 海藻由来フコキサンチンの抗肥満作用
- 著者
- 前多 隼人
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- オレオサイエンス (ISSN:13458949)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.10, pp.503-508, 2012 (Released:2015-02-14)
- 参考文献数
- 30
フコキサンチンはワカメやコンブなどの褐藻類に特徴的に含まれる,カロテノイドの一種である。近年,抗肥満,抗糖尿病,抗酸化,抗がん,血管新生抑制作用など,フコキサンチンの様々な生理機能が報告されている。これらの機能の中でも脂肪組織を介した抗肥満,抗糖尿病作用は特に注目されている。 フコキサンチンは,肥満による様々な疾患の原因となる白色脂肪組織の肥大化を抑える。その作用機構としてuncoupling protein 1(UCP1)タンパク質の,白色脂肪組織での異所性の発現誘導が考えられている。また,脂肪組織から分泌され体内の組織のインスリン抵抗性の惹起に関わるアディポサイトカインの分泌調節や,筋肉組織での糖取り込みの正常化により抗糖尿病効果を示す。近年ではフコキサンチンの体内動態とそれら代謝物による作用も明らかになりつつある。本項では特にこのようなフコキサンチンによる脂肪組織や筋肉組織を介した抗肥満作用,抗糖尿病作用の作用機構について解説する。
2 0 0 0 OA 東川清一 著 旋法論
- 著者
- 小野 亮祐
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育学 (ISSN:02896907)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.25-26, 2011 (Released:2017-08-08)
2 0 0 0 OA 女性高齢者の大腿部の形態と運動機能との関連
- 著者
- 村田 伸 江崎 千恵 宮崎 純弥 堀江 淳 村田 潤 大田尾 浩
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.939-942, 2010 (Released:2011-01-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3 1
〔目的〕女性高齢者の周径および大腿四頭筋筋厚を測定し,大腿四頭筋筋力や歩行・バランス能力との関連について検討した。〔対象〕地域在住の女性高齢者56名(平均年齢は71.6±6.5歳)とした。〔方法〕膝蓋骨上方10 cm部,15 cm部,20 cm部の大腿周径と大腿四頭筋筋厚を測定し,大腿四頭筋筋力,歩行速度,Timed up & go test(TUG)との関係をピアソンの相関係数を求めて検討した。〔結果〕すべての大腿周径と大腿四頭筋筋厚の測定値は,大腿四頭筋筋力と有意な相関を認めたが,膝蓋骨上方15 cm部と20 cm部の筋厚との相関係数が高かった。また,15 cm部と20 cm部の筋厚のみ,歩行速度やTUGと有意な相関が認められた。〔結語〕膝蓋骨上方15 cm部と20 cm部の大腿四頭筋筋厚は,筋力のみならず歩行能力やバランス能力をも反映する有用な指標となり得ることが示唆された。
2 0 0 0 OA 青果物の香気生成とストレス
- 著者
- 上田 悦範
- 出版者
- Japan Association of Food Preservation Scientists
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.41-45, 2002-01-31 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- Miho YOSHIOKA Zen KOBAYASHI Keisuke INOUE Mayumi WATANABE Kaori KATO Kazunori TOYODA Yoshiyuki NUMASAWA Shoichiro ISHIHARA Hiroyuki TOMIMITSU Shuzo SHINTANI
- 出版者
- Japanese Society for Brain Function and Rehabilitation
- 雑誌
- Journal of Rehabilitation Neurosciences (ISSN:24342629)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.33-36, 2019 (Released:2019-10-25)
The Trail Making Test (TMT) is widely used as a measure of attention impairment. The time needed to complete TMT (TMT score) is prolonged in association with attention impairment in patients with brain diseases. Thus far, however, there have been no reports of serial changes in the TMT score after minor ischemic stroke. We retrospectively investigated serial changes in the TMT score of 19 patients with minor ischemic stroke. We included patients in whom TMT could be performed both 4-11 days after onset (initial evaluation) and 14-47 days after onset (second evaluation). The mean value of the initial TMT-A scores was 58 seconds, and that of the initial TMT-B scores was 144 seconds. The mean value of the second TMT-A scores was 43 seconds, and that of the second TMT-B scores was 119 seconds. The TMT-A and TMT-B scores improved in 89 % and 74 % of patients, respectively. This study demonstrated that most minor ischemic stroke patients showed improvement in the TMT score 14 days or later after onset.
2 0 0 0 OA 実世界における人とロボットの共有信念の推定に基づいた相互適応的な発話生成
- 著者
- 中村 慎也 岩橋 直人 長井 隆行
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.663-682, 2009-10-15 (Released:2010-01-12)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4 2
本論文では,実世界状況において,ロボットが人と効率的及び相互適応的に共有信念を形成しながらコミュニケーションを行うための,発話生成手法を提案する.共有信念は,互いに共通する経験を基盤として形成され,対話者の心的状態の推定や曖昧な発話の理解に用いられる.提案手法は,ロボットが学習する信念システムとして,ロボットの想定する共有信念を表現する関数に加えて,人とロボットの想定する共有信念の一致度を表現する関数を扱う.共有信念を表現する関数は,確率モデルで表される音声言語や動作,オブジェクトの概念などを指示する様々な信念の重み付け和で表現される.共有信念の一致度を表現する関数は,発話が相手に正しく理解される確率の予測値を出力する.信念システムの学習は,人とロボットのオブジェクトを用いたインタラクションを通してオンラインで行われる.ロボットは,一致度を表現する関数を学習することで人の心的状態の推定と発話の予測理解率の推定が可能となり,環境だけでなく,相手との共有信念の一致度に応じて発話の単語数を増減させるなどの適応的な発話生成が行えるようになる.また,そうした発話によるインタラクションを通して一致度を表現する関数自体を更新し,人とロボットが相互適応的に共有信念の形成を行う.ロボットに学習させる信念システムや,人が行動を誤った場合のロボットによる正解の提示の有無など,様々な条件で実験を行い提案手法の有効性を評価した.
2 0 0 0 OA 天竜川・豊川の流路争奪に対する問題点
- 著者
- 冨田 芳郎
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.8, pp.555-563, 1966-08-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 11
これまで天竜川はその中流の中部(なかっぺ)付近で豊川を截頭し,その後に天竜水系の大千瀬川が豊川の旧河谷の風隙からその空谷或は化石谷に沿って頭部侵食による分水移動を行って,現在池場の長さ500m内外,海抜321mの谷中分水で裁頭後の豊川本流の源流と対峙していると考えられている.しかしこの池場の谷の地形を見ると,豊川の截頭前の旧河谷とは考えられず,むしろ西南日本の地体構造における内帯と外帯との境界線をなす中央構造線に沿う断層谷とみるべきで,この戴頭による流路争奪の事実はこの地域の地形発達史の現段階では考えられない.すなわち,池場とその西側の上流河谷の幅は,谷中谷の上谷があるとしても,旧豊川本流河谷としては甚だ狭いし,池場の両側の谷壁は,所謂screesというべき崖錐斜面であり,谷底はU字形の盆谷 (Muldental) で,流路の跡と見るべき河床の地形ではない.また池場の谷底の堆積物は拳大栗実大の亜角礫と粘土質の軟かいmatrixから成り,土石流による無層理又は不整層理の崩れ易い堆積物から成り,裁頭前の豊川の中流性旧河床を立証するような河流堆積層は認められない.ただ池場の谷の東西両側の谷底にそれぞれ現在の小流による小段丘があるだけである.さらに池場の谷の断層は崖錐層の被覆で確認されないが,池場から松平に至る間の流紋岩や石英安山岩には鏡肌を示す節理面があって板状節理を示し,節理面の方向が屡々中央構造線の方向と一致するものがあることから,この構造線に沿う破砕帯と考えられる. 由来断層谷といっても,多くはそこには河が流れて,河蝕が行われるが,この点では池場の谷は純粋な断層谷といえよう.しかし規模が小さいが,ここからENEの天竜川支流の水窪川の西方にあって,明かに中央構造線に沿った断層谷と見るべきものが,18km内外の長さで,佐久間から水窪まで及んでいる.1部は水窪川の支流や天竜小支流の厚地川で削られているが,その谷間では,開析段丘面のような緩斜面は崖錐の堆積面である.またこの谷には河蝕による分水峠があるが,一連の断層谷と見るべきで,池場の谷はその一小部分としての地形はよく似ているので,池場の谷を断層谷と認定して,この谷は戯頭された豊川の旧河谷ではなく,流路争奪の事実を疑うのである.
2 0 0 0 OA 女子高校生の通学靴の履き方に関する意識
- 著者
- 片瀬 眞由美 平林 由果 渡辺 澄子 栗林 薫
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.94, 2003 (Released:2004-05-25)
【目 的】ここ数年、靴の踵を踏みつぶしてスリッパのように引きずって歩く高校生の姿が目につくようになった。どのような意識が隠されているのか、その背景を明らかにするために、女子高校生の靴や足に対する意識と実態を調査することにした。今回は通学靴に焦点をあて、靴選びや履き方に関してのアンケート調査を実施した。【方 法】愛知県下の高等学校に在籍する女子高校生に対し、通学靴の履き方の実態や靴選びに関して調査を実施した(自記式集合調査法)。調査時期は2002年12月、有効回答数は1257(通学靴を指定している高等学校759、指定していない高等学校498)であった。【結果および考察】通学靴としてローファーを毎日履いているものは48%、スニーカーは38%でローファー派の方が多かった。足で気になっていることについては、「靴ずれ」が最も多く、ローファー派では9割が訴えたが、スニーカー派では5割に過ぎなかった。その他、足部の痛みや巻き爪、外反母趾、肩こり、足の疲れなどの訴えもあり、女子高校生の多くは足の悩みを抱えていることがわかった。一方、自分の足のサイズに関しては、「測定はしていないが大体知っている」が77%、「知らない」が19%であり、正確な足のサイズへの認識度は低かった。「正確に足のサイズを測ってみたいか」では「思う」と「思わない」が半々で、足のサイズへの関心はそれほど高くないことが窺えた。通学靴の踵を「踏んでいる」のは16%で、その理由は「脱ぎ履きが簡単だから」であった。本調査の結果から、女子高校生は見た目を優先して通学靴を選び、脱ぎ履きの楽な靴を求めてサイズを選んでいることが足の悩みにつながっている可能性があることが示唆された。
2 0 0 0 OA 糖・脂質代謝異常症の遺伝因子と食事因子に関する研究
- 著者
- 堀尾 文彦
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.267-274, 2018 (Released:2018-12-17)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
糖・脂質代謝異常症の原因遺伝子の同定と, 発症抑制する食事因子の探求とを目的とした。遺伝因子に関しては, マウス SMXA 組換え近交系統の中に高脂肪食誘発性2型糖尿病と脂肪肝を呈する SMXA5 系統を見出した。SMXA5 の原因遺伝子を同定するために高脂肪食摂取下で遺伝解析を行って, 糖尿病遺伝子座を第2番染色体に, 脂肪肝遺伝子座を第12番染色体に検出することに成功した。これらの遺伝子座を含む染色体部分置換マウスを作出して原因遺伝子の染色体上の存在領域を限局して, 糖尿病遺伝子については4つの候補遺伝子を, 脂肪肝遺伝子については1つの候補遺伝子を選抜した。食餌因子に関しては, コーヒー, 植物性タンパク質, キノコ由来ペプチドなどの糖尿病の発症抑制効果を見出した。コーヒーは, 2型糖尿病でのインスリン抵抗性を改善させて高血糖の発症を抑制すること, また膵臓β細胞の保護作用により1型糖尿病も抑制することを見出した。これらの成果は糖尿病・脂肪肝の新規の発症機構の発見と, 疾患を予防する食生活の構築に寄与するものである。
2 0 0 0 OA メダカ及金魚卵の孵化日數と水温との關係
- 著者
- 山本 孝治
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.105-109, 1937-07-15 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 6
Soon after spawning the eggs of the Japanese Killifish, Oryzias la ?? ipes (TEMMINCK & SCHLEGEL) and the Dutch-Lion-Head Goldfish, Carassius auratus (LINNAEUS) were kept at various constant temperatures. The time required for hatching and the percentage of the hatched fry were observed. To obtain a series of constant temperatures a SENO-TAUT??'s serial in ubator was made use of, in which 6 constant temperatures ranging from about 11° to 30°C. for the eggs of the Japanese Killifish and 10 constant temperatures ranging from about 12° to 31°C, for the eggs of The Dutch-Lion-Head Goldfish were maintained. The results obtained may be summarized as follows: 1) Water temperatures for normal development of the eggs range for the Japanese Killifish 18° to 30°C., and for the Dutch-Lion-Head Goldfish 15° to 23°C. 2) The relation between the temperature (θ) and the time in days required for hatching (T) may be expressed as given by HIGURASHI and TAUTI by the formula Teaθ=C, where a and C are constants specific to the eggs of the respective kind. The values of these constants found in the present experiment and those of Q10 calculated from them are for the Japanese Killifish a 0.0799, C 1.923 and Q10 2.22, and for the Dutch-Lion-Head Gordfish a 0.0933, C, 1.523 and Q10 2.54.
2 0 0 0 OA 臨床判断を基盤とした転倒危険性の感じ方は理学療法士経験年数で異なるか?
- 著者
- 松田 徹 吉田 晋 井上 美幸 村永 信吾 大嶋 幸一郎 川間 健之介
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.69-75, 2018 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 29
〔目的〕臨床判断を基盤とした転倒危険性の感じ方が,臨床経験により異なるか,Timed “Up& Go” Test (TUG)遂行時の高齢者映像から検討すること.〔対象と方法〕「学生」群32名,臨床経験「1-2年目」群46名,「3-4年目」群34名,「5-9年目」群43名,「10年目以上」群15名.映像を見て,Visual Analogue Scale(VAS)で評価した.本研究上定義した転倒リスク分類との一致率とVAS測定値を臨床経験で比較した.〔結果〕転倒高リスク映像にて,「学生」群よりも「1-2年目」群,「10年目以上」群の一致率が有意に高く,「10年目以上」群で最も高かった.〔結語〕10年以上臨床経験を積むことで,転倒リスクの高い高齢者映像をより正確かつ明確に評価できる可能性が示唆された.
2 0 0 0 OA 窮亦楽通亦楽を生きた人-遠藤隆次
- 著者
- 矢島 道子
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.77-80, 2006-03-28 (Released:2017-10-03)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 熊野灘のヨツバカワリギンチャク―100年越しの標本で,分類の混乱に終止符を!―
- 著者
- 泉 貴人 藤井 琢磨 柳 研介 藤田 敏彦
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.13-19, 2020-02-29 (Released:2020-03-13)
- 参考文献数
- 13
Isactinernus quadrilobatus Carlgren, 1918, the only species of genus Isactinernus, is characterized by an oral disc with four equally-sized lobes. In 2003 Synactinernus flavus Carlgren, 1918, which is characterized by four large and four small lobes alternately arranged, was synonymized into I. quadrilobatus because the difference of lobe shape was thought to be intraspecific variation, and thus the genus Synactinernus was also synonymized into Isactinernus. However, our molecular phylogenetic analysis of Actinernidae including I. quadrilobatus collected from the Kumano Sea revealed that I. quadrilobatus is genetically distinct from S. flavus. Our morphological comparison between the two species supported the result of the molecular analysis. Consequently, the genus Synactinernus was re-established and separated from Isactinernus. Additionally, during this study, we discovered and described an additional species of the genus, Synactinernus churaumi Izumi and Fujii, 2019.
2 0 0 0 OA 子どもの貧困と学術研究の隠れた枠組み
- 著者
- 佐々木 宏子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.10, pp.10_29-10_33, 2017-10-01 (Released:2018-02-10)
- 参考文献数
- 11