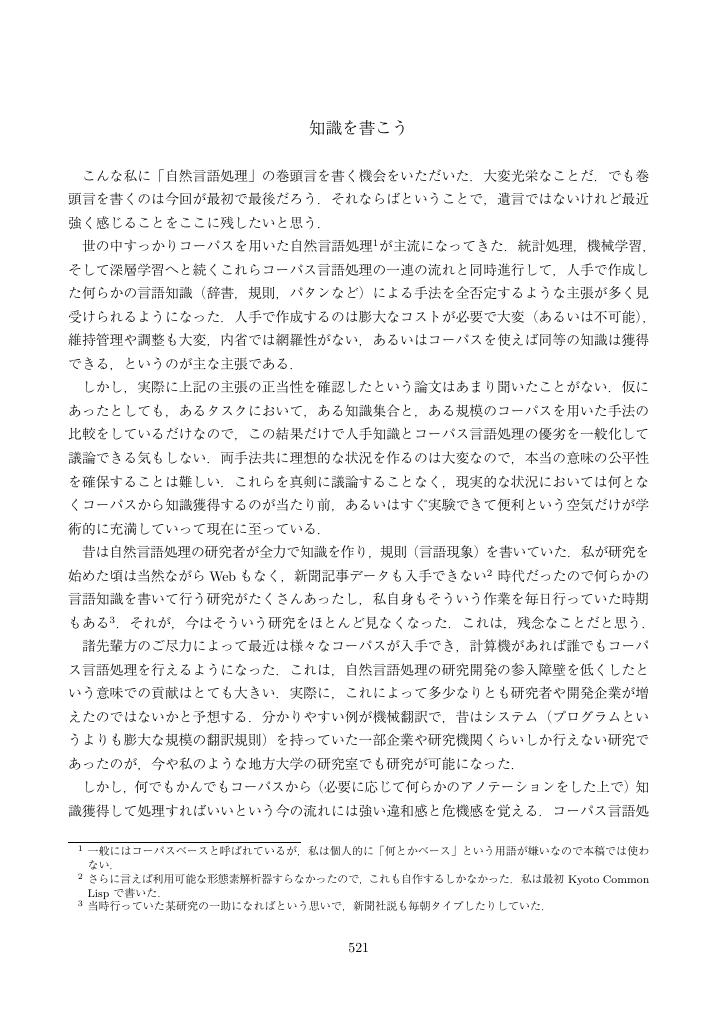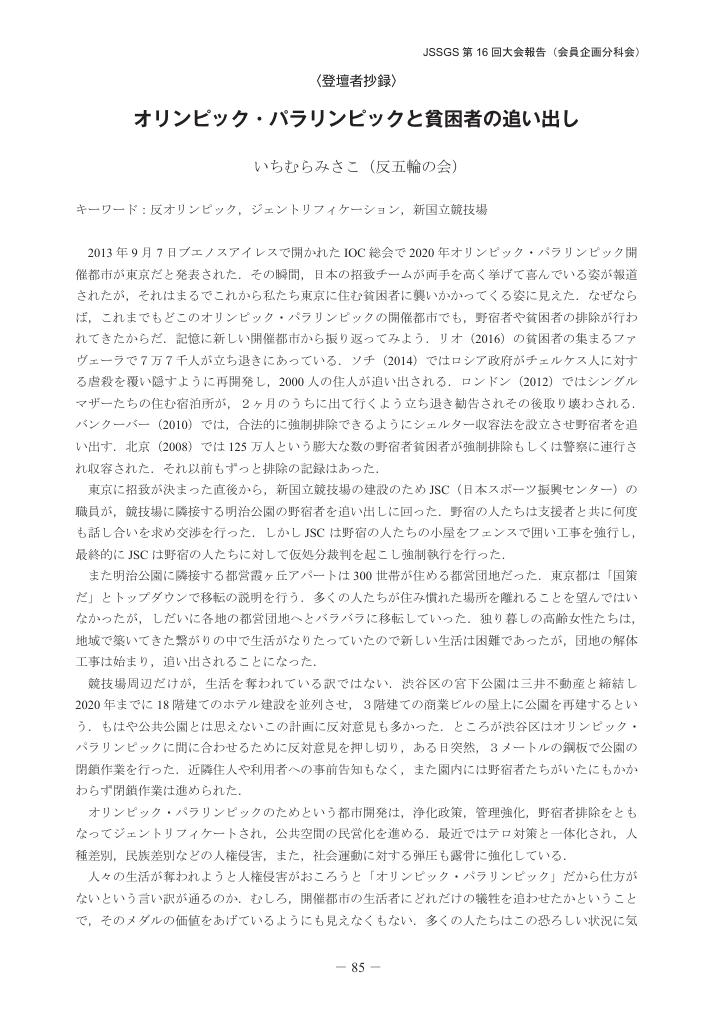110 0 0 0 OA 「女性は数学が苦手」
- 著者
- 森永 康子
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.49-61, 2017 (Released:2018-07-20)
- 参考文献数
- 76
- 被引用文献数
- 3
It is unclear why the number of women in the fields of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) is still small. In this review article, I focus on gender stereotypes (i.e., the belief that “women canʼt do math”) from a social psychological perspective. It has been reported that women and girls are influenced by negative stereotypes in experimental settings as well as in the real world. For example, researchers have found that negative stereotypes can undermine the performance of women in math exams. More recently, implicit stereotypes have been found to affect womenʼs math preferences either equally or even more than explicit stereotypes. How can we counteract the effects of negative stereotypes? Interventions, such as informing women that their math performances and career decisions are often unconsciously influenced by gender stereotypes, have been introduced based on accumulated knowledge of both gender and stereotypes. Having reviewed such literature, I conclude that psychologists in Japan should put more effort into conducting research on how to encourage women and girls to pursue their career plans, especially in the STEM field.
110 0 0 0 OA 心拍数が音楽聴取時の時間感覚に与える影響
- 著者
- 松田 憲 一川 誠 橘 佳奈
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.215-222, 2015 (Released:2015-02-27)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
We examined how changes in participants' heart rate affect their estimation of time when listening to music. We manipulated participants' heart rate using a cycling task on an exercise bike and by varying the tempo of music. The heart rates of 48 participants were measured before and after the pedaling task on the exercise bike. One week later, they listened to the music and estimated the temporal duration (60 seconds) under the non-manipulated condition (without exercise) and heart rate manipulated condition (with exercise). The results showed that the duration of the music (60 seconds) was underestimated after light exercise and overestimated after strenuous exercise. These results suggest that the acceleration of the internal time mechanism due to an increase in the heart rate affects the perceived duration of time with relation to music.
110 0 0 0 OA 哲學のアポロジー
- 著者
- 西田 幾多郎
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.1916, no.3, pp.11-14, 1916-06-17 (Released:2017-09-06)
110 0 0 0 OA 体罰をなくすために、ポジティブな行動支援から
- 著者
- 平澤 紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.119-126, 2015-02-25 (Released:2017-06-28)
- 被引用文献数
- 4
「体罰」をなくすためには、望ましくない行動を減少させる、より望ましい方法が必要である。本報では、その中心となるポジティブな行動支援について取り上げ、その特徴や方法、研究成果について解説した。ポジティブな行動支援は、個人の生活の質を向上し、それによって問題行動を最小化するための教育的方法とシステム変化の方法を用いる応用科学である(Carr et al., 2002)。その焦点は、その人の望ましくない行動を引き起こし、強化している要因の分析をもとに、望ましい行動を教え、その人の生活環境を再構築するところにある。このような予防的・教育的アプローチは、米国では、障害児教育制度に位置づけられ、個人に対する個別的な支援だけでなく、学校規模の支援として多くの研究成果が蓄積されている。今日、われわれは、「体罰」ではない、確かな教育的方法を有するのである。
110 0 0 0 OA 日本語における「近代的」セクシュアリティの形成
- 著者
- 渋谷 倫子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.49-62, 2006 (Released:2011-10-11)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 2
This paper investigates women's speech in modern Japanese language in terms of the historical process of its establishment. It is common knowledge that there are clear differences between men's speech and women's speech in Japanese language, which implies that some forms are used exclusively by one sex but not the other. It is also generally recognized that the origin of Japanese women's speech is teyo-dawa, the speech of female students of the Meiji period (1868-1912). However, it is difficult to assume that this speech of female students spread among the general population of women during this period, an era of no auditory mass media. Furthermore, few studies explain the reason why teyo-dawa was accepted as the speech of women despite the fact that it was severely castigated by the mass media of the Meiji period.I argue that the sex differences of modern Japanese language were first established in the speech of female characters of Meiji novels. Before the Meiji era, the most common theme of popular novels was the liaison between a man and a prostitute of the pleasure quarter. These prostitutes used particular social dialects that were spoken only in their quarters. In the Meiji period, in seeking a style for the novels of a new era, writers created "modern" women as the partners of their male protagonists. These women were characterized by having received western education and by their use of teyo-dawa speech. Although teyo-dawa was bitterly criticized by Meiji society, it became the marker of "modern" sexuality in the literary works, and later obtained the status of the model speech for general women.
110 0 0 0 OA 薬都富山を訪ねて
- 著者
- 東田 道久
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.1113-1115, 2015 (Released:2018-08-26)
北陸新幹線が開通し,関東から北陸へのアクセスが大変便利になった.東京から富山までは約2時間,名古屋と変わらない時間での往来が可能である.江戸の昔,越中富山藩は,加賀藩の負債も背負って独立,当初は経済的に恵まれない状況におかれていた.その状況を打開するために考え出された産業が「くすり」であった.くすりは命にかかわるため付加価値も極めて高く,また軽くて運びやすいため,遠方でも物流が容易である.江戸城内での販売促進キャンペーンを経て,売薬ネットワークも確立させ,越中・富山の産業として発展,今日まで続く「くすりの富山」ブランドの看板と独占的販売権 (懸場帳:かけばちょう) を築き上げてきた.本グラビアでは,今も富山の産業に深く根ざしている「くすり産業」の原点とも言えそうな昔ながらの趣を残す各地や博物館を訪ね,その歴史と,先人たちの熱意と情熱に思いを馳せる.(各施設等の説明文の後に,詳細情報をウェブより入手する際の検索ワードを記載した)
110 0 0 0 OA 知識を書こう
- 著者
- 山本 和英
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.521-522, 2017-09-15 (Released:2017-12-15)
110 0 0 0 OA 論文投稿に関わる剽窃等の問題についての考察
- 著者
- 酒井 善則 鶴原 稔也
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.239-243, 2012-01-01 (Released:2012-01-01)
- 参考文献数
- 11
学会への論文投稿は研究者等の重要なミッションであるが,最近二重投稿問題や剽窃問題等の増大が懸念されている.特に,最近のICTやインターネットの発展によりこれらの問題が顕著になっており,学会としての対応も求められている.剽窃問題等が明らかになった場合,研究者個人だけでなくその所属する大学や企業等の組織に与える影響も大きく,更には科学技術全体に対する社会的評価をおとしめることとなる.本稿ではこれらの問題の現状の一部を紹介し,背景について解説するとともに,倫理に関する啓発活動が重要なことを述べる.
- 著者
- 坂本 穆彦 廣川 満良 伊東 正博 長沼 廣 鈴木 理 橋本 優子 鈴木 眞一
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.265-268, 2021 (Released:2022-02-22)
- 参考文献数
- 18
筆者らの内,筆頭著者より6名は福島県県民健康調査の病理診断コンセンサス会議にて,各症例の病理組織診断を担当している病理医(病理専門医・細胞診専門医)である。福島第一原発事故(2011年3月)後の福島県民健康チェックのための福島県県民健康調査では,チェルノブイリ原発事故後の小児甲状腺癌の多発という教訓を踏まえた任意の小児甲状腺超音波検査などが施行されている。悪性ないし悪性の疑いとされた場合は,必要に応じて手術が勧められる。この県民健康調査については,調査対象の設定が不適切で,不必要な検査が行われている可能性があるという声があり,その立場からは,県民健康調査が過剰診断(overdiagnosis)であると批判されている。この過剰診断という語は病理医や細胞診専門家は良性病変を癌と診断する様な誤診を示す場合のみに用いている。このように,用語や定義の使用法にくい違いがあるままで用いられるため,種々の誤解が生じている。本稿では県民健康調査そのものの是非を論じることは目的としていない。筆者らの意図は,過剰診断および過剰手術/過剰治療についての定義・用法に関しての病理医と疫学者双方に立場の違いがあることを示し,今日の混乱の解決策を論じることにある。
109 0 0 0 OA 戦後の家庭料理に見られるマツタケ高級化の過程 ―料理雑誌・漫画記述や採取者の意識から―
- 著者
- 泉 桂子 佐々木 理沙
- 出版者
- 一般社団法人 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.1, pp.1-12, 2021-02-01 (Released:2021-05-07)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
現在マツタケは生育場所となるアカマツ林の荒廃と減少によりその生産量が減少しているが,季節の食材として珍重される。料理雑誌・漫画を資料に用い,マツタケの高級食材としての評価は家庭料理においていつ頃定着したのかを明らかにした。1950年代後半から1960年代の消費者にとってマツタケは一面では惣菜用のキノコであった。料理書では他のキノコの代替や節約料理の材料となり,洋食や中華料理にも用いられ,多様な調理方法,切り方や加熱法が見られた。レシピサイトを用いて家庭料理におけるマツタケの代替物を調査した。限られた資料からではあるがエリンギ単独,またはマツタケ味の吸い物の素(1964年発売)と組み合わせたマツタケ代替レシピが確認された。さらに,岩手県内の山村を事例として,マツタケの採取や生育環境づくり,その後の稼得機会の獲得,調理,贈与,保存の楽しみや技術について聴き取り調査を行った。採取者は高齢となってもマツタケ採取に熱中し,現金収入や共食,贈与を楽しみに採取のためアカマツ林の採取地に入り込んだり,環境整備を行ったりしていた。これら採取者の調理は和風料理であり,保存には冷凍や真空パックを用いていた。
109 0 0 0 OA 機械学習のコモディティ化
- 著者
- 田口 善弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.9, pp.659-660, 2019-09-05 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 3
シリーズ「人工知能と物理学」機械学習のコモディティ化
109 0 0 0 OA 口腔内異物 (イカ精子嚢) の2例
- 著者
- 木下 靖朗 冨田 陽二 早瀬 智広 中野 稔也
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.993-995, 1993-09-20 (Released:2011-07-25)
- 参考文献数
- 13
This report presents rate two cases of foreign bodies (sperm-bags of squid) in the oral cavity, which were found in a 38-year-old male and 49-year-old female.Several small thorn-shaped foreign bodies stuck in the oral mucosa were observed and removed successfully.
109 0 0 0 OA 電気分解陽極水によるウシコロナウイルスの不活化
- 著者
- 松本 光代 大塚 美奈 鈴木 祐子 福井 宏行 町田 季衣子 向井 孝夫 大堀 均
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.59-65, 2005 (Released:2006-08-01)
- 参考文献数
- 34
ウシコロナウイルス(BCV)は主な牛下痢症を発症し,また牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV)はウシに重篤な粘膜病を発症する可能性を持った病原体で,どちらも家畜飼育現場からの根絶が困難なウイルスである.本研究では消毒剤の新たな候補として電気分解陽極水のBCVおよびBVDVに対する不活化効果を検討した.電気分解陽極水は0.12%のNaClを含む水を電気分解して調製した.電気分解陽極水で1分間処理した両ウイルスを牛腎細胞に接種し,細胞上清の赤血球凝集反応もしくは細胞内RNAのRT-PCRによって,ウイルスの存在を検討した.その結果,電気分解陽極水で処理したウイルスは細胞内および培養上清から検出されなかった.本研究で調製した電気分解陽極水は,低pH値(3.0前後)であり,低濃度(7.0~20.0ppm)の遊離形有効塩素(EC)を含むことが示された.BCVの増殖はECを含まない低pH溶液あるいは低濃度のECを含むが高pH値(9.0以上)を示す溶液による各処理では阻害されなかったことから,電気分解陽極水のウイルス不活化はpHとECの相乗効果によるものと推察された.
- 著者
- Yuki Tamura Hideo Hatta
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.151-158, 2017-05-25 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 8
Heat stress treatment is a classic physical therapy, which is employed in the orthopedic field. In the field of physical fitness/sports science, morphological changes of skeletal muscle by heat stress have been well studied. In recent years, energy metabolic adaptations by heat stress have also been actively studied. In this review, we provide an overview of recent findings on heat stress-induced mitochondrial adaptations in skeletal muscles, and further discuss our unpublished data and recent findings in related research fields. First, we summarized heat stress-induced positive regulation of mitochondrial content and its underlying molecular mechanisms from perspectives of mitochondrial biogenesis and degradation. Consequently, we reviewed beneficial effects of heat stress on mitochondrial health in disused and aged muscles, focusing on mitochondrial stress response at the organelle level (mitochondrial selective autophagy; mitophagy) and molecular level (mitochondrial unfolded protein response). Finally, we overviewed future directions to better understand heat stress-induced mitochondrial adaptations in skeletal muscle.
109 0 0 0 OA 温水洗浄便座のノズルで穿孔し経肛門的小腸脱出をきたした直腸脱の1例
- 著者
- 吾妻 祐哉 中川 暢彦 佐藤 敏 石山 聡治 森 俊明 横井 一樹
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.3, pp.548-551, 2017 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
症例は72歳,女性.もともと直腸脱を指摘されていたが放置.排便後に温水洗浄便座を使用した.ノズルの先端が直腸内に入ったため立ち上がったところ,いつもと違う感覚があった.その後,経肛門的に小腸の脱出があり当院救急外来を受診した.来院時所見でも経肛門的に小腸の脱出を認めた.脱出した小腸は徒手整復困難であり緊急手術の方針となった.直腸前壁に3cm長の全層性裂傷を認め,外傷性直腸穿孔とそれに伴う経肛門的小腸脱出と考えられた.腹腔内の汚染は軽度.小腸の還納と直腸低位前方切除を施行.術後経過は良好で術後10日目に独歩で退院した.肛門からの小腸脱出は,直腸脱や子宮脱などの既往がある場合が多い.今回はさらに温水洗浄便座のノズルが原因と考えられる症例であり,直腸脱患者の温水洗浄便座使用に対しては注意喚起が必要である.
108 0 0 0 OA 新型コロナウイルスCOVID-19のエアロゾル感染の可能性 ―微粒子工学の立場からの考察―
- 著者
- 向阪 保雄 野村 俊之 内藤 牧男
- 出版者
- 一般社団法人 粉体工学会
- 雑誌
- 粉体工学会誌 (ISSN:03866157)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.10, pp.526-529, 2020-10-10 (Released:2020-12-09)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
Aerosol infection issues by COVID-19 were discussed from the viewpoint of particle technology, and the following conclusions were obtained: 1) Number of virus contained in a 10 μm droplet is very few, only 1 virus per 2000 droplets, whereas 0.5 virus in a 100 μm droplet, if 106 copies/mL of viral load in saliva is assumed. 2) Droplets larger than 100 μm can quickly settle down by gravity. 3) The possibility of aerosol infection is very low unless in unusual environments. 4) Mask is very effective, but the leakage from the space between mask and face has risk in heavy exhalation.
108 0 0 0 OA スギ花粉症有病率の地域差について
- 著者
- 村山 貢司 馬場 廣太郎 大久保 公裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.47-54, 2010-01-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
【目的】我が国におけるスギ花粉症の有病率は馬場の2008年の調査により,平均26.5%とされているが各地域の有病率には大きな差が存在する.これまで,中村,Okudaらによって全国のスギ花粉症有病率の調査が行われてきたが,主に抗体陽性率や発症率との観点から分析が行われており,わずかにOkudaによって飛散花粉数と有病率の関係が述べられているにとどまっている.大気汚染との関連では特定地域における調査はあるが全国的な解析はほとんどないのが現状である.本研究では花粉数,大気汚染,気象条件など外部条件が,地域間の有病率にどの程度影響を与えているかについて検討を行った.【方法】馬場の調査による各都道府県のスギ花粉症有病率と各地域の平均花粉数,花粉の飛散期間,2月および3月の湿度,SPM,NOx,Oxなどについて相関を求め,有病率の差に関与する因子を検討した.花粉数についてはスギおよびヒノキ科花粉の合計値とスギ,ヒノキ科に分けた場合についても検討した.相関の高い因子については1998年と2008年の有病率の差について同様の結果になるかを検討した.【結果】有病率と最も相関が高くなったのは花粉の飛散期間で,次いで花粉数,湿度の順であった.1998年と2008年の有病率の増加に関与したと考えられる因子は同様に花粉飛散期間,花粉数,湿度の結果であった.SPMなどの大気汚染に関しては有意な関係は見られなかった.湿度に関しては森らの調査による高湿度におけるダニ増殖の影響とは異なる結果になった.
108 0 0 0 OA 五島列島福江島におけるミナミヌマエビの初記録
- 著者
- 福家 悠介 岩﨑 朝生 笹塚 諒 山本 佑治
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.63-71, 2021-08-01 (Released:2021-08-26)
- 参考文献数
- 54
Neocaridina denticulata (Decapoda: Atyidae) is a freshwater shrimp with a land-locked life-history and is widely distributed in western Japan. The taxonomic confusion of this species, caused by the loss of type specimens, unknown type locality, and genetic and morphological geographical variation, has led to inconveniences in biodiversity conservation and the identification of exotic species that recently invaded Japan. Therefore, it is important to clarify this species’ distributional range and regional genetic and morphological characteristics to solve the problem. Here we report the first record of N. denticulata from Fukue-jima Island in the Goto Islands, Nagasaki Prefecture, Japan. Morphological analyses identified the population as N. denticulata, and mitochondrial DNA-based analyses suggested that the population was distinctly differentiated from the Kyushu populations. This population is essential for inferring the N. denticulata distribution formation and biota formation processes in the Goto Islands. On Fukue-jima Island, N. denticulata has only been found in one pond; thus, the Fukue-jima population is likely to be in critical condition.
108 0 0 0 OA XF-2の開発
- 著者
- 松宮 廉 神田 國一 安江 正宏 景山 正美
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.536, pp.476-484, 1998-09-05 (Released:2010-12-16)
108 0 0 0 OA オリンピック・パラリンピックと貧困者の追い出し
- 著者
- いちむら みさこ
- 出版者
- 日本スポーツとジェンダー学会
- 雑誌
- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.85-86, 2018 (Released:2018-12-29)