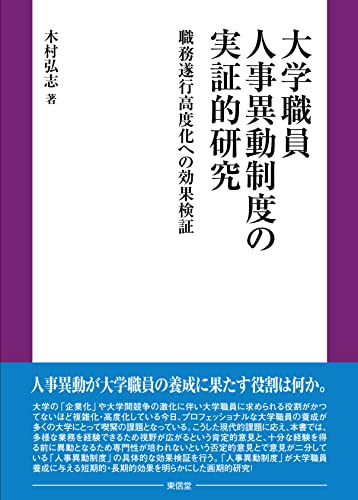2 0 0 0 OA 気持ちの理解における類似経験の想起の効果
- 著者
- 久保 ゆかり 無藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.296-305, 1984-12-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
Understanding empathetically how another person feels is defined here as the making of his/her “psychological world” being i nfluenced by his/her affect. It is also assuming an inclusion predicting his/her behavior, sympathizing with him/her, and imaging an effective way of interaction with him/ her.The purposes of this study are (1) to test the hypothesis that recalling one's own experience as similar to another person's in terms of its events and internal responses facilitating an empathic understanding of how he/she feels, and (2) if recalling similar experiences facilitate in fact the empathic understanding, to examine what kind of components are cansing such an effect; one component may be arousing the same valent (positive or negative) emotion, while another retrieving similar concrete individual episodes.To accomplish these purposes, we set up three conditions: first, Gr. S, subjects were asked to remember their own experiences similar to another person's emotional experience in terms of its and internal responses; second, Gr. E, subjects were asked to remember their own experiences that were not similar to another person's in its events and internal responses, but that aroused the same valent emotion. In the third condition, Gr. G, subjects were not instructed to remember any experiences, but they were taught how to grasp gists of a story. After receiving manipulations, subjects had to Iisten to the story of a child having lost his/her littlebird1; then, subjects had to answer a questionnalre.In the first experiment, 74 third graders (40 boys and 34 girls) were divided into three groups homogeneous by made according to their intellectual ability by their teachers. Each group received manipulations collectively. The empathic understanding score of Gr. S was significantly higher than that of Gr. E and Gr. G. This result confirmed the hypothesis; still, which component caused the effect conld not be examined, because a considerable number of subjects in Gr. E and Gr. G spontaneously remembered similar experiences.In the second experiment, 77 third graders (38 boys and 39 girls) were divided into three homogeneous groups on the basis of vocabulary test scores and reading ability scores rated by teachers. They received more stringent manipulations in small groups consisting of five to seven subjects. As a result, the rates of subjects in Gr. E and Gr. G who spontaneously remembered similar experiences showed a decrease of about 30 per cent. The empathic understanding score of Gr. S was significantly higher than that of Gr. E and Gr. G. The result of the first experiment was confirmed. When Gr. S were compared with modified Gr. E and Gr. G where subjects who spontaneously remembered similar experiences were excluded, the empathic understanding of Gr. S scored the highest of all three groups while that of modified Gr. E proved significantly higher than that of Gr. G.Overall results confirmed the hypothesis that recalling experiences similar to another person's facilitates the empathic understanding of how he/ she feels. Moreover such results suggest that the effect of recalling similar experiences is caused not only by an arousing of the same valent emotion but also by retrieving similar concrete and individual episodes.
2 0 0 0 大学職員人事異動制度の実証的研究 : 職務遂行高度化への効果検証
2 0 0 0 OA 夢と意識の構造とについて
- 著者
- 山崎 末彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1-2, pp.119-125, 1943 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 IR 大谷光瑞と台湾高雄熱帯農荘「逍遙園」の研究
- 著者
- Kenji Nashima Makoto Takeuchi Chie Moromizato Yuta Omine Moriyuki Shoda Naoya Urasaki Kazuhiko Tarora Ayaka Irei Kenta Shirasawa Masahiko Yamada Miyuki Kunihisa Chikako Nishitani Toshiya Yamamoto
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.QH-063, (Released:2023-05-31)
The pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) is an economically important tropical fruit crop. In this study, we performed quantitative trait locus (QTL) analysis using 168 individuals of the F1 population of ‘Yugafu’ × ‘Yonekura’ for 15 traits: leaf color (L*, a*, b*), harvest day, crown number, slip number, stem shoot number, sucker number, fruit weight, fruit height, fruit diameter, fruit shell color, soluble solid content, acidity, and ascorbic acid content. The constructed single-nucleotide polymorphism (SNP)-based genetic linkage map consisted of a total genetic distance of 2,595 cM with 3,123 loci, including 22,330 SNPs across 25 chromosomes. QTL analysis detected 13 QTLs for 9 traits: leaf color a*, harvest day, fruit weight, fruit height, fruit diameter, fruit shell color, soluble solid content, acidity, and ascorbic acid content. The causative gene for each QTL was predicted with two genes identified as candidate genes. The AcCCD4 gene on Aco3.3C08 was the predicted causative gene for the shell color QTL, which negatively controls shell color by carotenoid degradation. The Myb domain protein-encoding gene on Aco3.3C02 was the predicted causative gene for shell color and leaf color a* QTL, which positively regulates anthocyanin accumulation. The QTL and gene information provided here contributes to future marker-assisted selection for fruit quality.
2 0 0 0 OA 労働時間の短縮は家庭参加を促進するか?
- 著者
- 脇 みどり
- 出版者
- 明治大学大学院
- 雑誌
- 情報コミュニケーション研究論集 (ISSN:18848001)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.23-38, 2019-02-28
2 0 0 0 OA 失業と政治参加の平等性 投票参加頻度のマルチレベル順序ロジスティック回帰分析
- 著者
- 伊藤 理史
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.61-83, 2018-03-28 (Released:2021-12-01)
- 参考文献数
- 38
本稿の目的は、個人レベルの失業と地域レベルの失業率の効果を理論的・実証的に区別した上で、両者が投票参加にそれぞれどのような影響を与えるのか、検討することである。失業と政治参加の関係については、欧米諸国における政治社会学の古典的な問題関心であると同時に、二〇〇〇年代後半に生じた世界規模の景気後退以後、再び注目を集め実証研究が蓄積されている。このような問題関心は、政治参加の平等性に関するものとして理解できるが、従来日本は政治参加の不平等が少ない国として認識されてきたこともあって、十分に検討されてこなかった。欧米諸国を対象とした近年の投票参加の実証研究によると、個人レベルの失業と地域レベルの失業率の効果は、それぞれ異なることが示唆されているため、両者を区別した上で議論・分析を行う。 第一回SSP調査から得られたデータに対してマルチレベル順序ロジスティック回帰分析を行った結果、次の二点が明らかになった。(一)個人レベルの失業には、投票参加からの退出をもたらす効果があり、失業者の「声」は政治へ反映されにくい傾向にある。(二)地域レベルの失業率には、その地域に居住する人々に対して、失業を社会問題として認知させ政治に動員させる効果がないため、当事(失業)者以外からも、失業やそれにともなう貧困の是正を求める「声」は上がらない傾向にある。以上の結果より、現代日本においても失業と投票参加の間には、一定の政治参加の不平等が存在することが確認された。
2 0 0 0 OA 一般小中学生におけるASD特性と運動能力及び心理社会的適応との関連
- 著者
- 中島 卓裕 伊藤 大幸 村山 恭朗 明翫 光宜 髙柳 伸哉 浜田 恵 辻井 正次
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.40-50, 2022 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 42
本研究の目的は,一般小中学生における運動能力を媒介とした自閉スペクトラム特性と心理社会的不適応(友人関係問題,抑うつ)の関連プロセスを検証することであった。小学4年生から中学3年生の5,084組の一般小中学生及び保護者から得られた大規模データを用いて検討を行った。パス解析の結果,ASD特性が高いほど運動能力の苦手さがみられることが明らかとなった。また,ASD特性と抑うつとの関連においては26%が,ASD特性と友人関係問題の関連については小学生で25%,中学生で16%が運動能力を媒介した間接効果であったことが示された。これらの関連においていずれの性別及び学校段階においても有意な効果の差は見られなかったことから,性別及び学校段階によらず心理社会的不適応に対して運動能力が一定の寄与を果たしていることが示唆された。本研究は代表性の高い一般小中学生のサンプルでASD特性と運動能力,心理社会的不適応の連続的な関連を定量化した本邦初の研究であり,今後のインクルーシブ教育推進のための政策・実践の基礎となる重要なデータを提供するものである。
2 0 0 0 OA アイヌ口承説話における「熊送り」の検討 ――「互酬性の物語」の理解を目指して
- 著者
- 馬場 裕美
- 出版者
- 東北大学大学院文学研究科宗教学研究室
- 雑誌
- 東北宗教学 = Tohoku Journal of Religious Studies (ISSN:18810187)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.27-62, 2022-12-31
2 0 0 0 OA 五節舞姫の参入
- 著者
- 佐藤 泰弘 Yasuhiro SATO
- 出版者
- 甲南大学文学部
- 雑誌
- 甲南大學紀要.文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)
- 巻号頁・発行日
- vol.159, pp.1-32, 2009-03-23
2 0 0 0 OA 気象変化による慢性疼痛悪化のメカニズム(最前線,<特集>痛みとかゆみ)
- 著者
- 佐藤 純
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.226-228, 2005-03-01 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 啄木の短歌創造過程の心理学的研究(二) : 歌稿「暇ナ時」の逐次的分析
- 著者
- 大沢 博
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.263-280, 1979-11-30
2 0 0 0 OA 『孫子』形篇の攻守観について : 竹簡本と十一家注本の比較を中心に
- 著者
- 熊 征
- 出版者
- 北海道大学大学院文学院
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:24352799)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.157-187, 2019-12-20
本稿は,1972 年4月に山東省臨沂県銀雀山の漢墓から発掘された竹簡『孫子兵法』を取り上げ,その「攻」と「守」に対する考え方と,テキストの変遷に示される後世における解釈の変化について考察する。全体は3つの部分に分けられる。 第1部では,『孫子兵法』全体の攻守観についてまとめる。まず,『孫子兵法』を総括的に見て,その戦争に対する消極的な態度を分析し,戦争論より平和論を説いていることを明らかにする。そして,『孫子兵法』の「攻」と「守」を始めとする軍事の各方面,各段階における万全を追求する万全主義を論じる。最後に,『孫子兵法』全体は防御を重視する思想を説いていることを論じる。 第2部では,『孫子兵法』の攻守観が集中的に表れている形篇を中心に,十一家注本と竹簡本との相違点を比較し,両版本の重大な相違点に基づく攻守観の差異について考察する。主に,竹簡本の「善者」,「非善者」が,十一家注本では,それぞれ「善戦者」,「非善之善者」に作る点を取り上げ,竹簡本と比べて,十一家注本のほうが,「戦」のことをより積極的に説いていることを論述する。また,「攻」と「守」をめぐる改変として,竹簡本の「守則有余攻則不足」が,十一家注本では「守則不足攻則有余」に作る点,竹簡本の「不可勝守可勝攻也」が,十一家注本では「不可勝者守也可勝者攻也」に作る点,また,竹簡本の「昔善守者蔵九地之下勭(動)九天之上」が,十一家注本では「善守者蔵於九地之下善攻者動於九天之上」に作る点についての分析を通して,竹簡本では肯定される守備が,十一家注本では逆に否定的に扱われていることを論じる。これらの相違点の分析を通して,第1部でまとめた『孫子兵法』の攻守観と合わせて,竹簡本のほうが孫武の本意にふさわしいことを論じる。 第3部では,同時に出土した竹簡兵書である『孫臏兵法』と『孫子兵法』の間の継承関係から,『孫臏兵法』の攻守観について考察する。重点的にその威王問篇にある「必攻不守」に対する理解の仕方について分析する。戦争を消極的に見ている点,守備を重視し,万全を求める点において,孫臏が孫武と共通していることを明らかにする。それに基づいて考えれば,『孫臏兵法』威王問篇における「必攻不守」は,『孫子兵法』の「攻而必取(〔者〕),攻其所不守也」を継承している可能性が大きく,「必ず守らざるを攻む」と読むのが適切であることを論じる。
- 著者
- 奥村 亮太 谷口 忠大 萩原 良信 谷口 彰
- 雑誌
- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-06
2 0 0 0 OA V.成人急性リンパ性白血病(ALL)―診断と治療の目覚ましい進歩―
- 著者
- 長藤 宏司
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.7, pp.1301-1308, 2018-07-10 (Released:2019-07-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 1
・フィラデルフィア染色体(Philadelphia chromosome:Ph)陽性急性リンパ性白血病(acute lymphoblastic leukemia:ALL)とPh陰性ALLでは大きく治療方針が異なり,ALLの診断後,早期にPhの有無を判定することが必要である.・Ph陰性ALLに対しては,多剤併用化学療法を行う.・思春期・若年成人ALLは,小児プロトコールで治療することが望ましい.・Ph陽性ALLは,60歳以上の高齢者でも,チロシンキナーゼ阻害薬(tyrosine kinase inhibitor:TKI)を使用することにより,高率に完全寛解に導入できる.
2 0 0 0 OA ダンゴムシの生態と防除
- 著者
- 関川 紘
- 出版者
- 関東東山病害虫研究会
- 雑誌
- 関東東山病害虫研究会年報 (ISSN:03888258)
- 巻号頁・発行日
- vol.1974, no.21, pp.188-191, 1974-08-30 (Released:2010-03-12)
2 0 0 0 OA 出血型もやもや病治療の新たな展開
- 著者
- 舟木 健史 髙橋 淳 宮本 享 JAM Trial Group
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.149-155, 2019 (Released:2019-03-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
出血型もやもや病の自然予後は不良であり, 再出血予防は最大の臨床的課題である. 出血型もやもや病に対する無作為比較試験であるJAM Trialは, 直接バイパスが再出血予防に有効であることを証明した. そのサブグループ解析により示された, 後方出血群の高い再出血率は, 本症特有の脆弱側副路である脳室周囲吻合により説明される. 解剖学的に最も後方に位置する脈絡叢型吻合 (choroidal anastomosis) は, 再出血の強力な予測因子であり, 特に注意すべき脆弱血管である. 一方, 非出血例において脈絡叢型吻合の発達が, 将来の新規出血の要因かどうか, 介入が必要か否かについては不明であり, 次の10年で明らかにすべき疑問と思われる.
2 0 0 0 OA 人はなぜ歌うのか, 歌を学ぶのか ―赤ちゃんの音楽性を学際的に考える―
2 0 0 0 OA 脳深部刺激術について
- 著者
- 橋本 隆男
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.149-153, 2015-08-01 (Released:2016-09-01)