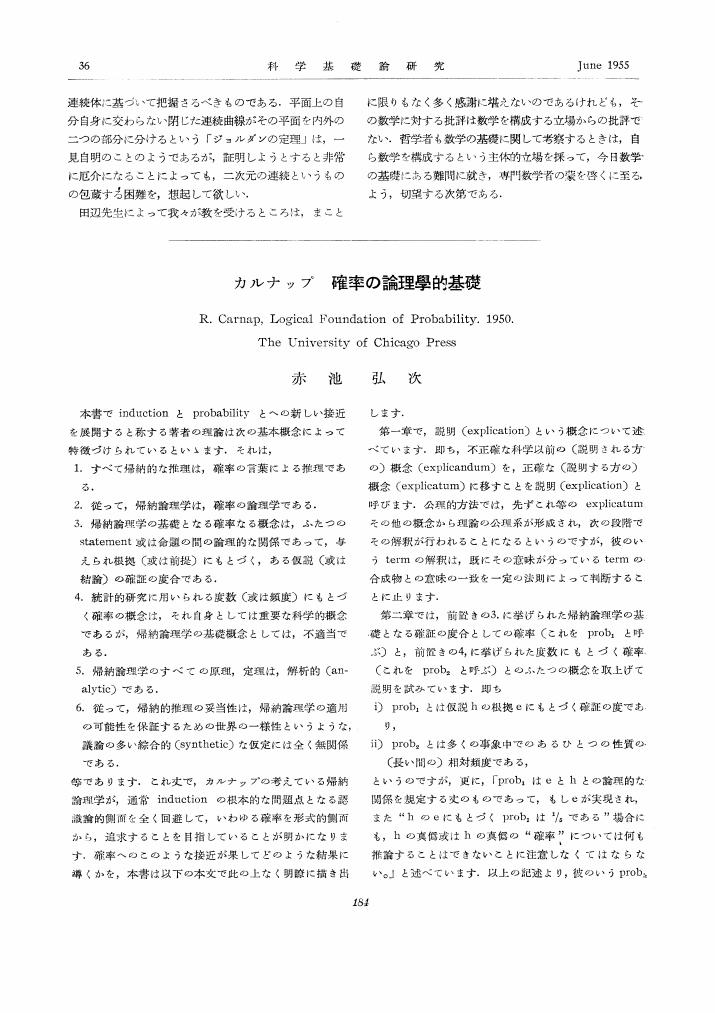2 0 0 0 OA 骨盤自動前後傾運動時の筋活動解析 前後傾可動域との関係
- 著者
- 高木 祥 金岡 恒治 大久保 雄 大塚 潔 宮本 渓 辰村 正紀 椎名 逸雄 宮川 俊平
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A3O2042, 2010 (Released:2010-05-25)
【目的】骨盤傾斜角度は脊柱アライメントに影響を与え、骨盤前傾位では腰椎前彎角は増加し、骨盤後傾位では逆に減少する。腰椎の過剰な前彎は腰痛の原因の一つと考えられ、腰痛のリハビリテーションとして腰椎前彎角を減ずることを目的に下肢のストレッチや骨盤後傾運動が行われている。骨盤前後傾運動においては,体幹の表層に位置するグローバル筋だけでなく,深層に位置するローカル筋の関与が最近の研究によって明らかにされてきているが,まだ詳細については不明な点が多い。また臨床において骨盤前後傾運動を実施する際,その運動範囲や運動様式には個人差が見られ,その評価は評価者の技術・経験などに影響される主観的なものであるため、より客観的に評価するための指標が望まれる。その指標の一つとして,骨盤前後傾可動域は比較的簡便かつ定量化が可能であり,有用だと考える。しかし,これまでに骨盤前後傾運動時の筋活動と可動域との関係を報告した研究は見当たらない。そこで本研究の目的は骨盤自動前後傾運動時の骨盤周囲筋の筋活動を明らかにし,さらに矢状面での骨盤前後傾可動域と筋活動との関係性を明らかにすることとした。【方法】健常成人男性12名(22.6±1.4歳,169.9±5.7cm,69.6±7.6kg)を対象とし,動作課題は立位骨盤中間位から最大前傾位までの骨盤前傾運動,次いで最大後傾位までの骨盤後傾運動を指示し,各運動中の筋電図を計測した。筋電図測定には,両側の腹直筋(RA)、外腹斜筋(EO)、脊柱起立筋(ES)および片側(右側)の広背筋(LD)、大殿筋(GMA)、半腱様筋(ST)、大腿直筋(RF)に表面電極(Vitrode F-150S; 日本光電)を貼布し,両側の腹横筋(TrA)、多裂筋(MF)にはワイヤ電極(UNIQUE MEDICAL社)を超音波ガイド下に23G注射針をガイドとして整形外科医によって挿入した。その後,電極が適切に刺入されていることを確認するために,電気刺激を加えて目的筋の収縮を超音波で描出した。ワイヤ電極刺入に関しては筑波大学倫理委員会の承認を得て実施した。サンプリング周波数は2000Hz,バンドパスフィルターは20-500Hzとした。等尺性最大随意収縮(MVC)時の筋活動で標準化した%MVCを算出し,さらに立位姿勢を保持するために要する筋活動の影響を取り除くため,骨盤前後傾運動時と安静立位保持時の%MVCの差で各筋を比較した。また骨盤前後傾可動域測定には,被験者の上前腸骨棘(ASIS)と上後腸骨棘(PSIS)にマーカーを貼付し,デジタルカメラを用いて矢状面における骨盤前傾位・中間位・後傾位の静止画を撮影した。その後,画像解析ソフトimage-J(NIH)を用いてASISとPSISを結んだ線が水平となす角度(骨盤傾斜角度)から骨盤前後傾可動域を算出した。さらに骨盤前後傾運動でそれぞれ大きい活動を示した筋を抽出し,筋活動と骨盤前後傾可動域との関係性について検討した。分析には骨盤前後傾運動時の各筋の筋活動の比較にTukey HSD法による多重比較検定を用い,骨盤前後傾可動域と筋活動との関係にはPearsonの積率相関係数を算出した。有意水準は5%未満とした。【説明と同意】被験者には事前に研究について書面と口頭による説明の後,同意を得て研究を実施した。【結果】骨盤前傾運動時には骨盤中間位に比較して,両側のMFが23.9%,右ESは19.0%,左ESは13.6%と有意に増加した。また骨盤後傾運動時は左TrAのみ14.7%と有意に増加した。また,特に大きい活動を示した両側MF(前傾)、左TrA(後傾)と骨盤前後傾可動域との相関係数はそれぞれ,0.68(右MF),0.62(左MF),0.53(TrA)であり,骨盤前傾可動域と両側MFでは有意に高い関係を示した。【考察】骨盤前傾運動では骨盤の上後方に付着するMFやESによって,骨盤の後方が引き上げられ,骨盤の前傾運動が生じると考えられる。一方の骨盤後傾運動では,これまで恥骨に付着するRAが主に作用すると考えられていたが,今回の結果ではRAよりもTrAの筋活動が大きかった。TrAは骨盤前方の腸骨稜や鼠径靭帯にも付着するため,収縮により骨盤の前方が引き上げられ,骨盤後傾運動が生じると考えられる。また,骨盤前傾可動域とMFの間には有意に高い関係が認められたことから,より大きく骨盤を前傾させるには,MFの大きい筋活動が必要とされることが考えられた。骨盤後傾運動では左TrAと後傾可動域に正の相関は認めたものの,ばらつきが大きく個人差や左右差が大きいことも推察された。【理学療法学研究としての意義】本研究により,骨盤自動前後傾運動時の筋活動が明らかとなり,骨盤の運動を客観的に評価する指標として,骨盤前後傾可動域の有用性が示唆された。
2 0 0 0 OA 縄文時代の植物のドメスティケーション
- 著者
- 那須 浩郎
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.109-126, 2018-08-01 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 137
- 被引用文献数
- 1 7
本論文では遺跡から出土したダイズ,アズキ,ヒエ属の種子サイズデータを集成し,縄文時代における形態上のドメスティケーション(種子の大型化)の過程を検討した.ダイズとアズキは6,000年前頃から4,000年前頃にかけて中部高地と関東地方西部地域(諸磯・勝坂式土器文化圏)において出土数が増加し,現在の野生種よりも大型の種子が出現していた.この種子の出土数の増加と大型化は,当時の人口増加と連動していた可能性があり,この時期に形態上のドメスティケーション(種子の大型化)が始まったと考えられる.しかしながら,この時期には小型の種子も依然として見られ,大型の種子をつける品種がまだ定着していなかったか,野生種の採集も継続していた可能性がある.4,000年前以降になると中部高地からは大型種子が見られなくなり,その代わりに九州地方や西日本で見られるようになる.この時期には大型種子の品種が定着し,栽培されていた可能性が高い.ヒエ属についても,東北地方北部で6,000年前頃,北海道渡島半島で4,500年前頃に,時期は異なるものの,同じ円筒式土器文化圏で大型種子が一時的に見られる.この大型化はそれぞれの時期の人口増加と連動しており,この時期に一時的な形態上のドメスティケーションが起きていた可能性があるが,その後は10世紀まで大型種子が見られない.10世紀以降には小型の種子も少なくなることから,この頃にヒエ属の大型種子が定着したと考えられる.
2 0 0 0 OA 薬剤漏出による皮膚組織傷害に対するアクリノール湿布の効果に関する実験的研究
- 著者
- 石田 陽子 三浦 奈都子 武田 利明
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.58-65, 2004-04-30 (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
薬剤漏出による皮膚組織傷害に対する処置として, アクリノール湿布は日常的に用いられている. しかしながら, その効果を裏づける科学的な実証データは少ない. そこで本研究では, 薬剤漏出による組織傷害に対するアクリノール湿布の作用を明らかにすることを目的に, 実験動物を用いた基礎的研究を行った. 起壊死性抗がん剤であるドキソルビシン (アドリアシン®) と起炎症性薬剤として知られているジアゼパム注射液 (セルシン®) を使用し, ラット背部皮膚にこれらの薬剤を漏出後, アクリノール湿布を4日間施行した. 湿布貼用後, 薬剤漏出部の肉眼的観察および組織学的検索を行った. その結果, 各薬剤を漏出したラット皮膚において, 肉眼的に異常所見は認められなかったが, 組織学的に, 皮下組織に重篤な浮腫や炎症性細胞の浸潤が観察され, 薬剤漏出による組織傷害像を確認した. このような薬剤漏出部において, 組織傷害の程度を, アクリノール湿布を貼用した群と貼用しない群で比較検討した結果, アクリノール湿布の効果を示す知見は得られなかった.
2 0 0 0 OA 瘟神の形成と日本におけるその波紋 -オニ(鬼)の発生と怨霊・御霊-
- 著者
- 山口 建治 Yamaguchi Kenji
- 出版者
- 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター
- 雑誌
- 年報 非文字資料研究 第9号 (ISSN:18839169)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.1-18, 2013-03-20
The Chinese character 鬼 came to be read “oni” in Japan when worship of the five chief demons of pestilence, 五瘟神, symbolizing the spirits of five people who died tragic deaths that came to be venerated as a guardian spirit to protect people from misfortune and harm like plagues, was introduced to Japan from China around the 8th century. The Chinese 瘟, “uən” changed to “oni” in Japan. Based on this theory, this paper will look at the relationship between Japanese ogres and two mythological spirits ― onryo(grudgebearing spirits) and goryo(evil spirits) ―both of which became known between the 8th and 9th centuries with reference to materials from the Heian Period. First, how the concept of the five chief demons of pestilence was formed amid the development of a folk ritual to drive away devils and diseases will be introduced. Second, the following five pieces of evidence that suggest that the demons were brought from China to Japan will be discussed in detail. (1) According to the dictionary compiled in the Heian Period titled Wamyosho, 瘧鬼 (gyakuki) was defined as “the spirit or ogre of pestilence,” whereas it was 瘟鬼 in the original. (2) In Manyoshu, or The Collection of Ten Thousand Leaves, the 鬼 that appears in a foreword written in Chinese seems to refer to the spirit of pestilence. (3) Ogres mentioned in Nihon Ryoiki, or The Miraculous Stories from the Japanese Buddhist Tradition, are either 疫神 or 疫鬼, meaning the spirit or ogre of pestilence, which are other names for 瘟神 or 瘟鬼 respectively. (4) A ritual to drive away the spirit of pestilence that often took place in the 8th and 9th centuries was actually meant for 怨霊( grudge-bearing spirits). These characters were read “oni ryau,” and the word was a synonym of “oni.” (5) 御霊社 was originally written 五霊社, which meant “a shrine to worship the five chief demons of pestilence from China.” From these proofs, it has been concluded that the ritual for onryo and goryo in the Heian Period was to worship oni and that it was a variation of the original Chinese version.
- 著者
- 松田 太希
- 出版者
- 日本体育大学スポーツ危機管理研究所
- 雑誌
- スポーツ危機管理研究 (ISSN:24358045)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.23-34, 2022-07-29
2 0 0 0 OA 近世都市大坂における自殺対策(前編)-千日墓所の死亡埋葬記録に基づいて-
- 著者
- 岸田 秀樹 Hideki Kishida 藍野大学医療保健学部作業療法学科 Aino University Faculty of Nursing and Rehabilitation Department of Occupational Therapy
- 雑誌
- 藍野学院紀要 = Bulletin of Aino Gakuin (ISSN:09186263)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.75-87, 2009-03-31
本稿では, 近世都市大坂の千日墓所の死亡埋葬記録の分析に基づいて, 1)大多数の死体が火葬にされ(平均95%), 2)土葬は自殺死体を含む不審死体(犯罪者の刑執行前の死体, 身元引受人のない死体, それらが疑われる死体)に適用される少数事例であったこと(平均5%), 従って3)都市大坂の墓所の本質的機能が火葬にあり, 専門的に火葬業務に従事する職業が成立していたこと, を明らかにする. さらに死亡埋葬記録に記載された死亡語彙を「死亡の種類」(病死, 自殺, 他殺, 事故死)の定義に基づいて分類し, 自殺を含むすべての死亡の種類を含意する可能性のある行倒死について, 1)享保飢饉を契機に町奉行所への届出が聖六坊の義務となったが, 検使役が出動した期間は14年間(1758-1772)に過ぎなかったこと, 2)行倒死体は墓所の大穴に投げ込むだけの土葬にされたこと, を明らかにする.
2 0 0 0 OA 回転タイヤのトレッドブロックひずみ・加速度・音圧の計測
- 著者
- 松原 真己 石井 航平 河村 庄造
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.123-128, 2023 (Released:2023-01-25)
- 参考文献数
- 7
タイヤの表面の直接路面と接触する部分はトレッド部と呼ばれ,タイヤの性能を評価する際に重要な役割を持つ.そこで本研究は,トレッドブロックが接地面内に侵入・離脱した際のひずみ分布・加速度・サブ溝音圧の同時計測を行い,放射音とトレッドブロック変形の関係性について検討した.
- 著者
- 大沢 知隼 橋本 塁 嶋田 洋徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.300-312, 2018-12-30 (Released:2018-12-27)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 4 4
本研究の目的は,集団ソーシャルスキルトレーニング(集団SST)の効果を左右する個人差として報酬への感受性に着目し,スキルの遂行に随伴する報酬のひとつである笑顔刺激に対する注意バイアス修正訓練によって,ソーシャルスキルの維持と般化が促進されるかどうか検討することであった。小中学生を,標準的な集団SSTを行う標準群と,集団SSTに加えて注意バイアス修正訓練を行う注意訓練群に振り分けた。ターゲットスキルの獲得がなされなかった可能性のある者を除外し,報酬への感受性の高低群に分けて分析を行った結果,小中学生ともにすべての条件において,獲得されたターゲットスキルが介入1か月後まで維持および刺激般化されることが示された。また反応般化については,攻撃行動は小学生のすべての条件で低減した一方で,向社会的スキルは小中学生ともに注意訓練群においてのみ増加が見られた。このことから,たとえターゲットスキルが維持および刺激般化されたとしても,スキルの種類によっては反応般化が起こりにくいこと,そして反応般化が起こりにくいスキルであっても,注意バイアス修正訓練を併用することで相応の反応般化が促される可能性があることが示唆された。
2 0 0 0 OA 百人一首と佐佐木信綱・愛国百人一首前後
- 著者
- 伊藤 嘉夫
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学紀要 = Journal of Atomi Gakuen Women's College (ISSN:03899543)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.三五-六八, 1971-03
2 0 0 0 OA 中年未婚者のiDeCo加入に関する実証分析
- 著者
- 丸山 桂
- 出版者
- 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
- 雑誌
- 年金研究 (ISSN:2189969X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.2-16, 2021-03-19 (Released:2021-03-19)
- 参考文献数
- 14
近年、老後の所得保障の自助努力として、私的年金制度、なかでも個人型確定拠出年金制度(iDeCo)が注目を集めている。しかし、その加入者に関する実証研究は、研究途上にある。本研究は、中年未婚者の個票データを用いて、iDeCo加入に関する実証分析と老後の低年金リスクが高い国民年金の保険料免除制度利用者との生活状況の比較を行った。主な分析結果は以下のとおりである。① 国民年金の保険料納付免除者は、仕事についていない者や非正規労働者の割合が高い。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、家計に深刻な影響があった者の割合は、国民年金保険料全額納付者や厚生年金加入者よりも、国民年金保険料滞納者、免除者に相対的に高かった。② iDeCoの加入状況を国民年金加入者と厚生年金加入者で比較すると、本来老後の年金額の上乗せ措置として加入が期待される国民年金加入者よりも厚生年金加入者に利用されている。iDeCo加入者は非加入者に比べ、収入や資産面でも余裕があり、NISA/つみたてNISAや個人年金制度も併用して、税制上の優遇措置を利用しながら、効率的に日常生活と老後の備えを行っている。③ 公的年金制度の繰り上げ制度/繰り下げ制度による給付額の減額・増額率を説明した上で希望する公的年金の支給開始年齢を尋ねた場合、国民年金の保険料免除者や滞納者は繰り上げ受給を望む者が相対的に多く、厚生年金加入者やiDeCo加入者には繰り下げ受給を選ぶ者が多い傾向が見られた。これは、現役時代にねんきん定期便で示される金額以上に、将来の高齢期の年金格差が拡大する可能性を示唆している。④ iDeCo加入について二項ロジスティック分析を行った結果、厚生年金加入者、金融資産額が高い者ほどiDeCoに加入する傾向にあり、個人年金やNISA/つみたてNISAを併用していることも明らかとなった。 今後とも、国民年金第1号被保険者に占める免除適用者数の増加が続き、経済的余裕のある者だけがiDeCoに加入し、税制上の優遇措置を二重三重に受け取る状況は老後の経済格差の拡大や所得再分配上の点から問題がある。公的年金の再分配機能とともに、本来加入すべき低年金者にいかにiDeCoの加入を促すか、金融リテラシーの形成支援も含めた検討を急がねばならない。
2 0 0 0 OA 酸化チタンを光触媒とする二酸化炭素の水による還元固定化
- 著者
- 安保 正一 山下 弘巳 河崎 真一 市橋 祐一
- 出版者
- The Japan Petroleum Institute
- 雑誌
- 石油学会誌 (ISSN:05824664)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.300-310, 1995-09-01 (Released:2008-10-15)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3 3
高活性な酸化チタン系触媒を二酸化炭素と水の存在下で光照射すると, 二酸化炭素の還元固定化反応が進行する。粉末酸化チタンやゾル-ゲル法調製Ti/Si複合酸化物を光触媒とした場合には主にメタンが, イオン交換やCVD法調製固定化酸化チタン (担体: 多孔性ガラス, ゼオライト) ではメタン, メタノールおよび一酸化炭素が生成する。反応収率は, 触媒や担体の種類, (水/二酸化炭素) 比, 反応温度などにより著しく変化する。UV, XAFS, ESR, FT-IR, XPSおよびホトルミネッセンスなどの手法で, 触媒の構造と励起状態のキャラクタリゼーションを行ったところ, 高活性な高分散酸化チタン触媒の活性種は孤立状態で存在する四配位酸化チタン種の電荷移動型励起種 (Ti3+-O-)*であることが分かった。また, 反応中間体の検討などから, 酸化チタン系触媒を光触媒とする二酸化炭素の水による固定化は, 二酸化炭素から一酸化炭素さらには炭素ラジカルの生成を経由する反応であると考えられる。
2 0 0 0 OA 元和・寛永期津軽藩の家臣団について : 『大日本古記録 梅津政景日記』の分析を通して
- 著者
- 福井 敏隆
- 出版者
- 弘前大学國史研究会
- 雑誌
- 弘前大学國史研究 (ISSN:02874318)
- 巻号頁・発行日
- no.84, pp.38-57, 1988-03-30
2 0 0 0 OA フランスにおける男性運動および男性性研究の動向
- 著者
- 海妻 径子
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.104-115, 2018-03-31 (Released:2021-11-12)
2 0 0 0 OA 生存権の法的性格
- 著者
- 齋藤 康輝
- 出版者
- 國士舘大學比較法制研究所
- 雑誌
- 比較法制研究 (ISSN:03858030)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, 1996
2 0 0 0 OA 下北半島浜尻屋貝塚出土中世小児人骨の歯冠形質
- 著者
- 鈴木 敏彦 澤田 純明 百々 幸雄 小山 卓臣
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.1, pp.27-35, 2004 (Released:2004-07-14)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 3
青森県下北半島浜尻屋貝塚の2002年の発掘調査において,中世に属する1体の小児人骨が出土した。本研究では,歯冠の計測値および非計測的形質について日本列島の各時代の集団との比較分析を行うことで,浜尻屋人骨の帰属集団を探った。歯冠サイズに関しては,浜尻屋人骨はアイヌと中世本土日本人の双方にオーバーラップしており,そのどちらに近いかを明らかにすることは難しかった。一方,非計測的形質に関しては,上顎前歯部の弱いシャベル形質や,下顎第二乳臼歯に見られたmiddle trigonid crestは,より縄文人的すなわちアイヌ的な形質特性を意味するものと思われた。以上を踏まえると,浜尻屋人骨は少なくとも渡来的形質を持った本土日本人ではなく,アイヌ,もしくは縄文・アイヌ的形質を備えた本土日本人のどちらかに属する可能性が高いと考えられた。
2 0 0 0 OA 子どもの金融リテラシーのジェンダーギャップに関する実証分析
- 著者
- 丸山 桂
- 出版者
- 生活経済学会
- 雑誌
- 生活経済学研究 (ISSN:13417347)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.159-178, 2022 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 40
The purpose of this study is to investigate the major factors affecting gender gap in children’s financial literacy by empirical analysis using microdata set. Even in lower elementary school grades, there is a difference in experience of talking about money or finance with their parents between boys and girls. More frequent parent-child discussion about money or finance has a positive impact on financial behavior and financial knowledge even in childhood. In this analysis, girls are less financially knowledgeable than boys. The reason is that girls tend to answer ‘I don't know’, rather than possibly answer a question incorrectly, compared to boys. The differences in response patterns to questions about financial knowledge are persistent between boys and girls from their elementary school period. Furthermore, those children who answered ‘I don't know’ tend to have lower financial literacy and financial attitudes, lower abilities at mental arithmetic, not having personal bank account, and live in households with less cultural capital and parent-child discussion about money and finance. It is necessary to consider the effects of encouraging discussion and questioning gender-based attitudes and roles in both the home and school education.
2 0 0 0 OA 近世北奥地域における造船界の歴史的動向
本論文は、現在の青森県域に相当する、弘前、八戸、盛岡の各藩領域、すなわち近世北奥地域における造船界の動向を明らかにし、その歴史的意義を論じるものである。序章では、造船史研究の諸問題と本研究の意義や視角を述べる。北奥地域における造船史研究が乏しいことから、本論文では、造船の数量的把握、造船にかかわる物資や人々の存在形態、造船ネットワークの様相など、きわめて重要な問題について追究する。おもな論点として、造船界の動向を顕著に反映する藩船の建造動向、一般商船を中心とする廻船建造の実態、船大工の存在形態、北奥アイヌを含めた一般領民による漁船製作の動向を取り上げる。以上について、筆者があらたに研究対象として提示する史料を含めた、豊富な史資料に依拠しながら多角的に検証し、系統立てて論じる。Ⅰ部では、北奥地域における廻船建造と船大工の動向について扱う。第1章では、とくに17世紀半ばの北奥地域を対象に、各領内諸湊の特長や海上交通との関係から諸廻船の船型や存在概況について分析し、近世廻船の主力である弁才船が普及していく状況などを指摘する。廻米や物資輸送に用いた各藩による藩船建造の事実から、相応の造船界が存在したことがみとめられる。第2章では、弘前藩領における一般商船の建造実態と造船資材の供給システムについて明らかにする。17世紀後半の領内では、全国各地の船頭などによる廻船建造が行なわれ、そのほとんどは1000石積級前後の弁才船べざいせんであり、当該期にはすでに地船としても普及したことを指摘した。領内では効率的な造船システムが確立され、同藩も困窮する日雇い層へ救済措置として他領船頭からの造船受注を進めつつ、同時に移入拡大を企図したことが判明する。第3章では、近世期を通じた弘前藩領における船大工の存在形態や造船技術力について論じる。十三に存在した船大工集団は、藩船のほかに領内外の一般商船の建造も数多く受注する領内最有力の造船技術者であった。ほか青森、小泊など、船大工棟梁もつとめるトップレベルの船大工が存在し、造船需要を支えたものといえる。第4章では、盛岡藩領田名部通(現在の下北半島一帯)および八戸藩領における船大工の動向を中心に、一般商船の建造実態を検証する。南部領における造船場は、八戸および田名部通の有力諸湊で、造船技術力の要は田名部通の有力諸湊や同藩領宮古など閉伊の船大工であり、他領の有力な船大工も参入した。北奥の太平洋沿岸地域に造船ネットワークが形成され、全国海運に供する造船需要の高まりを補ったといえる。Ⅱ部では、北奥地域における漁船製作とアイヌ民族による造船の問題を検討する。第5章では、北奥地域における漁船の製作動向を明らかにする。18世紀北奥地域における漁船の分野では、弘前藩領および八戸藩領では丸木船が主力で、盛岡藩領では地引網漁に用いる「図合船」「三羽船」が多い傾向であることから、それぞれの海況や漁獲対象に相応した漁船が普及したといえる。造船用材の供給、商品としての漁船の流通、修理を含めた受注製作など、その需要を満たすシステムが北奥地域に機能していたとみなすことができる。第6章では、北奥アイヌの造船について、「犾船」呼称についての整理、松前方面アイヌの縄綴船なわとじぶねとの比較検討、津軽領内アイヌの造船動向など、船体構造の面から検証した結果、津軽領内アイヌは、松前方面のアイヌの縄綴船を自らは製作せず、丸木船のほか一般和人領民同様の構造船を求めたことが明らかとなった。終章では、北奥地域造船界の歴史的特質を述べる。同地域には、17世紀中葉から全国各地の廻船商人などが蝟集し、廻船建造を発注していたことから、当該期、造船界の勃興をみることができるものの、領内海運界の興隆には直結しなかった。津軽領および盛岡藩田名部通の有力諸湊の船大工は、他領船大工と拮抗しつつ技術の練磨につとめ、大工集団や大工ネットワークも組織し、近世期を通じて、領内外の造船需要に応ずる基盤として存在し続けた。漁船の主力は、一般和人領民・アイヌともに近世を通じて単材刳船であったが、用材樹種の利用制限が、積載量の増大を実現する「合漁船」への発達を促した。丸木船から発展した「ムタマ造り」は、用材や造船技術の市場が北奥全体に展開されたことにより、同地域に特徴的な構造として定着したものとみなされる。津軽領内アイヌの場合、寛文期の蝦夷蜂起事件を一つの画期として、丸木船と舷側板とを縄で綴じ合わせる形式の縄綴船に拘泥せず、海運活動に資する廻船を指向した点に、その特質がみとめられる。以上の通り、北奥地域においては、領主権力、海商、船大工、一般和人領民、アイヌが、物資や情報、技術などさまざまな資源を相互に供給することにより藩領域を越えた複合的な造船界を形成し、海運や漁撈を支えたものと評価できる。
2 0 0 0 OA SilkBaseのアップデート ─タンパク質立体構造情報の配備─
- 著者
- 川本 宗孝 勝間 進
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.3_217-3_220, 2022 (Released:2023-01-20)
- 参考文献数
- 14
SilkBase (https://silkbase.ab.a.u-tokyo.ac.jp) is an integrated transcriptomic and genomic database for Bombyx mori and related species. This database not only provides the latest versions of genome sequences and gene models, but is also a genome browser and analysis tool that allows users to understand the landscapes of gene expression, PIWI-interacting RNA production, and histone modifications. Here we have updated SilkBase with protein structure predictions from a silkworm gene model using AlphaFold2, including other information such as the expression levels of each tissue and linkage in the genome browser.