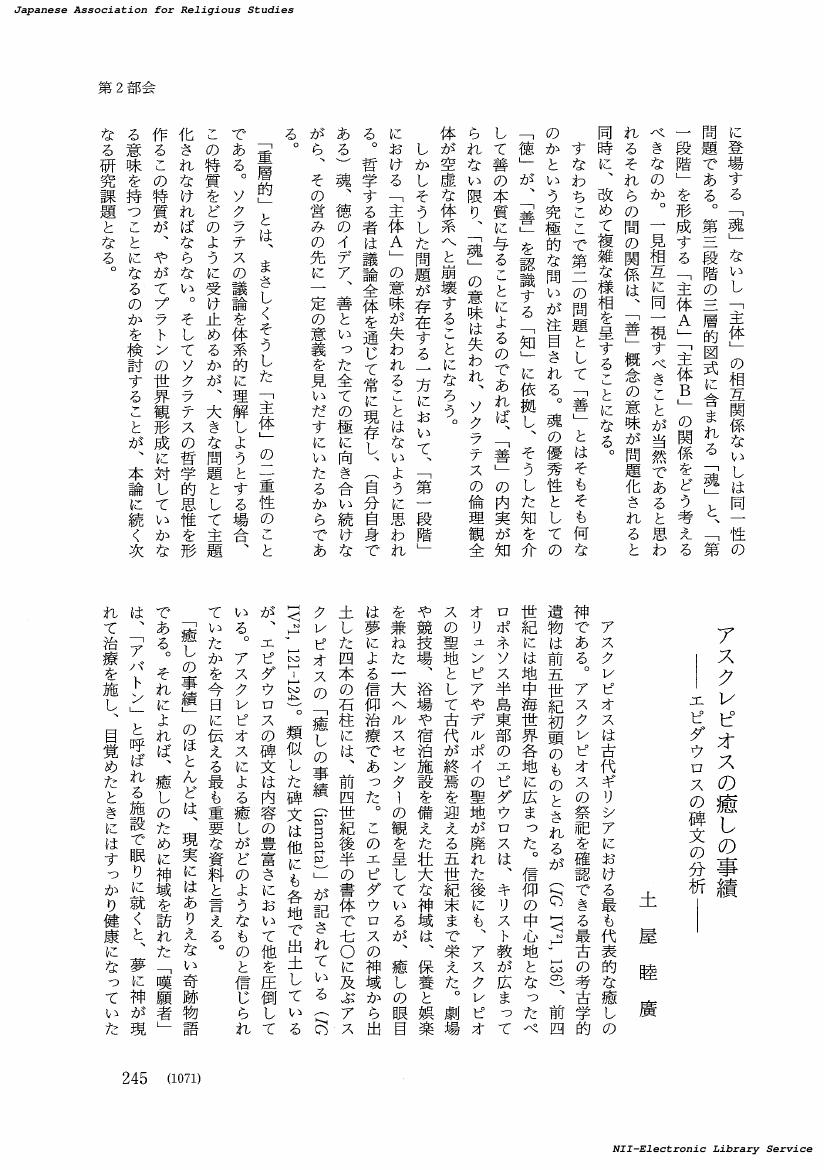63 0 0 0 OA 公共調達制度の歴史変遷に関する研究
- 著者
- 藤井 聡 宮川 愛由
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.I_97-I_109, 2016 (Released:2017-01-31)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
自然災害に見舞われるリスクが高い我が国において,社会資本整備のみならず,防災及び経済発展の担い手として,土木建設業が非常に重要な役割を果たしてきた.一方で近年,公共工事の入札市場では,闇雲な低入札等の弊害により,建設業界全体が疲弊しており社会全体が甚大な不利益を被ることが危惧されている.そこで本研究では,我が国の公共調達制度適正化に資する知見を得ることを目的として,明治初期から今日に至るまでの我が国の公共調達の歴史変遷を整理した.その結果,我が国の公共調達は純粋な競争を避け,実質的に受発注者で調整を行うことで個々の受注価格と請負者を特定し,その中で,適切な工事品質を確保するという公益に資する目的で行われていた談合の存在と,それを正式に活用するための制度発展という歴史的経緯の存在が示唆された.
63 0 0 0 OA 骨格筋裂傷損傷の初期再生過程における寒冷・温熱刺激の影響
- 著者
- 石田 静香 高木 領 藤田 直人 荒川 高光 三木 明徳
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.AbPI2070, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】外力によって損傷を受けた骨格筋は、Caイオンの流入により生じる二次的な損傷部と非壊死領域の間に境界膜を形成する(松本, 2007)。筋は損傷を受けると変性、壊死後、再生する、という過程をたどる(埜中, 2001)ことから、再生の前段階である変性、壊死という二次損傷を最小限に抑えることは、次に続く筋の再生過程にも大きく影響すると考えられる。臨床場面、特にスポーツの現場では筋損傷後に寒冷療法を用いることが多い(加賀谷, 2005)。われわれは筋損傷後に与える温度刺激が筋の再生にどのように影響するのかを調べてきた。高木(2009)は、寒冷刺激によってマクロファージの進入が遅れることから、骨格筋の再生が遅延する可能性を報告した。また、Kojimaら(2007)は温熱刺激が筋損傷後の再生に重要な役割を担うと報告している。そこで、われわれは実験動物に筋損傷を惹起させた後、その二次損傷と再生過程が温度刺激によってどのように変化するのかを、寒冷、温熱双方の刺激を加えることで確かめることとした。【方法】8週齢のWistar系雄ラット15匹の前脛骨筋を用いた。動物を筋損傷のみの群(C群:n=5)、筋損傷後寒冷刺激を与える群(CI群:n=5)、損傷後温熱刺激を与える群(CH群:n=5)の3群に分けた。前脛骨筋を脛骨粗面から4mm遠位で剃刀を用いて約2/3の深さまで横切断し、筋損傷を惹起した。筋損傷作製から5分後に20分間の寒冷刺激あるいは温熱刺激を加えた。寒冷刺激は高木ら(2009)の方法に倣い、ビニール袋に砕いた氷を入れ、筋を圧迫しないように下腿前面に当てた。温熱刺激は約42度に温めた湯を入れたビニール袋を下腿前面に当てた。湯を入れたビニール袋は2分毎に交換した。これにより、筋温は寒冷刺激で約20度低下し、温熱刺激で約10度上昇した。筋切断から3,6,12,24,48時間後に、動物を灌流固定し前脛骨筋を採取した後、浸漬固定を行い、エポキシ系樹脂に包埋し縦断切片を作製した。厚さ約1µmで薄切し、1%トルイジンブルーで染色して光学顕微鏡で観察した。【説明と同意】全ての実験は所属施設における動物実験に関する指針に従って実施した。【結果】損傷3時間後、全群で損傷部とその周辺に染色性の低下が見られた。これは48時間後まで徐々に進行した。CH群での染色性の低下が著明で、CI群では低下が抑制されていた。損傷3時間後から、全群で境界膜形成が進行し、12時間後には大部分の筋線維で境界膜が形成された。非壊死領域で、筋線維の長軸方向と平行に伸びる細長い空胞が3,6時間後に観察された。1視野あたりの空胞数の平均を調べたところ、C群1.0個、CI群2.3個、CH群4.3個であった。CI群、CH群ではC群と比較して大きな空胞が観察された。損傷3時間後、全群で単核の細胞が損傷筋線維内に観察され、本細胞は形態学的にマクロファージであると判断できた。筋線維内に進入したマクロファージ数は48時間後まで増加し続けた。筋衛星細胞は6時間後から全群で観察され、24時間後まで増加した。12時間後において全群で肥大化した筋衛星細胞が観察された。CH群では24時間後に、C群では48時間後に筋芽細胞が明らかに観察できたが、CI群では48時間後でも明らかな筋芽細胞は観察できなかった。【考察】損傷3時間後から観察された壊死領域の染色性の低下は、Caイオン流入による蛋白分解を示していると考えられる。CH群において染色性の低下が進行していたことから、今回の温熱刺激は蛋白分解を促進した可能性がある。CI群では染色性の低下が抑制されたことから、寒冷刺激は蛋白分解を抑制したと考えられる。損傷3,6時間後、境界膜が不完全な領域で、筋線維内に空胞が観察された。すなわち、この空胞は境界膜が不完全な段階でCaイオンが筋線維内に部分的に流入したために生じたと考えられる。CH群で多くの空胞が観察されたことは、温熱刺激により蛋白分解が促進され、境界膜形成前に二次損傷が進行した現象であろう。CI群における多数の空胞形成は、寒冷刺激により蛋白分解が抑制されたものの、境界膜形成や細胞小器官の集積がそれ以上に遅延したために生じたと考えられる。CH群における24時間後の筋芽細胞の出現は、骨格筋の再生過程の初期には温熱刺激が効果的である可能性を示唆していると考えられる。【理学療法学研究としての意義】本研究により、損傷急性期に与える温熱刺激は二次損傷を助長するが、再生過程においては効果的であることが示唆された。今後の臨床応用に興味深い示唆を与えたと思われる。
63 0 0 0 OA 外来哺乳類の管理戦略と生態系保全に関する研究
- 著者
- 亘 悠哉
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.277-281, 2016 (Released:2017-02-07)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 土屋 睦廣
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.1071-1072, 2009-03-30 (Released:2017-07-14)
63 0 0 0 OA イノシシ(Sus scrofa)の分布拡大時における水稲被害の地理的発生要因
- 著者
- 清水 晶平 望月 翔太 山本 麻希
- 出版者
- 日本景観生態学会
- 雑誌
- 景観生態学 (ISSN:18800092)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.173-182, 2013-12-25 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 4 3
イノシシ(Sus scrofa)による農業被害が近年深刻な社会問題となっている.被害の地理的発生要因を解き明かすことは,被害対策を効率的に実施するうえで重要である.本研究の調査地である新潟県上越市柿崎地区では,被害地域が大きく拡大した後,電気柵を設置したことにより,被害地域の縮小に成功している.そこで本研究では,新潟県上越市柿崎地区におけるイノシシ由来の農業被害に対し,被害の拡大前期(2004年~2007年),拡大期(2008年),そして,減少期(2009年~2010年)の3期に分け,3つの期間における被害地点とその周辺の地理的要因との関係を明らかにすることを目的とした.本研究では,「水稲共済損害評価に係る獣害(イノシシ)申告データ」と,現地踏査により作成した土地利用図を使用して分析した.被害地点と被害のない地点について,林縁や河川からの距離など,被害地点の景観構造を示す変数を説明変数としたロジスティック回帰分析を行った.また,電気柵を張る前と後の被害地点についても,同様にロジスティック回帰分析を行った.この結果,林縁,沢,耕作放棄地に近いほど被害が増加する傾向が認められた.河川,道路,都市部に関しては距離が遠いほど被害が増加する傾向が認められた.また,電気柵を設置したことにより,被害の分布が都市部に近づいていることが判明した.イノシシによる被害は見通しの悪い林縁や耕作放棄地の周辺で発生していることが明らかになり,イノシシによる被害対策には,林縁の刈払いや耕作放棄地の管理と個体数調整を同時に考慮した対策を見出す必要性があることを示した.電気柵を設置する場合は,十分な捕獲計画と併用するか,被害がまだ起きていないエリアも全体的に電気柵で一気に囲ってしまうなどの配慮が必要であろう.
63 0 0 0 OA 課題研究Ⅰ・Ⅱ 現代日本の教育課程政策における政治・行政・経営をめぐる諸問題
- 著者
- 天笠 茂
- 出版者
- 日本カリキュラム学会
- 雑誌
- カリキュラム研究 (ISSN:0918354X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.56-56, 2015 (Released:2017-01-17)
- 著者
- 間瀬 浩安 田中 彩乃 篠生 孝幸 野崎 司 浅井 さとみ 宮地 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.413-420, 2015-07-25 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 6
カフェインはコーヒーや紅茶などに含まれる一般的な物質である。また感冒薬や鎮痛薬など市販薬などにも含まれる物質である。今回,我々は血中カフェイン濃度についてLC-MS/MSを用いイブプロフェン,エテンザミドおよびロキソプロフェンとの同時分析を可能にした。カフェインのPrecursor ionは195.1 m/z,Product ionは138.1 m/zであった。固相カートリッジ抽出の回収率は90%以上であった。HLBを使用した検出限界は0.01 μg/mLであった。イブプロフェン測定法では1.1分に検出され,テオフィリンを測定した場合にもカフェインへの干渉はなかった。缶コーヒー飲用時の血中カフェインピーク濃度は5.65 μg/mL,ピーク時間は60分,半減時間は360分であった。カフェインがイブプロフェン等と同時に測定できることは,感冒薬や鎮痛薬の過量服用の場合の迅速測定に有用である。
- 著者
- Yuki IWAHANA Atsushi OHBUCHI Yuya KOIKE Masaru KITANO Toshihiro NAKAMURA
- 出版者
- (社)日本分析化学会
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.61-66, 2013-01-10 (Released:2013-01-10)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 5 19
Radioactive nuclides in the incinerator ashes of municipal solid wastes were determined by γ-ray spectrometry before and after the accident at the Fukushima nuclear power plant (March 11, 2011). Incinerator ash samples were collected in northern Kyushu, Japan, which is located approximately 1200 km west-southwest (WSW) of the Fukushima nuclear power plant, from April 2006 to March 2007 and from March 2011 to October 2011. 40K, 137Cs, 208Tl, 212Pb, 214Pb, 212Bi, 214Bi, and 228Ac were identified in the ashes before the accident (∼February 2011) and 134Cs was identified along with these eight nuclides in the ashes after the accident (March 2011∼). A sequential extraction procedure based on a modified Tessier method with added water extraction was used for 1st fly ash sampled in August 2011 because the highest activity concentrations of 134Cs and 137Cs were observed for this sample. The speciation of radioactive nuclides in the fly ash was achieved by γ-ray spectrometry and powder X-ray diffractometry for the extraction residues. Little variation was observed in the distribution of the chemical forms of 134Cs and 137Cs in 1st fly ash of municipal solid waste; one half of 134Cs existed as water soluble salts and the other half as carbonate compounds, whereas 75% of 137Cs existed as water soluble salts with the remainder as carbonates(10%) and sulfides (15%). These results show that 88% of the total radioactive Cs existed in water soluble and ion extractive forms and might be at risk for elution and diffusion with rain and wind.
62 0 0 0 OA 高等学校の地理教育・地学教育における教科書用語の問題点―用語問題の類型化と学術的整合性―
- 著者
- 山本 政一郎 尾方 隆幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.68-83, 2018 (Released:2018-03-16)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 2
高等学校の地理教育,地学教育で共通する自然地理学,地球物理学,地質学に関連する項目の用語や説明について,2017年度に使用されている「地理A」「地理B」「科学と人間生活」「地学基礎」「地学」の全ての教科書で比較検討した.その結果,地理教育,地学教育それぞれの中でも,両者の間でも異なる用語が多いことが分かった.また,学術用語と教育用語とに齟齬がある場合もみられた.今後は,現在の科学界の知見を高校教育に反映させて,よりふさわしい用語や説明を検討・採用していく必要がある.
62 0 0 0 OA 腸内細菌と発達障害
- 著者
- 三上 克央
- 出版者
- 消化器心身医学研究会
- 雑誌
- 消化器心身医学 (ISSN:13408844)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.2-5, 2015 (Released:2015-09-01)
- 参考文献数
- 18
発達障害は,典型的には発達期早期,しばしば就学前に明らかになり,個人的,社会的,学業または職業に機能の障害を引き起こす特徴をもつ。特に,コミュニケーションと社会性,想像性に問題を認める自閉スペクトラム症(Autism spectrum disorder,以下ASD)と腸内細菌との関係が近年注目されている。ASDには消化器症状を併存する頻度が高いとする研究成果は蓄積されつつあるが,近年はさらに,腸内細菌叢が発達障害の症状に影響を及ぼすことを示唆する報告が見られる。本稿では,人の腸内細菌叢の生後発達と腸内細菌叢の役割についてプロバイオティクスの中核であるビフィズス菌を中心に概観した上で,腸内細菌と発達障害の関係に焦点を当てて考察するとともに,腸内細菌の健全化の観点から,発達障害の症状に対する予防的アプローチの可能性にも言及した。
- 著者
- Bonpei Takase Takanori Ikeda Wataru Shimizu Haruhiko Abe Takeshi Aiba Masaomi Chinushi Shinji Koba Kengo Kusano Shinichi Niwano Naohiko Takahashi Seiji Takatsuki Kaoru Tanno Eiichi Watanabe Koichiro Yoshioka Mari Amino Tadashi Fujino Yu-ki Iwasaki Ritsuko Kohno Toshio Kinoshita Yasuo Kurita Nobuyuki Masaki Hiroshige Murata Tetsuji Shinohara Hirotaka Yada Kenji Yodogawa Takeshi Kimura Takashi Kurita Akihiko Nogami Naokata Sumitomo on behalf of the Japanese Circulation Society and Japanese Heart Rhythm Society Joint Working Group
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0827, (Released:2023-09-11)
- 参考文献数
- 738
- 被引用文献数
- 7
62 0 0 0 OA アセトアミノフェンの添加剤が原因と推察されたアレルギーの1例
- 著者
- 原口 哲子 髙橋 佳子 大久保 晃樹 西小野 美咲 榊 美紀 原口 優清
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.197-201, 2019 (Released:2019-08-27)
- 参考文献数
- 15
【緒言】解熱鎮痛剤であるアセトアミノフェンはWHO(世界保健機関)方式がん疼痛治療法では代表的な薬剤の一つとして位置づけられている.【症例】75歳,女性. 左上葉肺がん術後再発.多発骨転移によるがん疼痛に対しアセトアミノフェンを使用していたが,同薬剤の商品を変更しアレルギー症状が出現したため中止し,症状は消失した.同薬剤の別の商品へ変更し継続した.【考察】アレルギー症状はアセトアミノフェンの添加剤が原因と推察された.【結論】アセトアミノフェンによるアレルギー症状の出現時,規格を変更することで薬剤使用を継続できる可能性がある.
62 0 0 0 OA 「幸福な監視国家」の経済学 ―産業政策・監視技術・文化対立―
- 著者
- 梶谷 懐
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済研究 (ISSN:18805647)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1_1-1_12, 2022 (Released:2022-02-15)
- 参考文献数
- 41
本論文では,COVID-19の流行と米中対立の顕在化を題材に,現在の米国を中心としたリベラルな国際経済秩序が今後直面するであろう「危機」について,その具体的な性質について考察する.考察にあたっては,「産業政策」「監視技術」「文化対立」というお互いに密接な関連性を持っている三つのキーワードを軸に議論を進め,「危機」がもたらす価値観の対立をどう乗り越えるのかを検討する.
62 0 0 0 OA 戦前期の図書館における婦人室について : 読書する女性を図書館はどう迎えたか
- 著者
- 宮崎 真紀子
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.434-441, 2001-11-10 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 1
日本の戦前の図書館には婦人室があった。それは義務づけられたものではなかったが設置することが望ましいとされ,女性へのサービスの一環ともみなされていた。確かにその部屋は狭く,現代の感覚からすると押し込められた,というイメージでとらえられてしまうが,当時の状況を考えると,違う姿が浮かび上がる。婦人室を中心に,女性の図書館利用,そして図書館は女性利用者をどう見たかを考察する。
62 0 0 0 OA AlphaFoldによるタンパク質立体構造予測(実践編)
- 著者
- 大上 雅史
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.8, pp.443-446, 2023-08-25 (Released:2023-08-25)
- 参考文献数
- 17
62 0 0 0 OA 室町幕府の文書管理 南北朝~室町初期を中心に
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.4-23, 2022 (Released:2023-09-21)
62 0 0 0 OA 皮膚ガス測定および鼻腔内微生物検査に基づくPATMに関する考察
- 著者
- 川上 裕司 関根 嘉香 木村 桂大 戸高 惣史 小田 尚幸
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.19-30, 2018 (Released:2018-04-01)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
自分自身が皮膚から放散する化学物質によって,周囲の他人に対してくしゃみ,鼻水,咳,目の痒みや充血などのアレルギー反応を引き起こさせる体質について,海外ではPATM(People Allergic to Me)と呼ばれ,一般にも少しずつ知られてきている。しかしながら,日本では殆ど一般に認知されておらず,学術論文誌上での報告も見当たらない。著者らはPATMの男性患者(被験者)から相談を受け,聞き取り調査,皮膚ガス測定,着用した肌着からの揮発性化学物質測定,鼻腔内の微生物検査を実施した。その結果,被験者の皮膚ガスからトルエンやキシレンなどの化学物質が対照者と比べて多く検出された。また,被験者の皮膚から比較的高い放散量が認められたヘキサン,プロピオンアルデヒド,トルエンなどが着用後の肌着からも検出された。被験者の鼻腔内から分離された微生物の大半は皮膚の常在菌として知られている表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis)であった。分離培地上でドブ臭い悪臭を放つ放線菌(Arthrobacter phenanthrenivorans)が分離されたことはPATMと何か関連性があるかもしれない。また,浴室や洗面所の赤い水垢の起因真菌として知られている赤色酵母(Rhodotorula mucilaginosa)がヒトの鼻腔内から分離されたことは新たな知見である。この結果から,PATMは被験者の思い込みのような精神的なものではなく,皮膚から放散される化学物質が関与する未解明の疾病の可能性が示唆された。
62 0 0 0 OA 政治学者と政治家のあいだで 決断・対応・目標の政治学
- 著者
- 蒲島 郁夫
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.61-76, 2016 (Released:2019-12-01)
- 参考文献数
- 8
62 0 0 0 OA 大阪市警視庁の興亡 ―占領期における権力とその 「空間」 ―
- 著者
- 小宮 京
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.1_319-1_339, 2013 (Released:2016-07-01)
This article investigates the reform of Japanese Police System during 1945-55. Most of the existing studies of Japanese Police System under the Allied Occupation rarely discuss local Police System. Our main focus in this article is the Osaka Metropolitan Police Department (OMPD) during 1949-1954. In 1948, GHQ ordered the Tokyo Metropolitan Police Department (TMPD) to adopt a patrol system on the model of the American system. TMPD refused the directive. Next, GHQ carried out the same directive to Eiji Suzuki, the chief of the Osaka City Municipal Police. Suzuki founded OMPD which had an American type of the patrol system. After the Allied Occupation, OMPD was abolished because it was faithful to GHQ directives. Thus, OMPD was reorganized to the Osaka Prefectural Police Department. Japanese Police System returned to a highly centralized system as a result that most of the Police System reform under the Allied Occupation were denied.
62 0 0 0 OA 「島のケルト」再考
- 著者
- 田中 美穂
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.10, pp.1646-1668, 2002-10-20 (Released:2017-12-01)