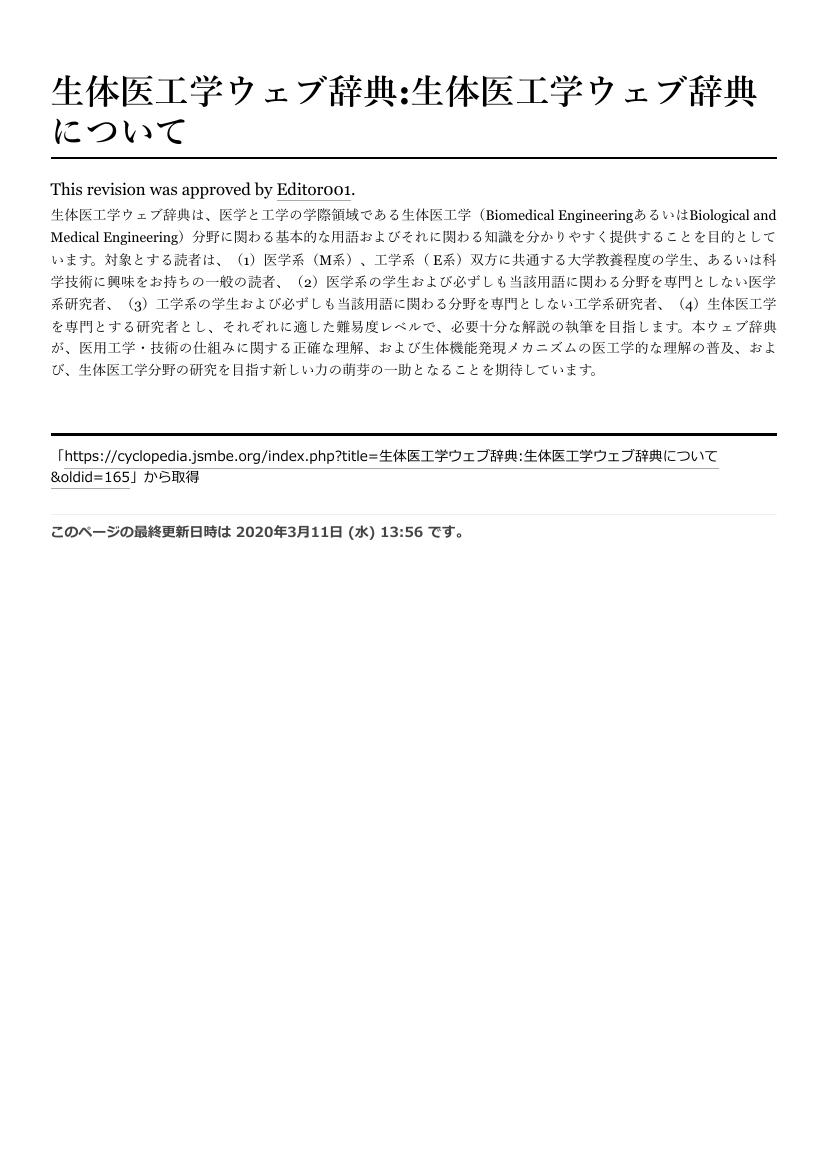2 0 0 0 OA 生体医工学ウェブ辞典(第一分冊)
- 著者
- 相川 慎也 芦原 貴司 天野 晃 有末 伊織 安藤 譲二 伊井 仁志 出江 紳一 伊東 保志 稲田 慎 井上 雅仁 今井 健 岩下 篤司 上村 和紀 内野 詠一郎 宇野 友貴 江村 拓人 大内田 研宙 大城 理 太田 淳 太田 岳 大谷 智仁 大家 渓 岡 崇史 岡崎 哲三 岡本 和也 岡山 慶太 小倉 正恒 小山 大介 海住 太郎 片山 統裕 勝田 稔三 加藤 雄樹 加納 慎一郎 鎌倉 令 亀田 成司 河添 悦昌 河野 喬仁 紀ノ定 保臣 木村 映善 木村 真之 粂 直人 藏富 壮留 黒田 知宏 小島 諒介 小西 有人 此内 緑 小林 哲生 坂田 泰史 朔 啓太 篠原 一彦 白記 達也 代田 悠一郎 杉山 治 鈴木 隆文 鈴木 英夫 外海 洋平 高橋 宏和 田代 洋行 田村 寛 寺澤 靖雄 飛松 省三 戸伏 倫之 中沢 一雄 中村 大輔 西川 拓也 西本 伸志 野村 泰伸 羽山 陽介 原口 亮 日比野 浩 平木 秀輔 平野 諒司 深山 理 稲岡 秀検 堀江 亮太 松村 泰志 松本 繁巳 溝手 勇 向井 正和 牟田口 淳 門司 恵介 百瀬 桂子 八木 哲也 柳原 一照 山口 陽平 山田 直生 山本 希美子 湯本 真人 横田 慎一郎 吉原 博幸 江藤 正俊 大城 理 岡山 慶太 川田 徹 紀ノ岡 正博 黒田 知宏 坂田 泰史 杉町 勝 中沢 一雄 中島 一樹 成瀬 恵治 橋爪 誠 原口 亮 平田 雅之 福岡 豊 不二門 尚 村田 正治 守本 祐司 横澤 宏一 吉田 正樹 和田 成生
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.Dictionary.1, pp.1-603, 2022 (Released:2022-03-31)
2 0 0 0 OA リンゴの摘果時間と果実重に及ぼす薬剤摘花・摘果の影響
- 著者
- 守谷(田中) 友紀 岩波 宏 花田 俊男 本多 親子 和田 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.283-289, 2016 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
リンゴの主要4品種において,摘果期間早期の落果量を増加させる摘花剤がもたらす摘果期間全体での省力効果および果実肥大促進効果を検証し,各品種における効率的な薬剤摘花・摘果の方法を検討した.頂芽果落果率や腋芽の結実花そう率の違いから,薬剤摘花・摘果の効果は品種により異なった.‘つがる’および‘ジョナゴールド’では,摘花剤単用は腋芽の結実花そう率が高いために腋芽果の摘果に時間を要し,省力につながらなかった.果実肥大を考慮すると,両品種においては摘花剤と摘果剤の併用が最も効果的であった.‘シナノスイート’では,薬剤摘花・摘果による摘果作業の省力効果はなかったが,果実肥大が促進されることから摘花剤散布が有効であった.‘ふじ’では,人工受粉によって果実重と種子数が増加するため,人工受粉をしたうえで摘花剤と摘果剤を併用することにより,摘果作業を大幅に省力しつつ果実肥大を期待できる.摘花剤単用は摘果剤単用より省力効果があった.
2 0 0 0 OA 長崎唐通事中の異国通事について
- 著者
- 和田 正彦
- 出版者
- Japan Society for Southeast Asian Studies
- 雑誌
- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.9, pp.24-50, 1980-02-25 (Released:2010-03-16)
There were, in the Tokugawa period, offices of interpreters called To-tsuji (Lit. Interpreters of Chinese). Within this category were two divisions; To-tuji To-kata (Interpreters of Chinese) and To-tsuji Shokoku-kata or Ikokutsuji (Interpreters of other Asian Languages). To-tsuji Shokoku-sata or Ikokutsuji included Tonkin-tsuji (Interpreters of Vietnamese), ..... The latter consisted of the Tonkin-tsuji (Interpretes of Vietnamese), Shamro-tsuji (Interpreters for Siamese), Mouru-tsuji (Interpreters of a language used in the Mughals) and Ruson-tsuji (Interpreters of a language used in Luzon under Spanish). This paper traces the history of the Ikoku-tsuji from its establishment to its abolition.It must be pointed out that both divisions, namely To-tsuji Tokata and Ikoku-tsuji were theoretically equal in status, yet, in fact, the latter was regarded as lower than the former. This is clearly shown in the difference in their pay-scales. The discrepancy in their actual position resulted from the differnces in their business. The To-tsuji To-kata was much more important than the Ikoku-tsuji not only because of the fact that only one or two vesseles which came to Nagasaki were from countries other than China, but also, because the To-tsuji To-kata played at the same time the role of commercial agents having discretionary powers of foreign trade. On the other hand the Ikoku-tsuji were no more than interpreters. It should be also taken into account that the To-tsuji To-kata were either Chinese living in Nagasaki or their descendants so that they easily got on good terms with Chinese merchants coming to Nagaski for trade. On the contrary among the Ikoku-tsuji, only the Gi family held the office hereditarily.As the number of vessels requiring Ikoku-tsuji dwindled, the work of the Ikoku-tsuji was gradually transfered to the sections of To-tsuji To-kata or Oranda Tsuji (Interpreters for Dutch). They held only the nominal position through hereditary until the last days of the Tokugawa Shogunate. The position of Ikoku-tsuji was, nevertheless, necesary to the Tokugawa Shogunate. Because of its policy of seclusion, the Shogunate had to be ready to receive and handle exclusively such vessels.It is be worthy of special note that there were some Japanese who studied languages of South and Southeast Asia, wrote the books of vocabulary and conversation of these languages despite it being the age of seclusion.
- 著者
- 和田 健太郎 邢 健 大口 敬
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.1-10, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 27
高速道路ボトルネックでは渋滞発生後の捌け交通量が渋滞発生時容量より低下する現象「Capacity Drop (CD)」が一般的に観測される.この現象は古くから知られているものの,そのメカニズムについては必ずしも明らかになっていない.本研究は,高速道路サグ・トンネル部を対象に近年提案された連続体交通流理論 (Jin, 2018; Wada et al., 2020) に基づき,CD 現象を実証的に分析する.具体的にはまず,従来の CD 現象の仮説と残された課題を明確化した上で,新たな理論の考え方,構成要素,予測される帰結を整理する.そして,理論的に予測される渋滞中の交通流特性と実観測データ(感知器および ETC2.0 データ)を定性的/定量的に照らし合わせることで,理論を検証するとともに,CD 現象に対する従来にない解釈が可能であることを示す.
- 著者
- 和田 健太郎 甲斐 慎一朗 堀口 良太
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.A_1-A_8, 2022-02-01 (Released:2022-02-18)
- 参考文献数
- 15
本研究は,高速道路サグ・トンネルボトルネックを対象として,渋滞発生後の捌け交通量が渋滞発生時容量より低下する現象「Capacity Drop (CD)」の影響を低減する走行挙動を考察する.具体的にはまず,近年提案された連続体交通流理論に基づき 2 種類の CD 回避運転挙動を提案し,その定性的特性について論じる.続いて,提案した挙動を実現する(自動運転)車両の混入率と捌け交通量の低下度合いの関係を理論およびシミュレーションにより定量的に分析する.そして,(i) CD 低減にはボトルネック区間の緩慢な追従走行(i.e., 勾配変化に対する補償遅れ)による速度回復遅れを防ぐことが肝要であること,(ii) ボトルネック下流における加速挙動の改善は一部車両のみではその効果が限定的であること,を明らかにする.
- 著者
- 和田 平悟 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.138-142, 2021 (Released:2021-12-25)
- 参考文献数
- 1
We report a case of left-side hemiplegia due to subarachnoid hemorrhage. When our patient walked with a T-shaped cane, almost no extension and adduction of the left hip joint from the left loading response to the left mid-stance, poor weight transfer to the left lower limb, and instability from the right mid-stance to the right terminal stance due to hyperabduction of the right hip joint were noted. The patient's right hip joint was externally rotated, and the pelvis was left rotated throughout both standing and walking due to internal rotation weakness of the right hip joint. The left hip joint was poorly flexed in the left swing phase due to hypotonia of the left iliacus muscle, and the left lower leg had been swinging out for many years due to left pelvic elevation along with left lumbar flexion. It was necessary to first address the problems of the right lower limb. Left hip extension, adduction, and internal rotation, left ankle dorsiflexion, and left foot supination were absent. In addition, horizontal movement of the pelvis was difficult. An approach improving the left rotation of the pelvis and external rotation of the left lower leg via external rotation of the right hip joint, resulted in extension and adduction of the left hip joint occurring in the middle stage of the left stance, enabling the patient to transfer weight onto the left lower limb.
2 0 0 0 OA メニエール病のイソバイド療法 : 投与法の検討
- 著者
- 徳増 厚二 長沼 英明 橋本 晋一郎 伊藤 昭彦 和田 昌興 岡本 牧人 山根 雅昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.64-72, 2007 (Released:2008-10-10)
- 参考文献数
- 17
Hyperosmotic solution of isosorbide has been used for treatment of Meniere's disease since Kitahara et al., Larsen et al. and Nozawa et al.. In recent studies reported that ADH is acting to open water channels, AQP-2 at the endlymphatic membrane and may act worse for labyrinthine hydrops. It is important the serum concentration of isosorbide after administration because ADH should be released if the serum osmotic pressure is elevated by isosorbide above more than 2% of normal serum osmotic pressure. In this study the equation predicting isosrbide serum concentration after oral administration was proposed on the basis of the data by Wakiya's report. It was confirmed the serum osmotic pressure remains below the threshold level for increasing ADH secretion by the routine method of 30 ml/once, 3 times every day. However, the method of 30 ml/once, single or two times every day should be recommended when the serum osmotic pressure before the medication is above 289 mOsm/kg.
2 0 0 0 アニメキャラクターを活用した観光まちづくり:鳥取県を事例に
- 著者
- 和田 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.17, 2010
日本の観光は近年,物見遊山,団体客,発地型,一過性,通過型などを特徴とする形態から,体験・交流,個人客・小グループ,着地型,持続性,滞在型などを特徴とする形態へと変化してきた。これらの新しい観光は,「見る」「食べる」といった従来からの目的に加え,「体験する」「学ぶ」「癒す」「追体験する」という目的も顕在化している。このうち,「追体験する」ことを主目的とする旅行形態として,小説や映画,テレビ番組,歌,漫画,アニメなど,メディアを介して記録・伝送・鑑賞される映像や画像,音楽,文章などのコンテンツに関わる場所を訪ねるコンテンツ・ツーリズムが盛んになりつつある。本発表では,コンテンツ・ツーリズムの一つとしてアニメキャラクターを活用した観光をとりあげ,鳥取県境港市と同北栄町を事例に,自治体や地元企業,市民・NPOなどの関係機関が観光地づくりにどのように関わっているかという点を中心に報告する。すなわち,2つの事例について,アニメキャラクターを活用した観光まちづくりの実態を報告するものである。 アニメキャラクターを活用した観光まちづくりは,コンテンツの種類および地域との関わりという2つの視点から,いくつかのパターンに分類できる。コンテンツの種類からみると,アニメは商業系アニメ,芸術系アニメ,自生系アニメの3つに分類できる。また,地域との関わりからみると,題材型,ゆかり型,機会型の3つに分類できる。 鳥取県境港市は,漫画家・水木しげる氏が育った地であることに着目して,水木氏の代表作品である「ゲゲゲの鬼太郎」を活用した観光まちづくりを推進している。1992年から商店街(水木しげるロード)に「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する妖怪などのブロンズ像を設置したほか,鬼太郎列車の運行(1993年~),水木しげる記念館の運営(2003年~),各種イベントの実施などにより,水木しげるロードへの入込客数は1994年の約28万人から2008年には約172万人へと大幅に増加した。取組みの中心的役割を果たしたのは,当初は境港市役所であった。その後,商店街にブロンズ像が設置され,集客効果が実感できるようになると,鬼太郎音頭保存会(1996年),水木しげるロード振興会(1998年)など市民活動団体が組織されたほか,境港市観光協会や境港商工会議所も妖怪そっくりコンテストや境港妖怪検定,妖怪川柳コンテストなどユニークなイベントを主催した。また,水木作品(漫画およびその原画)の著作権を保有する水木プロダクションが,水木氏ゆかりの境港市のまちづくりに協力的であったことも,市内の各主体による取組みを後押しした。例えば,水木プロダクションはブロンズ像や記念館展示物のキュレイションを担当したほか,市内事業者が関連グッズを開発する際の著作権使用料を減免するなどした。 鳥取県北栄町は,「名探偵コナン」の原作者・青山剛昌氏が同町出身であることに着目し,1999年から「名探偵コナンに会える町」づくりを推進している。具体的に,1999年にJR由良駅と国道9号を結ぶ県道を「コナン通り」と命名し,7体のブロンズ像を設置したほか,2007年に青山氏の作品や仕事ぶりなどを紹介する「青山剛昌ふるさと館」を整備した。同記念館の入館者数は年間約64,000人(2008年)である。北栄町の取組みは,旧大栄町商工会が提案した「コナンの里」構想をきっかけに,旧大栄町役場が地域振興券に名探偵コナンをデザインしたことに始まる。その後も旧大栄町(2005年から北栄町)が名探偵コナンを冠したイベントを開催したり,観光プロモーションを展開したりした。活動が進展するに従い,町民の活動に対する認知度と参加意欲が高まり,2000年にはコナングッズを販売する「コナン探偵社」が町民有志によって設立された。北栄町では,町役場が漫画の著作権者である小学館プロダクションとの交渉を担当している。小学館プロダクションは,作品のイメージ保持と適切な著作権管理の観点から,著作物使用協議を慎重に行うほか,ふるさと館での展示方法や接客方法について北栄町役場に対してきめ細かく指導している。しかし,こうした慎重な協議ときめ細かな指導は,北栄町にとって時間的・精神的な負担,迅速な観光プロモーションへの障害となっている面があることも否めない。
- 著者
- 勝木 桂子 相原 直彦 伊達 裕 武村 珠子 住田 善之 和田 光代 鎌倉 史郎 下村 克朗
- 出版者
- Japanese Heart Rhythm Society
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.291-300, 1997-05-25 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
心室内伝導障害例での持続型心室頻拍 (SVT) の発生予知に時間解析法による加算平均心電図 (SAEOG) が有用であるかを検討した.SAECGを施行した心室内伝導障害例70例を, 12誘導心電図から右脚ブロック型を示す36例 (RBBB群) と左脚ブロック型を示す34例 (LBBB群) に分類し, SVTの既往の有無 [SVT (+) 群, SVT (-) 群] でSAEOG各指標を検討した.RBBB群ではTQRSD, LAS40, RMS40の3指標とも, LBBB群ではRMS40のみでSVT (+) 群とSVT (-) 群との間に有意差が認められた.SVT (+) 群を分離するための診断基準は, RBBB群ではTQRSD≧160mseo, LAS40≧40mseo, RMS40≦14μVとなり, 川頁に感度77%, 85%, 77%, 特異性78%, 70%, 74%で, LBBB群ではRMS40≦14μVとなり, 感度82%, 特異性87%で良好な診断精度であった.以上より, SAEOG各指標はLPの診断基準を新たに設定することにより, 心室内伝導障害例においてもSVTの予知が可能であると結論される.
- 著者
- 新川 弘樹 井上 孝志 藤田 尚久 野尻 亨 古谷 嘉隆 黒田 敏彦 仲 秀司 安原 洋 和田 信昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.59-63, 2001
- 被引用文献数
- 3
V-P (脳室・腹腔) しゃんとの腹腔側ちゅーぶが直腸に穿通し, 肛門より脱出した稀有な1例を経験したので報告する. 症例は74歳の男性. 他院で脳内出血後の正常圧水頭症に対し, V-Pしゃんとを施行された. 10か月後, 髄膜炎で当院脳外科に入院, 抗生物質投与により軽快していた. 入院3か月後, 肛門よりしゃんとちゅーぶが脱出しているのを発見され, 当科紹介となった. 腹部には圧痛, 腹膜刺激症状を認めず, 白血球数6,400/mm<SUP>3</SUP>, CRP1.9mg/dlと炎症反応は軽度で, がすとろぐらふぃん <SUP>®</SUP>による注腸造影X線検査で造影剤の漏出は認めなかった. 大腸内視鏡検査ではちゅーぶは肛門縁から10cmの直腸右側壁を穿通していた. 腹膜炎所見がないことから, 経肛門的にちゅーぶを抜去した. 1週間後の注腸検査で造影剤の漏出がないことを確認し, 経口摂取を再開した. V-Pしゃんとちゅーぶの消化管穿通はまれであるが, 注意すべき合併症の1つと考えられた.
2 0 0 0 マルチスケール有限要素法による複合体の複素誘電率の計算
- 著者
- 鶴見 敬章 掛本 博文 和田 智志
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.258, 2003
プリント基板内への3次元実装化のためのポリマー/セラミックスコンポジットなどの新しい材料を設計する上で、コンポジットの誘電率を計算する手法が重要になってきている。本研究では、マルチ─スケール有限要素法という新しいソフトを開発した、この計算では、コンポジットの微構造をいくつかの基本単位の集合体と考え、あらかじめ基本単位について有限要素計算を行い、その後、集合体について計算を行う。ポリマー/チタン酸バリウムのコンポジットについて誘電率を計算したところ、チタン酸バリウム粒子の体積分率が60%以上の完全分散体で、電率が得られることがわかった。
2 0 0 0 IR 浅虫温泉と附近の名勝
2 0 0 0 IR 開かれた「窓」への感謝とともに : 法学部・市民講座・『更級日記』
- 著者
- 和田 律子
- 雑誌
- 流経法學 = Journal of the Faculty of Law, Ryutsu Keizai University
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.19-28, 2021-03-10
2 0 0 0 OA 日本におけるおっとせい研究の現状
- 著者
- 和田 一雄
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.2_7-13, 1965 (Released:2008-12-17)
- 著者
- 田上 裕記 生駒 直人 和田 浩成 渡邉 英将 大山 三紀 中井 智博 酒向 俊治 井奈波 良一
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.413-419, 2021
<p>【目的】看護師における労働生産性の実態を調査し,心身の健康に関するワーク・エンゲイジメント,ワーカホリズムおよび腰痛との関係性を明らかにすることを目的とした。【方法】病棟看護師女性73 名を対象とし,無記名自記式のアンケート調査を実施した。調査項目は,労働生産性,ワーク・エンゲイジメント,ワーカホリズム,腰痛の有無,期間とした。【結果】労働遂行能力は,ワーク・エンゲイジメント得点の間に有意な正の相関が認められ,ワーカホリズム得点間において有意な相関は認められなかった。ワーク・エンゲイジメントにおいて,腰痛群は,非腰痛群と比較して有意に低値を示し,ワーカホリズムでは両者に有意差は認められなかった。【結論】非特異的腰痛の有無および労働遂行能力は,ワーク・エンゲイジメントを説明する独立因子であり,ポジティブメンタルヘルスの重要性が考えられた。</p>
2 0 0 0 OA 外来がん患者への継続的な面談による薬剤師の印象変化とその影響因子
- 著者
- 小西 麗子 磯貝 潤一 石川 沙矢香 宮本 廉 和田守 翼 眞島 崇 向井 啓 小森 浩二 伊藤 慎二 河田 興
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-11, 2022 (Released:2022-02-10)
- 参考文献数
- 17
がん患者と薬剤師との信頼関係が構築されるには、面談時における薬剤師の印象が重要である。今回、患者が薬剤師に抱く印象を調査し、薬剤師の継続的な関わりによる印象の変化とその要因について検討した。 対象は、2018年8月から2020年8月に津島市民病院に通院し、初めて外来化学療法室でがん化学療法が導入される患者とした。初回の治療からがん薬物療法認定薬剤師が毎回面談し、初回と5回目の計2回、質問紙により印象を調査した。調査は、愉快さなどの形容詞対を7段階の尺度で評価し、年齢、性別、がん種、Stage、レジメン、有害事象とその対応について電子カルテの記録から収集した。また、予測5年生存率を算出し、患者の属性ごとに各形容詞対の変化を解析した。 14名に対し、3~4か月の間に各5回の指導・面談を行った結果、全体では安定感に関する項目が否定的な印象へ有意に変化した。しかし、年齢、性別、予測5年生存率、有害事象の訴えの有無を患者の属性として印象の変化を比較したところ、女性や有害事象を訴えた患者では、「愉快な」印象へ変化する傾向がみられた(p=0.031、p=0.027)。 がん患者の対応において、5回程度の指導・面談では薬剤師に抱く印象に大きな変化はみられないが、性別や有害事象への対応は印象に影響し、信頼関係構築に十分配慮されるべき要因である可能性が示された。
2 0 0 0 OA Annotated Checklist of Marine and Freshwater Fishes in the Hyuga Nada Area, Southwestern Japan
- 著者
- IWATSUKI Yukio NAGINO Hayato TANAKA Fumiya WADA Hidetoshi TANAHARA Kei WADA Masaaki TANAKA Hiroyuki HIDAKA Koichi KIMURA Seishi 岩槻 幸雄 投野 隼斗 田中 文也 和田 英敏 棚原 奎 和田 正昭 田中 宏幸 日高 浩一 木村 清志
- 出版者
- 三重大学大学院生物資源学研究科
- 雑誌
- 三重大学大学院生物資源学研究科紀要 = THE BULLETIN OF THE GRADUATE SCHOOL OF BIORESOURCES MIE UNIVERSITY
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.27-55, 2017-09
Annotated checklist of marine and fresh water fishes is reported from the Hyuga Nada area, including Miyazaki Prefecture, southern coastal area of Oita Prefecture and eastern coast of Kagoshima Prefecture, southwestern Japan. Such fishes are classified into 228 families, 680 genera and 1,340 species including 24 subspecies and 1 hybrid, consisting of natural inhabitants in the area, and invasive and introduced fishes as alien species out of Japan or from the other areas. Confirmation of each species on identification is based on voucher specimens kept in Miyazaki University and other museums, photographs of fishes taken in the area, confirmed photographs in websites and references formerly reported before August 2016. Fish occurrence tendency by our gross observation is noted at each species.
2 0 0 0 OA 超芸術トマソン再考 : 「不適合に見える」実用品は機能的に美しいという視点から
- 著者
- 和田 寧路
- 出版者
- 成城大学大学院文学研究科美学・美術史専攻
- 雑誌
- 成城美学美術史 = Seijo bigaku bijutsushi : studies in aesthetics & art history (ISSN:13405861)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.45-60, 2020-03-20
2 0 0 0 IR 水俣病とアセチレン系有機合成化学工業
- 著者
- 和田 俊二
- 出版者
- 滋賀大学経済学会
- 雑誌
- 彦根論叢 (ISSN:03875989)
- 巻号頁・発行日
- no.146, pp.24-51, 1970-11
2 0 0 0 仮想社会と現実社会の融合:3D仮想空間「セカンドライフ」を事例に
- 著者
- 和田 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.33, 2009
「セカンドライフ」は,従来のインターネット・サービスと比べて,表現の幅と活動の幅が大きく広がったとされる(山口,2007)。本研究は,「セカンドライフ」にみられる表現の幅と活動の幅の拡大が,従来のインターネット上でのコミュニケ―ションの方法や社会的ネットワークの構造や形成過程,さらにサイバースペースとジオスペースの相互関係をどのように変化させているかという点について論じることを目的とする。3D仮想空間は独自のコミュニケーション環境を持つ空間であり(山口・野田,2008),それを生み出す独自機能として,アバター,チャット,自己組織化,の3点をあげることができる。自己表現,変身願望,着せ替え人形としてアバターは,それ自体を話題にできることや文字以外に表情やしぐさで表現できることから,利用者間のコミュニケーションを活発にする働きがあるとされる。チャットはコミュニケーションの同期性は高いが,情報の蓄積性が乏しい。自己組織化とは利用者の行動と相互作用がその空間構造や社会規範を規定していくことをいう。2001年にプロトタイプが開発され,2003年6月に商用サービスとなった「セカンドライフ」では,上記に加え,仮想空間内の瞬間移動,持ち物の所有・管理,友達の設定,コミュニティの形成,土地の所有,オブジェクトの作成と著作権の付与,仮想通貨リンデンドルの付与および支給,仮想通貨リンデンドルとアメリカドルの交換などの機能・サービスが提供されている。「セカンドライフ」の利用者数は,2006年の約10万人から2007年5月には約650万人に急増した。そのうち日本人の利用者数は約4万人(2007年5月)と言われる。インターネットメディア研究所が2007年に実施した日本人の利用動向調査によると,利用者の年齢は20代後半から30代が中心である。利用者の居住地は関東地方が突出する。職業はほとんどが社会人で,しかもITリテラシーが高いと思われる層の利用が多い。しかし,継続的な利用は初期登録者の1/4程度といわれ,利用が定着しない理由として,全体像がつかみにくいこと,楽しみ方がわかりにくいことなどが指摘されている。その中で,継続的に利用するようになった者は,仮想街の見物,知人や初対面の人とのチャット,買い物,オブジェクトの作成,ダンス,イベント参加など,様々な方法により「セカンドライフ」で長い時間を過ごしている。また,日本人や日本企業の利用を支援する仮想市民ネットワークやコンサルタント企業も存在する。「セカンドライフ」は世界中からアクセス可能で,「セカンドライフ」内では国・地域の境を越えて利用者同士が仮想的に接近・接触したり,コミュニケーションしたりすることができる。そのため,ジオスペースとは無関係に思われる。しかし,次の5点において,「セカンドライフ」にも地理を見いだすことができる。第1は管理区域としての地域(「シム」)であり,設計者が設定したグリッド(緯度経度に相当)がその位置を規定する。第2は「セカンドライフ」内に形成される仮想都市の存在である。AKIBAやOKINAWAといった日本人街の形成も進んでいる。これらは仮想空間に形成される地理といえる。第3はジオスペースの地域コンテンツの発信である。自治体や観光協会などが観光情報を提供するとともに,仮想体験を通じて,集客や販売の促進に結びつけようとしている。第4は特定地域の課題解決に向けた国や地域の境を越えた協力活動である。新潟県中越地震に関する募金活動などがその例である。第5は「セカンドライフ」内での対人関係の形成とジオスペースでの地域単位でのイベント開催である。これらはジオスペースにおける地理を反映している。このように,「セカンドライフ」にみられる地理は,仮想社会(サイバースペース)と現実社会(ジオスペース)が入り交じったものとなっている。また利用者は,仮想経験とジオスペースでの行動,およびそれぞれをベースとした2種類のコミュニケーションを展開している。