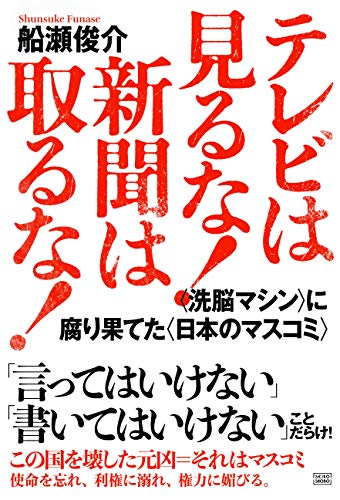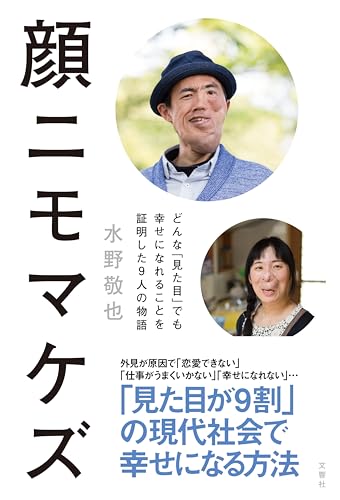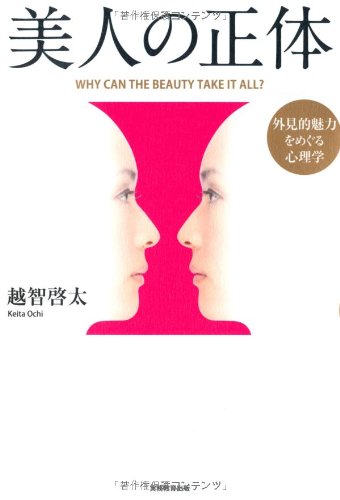1 0 0 0 OA Capillary gingival hemangioma in a cat
- 著者
- Se Eun KIM Na-Young LEE Jeong-Seop OH Dae-Yong KIM
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-0311, (Released:2023-10-26)
A 12-year-old spayed female American short-haired cat presented with a palatal gingival mass located between the right maxillary third incisor and the canine teeth. The mass was dark red and had a narrow attachment to the gingival margin of the canine tooth. The mass was completely removed by marginal excision and the histopathological diagnosis was a capillary hemangioma. The mass did not relapse until 1 year later; however, the tooth was extracted because of cervical resorption of the right maxillary canine immediately adjacent to the mass resection site. This report presents a rare case of the gingival hemangioma in a cat and the possibility of a causal relationship between the occurrence of external cervical tooth resorption and hemangioma resection.
1 0 0 0 OA 17)急性大動脈解離の診断と治療に関する最新知見
- 著者
- 吉野 秀朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.9, pp.2031-2038, 2015-09-10 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 吉田 大地 細川 清人 北山 一樹 加藤 智絵里 小川 真 猪原 秀典
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.223-232, 2021 (Released:2021-08-26)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2 2
Acoustic Voice Quality Index(AVQI)は持続母音と文章音読の両者の録音音声を用いた音響分析手法であり,日本語においても高い診断性能が報告されている.しかしながら,文章音読の課題文が異なれば診断性能が損なわれる可能性がある.そこで当研究では,課題文の変更による診断性能への影響を調査した.全311録音について,「北風と太陽」の第2文までの計58音節を既報で使用された前半30音節と検証用の後半28音節に分割しそれぞれのAVQI値を求めた.聴覚心理的評価との相関係数はそれぞれ0.850および0.842,受信者操作特性曲線の曲線下面積はそれぞれ0.897および0.892であり,ともに良好な診断性能が確認された.また,両者の値の差はわずかであった.当検討における課題文の変更はAVQI値の変動に大きな影響を与えず,AVQIは課題文変更をある程度許容できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 『ロウソクの科学』を用いた三読法による燃焼の指導 ―科学のテクスト読解としての理科学習―
- 著者
- 比樂 憲一 遠西 昭寿
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.155-162, 2023-11-30 (Released:2023-11-30)
- 参考文献数
- 20
本研究は,小学校第6学年「燃焼の仕組み」に,『ロウソクの科学』(ファラデー,2012)のテクストの一部を用い,三読法(石山,1973)による解釈的読みによって,「炭素と酸素の結合による二酸化炭素の生成」を理解させることを試みた実践的研究である。児童はテクストに科学的な問題を発見し,理論,実験方法,得られる結果を読み取りながら有意味に実験を行うことができた。また,実験の成功から理論を確証することでテクストの読みを確かにすることができた。ここでは,粒子モデルを導入して「炭素と酸素の結合」をイメージさせる指導がテクストの読解を支援した。また,テクストの中心的な内容を児童実験で,補足的な内容を演示実験で行うことで,燃焼単元の標準時間内に本実践を組み込むことができた。児童は科学のテクスト読解により「炭素と酸素の結合」を理解することができた。
1 0 0 0 OA 当院における、LUCAS2自動心臓マッサージ装置導入前後でのCPA搬送症例の転帰比較検討
- 著者
- 酒井 久司
- 出版者
- 日本蘇生学会
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.237a, 2018-10-31 (Released:2018-12-28)
PDFファイルをご覧ください。
1 0 0 0 OA 木材の硫化水素型高温温泉水による改質
- 著者
- 佐々木 陽 久保田 史 高橋 亨 梅津 芳雄 成田 榮一 森 邦夫
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子論文集 (ISSN:03862186)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.316-324, 1997-05-25 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
硫化水素型合成温泉水 (湯花の抽出溶液) を用い木材を長時間煮沸処理すると, 蒸留水で処理した場合よりも, 重量の減少が大きく, 空隙率の高い木材が得られた. その時の抽出溶液を液体クロマトグラフで分析した結果, 針葉樹ではアラビノース, キシロースが, 広葉樹ではキシロースが確認され, いずれも合成温泉水処理した溶液で顕著に認められた. 抽出された糖類は木材の非晶部分であるヘミセルロースが加水分解されたもので, 合成温泉水処理によりさらに分解が進んだ結果と考えられる. スギの100時間煮沸処理では, ホロセルロースが蒸留水の場合約18%, 温泉水の場合22%減少し, また, リグニンはこれらの処理において, 見かけ上前者で18%, 後者で20%増加していることから, 熱水処理によるリグニンの分解溶出は認められなかった. 合成温泉水処理により, 水溶性の非晶部分が加水分解されるため, 水に対する木材の膨潤性が改善され, 寸法安定に優れた木材が得られることが分かった.
1 0 0 0 OA グルタミン酸受容体抗体の意義
- 著者
- 高橋 幸利
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.99-105, 2013 (Released:2014-10-11)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 7
非ヘルペス性急性辺縁系脳炎を代表とする神経細胞表面抗原に対する自己抗体の関与する脳炎では比較的予後が良いとされる. 非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の抗NMDA型glutamate receptor (GluR) 抗体は, NMDA型GluRの内在化により脳炎症状を起こすと考えられているが, シナプス外NMDA型GluRの内在化により, グルタミン酸などによるGluR活性化—アポトーシス (興奮毒性) を抑制, 予後を改善している可能性がある. シナプスのNMDA型GluRは内在化されにくく, cAMP-response-element-binding-proteinリン酸化が保持され, 細胞生存が可能となっている可能性がある.
1 0 0 0 OA 双極性障害の診断と薬物治療
- 著者
- 久住 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.707-712, 2020 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 16
双極性障害は, うつ症状で発症することが多く, 初発時に単極性うつ病と鑑別することは容易ではない. しかし, その治療は後者では抗うつ薬が使われるのに対し, 前者では気分安定薬が用いられ, 抗うつ薬の併用は無効なばかりか, 気分変動を不安定化する. 双極性うつ病と単極性うつ病を鑑別する際に, Ghaemiが提唱した双極スペクトラム障害の概念は有用である. 特に双極性障害の家族歴や抗うつ薬によって惹起される軽躁・躁症状がある場合には, 発揚性パーソナリティ, 若年発症, 反復性の大うつ病エピソード, 短い大うつ病エピソード, 非定型うつ症状, 精神病性うつ病, 産後うつ病, 抗うつ薬の効果減弱, 抗うつ薬治療への非反応などの双極性障害を示唆する徴候 (bipolarity) を注意深くとらえることで, 潜在する双極性障害を見つけ出すことが可能になる.
1 0 0 0 OA ヒト脳の側性化と臨床 ―言語と空間性注意の神経ネットワーク―
- 著者
- 石合 純夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.182-191, 2022-02-18 (Released:2022-04-13)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA Vocal cord dysfunction に対する口すぼめ吸気法
- 著者
- 丸山 裕美子 塚田 弥生 平井 信行 中西 庸介 吉崎 智一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.1, pp.53-61, 2015-01-20 (Released:2015-02-05)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
Vocal cord dysfunction (VCD) における声帯奇異運動は一般的に一過性かつ発作性である. われわれは36例の VCD 加療経験の後, 持続的に声帯奇異運動を認める症例を経験し, 声帯奇異運動が「口すぼめ吸気法」施行中に改善し呼吸法中止により再発することを確認した. VCD は気道刺激に対する声門閉鎖反射亢進と, 吸気時の声門下陰圧に対する能動的声帯内転運動により生ずると考えられている. 今回われわれが初めて提唱した「口すぼめ吸気法」は, 緩徐な吸気の実現を容易にし, 声門上腔の陰圧化により声門上下腔の気圧差を減少でき, 器具を用いず即実行できる簡便な方法であり, VCD に対し試行する価値があると考える.
1 0 0 0 OA 南京虫の話 (二)
- 著者
- 戸田 亨
- 出版者
- 社団法人 大阪生活衛生協会
- 雑誌
- 家事と衛生 (ISSN:18836615)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.7, pp.19-22, 1931-07-01 (Released:2010-10-13)
1 0 0 0 OA 看護技術のイノベーションの普及 ―日本における褥瘡ケアの普及過程から―
- 著者
- 佐々木 杏子
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.4-13, 2014-01-20 (Released:2016-07-08)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
本研究は,看護技術のイノベーションといえる褥瘡ケアの日本における普及過程を,文献レビュー,普及を裏付ける資料,インタビュー調査により明らかにし,その結果をロジャーズのイノベーション普及理論に基づき分析を行い,普及に影響した要因を明らかにする事例研究である.褥瘡ケアの普及の第一の促進要因として,課題とする現象に深く関心を寄せ活動を行う複数のチェンジ ・ エージェントの存在があげられた.チェンジ ・ エージェントを核として,現場で技術を示すことのできるローカルオピニオンリーダーが多数存在し実践活動を行っていること,マスメディアや学会等をはじめとするさまざまなコミュニケーション ・ チャンネルを有効活用したことも普及に関連した.また,イノベーションの科学的根拠を蓄積する研究が,基礎研究も臨床研究も積み重なっていなければならないことも示された.褥瘡ケアに特有な要因として,長年の褥瘡ケアへの不全感,成果が目に見えることがあげられた.
1 0 0 0 OA 小児マイコプラズマ肺炎の回復期に対する麻杏甘石湯の効果
- 著者
- 宮崎 瑞明
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.535-540, 1994-04-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
平成4~5年に当院で経験した小児マイコプラズマ肺炎で, CRPが陰性化するまで西洋薬を投与し, この時点で咳嗽と口渇の認められた19例に麻杏甘石湯エキスを1日2~3g投与したものを漢方併用群とした。千葉市立海浜病院小児科の西洋薬で治療した小児マイコプラズマ肺炎の軽症例16例を西洋薬治療群とした。使用抗菌剤はリカマイシン, 又はミノマイシンの内服で, 診断はペア血清のマイコプラズマ抗体価 (CF, HA) 4倍以上を基準とした。漢方併用群は全例, 麻杏甘石湯2~4日の投与により咳嗽が消失した。漢方併用群の平均抗菌剤投与日数は7.1±1.3日, 平均咳嗽消失日数は10.2±1.2日であり, 西洋薬治療群のそれぞれ10.8±2.0日, 12.3±4.7日と比べ短かった (P1<0.0001, P2=0.06)。小児マイコプラズマ肺炎の回復期にみられる咳嗽, 口渇を麻杏甘石湯の主証と一致すると考え, 本方投与によりこれらの症状が改善した。麻杏甘石湯がマイコプラズマ肺炎の咳嗽に有効であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 無線LAN規格による端末同時接続性能差について
- 著者
- 浜元 信州 井田 寿朗 齋藤 貴英 小田切 貴志 綿貫 明広 横山 重俊
- 雑誌
- 研究報告インターネットと運用技術(IOT) (ISSN:21888787)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020-IOT-50, no.8, pp.1-8, 2020-07-03
群馬大学では,2020 年 4 月に全学無線 LAN システムの更新を行なった.本更新で無線 LAN アクセスポイントを全学的に増設したが,教室や会議室などの無線 LAN 導入の際には,アクセスポイント当たりの接続台数を算定することが必要となる.このため,本学の教育用端末を利用し,アクセスポイントに同時接続を行い評価試験を行なった.評価試験の結果,平均速度は,端末数 N の関数として,IEEE802.11n で 2.4GHz の場合には 60.261/N[Mbps],5GHz の場合には 148.26/N[Mbps],IEEE802.11ac の場合 181.64/N[Mbps] となった.また,1 アクセスポイントあたりの接続台数は,平均速度分布の歪度が正になることを条件とした結果,IEEE802.11n で 2.4GHz 接続で 12 台程度,5GHz の接続で端末数 30 台程度,IEEE802.11ac の場合は端末数 36 台程度と考えられることがわかった.
1 0 0 0 OA 肥後熊本藩の宝蔵院流
- 著者
- 石川 哲也
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.Supplement, pp.10, 2006 (Released:2012-11-27)
1 0 0 0 OA アルゴリズム化基準による高頻度取引(HFT)の特性分析
- 著者
- 大山 篤之 津田 博史
- 出版者
- 一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会
- 雑誌
- ジャフィー・ジャーナル (ISSN:24344702)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.55-69, 2022 (Released:2022-06-08)
- 参考文献数
- 4
本研究では,HFTの実態を把握すべく,東証の板再現データ(2010年1月から2015年9月までの全数調査約256億件の注文情報)からHFT業者の日本市場への参入の軌跡や,市場シェア,取引スタイル等を分析した.先行研究では,コロケーション経由に基づくHFT判定が主流であったが,各仮想サーバに対して,これまで行われなかった膨大な注文情報を細かく集計する探索型の分析を通じて,①手動注文と成行注文が顕著に含まれない仮想サーバと含まれる仮想サーバに分類された点,②HFT特有の高頻度性を有する仮想サーバが前者であるという点の2つの新たな知見が得られた.そこで,本研究では,この新たな知見に基づきアルゴリズム化基準(「取引自動化」と「仮想サーバの専有」を基準とした『アルゴリズム化基準』)を提案することで,これまで把握されてこなかったHFTの全貌や実態を下記通り明らかにすることができた.(1)この提案したアルゴリズム化基準によって,典型的なHFT(高頻度かつ高速の注文を行う者)の取引グループを捕捉できた,(2)特に,2014から2015年の観察期間では,仮想サーバの約65%,注文総数の約70%,売買代金の約45%がHFTによって占められていること,(3)HFTはザラバで注文を行う一方,信用取引を行わないこと,(4)IOC注文を行うのは,HFTの中でも特にアルゴリズム化度合が高いグループに限定されること,(5)HFTの中でも特にアルゴリズム化度合及び高頻度性の双方が高いグループで,空売り注文を駆使し,マーケットメイク(メイク注文が多くテイク注文が少ない)を行っていること,がそれぞれ判明した.
1 0 0 0 美しさという神話
- 著者
- リタ・フリードマン著 常田景子訳
- 出版者
- 新宿書房
- 巻号頁・発行日
- 1994