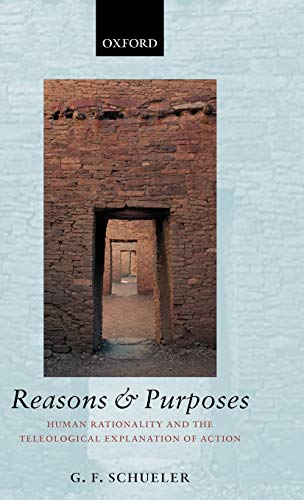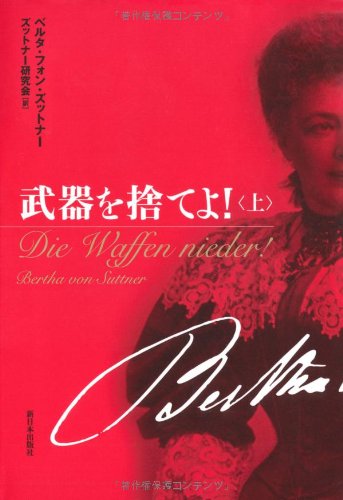- 著者
- 飯尾 哲司 藤岡 成美 舟橋 弘晃 間野 義之
- 出版者
- 日本スポーツ産業学会
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.1_63-1_73, 2023-01-01 (Released:2023-01-23)
- 参考文献数
- 22
Why do athletes choose to become second-career teachers? This qualitative research explores the factors influencing elite athletes’ choice of becoming a teacher after retirement. Semi-structured interviews were conducted with ex-professional athlete teachers (7 baseball players and 7 football players) to discuss the reasons for career choice and factors influencing their decision. The data, which were recorded, transcribed and analyzed through the application of principles from Grounded Theory, resulted in 20 concepts in 9 categories. Examples of categories include achievement of a stable livelihood, desire to remain involved in their sports, and influence of significant others. Ex-professional baseball players samples “needed” to become teachers in post-retirement to lead high school club activities due to the former student baseball eligibility restoration system. Meanwhile, former J. League players tended to become teachers to secure a stable future for themselves.
- 著者
- João M. Santos Sara Pereira Diana B. Sequeira Ana L. Messias João B. Martins Henrique Cunha Paulo J. Palma Ana C. Santos
- 出版者
- Nihon University School of Dentistry
- 雑誌
- Journal of Oral Science (ISSN:13434934)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.171-177, 2019 (Released:2019-03-28)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 13 31
This study evaluated the biocompatibility of a new silicone-based sealer (GuttaFlow Bioseal) in rat subcutaneous tissue and compared the results with those for GuttaFlow2 and AH Plus. Each of 16 Wistar rats received four subcutaneous tissue implants, namely, GuttaFlow Bioseal, GuttaFlow2, AH Plus, and one empty polyethylene tube. Eight rats were euthanized at day 8 and the remaining eight at day 30. Histological sections were stained with haematoxylin and eosin and analysed with a light microscope. Scores were established for inflammatory reaction, macrophage infiltrate, thickness of the fibrous capsule, and vascular changes. Differences between groups were assessed by using the Friedman test with Bonferroni correction. Histological analysis showed that GuttaFlow Bioseal had the lowest inflammatory reaction of all tested sealers at day 8. At day 30, the silicone-based sealers had similar inflammation profiles, but inflammation scores were nonsignificantly higher for AH Plus than for the negative control. The inflammatory reaction decreased from day 8 to day 30 in all sealers. GuttaFlow Bioseal had the most macrophage infiltrate. Under the present experimental conditions, GuttaFlow Bioseal induced limited inflammatory reactions at days 8 and 30, and initial inflammatory reactions to GuttaFlow2 and AH Plus subsided within 30 days. All tested sealers exhibited satisfactory biocompatibility at day 30 after subcutaneous implantation.
1 0 0 0 OA 大気汚染と酸性霧の形成
1 0 0 0 OA 霧が大気汚染物質の挙動に与える影響についての数値シミュレーションによる解析
- 著者
- 井上 和也 安田 龍介 池田 有光
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.282-301, 2002-09-10 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 28
霧が発生すると, 可溶性の物質は霧に溶け込み, 更に液相で化学反応を受けるなどして影響を受けることはすでに良く知られている。しかし, 霧が存在することによる大気汚染物質の挙動への影響はこれだけではないと考えられる。すなわち, 霧が生じることにより大気の成層状態が変化し, 乱流拡散能が変化することを通して, 大気汚染物質の物理的な挙動も影響を受けると考えられる。本研究では, 霧が存在することによる大気汚染物質の挙動への影響, 特に地表面への沈着量への影響について, 気象モデル, 沈着モデル, 液相化学モデルを組み合わせて数値シミュレーションを行うことにより調べた。対象とした期間は霧が頻発する夜間である。本研究で得られた主な結果は以下の通りである。(1) 霧が発現すると, 大気成層状態は霧層下層で不安定化, 霧層上部で安定化することが確認された。(2) 地表面への沈着量は, 霧への溶解や液相での酸化反応などしない物質でさえも (1) の効果によって増大する。(3) 総硫黄成分の沈着量も, 霧が出現する場合には増大し, 特に, 硫酸イオンの沈着量は, 霧粒への溶け込みや液相酸化反応などの影響に (1) の効果も加わり, 数十倍程度大きくなる。得られた結果は, 大気汚染物質の沈着量を推定する際には, 霧水による沈着, また, 霧が作り出す温度環境のもとで沈着が増大する効果も適切に取り入れる必要があることを示唆した。
1 0 0 0 OA <論文>プラグマティズムから見た進化論と宗教の関係
- 著者
- 林 研
- 出版者
- 大阪経済法科大学21世紀社会総合研究センター
- 雑誌
- 21世紀研究 = Bulletin of Centre for Research on 21st Century Society (ISSN:24327042)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.29-41, 2021-03-31
1 0 0 0 An Overview of CO2 Mitigation Options for Global Warming—Emphasizing CO2 Sequestration Options
- 著者
- Akihiro Yamasaki
- 出版者
- The Society of Chemical Engineers, Japan
- 雑誌
- JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN (ISSN:00219592)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.361-375, 2003 (Released:2004-02-21)
- 参考文献数
- 114
- 被引用文献数
- 244 295
CO2 mitigation options have been overviewed from an engineering point of view. There have been proposed a number of mitigation options, which can be divided into three categories; 1. reduction of energy intensity; 2. reduction of carbon intensity; 3. carbon sequestration. In this review paper, various mitigation options are reviewed focusing on the carbon sequestration options.A reduction in energy intensity is essentially an energy saving. A reduction in carbon intensity could be achieved by switching to energy resources with lower carbon contents. Based on the 2001 IPCC report, the mitigation potential related to energy intensity is estimated at 1, 900–2, 600 Mt-C/year in 2010, and 3, 600–5, 050 Mt-C/year in 2020, including other greenhouse gas equivalents. There are additional benefits in implementing these options; they are economically beneficial, and have no associated harmful effects. The carbon sequestration options can be divided into two categories; the enhancement of the natural sinking rates of CO2, and a direct discharge of anthropogenic CO2. The relevant sequestration options in the first category include terrestrial sequestration by vegetation, ocean sequestration by fertilization, and an enhancement of the rock weathering process. In the direct discharge options, the CO2 produced from large point sources, such as thermal power stations, would be captured and separated, then transported and injected either into the ocean or underground. Although the sequestration options are less beneficial in terms of cost per unit CO2 reduction compared to other options, technical developments in sequestration options are necessary for the following reasons; 1. A huge potential capacity for carbon sequestration, 2. carbon sequestration enables a continuous use of fossil fuels, which is unavoidable at the moment, before switching to renewable energy sources. Each sequestration option has advantages and disadvantages in terms of capacity, cost, the time scale of the sequestration, the stability of sequestered CO2, and additional environmental impacts, which depend on the location, time, and amount of sequestration. Thus, reliable evaluations of the mitigation efficiency are essential for each sequestration option upon implementation.
1 0 0 0 OA ヒトの脳の巨視的構造と機能の発達
- 著者
- 多賀 厳太郎
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.23-27, 2013-03-05 (Released:2013-05-17)
- 参考文献数
- 39
胎児期から乳児期にかけて,ヒトの脳のマクロな構造と機能がどのように発達するのかについて,実証的な知見が蓄積されてきた.自発活動とネットワークの形成過程に注目し,脳の発達とヒトの行動発現の原理について議論する.
1 0 0 0 OA 軽種馬における「生産過剰」の構造 : 日高地方における軽種馬生産の研究(5)
- 著者
- 岩崎 徹 進藤 賢一 イワサキ トオル シンドウ ケンイチ Toru Iwasaki Ken-ich Shindo
- 雑誌
- 経済と経営
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.747-774, 1993-03-31
- 著者
- G.F. Schueler
- 出版者
- Clarendon Press
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 事故航空機の自立誘導制御技術の開発と模型実験の研究
事故や故障が発生した場合の航空機の安全な自立的誘導制御技術を研究するとともに、飛行試験を模型航空機で実験する方法の研究を推進するのが本研究の目的である。事故や故障が発生した場合に、機体の姿勢を自動的に安定化する方法に関しては、本年度はニューラルネットワークによるフィードバック誤差学習法を研究し、シミュレーションならびに実機飛行試験によってその有効性を確認した。その結果は、飛行機シンポジウム(日本航空宇宙学会)、交通・物流部門大会(機械学会)において発表し、H18年8月開催予定の誘導制御シンポジウム(米国航空宇宙学会)で講演する。模型飛行機実験に関しては、ラジコン機の製造・飛行を実施し、指定したウェイポイントを自動で飛行する自律飛行試験に成功した。また、携帯電話回線を利用したデータ通信による飛行制御にも成功した。その成果は新聞、TVでも紹介された。模型飛行機の製作と実験に関しては、教育的効果も高いので、他の研究室、専攻も参加する研究科内の研究会プロジェクトを立ち上げ、活動を開始し、本年度は第1回全日本学生室内飛行ロボットコンテストを日本航空宇宙学会の主催により開催した。
1 0 0 0 OA 種子島と奄美大島から得られた薩南諸島初記録のヨウジウオ科タニヨウジ
- 著者
- 橋本 慎太郎 是枝 伶旺 古
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.9-13, 2023-02-07 (Released:2023-02-08)
1 0 0 0 OA 衝撃によるねじの締付け
- 著者
- 玉置 正恭
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.343-347, 1983-03-05 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
Few research works have been reported so far on the tightening of bolted joints by means of successive impacts, whereas the impact-wrenching is one of the most practical methods for the tightening of bolted joints. The process of the tightening of bolted joints by means of the swinging hammer is analysed and the theoretical results are compared with the experimental data. The substantial agreements between the theory and the experiment are confirmed. The results are summarized as follows. (1) The clamping force by an impact of the swinging hammer is concerned in the square root of the available energy of the hammer. (2) The increase of clamping force by an impact depends not only on the available energy of the hammer but also the existing clamping force just before the impact and the stiffnesses of the bolt and the clamped parts. (3) The clamping force by successive n impacts is proportional to √n·F1, where F1 is the initial clamping force.
1 0 0 0 OA 『ブッデンブローク家の人々』とプロテスタンティズム
- 著者
- 高山 秀三
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.57-89, 2022-03-31
トーマス・マンは信仰の人ではなかったが,その作品にはキリスト教的なモチーフが多く取り扱われている。マンにとって,キリスト教はヨーロッパ文化の根底にあるものとして生涯をとおして大きな関心の対象だった。『ブッデンブローク家の人々』はプロテスタンティズムを精神的基盤とするドイツの市民社会を舞台とする小説であり,マンにとってはじめて本格的に宗教を取り扱うことになった作品である。この小説では,市民社会のなかでプロテスタンティズムが息づいている様相が,人々の具体的な生活を通して活写されている。舞台となっている時代は大きな社会変動の時代であり,プロテスタンティズム信仰の衰退期でもあった。『ブッデンブローク家の人々』は資本主義の進展や教養市民層の興隆などの社会変動に対応できないままに,信仰を失っていった伝統的な市民家族の四代にわたる没落の歴史である。本論はこの一族の没落と信仰喪失の過程に焦点をあてている。
1 0 0 0 OA 研究展望 作家と文学賞 文学の価値はいかに創出されるのか
- 著者
- 野中 潤
- 出版者
- 昭和文学会
- 雑誌
- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.85-87, 2013 (Released:2022-11-19)
- 著者
- 長瀬 美樹
- 出版者
- The Kyorin Medical Society
- 雑誌
- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.147-152, 2022-12-28 (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 6
杏林大学医学部肉眼解剖学教室は,良医の育成に役立つ解剖学教育を目指している。解剖学実習では,本学で開発した,ホルマリン・フリーで組織や関節の柔軟性が保たれるピロリドン固定法を用いて,「臨床手技を体験しつつ当該部位の構造を学ぶ」という新しいスタイルの解剖学特別実習の実現に向けて検討を重ねてきた。そして2022年度,麻酔科学教室と連携して解剖学実習にご遺体を用いた気管挿管ハンズオンセミナーを導入し,気管挿管手技を全学生に体験してもらうと同時に,口腔側からみた喉頭の構造を理解してもらうことができた。また,医学部と保健学部のコラボレーションにより解剖体のオートプシーイメージングに着手し,解剖学実習に全身CT・脳MRI画像を取り入れる「解剖学実習と医用画像読影の統合的教育」を開始した。この取り組みにより,人体構造の三次元的理解が深まり,CTとMRIの正常画像を系統的に学ぶ機会が得られ,学習意欲の向上につながっているようである。今後,医用画像読影能力の高い学生・医師の育成に役立つことを期待している。いずれも先進的な取り組みであり,今後改良を重ね,よりよい解剖学教育を実践していきたい。
1 0 0 0 血液疾患に合併した新型コロナウイルスオミクロン株感染症の転帰
- 著者
- 萩原 政夫 林 泰儀 中島 詩織 今井 唯 中野 裕史 内田 智之 井上 盛浩 宮脇 正芳 池田 啓浩 小沼 亮介 熱田 雄也 田中 勝 今村 顕史
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.3-8, 2023 (Released:2023-02-11)
- 参考文献数
- 19
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)オミクロン株流行期において,当院血液内科外来通院中に感染し,発症した11症例について報告する。化学療法が施行中の5例中4例が中等症-II以上となり,内2例はその後重症化し死亡に至った。一方で未施行の6例では1例のみが中等症-IIに進行するも重症化は免れ,残り5例は軽症から中等症-Iに留まった。モノクローナル抗体治療薬が発症から8日以内に投与された4例は全て生存し,投与がされなかった1例と投与が遅れた1例はSARS-CoV2 IgG抗体価が低値のまま死亡に至った。変異株の中では比較的重症化率の低いとされるオミクロン株の感染においても血液悪性疾患,特に化学療法によって免疫不全状態にある場合の重症化リスクは依然として高く,特異抗体の獲得が不十分あるいは大幅に遅延することがあり得るため,抗ウイルス薬に加えて積極的な抗体療法が予後を改善する可能性がある。
1 0 0 0 武器を捨てよ!
- 著者
- ベルタ・フォン・ズットナー著 ズットナー研究会訳
- 出版者
- 新日本出版社
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 OA ゴボトの一夜
- 著者
- 森 孝晴 劉 鵬 モリ タカハル リュウ ホウ Takaharu Mori Peng Liu
- 出版者
- 鹿児島国際大学国際文化学部
- 雑誌
- 国際文化学部論集 = The IUK journal of intercultural studies (ISSN:13459929)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.109-121, 2022-09
1 0 0 0 OA 田代安定の台東調査と『台東殖民地予察報文』
- 著者
- やまだ あつし
- 雑誌
- 人間文化研究 = Studies in Humanities and Cultures (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.149-166, 2022-07-31
台湾大学にある田代安定の蔵書と手書き資料は現在、田代安定文庫として外部公開されており、手書き資料はWEB 上の画像として閲覧することができる。しかしながら田代の筆跡は読み辛く、従来の研究は手書き資料群をまとまって読み解いてはいない。本論は、田代の台湾総督府民政局殖産部拓殖課での活動でも、特に『台東殖民地予察報文』と関係の深い台東について記載された、19 世紀末作成の手書き資料群をまとまって読み解く試みである。それによって、田代の調査と報告書編集の過程、そして成果物である『台東殖民地予察報文』の問題点を明らかにする。本論に関係する田代の手書き資料群は、フィールドノートと収集文書に分かれていた。フィールドノートは、台東に居住するピュマ族やアミ族等の言語に関する語彙ノートの系統と、調査日誌の系統とに分かれる。収集文書は、当時の台東の民政機構が収集した資料を田代らが書き写したメモと、田代自ら収集し分析した調査データ、および報告書類がある。収集文書のデータは後に報告書類とともに『台東殖民地予察報文』としてまとめられたが、当初の調査の重要部分であった「原野」の記述が『台東殖民地予察報文』ではばっさり削られるなど、手書き資料群が『台東殖民地予察報文』にまとめられるまでに大幅な改編があった。『台東殖民地予察報文』で述べられた構想に限らず、田代の構想が当時の台湾総督府首脳部に取り上げられることは少なかった。『北海道殖民地撰定報文』など同種目的の報告書と『台東殖民地予察報文』の細部とを読み比べると、田代の計画の細部は、現実の殖民地開拓では成功し得ない構想が多い。それが恐らくは田代の構想が首脳部に取り上げられなかった理由であろう。