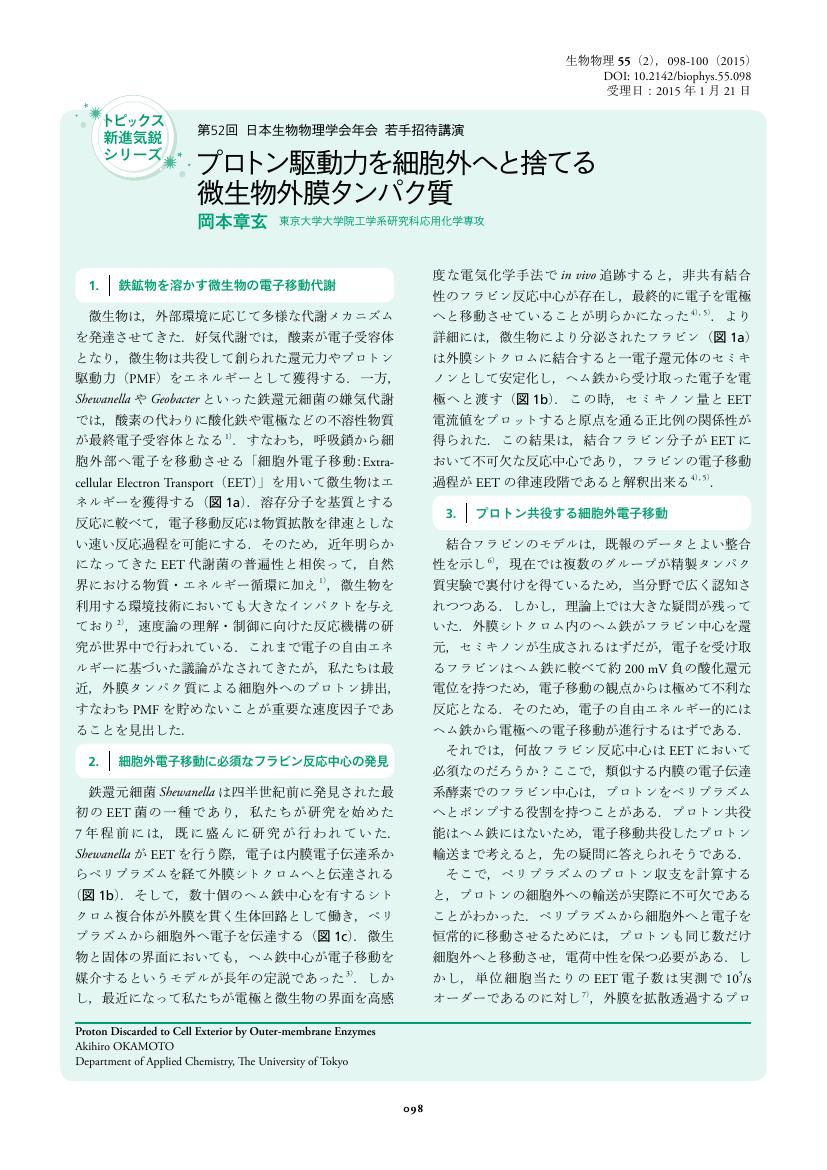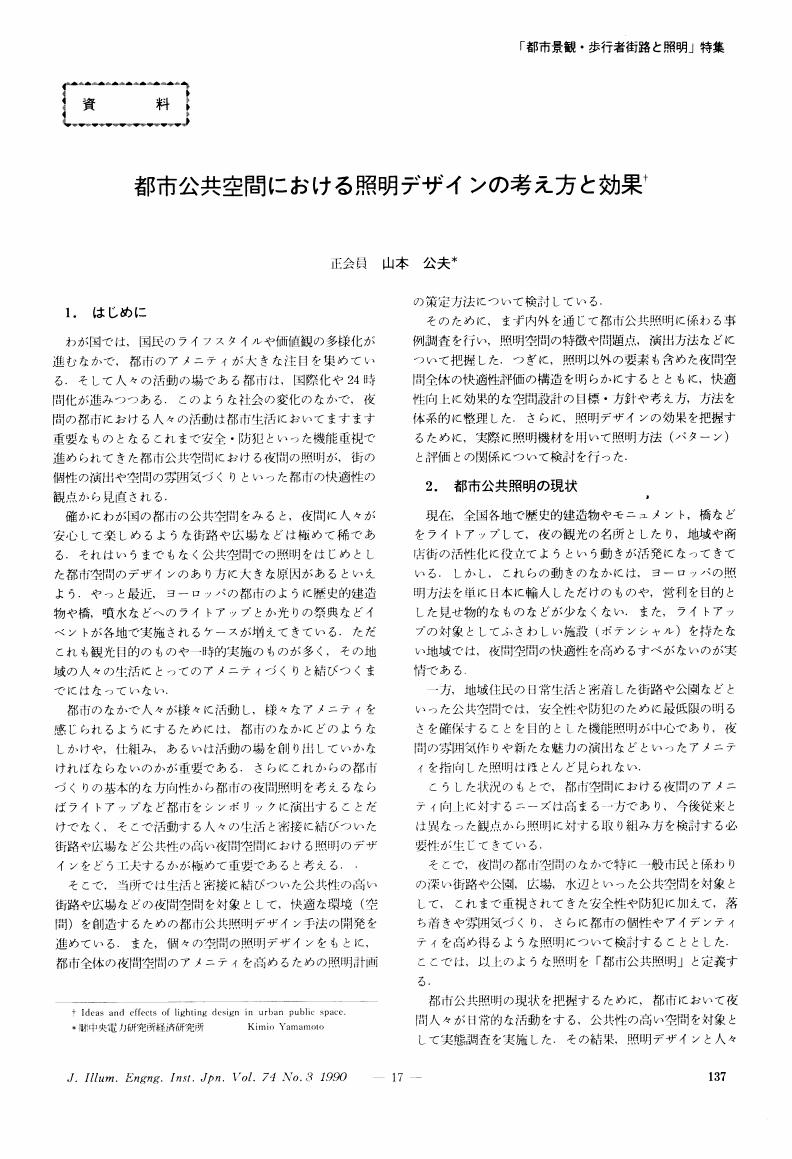1 0 0 0 OA 心理社会的治療法 ―SST,認知機能改善療法,心理教育―
1 0 0 0 OA アイヌの酒 (12)
- 著者
- 加藤 百一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.10, pp.873-877, 1970-10-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 14
アイヌの手によってついに栽培されなかった米を原料とした酒が, どうしてアイヌ・モシリの人々になじまれ, さらに近世の (アイヌの酒) となったか, この課題を解決するためには16世紀中期以降の蝦夷地における和人の進出, 交易の姿から見極めねばならない。本稿においては蝦夷地に渡った和酒について記述されている。
1 0 0 0 OA プロトン駆動力を細胞外へと捨てる微生物外膜タンパク質
- 著者
- 岡本 章玄
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.098-100, 2015 (Released:2015-03-31)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 脳血管障害片麻痺患者に対するロボット型短下肢装具のリハビリテーション介入効果の検討
- 著者
- 川北 大 飯田 修平 内藤 秋光 藤田 拓也 小瀧 敬久 佐藤 絵美 岡田 雄大 池田 喜久子 玉利 光太郎 阪井 康友
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.56-62, 2023 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 28
〔目的〕回復期の片麻痺患者に対してロボット型短下肢装具(R-AFO)を用いたリハビリの効果を検討すること.〔対象と方法〕対象は24名の脳血管障害片麻痺患者.介入期間は10日間で,評価は介入前,介入後の2回実施した.R-AFO群は,通常の理学療法練習60分と,R-AFOを使用した起立や歩行練習を20分の計80分間,非実施群は,通常の理学療法練習を80分間行った.〔結果〕通常群よりもR-AFO群で有意に効果が認められた項目は,歩行速度,麻痺側片脚支持時間,片脚支持時間の左右対称性割合,機能的自立度評価法(FIM)であった.〔結語〕R-AFO装着下での麻痺側に荷重を促す歩行訓練を反復して行ったことで,麻痺側片脚支持時間の割合の増大による,歩行左右対称性の改善効果を有する可能性を示唆した.
1 0 0 0 OA 「外が濱」の敵討 : 『武道伝来記』の空間性(<特集><近世>という空間)
- 著者
- 大久保 順子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.14-21, 2004-10-10 (Released:2017-08-01)
モデルとされる敵討事件説話の「實」と異なる「虚妄の説」として椋梨一雪の批判を浴びた井原西鶴の『武道伝来記』は、先行作品や地方伝承等が方法的に織り込まれ仕組まれた諸国咄としての創造性に富む作品である。巻七の二「若衆盛は宮城野の萩」に描かれる登場人物の関係性や、事件展開の意味と精神性は、その舞台空間である「外が濱」の文芸的イメージを鍵として解読することができる。
1 0 0 0 OA 空間の心理評価における評価対象および評価方法の検討
- 著者
- 田中 宏子 植松 奈美 梁瀬 度子
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.347-356, 1989-12-15 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 14
空間の心理評価における実験方法の検討である. まず, 実大模型, 縮尺模型およびスライドの3つの評価対象における心理量の関連をSD法により検討した. 取り上げた要因は居間に置かれた家具の量と配置である. 因子分析の結果, いずれの評価対象も2つの共通因子が析出され, 価値因子と活動性因子と意味づけた. 活動性因子においては3者の感覚は非常に似通っていたが, 価値因子については在室感・臨場感といった空間と人間との相互作用が影響しており, 空間の価値判断と深い関わりがあると考えられる. ついでSD法の評価の妥当性を確認するために, ME法, 一対比較法の比較検討も試みた. その結果, かなりの整合性が認められた.
- 著者
- Hiroaki ABE Kei KADOWAKI Naohide TSUJIMOTO Toru OKANUKA
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.195-203, 2021-12-20 (Released:2021-12-20)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 7
Impairments resulting from stroke lead to persistent difficulties with walking. Subsequently, an improved walking ability is one of the highest priorities for people living with stroke. The degree to which gait can be restored after a stroke is related to both the initial impairment in walking ability and the severity of paresis of the lower extremities. However, there are some patients with severe motor paralysis and a markedly disrupted corticospinal tract who regain their gait function. Recently, several case reports have described the recovery of gait function in stroke patients with severe hemiplegia by providing alternate gait training. Multiple studies have demonstrated that gait training can induce "locomotor-like" coordinated muscle activity of paralyzed lower limbs in people with spinal cord injury. In the present review, we discuss the neural mechanisms of gait, and then we review case reports on the restoration of gait function in stroke patients with severe hemiplegia.
- 著者
- 松本 輝紀 大井 尚行
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.35, pp.27-32, 2001-10-31 (Released:2012-08-01)
- 参考文献数
- 16
What are the determinants of personal space in the limited space like a room in our house? This article discusses the question on the study of personal space in the limited space. The experiment were executed in order to understand the relationship between a scale of space and characteristic of personal space from the viewpoint of posture and depth of space. The results of the experiments were summarized as follows: 1) When the point of view became higher, the size of the personal space became larger, 2) When the depth of the room became larger, the size of the personal space became larger.
1 0 0 0 OA 小規模オフィスビル内環境の評価方法に関する研究
- 著者
- 垣鍔 直 宇野 勇治 正田 浩三 杖先 寿里
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.5, pp.189-192, 1997-12-20 (Released:2017-01-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
According to the building management and sanitary law, large office buildings of which floor area exceeds 3000 m^2 are to be maintained so as to keep indoor environments with high quality. However, small buildings have been exemplified. In this study, large buildings and small buildings were investigated on air quality and thermal environment. It was then found that both thermal environment and air quality in the small buildings were necessary to be improved due mainly to insufficient ventilation.
- 著者
- 森保 洋之 河野 佐知
- 出版者
- 日本インテリア学会
- 雑誌
- 日本インテリア学会 論文報告集 (ISSN:18824471)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-8, 2000 (Released:2022-06-01)
本研究は, インテリア計画についての基礎的研究で,住宅の公的空間であるリビング・ダイニング(LD)空間モデルを用いて, LD空間を把握,構成する際の形態構成と空間意識に関する基礎的な指針を得ることを目的としている。具体的には, LD空間において,準箱庭形式による家具,間仕切りの配置の仕方等を含む形態構成を通して,人が空間を知覚し把握する際に感じる一体性,連続性,方向性の位置付け, その中でも特に連続性が持つ意味の明確化と,その形態構成の仕方と空間意識との関係について解析しており,一定の成果を得ている。
1 0 0 0 OA 漢方薬が原因と考えられた劇症肝炎の1症例
- 著者
- 山崎 潔 鈴木 一幸 佐藤 公彦 大内 健 吉成 仁 磯崎 一太 中舘 一郎 班目 健夫 吉田 俊巳 柏原 紀文 佐藤 俊一 村上 晶彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.724-729, 1991-07-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 9 6
漢方薬が原因と推定された劇症肝炎の1例を経験した.症例は62歳男性.痔核治療のため漢方薬(金鵄丸)の服用を開始したところ,6週間後に倦怠感と尿濃染が出現した.服用中止により一旦症状の消失をみたが,服薬再開後5週間で上記症状が再出現,黄疸の出現をみ入院となった.凝固能低下が著明で(PT 28%, HPT 19%),種々の治療にもかかわらず,4週間後多臓器不全の状態で死亡した.剖検肝は495gと萎縮著明で,肝組織像は広範性肝壊死を示した.金鵄丸による薬剤性肝炎は本例を含め9例が報告されている.その特徴は,金鵄丸が原因との認識が遅れたため反復服用により肝炎の繰り返しをみる例が多いこと,発疹,好酸球増多がみられないことであった.本例は,漢方薬により劇症肝炎を来した初めての報告である.漢方薬の使用が増加しているおり,漢方薬によっても本例のごとき重症肝障害が惹起されうることに注意すべきである.
1 0 0 0 OA 18世紀の英国でスコットランド音楽はどう伝えられたか:J.オズワルドの創作活動に着目して
- 著者
- 高松 晃子
- 出版者
- 聖徳大学大学院音楽文化研究科聖徳大学音楽学部音楽文化研究会
- 雑誌
- 音楽文化研究 (ISSN:13467050)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.115-131, 2022-03
1 0 0 0 OA 当院における黄芩含有漢方薬による肝障害の頻度について
- 著者
- 萬谷 直樹 岡 洋志 渡邊 妙子 長崎 直美
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.377-381, 2017 (Released:2018-02-07)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 3
黄芩含有漢方薬による肝障害の頻度を推定するため,当院の全てのカルテをレトロスペクティブに調査した。黄芩含有方剤を服用した2430例のうち,1547例(63.7%)で肝機能検査が施行されていた。1547例のうち黄芩含有漢方薬による肝障害が否定できない例を19例(1.2%)みとめた。その肝障害の臨床像は過去の報告と大差がなかった。 今回の調査でも黄芩含有方剤による肝障害の頻度は1%前後であると推測され,過去の文献報告と一致していた。
1 0 0 0 OA 都市公共空間における照明デザインの考え方と効果
- 著者
- 山本 公夫
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.137-142, 1990-03-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 大森 正登 今川 望 平手 小太郎
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.456, pp.63-73, 1994-02-28 (Released:2017-01-27)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
About the space that a designer planned, we developed the system for simplified forecast of comfort on post occupancy environment. This is the system which designer and building-owner are able to get support in case of planning to improve comfort in the office space. In this system, user describes the space which they want to evaluate comfort in terms of component's grade. After user select early frequency distribution equivalent for component's grade, this system does output frequency distribution forecast of comfort on post occupancy environment with method of exchange by varoius weighting coefficients. As a result, the distribution actually measured by test closely matched the distribution forecasted by above procedure. We could verify that this system is potentially capable of doing "Ante Occupancy Evaluation" on office environment, and that the assumption which was introduced in the middle of forecasting distribution is not greatly beside from the process of comfort-judgement by human subjects.
- 著者
- 坂口 武司 山中 俊夫 甲谷 寿史 桃井 良尚 相良 和伸
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.736, pp.569-578, 2017 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
Not only spaces of study, such as, a classroom and a library, but also those for informal communication in lunch time and after school, such as, courtyard and entrance hall, are one of the most important factors for campus planning. To say about communication spaces, the environment and its influence on the state of mind and the behavior of the students must be different between the indoor communication space where the thermal condition is controlled by artificial devices, and that of outdoor where the thermal condition changes naturally. But, few studies are found from the viewpoint of thermal condition and usage of those spaces. The purpose of this study is to figure out the thermal and architectural influences of the indoor and outdoor community spaces of the junior and senior high school buildings on the state of mind and the behavior of the students through the year. The research of the thermal environment, the observational survey and the questionnaire survey have been done in June, September, October, November, and February, in the junior and senior high school. The results are shown as follows. 1. Both the result of the observational survey and the questionnaire survey shows that students stay hall and courtyard having a lunch and chattering in lunch time, then, after school, they were mainly studying in the hall, chattering and having rendezvous with friends in the courtyard. The staying time is longer in the hall than in the courtyard. So, it found that students chose which to stay depend on the staying time and purpose. 2. The research of the thermal environment and observational survey show that there was no correlation between the number of students in the hall or courtyard and the temperature, and also that students kept staying in the courtyard in high temperature as 28 degree centigrade in September. 3. There was a weak positive correlation between the temperature and the rate to choose staying in the courtyard. In September, in spite of the heat, the rate increased. In February, because of the cold, the rate decreased. 4. PMV of the hall and courtyard was almost within +1.0 to -1.0 through the year. In June and September, in the courtyard, PMV increased more than +1.0, but the number of the students staying there didn't decrease. 5. The thermal sense in February shows that the ratio of the sum of the cold and slightly cold in the hall was more than that in the courtyard. It can be inferred that the students' basic metabolic rate is higher than those of the grown-up, and also, that students have chosen to stay outside by themselves, knowing it's cold there. 6. In the courtyard, there was no correlation between the evaluation of thermal comfort and PPD. One of the reasons is assumed that there are a lot of stimulus in outdoor except for thermal stimuli, one more reason is also assumed that thermal condition such as heat and cold outdoor is tend to be widely accepted compared with indoor. 7. The students' evaluation shows that furniture and vending machines promote to stay in the courtyard. 8. The students' evaluation shows that they feel natural factors, such as, “wind” , ”shade of tree”, “sunshine”, and “sky”, more in the courtyard than in the hall. 9. The students' evaluation shows that there were about 30% replies of the long distance from the classroom to there, for the reason why students don't stay in the hall or the courtyard. But, another evaluation shows there is not obvious relation between the distance and the number of staying students. On the other hand, the reason to stay in the hall or courtyard has a difference by grade. Those results are expected to be the basic data necessary for planning informal communication spaces in schools, specially in the outdoor.
1 0 0 0 OA 上層・下層居室からの空間形状意識と印象評価 住宅居室における吹抜け空間の研究
- 著者
- 松本 直司 高木 清江 三輪 真裕
- 出版者
- 日本インテリア学会
- 雑誌
- 日本インテリア学会 論文報告集 (ISSN:18824471)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.17-22, 2006 (Released:2022-06-01)
本研究では,住宅居室を対象に,吹抜け空間形状と空間形状意識,印象評価の3つの関係性を求め,上層居室からと下層居室からでそれらがどのように異なるかを明確にすることを目的とする。 実験は,1 /10縮尺模型を用い,居室の印象を11評価尺度による SD 法で評価した。 分析の結果,吹抜け空間を評価する尺度は,上層・下層居室ともに「スケール性」「快適性」「関係性」「特異性」の4軸であった。空間形状意識では,下層居室からは上層居室からに比べ,レベル差に大きく影響された。上層・下層居室からの空間形状意識は,ともに「空間重複型」が最も快適な空間となった。吹抜け空間においては快適な居室を計画するためには,一体的であるより,ある程度の分離感をつくる必要がある。
1 0 0 0 OA 住民観察にもとつく快適環境指標の開発 ―川崎市の環境観察指標―
- 著者
- 原科 幸彦 田中 充 内藤 正明
- 出版者
- 社団法人 環境科学会
- 雑誌
- 環境科学会誌 (ISSN:09150048)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.85-98, 1990-04-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5
環境の快適さの評価は住民の主観によるところが大きく,環境基準というような一律の尺度で行うことはできない。また,快適さの状態も従来の公害項目のように機器計測により把握することは困難である。そこで本研究では,これまでの環境指標の考え方を一歩進め,環境の快適性を人々の目や耳などの五感でとらえ「計量化」することを考えた。すなわち,住民自らが環境を観察してその結果にもとづき評価できる環境観察指標の開発を試みた。 このため,川崎市において小学校5年生の児童とその保護者を対象に環境観察調査を実施し,市内全小学校111校から約3800票が得られた。この調査では,児童に対しては自然観察を,保護者に対しては都市環境の快適面の5つの側面についての観察と評価を行ってもらった。この調査結果の分析から以下の諸点が明らかとなった。 自然環境の観察結果からは,セミ,カブトムシ,ヘビなど特定の生きものの発見率と快適環境評価との間に強い関連のあることがわかった。また環境の快適さの観察と評価からは,機器による計測にはなじまない「街の落ち着きやたたずまい」と「緑のゆたかさ」の2つが住民観察による有力な指標となりうることが示された。これら2つは快適性の総合評価に,特に強く寄与していることも明らかとなった。そして,従来から機器計測が行われてきた大気汚染と騒音も,「空気のきれいさ」と「静かさ」という観察によりかなり適切に把握できることが明らかとなった。さらに,生活環境を安全,健康,利便,快適,地域個性,人間関係の6項目で総合的に評価した場合,快適面は最も高い寄与を示すことが明らかになり,都市環境評価における快適性の重要性が確認された。
- 著者
- 田中 宏明
- 出版者
- 北海道大学高等教育推進機構
- 雑誌
- 高等教育ジャーナル : 高等教育と生涯学習 (ISSN:13419374)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.37-42, 2016-03