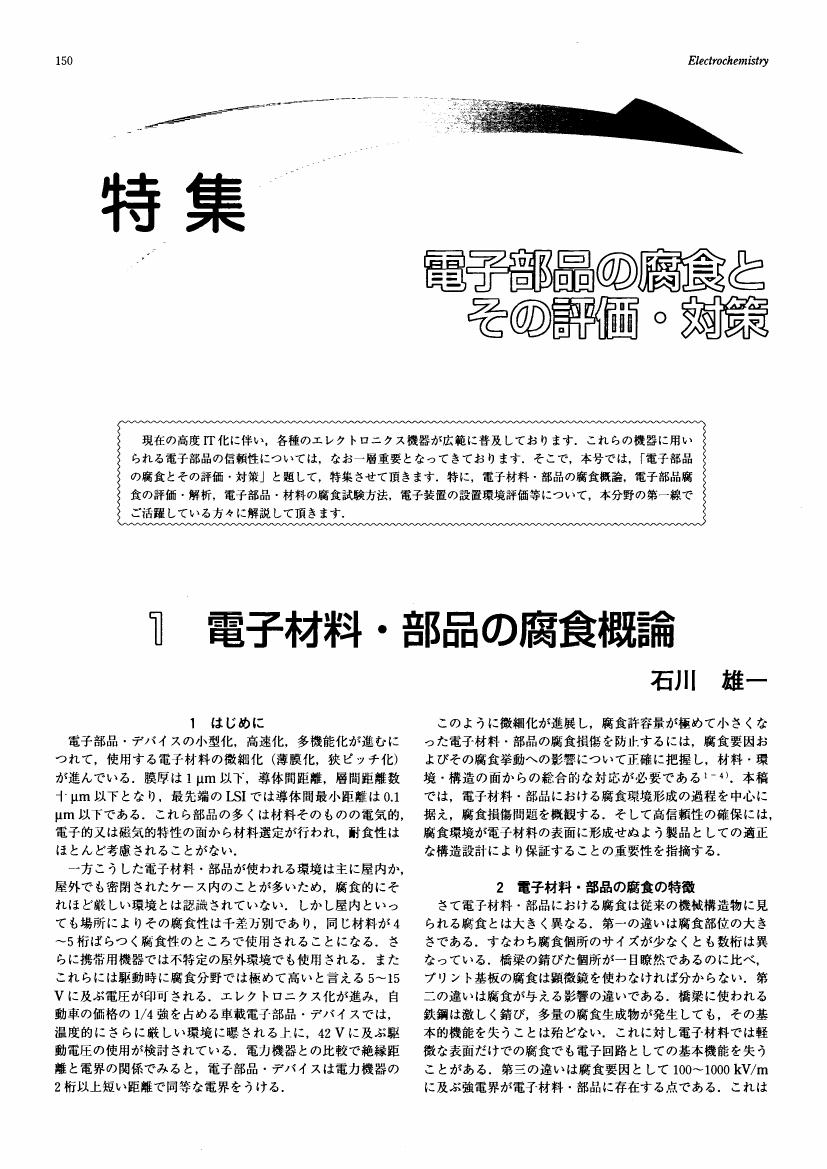- 著者
- Takeshi Kinjo Daijiro Nabeya Hideta Nakamura Shusaku Haranaga Tetsuo Hirata Tomoko Nakamoto Eriko Atsumi Tatsuya Fuchigami Yoichi Aoki Jiro Fujita
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.83-87, 2015 (Released:2015-01-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 8 9
A 62-year-old woman complained of diarrhea and vomiting after receiving chemotherapy for cervical cancer in association with high doses of corticosteroids. Two months later, the patient developed acute respiratory distress syndrome, and numerous Strongyloides stercoralis parasites were found in the intrabronchial discharge. Ivermectin was administered daily until nematodes were no longer detected in the sputum, and the patient's condition was successfully rescued. Antibodies for human T-cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1) were positive. HTLV-1 infection and the administration of corticosteroids are known risk factors for strongyloides hyperinfection syndrome. Therefore, physicians should consider this disease in the differential diagnosis of patients from endemic areas who present with gastrointestinal symptoms under these risk factors.
1 0 0 0 OA 少数者影響過程の時系列的分析
- 著者
- 吉山 尚裕
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.47-54, 1988-08-20 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 14
本研究は, 第一に少数者行動の一貫性が, 多数者に生起する少数者への同調行動の内面化に及ぼす効果を時系列的に検討し, 第二に多数者の少数者に対する属性認知 (自信と能力) の成立過程について吟味した。被験者は男子大学生80名。5人集団が構成され10試行群と20試行群の2条件に割りあてられた。実験集団の1人はサクラ (少数者) であった。集団状況において, 被験者はスクリーン上に70cmの長さの線分を3.3m離れた位置から実際に構成するように教示された。そのとき, サクラは一貫して逸脱した長さ (85cm) を呈示した。試行終了後, 被験者は個人状況において線分を構成した。結果は次の通りである。1. 多数者は少数者側への同調行動を生起させたが, 時間経過に伴う内面化の進行は見いだされなかった。2. 多数者は少数者に対して自らよりも“能力”を低く, “自信”を高く認知した。3. 多数者の少数者に対する“自信”認知は, “能力”認知に比べ敏感ではなく, その成立に時間を必要とした。4. また, 多数者は少数者との行動のズレが大きい場合に, 少数者の“自信”を自らよりも高く認知した。少数者の行動一貫性および少数者と多数者の行動のズレは, 多数者の少数者に対する“自信”認知成立の決定因であると結論された。また, 実験結果から今後検討すべきいくつかの間題が討論された。
1 0 0 0 OA スポーツ競技者のGritとバーンアウトの直線および曲線的関係
- 著者
- 雨宮 怜 吉田 昌宏 坂入 洋右
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.29-37, 2021-03-25 (Released:2021-03-25)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
This study examined the correlation between athletes’ grit and burnout using linear and quadratic regression analyses. Study participants comprised of 314 university athletes who answered a questionnaire on socio-demographic variables, the Short Grit Scale (Grit-S), and the Burnout Scale for University Athletes (BOSA). The multiple regression analyses showed negative linear correlations between grit and burnout subscale or total burnout scores. Furthermore, the relationship between the squared term of perseverance and interpersonal exhaustion, team devaluation, and burnout were positively significant, and the squared term of grit was positively connected to interpersonal exhaustion and team devaluation in BOSA. The results indicate that if grit or perseverance were found to be too high, athletes were inclined to experience interpersonal exhaustion, team devaluation, and burnout easily.
1 0 0 0 OA エアバッグを用いた子ども向けの呼吸誘導ぬいぐるみの開発
- 著者
- 浦谷 裕樹 大須賀 美恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.428-434, 2015-12-20 (Released:2016-09-28)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4 4
自然災害や事故・事件等の影響により,その後心の病である心的外傷後ストレス障害(PTSD:posttraumatic stress disorder)を発症する子どもたちがいる.心身を落ち着ける呼吸法の習得によりPTSDの症状を改善できるといわれている.そこで,子どもたちがリラックスできるように,2つのエアバッグを用いて呼吸計測をしながら,腹部を上下させて呼吸誘導ができる呼吸誘導ぬいぐるみを開発した.7 ~10歳の健康な女児12名を対象に評価実験を実施した結果,エアバッグのセンサで呼吸計測ができ,ぬいぐるみの腹部の動きによる呼吸誘導が可能であることが示された.開発した呼吸誘導ぬいぐるみによるリラクセーション効果の検証は今後の課題である.
- 著者
- 山下 里香
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.61-76, 2014-09-30 (Released:2017-05-03)
継承語は移民コミュニティの民族アイデンティティの要のひとつ,またコミュニティの団結の資源とされることが多い.特に,第二世代以降には,コミュニティ内でのフォーマルな場面や,上の世代との会話に使われると言われる(生越,1982, 1983, 2005; Li, 1994).また,語用論的には,言語選択や言語の切り替えは,コンテクスト化の手がかり(contextualization cues)という,談話の機能を持つとも言われる(Gumperz, 1982).日本語と継承語が流ちょうに話せる子どもたちは,移民コミュニティにおいて実際にどのように複数の言語を使用しているのだろうか.本研究では,コミュニティでの参与観察をふまえて,在日パキスタン人バイリンガル児童のモスクコミュニティの教室での自然談話を質的に分析した.児童らの発話の多くは標準日本語のものであったが,ウルドゥー語や英語の単語,上の世代が使用する日本語の第二言語変種(接触変種)に言語を切り替えることがあることがわかった.児童らは,こうした日本語以外の言語・変種を,上の世代の言語運用能力に合わせて使用していたのではなく,談話の調整や,時には上の世代に理解されることを前提としない意味を加えることで自分たちの世代と上の世代との差異を確認し強めながら,世代間の会話の資源として利用していることがわかった.
1 0 0 0 OA 知的ギフテッド児の発達特徴と学校適応に関する研究
- 著者
- 本郷 一夫 松本 恵美 九里 真緒
- 出版者
- 東北教育心理学研究会
- 雑誌
- 東北教育心理学研究 = THE TOHOKU JOURNAL OF PSYCHOLOGY IN EDUCATION (ISSN:09119515)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.39-52, 2022-03-31
- 著者
- 清水 義之 橘 一也 津田 雅世 籏智 武志 稲田 雄 文 一恵 松永 英幸 重川 周 井坂 華奈子 京極 都 奥田 菜緒 松本 昇 赤松 貴彬 竹内 宗之
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.287-292, 2017 (Released:2018-05-14)
- 参考文献数
- 17
近年,小児における末梢挿入式中心静脈カテーテル(peripherally inserted central catheter:以下PICC)は,新生児領域では頻用されており,幼児や学童においても,重要な静脈アクセス用デバイスである.PICC 留置は視診または触診により静脈を穿刺する以外に超音波ガイド下に留置する方法があるが,わが国において,小児患者に超音波ガイド下にPICC を留置する報告はない.われわれは,41 名の小児において,リアルタイム超音波ガイド下にPICC 留置を試みた.56 回中50 回(89%)PICC 留置に成功し,重篤な合併症は認めなかった.屈曲による滴下不良はなく,62%の症例で合併症なく使用された.留置にはある程度の慣れと,鎮静が必要であるものの,静脈のみえにくい年少児でも留置可能であり,小児における有用なルート確保手段であることが示された.
1 0 0 0 カプサイシン入りガムを使用した嚥下訓練
- 著者
- 梅野 博仁 濱川 幸世 権藤 久次郎 白水 英貴 吉田 義一 中島 格
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.285-288, 2002 (Released:2007-10-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 5 3
成人10名にカプサイシンを10-6 mol/mlに溶解させた蒸留水を口腔内に噴霧し,噴霧前と噴霧後の唾液中に含まれるサブスタンスP(以下SPと省略)の濃度を測定した。同様に,成人10名にカプサイシンを1枚につき6×10-8 mol程度含有した市販のガムを使用して,ガムを噛む前と噛んだ後の唾液中SPの濃度も測定した。その結果,カプサイシン投与後,ガムを噛んだ後,ともに有意な唾液中のSPの上昇を認めた。同様に筋萎縮性側索硬化症,パーキンソン病,眼咽頭型筋ジストロフィー症,ギランバレー症候群,脊髄小脳変性症患者でも,カプサイシン投与でSPが有意に上昇した。したがって,カプサイシン入りガムを噛むことで咀嚼・嚥下の訓練になり,さらに唾液中のSPが上昇することで嚥下反射が起こりやすくなることが期待できる。嚥下訓練にカプサイシン入りガムを用いるのは有用と考えられた。
1 0 0 0 OA 嘉数 啓:島嶼学
- 著者
- 松山 洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.1, pp.40-41, 2020-01-01 (Released:2023-02-19)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 乾燥肌やアトピー性皮膚炎へのコラーゲントリペプチドの内服効果
本研究は、アトピー性皮膚炎におけるコラーゲントリペプチドの効果を検討した。申請者はこれまで、乾燥肌モデルマウスにおいてコラーゲントリペプチドが真皮のヒアルロン酸のヒアルロン酸産生を促し、乾燥にともなう痒みを改善することを明らかにした。その機序を明らかにするために本研究では、炎症性サイトカインであるIL-13、TNF-α、IFN-γを添加したヒト表皮角化細胞にコラーゲントリペプチドを添加し、TARC、TSLPの産生を測定することにより、コラーゲントリペプチドが炎症時の表皮角化細胞に与える影響について解析を行った。TARCの産生をRT-PCRで測定した結果、コラーゲントリペプチドを添加していない表皮角化細胞と比べて、TARCの産生が抑制されていた。また、TSLPについても同様の結果が得られた。ELISA法でTARCの蛋白定量を行った結果、コラーゲントリペプチドにより表皮角化細胞のTARCが低下する傾向がみられたが、有意差はみられなかった。同様に、TSLPをウエスタンブロット法で確認したところ、コラーゲントリペプチドの添加によりTSLPのタンパク量が減少することが明らかになった。さらに、13人のアトピー性皮膚炎患者に対して、コラーゲントリペプチド(7人)、コラーゲンペプチド(6人)を12週間投与し、SCORAD、角質水分量、痒みの評価、血清中のTARC、IgE、LDHおよび好酸球数を測定した。その結果、コラーゲントリペプチド投与群でのみ、内服投与開始前と比べて皮疹面積、SCORAD、TEWLが改善していた。コラーゲントリペプチド群では投与前と比べてTARCの減少がみられた。血清中のIgE、LDHおよび好酸球数についてはいずれの群でも投与前後で有意差は認めなかった。
1 0 0 0 OA グリム童話「ルンペルシュティルツヒェン」の明治期から大正期の翻訳
- 著者
- 野口 芳子
- 出版者
- 梅花女子大学・大学院児童文学会
- 雑誌
- 梅花児童文学 = The Baika Journal of Children’s Literature (ISSN:13403192)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.19-33, 2022-03-15
明治期から大正期の間にこの話の邦訳は合計7 話出版されている。そのうちドイツ語から訳されたものは2 話、英語訳からは3 話、ロシア語訳からは1 話、底本が不明のものは1 話である。改変箇所は英語訳の影響を受けたものが多く、ドイツ語原典に忠実な訳は1 話しか存在しない。小人の名前については、ドイツ語の名前を使っているものが2 話、ロシア語の名前が1 話、日本語の名前が4 話ある。名前を当てられた小人は最後の場面で体を引き裂くのではなく、片足で跳んで逃\げると改変されているものが多い。これは底本に使用された英語訳に施された改変である。日本人訳者によって行われた改変は、生まれた赤子の性別を男性にしたことである。ドイツ語の原典では「最初に生まれた子」としか表現されていないのに、多くの日本語訳では「王子」にされている。1873 年の太政官布告263 号で貴族や華族に対して長男の家督相続が日本史上初めて法的に明確化された。そのような日本の社会状況がおそらく改変に反映されたのであろう。
- 著者
- 二階 哲朗 齊藤 洋司
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.5, pp.557-562, 2007 (Released:2007-10-06)
- 参考文献数
- 39
レミフェンタニルは, その薬理作用から鎮痛を主体にした手術麻酔管理が可能となる画期的なオピオイドである. しかしレミフェンタニルの超短時間作用性を考慮した場合, 麻酔からの覚醒や呼吸状態の回復は速やかであるが, その一方, 術後疼痛管理には注意を要する. 局所麻酔薬とフェンタニルやモルヒネを併用した持続硬膜外鎮痛やintravenous patient controlled analgesia (ivPCA) 法は, レミフェンタニル麻酔後の安全かつ効果的な術後鎮痛方法である. 麻酔中の疼痛管理から術後疼痛管理への適切な切り替え方法が重要となる.
1 0 0 0 OA ロケットエンジン動的シミュレータ(REDS)
- 著者
- 木村 俊哉 高橋 政浩 若松 義男 長谷川 恵一 山西 伸宏 長田 敦 Kimura Toshiya Takahashi Masahiro Wakamatsu Yoshio Hasegawa Keiichi Yamanishi Nobuhiro Osada Atsushi
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 = JAXA Research and Development Report (ISSN:13491113)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-RR-04-010, 2004-10-25
ロケットエンジン動的シミュレータ(Rocket Engine Dynamic Simulator: REDS)とは、ロケットエンジンの始動、停止、不具合発生時などのエンジンシステム全体の過渡特性を、コンピュータを使って模擬し評価する能力を持った計算ツールである。REDSでは、ロケットエンジンの配管系を有限個の配管要素の連結(管路系)としてモデル化し、この管路系に対しボリューム・ジャンクション法と呼ばれる手法を用いて質量、運動量、エネルギーの保存方程式を時間発展的に解くことによって管路内(エンジン内)における、燃料、酸化剤、燃焼ガスの流動を計算する。ターボポンプ、バルブ、オリフィスなどの流体機器はボリューム要素やジャンクション要素にそれらの対応する作動特性を持たせることで動作を模擬する。燃料や酸化剤の物性については、ロケットエンジンの特殊な作動範囲に適応するよう別途外部で開発された物性計算コード(GASPなど)を利用するが、そのためのインターフェースを備える。燃焼ガスの物性計算については、熱・化学平衡を仮定した物性計算を行い、未燃混合ガスから燃焼状態、燃焼状態から未燃混合状態への移行計算も行う。ターボポンプの運動は、ポンプやタービンの特性を考慮したポンプ動力項、タービン動力項を加速項とする運動方程式を流れの方程式と連立して時間発展的に解くことによって求める。未予冷区間においては、配管要素と流体との間の熱交換を、熱伝導方程式を解くことによって求め、再生冷却ジャケットにおいては、燃焼ガスから壁、壁から冷却剤への熱伝達を考慮する。燃焼室、ノズル内においては、燃焼ガス流れの分布から熱流束の分布を考慮する。今回のバージョンでは、2段燃焼サイクルを採用した日本国の主力ロケットLE-7AおよびLE-7の始動、停止過程時における動特性を模擬することを目的にエンジンモデルを構築し、実機エンジン燃焼試験の結果と比較することでシミュレータの検証を行った。ただし、ボリューム要素の組み合わせは任意であり、エキスパンダーサイクルなどの新しいエンジンシステムに対しても適用が容易に出来る。計算の高速化のために2CPU以上用いた並列処理への対応を行い、ネットワークで接続した複数のPC(PCクラスタ)を用いた並列計算も可能である。
1 0 0 0 OA ローレンタイド氷床に存在した巨大氷床湖の決壊について。
- 著者
- 庄司 義則
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
最終氷期の北米大陸北部に、厚さ3,000m以上にも及ぶ巨大なローレンタイド氷床が形成されていた。そこにアガシー湖という巨大な氷床湖が形成され、その決壊が地球環境へ重大な影響を与えたという説が存在する。しかし、決壊の実態ははっきりしていなかった。そこで、NOAAから公開されている地形データを使い、自作ソフトを使って分析した。その結果、アガシー湖の水量は、これまでの説より遥かに少ない事が分かった。さらに、周辺の地形から見てアガシー湖は、大規模決壊するような湖ではない事も判明した。そこで、北米大陸の傾斜地図を作成したところ、アガシー湖付近に大規模決壊の侵食の痕とみられる地形が発見された。これにより、アガシー湖決壊は、別のさらに巨大な氷床湖決壊により引き起こされた事が判明した。本研究は、ローレンタイド氷床に存在した巨大氷床湖の決壊メカニズムと規模を考察したものである
1 0 0 0 OA 電子材料・部品の腐食概論
- 著者
- 石川 雄一
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- Electrochemistry (ISSN:13443542)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.150-155, 2005-02-05 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 3
1 0 0 0 OA 入浴後のストレッチングは柔軟性の改善に有用か? 単盲検ランダム化比較試験による検討
- 著者
- 大西 琴乃 烏山 昌起 河上 淳一 濵本 明日香
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会 九州ブロック会
- 雑誌
- 九州理学療法士学術大会誌 九州理学療法士学術大会2022 (ISSN:24343889)
- 巻号頁・発行日
- pp.4, 2022 (Released:2022-11-29)
【目的】ストレッチングは傷害予防や健康維持・向上など幅広く活用される. 先行研究では, ストレッチングと温熱療法の同時施行はストレッチング単独と比べて柔軟性が向上すると報告されており, 加温効果の併用は効率的な介入手段と考えられる. この加温効果を日常生活で簡便に利用できる手段として“入浴”が挙げられ, 臨床の指導においても入浴後のストレッチングを推奨する場面は多く見受けられる. しかし, これまでに入浴後のストレッチング効果を検証した報告は散見されず, その有効性は不明である. そこで,本研究の目的は入浴前後のストレッチングが柔軟性に与える影響を比較検討することである.【方法】本研究はCONSORT 声明に準拠した. 対象は研究協力が得られた健常成人20 名( 男性14名,女性6名,平均年齢21.6 歳) であった。群の割り付けは単純ランダム割り付け法を採用し, 本研究の評価に関与しない者が入浴前ストレッチング群(以下; 入浴前群)10名と入浴後ストレッチング群(以下; 入浴後群)10 名に割り付けた. 介入はハムストリングスの伸張性向上を目的としたストレッチングとし, 伸張時間30秒3セットを5日間実施した.対象者には介入期間中に本研究以外のストレッチングや下肢の激しい運動を控えるように指示した. 入浴後群の入浴時間は10 分以上, 温度は38 度~42度,ストレッチングのタイミングは入浴後12 分以内とした. 評価項目は, 背臥位股関節90°屈曲位での膝関節伸展角度とし, 角度測定はデジタル傾斜計DL-155V を用いた. なお, 評価者2 名は対象者が入浴前群・入浴後群のいずれの割り付けか分からない状態( 盲検化) とした. 統計は介入前後の群内比較はWilcoxon 符号順位検定, 群間比較はMannWhitney U 検定を用いた. また, 事後分析として検出力を算出した. 有意水準は全て5%とした.【結果】本研究は計19 名( 入浴前群1 名は他の介入を受け除外) が全ての介入を完了した. 入浴後群の膝関節伸展角度は, 介入前後(pre 26.4 ± 11°, post18.4 ± 11°) で有意な改善を認めた(p=0.03). 一方, 入浴前群の膝関節伸展角度は, 介入前後(pre 33.4 ± 10°, post 28.7 ± 8°) で有意差を認めなかった(p=0.11). さらに, 介入後の膝関節伸展角度は, 入浴後群(18.4 ± 11°) は入浴前群(28.7 ± 8°) と比較して有意に低値であった(p<0.01). 事後分析の結果, 検出力は0.93 であった.【考察】本研究は, 入浴後群の膝関節伸展角度は入浴前群と比べて有意な改善を認めた. その理由として, 疼痛閾値の上昇が挙げられる. 入浴の温熱刺激を加えたことで, ゲートコントロール理論に基づきストレッチング時の伸張痛が軽減することが予想される. その結果, 入浴後群は入浴前群と比較してより強度のストレッチングを行えるようになり, 膝関節伸展角度が向上したと推測した. さらに, 入浴に伴う加温効果によって筋温に変化が生じ, 柔軟性に寄与した可能性も考えられる. これらの要因によって, 入浴後群は入浴前群よりストレッチング効果が得られたと推測された.【結論】本研究は, “入浴後におけるストレッチング指導”の有用性を支持する結果であり, 入浴後のストレッチングは柔軟性の改善に効果的な手段と示唆された.【倫理的配慮,説明と同意】本研究は倫理委員会( 番号2124 号) の承認を得ている.
1 0 0 0 OA 高校生のヘルスリテラシーに及ぼす要因分析—青森県内と長野県内の高校生調査の比較から—
- 著者
- 笠原 美香 吉池 信男 大西 基喜
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.145-153, 2021-05-31 (Released:2021-06-16)
- 参考文献数
- 29
目的:青森県内と長野県内の高校生を対象とし,ヘルスリテラシー(Health Literacy: HL)に関して両県の地域差を含む実態を明らかにすること,およびHLの高低を規定する要因を明らかにすること.方法:2018年7月3日~24日に,青森県B市6校806人(公立,私立),長野県C, D市4校978人(公立のみ)の高校2年生を対象に自記式質問紙調査による横断研究を行った.調査項目は,性別,相互作用的・批判的ヘルスリテラシー(Communicative and Critical Health Literacy: CCHL),インターネット利用状況,学習面に影響すると考えられる「将来の夢」や目標を持っている,自分は「やればできる」と思う,学習意欲(勉強は好きである,保健の学習は好きである),「将来の生活習慣予測」である.各項目について地域間で比較を行った後に,重回帰分析によってCCHLが高いことと関連する因子を検討した.結果:青森県の高校生は,長野県の高校生に比べて,インターネットの使用頻度やCCHLが高かった.また,CCHLが高いことは,インターネット利用状況,「将来の夢」や目標を持っている,自分は「やればできる」と思う,保健学習が好きであること,将来,定期的な運動をする,定期的に体重管理をすると予測していることと,正の関連が見られた.結論:高校生のHL教育を推進していく上では,インターネットを利用した健康情報の活用,「将来の夢」や目標を持つこと,自分は「やればできる」と思える状況を促す教育が重要である.
1 0 0 0 OA 離散スペクトル幾何へのいざない
- 著者
- 砂田 利一
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 総合講演・企画特別講演アブストラクト (ISSN:18843972)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.Spring-Meeting, pp.82-92, 1998 (Released:2010-07-01)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 PM2.5による大気汚染の現状と対策
- 著者
- 遠藤 真弘
- 出版者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13493019)
- 巻号頁・発行日
- no.866, pp.巻頭1p,1-10, 2015-04-28
1 0 0 0 OA フェイルセーフと制御システム設計
- 著者
- 金井 喜美雄
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.173-181, 1990-02-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 17