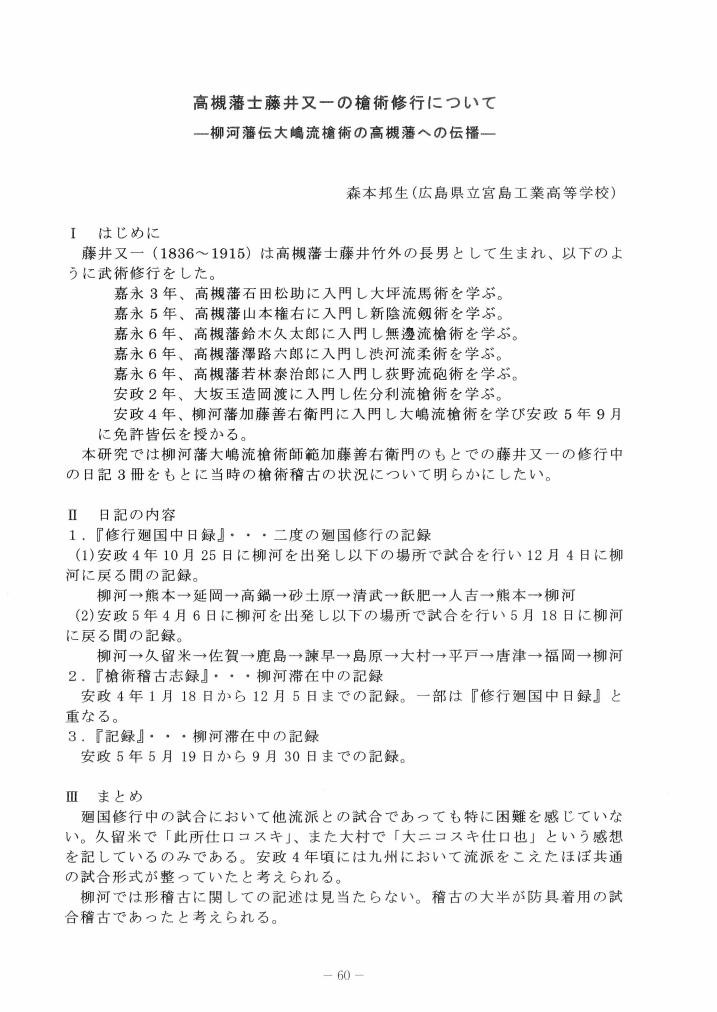1 0 0 0 OA 歩道計測型MMSを用いた歩道空間のバリア評価手法
- 著者
- 江守 央 佐田 達典 岡本 直樹 岩上 弘明
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F3(土木情報学) (ISSN:21856591)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.I_175-I_181, 2016 (Released:2017-03-24)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
近年,MMSによる3次元点群データの活用が注目をされている.特に道路空間においては,道路上から見える路面・道路構造物・周辺の樹木などの点群データを取得することにより道路の基礎情報として道路計画等に活用されつつある.一方,歩道空間においては,超高齢社会を迎えた我が国では移動円滑化促進が必要とされており,歩道空間の平坦で連続的な移動が求められている.このようなバリアフリーに向けた整備において,歩道の状況を的確に把握することは重要な課題とされている.このようなことから本稿では,歩道を歩行しながら計測する歩道計測型MMSを用いて計測した歩道空間の3次元点群データより,歩道空間のバリア評価を実施し, その有用性について考察する.
1 0 0 0 OA 投球動作解析システムによるTOPポジションの運動学的解析(1部 生体計測)
- 著者
- 中村 真里 中村 康雄 林 豊彦 福田 登 駒井 正彦 橋本 淳 信原 克哉 Chao Edmund Y.
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.13-25, 2002-06-25
- 被引用文献数
- 9 4
Baseball pitching involves a complicated and rapid movement that has been investigated to prevent injuries and to improve the pitching performance. It is difficult to assess the pitching motion with high accuracy and a high sampling rate, due to the limitations of preexistent camera systems. The current camera system, however, has enough capacity to measure pitching motions with high accuracy and a high sampling rate. We have been diagnosing shoulder joint injuries caused by pitching. The patients (N=939) felt pain during the pitching sequence as follows: top position (32.5%), maximum external rotation (27.2%), and ball release (14.5%). Hence the top position is one of the most important postures to investigate the mechanisms of shoulder joint injury in pitchers. There have been no studies that focused on the top position, however. The main purpose of this study was to develop a system to assess the pitching motion accurately. Another purpose was to estimate the instant of the top position and evaluate the kinematics of the shoulder and elbow joints. Pitching movement was assessed using a motion capture system (ProReflex MCU500, Qualisys Inc., Sweden) in a studio that has an official pitcher's mound and home base. This system can record the positions of reflective markers at 500 Hz using seven CCD cameras. Thirty-two markers were mounted on the joints and body landmarks of each subject. Two markers were mounted on the ball. The pitching motions of eleven subjects were assessed, after a period for warm up. Kinematics parameters were calculated using three-axis gyroscopic Euler angle. The instant of the top position was observed for all subjects before the lead foot touched the ground. The interval from the top position to ball release was 0.242±0.0438 [s] (n=11). The subjects were divided into two groups by the type of posture at the instant of the top position, as follows: internal rotation group (n=5), 11.8±6.08 degrees, and external rotation group (n=6), 38.1±19.97. Other kinematics parameters at the top position were adduction of the shoulder at 74.2±19.84 degrees, horizontal adduction of the shoulder at 37.3±14.10 degrees, and extension of the elbow at 92.1±21.63 degrees. The timing and posture of the estimated top position were almost the same as those of the conventional top position. From the top position to lead foot contact on the pitching sequence, there were three patterns of elbow leading. The three patterns did not depend upon experience. We interpreted them as individual variations.
- 著者
- 原島 省 呉 在龍 姜 聲舷
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.79-90, 2001
海洋環境の変動をモニターするプラットフォームとして,定期航路船舶の連続取水系の利用が有効な手段となっている.主な理由は,観測専用船と異なり,維持経費がかからないことや,多様なフロースルー型の計測手法が適用できることなどであるが,最も本質的な点は,計測頻度が高いこと,長期間持続することが可能なこと,計測の空間的密度を高くできることから,植物プランクトンのブルームなど重要な海洋変動のスペクトルに対応する時空間スケールをカバーできることである.本報告では,国立環境研究所のフェリーによる海洋環境モニタリングの実行例(1991~現在),韓国海洋研究所による同様の実行例(1998年~現在),および諸外国の実行例や計画例を紹介し,フェリーの利用による特記的な成果を示すとともに,今後の課題や発展の可能性について述べる.
1 0 0 0 周術期の栄養管理
- 著者
- 小山 諭 森 直治 LJUNGQVIST Olle FEARON Ken SOOP Mattias DEJONG CHC
- 出版者
- 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 静脈経腸栄養 : 日本静脈経腸栄養学会機関誌 = The journal of Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ISSN:13444980)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.723-735, 2011-03-25
- 参考文献数
- 80
手術や外傷に伴うストレス反応は、生体にとって本来、有益な現象であるが、制御を失うと有害なものとなる。患者を手術から早期に回復させ、手術アウトカムを最良のものにするために、侵襲を最小限にし、栄養管理をはじめとする集学的な周術期管理を行うことが重要である。ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) プログラムと呼ばれるこのモダンな周術期管理は、術前絶食期間を最短として炭水化物の負荷を行い、術前腸管のプレパレーションや術後経鼻胃管留置を回避し、胸部硬膜外ブロックや非オピオイド性の鎮痛薬投与による鎮痛、早期経口摂取・早期離床の励行、適正な周術期の輸液・血糖管理、術前低栄養の是正等を行うことにより、術後の回復に有害な種々の生体反応、インスリン抵抗性や腸管麻痺を軽減し、手術侵襲からの早期回復と良好な手術アウトカムをもたらす。
1 0 0 0 我々のリハ医学革新への軌跡
- 著者
- 木島 英夫
- 出版者
- バイオフィリア リハビリテーション学会
- 雑誌
- バイオフィリア リハビリテーション学会研究大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2013
<p><tt> 過去40 年にわたる経験から、我々が研究を進める手法は中枢性の麻痺にたいして痙性発生を予防し、改善する効果があるものと考えられ、その機序の解明が望まれてきました。 </tt></p><p><tt> 我々は特定の一施設の入所者のみが、「インペアメントレベル(解剖学的機能損傷)からの日常生活自立」のためのリハビリテーションを実施でき、受益できるのではなく、日常生活を自立したいと願う全ての高齢障害者に提供できるよう願い研究を続けてきました。獲得した多くの公的研究助成を通じ、現在実施している我々の研究が社会に貢献できる日が近づきつつあると思っています。 </tt></p><p><tt> 研究を振り返ると、滝沢茂男氏は、政治家として大成することを嘱望された藤沢市の青年議員でした。高齢社会への深い洞察を持ち、広い視野を持っていたからこそ、誰も気づく事のなかった訓練結果と手法の特異性、そして手法のシステム化・プログラム化が可能なほどの合理性に気づき、市会議員の座を投げ打ち、引退する県会議長の出馬要請に応じることなく、この研究に取り組んできました。そして氏がこのプログラムを社会に提供するため持てる全ての手段を用いて奮闘する姿に感銘を受け、協力を惜しまず研究を共にしてきた多くの同志がおり、これら無私の活動の成果として、本日の講演会が可能になったと言えます。 </tt></p><p><tt> 氏の願いであり、我々の願いである「団塊世代高齢化による社会崩壊を防ぐ」が、手段提供の実現から国民意識の高まりを呼び起こし、実現できると確信しています。</tt><tt><b> </b></tt></p>
1 0 0 0 バイオフィリアリハビリテーション学会初代会長挨拶
- 著者
- 木島 英夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 高齢市民が活躍するための社会技術研究会
- 雑誌
- バイオフィリア (ISSN:21868433)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.2, pp.99-100, 2015
- 被引用文献数
- 1
私はバイオフィリアリハビリテーション学会設立時に会長を務めた。それまで21世紀リハビリテーション研究会と称したが、初代会長は滝沢恭子氏、2 代は福井圀彦氏、3 代で名称が替り、記名の学会になった。学会設立時の就任挨拶で、「介護・依存から自立へ・2025 年で16%弱と想定される要介護老人の発生を10%以下にする。を実現するため、会員諸兄の一層の研究努力を期待致します。」と述べたが、国内ばかりでなく、世界に目を向けた活動を継続している状況は期待に違わぬ活動と喜んでいる。<br>私がこの学会の会長に就任したのは、「寝たきりをなくすという滝沢茂男氏の努力がどのような結果をえられるか見守る」ことが中心であった。<br>氏は、政治家として大成することを嘱望された藤沢市の青年議員であった。高齢社会への深い洞察を持ち、広い視野を持っていたからこそ、誰も気づく事のなかった訓練結果と手法の特異性、そして手法のシステム化・プログラム化が可能なほどの合理性に気づき、市会議員の座を投げ打ち、引退する県会議長の出馬要請に応じることなく、この研究に取り組んだ。氏がこの国際活動を国内学会の部会として立ち上げ、部会長を務め、さらには国内学会全会員合意の下、独立組織に再編して、理事長として活動を継続していることは望外の喜びである。<br>思えば、志をたて、親である滝沢恭子氏の実施しているリハビリテーションの方法をシステム化し、着実に世に出す努力を続けていた氏から、「泣き言」といってもよい「僕がドクターならはやいのに」との言葉を聞き、私が協力を申し出てから、20 年を経た。当時理学療法士の参加による組織としてかなりの実績をあげていたが、論文発表をする医師はいなかった。そのままでは個人の経験が個人の経験のままで終わってしまったことであろう。元日本臨床整形外科医会故金井司郎理事長と相談し、論文採用に向けて、氏を全国の臨床整形外科医会々員に紹介し、説明に当たってもらい、その後論文をまとめて、発表したことは忘れられない。多くの藤沢市内臨床整形外科医会々員の協力も得て発表したこの論文が、学会へ進歩する基礎となった。当時、学会への組織変更にあたり、「思いたつ者はいても実現できるものはほとんどいない」として、監事を快諾する医師や、ES細胞を利用した神経伝達機構の再生を研究する部会を提案する内科医がいた。 <br>氏の提唱する、高齢障害者の自立こそが、団塊世代の高齢化に伴う社会崩壊を防ぐとの認識は、時代の移り変わりと共に重要になり、識者の中では共通の認識になっている。神経伝達機構再生研究の提案は実現できずに終わったが、世界で活動する本学会の今後の焦点として、分子遺伝学からの脳機能再建が課題になっていると聞く。今回PubMed 登録にむけて、日本語論文集を再編し、世界の読者へ知識を提供することになった。我々のこれまでの研究がまだ陳腐化していないことは医学改革の困難さを示している。ぜひ広く英知を集め、簡単ながら、効果の高いタキザワ式リハビリテーションがリハビリテーション医療の中核になるよう読者各位の研究参加、普及推進を期待している。
1 0 0 0 OA 都市化と小売商業
- 著者
- 竹林 庄太郎 Shotaro Takebayashi
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.5-6, pp.161-194, 1971-03-18
研究
- 著者
- Abe T. Kawamoto K. Yasuda T. Kearns C. F. Midorikawa T. Sato Y.
- 出版者
- 日本加圧トレーニング学会
- 雑誌
- International Journal of KAATSU Training Research (ISSN:13494562)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.19-23, 2005
- 被引用文献数
- 1 68
The purpose of this study was to investigate the effects of short-term KAATSU-resistance training on skeletal muscle size and sprint/jump performance in college athletes. Fifteen male track and field college athletes were randomly divided into two groups: KAATSU (resistive exercise combined with blood flow restriction, n=9) and control (n=6) groups. The KAATSU group trained twice daily with squat and leg curl exercises (20% of 1-RM, 3 sets of 15 repetitions) for 8 consecutive days while both KAATSU and control groups participated in the regular sprint/jump training sessions. Maximal strength, muscle-bone CSA, mid-thigh muscle thickness (MTH), and sprint/jump performance were measured before and after the 8 days of training. The muscle-bone CSA increased 4.5% (p<0.01) in the KAATSU group but decreased 1% (p>0.05) in the control group. Quadriceps and hamstrings MTH increased (p<0.01) by 5.9% and 4.5%, respectively, in the KAATSU group but did not change in the control group. Leg press strength increased (9.6%, p<0.01) in the KAATSU group but not (4.8%, p>0.05) in the control group. Overall 30-m dash times improved (p<0.05) in the KAATSU-training group, with significant improvements (p<0.01) occurring during the initial acceleration phase (0-10m) but not in the other phases (10-20m and 20-30m). None of the jumping performances improved (p>0.05) for either the KAATSU or control groups. These data indicated that eight days of KAATSU-training improved sprint but not jump performance in collegiate male track and field athletes.
1 0 0 0 ご挨拶
- 著者
- 木島 英夫
- 出版者
- バイオフィリア リハビリテーション学会
- 雑誌
- バイオフィリア リハビリテーション学会研究大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.265, 2013
本調査研究の当初計画は,歩行器を用い,高齢者の歩行能力を維持し日常生活の自立をすすめるであった. 在宅での歩行器利用によるADL向上について,顕著な成績を上げ,終了したことは,高齢化が進み老後を心配する国民の不安を一部でも和らげるために,喜ばしい.テクノエイド協会から指導があり,「脳血管障害や下肢骨折を受傷した後でも,高齢障害者が自分で生活できる健康を取り戻すことを可能にする,老健施設で実施されているタキザワプログラムによる創動運動の実施に係る評価研究」を今回の研究に追加した.追加により,「介護・依存から自立へ」と題した我々の進めている研究を,研究助成の下で実施できたことは価値が高い. 研究結果が国民福祉向上に寄与できることを確信している. 藤沢市民病院開院以来高い効果を上げ続けてきた訓練手法の実施を,受傷後慢性期廃用性の後期高齢者に対し,藤沢市機能訓練会で藤沢の整形外科医師らが見てきたのと同様に,リハ医師をはじめ10人以上の専門家が実施現場で確認した. そしてその効果を,定性的評価とはいえ,評価し得たことは画期的である. 今後の研究の方向性,普及の必要性を公的に報告できたことは研究の進度に大きな影響を与える. 過去30年にわたる経験から,福祉用具研究開発実施(進捗)状況報告書に報告の通り,この手法は中枢性の麻痺にたいして痙性発生を予防し,改善する効果があるものと考えられ,その機序の解明が望まれる. 我々は特定の一施設に入所している入所者のみが,「インペアメントレベル(解剖学的機能損傷)からの日常生活自立」のためのリハビリテーションを実施でき,受益できるのではなく,日常生活を自立したいと願う全ての高齢障害者に提供できるよう願い研究している. テクノエイド協会の指導で研究し得たことにより,現在実施している我々の研究に新たな研究者の参加が可能になり,そして新たな研究者の参加は,研究をさらに促進するに違いない. 終わりに,滝沢茂男氏は,政治家として大成することを嘱望された藤沢市の青年議員であった. 高齢社会への深い洞察を持ち,広い視野を持っていたからこそ,誰も気づく事のなかった訓練結果と手法の特異性,そして手法のシステム化・プログラム化が可能なほどの合理性に気づき,市会議員の座を投げ打ち,引退する県会議長の出馬要請に応じることなく,この研究に取り組んだ. そして氏がこのプログラムを社会に提供するため持てる全ての手段を用いて奮闘する姿に感銘を受け,協力を惜しまず研究を共にしてきた多くの同志がいた. これら無私の活動の成果として,公的報告が可能になったとも言える. 氏の願いであり,我々の願いである「団塊世代高齢化による社会崩壊を防ぐ」を実現する為に,本年アムステルダムで開催される第一回世界リハビリテーション医学会(The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine)において,我々は共に,「創動運動による寝たきりからの歩行再獲得と,団塊世代高齢化による社会崩壊を防ぐ為の方法の提案」(Re-acquirement of walking from bedridden by motivative exercise and proposition of the solution to the aging crisis)を発表する. 我々の研究が本研究報告を契機に今後ますます実りあるものになる事を確信している.
1 0 0 0 IR 蛤のうしお汁の研究-2-蛤の鮮度,大きさが味に及ぼす影響
- 著者
- 小畑 八寿世 川口 京子
- 出版者
- 東京聖栄大学
- 雑誌
- 聖徳栄養短期大学紀要 (ISSN:02866366)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.p30-33, 1975-03
- 著者
- KAHOKEHR Arman SAMMOUR Tarik SOOP Mattias HILL Andrew G.
- 雑誌
- Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences (ISSN:18686974)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.5, pp.637-656, 2010-09-01
- 参考文献数
- 88
1 0 0 0 自動車エンジン用マイクログローブ軸受の溝寸法の最適化
- 著者
- 加藤 善一郎
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.974-977, 2020
開発当時使用されていた銅鉛合金を使用してマイクログルーブ軸受の検討をしていたので、検討結果を報告する。エンジンテストベンチでのマイクログルーブ軸受の磨耗試験で溝の深さに対する幅の比の最適値が明らかになる。適正に設計されたマイクログルーブ軸受の摩擦損失トルクは、平滑軸受と比べてわずかに低減している。その分、オイルクリアランスの上限が縮小可能と考える。適正に設計されたマイクログルーブ軸受の耐久試験で焼付き・疲労など全く見られず摩耗についても良好な結果が得られた。マイクログルーブ軸受の最適な溝寸法は、溝の深さ2.5~4.5μmそして溝の幅0.15~0.25mmである。
- 著者
- 大西 明宏 江原 義弘
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 = Journal of the Society of Biomechanisms (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.152-159, 2005-08-01
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 6 2
3段の実験用階段を製作し,若年健常男女20名を対象として室内にて歩行計測をおこなった.モーションキャプチャ装置にて踵に貼付したマーカーの軌跡を計測した.その結果,踵軌跡は緩やかな曲線を描く場合と,直線を描く場合とがあり,後者の場合にはヒールクリアランスが短くなることがわかった.本研究ではその特徴をもとにして,安全及び危険な階段寸法を算出する数式モデルを開発した.本モデルでは適切なパラメータを与えることでヒールクリアランスとよく対応する値を計算により求めることができた.この値が負であれば危険,正であれば安全と判定することで安全な階段寸法を導き出した.長寿社会対応住宅設計指針に則った階段寸法は数式モデルにより算出された安全な階段寸法を満たしており,妥当であることが明らかとなった.
1 0 0 0 カウコンフォートの改善を目的としたトンネル換気効果
- 著者
- 竹下 幸広 吉原 由実子 村尾 克之
- 出版者
- 島根県立畜産試験場
- 雑誌
- 島根県立畜産試験場研究報告 (ISSN:09146296)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.23-25, 2005-03
トンネル換気方式をとる県内の酪農家において、牛舎内の換気を風向・風速調査に基づく入気口の改善が、暑熱環境下における乳用牛の生理的、行動的反応に及ぼす効果を検討した。試験区分は試験日及び入・排気口の構造により2期に区分し、従前構造(H16. 8.20-Hl6.8.27)を1期、入気口改善構造(H16.8.28-H16.9.3)を2期とした。1期で牛舎内の気流をシャボン玉により可視化し、11ヵ所で風向・風速を調査した結果、牛床からの高さ0.4mの淀み部分(風速0.0m/秒)が3ヵ所見られた。また牛床からの高さ1.8mと0.4mの平均風速を調査した結果、1.8mが1.36m/秒、0.4mが0.83m/秒と差が大きかった。2期でシャボン玉により風向を確認しながら、牛舎側面の入気口の高さを0.9m-2.0mから0.9m以下へ、側面の入気口の間隔を2mに変更し、風速を調査した結果、0.0m/秒であった3ヵ所の淀み部分はそれぞれ1.28m/秒、1.34m/秒、1.20m/秒となり淀み部分が無くなり、牛床からの高さによる平均風速も1.8mが1.26m/秒、0.4mが1.23m/秒となった。生理的反応の直腸温と呼吸数は1期が38.9℃、54.5回/分、2期が38.5℃、48.3回/分で、それぞれ2期が1期に比較し有意(p<0.05)に低かった。行動調査において佇立時間は、1期が770.2分/日、2期が650.8分/日で、2期が1期に比べ有意(p<0.05)に減少した。横臥時間については1期が669.8分/日、2期が757.4分/日で、2期が1期に比べ有意(p<0.05)に増加した。採食時間については1期が405.7分/日、2期が407.2分/日となり有意差は認められなかった。
1 0 0 0 OA 価格プロモーションのためのマーケット・セグメンテーション
- 著者
- 奥瀬 喜之
- 出版者
- 専修大学商学研究所
- 雑誌
- 専修ビジネス・レビュー = Senshu Business Review (ISSN:18808174)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.27-34, 2010-03-31
Tellis (1986) に示されている、地理的プライシング、第二市場プライシングといった差別的な価格戦略を実践するためには、消費者の価格反応の異質性を把握する必要がある。本稿では、セグメントによって異なる消費者価格反応を検出することを目的として、3つの価格反応変数によるマーケット・セグメンテーションを試みた。分析データとしてスーパーマーケットにおける購買履歴データが用いられ、分析手法としては潜在クラス分析が用いられた。
1 0 0 0 理論社会学としての公共社会学にむけて
- 著者
- 盛山 和夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.92-108, 2006
一昨年のアメリカ社会学会会長ビュラウォイの講演以来, 「公共社会学」に対して熱心な議論が交わされている.これは現在の社会学が直面している困難な状況を「公衆に向かって発信する」という戦略で克服しようとするものだが, この戦略は間違っている.なぜなら, 今日の社会学の問題は公衆への発信がないことではなくて, 発信すべき理論的知識を生産していないことにあるからである.ビュラウォイ流の「公共社会学」の概念には, なぜ理論創造が停滞しているのかの分析が欠けており, その理由, すなわち社会的世界は意味秩序からなっており, そこでは古典的で経験的な意味での「真理」は学問にとっての共通の価値として不十分だということが理解されていない.意味世界の探究は「解釈」であるが, これには従来から, その客観的妥当性の問題がつきまとってきた.本稿は, 「よりよい」解釈とは「よりよい」意味秩序の提示であり, それは対象世界との公共的な価値を持ったコミュニケーションであって, そうした営為こそが「公共社会学」の名にふさわしいと考える.この公共社会学は, 単に経験的にとどまらず規範的に志向しており, 新しい意味秩序の理論的な構築をめざす専門的な社会学である.
1 0 0 0 OA 高槻藩士藤井又一の槍術修行について ―柳河藩伝大嶋流槍術の高槻藩への伝播―
- 著者
- 森本 邦生
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Supplement, pp.60, 2010 (Released:2014-04-04)
- 著者
- 小松 耕史 松本 純 上片野 一博
- 出版者
- 日本獸医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.9, pp.659-664, 2014
- 被引用文献数
- 1
鹿児島県のタイストール式1酪農場において,<i>Chorioptes texanus</i>による皮膚病変及び掻痒症状が多発した.そこでエプリノメクチン製剤(0.5mg/kg)を62頭に投与し,牛群全体の掻痒症状,病変,カウコンフォート及び乳量への影響を評価した.さらに,病変及び乳量について掻痒の有無により群分けし比較した.群全体において,掻痒の指標である尾振り率及び病変部スコアは投与後有意に低下した.カウコンフォートの指標であるStanding idle(起立)の割合は投与後有意に低下し,305日補正乳量は増加した.また,掻痒を示す群では病変部スコアが高く投与後の乳量変化に乏しかったが,掻痒を示さない群では乳量増加が大きかった.群全体において本剤の治療効果が認められたが,罹患牛においてカウコンフォート及び生産性を適正に維持するためには,早期治療により病変を進行させないことが重要と考えられた.
1 0 0 0 最近のオートフォーカス関係の特許係争 (2)
- 著者
- 小倉 磐夫
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.451-457, 1994