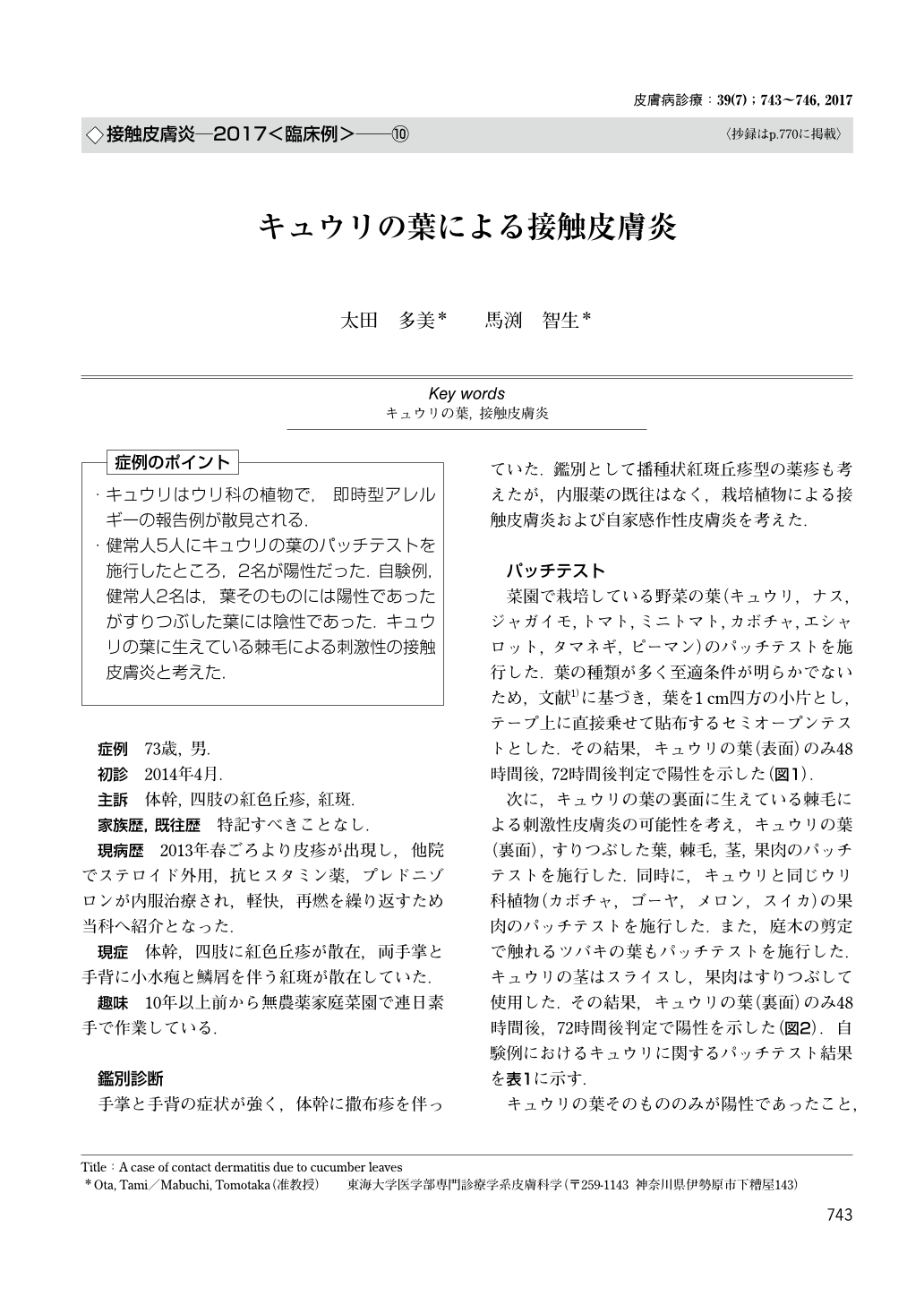- 著者
- 鎌田 裕美
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.137-139, 2020-01-11 (Released:2020-01-11)
1 0 0 0 卵巣摘出によるサル下顎頭の骨密度および構造変化について
- 著者
- 渡邉 直子 田中 みか子 アンワル リズワナ ビンテ 河野 正司 花田 晃治 江尻 貞一
- 雑誌
- 日本骨形態計測学会雑誌 = Journal of Japanese Society of Bone Morphometry (ISSN:09174648)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, 2003-05-30
- 著者
- 井徳 正吾
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 情報研究 = Information and communication studies (ISSN:03893367)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.1-18, 2021-01-31
Toyota introduced Lexus in 1989 in the United States. On the other hand, the same car same car was released in japan as Celsior. Let's consider what values were shared and not shared among these two different brands. 16 years later, Toyota decided to align these brands globally and changed the car from Celsior to Lexus. I will discuss which principals were carried over from Celsior to Lexus from the perspective of branding strategy.
- 著者
- 反田 栄一
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.186-193, 1986
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 台湾における省籍の違いに着目した商店街景観認知の評価分析
- 著者
- 劉 淑恵 浅見 泰司
- 出版者
- Japan Association for Real Estate Sciences
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.103-114, 2002-05-10 (Released:2011-06-15)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
With the focus on the shopping street, this study tries to search and analyze the influences of province on theevaluation of shopping streetscape in Tainan. Through questionnaires of streetscape-consciousness, acomparison of landscape of shopping street is made. According to the result, the provincial difference occurredon1980s more than on1930s, when compared with1930s streetscape-consciousness and1980s streetscapeconsciousness.In particular, “Benshen” and “Waishen” tend to have different view in monotony of the1930sstreetscape, and “Benshen” and “Keja” tend to have different view in familiarity of the 1980s streetscape. Thesedifferences may be caused due to the change in the attitude of “Benshen” toward the environment of cities in Taiwan.
1 0 0 0 OA 「誰もやっていない研究」&「続ける研究」
- 著者
- 黒田 章夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.4, pp.161, 2021-04-25 (Released:2021-04-25)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 川端 昭夫 木村 吉次
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.69_1, 2017
<p> 本研究の目的は、大正11年から昭和3年まで陸軍戸山学校教官であった大井浩を取りあげ、その欧州体育・スポーツ視察並びに体育論を検討し、また、大正・昭和初期の日本の社会体育促進との関わりについて考察する。主な資料は、「体育と武道」、「研究彙報」、「皆行社記事」、「陸軍大日誌」に収録された論文論説、また陸軍戸山学校関連書籍並びに朝日新聞を調査した。得られた結果を以下に示す。1)大井浩は、欧州諸国の視察の結果、軍隊体育、体育・スポーツ事情について度々報告した。軍隊体育における運動競技(スポーツ)の日本に適した様式による導入、日本における武道精神を含めた武道の普及、国民の軍事予備教育を意図した国民体育、特に青年体育の推進を奨励した。2)欧州諸国の視察報告を通して、日本の社会体育の普及の必要性を提言した。3)欧州諸国における女子体育・スポーツの隆盛を報告して、日本でのその普及を期待した。4)欧州諸国の新しい体操の趨勢や集団体操(マスゲーム)の隆盛を報告し、実際に第2回明治神宮競技大会のマスゲームの部の創設や戸山学校生による集団体操の演技参加を行い、日本で初めての公的なマスゲームの大会を実現した。</p>
1 0 0 0 IR 「eスポーツ」のスポーツ化に関する探索的研究 : eスポーツの日韓比較
- 著者
- 川又 啓子 Kawamata Keiko 大島 正嗣 Oshima Masatsugu 丸山 信人 Maruyama Nobuhito 原田 美穂 Harada Miho 佐藤 薫生 Sato Shigeo 川口 洋司 Kawaguchi Yoji
- 出版者
- 青山学院大学総合文化政策学会
- 雑誌
- 青山総合文化政策学 (ISSN:18836992)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.15-50, 2019-09-20
1 0 0 0 心理学的男女両性具有性の形成に関する一考察
- 著者
- 土肥 伊都子
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.192-203, 1994
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 松岡 恵悟
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.174, 2005
仙台市の都心部では、1990年代末に大規模な賃貸オフィスビルが相次いで開発された。それらを含め1996年から2000年の間に竣工した賃貸オフィスビルの合計床面積は約35万m<SUP>2</SUP>のぼり、1995年までの都心部全体のストック(約151万m<SUP>2</SUP>)の4分の1に近い床面積が短期間に新たに供給された。そして、それらの新たなビル立地は、都心業務地域の核心的な地区よりもむしろ、仙台駅北部の戦後区画整理が行われず再開発の必要性が高い地区や、東部の1980年代に基盤整備が進められた地区に多く見られた(図1)。この研究では、これらの新規ビル立地がテナント・オフィスの入居を通じて都心空間の構造にどのような影響を与えたのかを明らかにすることを目的とした。<BR> 近年、仙台市の都心部においても、他の多くの主要都市と同様に賃貸オフィスビルの空室率が高く、とくに1999年以降は10%を超える水準にある。仙台市は東北地方の地方中枢都市であり「支店経済」を基盤として発展してきたが、長引く不況のなかで支店の新規立地は少なく、既設支店の縮小・統合・撤退もみられるなど、オフィス空間の需要増が見込める状況にはない。しかしながら、その一方で設備の整った新しく大規模なビルは相対的に人気が高く、おおむね95%以上の入居率を維持している。<BR> オフィスビルは一般に竣工後時間を経るにしたがって陳腐化が進み、魅力を減じてゆく。とくにここ数年はオフィスのIT対応が強く求められたため、これに設備面で対応できない古いオフィスビルは市場での競争力を弱め、新しいビルの優位性が際立つようになった。そのため、新しく大規模なビルや設備のより優れたビルは、周辺の既存支店の借り換え需要に支えられ、テナントを集めることが相対的に容易であると言える。<BR> 上述の新しい大規模ビルのうち1998年と99年に竣工した7棟について、入居オフィスの企業概要や以前の立地場所を調査したところ、各ビルとも大企業オフィスが多数含まれ70%前後が借り換えによるものであることが判った。なお、この調査は企業のホームページや会社年鑑、電話帳や住宅地図を資料として行った。また、移転前の入居ビルにおける空室の充てん状況についても調査を行った。その結果、相対的に新しいビルや規模の大きいビルでは、より古く小規模なビルなどからの借り換えにより、充てんが進みやすい傾向を見てとることができた。そして一方で古いビルのなかにはテナント転出後の充てんが進まず、空室率が60%を超えるものも見られた。<BR> 以上のようなテナント・オフィスの移動を通じて、新たに大規模ビルが立地した仙台駅北部や東部地区は業務空間としての性格を強め、一方で古いビルの比率が高い核心的な地区ではオフィス立地数や従業者数が減少し空室率が上昇するという、都心空間の再編成が起こっていることを確認できた。
- 著者
- 北 仁美
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
<B>Ⅰ.はじめに</B><BR> 日本の大手食品製造業の事業所の海外展開が進行している。その背景には、日本国内の市場の成熟化や消費の縮小、農産物の自由化などがある。食品関連産業は生産・調達された農産物を処理・加工する。そのため、農産物の生産から消費までの輸送距離と時間がより一層拡大した。日本の大手食品関連産業が積極的に関与してきた農産物の国際的な流動が、加工・調理された食品を含む食料の国際的な流動へと拡大した。<BR> 本研究は、日本の大手食肉加工企業である日本ハム株式会社(以降、日本ハムと略記)を事例に、企業戦略によってグローバルスケールでの食料の国際的な流動がどのように変化してきたのかについて検討する。その際、海外におけるグループ企業の配置と日本国内向け製品の原料の原産国に着目する。<BR> 本研究の意義は、「食料の地理学」において食肉とそれに関連する加工品を事例に、日本企業の多国籍化のインパクトを示し、大企業を対象とすることの重要性を強調することにある。<BR><B>Ⅱ.分析方法</B><BR> 分析にあたってまず、日本の食品製造業における海外進出の動向を把握する。続いて、一定の期間ごとに日本ハムの海外における事業所の配置と各事業所の機能を明らかにする。さらに企業のホームページ等から日本国内に流通している製品の原料の原産国の情報を加える。以上により畜産物の生産・調達から販売にいたる国際的な供給システムを把握することを試みた。本研究において流動とは、A国から日本への輸出のみならず、A国とB国の現地法人間の輸出入も含む。<BR><B>Ⅲ.結果および考察</B><BR> 日本ハムは、グループ企業以外の企業からの食肉の輸入、海外の事業所間での企業内貿易、特に三国間貿易によって国際的な食料の流動に関与してきた。1980年代以降、日本ハムは相次いで海外の大企業を買収し、グループ企業間で行う三国間貿易の海外拠点の構築に向けて現地法人を設立した。その目的は、日本国内への食肉の供給のみならず、世界各国への食肉供給にある。三国間貿易とは、豚肉の場合、商社に類似した機能をもつイギリスの英国日本ハムが、欧州各国(主にデンマーク)で生産された豚肉を日本や韓国、中国へ輸出することを指す。その他のケースとして牛肉の場合には、オーストラリア産の牛肉をオーストラリアの現地法人から英国日本ハムを経由して、イギリスを含む欧州各国に販売している。<BR> 以上のように、日本ハムは事業所の多国籍化を推進してきた。しかし、日本ハムによる食料の国際的な流動の焦点になっているのは、依然として食料を大量に輸入する日本である。また、日本ハムの海外事業における売上高は依然として1割強しかない。<BR> 上記で述べた日本ハムによる食料の国際的な流動は、世界全体からみればごく一部に過ぎない。しかし、食料の国際的な流動を解明することにより、大企業による食料の生産から販売に至る系列的なシステムの形成が加速していることが明らかになった。企業買収等による資本蓄積の拡大や多国籍化は、食料供給においてさらなる優位性を発揮する。一部の大企業が中心となった食料の供給体制が今後も進展していくことが予想される。
- 著者
- 問川 博之 磯田 功司
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合リハビリテーション (ISSN:03869822)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.1303-1310, 2012-10
1 0 0 0 ベンチャー企業の会社概要ページの自動抽出
- 著者
- 柴田 有基 澤井 千春 篠田 広人 石野 亜耶 竹澤 寿幸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.4P2GS602, 2020
<p>近年,AIなどの新しい技術を使用したベンチャー企業が数多く創業されている.このようなベンチャー企業に対する,ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの投資も増加している.投資を行う上で,どのようなベンチャー企業があり,どのような活動をしているのかといった企業情報は,重要な判断材料である.しかし,ベンチャー企業は,上場企業とは異なり,情報が整理され公開されていないことが多いため,企業情報を収集するのは困難である.この問題を解決するために,我々は,Webからベンチャー企業の情報を網羅的に自動で収集するための研究を行っている.その第一歩として,AI関連のベンチャー企業のホームページから,会社概要が掲載されているページ(会社概要ページ)を,機械学習を用いて自動抽出する手法を提案する.提案手法の有効性を確認するための実験を行い,提案手法では精度0.794、再現率0.452で会社概要ページを抽出することができた.</p>
1 0 0 0 キュウリの葉による接触皮膚炎
【目的】<br> 近年、食品添加物が「無添加」又は「不使用」である旨を表示した食品が多く販売されており、テレビコマーシャルや企業のホームページで協調されている例も多い。これらは、食品添加物を使用しない食品を望む一部の消費者向けの食品として開発、販売されてきたものであるが、このような表示により、食品添加物使用の意義、有用性、安全性に対する誤解を招くとともに、食品添加物を用いた加工食品全般に対する信頼性を低下させているおそれがある。今回、このような懸念を明確にして問題提起することを目的とし、一般消費者を対象にアンケート調査を行った。<br>【方法】<br> 人口比で割り付けた15~74歳の一般消費者1600人(男女各800人)を調査対象とし、「無添加」「不使用」と表示された食品に対する安全性の認識や、表示の規制に対する意見等について、インターネットを用いた選択式のアンケート調査を行った。<br>【結果】<br> アンケート調査の結果、「○○○無添加」や「○○○不使用」と表示された食品は、食品添加物○○○を使用した食品より安全と思っている回答者が約半数あった。このことから、このような表示が多くの消費者に対し食品添加物の安全性について誤解を招いていることが明らかとなった。<br> また、「無添加・不使用」とされた食品添加物が有害のおそれのないと国が認めたものであることや、それらの食品添加物と同一成分や同じ機能の成分が当該食品に含まれている場合があることを回答者に伝えた後、「無添加」や「不使用」の表示に対する規制についての意見を問うたところ、約6割が優良誤認を招くこのような表示を規制すべきと回答した。
1 0 0 0 OA 地域移行支援の哲学 ―政策と実践への具現化(embodiment)―
- 著者
- 白石 裕子
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.Supplement, pp.1-5, 2021-02-26 (Released:2021-02-26)
1 0 0 0 東京都港区における経営コンサルタント企業の立地
- 著者
- 新名 阿津子
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.235, 2005
1.研究の背景と目的21世紀,日本は急速に進みつつある知識社会への移行に直面している(鴨志田2004)。経済学の分野においても,知識経済化の進展が指摘されているが,地理学の分野においては知識経済化に伴う知識産業の立地およびその変容に関する研究は萌芽的研究領域であるため,研究の蓄積が少ないのが現状である。一方で,本研究の対象である経営コンサルタント企業の立地をみると,東京都一極集中型の様相を呈しており,東京都23区内においても,都心地域への集積が顕著にみられる。そこには都市という地域的基盤の上での,知識産業の輩出・成長プロセスがあるのではないかと考えられる。そこで,本報告では知識集約型事業所サービス業の好例(Muller and Zenker, 200)とも言われている経営コンサルタント業を取り上げ,日本において最も多くの当該企業が立地している東京都港区を事例に,事業所の立地およびその設立過程に着目し,都心における当該産業の輩出・成長プロセスを明らかにすることを目的とする。2.資料と研究の方法 本報告が対象とする企業はNTT発行のタウンページの「東京都港区」に記載されている712社 のうち,自社ホームページを開設しているなどして合法的な企業活動の実態が確認できた252社である。それらの立地を把握した上で,研究対象企業の設立年次や資本金などに関するデータを,対象企業のホームページや出版物,企業案内などから収集した。それを元に,事業所の設立過程と事業所の立地展開に関するアンケート調査・聞き取り調査を実施し,経営コンサルタント企業の立地過程について実態の把握を行った。3.事業所の立地(1)外資系企業 港区は各国大使館が立地する地域であり,かつその周辺では大規模な再開発事業による最新のオフィスビルが供給されていることから,グローバルな事業展開を行う多国籍企業にとって好条件な地区となっており,外資系企業の赤坂及びその周辺における集積が顕著である。(2)国内系企業 国内系企業はその事業所の設立過程によって,個人独立開業による事業所と,出資企業からの分社化によって設立された事業所では立地およびその要因が異なる。 個人独立開業型の事業所の立地過程では,金融・サービス業を中心とした産業集積がみられる都心から輩出された知識労働者による起業と,その事業所の都心立地および都心内部での企業成長が確認された。 分社化型事業所の立地は2つのパターンに分類される。_丸1_分散化型:母企業と分社化された事業所の集中立地による企業成長から,立地の分散化による母企業からの独立。_丸2_近接型:出資企業と事業所の近接立地による関係性強化。 今回の発表では,上記の国内系企業の立地展開と事業所設立過程について,詳細な報告をしたい。
- 著者
- 山田 祥恵
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.684-688, 1998
- 参考文献数
- 1
弊社は「メッセージを伝えたい人とメッセージを受け取る人を『つなげて』, メッセージを『伝える』」コミュニケーションのコンサルティングを行っている。コミュニケーションの媒体として企業のホームページを制作する機会が増えてきた。1996年に「ウィメンズ・ゲートウェイ」という"世界中で活躍するプロ意識のある女性のためのホームページ"を開設し, 情報提供やオンライン上での交流の場の提供も行っている。その他, 働く女性のネットワーク「NAPW」の運営や国際女性ビジネス会議の開催など, 女性を対象とした活動も多い。それらの活動を通して, 「リンクする」「リンクを作る」ということについて日頃感じていること, 考えていることを述べたい。
1 0 0 0 OA 指紋を鍵とするファイル暗号化システムの開発
従来の指紋を用いたファイル保護システムでは、認証によってファイル本体、もしくはファイルを暗号化する鍵へのアクセス制御を行っていた。しかしこの方法では、認証のための指紋情報がローカルに保存されるため、別のPCへファイルを移動して使用する場合などでは安全性を保つことが困難であった。一方我々の提案するシステムでは、指紋を暗号の鍵として用いた暗号化、復号化を行うことにより、認証情報をローカルに残さずにファイルを保護することが可能となった。
1 0 0 0 OA ホーフマンスタール•「六七二夜の物語」試論
- 著者
- 井上 修一
- 出版者
- JAPANISCHE GESELLSCHAFT FUER GERMANISTIK
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.64-72, 1971-03-31 (Released:2008-03-28)
IIn "ad me ipsum“ bezeichnet Hofmannsthal seine Jugendzeit als glorreiche und gefährliche Praeexistenz, in der sich kein Ich befindet. Dazu sagt er noch im imaginären Brief an C. B. "Ich staune, wie man es (=Hofmannsthals Jugendoeuvre) hat ein Zeugnis des l'art pour l'art nennen können-wie man hat den Bekenntnischarakter, das furchtbar Autobiographische daran übersehen können“. Dies Autobiographische, wie es in "ad me ipsum“ steht, bedeutet seine Selbstentwicklung von Praeexistenz zu Existenz, vom schönen ästhetischen Leben zum wirklichen Leben, also der Weg zum Sozialen als Weg zum höheren Selbst. Auf "ad me ipsum“ gegründet, interpretiert R. Alewyn in "Über Hugo von Hofmannsthal“ die Jugendwerke Hofmannsthals und kommt zu einem berühmten schematischen Schluß "vom Tempel auf die Straße“. Heute scheint diese Formulierung als unwiderlegbar zu gelten, aber nach meiner Meinung, entspricht seine Behauptung nicht dem eigentlichen Inhalt der Werke von Hofmannsthal. Vor allem ist diese Formulierung, die das Ich oder das bewußte Verhalten für wichtig hält, allzu rationalistisch, während die Werke Hofmannsthals sinnlich sind.IIHofmannsthals "Märchen der 672. Nacht“ beschreibt die sinnlich drohende, verschlungene Welt. Der Kaufmannssohn ist ein Ästhet, der in schöner Praeexistenz lebt, aber er hat keine Sehnsucht nach dem wirklichen Leben, wie sie Claudio in "Der Tor und der Tod“ hat. Er liebt Kunstwerke, aber er fühlt keinen Neid auf Künstler, der in "Der Tod des Tizian“ an Desiderio frißt, sondern er bleibt ein Liebhaber. Er betätigt sich weder am Leben noch an der Kunst. In "ad me ipsum“ ist ihm vorzuwerfen, daß er kein aktives Ich hat. Aber deswegen schärft sich seine Sinnlichkeit, und er kann die seltsame Zauberkraft der verschlungenen Welt empfinden und sich der Anziehungskraft überlassen. Der Diener, die drei Dienerinnen, das furchtbare Kind an der Scheibe des Glashauses und die Edelsteine im Märchen sind alle nichts anderes als die Personifikationen der seltsamen, unwiderstehlichen Anziehungskraft des Schicksals. Diese Anziehungskraft beherrscht die Welt hinter den Erscheinungen. Der Rationalist, der sich immer auf sein Ich gegründet verhält, sieht nur Tatsachen. Aber der Kaufmannssohn, nämlich der passive Ästhet, beschäftigt sich mit der geheimen Welt, die in einem Sinne noch wirklicher ist als die sachlichen Erscheinungen. Also kann man seine Passivität, seinen Mangel an Ich und sein Sich-tragenlassen auch eine Art von Fähigkeit nennen.