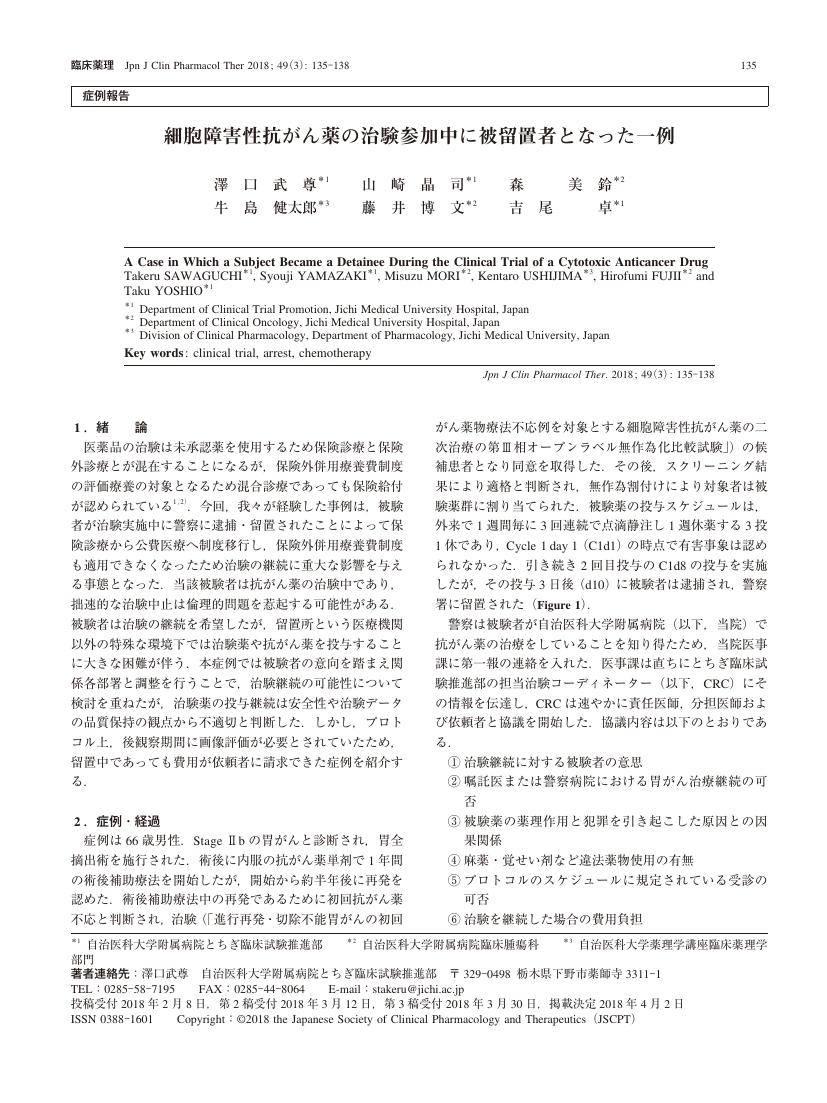3 0 0 0 OA 父親・母親の養育スタイルに関する大学生の回想とアイデンティティ形成
- 著者
- 平田 裕美
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.89.16071, (Released:2018-07-14)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
The impact of parenting on the family orientation of university students and their identity formation during adolescence was investigated to identify parenting styles that promoted identity integration and minimized confusion. In addition, cooperation between fathers and mothers was analyzed to explain parenting styles. The results indicated that students of both genders who were raised by parents with an authoritative style more often evaluated that their parents cooperated in raising them compared with those who were raised with other parenting styles. Moreover, identity integration was significantly higher among students who were raised with an authoritative parenting style than among those raised with an authoritarian and uninvolved parenting style, whereas the opposite outcome was seen for identity confusion. Therefore, it was concluded that in the process of identity formation during adolescence, parenting styles that are responsive to children are essential, as is putting demands on them to mature based on proper criteria, i.e. disciplining them. However, further discussion is required about the fact that no differences were seen for the permissive parenting style.
3 0 0 0 OA ウナギ回遊生態の解明
- 著者
- 塚本 勝巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.350-356, 2006 (Released:2006-06-07)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2 4
3 0 0 0 OA 音楽が時間経過に及ぼす影響-仮説的研究-
- 著者
- 落合 太郎 大嶺 茉未
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.83, 2015 (Released:2015-06-11)
本研究は音楽が時間経過の感覚にどのように影響を与えるか?という命題を簡単な実験によって検証したものである。音楽が人の情緒に直接作用することは経験上誰もが知っていることであるが、これが時間経過の感覚にどのように作用するかはまだ解っていない。西洋音楽の3要素であるテンポ、ハーモニー、メロディをはじめ印象や音の高さが、どのように実際の時間経過時間と感覚時間の差となって表れるかを検証した。誰もが知っているモーツアルト「きらきら星」(k.265/K.300e)の主題と12の変奏曲のなかから特徴的な9曲を選定していずれも60秒に編集し、感覚時間等を18名の被験者に聞いた。全曲が同じ時間であることは被験者に伝えず、曲の要素を変えながら感覚・イメージへの影響をアンケートで設問した。仮説としては、速いテンポの曲が短い時間経過を感じると想定した。しかし結果は真逆で、静かでスローな曲は時間経過が短く、ダイナミックでアップテンポな曲は時間経過を長く感じさせた。2011年に著者らが発見した「逆浦島時間」の仮説と符合して、音楽が感覚を活性化して「逆浦島時間を誘発する」という結果となった。
3 0 0 0 OA 動物介在療法のPOMSと唾液アミラーゼを用いた心理的・生理的評価
- 著者
- 森田 由佳 江原 史雄 森田 義満 堀川 悦夫
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.401-404, 2018 (Released:2018-07-06)
- 参考文献数
- 11
〔目的〕動物介在療法の効果を心理尺度,生理学的手法を用いて示し,その効果の検証を行うことである.〔対象と方法〕対象は,佐賀大学学生30名(男性15名,女性15名),年齢:20.6 ± 0.7歳(平均 ± 標準偏差)とした.方法は,対象者に介在動物であるトカラヤギ2頭と触れ合ってもらい,その前後で気分プロフィール尺度であるPOMSと,唾液アミラーゼ活性を測定した.〔結果〕POMS,唾液アミラーゼ活性ともに,介入前と比較して介入後が有意に低下した.〔結語〕動物介在療法による効果を心理尺度,生理学的手法を用いて示すことができた.今後,障がいなどを持つ高齢者のリハビリテーションに応用し,その際の治療効果判定の一助となると考えられる.
3 0 0 0 OA K・B・ウルフ著 / 林邦夫訳, 『コルトバの殉教者たち : イスラム・スペインのキリスト教徒』, 刀水歴史全書, 48, 刀水書房, 一九九八・八刊, 四六, 二一六頁, 二八〇〇円
- 著者
- 立石 博隆
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.3, pp.429-430, 1999-03-20 (Released:2017-11-30)
- 著者
- Sangwan PARK Kiwoong KIM Youngbeum KIM Kangmoon SEO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-0532, (Released:2017-12-15)
- 被引用文献数
- 6
A seven-month-old female domestic shorthaired cat was presented for buphthalmos in the right eye and corneal cloudiness in the left eye. Full ophthalmic examinations were performed for both eyes and enucleation was done for the right nonvisual eye. Congenital glaucoma caused by anterior segment dysgenesis was confirmed for the right eye. In the left eye, slit-lamp examination revealed focal corneal edema with several iris strands from iris collarette to the affected posterior corneal surfaces. Circular posterior corneal defect was suggested to be the cause of edema. Goniodysgenesis, additionally, was identified. Taken together, the diagnosis of Peters’ anomaly which is a subtype of anterior segment dysgenesis was suggested in the left eye.
3 0 0 0 OA スペイン語の開音節化とラテン語の音節音量
- 著者
- 高垣 敏博
- 出版者
- 日本イスパニヤ学会
- 雑誌
- HISPANICA / HISPÁNICA (ISSN:09107789)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.23, pp.81-99, 1979-10-15 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 30
3 0 0 0 OA 高等教育における学習者のラーニングエクスペリエンスの形成に影響を与える要因
- 著者
- 川本 弥希 渡辺 雄貴 日高 一義
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.363-374, 2018-03-01 (Released:2018-03-16)
- 参考文献数
- 34
大学の授業設計において,学生の学習エンゲージメントの向上が注目されている.しかし,それら学習者の情意的な領域をどう捉え,評価すればいいのかの議論は十分に行われていない.そこで,学習エンゲージメントの形成へ影響を与える要因の抽出,及び関連する心理的概念の体系化を目的として,47名の日本の大学生を対象に,質的および量的調査を実施し,PARRISH のラーニングエクスペリエンス(LX)の形成に影響を与えている要因の分析を行った.その結果,PARRISHの定義にはない2つの外的要因,(1)他の授業の課題が忙しい等のその講義以外の要因や(2)友人など周囲の状況に影響を受けた等の講義品質以外の要因が抽出された.また,自律的動機,自己有用感,熟達目標,自己効力感の既存の心理尺度と,LX レベルに有意な正の相関関係があることがわかった.
3 0 0 0 OA 食の安全教育を目的としたカードゲーム教材「食のカルテット」の利用可能性の検討
- 著者
- 堀川 翔 赤松 利恵 堀口 逸子 丸井 英二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.129-139, 2012 (Released:2012-04-24)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
【目的】小学校高学年向けの食の安全教育に用いるカードゲーム教材「食のカルテット」のルールや内容,受け入れやすさについて利用可能性を検討すること。【方法】2011年9月から11月に,A県1市1町の小学校計6校の5年生,6年生,教職員を対象に,「食のカルテット」の施行及び自己記入式質問紙調査を実施した。「食のカルテット」は,食の安全の内容を中心とした,食に関する全般的な知識を習得することを目標としたカードゲーム教材である。ゲームの実施前及び実施後に「食のカルテット」の内容を10問質問し,ゲーム実施前後の回答を,各問題の正答率はMcNemar検定,合計得点はWilcoxonの符号付き順位検定によって比較した。また,児童及び教職員にゲームの内容やルールについての評価を質問した。【結果】児童294人,教職員28人が質問紙に回答した。「食のカルテット」の内容の問題は,実施前より実施後で正答率が上がったものと下がったものがみられたが,10問の合計得点は実施後が有意に高かった(Z=-3.657,p<0.001)。91.8%の児童がゲームを「とても楽しかった」と回答しており,自由記述(84.0%が回答)でも「楽しみながら・遊びながら学べた」という記述が回答者の34.0%にみられた。教職員の自由記述(63.3%が回答)でも「食に関する知識が身につく」,「楽しみながら学べる」などの意見が得られた。【結論】児童の回答から,「食のカルテット」のルールは児童に受け入れられ,楽しく学べる教材であることが示された。今後は,教材としての効果を検討する必要がある。
3 0 0 0 OA MEG–BMI to Control Phantom Limb Pain
- 著者
- Takufumi YANAGISAWA Ryohei FUKUMA Ben SEYMOUR Koichi HOSOMI Haruhiko KISHIMA Takeshi SHIMIZU Hiroshi YOKOI Masayuki HIRATA Toshiki YOSHIMINE Yukiyasu KAMITANI Youichi SAITOH
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.st.2018-0099, (Released:2018-07-12)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 6
A brachial plexus root avulsion (BPRA) causes intractable pain in the insensible affected hands. Such pain is partly due to phantom limb pain, which is neuropathic pain occurring after the amputation of a limb and partial or complete deafferentation. Previous studies suggested that the pain was attributable to maladaptive plasticity of the sensorimotor cortex. However, there is little evidence to demonstrate the causal links between the pain and the cortical representation, and how much cortical factors affect the pain. Here, we applied lesioning of the dorsal root entry zone (DREZotomy) and training with a brain–machine interface (BMI) based on real-time magnetoencephalography signals to reconstruct affected hand movements with a robotic hand. The DREZotomy successfully reduced the shooting pain after BPRA, but a part of the pain remained. The BMI training successfully induced some plastic changes in the sensorimotor representation of the phantom hand movements and helped control the remaining pain. When the patient tried to control the robotic hand by moving their phantom hand through association with the representation of the intact hand, this especially decreased the pain while decreasing the classification accuracy of the phantom hand movements. These results strongly suggested that pain after the BPRA was partly attributable to cortical representation of phantom hand movements and that the BMI training controlled the pain by inducing appropriate cortical reorganization. For the treatment of chronic pain, we need to know how to modulate the cortical representation by novel methods.
- 著者
- 谷口 祥一 木村 麻衣子
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.59-76, 2018 (Released:2018-07-04)
- 参考文献数
- 17
国立国会図書館件名標目表において,細目を伴った件名標目には代表分類記号が原則付与されていない。国立国会図書館作成の書誌レコードに付与された細目付き件名と日本十進分類法 9版の分類記号の組み合わせの中から,当該件名の代表分類記号となりうるものを機械学習によって同定することを試みた。 まず,出現した件名・分類記号ペアに対して人手によって適切性を判定し,機械学習用の学習・評価用データを整備した。その結果,件名を構成する主標目の代表分類記号と完全一致または前方一致となる分類記号の約 8割が,細目付き件名の代表分類記号として適切と判定された。 機械学習の適用実験では,学習用データの設定において 2つの方式,件名・分類記号ペアの属性群設定において 5つの属性集合,それに 7つの機械学習法という条件を組み合わせた実験とした。実験の結果,機械学習は一定程度の有効性は見せたが,大きく有効との結果を示すまでに至っていない。
3 0 0 0 細胞障害性抗がん薬の治験参加中に被留置者となった一例
- 著者
- 澤口 武尊 山崎 晶司 森 美鈴 牛島 健太郎 藤井 博文 吉尾 卓
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.135-138, 2018-05-31 (Released:2018-06-21)
- 参考文献数
- 4
3 0 0 0 OA 大規模災害時におけるソーシャルメディアの活用―情報トリアージの適用可能性
- 著者
- 藤代 裕之 松下 光範 小笠原 盛浩
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.49-63, 2018 (Released:2018-05-19)
- 参考文献数
- 10
東日本大震災以降,ソーシャルメディアは大規模災害時の情報伝達ツールとして重要度を増しているが,情報爆発やデマといった課題により活用が困難になっている。本研究では,課題解決を目的に,限られた時間的制約のもとで優先度の高い情報を整理する情報トリアージのソーシャルメディアへの適用可能性を検討する。調査手法は,熊本地震に関するソーシャルメディア情報を収集・分析するとともに,報道機関や消防機関に対してソーシャルメディア情報の影響についてインタビューを行った。その結果,ソーシャルメディアから救助情報を探すことは困難であること,消防機関では通常時には情報トリアージが機能しているが,大規模災害時にはソーシャルメディアの情報を含む膨大な通報が寄せられたことにより,機能不全に陥っていたことが明らかになった。ソーシャルメディア情報の整理を消防機関の活動と連携して行うことで,情報トリアージが機能し,情報爆発やデマといった課題を解決出来る可能性があることが明らかになった。本研究は,大規模災害時の情報伝達ツールとしてソーシャルメディアを活用するためには,ソーシャルメディア情報のみを対象に研究するだけではなく,被災地での活動を調査し,連携する方法を検討することが重要であることを示している。この知見は,救助活動のみならずソーシャルメディアを通した被害状況の伝達や物資支援などにも応用が可能であろう。
- 著者
- 下島 優香子 井田 美樹 西野 由香里 石塚 理恵 黒田 寿美代 仲真 晶子 平井 昭彦 貞升 健志 甲斐 明美
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.209-214, 2015-12-30 (Released:2016-01-08)
- 参考文献数
- 28
2010~2013年に都内の食肉処理場および小売店で購入した牛内臓肉104検体について,糞便系大腸菌群,VTEC,C. jejuni,C. coli,SalmonellaおよびL. monocytogenesの調査を行った.その結果,糞便系大腸菌群は, 85検体(81.7%)が陽性であった.VTECは25検体(24.0%)から31株検出された.そのうち1検体は糞便系大腸菌群陰性であった.血清群O157は 17検体(18株),O26が1検体(1株),O103が1検体(1株),その他の血清群(O1,O28,O91,O153,OUT)が7検体(11株)から検出された.付着遺伝子保有状況を調べた結果,eaeは血清群O157,O26,O103の20株が陽性,saaは血清群O28,O153,OUTの5株が陽性であった.aggRはすべての株が陰性であった.C. jejuniは42検体(40.4%)から50株,C. coliは16検体(15.4%)から16株が検出された.Salmonellaは4検体(3.8%)から5株検出され,血清群はO4群が4株(いずれも血清型Derby),O3, 10群が1株(血清型Amsterdam)であった.L. monocytogenesは22検体(21.2%)が陽性であった.以上の結果から,牛内臓肉は腸管出血性大腸菌を含む食中毒菌に高率に汚染されていることが明らかとなった.
3 0 0 0 OA 『女学雑誌』におけるキリスト教改良主義と文学
- 著者
- 岡田 章子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.242-258, 2009-09-30 (Released:2012-03-01)
- 参考文献数
- 22
本稿は,『女学雑誌』の文学を,キリスト教改良主義による女性と文学の新しい関係性という観点から捉え,その新しい関係性が,後の『文学界』における文学の自律性を求める動きにおいて,どのような意義をもっていたのか,を検討するものである.『女学雑誌』の文学志向は,当時の英米の女性雑誌に影響されたものであり,同時にそれは,明治20年代における「社会のための文学」という潮流において好意的に捉えられ,女性に向けて新しい小説を書く女性作家の登場を促した.彼女たちは,あるいは口語自叙体の小説によって女性の内面を語り,あるいは平易な言文一致体によって海外小説を翻訳するなど,独自の成果を生み出した.しかし,キリスト教改良主義の社会運動や道徳に縛られた文学は,やがて文学の自律性を求める『文学界』の離反を招き,「社会のための文学」ではなく,文学の自律性,ひいては社会における文学の独自の意義が追求されることになった.しかし,こうしたブルデューの定義するような「文学場」の構築を求める動きは,『女学雑誌』との断絶よりも,むしろ共通する「社会にとって文学とは何か」の問いを前提にしたものであり,しかも,樋口一葉という女性作家の,女性の問題のまなざしにおいて成立したという意味で,『女学雑誌』は日本の近代文学の成立において,従来論じられてきた以上に不可欠な役割を担っていた,といえるのである.
3 0 0 0 OA 森林と洪水
- 著者
- 蔵治 光一郎
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第118回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.165, 2007 (Released:2007-03-26)
- 著者
- Xi LI Kazuhiko HIGASHIDA Takuji KAWAMURA Mitsuru HIGUCHI
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.233-238, 2018 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 6
It is known that a high-fat diet induces an increase in mitochondrial biogenesis in skeletal muscle. To examine the time course of decrease in mitochondrial biogenesis in skeletal muscle after discontinuing a high-fat diet feeding, C57BL/6 mice were fed a high-fat diet for 4 wk and then switched to the control diet for another 3 or 7 d. During the high-fat diet withdrawal period, the protein content of the mitochondrial respiratory chain decreased faster than the fatty acid oxidation enzymes. The mitochondrial DNA copy number remained high for at least 1 wk after withdrawing the high-fat diet. These results suggested that after switching to the control diet following a period of high-fat diet, the increased mitochondrial biogenesis levels are maintained for a few days, and the rate of decline is divergent between the different mitochondrial components.
- 著者
- Seitaro OHTSU Masamitsu YAMAGUCHI Hisashi NISHIWAKI Eiichiro FUKUSAKI Shuichi SHIMMA
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- pp.18SCP04, (Released:2018-06-29)
- 被引用文献数
- 12
3 0 0 0 OA ソ連ЛК-3掘進機使用実績について
- 著者
- 重光 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.941, pp.751-754, 1966-09-25 (Released:2011-07-13)
At Chikubetsu Coal Mine, we have begun excavation of prospecting mine road about 1, 700 meters long, using Russian PK-3 heading machine since February, 1966.There are some difficulties in working, e. g. maintenance of PK-3's loop-feeder and transporting debris cars, we could perform heading of mine road in coal seam 20 meters per day.
3 0 0 0 OA 未成年者を被保険者とする生命保険契約についての一考察
- 著者
- 菊池 直人
- 出版者
- 日本保険学会
- 雑誌
- 保険学雑誌 (ISSN:03872939)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.626, pp.626_127-626_144, 2014-09-30 (Released:2015-08-13)
- 参考文献数
- 26
日本では,未成年者を被保険者とする死亡保険契約について,保険法上特段の規定はなく,道徳危険については,保険者の自主規制や金融庁の監督によって対応がなされている。すなわち,保険金額の相当性および適切な引受・支払基準の構築,その遵守など,運用上の問題に収束したといえる。一方,諸外国に目を向けると,未成年者を被保険者とする死亡保険契約については,立法上制限を設ける例が多数みられる。多くの場合,意思能力の有無を判断材料とし,保険契約を禁止したり,保険金額を制限したりしている。これは,被保険者の同意とは,当該保険について了承する意思表示であるとともに,道徳危険を伴う保険についての自己決定であるとして,未成年者といえども代理による同意を実質的に認めない。我が国の未成年者の生命保険契約は,過去の事例からも道徳危険性は少ないとされてもいるが,意思能力の有無に基づく保険契約上の規制が必要であると思われる。