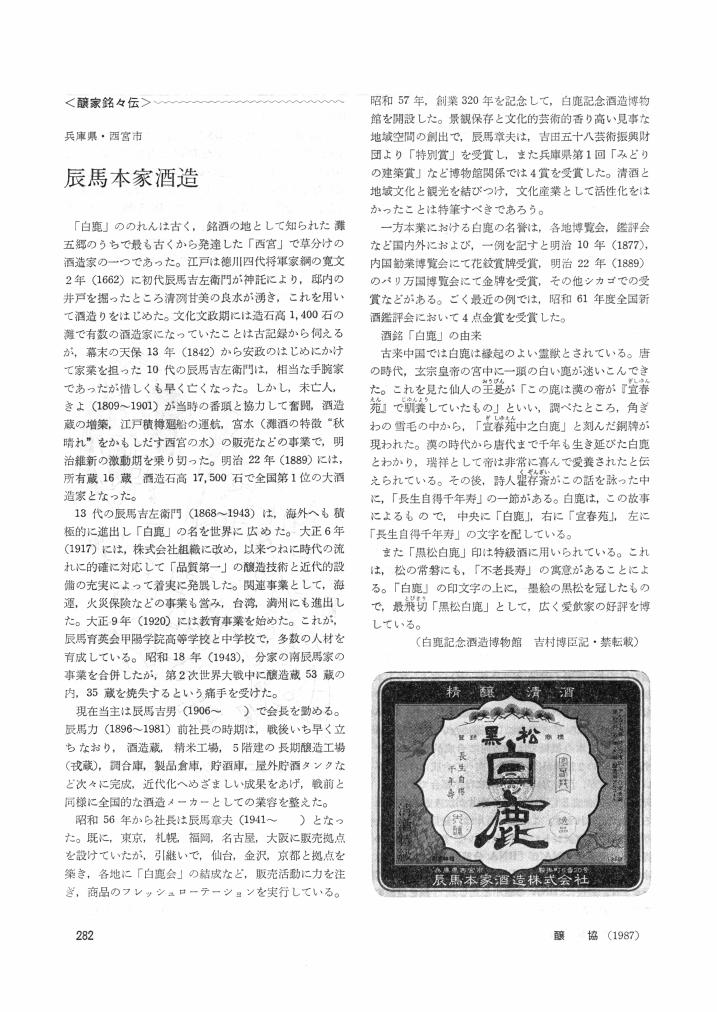2 0 0 0 OA 意思決定の葛藤をアセスメントするスクリーニングツールSURE test日本語版の開発
- 著者
- 大坂 和可子 青木 頼子 江藤 亜矢子 北 奈央子 有森 直子 中山 和弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.334-340, 2019 (Released:2020-03-14)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
目的:本研究の目的は,患者の意思決定の葛藤をスクリーニングするSURE(Sure of myself; Understand information; Risk-benefit ratio; Encouragement)test日本語版を,言語的妥当性を踏まえ開発することである.方法:SURE test日本語版は,第1段階:2名による順翻訳,第2段階:順翻訳統合,第3段階:2名による逆翻訳,第4段階:研究者協議(暫定版作成),第5段階:一般市民,医療者への調査,第6段階:再検討,を経て開発した.結果:暫定版作成後,第5段階の一般市民と医療者32名の調査において,「わかりやすい」と回答した割合は各項目で47%から78%であった.第6段階にて言語的妥当性を再検討し,日本語版を確定した.結論:一連の過程を経て,言語的妥当性を踏まえたSURE test日本語版を開発した.
2 0 0 0 OA 初期の聖書註解と本文批評
- 著者
- 手島 勲矢
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.33-44, 1995-09-30 (Released:2010-03-12)
Textual criticism of the Hebrew Bible is often described as requiring both “scientific” and “artistic” qualities in balance. However rigorously one conducts the weighing of essential data of manuscripts and witnesses and accounts for variants by textual principles, it is impossible to prove scientifically every textual decision one makes; it is particularly frustrating when one faces equally probable variants of MT, LXX, and the Qumran evidence, where any preference for one reading or another is arbitrary. This paper will argue that, in such a case, knowledge of early biblical interpretation can equip textual critcs with additional means to grade such ancient variants.For the proposed study I will use exegetical material from rabbinic and Second Temple texts to help determine what is a pristine reading and what are scribal variants. In particular, choosing a problematic biblical account of David and Bathsheba's incident, I will focus on textual variants of LXX (Lucianic and non-Lucianic readings), Targum, MT, and 4QSam concerning three specific parts of 2Sam 11: 2, 4: 1)_??__??__??__??__??_2)_??__??__??_3)_??__??__??_. Examining how these parts determine the understanding of the story as a whole in midrashim, a Talmudic discourse, Josephus' Jewish Antiquities, and the Damascus Document, and suggesting specific concerns of early biblical exegetes about these parts, I will try to show how the concerned variants address themselves to these exegetical concerns. In this way, the study proposes to determine the degree of tendentiousness in each variant, which will be a guideline to sort out a superior reading.Thus, the paper will not only stimulate fundamental thoughts as to the present practices of textual criticism but also expose the richness of early biblical interpretation of the biblical account in the exegetical problems as well as the solutions.
2 0 0 0 OA ラクトフェリン
- 著者
- 山内 恒治
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.193, 2006-03-15 (Released:2007-03-09)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 1
ラクトフェリン(LF)は,トランスフェリンと類似の構造をもつ分子量約80,000の鉄結合性の糖たんぱく質である.1939年にSørensenらによって牛乳の乳清画分から赤色たんぱく質として発見され,1960年に母乳と牛乳から単離された.LFは特に初乳での濃度が高く,たんぱく質中の数十%の割合を占め(図1),乳児(仔)の感染防御に重要な役割を果たしていると考えられている.また,涙や唾液などの外分泌液や白血球の一種である好中球にも存在する.LFの生理機能として,1)抗菌・抗ウイルス活性,2)ビフィズス菌増殖促進作用,3)免疫調節作用,4)抗酸化作用,5)鉄吸収調節作用などの多様な作用が知られている.抗生物質の場合,全ての細菌に抗菌作用を示し腸内ではその菌叢全体を死滅させるのに対して,LFは有害菌である大腸菌を抑制する一方,有用菌であるビフィズス菌に対しては増殖効果を示す.LFは胃の消化酵素であるペプシンによる加水分解を受け,より強い抗菌活性をもつペプチド“ラクトフェリシン®”が生成される.このペプチドは細菌や真菌など多くの病原菌に対して殺菌的な抗菌活性を示す.また,抗菌活性以外にも免疫調節作用など種々の生理活性を示し,LFの多様な機能の一端を担うペプチドと考えられている.近年の研究において,LF経口投与による種々の細菌,真菌に対する感染防御機能が明らかとなりつつある.その作用機序として,経口投与されたLFが腸管免疫系に作用し,免疫ネットワークを介して全身免疫系機能が亢進され,生体防御能が高まるものと考えられる.また,大腸はじめ,膀胱,食道,肺,肝臓についてモデル動物における発がん抑制効果が報告されている.ヒトにおいては,乳児におけるビフィズス菌叢の形成促進のほか,足白癬における皮膚症状の改善効果や,C型慢性肝炎における抗ウイルス作用の効果など,LF経口摂取による臨床試験成績が報告されている.LFは未加熱の牛乳には約20mg/100ml,ナチュラルチーズには約300mg/100g含まれており,長い食経験がある.ラットを用いた亜急性毒性試験において毒性は認められず,Ames試験,染色体異常試験,小核試験の遺伝毒性試験でも異常は認められていない.また,これまでの臨床試験においても特に副作用は認められず,ウシLFの食品としての安全性は極めて高いものと考えられる.LFの応用に当たっては,牛乳やチーズホエイを原料として,工業的規模で陽イオン交換カラムを用いた分離精製および膜処理技術を用いた脱塩・濃縮による高純度での生産が確立された.分離精製されたウシLF粉末は淡赤桃色の色調で無味無臭,水に対する溶解性は高く,溶解度は40%である.LFの水溶液は酸性条件では安定でpH4では90℃~100℃5分の処理でも変性しない事が見出された.本特性を利用することにより,活性を保持したLFを含有した食品の製造が可能となった.現在,LFは育児用ミルク,ヨーグルト,乳酸菌飲料,サプリメントなどに広く応用されている.機能性を持った食品よって生活の質の向上や疾病リスクの低減を図る動きは日本だけでなく欧米でも高まっており,今後の更なるエビデンスの蓄積に基づくLFの機能性食品への応用が強く期待される.
- 著者
- 鈴木 基雄 登内 道彦 村山 貢司 光本 浩太郎
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.281-289, 2005 (Released:2007-01-12)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
Durham method has been adopted widely in Japan as the measurement method for counting the number of pollens. However, it is a tedious method for researchers because they have to count the exact number of pollens on plates using a microscope. Therefore the number of pollens has been reported only once a day from most of the observatories. In order to obtain the hourly number of pollens for further researches, automatic pollen counters have been developed.We evaluated the performance of the pollen counter KP-1000 (Kowa Co. Ltd.), which had been developed by the project of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. In order to evaluate the capability for counting Cedar and Cypress pollen particles, we compared the number of pollens measured by KP-1000 with the number of pollens obtained by Durham method and the number of pollens caught on the outlet filter of KP-1000. Furthermore we compared the number of pollens measured by KP-1000 with the number of pollens counted by another pollen counter KH-3000 (Yamato Mfg. Co. Ltd.). The result of the comparison showed that KP-1000 could distinguish Cedar and Cypress pollens accurately.We found the high concentration of pollens in early mornings through the hourly observation of Cedar and Cypress pollens during the spring of 2005. By using the Backward Trajectory Method, we found that the high concentration phenomena of pollens were brought by the long distance transportation of pollens from Shizuoka area via Izu Peninsula and Kanagawa to Tokyo.
- 著者
- 生出 慶司
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.67-70, 1996-10-25 (Released:2018-03-29)
- 著者
- 永田 嘉代 新田 和枝 大沢 武志 井上 健治 柳井 晴夫 岡部 教子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第8回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.232-237, 1966-09-28 (Released:2017-03-30)
2 0 0 0 OA 農業高校の今日的存在意義に関する一考察
- 著者
- 佐々木 正剛 小松 泰信 横溝 功
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.84-93, 2001-09-25 (Released:2011-09-05)
- 被引用文献数
- 1 2
Recently, the meaning of the food-agriculture education has been pointed out drawing attention to the education power which agriculture has. An agricultural high school is an educational institution concerned with agriculture. However, its environment is severe. An agricultural high school is the best base facility for food-agriculture education.The followings were pointed out.Firstly, an agricultural high school provides a place for experience study. Secondly, it provides the region with an agricultural technology center and a life study center. Thirdly, it provides a broad network between agricultural high schools. Fourthly, as students are used as assistants, it provides a chance for them to develop their own education skills.
2 0 0 0 OA 老人福祉センターを利用する高齢者の足トラブルの実態と関連要因の分析
- 著者
- 狩野 太郎 小川 妙子 樋口 友紀 廣瀬 規代美
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.335-341, 2014-11-01 (Released:2015-01-07)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
【背景・目的】 本研究は, 老人福祉センターを利用する高齢者の足トラブルの実態と, 疾患及び足トラブル相互の関連を分析し, 足トラブルが発生するメカニズムの検討を目的とした. 【方法と対象】 利用者101名を対象に, 足部の観察と面接調査を行った. 足トラブルと疾患及び足トラブル相互の関連についてχ2検定を用いて分析した. 【結 果】 足トラブルは足部皮膚乾燥44.6%, 角質肥厚40.6%, 肥厚爪37.6%の順となっていた. 角質肥厚・足部皮膚乾燥・肥厚爪と高血圧に関連が見られた. 足トラブル相互の関連については, 角質肥厚と肥厚爪, 胼胝と巻き爪に有意な関連が見られた. 【結 語】 高血圧と足トラブルの関連については不明な部分が多いものの, 末梢循環の低下や降圧利尿剤による影響が考えられ, 足部皮膚乾燥や角質肥厚を有する者の割合が高いことから, 重点的フットケア指導が有用と思われる.
2 0 0 0 OA 「名塩蘭学塾」8年の重み
- 著者
- 小畑 登紀夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会
- 雑誌
- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.3-18, 2012 (Released:2012-04-20)
- 参考文献数
- 25
2 0 0 0 OA 女子やり投げ競技者における成功試技と失敗試技とが生じる動作要因の検討
- 著者
- 瀧川 寛子 堀内 元 田内 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.143-152, 2020 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to investigate motion factors in female javelin throwers during success and failure trials from a biomechanical standpoint. Fourteen throwers who participated in the Japanese Women’s Javelin Championships Final were investigated during both success trials and failure trials and the results were compared. The success trial was set as the best record and the failure trial as the worst record. Timing points of throwing motion were set at right foot contact (R-on), left foot contact (L-on) and javelin release (REL). The main results were as follows; 1) There was no significant difference in approach velocity between the success and failure trials. 2) In the success trials, peak speeds of the right shoulder, elbow joint and javelin were higher than those in the failure trials. 3) In the success trials, the left rotation velocity of the shoulder angle was larger than that in the failure trials just after L-on. 4) In the success trials, the forward rotational velocity of the trunk was larger than that in the failure trials just after L-on. 5) In the success trials, the throwers maintained a more extended position of the left knee angle than in the failure trials between L-on and REL. These results revealed that superiority or inferiority for female javelin throwers at the same competition level was determined not by the approach velocity, but by the blocking motion of the left leg. Although the importance of this left leg blocking motion has been reported many times in previous studies of throwers with different performance levels, it has been shown here to play an important role in the success of individual performance.
- 著者
- 藤田 正雄 波夛野 豪
- 出版者
- 日本有機農業学会
- 雑誌
- 有機農業研究 (ISSN:18845665)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.53-63, 2017-12-25 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 16
有機農業への新規および転換参入者を対象とするアンケート調査を2013年9月から12月に実施した.新規および転換参入ともに,参入のきっかけは「安全・安心な農産物を作りたい」が最も多く,販路を自分で開拓し,農業粗収益,実施面積も,参入時に比べ増加していた.しかし,栽培技術の未熟さが,新規,転換参入ともに経営安定の課題であった.また,有機農業の実施面積率では,新規参入者は開始時より100%実施しているという回答が多く,転換参入者は部分実施が多かった.販売先では,参入時において新規が消費者への直接販売,転換は農協・生協が多かったが,現在ではともに流通業者の割合が増加していた.有機農業者を増やすには,栽培技術の確立と地域の条件に応じた普及体制の整備が求められる.
2 0 0 0 OA 一元化される教師の〈語り〉
- 著者
- 伊勢本 大
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.259-279, 2018-05-31 (Released:2020-03-13)
- 参考文献数
- 27
本稿の目的は,研究協力者である教師たちの〈語り〉から「教師である」という物語がいかに構成されるのかを明らかにすることである。 日本社会において,批判対象として教職を捉えようとする論理が根強く存在する一方,教師の働き方を見直し,彼/女たちを救済しようとする動きも広まっている。これらのことからも示されるように,教師に対する世間のまなざしは錯綜している。そうした今日的状況において必要となるのが「教師であるとはどういうことなのか」という根源的な問いに,教師たちの〈語り〉から回答を示す試みである。 本稿を通して描かれるのは「教師である」ということが,教師個人が「献身的教師」をめぐる物語と対話し,その物語といかに折り合いをつけながら自らの職業アイデンティティを語ることができるのか,というフレキシブルな解釈・交渉実践だという側面である。それはつまり,教師たちが「教師である」ことを表現する個別の物語は,それぞれの形で紡がれる,開かれた可能性を有していることを意味する。 近年,教師の長時間労働の問題改善に向けて学校現場の働き方を見直すという方向で議論が進められている。しかし,教師の生きやすい現実を形作る上では,まず彼/女たちを一人の人間として理解することが何よりも重要となる。本稿の議論は,これまで教育社会学において十分に関心が寄せられてこなかった,教師の個別性を保障するための枠組みの意義を示唆している。
2 0 0 0 OA 浸漬温度と白米および蒸米の吸水性
- 著者
- Norihide Sugisaki Hiroaki Kanehisa Kenji Tauchi Seita Okazaki Shigeo Iso Junichi Okada
- 出版者
- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences
- 雑誌
- International Journal of Sport and Health Science (ISSN:13481509)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-7, 2011 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 9 24
The purpose of this study was to investigate the relationship between 30-m sprint running time and muscle cross-sectional areas of the psoas major and lower limb muscles. In sixteen male college short and middle distance runners, the muscle anatomical cross-sectional areas (CSAs) of the psoas major, the quadriceps femoris, the hip adductors (ADD), the hamstrings, the triceps surae, and the tibialis anterior and extensor digtrum longus complex (DF) were measured using a magnetic resonance imaging system. In addition, the relative values of CSA to the two-thirds power of body weight (CSA-to-BW2/3) were calculated. A stepwise multiple regression analysis produced a prediction equation (R2=0.605) of 30-m sprint running time with explanatory variables of ADD CSA-to-BW2/3 and DF CSA. The ADD CSA-to-BW2/3 had a negative partial regression coefficient (r=−0.768, p<0.01) and the DF CSA had a positive partial regression coefficient (r=0.526, p<0.05). From the present results, it is concluded that to have greater hip adductor muscles relative to the body size and smaller dorsiflexors is advantageous for achieving higher performance in 30-m sprint running.
- 著者
- 児玉 由佳
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.26, 2020-03-05 (Released:2020-03-05)
2 0 0 0 OA 帝王切開で出産した女性の妊娠中から産後1か月までの心理的プロセス―覚悟と納得―
- 著者
- 谷口 綾 大久保 功子 齋藤 真希 廣山 奈津子 小田柿 ふみ 三隅 順子
- 出版者
- Japan Academy of Nursing Science
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.94-102, 2014-03-20 (Released:2014-05-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 1
目的:帝王切開で出産した女性の,妊娠中から産後1か月までの帝王切開に対する心理的プロセスとその影響要因を明らかにし,看護支援への示唆を得ることを目的とした.方法:グラウンデッド・セオリー・アプローチを用い,帝王切開後の女性18名に半構造化面接を行って分析し理論化を試みた.結果:女性は帝王切開に対する〈心づもり〉と〈意味づけ〉のプロセスをたどることで,帝王切開に対する〔覚悟〕と〔納得〕に至る.それらは〈帝王切開の可能性の認識〉をした時点から始まり,〈手術への恐怖〉や〈自然分娩への未練〉は阻害要因,医療者や経験者とのやりとりは促進要因となる.〈意味づけ〉は分娩後にも続く.緊急帝王切開では〈心づもり〉や〈意味づけ〉ができないまま手術に臨む場合があるが,〔納得〕するためには,分娩後に〈意味づけ〉が行われる.考察:帝王切開に対する〔覚悟〕と〔納得〕の理論を軸に,〈心づもり〉と〈意味づけ〉を促すような具体的な看護支援が示唆された.
2 0 0 0 OA 塩および海水の資源的開発 特集 (2)
- 著者
- 鈴木 篁
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.5, pp.274-278, 1966 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- 杉山 寿美 三宅 彩矢 多田 美香 水尾 和雅 都留 理恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.64-71, 2011 (Released:2014-08-08)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
加熱過程および保存過程における煮汁に含まれるコラーゲン,グリセリド,塩化ナトリウムの大根への浸透と大根の硬さについて検討した。その結果,加熱過程では大根の重量が減少すること,グリセリドおよびコラーゲンは大根内部へほとんど浸透しない一方,塩化ナトリウムは速やかに浸透することが示された。グリセリド,コラーゲン,塩化ナトリウムのいずれも大根表面部と内部の量は有意に異なっていた。また,加熱温度が高く,加熱時間が長い場合は内部よりも表面部が硬いことも示された。保存過程では,温蔵,冷蔵保存のいずれでも大根の重量が増加すること,大根表面部と内部の塩化ナトリウム量の濃度差が認められなくなる一方,グリセリドおよびコラーゲン量には差が認められること,大根表面にはコラーゲンが温蔵保存で浸透し,グリセリドが冷蔵保存で表面に付着することが推察された。これらのことから,保存過程が煮物のおいしさに影響することが推察された。
2 0 0 0 OA 辰馬本家酒造
- 著者
- 吉村 博臣
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.282, 1987-04-15 (Released:2011-11-04)
2 0 0 0 OA 足内側縦アーチに対する後脛骨筋の効果
- 著者
- 高田 雄一 神谷 智昭 渡邉 耕太 鈴木 大輔 藤宮 峯子 宮本 重範 内山 英一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Ab0445, 2012 (Released:2012-08-10)
【はじめに、目的】 足のアーチ構造は1Gの重力場でヒトの歩行時に有用な働きをしている。後脛骨筋は足アーチを支える重要な動的支持組織であると報告され、後天性扁平足の主な原因は後脛骨筋機能不全だと言われている。足ア−チは骨・関節・靱帯による静的なサポートと筋肉による動的なサポートが互いに協力することにより、重力に逆らい直立二足歩行する人体の重さを支えている。適度な弾性をもった足ア−チは歩行時の衝撃を緩和し、より中枢の関節を保護している。この力学的特性を解明するためには、1回の荷重負荷試験から求められる足アーチの単なる破断強度ではなく、日常生活で実際に骨・関節・靱帯にかかる生理的負荷領域での繰り返し負荷試験(fatigue test,疲労試験)により足アーチの疲労特性を調べることにより、はじめて、より適切な生理的負荷領域での足アーチの力学特性を解明することができる。本研究の目的は反復垂直荷重時に、足内側縦アーチに対する後脛骨筋の動的な効果を検討することである。【方法】 未固定凍結下肢標本を14肢使用した。平均年齢は82歳(59-92歳)だった。標本は7肢ずつ、後脛骨筋牽引群と後脛骨筋非牽引群の2群に分けた。足アーチの疲労特性を計測するために、医療機器開発メーカーであるメディセンス(株)と共同で繰り返し荷重システム、制御・解析アプリケ−ションの開発を行った。万能試験機(株式会社 島津製作所,AG-I)、LEDマーカ(株式会社 パナソニック,1.6 x 0.8 mm 矩形赤色発光ダイオード)とCCDカメラ(株式会社メディセンス,解像度640x480 pixels)で構成する微小変位解析システム、反復荷重負荷システムと組み合わせによる繰り返し荷重−変位解析システムの開発を行った。下腿を中1/3で切断し、専用ジグで固定した標本に万能試験機を用いて、0-500N,1Hzで反復軸荷重を10,000サイクル負荷した。舟状骨高の計測は舟状骨内側に設置したLEDの位置情報を経時的に測定し、それを座標軸に変換して記録した。後脛骨筋牽引群は軸荷重に同期したステップモ−タ(株式会社 メディセンス,最大トルク 6 kg・cm, 回転速度 60 deg / 0.1 sec)荷重負荷システムを用い後脛骨筋腱中枢部をワイヤーでロ−ドセルを介して反復荷重した。そして垂直荷重に同期して、後脛骨筋の筋収縮を模した0-32Nの牽引力が発生するように設定した。最小荷重時と最大荷重時の足ア−チの高さの変化は舟状骨高を足底長で除したBony Arch Index(BAI)で評価し、BAI<0.21をlow archとした。後脛骨筋牽引群と後脛骨筋非牽引群でそれぞれ1,000 cyclesごとの値で両群間を比較し、統計処理はstudent‘s t-test により、有意水準は 5%とした。【倫理的配慮、説明と同意】 遺体は、死亡後24時間以内に本学医学部解剖学第二講座に搬送され、本人の生前同意と死亡後の家族の同意が得られている。【結果】 最大荷重時BAIの初期値は後脛骨筋牽引群0.239±0.009、後脛骨筋非牽引群0.239±0.014だった。両群共に最初の1,000サイクルでBAIは大きく低下した。その後、後脛骨筋牽引群の平均BAIはほぼ一定の値で経過し、10,000サイクルで0.212±0.011となった。一方で後脛骨筋非牽引群のBAIは徐々に低下し続け、3,000サイクルでlow archの基準となるBAI<0.21になった。7,000サイクル以降で両群間に有意差を認め、後脛骨筋牽引群は内側縦アーチが維持されていた。【考察】 本研究結果で後脛骨筋牽引群の平均BAIは、最終的に荷重時BAI>0.21を維持した。このことは反復荷重条件においても後脛骨筋が内側縦アーチ保持に重要であることを示した。一方、後脛骨筋非牽引群では最終的にlow archの基準に至ったことから、静的支持組織のみでは内側縦アーチ保持が困難であることがわかった。【理学療法学研究としての意義】 本研究は扁平足変形の主原因である後脛骨筋機能不全に対する運動療法やその予防に有用な情報を提供すると考えられた。