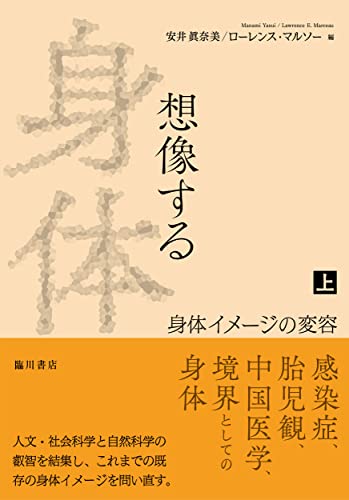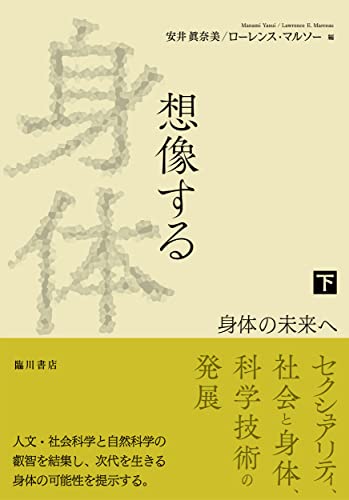2 0 0 0 OA 躯幹と顔面の角度が意識性に及ぼす影響
- 著者
- 鈴木 晶夫 春木 豊
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.378-382, 1992-02-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 8 4
Posture is a nonverbal behavior and a universal means of animal and human communication. It is observed not only in interpersonal communication but in clinical situation. Our recent research shows that posture affects the mood and emotional awareness of the subjects. This study compared the subjects' awareness between two groups, the operational group (actual posture) and the image group, which only imagined a postural change. Six kinds of posture were adopted. These postures included two dimensions; inclination of trunk (straight or bent), and head (up, front or down). In these conditions the subjects estimated their mood and emotional awareness with 17 pairs of adjectives on a 3 point scale. The results of ANOVA showed statistically significant differences in conditions of both inclination of trunk and head. Especially, when the subject bent his back while hanging his head, this made most feeble, lifeless, and shadowy mood than any other postures. The authors confirmed that posture exerted a strong influence on one's emotional awareness.
2 0 0 0 OA ヒラメ・カレイの体の左右非対称性と内蔵・脳の左右非対称性形成との関わり
- 著者
- 鈴木 徹 橋本 寿史 有瀧 真人 宇治 督 黒川 忠英
- 出版者
- Japanese Society of Animal Breeding and Genetics
- 雑誌
- 動物遺伝育種研究 (ISSN:13459961)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1-2, pp.47-57, 2005-12-01 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 31
2 0 0 0 OA 帝政ロシアの民族政策 : 18世紀のヴォルガ流域とウラル
- 著者
- 豊川 浩一
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.73-96, 1992
2 0 0 0 OA 金融政策と金融機関の健全性
- 著者
- 植田 宏文 Hirofumi Ueda
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.875-898, 2021-03-12
鈴木良始教授古稀祝賀記念号(Honorable issue in commemoration of Prof. Yoshiji Suzuki's 70 years of age)
- 著者
- 石灘 早紀
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.33-60, 2022-12-15 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 43
インフォーマル経済は多くの国ぐにで,当局から黙認あるいは容認されながら行われてきた。一方,それとは異なるあり方も存在している。本稿では,当局がインフォーマル経済に対して人道的観点から規制を行うことが,従事者にどのような影響を与えるかについて,スペイン領セウタとモロッコの国境地帯で行われていた「密輸」の事例をもとに考察する。「密輸」は,関税を支払わずにセウタからモロッコに商品を持ち込むものであるが,当局が事実上管理し,従事者の労働環境の改善を目指した規制を行ってきた。このような規制が従事者に及ぼす影響を,越境者やジェンダーの視点も取り入れながら論じる。本稿は,人道的観点からなされた規制が従事者の収入を減らし,従事者をより周辺的な経済活動に追いやるという再周辺化を引き起こしたことを明らかにした。そのような再周辺化の深刻度は,越境者や女性といった脆弱な属性をもつことにより増していた。
2 0 0 0 OA アートの理解と塚田の時空間学習則
- 著者
- 毛内 拡 塚田 稔
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.112-118, 2022-09-05 (Released:2022-10-05)
- 参考文献数
- 13
本稿では,2021年に神経回路学会の名誉会員にご就任され,2022年の日本神経回路学会学術賞を受賞された塚田稔先生の業績を,「神経科学とアートの理解」という観点から紹介する.塚田先生は,玉川大学名誉教授で,日本神経回路学会の設立にもご尽力された.研究では,Hebb則と双璧をなす,脳で行われている学習の基礎原理である時空間学習則に関する多くの研究を,理論と実験の両側面から主導してきた.また,現役の画家でもあり,数多くの賞に入選し,大学や研究所,ホテル,個人などに多くの作品が収められている.アートを生み出し,理解する脳のしくみについても示唆に富んだ提案をされており,代表的な著書に「芸術脳の科学~脳の可塑性と創造性のダイナミズム~」(講談社ブルーバックス,2015)がある.この度著者(毛内)は,大変幸運なことに,塚田先生のご自宅のアトリエに伺い,直接インタビューを行う機会をいただいた.本稿は,そのインタビューの一部を解説記事としてまとめたものである.絵画を見ているときに脳のどこが働いているのか,神経科学的に考えてから見て絵画がわかるとはどういうことなのかを,「塚田の脳の自己組織化と芸術」の観点からご解説いただき,今後の展開についてもご紹介いただく.
- 著者
- 毛利 康秀
- 出版者
- コンテンツツーリズム学会
- 雑誌
- コンテンツツーリズム学会論文集 (ISSN:24352241)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.13-23, 2017 (Released:2021-08-27)
本稿は、コンテンツツーリズム領域における歴史的・社会的知見の積み増しを目指して、絵葉書のメディア的な機能に着目し、観光資源としての分類法を確認しつつ、絵葉書が近代観光の発達に果たした役割、特にコンテンツツーリズムの発達に及ぼした影響に関する再評価を試みた。 コンテンツの意味するところは幅広いが、観光資源としてのコンテンツという視点から見た場合、「地域イメージと結びつき、その地域を訪れる動機となる情報内容」が相当し、それは小説や映画・ドラマなどのオリジナル作品(一次コンテンツ)、作品を二次利用した無形・有形の関連物(二次コンテンツ)に分類することが出来る。さらに、関連する記事、批評、評判情報、ファンの意見交換などのコミュニケーション活動全般もコンテンツと見なすことが可能であり(三次コンテンツ)、この3種に分類されるコンテンツ群はいずれもコンテンツツーリズムを発達させる重要な要素となる。 ここで、コンテンツとしての絵葉書に着目すると、絵葉書は画像情報とともに信書を伝達出来るメディアであり、パーソナルメディアとしてはもちろん、画像情報を広く拡散するマスメディアとしての側面も有しており、特に黎明期にはその傾向が強かった。それ自体がコンテンツとしての性格を帯び、有力な観光資源にもなっている。 本稿では、主に戦前期から戦後にかけての熱海・那須塩原(金色夜叉)、下田(唐人お吉)、ハルビン(ハルピン見物)の絵葉書を事例として検討を行った。作品のモデルとなったそれぞれの地域において風景写真の絵葉書が大量に制作され、近代観光の体験を共有するメディアとして流通していたが、それに加えて作品世界を表現した絵葉書や作品のモデル地をあしらった絵葉書が作られ、さらには地域イメージを表象したオリジナル作品と呼ぶべき絵葉書も作られていた。すなわち絵葉書は、作品世界の創造(一次)、作品世界の二次的表現やモデル地の表現(二次)、関連コミュニケーション(三次)という、コンテンツの類型の全てをカバー出来るメディアであり、コンテンツツーリズムの発展に寄与するメディアでもあったと再評価することが可能である
- 著者
- IVINGS Steven
- 出版者
- International Research Center for Japanese Studies
- 雑誌
- Japan Review : Journal of the International Research Center for Japanese Studies (ISSN:09150986)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.187-189, 2022-12
2 0 0 0 OA 補償的消費研究の整理と今後の研究
- 著者
- 速水 建吾
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.54-62, 2022-09-30 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
近年,自己不一致によって生じる脅威に対する消費者の反応に着目した研究が注目を集めている。こうした自己不一致による脅威と消費者の反応は消費者行動研究の領域において,補償的消費という概念で捉えられている。本稿では,2017年から2022年の間に発表された補償的消費に着目した研究をレビューした。これにより既存研究の知見を統合し,既存研究に残された「対処方略の決定要因」に関する課題,「逐次的な補償的消費」に関する課題,企業や社会にとって「ネガティブな消費者の行動を導く対処方略を回避する方法」に関する課題の3つの課題を明らかにした。また最終節では既存研究の課題をもとに今後の研究の方向性を議論した。
2 0 0 0 身体イメージの変容
はじめに 身体イメージの変容を考える / 安井眞奈美, ローレンス・マルソー 第I部 感染症を考える1章 疫病の語彙 : 病因としての「毒」と「虫」 / 香西豊子2章 安政六年京都のコレラ流行と御千度 / 鈴木則子3章 「何より清潔、よく顔を洗へ」 : 近代日本におけるトラホームについて / アストギク・ホワニシャン4章 植民地支配における感染症対策 / 財吉拉胡コラム 新型コロナ感染予防対策としてのマスク着用と身体イメージ / 波平恵美子第II部 産む身体・産まれる身体1章 妊婦と胎児の身体を可視化する : 明治時代初期の錦絵を中心に / 安井眞奈美2章 死体から生まれた赤子 : 戯作に見る母と子の身体 / 板坂則子コラム 江戸の乳と生殖・胎児観 / 沢山美果子3章 「もの言う赤子」と予言する身体 : 鬼子、予言児、件の系譜 / 今井秀和4章 胎児観の変遷 : 身体と魂をめぐって / 鈴木由利子インタビュー 産科医療における胎児のイメージ / 遠藤誠之, 安井眞奈美第III部 身体を把握する1章 異相と観相と肖像画 : 『論衡』の受容と男女の相に関連して / 相田満2章 生と死の境界 : 江戸時代鍼灸銅人形における身体観念 / 姜姗, 稲田健一3章 境界としての身体 : 外邪・怪異と内なる神々の交錯するトポス / 越智秀一コラム 江戸時代解剖図と絵画表現の境界 / 木森圭一郎4章 芸術と民族学の不協和音 : ポール・ジャクレーが描くミクロネシアの人びとの皮膚 / 桑原牧子インタビュー 発生学の立場から妖怪「一つ目小僧」を解明する / 高橋淑子, 安井眞奈美 共同研究会一覧索引執筆者一覧
2 0 0 0 身体の未来へ
はじめに 身体の未来へ / 安井眞奈美, ローレンス・マルソー 第I部 表象される身体・セクシュアリティ1章 近世日本の絵入文学における身体像 : 形と機能 / ローレンス・マルソー2章 自然を男女になぞらえる : 宮負定雄「陰陽神石図」と平田国学を中心に / 石上阿希コラム 狸と精神 / 井上章一ディスカッション 「性器崇拝」の時空間 : 「狸の金玉」を中心に / 井上章一, 安井眞奈美, ローレンス・マルソーコラム 武術の極意を自然現象に喩える / 山田奨治3章 布・衣服との関係からみる奪衣婆信仰の展開 / 坂知尋コラム 広告としての「少女」の身体 : ポスター《森永ミルクチョコレート》(一九三七年)を手がかりに / 前川志織第II部 社会を動かす身体1章 近代日本における身体障害の表象 : 盲・聾・唖のイメージをめぐって / 木下知威2章 音楽を纏う身体 : 近代精神科医療における音楽療法実践をめぐって / 光平有希3章 戦時下の国民身体管理と産婆会 : 人的資源確保政策を中心に / 阿部奈緒美4章 松本清張の小説における殺人犯罪と「法医学」 / 金容儀5章 使い分けられる身体 : 虚偽の出家主義と僧侶の妻帯 / 川橋範子コラム スポーツ空間の形状と身体 : 「逃げ場」を巡る丸と四角 / 田里千代第III部 未来を築く身体1章 産む身体の諸相 : リプロダクションのコンテクストをめぐって / 松岡悦子2章 医療の中の死者と身体 : 病院における死後の処置を通して / 中本剛二3章 認知症診療における身体イメージの創出 : 画像診断によるアルツハイマー型認知症の描出と実体化 / 倉田誠4章 視覚による身体のイメージと制御 : 自己運動感覚と姿勢制御に関する心理実験からの考察 / 蘆田宏インタビュー バーチャルミュージアムによって拡張されるアート / 伊藤謙, 五十里翔吾, 武澤里映, 布施琳太郎結語にかえて 未来を生き抜く<身体>の可能性へ / 安井眞奈美, ローレンス・マルソー 共同研究会一覧索引執筆者一覧
2 0 0 0 OA 熊谷圭知著『パプアニューギニアの「場所」の物語―動態地誌とフィールドワーク―』
- 著者
- 杉江 あい
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.164-165, 2020 (Released:2020-07-23)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 御神渡りの発生と成長発達について
- 著者
- 東海林 明雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.403-419, 2021 (Released:2022-02-16)
- 参考文献数
- 36
御神渡りは諏訪湖が有名で,20世紀初頭から研究記録があり,その成因は,氷板の熱収縮・膨張により「その隆起は氷温の上昇による,熱膨張によって起る」,つまり「氷温上昇時の昼間に起こる」とされて来た.そして,この成因論が「従来説」として一世紀に亙って踏襲されてきた.しかし,浜口は,この説が観測データによらない推論であった事に着目して,新しい成因論を提起した.その理論は,火山物理学と地震学的観点をもとにしている.それによると,御神渡りの隆起は「氷温低下時の夜間に起こる」ことになり,従来説の昼間とは逆の結果になる.本報では,これまでの屈斜路湖の御神渡りの割れ目幅の定量的観測やビデオカメラによる御神渡り発生映像記録,さらに最近の現地での観測による検証によって,夜間冷却時の氷板収縮時に開いた水面で新たな氷が生成され,昼間の氷温上昇時の氷板膨張により御神渡りは発生することを実証した.また,従来の研究は,御神渡り発現(発生)時の研究に留まっていた.本報では,一旦発現した御神渡りのその後の成長発達の観測記録を取得し,成長発達の基本プロセスを解明できたと考える.
2 0 0 0 OA 小学生における立位姿勢と座位姿勢の特徴
- 著者
- 小山 浩司 古島 弘三 菅野 好規 新津 あずさ 小太刀 友夏 新納 宗輔 上野 真由美 高橋 英司 足立 和隆
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.443-453, 2022-10-01 (Released:2022-09-13)
- 参考文献数
- 31
Previous studies have reported that poor posture can induce various musculoskeletal disorders. Recently, poor posture in children has become a problem. This study aimed to determine the characteristics of sagittal spinal alignment in standing and sitting positions in elementary school students and how spinal alignment changes from standing to sitting position. Moreover, it clarifies how poor posture (hyperkyphosis) in the standing position affects sitting posture. This study was conducted among 83 elementary school students. The Spinal-Mouse® System was used to measure the thoracic kyphosis angle (TKA), upper thoracic angle (UTA), lower thoracic angle (LTA), lumbar lordosis angle (LLA), and sacral anteversion angle (SAA) in the standing and sitting positions. Hyperkyphosis was defined as a thoracic kyphosis angle of >40°. Participants were assigned to two groups: hyperkyphosis and non-hyperkyphosis. Significant differences were noted in all spinal alignment characteristics in both the positions. When spinal alignment was changed from standing to sitting, ΔUTA and ΔLTA correlated with ΔLLA and ΔSAA, respectively. A strong negative correlation was noted between ΔLLA and ΔSAA. In the sitting position, TKA, UTA, and LLA were significantly higher in the hyperkyphosis group than in the non-hyperkyphosis group. ΔUTA was significantly higher in the hyperkyphosis group than in the non-hyperkyphosis group when spinal alignment was changed from standing to sitting. The characteristics of sagittal spinal alignment in the sitting position were significantly different from those in the standing position. The study findings suggest that poor posture (hyperkyphosis) in the standing position affects the sitting posture.
2 0 0 0 OA 学校不適応傾向の児童・生徒に対するアニマルセラピーの心理的効果についての分析
- 著者
- 飯田 俊穂 熊谷 一宏 細萱 房枝 栗林 春奈 松澤 淑美
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.11, pp.945-954, 2008-11-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 19
動物とのふれあいが人によい効果をもたらすことは知られている.特に子ども・障害者・高齢者などによい効果をもたらすことが新聞,雑誌などで取り上げられており,不安やストレスの軽減効果が示されたとの報告や,ペットといるだけで精神状態が安定し自然治癒力が高まるなどの報告もある.そこで今回われわれは,学校不適応傾向の児童・生徒に対するアニマルセラピーの心理的効果についての分析を試みた.結果として3回以上のアニマルセラピーで,Profile of Mood States(POMS)(緊張-不安,活気,疲労,混乱),AN-EGOGRAM(NP,FC,AC)に有意な変化を認めた.POMS(抑うつ-落ち込み,怒り・敵意)の値は低下,AN-EGOGRAM(CP,A)の値は上昇したものの有意差は認めなかった.以上のことより,アニマルセラピーを3回以上施行した症例に対し,心理状態(緊張-不安,活気,疲労,混乱)の改善,自我状態の安定傾向を認めた.
2 0 0 0 OA 生体インピーダンスによる妊婦の体水分と妊娠·分娩期の異常との関連:パス解析を用いた検討
- 著者
- 中田 かおり 堀内 成子
- 出版者
- 一般社団法人 日本助産学会
- 雑誌
- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.78-88, 2016 (Released:2016-09-01)
- 参考文献数
- 19
目 的 生体インピーダンスによる妊婦の体水分と関連のある妊娠・分娩期の異常(切迫早産,妊娠高血圧症候群(PIH),低出生体重等)を探索し,関連を検討する。対象と方法 妊娠26週から29週の健康な単胎妊婦を対象とした。データ収集は,妊娠26~29週と妊娠34~36週の妊娠中2回と,分娩終了後に実施した。生体インピーダンスの測定には,マルチ周波数体組成計を使用した。妊婦の体水分と関連のある生理学的検査値と妊娠・分娩経過に関するデータは,質問紙と診療録レビューにより収集した。変数間の関連は,パス解析により検討した。結 果 研究協力の承諾を得られた340名の内,332名を分析対象とした。生体インピーダンスとの関連性が示唆された妊娠・分娩期の異常は,「切迫早産およびその疑い(妊娠26~29週の測定後から妊娠34~36週の測定まで)」(p結 論 体水分をあらわす指標と生体インピーダンスおよび,特定の妊娠・分娩期の異常との関連性が示唆された。しかし,異常の予測につながる指標の組み合わせは特定できなかった。今後,妊婦の生活やリスク発見後の対応を考えながら,妊娠期の健康につながる体水分評価指標の組み合わせや基準値を探索する,基礎研究が必要である。
2 0 0 0 OA ヒト声帯筋の筋線維構成: 筋線維型の比率
- 著者
- 木村 忠直 永井 真由美 白石 葉子 白石 尚基 猪口 清一郎
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.601-609, 2000-10-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 29
声帯筋を含む甲状被裂筋における横断面の100ポイントから求めた単位面積1mm2あたりの筋線維数は, 男女25例 (♂14, ♀11) の平均値で639.8±48.6であった.収縮機能が異なる筋線維型の比率の平均値は, 緊張性収縮と持久力を有するタイプIの赤筋線維が43.7%で最も高かった.次いでタイプIとIIの両形質を示すタイプIIIの中間筋線維が28.8%, 速動性と瞬発力を発揮するタイプIIの白筋線維が27.6%となり, タイプIの赤筋線維の割合は有意に高かった.また筋線維型の性差を比較すると女性ではタイプIIIの中間筋線維が, わずかに高いのに対し, 男性ではタイプIの赤筋線維とタイプIIの白筋線維が高かったが, それぞれ有意差はみられなかった.また甲状被裂筋と前脛骨筋との比較では, 甲状被裂筋の赤筋線維が有意に高かった.以上の結果よりヒトの発声に関与している声帯筋を含む甲状被裂筋はタイプI型の赤筋線維の比率が多い筋であることが示された.
- 著者
- Takuma Tsukioka Kiyotoshi Inoue Hiroko Oka Shinjiro Mizuguchi Ryuhei Morita Noritoshi Nishiyama
- 出版者
- The Editorial Committee of Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery
- 雑誌
- Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISSN:13411098)
- 巻号頁・発行日
- pp.oa.12.01986, (Released:2012-12-26)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 7 12
Purpose: Pleurodesis continues to play a central role in the management of pneumothorax. In our institute, a 50% glucose solution is used for pleurodesis. We retrospectively analysed the treatment effects of pleurodesis in patients with spontaneous pneumothorax in whom an operation was contraindicated because of underlying disease.Methods: 13 patients (18 cases) with spontaneous pneumothorax were treated with pleurodesis with a 50% glucose solution. After local anesthesia of parietal pleura, 200 to500 mL of a 50% glucose solution was instilled into the pleural space. Pleurodesis was repeated two or three times, until the air leakage stopped.Results: Air leakage stopped in all cases and there were no treatment-related deaths.Overall survival rates at 1, 2, and 3 years after treatment were 83%, 74%, and 49%, respectively. Post-treatment recurrence was observed in six cases. Four cases of recurrence were treated with pleurodesis with a 50% glucose solution. All cases of recurrence occurred within 3 months after pleurodesis.Conclusion: Pleurodesis with a 50% glucose solution is effective and safe in patients with pneumothorax. This procedure can be performed in patients with recurrent pneumothorax as well as patients with a first episode of pneumothorax in whom prolonged air leakage is predicted.
2 0 0 0 民放
- 著者
- 日本民間放送連盟 [編集]
- 出版者
- 日本民間放送連盟
- 巻号頁・発行日
- 1971
- 著者
- Junji Seto Yoko Aoki Kenichi Komabayashi Yoko Ikeda Mika Sampei Naomi Ogawa Yumiko Uchiumi Shunji Fujii Masami Chiba Emiko Suzuki Tatsuya Takahashi Keiko Yamada Yoshiko Otani Yoshihiro Ashino Kyoko Araki Takeo Kato Hitoshi Ishikawa Tatsuya Ikeda Hideaki Abe Tadayuki Ahiko Katsumi Mizuta
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.6, pp.522-529, 2021-11-22 (Released:2021-11-22)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2 6
Public health interventions have played an important role in controlling coronavirus disease 2019 (COVID-19), which is a rapidly spreading infectious disease. To contribute to future COVID-19 countermeasures, we aimed to verify the results of the countermeasures employed by public health centers (PHCs) against the first wave of COVID-19 in Yamagata Prefecture, Japan (Yamagata). Between January and May 2020, 1,253 patients suspected of SARS-CoV-2 infection were invited for testing. Simultaneously, based on retrospective contact tracings, PHCs investigated the infection sources and transmission routes of laboratory-confirmed COVID-19 cases and tested 928 contacts. Consequently, 69 cases were confirmed between March 31 and May 4, 58 of whom were from among the contacts (84.1%; 95% confidence interval [CI] 75.5–92.7). The spread of infection was triggered in cases harboring epidemiological links outside Yamagata. Subsequently, the number of cases rapidly increased. However, PHCs identified epidemiological links in 61 (88.4%; 95% CI 80.8–96.0) of the 69 cases, and transmission chains up to the fifth generation. Finally, the spread of infection ended after approximately one month. Our results indicate that the identification of infection sources and active case finding from contacts based on retrospective contact tracing was likely to be an effective strategy in ending the first wave of COVID-19 in Yamagata.