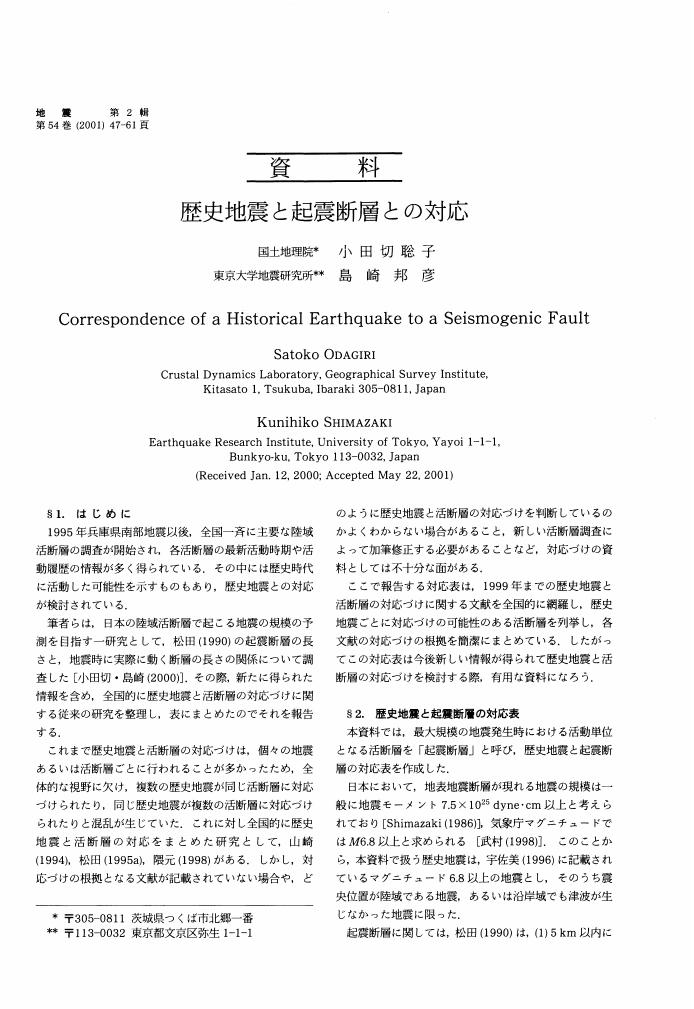2 0 0 0 OA 蝦夷地紀行の食文化考
- 著者
- 川井 美佳 池添 博彦
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.23-34, 1996-03-25 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 18
2 0 0 0 OA 建築デザイン教育に学ぶ景観デザイン教育のありかた
- 著者
- 重山 陽一郎
- 出版者
- University of Tokyo (東京大学)
- 巻号頁・発行日
- 2004-05-20
■研究の背景と意義// 「景観デザイン(土木分野で主に「美」を対象としたデザイン)」は、まだまだ若い分野であり、景観デザインを担う人材は全く不足している。// また、大学の土木関連学科では設計に関する職能教育をほとんど行っていないため、卒業してもプランニングもデザインもできない。このような訓練は就職後の実務教育に任されてきたが、社会情勢が変化し、企業は新人を一から教育する余裕をなくしつつある。これからの大学の土木関連学科では、計画や設計の能力を育成し、就職直後からある程度の戦力となるようにしなければならない。// しかし、優れた景観デザインの専門家を育成する方法は未だ確立されておらず、そのレベルは他の領域よりも明らかに低い。本研究は、景観デザイン教育のありかたを明らかにすることによって、短期的には優れた景観デザインの担い手の育成を、長期的には優れた景観の創出を志すものである。//■研究の目的と方法// 景観デザイン教育は、既に少数の大学において実行されている。これらの教育は、建築デザイン教育などを手本とし、大学教員や実務設計者との議論をふまえて構築されている。その過程で、景観デザイン教育のありかたについては、経験的にだいたい分かっていることが既にいくつかある。本研究の目的は、この「だいたい分かっていること(初期案)」を検証し、改良を加えて新たな景観デザイン教育のあり方を提案することである。// 検証の第1の方法は、建築デザイン教育に関する調査である。デザイン教育の点では、建築学は、土木工学よりもはるかに先輩であり、景観デザイン教育について考えるには、まず、建築デザイン教育について学ぶ必要がある。建築デザイン教育と、そこから育った人材、成果としての建築物などを調査・分析することにより、建築デザイン教育の特徴や課題を浮き彫りにし、翻って、従来の土木デザイン教育との比較を行うことにより、景観デザイン教育のあり方を検証する。第2の検証方法は、筆者が現在携わっている景観デザイン教育の経験に基づくものであり、初期案の改良を提案する。//■研究の枠組み// 本研究の枠組みを、図1に示す。// 本研究では、まず第1章「序章」で研究全体の背景や目的、研究の枠組みについて整理した。また、既往研究を概観し、景観デザイン教育について、既にだいたい分かっていることを整理し「景観デザイン教育のありかた:初期案」としてまとめた。// 第2章「優れた建築家の学歴・職歴」、第3章「インタビューによる建築デザイン教育の調査」、第4章「教員とカリキュラムの大学間比較」、第5章「建築デザインの評価基準の特徴と課題」では、上記の「初期案」を検証するために、建築デザインと建築デザイン教育について調査を行い、それを参考にして、景観デザイン教育のいくつかの項目について検証や、改良への示唆を得た。また、第6章では、それまでの研究内容を「結論1:建築デザイン教育の特徴と課題」としてまとめた。// 第7章「建築デザインと従来の土木デザイン、および景観デザインの評価基準の相違」では、建築デザイン教育から何を学び、何を改良すべきか明らかにするために、建築デザインと従来の土木デザイン、および景観デザインの評価基準の相違を把握した。これらに基づいて景観デザイン教育のいくつかの項目について検証や、改良への示唆を得た。// 第8章では、これまでの検証や改良への示唆を受けて、「結論2:景観デザイン教育のあり方」を提案した。また、この提案は筆者によって既に実践されており、その内容は第9章「景観デザイン教育の実践」で報告した。教育実践に基づいた評価と改良への示唆はフィードバックされ、第8章では、筆者の教育実践に基づいた提案も行った。//■結論:景観デザイン教育のあり方//□前提条件// 優れた建築家の出身大学は、極めて少数の大学に偏在しており、職歴についても偏りがある。ある学歴・職歴のパターンに沿って修行することは、優れた建築家になるための必要条件に近く、これ以外の学歴・職歴では可能性がかなり低い。したがって、優れた建築家は建築家自身の努力や偶然だけで育成されるのではなく、優れた建築家を育てる建築デザイン教育が確かに存在する。したがって、優れた景観デザインの専門家を育成する教育も存在し得ると考えられる。//□教育目標:どのような人材が必要なのか// 建築デザイン教育の調査結果に基づき、景観デザイン教育が育成する人材が身につけるべき能力を提案した。また、筆者の教育実践の経験に基づき、それらの教育を行うべき時期や手段によって分類した。//□教育内容// 建築デザイン教育の内容について、従来の土木デザイン教育との比較を行い、両者に共通の項目と建築デザイン教育独自の項目に分類したものが表1である。表の左側(建築独自の項目)は、インタビューにおいて建築家が師匠から学んだこととして力説する項目でありながら従来の土木デザイン教育では抜け落ちているため、景観デザイン教育ではこれらの項目も重視すべきであろう。また、筆者の教育実践の経験に基づき、教育目標として提案した能力毎に、具体的な教育内容を提案した。//□教育方法// 建築デザイン教育の調査では、優れた建築家を多数輩出する大学では、設計演習に非常に長い時間を割いていることが明らかとなった。したがって、景観デザイン教育においても設計演習の充実が必要だと考えられる。しかし、その時間数の目安は判断が困難な問題である。というのは、建築の設計演習の時間数が、土木に比べてはるかに多く、容易にその差を詰めることができるとは考えられないからである。これは、土木工学の扱う施設の範囲が非常に広いため、やむを得ない面がある。優れた景観デザイン教育を行うためには、設計演習の時間数を増やすことが望ましいが、その時間数は建築との比較で判断できるものではなく、土木関連学科の教育内容や教育方法を全体的に見直し、そこでの議論に基づいて判断するものであろう。// 筆者の教育実践に基けば、設計演習は学部で135時間、大学院で56時間程度が望ましいと提案した。//□教員// 建築デザイン教育においては、プロフェッサーアーキテクトが決定的に重要性であることが明らかとなった。優れた建築家を多数輩出する大学では、数多くの優れた建築家が大学教育者を兼務している。したがって、景観デザイン教育においてもプロフェッサーアーキテクト(実務経験者)の存在が重要であることは明らかである。土木分野では設計の実務者が大学教員を兼ねる例は極めて少ないが、今後はそれを増やすことが必要である。// 筆者の教育実践に基づく提案としては、大学の土木関連学科では、最低4人の実務経験者が必要だと提案した。4人とは、プランニング、意匠設計、構造設計、施工の実務経験者である。//□学生// 既往研究によれば、優れた建築家となる可能性の高い学生は、絵画、彫刻などの芸術的センスと、理数系の興味と力量を併せ持っている学生である。また、本研究では、優れた建築家の多くが高校の成績も優秀であることが明らかとなった。景観デザイン教育に求められる学生像も同様だと考えられ、このような学生を招くためには、入学試験にデッサンなどの実技を取り入れることも考えられる。しかし、残念ながらほとんどの土木関連学科は、現状では志願者が少ないため学生を選り好みできる状態ではない。今後はまず、若者に土木工学の魅力を伝えるところからスタートしなければならない。//□教育環境・設備、ほか// 前述のように、建築デザイン教育にとって設計演習は非常に重要である。本研究では、教育設備に関する調査は行っていないが、どこの大学でも建築学科には設計演習室があり、学生の創作活動の拠点となっている。一方、土木関連学科では設計演習室が充分に備えられていることは少ない。// 景観デザインでは、建築デザインよりも広いスケールをデザインの対象とする場合が多いため、巨大な模型を作成する必要が出てくる。このようなスペースの確保は難しい問題ではあるが、それなしでは景観デザイン教育が非常に困難となることも確かである。// 筆者の教育実践に基づけば、低学年では設計演習の敷地を小規模に押さえることにより、学生は自宅での図面や模型の製作が可能であり、高学年で履修者が絞られた後に、1人1台のテーブルを用意した設計演習室を用意することが望ましいと提案した。また、ワークステーション室や、優れた事例のデータベースの重要性なども指摘した。
2 0 0 0 心理学の立場から~知能検査が測定するものは何か?~
- 著者
- 大六 一志
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.239-243, 2009
今日の知能検査が何を測定しようとしており、今後どのような方向に発展しようとしているのかについて検討した。21世紀に入ってウェクスラー知能検査は言語性IQ、動作性IQを廃止し、知能因子理論に準拠するようになった。また、数値だけでなく質的情報も考慮したり、課題条件間の比較をしたりすることにより、入力から出力に至る情報処理プロセスのどこに障害があるかを明らかにし、個の状態像を精密に把握するようになっている。現在は、高齢者の知的能力の測定に対するニーズがかつてないほど高まっていることから、今後は高齢者の要素的知的能力の測定に特化した簡便な知能検査が開発されるとよいと考えられる。
2 0 0 0 OA 泉鏡花「年譜」補訂(七)
- 著者
- 吉田 昌志
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.845, pp.53-64, 2011-03-01
2 0 0 0 OA HMDVRのための可視光LEDによる手への非接触型温覚提示
- 著者
- 界 瑛宏 山口 勉 三武 裕玄 長谷川 晶一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.83-92, 2019 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 34
In this study, we propose and evaluate a warmth display, which is designed to heat a part of user's hand when the part of the hand get warmth in virtual world displayed by Head Mounted Display. For the heat source, we use visible light LED because it is easily available and controllable. Arranging several LEDs around the hand, the display can warm some part of the hand. As it warms hands without contact, the heat from the display can be cut off immediately and interactive warmth presentation is possible. Moreover, we evaluated the safety, reaction time, sensation of warmth and temperature change caused by the display.
2 0 0 0 OA 宿泊レビューの数値評価を考慮した感想コメント分析
- 著者
- 辻井 康一 津田 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第28回全国大会(2014)
- 巻号頁・発行日
- pp.4A13, 2014 (Released:2018-07-30)
インターネット宿泊予約サイトの宿泊レビューには、5段階の数値評価と感想コメントが記載されている。数値評価のすべての項目のうち、1つだけの評点を変える宿泊者が存在する。この宿泊者のこだわりと考えられる数値評価に対し、感想コメントには数値評価を変えた理由となる具体的な評価内容が記載されていると想定される。テキストマイニングを用いて感想コメントから評価表現を抽出し、その特徴を検証する。
2 0 0 0 OA On Arabo-Persian Elements in Modern Bengali
- 著者
- 溝上 富夫
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.1023-1019, 1973-03-31 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 花村 博司
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.75-92, 2015-09-30 (Released:2017-05-03)
本稿は,新出型・再開型・前提提示型という,日本語の会話における話題転換の型により,接続表現や言いよどみのような話題転換表現がどのように使いわけられているかをあきらかにする.新出型は転換後の話題が以前の話題とつながらない型,再開型は転換後の話題が以前の話題とつながる型,前提提示型は話題を継続するための前提的発話が直前の話題とはつながらない型である.これまでの研究で,前提提示型は話題転換として取りあげられていない.つながりのあるいくつかの発話a_1, a_2, … a_nから構成されるまとまりを話題Aと考えると,前提提示型話題転換では,話題Aにつながる話題Bの最初の発話b_1が直前の話題Aとはつながらない.たとえば,「ダブルワーク」についての話題Aに,「平日の休みにバイトしてくれと嫁に言われる」という発話b_nを追加する前提として,「時短休暇は平日休みになるシステム」という説明の発話b_1を入れるような場合である.話題転換表現は,3つの型でまったく異なる使用傾向がある.新出型では,先行話題の終了を示す沈黙が出やすく,接続表現は出にくい.再開型では,「でも」などの接続表現が出やすく,言いよどみは出にくい.前提提示型では,「あの」などの言いよどみのあとに沈黙が出やすく,先行話題終了の沈黙は出にくい.前提提示型の最初の発話で聞き手とのあいだに認識のずれが生じないように,話し手は話題転換表現を使いわけている.
- 著者
- 細井 真 本村 廣司 藤井 元 人見 充
- 出版者
- 立命館大学大学行政研究・研修センター
- 雑誌
- 大学行政研究 = 大学行政研究 (ISSN:18808271)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.101-115, 2015-03
2 0 0 0 OA 歴史地震と起震断層との対応
- 著者
- 小田切 聡子 島崎 邦彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.47-61, 2001-07-15 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 撤回:てんかん外科手術から得られる病態生理
- 著者
- 鎌田 恭輔 小川 博司 田村 有希恵 広島 覚 安栄 良悟
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.250-262, 2017 (Released:2017-04-25)
- 参考文献数
- 42
論文撤回のお知らせ 論文題目:てんかん外科手術から得られる病態生理 著 者:鎌田 恭輔、小川 博司、田村 有希恵、広島 覚、安栄 良悟 掲 載 誌:脳神経外科ジャーナル Vol.26 No.4 pp.250-262 当論文は,2017年3月24日に公開いたしましたが,著者からの申し出により撤回されました.
2 0 0 0 OA アイヌの酒 (1)
- 著者
- 加藤 百一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.285-291, 1968-03-15 (Released:2011-11-04)
本号より5回にわたリアイヌの酒の貴重な資料を著者にお願いしました。著者は北海道大学卒, 前札幌国税局鑑定官室長として北海道の実情にくわしいことはよく知られていますが, 本稿の資料の集成には多大の御苦心があったことと思います。
2 0 0 0 OA 集中治療室で終末期に至った患者に対する急性・重症患者看護専門看護師の倫理調整
- 著者
- 伊藤 真理 栗原 早苗 榑松 久美子 多田 昌代 戸田 美和子
- 出版者
- 日本クリティカルケア看護学会
- 雑誌
- 日本クリティカルケア看護学会誌 (ISSN:18808913)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.11-21, 2014-10-01 (Released:2014-10-01)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 1
本研究の目的は,集中治療室で終末期に至った患者に対し,急性・重症患者看護専門看護師(以下,CCNS )が,どのような倫理調整を行っているかを明らかにすることである.10 名のCCNS を対象に半構造化面接を行い,質的帰納的手法で分析した.分析した結果,【終末期に至る予測と積極的治療の限界を見極める】【患者の意思確認が難しい状況でもあきらめずに意思をくみ取る】【一人で意思決定しなければならない家族の重荷を分かち合う】【代理意思決定をする家族の後悔を最小限にする】【患者の命をあきらめきれない家族の苦悩を引き受ける】【集中治療の延長線上で可能な限り望ましい看取りを行う】【困難な決断をしなければならない医師の重責を理解し対立を避ける】【患者を失う医療者のやるせない気持ちに対処する】など,13 カテゴリーが抽出された. CCNS は,患者を対象とした権利擁護,家族を対象とした代理意思決定支援と悲嘆ケア,患者と家族を対象とした望ましい死への援助,医療チームを対象とした終末期ケアにチームで取り組む土壌作りを担っていたと考えられる.
2 0 0 0 OA 現代理論地図学の発達に関する研究
- 著者
- 金窪 敏知
- 巻号頁・発行日
- no.931, 1989
2 0 0 0 OA 弓道における矢の貫徹力に関する力学的考察
2 0 0 0 OA 研究史からみた弥生時代の鉄器文化 : 鉄が果たした役割の実像
- 著者
- 野島 永
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.185, pp.183-212, 2014-02-28
1930年代には言論統制が強まるなかでも,民族論を超克し,金石併用時代に鉄製農具(鉄刃農耕具)が階級発生の原動力となる余剰を作り出す農業生産に決定的な役割を演じたとされ始めた。戦後,弥生時代は共同体を代表する首長が余剰労働を利用して分業と交易を推進し,共同体への支配力を強めていく過程として認識されるようになった。後期には石庖丁など磨製石器類が消滅することが確実視され,これを鉄製農具が普及した実態を示すものとして解釈されていった。しかし,高度経済成長期の発掘調査を通して,鉄製農具が普及したのは弥生時代後期後葉の九州北半域に限定されていたことがわかってきた。稲作農耕の開始とともに鍛造鉄器が使用されたとする定説にも疑義が唱えられ,階級社会の発生を説明するために,農業生産を増大させる鉄製農具の生産と使用を想定する演繹論的立論は次第に衰退した。2000年前後には日本海沿岸域における大規模な発掘調査が相次ぎ,玉作りや高級木器生産に利用された鉄製工具の様相が明らかとなった。余剰労働を精巧な特殊工芸品の加工生産に投入し,それを元手にして長距離交易を主導する首長の姿がみえてきたといえる。また,考古学の国際化の進展とともに新たな歴史認識の枠組みとして新進化主義人類学など西欧人類学を援用した(初期)国家形成論が新たな展開をみせることとなった。鉄製農具使用による農業生産の増大よりも必需物資としての鉄・鉄器の流通管理の重要性が説かれた。しかし,帰納論的立場からの批判もあり,威信財の贈与連鎖によって首長間の不均衡な依存関係が作り出され,物資流通が活発化する経済基盤の成立に鉄・鉄器の流通が密接に関わっていたと考えられるようにもなってきた。上記の研究史は演繹論的立論,つまり階級社会や初期国家の形成論における鉄器文化の役割を,帰納論的立論に基づく鉄器文化論が検証する過程とみることもできるのである。
2 0 0 0 γ‐アミノ酪酸を畜積させた茶の製造とその特徴
- 著者
- 津志田 藤二郎 村井 敏信 大森 正司 岡本 順子
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.7, pp.817-822, 1987
- 被引用文献数
- 33 45
(1) 茶葉を窒素ガスや炭酸ガスのなかに入れ,嫌気的条件に置いたところ, γ-アミノ酪酸とアラニンが増加しグルタミン酸とアスパラギン酸が減少した.一方,テアニンやカフェイン,タンニン含量は変動しなかった.<br> (2) γ-アミノ酪酸は血圧降下作用を示す成分であるといわれることから,窒素ガス処理を行った茶葉で緑茶を製造した.その結果,一番茶,二番茶,三番茶ともにγ-アミノ酪酸含量が150mg/100g以上になった.<br> (3) ウーロン茶,紅茶のγ-アミノ酪酸含量は,茶葉を萎凋する前に窒素ガス処理するより,萎凋後に窒素ガス処理するほうが高くなった.<br> (4) 窒素ガス処理した茶葉から製造した茶は独特な香りを持っていたので, GC-MSで香気成分を分析,同定したところ,窒素ガス処理しないで製造した茶に比べて,脂肪酸のメチルやエチルエステルが増加していた.しかし,これらの成分の臭いは窒素ガス処理した茶が持つ香りとは,異なっていた.
2 0 0 0 OA 食育の背景と経緯 : 「食育基本法案」に関連して
- 著者
- 森田倫子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.457, 2004-10
- 著者
- 山本(前田) 万里 廣澤 孝保 三原 洋一 倉貫 早智 中村 丁次 川本 伸一 大谷 敏郎 田中 俊一 大橋 靖雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.23-33, 2017-01-15 (Released:2017-01-24)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 2
内臓脂肪を減少させメタボリックシンドローム(MetS)を予防する食品は有用であり,MetS改善作用の評価は,農産物単品にとどまってきたため,日常消費される組み合わせ食品としての有用性の検証が必要である.肥満傾向を有する健常な成人の昼食に,機能性農産物を組み合わせた機能性弁当を継続摂取させ,機能性農産物を使用していないプラセボ弁当を摂取した場合と比較して,腹部内臓脂肪の減少効果について検証した.BMIが25以上30未満および内臓脂肪面積が100cm2以上の肥満傾向を有する健常な成人を対象に,ランダム化プラセボ対照試験を行った.被験食品は,機能性農産物を使用した「おかず」,「べにふうき緑茶」および「米飯」(50%大麦ご飯および玄米),プラセボ対照食品は,機能性農産物を使用しない「おかず」,「茶」(麦茶)および「米飯」(白飯)であり,3因子の多因子要因1/2実施デザインを採用して,試験群は機能性の「おかず」「茶」「米飯」それぞれ1要素のみ被験食品とする3群とすべての機能性要素で構成される被験食品1群の計4群とした.平日の昼食時に12週間摂取した.主要評価項目は,内臓脂肪面積,副次評価項目は,ヘモグロビンA1c (HbA1c),グリコアルブミン,1,5-AG(アンヒドログルシトール)などとした.159名が登録され中途脱落はなかった.全期間の80%以上の日で弁当の配布を受けたPPS (Pre Protocol Set)解析対象者は137名であった.試験に入ることによる効果はPPSで-8.98cm2と臨床的にも統計的にも有意であった(p=0.017)).主要評価項目のサブグループ解析の結果,試験開始時の内臓脂肪面積が中央値100∼127cm2の被験者で,被験米飯の効果はPPS で平均-7.9cm2であり,p値は0.053とほぼ有意であった.被験米飯については女性でも有意な(平均値-14.9cm2,p=0.012)減少効果が観察された.副次評価項目では,1,5-AG に関してべにふうき緑茶の飲用で有意差が認められた.また,安全性に関して特筆すべき問題は生じなかった.食生活全体の変化と機能性農産物を使用した機能性弁当の連続摂取により,内臓脂肪面積の低減効果等の可能性が示唆された.