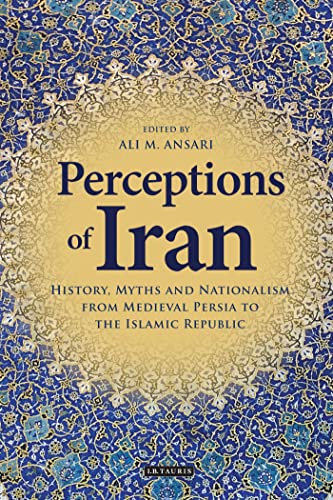2 0 0 0 OA 逸話文庫 : 通俗教育
2 0 0 0 正宗 : 日本刀の天才とその系譜 特別展
- 出版者
- 根津美術館
- 巻号頁・発行日
- 2002
2 0 0 0 OA 岩手県における死産、早期新生児死亡に対するケアの実態調査
- 著者
- 藤村 由希子 安藤 広子
- 出版者
- 岩手県立大学
- 雑誌
- 岩手県立大学看護学部紀要 (ISSN:13449745)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.83-91, 2004-03
- 被引用文献数
- 6
岩手県内における死産,早期新生児死亡における助産師・看護師の対応の現状について把握し今後のケアの検討資料とすることを目的に実態調査を行なった.24施設で勤務する助産師・看護師を対象に割り当て抽出法により質間紙を205部郵送し,178名から有効回答を得た (有効回答率86.8%).調査期間は2003年3-4月であった.調査対象者の年齢は30代が61名(34.2%)と最も多く,臨床経験年数は15.9(±8.7)年であった.児が亡くなった場合スタッフ間で毎回カンファレンスを行っているのは57名(32.0%)であった.亡くなった児の写真や足形などの遺品を渡しているのは28名(15.7%)であった.亡くなった児と母親との面会を積極的にすすめていろのは47名(26.4%),父親との面会を積極的にすすめているのは86名(48.3%)であった.退院後に何らかのケアを行っているのは54名(30.4%)であった.児を亡くした母親や家族と接する時に「悩んだことがある」は156名(87.6%)で,言葉かけや態度などについで悩んでいた.亡くなった児との面会は母親よりも父親の決定に委ねられていることや退院後のケアが行われていないことから,母親およびその家族への対応についての検討が必要である.また看護職者の多くがケアへの戸惑いや悩みを抱えているにもかかわらず,カンファレンスも少ないことから,今後のケアのあり方として,スタッフ間での情報や知識の共有の機会が必要である.
- 著者
- Eikan Mishima Hideki Ota Takehiro Suzuki Takafumi Toyohara Kazumasa Seiji Sadayoshi Ito Yoshikatsu Saiki Kei Takase Takaaki Abe
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.3855-19, (Released:2020-01-17)
- 参考文献数
- 21
We report a case in which diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) demonstrated renal artery stenosis-related renal ischemia and the therapeutic efficacy of revascularization. The patient was a 73-year-old man, who underwent descending thoracic aortic replacement due to DeBakey IIIb chronic aortic dissection, and who showed progressive renal dysfunction due to right renal artery stenosis caused by false lumen thrombosis. DWI demonstrated a decreased apparent diffusion coefficient (ADC) in the right kidney, indicating renal ischemia. Angioplasty with stenting restored renal perfusion and improved the renal function, resulting in the normalization of the decreased ADC in the treated kidney. Thus, DWI can be used to monitor renal ischemia in cases involving advanced renal artery stenosis.
2 0 0 0 OA 観察・実験に対する興味と学習方略との関連の検討
- 著者
- 原田 勇希 中尾 友紀 鈴木 達也 草場 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.409-424, 2019-11-29 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 5
本研究は,中学生の観察・実験に対する興味の構造を明らかにすることと,興味と学習方略との関連性について検討することを目的とした。確証的因子分析の結果,興味の構造として階層因子モデルが採択された。すなわち,観察・実験に対する興味は,“ポジティブな感情”の程度と,“観察・実験に対する価値の認知”の直交する2つの次元から捉えられることが示されたといえる。また,ポジティブな感情の程度と“思考活性志向”には観察・実験における深い学習方略(関連付け方略など)の使用を促進する効果が見出された。一方,“体験志向”は深い学習方略の使用を抑制する効果が見出された。さらに,本尺度の因子構造を反映した尺度得点の算出方法が検証され,分析用プログラムが作成された。
2 0 0 0 IR 村山政権期における日本社会党の政策転換--村山首相を中心として
- 著者
- 篠原 新 Shinohara Hajime
- 出版者
- 九州大学法学部政治研究室
- 雑誌
- 政治研究 (ISSN:02898357)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.175-201, 2008-03
- 著者
- 安元 暁子 木村 幹子
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.319-327, 2009 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 74
生物多様性がどのように構築されてきたのか、また、種分化がどのように起こり得るのかは、生物学における古くからの中心的な課題である。生物学的種概念に基づくと、種とは互いに生殖的に隔離された集団である。そのため、種分化は何らかの形で生殖隔離が進化することを必要とする。生殖隔離を進化させうる主要な原動力として、遺伝的浮動や異所的な環境条件への適応などが挙げられてきたが、動物においては性選択が長年注目されてきた。しかし、性選択単独では生殖隔離を進化させうる条件は限られており、近年は新たな原動力として、環境適応と性選択が関連している状況や、交配をめぐる雌雄の利害の不一致が引きおこす性的対立と呼ばれる状況が注目を浴びている。本総説では、まずは、種分化の研究のこれまでの概略を述べた後、ゲノミクス的手法から環境適応と性選択の双方に関わりのある遺伝子を明らかにし、種分化への寄与を示唆した研究についてレビューする。次に、性的対立の強さを操作することで数十世代後に生殖隔離が進化しうるかを調べた実験進化研究について、現状を整理する。最後に、ゲノミクス的手法が一般的になった今、これから重要となるトランスクリプトミクスとプロテオミクスが性選択や性的対立による種分化の研究にどのように寄与できるかを概観する。
2 0 0 0 Perceptions of Iran : history, myths and nationalism from medieval Persia to the Islamic Republic
- 著者
- edited by Ali M. Ansari
- 出版者
- I.B. Tauris
- 巻号頁・発行日
- 2014
2 0 0 0 OA 記述式項目の使用に関する教育測定学的考察
- 著者
- 野澤 雄樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.131-148, 2019-03-30 (Released:2019-09-09)
- 参考文献数
- 109
テストが測定対象とする学力が,基礎的な知識・技能を中心としたものから高次思考スキルを重視したものに移行するのに伴い,受験者に解答の生成を求める形式の項目が多用されるようになってきている。この傾向は歴史的に選択式項目が広く用いられてきた米国において顕著であるが,国内においても,大学入学共通テストで部分的に記述式項目が出題されることになるなど,類似した動きが見られる。一方で,記述式項目を含んだテストの運用にはさまざまな課題が存在しており,それらを解決するために教育測定の理論面および実践面での強化が求められる。本稿では,記述式項目を使用する際に考慮すべき教育測定学的なテーマのうち,(a)項目形式が測定に与える影響,(b)記述式項目を含んだテストにおける等化,(c)テストの使用がもたらす結果の検証,の3つを取り上げた。これらのテーマは,国内では議論されることが少ないものの,妥当性との関連が深い重要なテーマである。各テーマについて,研究が進んでいる米国での議論を参考に,今後必要となる研究について考察した。全体考察では,日米の違いや,国内の教育測定学が抱える課題について指摘した。
2 0 0 0 硝酸化学熱傷の1例
- 著者
- 井上 雅子 徳野 貴子 加藤 りか 池田 政身
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.15-17, 2012-02-01 (Released:2012-04-16)
- 参考文献数
- 8
56歳,男性。硝酸運搬船で作業中に98%の硝酸で受傷,作業服と長靴を取るのに手間取り約10分後より流水で洗い流し,着岸まで約1時間風呂で水につかっていた。着岸後近医受診しワセリンを塗布され,約48時間後に当院を受診した。初診時,左上腕,両側臀部から大腿,両側下腿にかけて受傷部周囲に水疱形成がみられ,中心部は黒色から黄色の痂皮が付着したII度深層からIII度の化学熱傷,両側手掌は水疱を伴い黄色に変化した化学熱傷がみられた。血栓性静脈炎の既往があり,ワルファリンカリウム,アスピリンを内服していた。入院2日目より38℃から40℃の発熱,炎症反応高値であったので抗生剤投与を行った。発熱は4日後より治まり,内服中であったワルファリンカリウム,アスピリンを中止して入院10日目にデブリードマンおよび mesh skin graft 施行した。真皮深層まで壊死に陥っていたため,移植皮膚の定着が悪く再手術を必要とした。化学熱傷の治療では,速やかに長時間洗浄することと,可能な限り早期にデブリードマンを施行することが重要である。本症例では,硝酸の濃度が極めて高かったこと,着衣をとり流水で洗浄するまでに時間がかかったこと,当院受診までに約48時間経過していたこと,さらに抗凝固剤を内服していたためデブリードマンを施行する時期が遅れたことなど,様々な理由によって深い潰瘍を形成してしまい治療に難渋した。
- 著者
- 井芹 真紀子
- 出版者
- クィア学会
- 雑誌
- 論叢クィア (ISSN:18832164)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.37-57, 2013
2 0 0 0 OA 食餌由来腸内細菌代謝産物による褐色脂肪組織機能調節
- 著者
- 後藤 剛 Kim Minji 川原崎 聡子 高橋 春弥 河田 照雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- オレオサイエンス (ISSN:13458949)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.145-152, 2019 (Released:2019-09-25)
- 参考文献数
- 33
腸内細菌叢は宿主のエネルギー代謝調節において重要な役割を果たすことが明らかになりつつあるが,その詳細な分子機構は未解明な部分が多い。短鎖脂肪酸をはじめとする腸内細菌由来代謝産物による宿主代謝調節機構がその一翼を担っていると考えられる。褐色脂肪組織は低温下での体温維持に寄与する高い熱産生能を有する脂肪組織であり,その活性強度が成人の肥満度と逆相関することが明らかにされ,肥満や肥満に伴う代謝異常症の予防・改善の標的組織として注目されている。近年,腸内細菌叢と褐色脂肪組織機能の関連性が報告されつつあり,食餌由来の腸内細菌代謝産物を介した褐色脂肪組織機能調節機構の存在が示唆されている。本作用は腸内細菌叢による宿主エネルギー代謝調節機構の一端として寄与していることが推定される。本稿では,褐色脂肪組織機能および食餌由来腸内細菌代謝産物による褐色脂肪組織機能調節作用について概説したい。特に,近年同定された食餌由来不飽和脂肪酸由来の腸内細菌産生修飾脂肪酸の機能について,私達が行っている研究結果について中心に紹介する。
2 0 0 0 OA 古代中国人類集団の遺伝的多様性とその変遷ならびに生活史の解明
- 著者
- 西川 満則 横江 由理子 久保川 直美 福田 耕嗣 服部 英幸 洪 英在 三浦 久幸 芝崎 正崇 遠藤 英俊 武田 淳 大舘 満 千田 一嘉 中島 一光
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.491-493, 2013 (Released:2013-09-19)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 2
緩和ケアとは,生命を脅かす疾患による問題に直面した患者・家族の苦痛を和らげquality of life(QOL)を改善するプログラムである.日本の緩和ケアは,がんを中心に発展し非がんへ広がりつつある.当院では,非がんも対象に加え緩和ケアを推進すべくEnd-Of-Life Care Team(EOLCT)を立ち上げた.当初6カ月間の延べ依頼数は109件で,約4割を占める非がんの内訳は,認知症,虚弱,慢性呼吸器疾患,慢性心不全,神経難病等であった.活動内容は,オピオイド使用も含めた苦痛緩和,人工呼吸器・胃瘻・輸液の差し控え・撤退の意思決定支援(Advance Care Planning:ACP),家族ケアで,法的・倫理的問題に配慮し活動している.このEOLCTの活動は,老年医学会の立場表明,厚生労働省の終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインに親和的であり,非がん疾患も含めた緩和ケアを推進する有用なシステムになりうる.特に胃瘻や人工呼吸器の選択に象徴される難しい意思決定を支援する働きが期待される.
2 0 0 0 OA 東洋レーヨン(株)基礎研究所における情報管理の実際
- 著者
- 西村 徹
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.8, pp.425-432, 1968-11-20 (Released:2016-03-16)
- 著者
- 石井 翔大
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- no.747, pp.949-955, 2018-05
This study aims to elucidate Hiroshi Ohe's activities in the Ministry of Education and to consider the architectural view of Ohe before the world war II.<br> Hiroshi Ohe (1913-1989) worked as a technician at the Ministry of Education from 1938 to the beginning of 1941 and was involved in the construction of the Jinmu Emperor's honoring monument and the National History Museum. This study collected and analyzed primary materials such as sketches, drawings, and documents created by Ohe during the Ministry of Education's Technical Time, which have been stored in the Ohe Architecture Atelier (formerly Ohe Hiroshi Architects). The design process of Jinmu Emperor's honoring monument from the first stage to the fourth stage can be considered a process of a gradual reduction in the conceptions of Ohe.<br> It is assumed that the theme of Ohe's sketches in the first stage was to superpose the space containing the monument by creating a plan and sequence in order to gradually join the area on the outside to that on the inside. Therefore, it can be pointed out that Ohe's intention in the later years, which emphasizes the psychological changes in people who experience building, has already been taken into account in the design of the monument.<br> In the later years, Ohe developed criticism against modernist architecture, advocating the principle of “interminglement and coexistence” and arguing about the importance of roofing and decoration.<br> It is assumed that the sketch of Fig. 11 contains the themes of roofing and decoration, deviating from simplicity that is one of the features of modernism architecture. Therefore, this sketch is considered an important material foretelling the construction of Ohe during the later years.
2 0 0 0 副咽頭間隙腫瘍29例の検討:―悪性例を含めて―
- 著者
- 真栄田 裕行 金城 秀俊 上里 迅 安慶名 信也 又吉 宣 鈴木 幹男
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.6, pp.397-403, 2019
<p>Introduction</p><p>Although many tumors arising from parapharyngeal space are benign, we sometimes find malignant tumors. We have attempted to examine the clinical findings of parapharyngeal tumor in our institution and to consider how to deal with malignant tumor.</p><p>Materials</p><p>There were 29 cases of parapharyngeal space tumors involving malignancies in our institution.</p><p>Results</p><p>There were 20 benign cases composed of 7 cases of schwannoma, 6 cases of pleomorphic adenoma, 3 cases of paraganglioma, and one case each of cavernous haemangioma, cyst and meningioma, basal cell adenoma. On the other hand, there were 4 malignant tumors composed of one case each of malignant schwannoma, carcinoma ex pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma and malignant paraganglioma. We presumed that one cases out of the 4 malignancies cases was a malignant tumor from the preoperative image findings. However, it was difficult to diagnose the other 3 cases with malignancies by investigation.</p><p>Discussion</p><p>Malignant tumors occurring in the parapharyngeal space were distributed salivary gland tumors and others. Because salivary gland tumor grow earlier and invade muscles, nerves and vessels rapidly, it is difficult to treat them radically. On the other hand, because the tumors arising from the salivary gland have a specific pathology, and exhibit slow growth, patients can expect a long life term despite having such tumors. In our examination, death occurred in one case only, the carcinoma ex pleomorphic adenoma.</p>
2 0 0 0 術前診断が困難であった副咽頭間隙腺様囊胞癌の一例
- 著者
- 真栄田 裕行 杉田 早知子 山城 拓也 崎浜 教之 鈴木 幹男
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会
- 雑誌
- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.53-58, 2019
副咽頭間隙原発の腺様囊胞癌の報告は少なく,本邦の過去の報告は 8例のみであった。今回われわれは副咽頭間隙発生の早期腺様囊胞癌を経験した。患者は63歳の女性。左副咽頭間隙に発生した腫瘤は画像所見からは多形腺腫も考慮されたが,形状や耳下腺との非連続性から神経鞘腫と診断した。経頸部アプローチにより腫瘤が摘出され,術後に腺様囊胞癌と判明した。副咽頭間隙に腺様囊胞癌が生ずる認識があれば,術前に細胞診やFDG-PET検査を施行して正確な診断がついた可能性もある。また治療に関しても腫瘍を明視下に置いた種々の術式により,完全切除も可能であったと思われた。再発時には拡大切除および術後照射が現実的な治療方針ではないかと考える。
2 0 0 0 OA 野生動物におけるロードキル,バリアー効果とミティゲーション技術に関する研究の現状と課題
- 著者
- 園田 陽一 武田 ゆうこ 松江 正彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究(オンライン論文集) (ISSN:1883261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.7-16, 2011 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 108
- 被引用文献数
- 5 2
This study reviewed recent studies of road-kill, barrier effect and mitigation techniques on wild animals. It also surveyed road-crossing structures used in Japan. By comparing Japanese and international case studies, we addressed the possibility of studies on road-kill, barrier effect and mitigation technique development in Japan. The road-studies in Japan were mostly studies of the road-kill of Sika deer, Cervus nippon yesoensis, and Raccoon dog, Nyctereutes procyonoides. There were fewer Japanese studies on roadkill and barrier effect examining species, taxa, and landscapes than international studies. Most of the road-crossing structures were underpasses, box-culverts, and pipe-culverts targeting large and mid-sized mammals. There were fewer eco-bridges targeting arboreal mammals and amphibian tunnels targeting herptiles in Japan. In the future, it will be necessary to analyze the factors influencing road-kill and barrier effect of various species and taxa in order to develop mitigation techniques targeting arboreal mammals and herptiles, and to develop quantitative methods for monitoring wild mammals utilizing road-crossing structures as movement corridors.