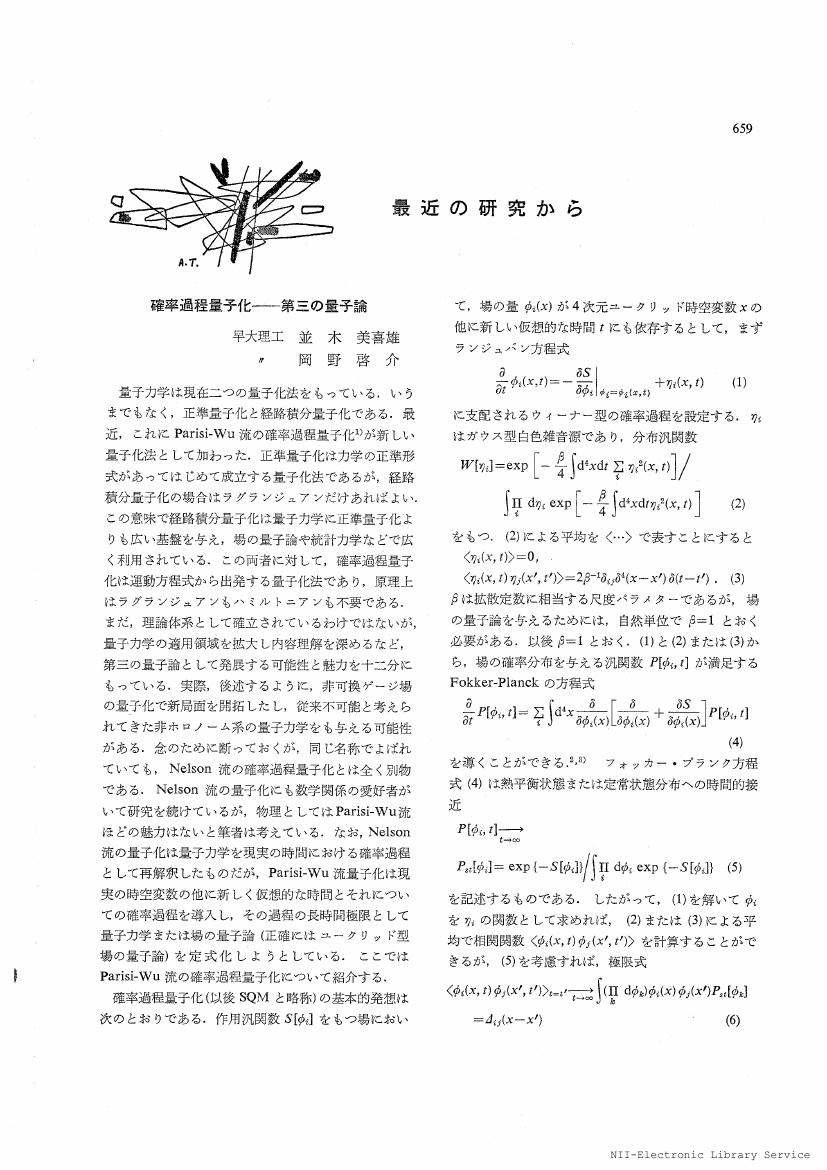56 0 0 0 OA 家畜精液の生化学的研究家畜精漿中の化学成分含量などについて
- 著者
- 広江 一正 富塚 常夫
- 出版者
- 日本繁殖生物学会
- 雑誌
- 家畜繁殖研究會誌 (ISSN:04530551)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.95-99, 1965-11-30 (Released:2008-05-15)
- 参考文献数
- 21
1.牛精漿中の化学成分含量の測定を行なった。果糖713±246.0,総窒素813±167.0,アスコルビン酸8.6±1.52,酸溶性総リン35.3±6.34,カルシウム30.9±11.05.ナトリウム267±39.8,カリウム124±61.1,および塩素154±26.9mg/100ml精漿。また同時に山羊,馬,豚,兎についても測定を行なった。2.牛精漿中の総窒素,アスコルビン酸,酸溶性総リン,カルシウム,ナトリウム,カリウムでは果糖と同じく季節的な量的変化は見られなかった。3.3回続けて精液採取を行なったある1頭の牛の例では,果糖および総窒素は次第に増加の傾向を,アスコルビン酸,酸溶性総リン,カルシウムは次第に減少の傾向を示した。4.尿導球腺液および精のう液についてその化学成分含量の測定を行なった。尿導球腺中の成分含量は精液に比べて非常に少なかったが,精のう液中の成分含量は精液中の含量よりも若干多かった。このことは電気刺激射精法で採取した精液中には尿導球腺液が混入していることを示すものと考えられた。
56 0 0 0 OA 剣道における片手打ちの打撃力に関する研究
- 著者
- 浅見 裕 横山 直也 百鬼 史訓 田中 幸夫 田中 秀幸 大矢 稔 山神 眞一
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.12-19, 1994-08-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 14
For the purpose of determining the technical characteristics of the Kendo strike with the Jodan-no-Kamae in Kendo, we measured the impact force of the one-hand Shomen-and Kote-uchi using as subjects five college Kendo club students. And analyzed the data by a motion analysis system with a video tape recorder. We also measured the impact force of the two-hand Chudan-no-Kamae strike for comparison. The following are the results obtained from a biomechanical examination of the data.1. The downward maximum magnitude of the impact force of the one-hand Kote-Uchi (150.03 ± 21.35kgf) was greater than that of the one-hand Shomen-Uchi (120.99 ± 11.55kgf). This difference was a characteristic of the one-hand strike but not of the two-hand strike.2. The angular motion at the left shoulder, from which the Shinai is brought down, was greater for the one-hand Kote-Uchi than for the one-hand Men-Uchi. This will explain why the vertical component force of the one-hand Kote-Uchi was greater than that of the one-hand Men-Uchi.3. With respect to the vertical movement of the Kensen, the maximum speed was greater for the one-hand Kote-Uchi than for the one-hand Men-Uchi while the opposite was the case with respect to the forward movement. This was in accord with the observation that the maximum magnitude of the impact force was greater for the one-hand Kote-Uchi than for the one-hand Men-Uchi with respect to the vertical movement whereas the opposite was the case with respect to the forward movement.4. The correlation coefficient between the impact time and the maximum magnitude of the impact force was small whereas the correlation coefficient between the impact time and the impulse value was great.5. There was not an appreciable difference in the magnitude of the impact force between the one-hand and two-hand Men-Uchi. However, with respect to the right Kote-Uchi, the maximum magnitude of the impact force was greater in every direction for the one-hand strike than for the two-hand strike. Most notably, with respect to the downward movement, the maximum magnitude of the impact force of the one-hand Kote-Uchi was greater than that of the two-hand Men-Uchi.
56 0 0 0 OA 組合せ最適化入門:線形計画から整数計画まで
- 著者
- 梅谷 俊治
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.1059-1090, 2014-09-16 (Released:2014-12-16)
- 参考文献数
- 41
線形計画問題において変数が整数値を取る制約を持つ整数計画問題は,産業や学術の幅広い分野における現実問題を定式化できる汎用的な最適化問題の 1 つであり,最近では分枝限定法に様々なアイデアを盛り込んだ高性能な整数計画ソルバーがいくつか公開されている.しかし,整数計画問題では線形式のみを用いて現実問題を記述する必要があるため,数理最適化の専門家ではない利用者にとって現実問題を整数計画問題に定式化することは決して容易な作業ではない.本論文では,数理最適化の専門家ではない利用者が現実問題の解決に取り組む際に必要となる整数計画ソルバーの基本的な利用法と定式化の技法を解説する.
56 0 0 0 OA DRC決勝戦における歩行安定化制御
- 著者
- 梶田 秀司
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.140-143, 2018 (Released:2018-04-15)
- 参考文献数
- 16
56 0 0 0 OA 治療によりインスリン初期分泌正常化を認めた再発性清涼飲料水ケトーシスの1例
- 著者
- 二田 哲博 野見 山理久 浅野 喬
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.393-396, 2000-05-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 7
症例は27歳男性. 16歳時, コーラの多飲を契機にケトアシドーシスで糖尿病発症. 初回入院時体重100.5kg, 身長176cm, 空腹時血糖516mg/dl, 血中総ケトン体13, 164μmol/l, 食事療法と15日間のインスリン使用により, 退院時体重84kgとなり, 75gOGTTにてインスリン分泌を含め血糖値は正常化した, 22歳より体重増力口を伴うインスリン抵抗性の増悪を認めたが, インスリン分泌の低下はなかった. 27歳時体重122kgで空腹時血糖347mg/dl, 尿中ケトン体 (3+) にて再入院, 食事療法による体重減量と13日間のインスリン使用後, 再びインスリン分泌を含め血糖値の正常化を認めた. 本症例はインスリン分泌が比較的保たれていたにもかかわらず, 高度肥満によるインスリン抵抗性と大量の清涼飲料水による過大な負荷により糖尿病性ケトアシドーシスが発症したと思われ, それらの負荷の軽減によりインスリン分泌が改善したものと考えられる.
56 0 0 0 OA 確率力学としての最適輸送問題
- 著者
- 三上 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.364-382, 2006-10-26 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 83
56 0 0 0 OA がん治療とサルコペニア
- 著者
- 海道 利実 濱口 雄平 奧村 晋也 小林 淳志 白井 久也 上本 伸二
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.822-828, 2017 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
サルコペニアとは、筋肉量の低下に筋力の低下または身体機能の低下を伴う病態である。その成因によって、加齢に伴う筋肉量の減少である一次性サルコペニアと、活動性の低下 (廃用性萎縮) や低栄養、臓器不全や侵襲、腫瘍などの疾患に伴う筋肉量の減少である二次性サルコペニアに分類される。サルコペニアは生命予後に影響し、特に消化器外科領域においては、手術患者の高齢化による一次性サルコペニアと低栄養や担がん状態、手術侵襲などによる二次性サルコペニアを伴う患者が増加しており、今後、ますます重要な問題となるであろう。事実、最近、消化器領域を中心に、サルコペニアの意義に関する論文が急増している。そのほとんどが、術前サルコペニアは予後不良因子であるという論文である。したがって、今後、サルコペニアをターゲットとした栄養・リハビリテーション介入が、消化器がん治療成績向上の新たなブレークスルーになると期待されよう。
- 著者
- Yusuke Hibino
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.219-223, 2018-11-25 (Released:2018-11-25)
- 参考文献数
- 5
A new finless ophichthid eel, Apterichtus soyoae, is described based on a single specimen collected from off Tori-shima island, Zunan Islands of Izu Islands, southern Japan. The new species is similar to A. moseri and A. klazingai in its numbers of supratemporal pores, preopercular pores, and vertebrae. The new species differs from A. moseri in having more supraorbital pores (1+6 vs. 1+4), the number of branchings of the supraorbital canal (1 vs. 0), shape of the snout (distinctly pointed vs. relatively blunt), eye size (50% of snout length vs. 35–45%; 8.8% of head length vs. 6.3–8.0%), and the number of vomerine teeth (1 vs. 2–5). Apterichtus soyoae can also be distinguished from A. klazingai by the number of branchings of the supraorbital canal (1 vs. 2), the number of infraorbital pores (7 vs. 9), and the location of the lower jaw tip (anterior to a vertical through anterior margin of eye vs. posterior to the vertical). The number of supraorbital pores and branchings of the canal are discussed.
56 0 0 0 OA 過去20年間に邦文で報告された温泉の健康増進作用に関する研究論文のレビュー
- 著者
- 王 紅兵 鏡森 定信
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.81-102, 2006 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 1
The studies on spa's health promotion effects on healthy or slightly unhealthy persons published in past two decades in Japan have been reviewed. Multidimensional findings from these studies have suggested that the spa resort using may have the effects of increasing and retention of skin and body temperature, improving peripheral circulation function, lowering blood pressure, improving gastrointestinal hormones secretion and increasing gastric mucosal blood flow, bettering metabolism, regulating the function of immune system, regulating the balance of autonomous nervous and internal secretion systems, relieving stress and relaxing, improving the quality of life (QOL), relieving the symptoms of those who are slightly unhealthy, promoting physical strength and fitness, promoting the well-being of the aged, reducing medical expenses of individuals or the community, keeping skin in good shape and restraining the skin's aging.Of the 58 papers reviewed, the studies of hot spring bathing effects on increasing and retention of skin and body temperature, improving peripheral circulation function and lowering blood pressure were the most in numbers (12 papers, 20.7%), and then the studies of relieving the symptoms of those who were slightly unhealthy (10 papers, 17.2%). Case-control studies (26 papers, 44.8%) were the most used study designs, and then the clinical observation (20 papers, 34.5%). No findings from any one study reviewed in this paper showed that the spa resort using had definite evidence of health promotion effects. Probable effects were suggested from 32 studies (55.2%), but findings from the rest ones (26 papers, 44.8%) showed little evidence to support this consideration. Recently randomized controlled trials (RCT) had been used in studying the health effects of spa resort using in Japan and showed significantly better effects in the intervention group. However, the intervention methods used in the studies were comprehensive health education combing the instructions in appropriate ways of hot spring bathing and education on lifestyle and exercise. It was difficult, if not impossible, to separate the effect of hot spring bathing alone from the combination. The outcomes as effects used in the studies were blood profile, physique and other non-specific items. It may be also difficult to design and carry out a near perfect RCT study on the health promotion effects of spa resort using in field in the future. However, based on experience from past studies it is practicable and important to purse better epidemiological methods such as randomizing and crossover design. On the other side, as specific readers can be influenced marvelously by one book, the health conditions of users may be improved greatly and continuously by some spa. While evidence-based health care places emphasis on RCT, it is also extremely important to inspect the health promotion effects of spa using systematically and rapidly from the viewpoint of narrative-based health care.
- 著者
- JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO MARÍA MARTINÓN-TORRES
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.3, pp.149-155, 2014 (Released:2014-12-23)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4 9 1
The Early Pleistocene human fossil remains recovered from the TD6 lithostratigraphic unit of the Gran Dolina cave site in the Sierra de Atapuerca, northern Spain, show a mosaic of primitive and derived features. Among the latter, the modern human-like midfacial topography, as well as several synapomorphies shared with some European Middle Pleistocene hominin and Neanderthals, represents a challenge for the phylogenetic interpretation of Homo antecessor. Using an ontogenetic approach of the maxilla ATD6-69, Freidline et al. (Journal of Human Evolution, 65: 404–423 (2013)) have confirmed previous observations that H. antecessor adults had a set of facial features characterizing H. sapiens. However, Freidline and collaborators proposed that the evolution of modern-looking facial morphology occurred independently in Africa, Asia, and Europe and at several times during the Early and the Middle Pleistocene. Following their line of reasoning, the presence in H. antecessor of some features shared with the European Middle Pleistocene hominins and the Neanderthal lineage could also be interpreted as convergences. However, instead of supposing multiple, parallel evolution, we suggest that a more parsimonious interpretation envisages the hypothetical existence of an Early Pleistocene hominin population, from which several hominin lineages originate and inherit particular combinations of derived features. The TD6 hominins probably represent a side branch of this cladogenetic event, which evolved in Western Europe.
56 0 0 0 OA 基礎生命科学の憂うべき状況について
- 著者
- 大隅 良典
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.72-73, 2008-05-01 (Released:2012-02-15)
56 0 0 0 OA HIV感染患者における透析医療の推進に関する調査
- 著者
- 秋葉 隆 日ノ下 文彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.111-118, 2013-01-28 (Released:2013-02-20)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
エイズ感染患者の透析医療の確保に関して透析施設のHIV患者受け入れの現状を把握し今後の対策の資料とするため調査を行った.全国の透析施設3,802施設にアンケートを発送,1,552通(回収率40.82%)を得た.透析を必要とするHIV陽性者の透析受け入れの経験のある施設は94施設(6.2%),経験のない施設1,434施設(93.8%)で,平成23年11月現在のHIV患者透析実施患者数は89名(60施設,各施設1~7名,1.48±1.12名)だった.この施設は今後も「受け入れる」が69施設,「難しい」23施設で74.2%の施設が今後も受け入れを継続するとの意向を示された.受け入れの経験がない医療機関の今後の方針は「紹介があれば受け入れる方針である」227施設(15.7%),「今後,受け入れを検討する」445施設(30.7%),「受け入れることは難しい」776施設(53.6%)と約半数が今後の受け入れの可能性を表明した.しかしながら,「受け入れがたい理由」として,「HIV陽性者専用のベッドが確保できない.」「HIV陽性者への対応手順が整理されていない.」「透析中に急変した際のバックアップ体制が得られるのか心配」などの懸念が高頻度に示され,公的な援助なしに民間施設がHIV患者を受け入れるには多くの難関があることが明らかになった.
55 0 0 0 OA 確率過程量子化 : 第三の量子論
- 著者
- 並木 美喜雄 岡野 啓介
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.8, pp.659-662, 1983-08-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 32
55 0 0 0 OA 中国の公共交通機関における性暴力反対運動と女性専用車両 ――香港・台湾・日本との初歩的比較も――
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.21-39, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 14
本稿では、中国で2012年に活動を開始した「行動派フェミニスト」がおこなってきた公共交通機関における性暴力反対運動について考察した。その際、香港・台湾・日本との初歩的比較もおこなった。 中国における公共交通機関における性暴力反対運動も、実態調査をしたり、鉄道会社に対して痴漢反対のためのポスターの掲示や職員の研修を要求したりしたことは他国(地域)と同じである。ただし、中国の場合は、自らポスターを制作し、その掲示が断られると、全国各地で100人以上がポスターをアピールする活動を、しばしば1人だけでもおこなった。この活動は弾圧されたが、こうした果敢な活動によって成果を獲得したことが特徴である。 また、中国のフェミニストには女性専用車両に反対する傾向が非常に強く、この点は日本などと大きな差異があるように見える。しかし、各国/地域とも、世論や議会における質問の多くは女性専用車両に対して肯定的であり、議会では比較的保守的な政党がその設置を要求する場合が多いことは共通している。フェミニズム/女性団体の場合は、団体や時期による差異が大きいが、各国/地域とも、女性専用車両について懸念を示す一方で、全面否定はしてないことは共通している。中国のフェミニストに反対が強い原因は、政府当局がフェミニストの活動を弾圧する一方で、女性に対する「思いやり」として女性専用車両が導入されたことなどによる。
55 0 0 0 OA 黄砂によって輸送される病原性物質
- 著者
- 礒田 博子 山田 パリーダ 森尾 貴広
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.2_60-2_64, 2011-02-01 (Released:2011-06-18)
- 著者
- 縄田 健悟 池田 浩 青島 未佳 山口 裕幸
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.76-86, 2023-11-30 (Released:2023-11-30)
- 参考文献数
- 30
This study aimed to examine how workplace teleworking affects teamwork. Teamwork in remote situations has been studied from the perspective of virtual teams and team virtuality. Team virtuality can be classified into two aspects: (1) geographic dispersion and (2) technology use. Telework increases both geographic dispersion and technology use. On the other hand, past studies have not sufficiently examined how these two aspects affect teamwork. In this study, we examined the relationship between the two aspects of team virtuality and teamwork by analyzing two datasets, one at the individual level (Study 1, individual N=567) and the other at the team level (Study 2, team N=53). The results of Study 1 revealed that geographic dispersion was negatively associated with teamwork, while technology use was positively associated with teamwork. Study 2 showed a similar overall trend of association, although some aspects did not achieve statistical significance. Telework was positively associated with both geographic dispersion and technology use. In other words, the two aspects of team virtuality were shown to have potentially conflicting effects. Furthermore, Study 1 showed an interaction effect between these two aspects, suggesting that technology may moderate the negative effects of geographic dispersion on teamwork.
55 0 0 0 OA 世界の日本語学習者の辞書ツール使用事情―スマホによる語彙検索行動の適切な支援のために―
- 著者
- 石黒 圭 佐野 彩子 吉 甜
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.5-20, 2023-09-30 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 7
日本語学習者の多くが,スマホやタブレット,PCを用いて辞書アプリやインターネット上の辞書を利用している.本研究では,世界各地域の日本語学習者110名を対象に,日常生活において語彙検索行動を行う際に使用したデバイスの画面録画機能を用いて,語彙検索行動を記録してもらうことを試みた.また,この調査記録を,入力言語,入力方法,検索に使用するリソース,検索過程,および検索行動の成否の観点から分析した.その結果,日本語学習者は既習の知識を組み合わせたり応用したりしながら,工夫して語彙検索を行う一方,日本語の誤りや検索方法の誤りのために検索に時間を要したり求める情報にたどりつけなかったりする状況も少なくないことが明らかになった.日進月歩で発展を遂げるテクノロジーによって,日本語学習者の語彙検索の環境も大きく変容している.このような個別事例の分析の蓄積を生かし,今後は語彙検索行動にかんする新たな支援の可能性を探りたい.
55 0 0 0 OA 自殺率に対する積極的労働市場政策の効果
- 著者
- 柴田 悠
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.116-133, 2014 (Released:2015-07-04)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
日本では, 1998年以降, 貧困や孤立といった社会的状況によって自殺に追い込まれる人々が増えた. 憲法第13条において「国民の生命の権利を最大限尊重すべき」とされている日本政府には, 社会政策によってそのような状況を改善し, 不本意な自殺を予防する責務がある. では, どのような社会政策が自殺の予防に有効なのか.本稿では, 公的な職業訓練・就職支援・雇用助成を実施する「積極的労働市場政策 (ALMP)」に着目した. ALMPは, 「孤立した貧困者」を他者 (支援スタッフや訓練参加者) や労働市場へと繋ぎとめ, 社会経済的に包摂する機能をもつ. 自殺にもっとも追い込まれやすいのが「孤立した貧困者」であるならば, 日本においてALMPは彼らの自殺を予防できるのだろうか. あるいは逆に, 彼らを自殺へとますます追い込んでしまうのだろうか. そこで本稿は, この問いに対して実証的に答えることを目的とした.先行研究よりも広範なデータと比較的精緻な推定モデルで分析した結果, 自殺率の増減の一部は, 失業率上昇率の増減 (貧困者の増減) と, 離婚率の増減と新規結婚率の減増 (孤立者の増減), ALMP支出の減増 (孤立した貧困者の放置/包摂) によって説明できた. またそれらの要因は, 日本での1991~2006年の自殺率変動 (前年値からの変化) のおよそ10~32%を説明した. 他方でALMP以外の社会政策は, 有意な自殺予防効果を示さなかった.
55 0 0 0 OA コンテンツ消費における「オタク文化の独自性」の形成過程
- 著者
- 永田 大輔
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.21-37, 2015-02-28 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 16
This paper discussed the process of creating “otaku originality” within the context of their consumption. Otaku considered their culture original and distinct from that of normal anime consumers in the 1980s. In prior studies, people called otaku were those committed to worthless culture. Though people regarded otaku culture as worthless, we should observe its formation process. Otaku made it a culture of worth for their community, turning it into a high context culture. Becoming a high context culture meant it achieved interactions with people other than anime fans, but how was this happen?This paper focuses on anime fan culture, and discusses the video environment and active television viewing. The VCR diffusion rate increased from 2.2% to 66.8% during the 1980s. Otaku started to watch videos with their friends. They wanted to show their videos to their friends. However, this was considered an unnatural behavior. This paper mainly analyzes community with video consumption among anime fans and discusses their motivations. They wanted to show off the VCRs “Slowmotioning” meant “unique watching”. Originally, anime meant “animation”, but their activity enabled anime fans to enjoy “pictures”. Consumers could attain “creators literacy”. However, this literacy was marketed by the creators. Anime magazines evaluated this marketing. The culture of editing by anime fans formed a frame. They consumed the unique experience of watching anime together as consumers who had a specific literacy. Otakus’ high contextual culture, including their knowledge and literacy, was created by interactions between creators and consumers of anime magazines.
55 0 0 0 OA 新卒採用のジェンダー不平等をもたらす企業の組織的要因 ――企業の経営状況との関連に着目して――
- 著者
- 吉田 航
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.314-330, 2020 (Released:2021-09-30)
- 参考文献数
- 32
雇用をめぐるジェンダー不平等の生成メカニズムを明らかにする上で,企業側の要因に着目する重要性が指摘されている.先行研究の多くは,企業組織の制度や権力関係に着目し,これらが不平等に与える影響を検討してきた.本稿では,この視点をさらに発展させ,こうした組織的要因の効果が,組織が置かれた環境の変化と連動して,どのように変化しているかを検討した.とくに本稿では企業の経営状況に着目し,組織の制度や権力関係が,企業の経営状況に応じてどのような影響をジェンダー不平等に与えているかについて,国内大企業の新卒採用を対象に分析した. 分析から,組織的要因がジェンダー不平等に与える効果は,必ずしも企業の経営状況から独立に発揮されるわけではなく,一部の組織的要因については,その効果が経営状況によって変化していることが示された.ワークライフバランス改善に向けた企業内施策は,基本的には新卒女性採用比率に影響しないものの,業績が悪いと,施策が充実している企業ほど女性採用比率が低くなる傾向にあった.一方で,女性管理職比率の高さは,新卒女性採用比率を高める効果を持ち,この効果は業績の良し悪しによらず確認された.先行研究で検討されてきた組織の制度・権力関係の効果について,企業の経営状況との関連を検討した本稿は,こうした要因が雇用の不平等に影響するメカニズムの精緻化に貢献するものである.