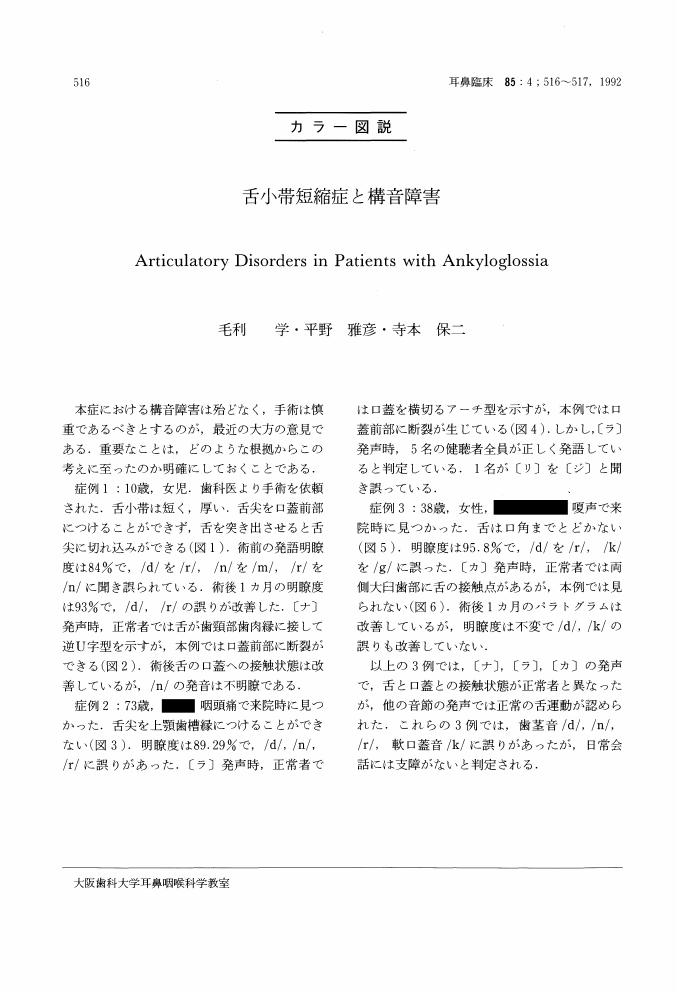3 0 0 0 OA 社会政策における互酬性の批判的検討
- 著者
- 平野 寛弥
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.239-255, 2012-09-30 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 33
本稿は, 社会政策における互酬性の変遷をその構造に着目して比較分析することにより, それぞれの互酬性の異同を明らかにするとともに, 新しい互酬性として提案されたTony Fitzpatrickの「多様な互酬性」がもつ社会構想としての可能性を検討するものである.第2次世界大戦後に成立した福祉国家体制が変容していくなかで, 社会政策における互酬性もまた変遷を遂げてきた. とりわけ現在支配的な言説となっている「福祉契約主義」においては, 権利に伴う義務の重要性が強調され, 権利を制約しようとする傾向が強まっている. これに対して「福祉契約主義」の対抗言説として提唱された新たな互酬性の1つである「多様な互酬性」は, 無条件な義務を前提としつつも, 権利に伴う義務の要求を逆手に取り, 義務の履行条件として無条件な権利の要求の正当性を主張する戦略であることが明らかとなった.この「多様な互酬性」からは, 無条件での基礎的生活保障の提供や「ヴァルネラブルな人々」に対する公正な保護, 多様な義務の選択可能性など, 現在直面している社会問題に対する新たな対応策への示唆を引き出すことができる. これらの内容は, 「多様な互酬性」が社会政策における配分原理という位置づけをはるかに超えて, ラディカルな社会変革の可能性を秘めた1つの社会構想ともいえる射程を有していることを示している.
3 0 0 0 OA 拡張現実感を用いた様々な光源環境下における対数美的曲面の再現に関する研究
- 著者
- 平野 亮 原田 利宣 床井浩平
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.2028-2035, 2012-08-15
本研究では,拡張現実感により現実空間における光源環境を再現し,その中で対数美的曲面をシミュレーションするシステムを開発した.具体的には,精密な拡散反射色で曲面の映り込みを再現するため,金属半球に反射した光源環境を球面調和解析した結果を用いてレンダリングを行った.また,開発したシステムを用いて,様々な光源環境下(晴天,曇天,夕日)における曲面の印象の違いに関する評価実験を行い,光源環境が曲面の印象に与える影響を明確にした.
3 0 0 0 座談会 『選挙学会紀要』10号を振り返って
3 0 0 0 OA 映画『プレステージ』に見るシルクハットの役割と意味
- 著者
- 平野 大
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.155-176, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)
- 参考文献数
- 41
【要旨】 本稿は、クリストファー・ノーラン監督による映画『プレステージ』について、シルクハットというアイテムに焦点を絞り、これを分析の手がかりとしながら、読み解いていくことを目的としている。同時に、いままであまり注目されてこなかったファッション・アイテムである帽子の、分析ツールとしての可能性の一端を提示していくことも試みていく。 映画『プレステージ』は19世紀末のロンドンを舞台に、「人間瞬間移動」を得意演目としていた二人の奇術師が繰り広げる確執の物語である。 本作を検証するにあたり、特に注目するシーンがある。それは、オープニングとエンディング部分に見られる数多くのシルクハットが空き地に散乱しているシーンである。アメリカの映画研究家、トッド・マガウアンは、『クリストファー・ノーランの嘘― 思想で読む映画論(The Fictional Christopher Nolan)』の中で、このシーンに関して「過剰な帽子は、創作活動に必然的に付随する余剰物である」と述べている。 このマガウアンの視点は、ノーランの映画製作観に鋭く踏み込む画期的なものである。しかし、果たしてシルクハットは、本当に創作活動の「余剰物」に過ぎないのであろうか。本作におけるシルクハットは「余剰物」以上の役割と意味を担っているのではなかろうか。 本稿においては、このマガウアンの指摘に対して、シルクハットの歴史や象徴性をふまえながら、検討を加えていく。
3 0 0 0 OA アラブ・イスラーム世界におけるマルクス主義の展開―運動・哲学・歴史像をめぐって
- 著者
- 栗田 禎子 長澤 榮治 水島 多喜男 阿久津 正幸 小林 春夫 鈴木 規夫 阿久津 正幸 清水 学 千代崎 未央 平野 淳一 湯川 武
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
従来、現代中東の社会運動をめぐる研究では、専らいわゆる「イスラーム主義」運動のみが脚光を浴びる傾向があったが、本研究では中東におけるマルクス主義の問題に着目し、その展開過程の特質を、運動、思想、歴史的・社会的背景という角度から分析した。研究の結果、中東のマルクス主義はこの地域の置かれた社会的・経済的現実と対峙し、地域に根ざした「知」の伝統(アラブ・イスラーム哲学の蓄積等)とも対話・格闘しながら発展してきたものであり、欧米からの単なる「移植」の産物ではないことが明らかになった。また、中東の社会・政治のあり方に関する従来の固定的・静態的イメージの見直しを行なうことができた。
3 0 0 0 OA 糠床の熟成に関する研究 熟成中の菌叢および糠床成分の変化
- 著者
- 今井 正武 平野 進 饗場 美恵子
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11, pp.1105-1112, 1983 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 8 7
野菜を漬けた糠床Tと対照床Cにおいて, 120日間熟成し微生物叢と成分の変化を追跡した.成分的変化としては,糖は30日までにほとんど消費され酸に変化した.脂質は増加し,ホルモルN,揮発性塩基性NはT床において60日間で急激に増加した.菌叢の変化としては初めEnterobacterを中心とするグラム陰性菌が優勢であったが, 30日以内にLactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Pec. halophilusが菌叢の大部分を占めた.熟成が進むにつれ, T床では酵母,乳酸菌以外のグラム陽性菌,そしてProteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae類縁菌を中心とするグラム陰性菌が多数検出され,それらのバランスが熟成臭に重要な影響を持つと思われた. 糠床中の食塩濃度は酸の生成やグラム陰性菌等の生育に密接な関係を持ち,酸や揮発性塩基性物質等のフレーバーに影響する重要な役割を持っていると考えられる.
3 0 0 0 OA 口腔出血を呈した特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) の2例
- 著者
- 市原 雅也 依田 知久 小泉 貴子 斉藤 美香 平野 浩彦 山口 雅庸
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.104-109, 2004-09-30 (Released:2014-02-26)
- 参考文献数
- 12
特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) は血小板が減少する後天性疾患であり, ITPの患者において口腔症状が頻繁に観察される。本来ITP治療の第一選択は副腎皮質ステロイド療法であり, ついで摘脾, 免疫抑制療法の順序である。そのほかに標準的な治療に反応しない, いわゆる難治例では免疫グロブリン大量静注療法 (IVIg療法) などが適用される。また最近, H.pylori陽性ITP症例における除菌療法の有効性が注目され厚生労働省によるITPの新しい診断基準, 治療プロトコールの作成が行われている。今回, われわれは口腔症状を呈したITP症例2例を経験したのでその概要を報告する。症例1は87歳, 男性, 口腔内出血を主訴に受診した。口腔出血, 血腫, 体幹の紫斑がみられITPと診断された。止血処置およびIVIg療法を施行された。その後血小板回復がみられ, 咬傷および感染予防のため抜歯を行った。症例2は69歳, 女性, 口腔内腫脹を主訴に受診した。ITPと診断されており, H.pylori除菌療法を受け, 血小板の回復がみられたために歯肉腫脹の原因歯を抜歯した。その後の経過は順調で後出血はみられなかった。
- 著者
- 平野 康次郎 洲崎 勲夫 徳留 卓俊 新井 佐和 藤居 直和 嶋根 俊和 小林 一女
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.666-672, 2019 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 26
歯性副鼻腔炎は歯性感染が上顎洞および副鼻腔に波及した疾患である。不十分な根管治療後の根尖病巣や歯根嚢胞が原因となることが多い。歯根嚢胞による歯性副鼻腔炎では原因歯の治療が必要であり根管治療や歯根端切除術などが試みられるが,開口状態で行う根管治療の限界や,歯根形態や根管形態により完全な根管治療を行うことは困難であり抜歯となるケースが多い。今回我々は,歯根嚢胞による歯性副鼻腔炎の患者に対しEndoscopic Modified Medial Maxillectomy(EMMM)によって経上顎洞的に歯根嚢胞を切除し,歯根端切除術を行うことにより歯牙を温存し良好な経過を得た症例を経験したので報告する。EMMMで上顎洞にアプローチし,ナビゲーションで歯根嚢胞の位置を同定し歯根嚢胞を切除した。その後に経上顎洞的にダイヤモンドバーで歯根端切除術を行った。術後経過は良好であり術後1年6か月の時点で歯牙は温存され歯根嚢胞の再発は認めていない。EMMMは鼻腔形態を保ちつつ上顎洞への広い視野と操作性が確保できる手術方法であり,上顎洞底部の病変である歯根嚢胞に対して有用であった。また,経上顎洞的にアプローチすることにより歯根尖切除も可能であった。今後長期の経過観察とさらなる症例の蓄積が必要であるが,歯牙温存希望の歯性副鼻腔炎の患者において選択肢の一つとなり得る術式と考えられる。
3 0 0 0 OA 公理的設計に基づくアクティブトルクロッドの創案と実現
- 著者
- 佐藤 裕介 金堂 雅彦 平野 芳則 山内 亮佑 谷村 浩史 舩津 宣成 藤井 隆良
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.1618-1623, 2019 (Released:2019-11-25)
- 参考文献数
- 14
ダウンサイジングターボ等の内燃機関の大幅な燃費向上は、エンジン加振力増大を招くため、車体への加振力を遮断する新たなマウントシステム構築が必要である。要求機能が相反した複雑なシステムを単純化して成立させる公理的設計を活用して、アクティブトルクロッドシステムを創案し、燃費向上と静粛性を両立させた。
3 0 0 0 OA ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進に取り組む小学校の類型化の試み
- 著者
- 平野 智紀 中尾 教子 脇本 健弘 木村 充 町支 大祐 野中 陽一 大内 美智子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Suppl., pp.125-128, 2020-02-20 (Released:2020-03-23)
- 参考文献数
- 7
本研究では,横浜市の公立小学校の校長を対象に行った質問紙調査をもとに,ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進の実態の類型化を行った.推進のタイプについてクラスタ分析を行い,5つのクラスタを得た.クラスタごとの特徴を分析すると,ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進に取り組んでいる学校はカリキュラム・マネジメントが進んでおり子どもの成長を実感していることが明らかになった。教員同士が高め合う学校文化が重要であることも示唆された.
3 0 0 0 OA 仙台湾における福島第一原発事故由来の放射性セシウムの挙動
- 著者
- 平野 信一 山田 努 杉原 真司
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2016年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100144, 2016 (Released:2016-11-09)
【目的】 東北地方太平洋沖地震の津波から5年余りが経過したが、沿岸域はいまだに東電福島第一原子力発電所事故による放射性物質汚染にさらされている。本研究では、阿武隈川水系などから仙台湾に流入する堆積粒子と原発事故由来の放射性物質の移動・拡散・濃縮を明らかにする。 【方法】 宮城/福島県境沖から仙台港までの仙台湾沿岸域においてこれまで10回(平成24年3月~平成27年9月)にわたり底質試料をエクマンバージ型採泥器、フレーガーコアラ―を使用し採取した。採取試料の堆積物放射能の測定に際しては、九州大学アイソトープ統合安全管理センターのゲルマニウム半導体検出器を使用し、経時変化・深度変化について論じた。 【結果】 試料の137Csの測定結果から、阿武隈川河口沖では、他の海域に比べて放射性セシウムの集積が顕著であることが明らかとなった。この海域においても、より陸地側(水深の浅い)の地点よりも、水深約20 mの地点(B3地点)で集積が進んでいる。これは、阿武隈川集水域で沈着放射性物質の自然除去が継続的に進行しているためと考えられる。集水域で放射性セシウム(134Cs、137Cs)の地表移動過程を経時的に観測した結果から、集中降雨時に大量の放射性物質が河川系を経て流出することが明らかとなっている(Minoura et al., 2014)。沈着放射性セシウムは、細粒物質(フミン、粘土粒子など)に付随している。これら浮遊物が増水時に河川を経て河口から流出し、陸水が海水と混合する過程で凝集し阿武隈河口沖に沈積したと解釈される。セシウム濃度の増大傾向は、集水域における放射性物質が降水により易動的となり、地表流水により効果的に排出されている可能性を示唆している。河口沖で凝集・沈積した細粒堆積物は、再移動作用が波及しない限り、緩やかな生物擾乱を受けながら集積してゆく。この堆積効果により、地表沈着放射性物質は河口沖に埋積される。しかし、強力な底層流を促す沿岸流の発達などは、こうした底質を大規模に侵食する可能性がある。その場合には、埋積された放射性物質の急激な拡散が懸念される。 また、名取川河口沖、特に水深20 m付近のD4地点でも放射性セシウムの中濃度集積が進んでおり、名取川上流域および河口沖でも、それぞれ阿武隈川集水域および河口沖における同様な過程が進行しているとことが予想される。 このように、大河川河口沖では、内陸から流送された放射性物質が水深約20mの海底に堆積しホットスポットを形成していた。
3 0 0 0 OA 撰択的無嗅覚症
- 著者
- 山田 成子 渡辺 泰夫 平野 優子 内藤 儁
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.401-406, 1973-03-20 (Released:2008-12-16)
- 参考文献数
- 14
嗅覚の生理に関しては不明の処が少なくない,嗅覚は非常に鋭敏な感覚であるが,万余の匂いが,どのようにして末梢のreceptorに受容されるのか,末梢のreceptorの受容機構はどの様になつているか,また末梢で受容された刺激は,中枢へどの様に伝達されるか,など未だ未解決の問題が多い.嗅覚の検査に用いられるべき嗅素として,最も適当な匂いは何であるかという基本的な問題も解決されていない.このような現状において文部省科学研究班,"嗅覚測定の基準設定"が結成された.私どもはこの班の一員として次の10種の嗅素の各種濃度(10-1より10倍稀釈で10-14迄)で日本人の平均閾値の測定を行なつている.使用ている嗅素は,バラ臭,糞臭,腐敗臭,樟脳臭,酸臭,麝香,フェノール臭,焦臭,果実臭,にんにく臭,である.撰択的無嗅覚症(selective anosmia or specific anosmia Amoore)という病名はAmooreにより使用され,ある種の匂いにのみ特異的に閾値の高い場合に用いられる.現在まで238名の測定対象に8名の撰択的無嗅覚症例を認めた.このような8症例の中,2例は嗅覚障害を自覚していない.男女性別に差はなく 男女共各4名である.撰択的無嗅覚症がみとめられた嗅素はフェノール臭,麝香臭,パラ臭,糞臭である.撰択的無嗅覚症の機構は不明であるが,恐らく嗅覚受容機構における部分的障害と考えられる,Amooreによれば,青酸,メルカプタン,イソ酪酸に嗅盲が認められるが,嗅盲は遺伝的因子が強いと考えられる,一方,撰択的無嗅覚症は後天的な受容機構の受傷性の差によつてもおこることが考えられる.撰択的無嗅覚症に認められる嗅素は嗅覚機能検査に必要な基本的嗅素の1つであると思われる.
- 著者
- 平野 隆之 奥田 佑子
- 出版者
- 日本福祉大学社会福祉学部
- 雑誌
- 日本福祉大学社会福祉論集 (ISSN:1345174X)
- 巻号頁・発行日
- no.134, pp.91-106, 2016-03
生活困窮者自立支援制度の「自由な運用」を推進する方法として,東近江市でのモデル事業の研究で明確となった「実施体制」と「体制整備」との相互関連性を,大津市と高島市のなかにも見出すという研究方法を用いて,かかる推進枠組みの有用性と運用面での活用方法を検討した.その結果,実施体制のなかでも入口の相談強化や出口のプログラム創出には,体制整備として,①庁内・庁外を問わず連携会議の場の創出に加え,その場のマネジメントが重要であること.また,通常の会議とは異なった場の設定も有用であり,②手引きの作成や地域福祉計画等の委員会が相当すること.国のマニュアルにある「資源の開発」は各自治体においてハードルが高いことから,民間組織が先行する取り組みを評価し制度運用に活用することが有効な方法であり,そのための体制整備としては,③資源の開発における公民協働の方式が有効である.実施体制とその体制整備の概念化は,運用上の指針として,また比較分析の枠組みとして有用である.
- 著者
- 上野 雄己 平野 真理 小塩 真司
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- pp.28.1.10, (Released:2019-06-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
This study aimed to reinvestigate age differences in resilience in a large cross-sectional Japanese sample (N=18,843; 9,657 men, 9,156 women; meanage=47.74 years, SDage=14.89, rangeage=15–99 years). The data were obtained from a large cross-sectional study by NTT DATA Institute of Management Consulting, Inc. The results of hierarchical multiple regression indicated that age and squared term of age were significantly positively associated with resilience. These results reconfirm that resilience in Japanese individuals increases with age, corroborating the findings of previous studies.
3 0 0 0 OA しきい値なし波形相関による前震検出
- 著者
- 平野 史朗 川方 裕則 土井 一生
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
Revisiting earthquake catalogs have revealed that 40% or more of major earthquakes are accompanied by foreshock activities, at least in California [Abercrombie & Mori 1996 Nature] and Japan [Tamaribuchi et al. 2018 EPS].To investigate whether the foreshocks are magnification and activation of background seismicity, we have to compare waveforms due to the foreshocks and background events that might be sometimes uncataloged because of their small sizes.We can mine even small seismic signals similar to some template waveforms from continuous waveform records by using a matched-filter analysis based on cross-correlation coefficients (CC) between the template waveforms and continuous records.However, in the conventional analysis, we have to define a threshold of CC to detect similar seismic waveforms, which have been chosen subjectively and empirically.Then, we propose a threshold-free method to detect outliers from the empirical distribution of CC among seismic waveforms.In our framework, empirical distributions of the coefficients are modeled by the theory of extreme value statistics, and the detectability is automatically determined from Akaike's Information Criterion (AIC), depending on data.We applied the method of seismic signal detection to 2-years-continuous records before an M5.4 earthquake in Nagano, Japan (June 30, 2011) that followed 27 foreshocks cataloged by JMA.First, we found that the empirical frequency distribution of CC between the continuous records and foreshocks did not follow a normal distribution, which means that we cannot estimate the possibility of a false positive by assuming the normal distribution as a model.Instead, we also found that the maximum value of CC in every few seconds follow the Gumbel distribution after elimination of some outliers.The elimination can be achieved by comparing AICs of data including and excluding the outlier candidates.Given this method, we found a similar event ~2 months before the mainshock and 3 similar events 3-4 days before the mainshock.This result implies that the foreshocks were not similar to background events, and hence, not magnification or activation of them.
3 0 0 0 OA 舌小帯短縮症と構音障害
- 著者
- 平野 淳一
- 出版者
- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 : Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.555-559, 2014-03-14
3 0 0 0 IR タンパク質の消化吸収に対する食物繊維の影響
- 著者
- 平野 千鶴 藤森 直江 菊野 惠一郎
- 出版者
- 和洋女子大学
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要. 家政系編 (ISSN:09160035)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.17-24, 1991-03-31
食物繊維が,他の栄養素の消化を妨げるという作用に着目し,食物繊維の種類や摂取量によるタンパク質の消化吸収への影響を調べた。結果は次の通りである。1)精製したセルロースパウダーは,殆ど影響を及ぼさなかった。2)ごぼうの繊維を,多く摂取するほど消化率は低下した。3)ごぼうに含まれる種々の繊維の分析を行い,タンパク質の消化吸収に影響を及ぼしている繊維は何かを追求し,また,食物繊維を長期間に渡って摂取すると,どの様に消化率に影響を及ぼすか,今後検討していきたい。本実験に御協力頂きました江藤圭子,春日麗子,加庭桂子,神戸香の諸氏に感謝致します。
3 0 0 0 関東平野における雷雨性降雨と風の場の構造に関する研究
近年,関東平野では夏季の夕方に集中豪雨が頻発する.著者ら1)はこれらの集中豪雨発生要因の解明を目的とし,関東平野各地において大気観測を行い,海風が水蒸気及びエアロゾル輸送に与える影響を明らかにしてきた.本稿は,その一環として2005年4月26日に関東平野西部で発生した降雨域の移動と雨域内の風の場,及び上空の風との関係について解析したものである.以下に得られた知見を示す.1)降雨域の瞬間降雨強度が強くなると,その移動速度も増加した.2)VVP法を用いて算出した降雨域内の風の場は,降雨域の移動方向とほぼ同方向であった.3)降雨域の高度は4km程度であり,高度1.5km付近において瞬間降雨強度が強かった.4)降雨域の通過とともに水平風速が約8m/s程度増加し,その後風向が北に変化した.