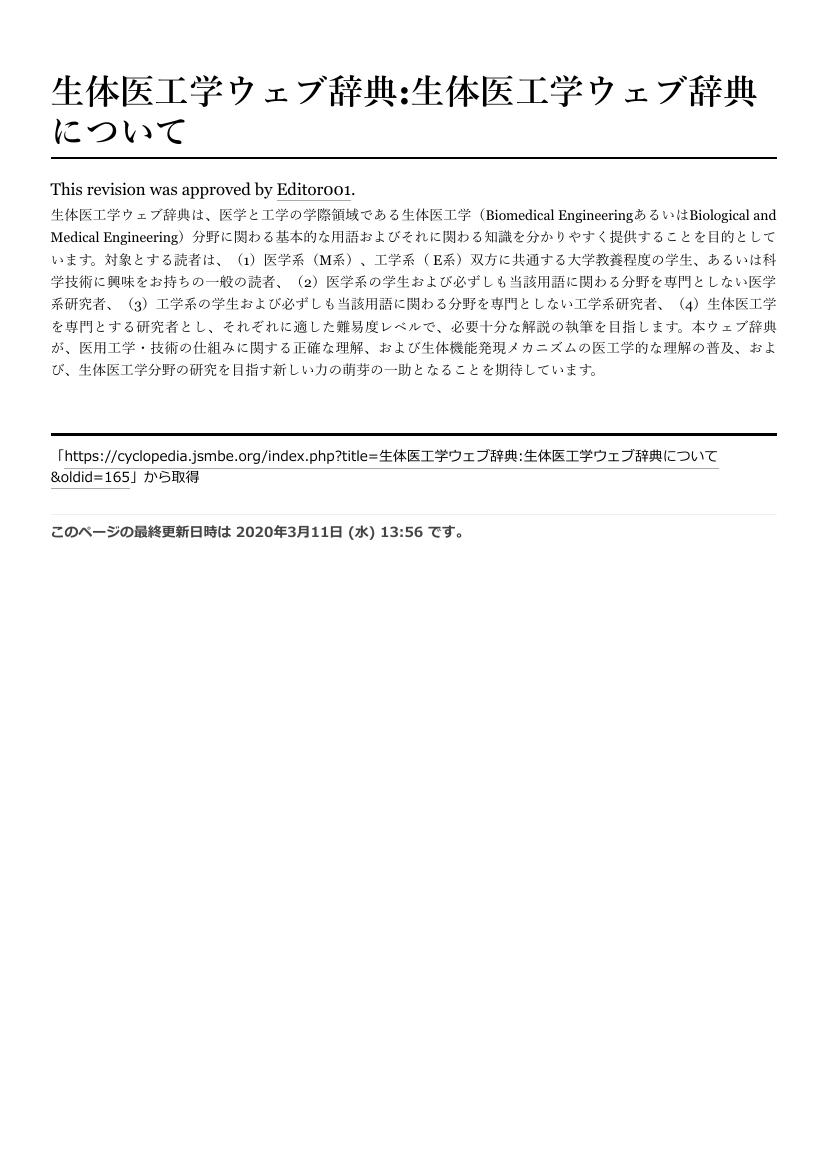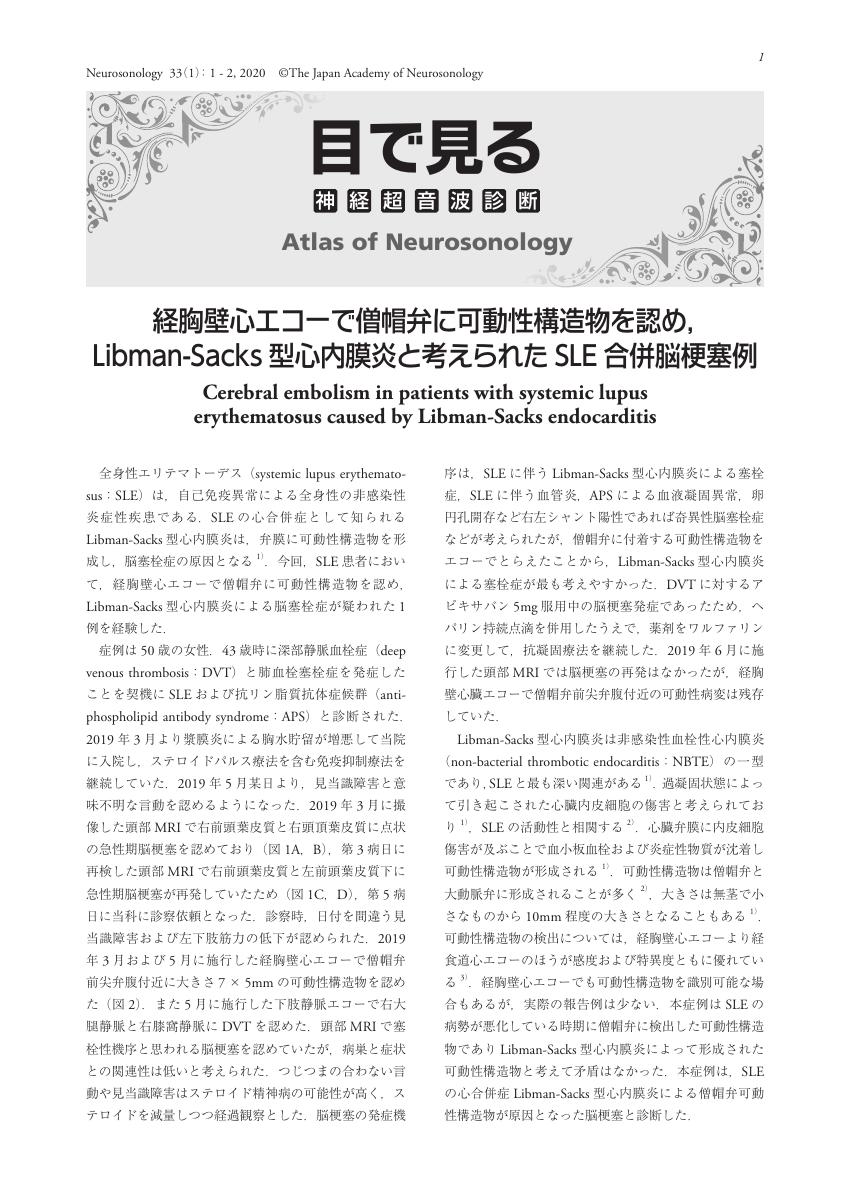2 0 0 0 OA 3.高カリウム血症と低カリウム血症
- 著者
- 平野 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.10, pp.1838-1843, 1997-10-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
生体へのK負荷, K欠乏に対する調節系として腎が最も大きな役割を果す.皮質集合管主細胞のK分泌と介在細胞のK吸収によるKバランス維持機構が明らかになってきた. Kは主要な細胞内電解質であり,細胞機能の維持には不可欠である. K不足, K過剰は神経および筋肉系に影響を及ぼす.高K血症が疑われる場合には血清K濃度と心電図をチェックし,即時的に処置をする.一方,低K血症は原因の除去・原疾患の治療が第一である.
2 0 0 0 OA 会議報告:AAMAS 2022(The 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems)
- 著者
- 平野 正徳
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.679-680, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)
2 0 0 0 OA 掌蹠膿疱症診療の手引き2022
- 著者
- 日本皮膚科学会掌蹠膿疱症診療の手引き策定委員会 照井 正 小林 里実 山本 俊幸 大久保 ゆかり 阿部 名美子 井汲 菜摘 石井 まどか 伊藤 明子 梅澤 慶紀 金蔵 拓郎 川上 洋 岸部 麻里 黒木 香奈 車谷 紋乃 河野 通良 清水 忠道 辻 成佳 十一 英子 中村 元樹 西田 絵美 葉山 惟大 平野 宏文 藤澤 大輔 藤城 幹山 藤田 英樹 松本 由香 森田 明理 村上 正基
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, no.9, pp.2055-2113, 2022-08-20 (Released:2022-08-23)
- 参考文献数
- 384
2 0 0 0 OA 社員格付原理としての役割主義の機能要件 ──人事部の権限と体制に着目して──
- 著者
- 江夏 幾多郎 平野 光俊
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.67-79, 2012-03-20 (Released:2022-08-27)
- 参考文献数
- 44
近年の日本企業で普及しつつある社員格付原理としての役割主義について理論的に定式化し,その機能要件を明らかにした.統計的分析の結果によると,能力主義と職務主義の性質を併せ持つ役割主義が業績に負の影響を与える傾向は,人事権が人事部に集中するほど弱くなる.また,対正規従業員比でスタッフ数が少ない,少数精鋭的でありうる人事部ほど,「役割主義×人事部集権」の機能性の向上に貢献できることが示された.
- 著者
- 漆畑 文哉 吉田 淳 平野 俊英
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.174-186, 2022 (Released:2022-07-08)
- 参考文献数
- 29
To clarify the learning effect of classes using granular models, a model of concrete objects in which learners can represent and manipulate thermal phenomena dynamically, and an animation that shows the representational operations were created. Using these, we conducted a class on how water heats up (convection), analyzed the learners’ expressive manipulations to explain thermal phenomena, and investigated whether the convection concept was formed. The results indicated that some learners changed their convection concept into a scientific interpretation after the explanatory activity using the model and animation. Therefore, the results suggest that learning to manipulate scientific representations using animation with models is effective in promoting the elaboration of convection concepts.
2 0 0 0 OA 現代日本の宗教と法
- 著者
- 平野 武
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.71-85, 2003-10-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 24
2 0 0 0 OA 自宅で発症した美容院卒中症候群の1例 日常生活の頸部後屈により発症した脳梗塞
- 著者
- 植田 明彦 寺崎 修司 永沼 雅基 松浦 豊 橋本 洋一郎 平野 照之 内野 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.461-464, 2004-09-25 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 10
症例は30歳男性.3年前よりソファーに寝そべり肘掛けから頭部を垂らし頸部を後屈させて,ドライヤーで髪を乾かす習慣があった.2002年12月2日,この姿勢で頸部を左に回旋させたところ,急に回転性のめまいが出現したため,当院を受診した.来院時,右注視方向性眼振,構音障害,顔面を含む右半身の温痛覚低下を認め,左延髄外側症候群を呈していた.MRIT2強調画像で左延髄外側に高信号域を認めた.左椎骨動脈V3部にMRIでinitimal flap,intramural hematomaを認め,脳血管造影では,string signを認めたため,椎骨動脈解離と診断した.近年,美容院での洗髪の際に頸部を後屈させた姿勢で発症する美容院卒中症候群(beauty parlor stroke syndrome)が注目されているが,本症例も同様の機序で発症したと考えられた.
2 0 0 0 OA 白亜紀海洋無酸素事変
- 著者
- 平野 弘道 安藤 寿男
- 出版者
- 石油技術協会
- 雑誌
- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.305-315, 2006-05-01 (Released:2007-11-01)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 4 2
Thirty years passed since the Cretaceous Oceanic Anoxic Events were proposed by Schlanger and Jenkyns (1976). Three events, OAE1 to 3 were recognized at the beginning of the research. Nowadays, however, OAE1 is subdivided into four subevents, OAE1a, b, c, and d. The OAE1b subevent is further subdivided into three components, Jacob, Paquier, and Leenhardt. The existence of Mid-Cenomanian Event (MCE) between OAE1d and OAE2 is drawing attentions of world scientists. A concise review of the researches on these events and subevents is followed by more detailed descriptions of the synonymy (local names), geographic distribution, age, stable carbon isotope fluctuations, extinction and/or radiation of fossils, major synchronous events, characteristics including the duration and the types of kerogen, and their causal factors. It is recognized that all OAEs do not have the same causal factor. The western part of the Tethys and the narrower early Atlantic were rather closed basins, where anoxic to dysoxic conditions easily occurred through the stratification of water column by run off, like the Sapropel event 1 in the Holocene Mediterranean Sea. The Cretaceous global OAEs may have occurred either by the stagnation of the deep water associated with the global warming or by propagation of marine organisms. Due to a large amount of input of terrestrial siliciclasitics, the regional influence of OAEs in the Japanese Cretaceous strata may differ from that of the Tethyan/Atlantic region, even if the occurrence of OAEs is ocean wide or globally synchronous.
2 0 0 0 OA 音声外科のすべて―過去から未来へ―
- 著者
- 平野 滋
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.163-167, 2016-03-20 (Released:2016-04-19)
- 参考文献数
- 25
再生医療は20世紀後半のブレークスルーであり, 21世紀における発展が期待されている. 喉頭領域においても枠組み, 筋肉, 粘膜, 反回神経などの再生研究が活発に行われており, 一部は既に臨床応用に至っている. 再生医療は細胞を用いることで失われた組織を造る, あるいは失われた機能を復活させることを目的とし, 細胞およびその調節因子, さらに細胞が活動できる土台の3要素を駆使することで組織再生を図るものである. 声帯の硬化性病変である瘢痕や萎縮に対しては, 種々の幹細胞や細胞増殖因子を用いた再生実験が進んでいるが, 中でも塩基性線維芽細胞増殖因子と肝細胞増殖因子が有望視されており, いずれも臨床応用に至っている. 枠組みの再生には人工の足場材料の開発が, 反回神経においては各種ポリマーを用いた神経再生誘導チューブの開発が進められているが, 最近の脱細胞技術の発展により, さらに大きな組織, 例えば喉頭全体の再生用足場材料についても研究が開始されている. これらの研究が進むことで喉頭全摘後の喉頭再生も夢ではなくなることが期待される.
2 0 0 0 OA 河川におけるセキレイ類の順位性
- 著者
- 平野 敏明 樋口 広芳
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2-3, pp.79-80, 1986-12-25 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
A dominance hierarcy of Motacilla wagtails (M. grandis, M. alba, and M. cinerea) and Water Pipits (Anthus spinoletta) was investigated on a stream in Utsunomiya, central Japan, in the winters of 1981-1983. An almost linear hierarchy existed among the species and between sexes, with ranking (most to least dominant) as follows: male M. grandis, female M. grandis, male M. alba, female M. alba, M. cinerea, and A. spinoletta. The proportion of victories by dominants was 100% except for a few encounters (5.7%) between female M. grandis and male M. alba. Dominance status was not necessarily related to their body sizes. Male M. grandis chased the other species more severely and more frequently than the others did.
2 0 0 0 OA 生体医工学ウェブ辞典(第一分冊)
- 著者
- 相川 慎也 芦原 貴司 天野 晃 有末 伊織 安藤 譲二 伊井 仁志 出江 紳一 伊東 保志 稲田 慎 井上 雅仁 今井 健 岩下 篤司 上村 和紀 内野 詠一郎 宇野 友貴 江村 拓人 大内田 研宙 大城 理 太田 淳 太田 岳 大谷 智仁 大家 渓 岡 崇史 岡崎 哲三 岡本 和也 岡山 慶太 小倉 正恒 小山 大介 海住 太郎 片山 統裕 勝田 稔三 加藤 雄樹 加納 慎一郎 鎌倉 令 亀田 成司 河添 悦昌 河野 喬仁 紀ノ定 保臣 木村 映善 木村 真之 粂 直人 藏富 壮留 黒田 知宏 小島 諒介 小西 有人 此内 緑 小林 哲生 坂田 泰史 朔 啓太 篠原 一彦 白記 達也 代田 悠一郎 杉山 治 鈴木 隆文 鈴木 英夫 外海 洋平 高橋 宏和 田代 洋行 田村 寛 寺澤 靖雄 飛松 省三 戸伏 倫之 中沢 一雄 中村 大輔 西川 拓也 西本 伸志 野村 泰伸 羽山 陽介 原口 亮 日比野 浩 平木 秀輔 平野 諒司 深山 理 稲岡 秀検 堀江 亮太 松村 泰志 松本 繁巳 溝手 勇 向井 正和 牟田口 淳 門司 恵介 百瀬 桂子 八木 哲也 柳原 一照 山口 陽平 山田 直生 山本 希美子 湯本 真人 横田 慎一郎 吉原 博幸 江藤 正俊 大城 理 岡山 慶太 川田 徹 紀ノ岡 正博 黒田 知宏 坂田 泰史 杉町 勝 中沢 一雄 中島 一樹 成瀬 恵治 橋爪 誠 原口 亮 平田 雅之 福岡 豊 不二門 尚 村田 正治 守本 祐司 横澤 宏一 吉田 正樹 和田 成生
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.Dictionary.1, pp.1-603, 2022 (Released:2022-03-31)
2 0 0 0 明治前期東京時計産業の功労者たち
- 著者
- 平野光雄 著
- 出版者
- 「明治前期東京時計産業の功労者たち」刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1957
2 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム障害が併存する強迫性障害の実行機能に着目した心理プログラム開発
強迫症の治療には,暴露反応妨害法を含む認知行動療法が有効である。しかし,認知機能の低下や自閉スペクトラム症の併存や、それに伴う実行機能の低下が、認知行動療法の治療効果に影響を与えている可能性がある。強迫症の治療効果に影響を与える要因を調査した結果、実行機能の機能の一部である作業記憶と、自閉スペクトラム症の特性を示すコミュニケーション能力の低下が、強迫症の認知行動療法に対する効果を低下させる可能性が示され、自閉スペクトラム症を併存する強迫症の実行機能に着目した心理プログラムを開発の助けとなる知見を得た。
2 0 0 0 OA 統合失調症の幻聴の神経基盤─脳構造・脳機能研究
- 著者
- 鬼塚 俊明 中村 一太 平野 昭吾 平野 羊嗣
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.73-78, 2019 (Released:2019-12-28)
- 参考文献数
- 5
幻聴が起こるメカニズムは単純なものではないが,症状と関連のある脳構造・脳機能研究を行うことは重要と思われる。本稿では我々が行った研究で,幻聴の重症度と関連のあった脳部位・脳機能研究での結果を紹介する。脳構造研究では,外側側頭葉の亜区域を手書き法にて測定し,体積を測定した。幻聴のある患者群で左の上側頭回は著明に小さく,左中側頭回,左下側頭回でも有意に小さいという結果が得られた。すなわち,幻聴のある患者群は幻覚のない患者群に比べ,左半球優位(特に上側頭回)に体積減少があることが示唆された。 声に対するP50mの研究では,左半球の抑制度と幻聴のスコアに有意な正の相関を認めた(ρ=0.44,p=0.04)。つまり,人の声に対するフィルタリング機構の障害が強い統合失調症者ほど,幻聴の程度が重度であるということが示唆された。さらに,聴覚定常状態反応の研究では,80 Hzのクリックに対する左半球のASSRパワー値と幻聴の重症度に有意な負の相関を認めた(ρ=‐0.50,p=0.04)。つまり,左半球の80 Hz‐ASSRの障害が強い統合失調症者ほど幻聴の程度が重度であるということが示唆された。 今後,脳構造・脳生理学的研究は統合失調症の病態解明のアプローチとして一層重要になっていくと思われる。
2 0 0 0 OA 江戸時代の高齢者の齲蝕
- 著者
- 藤田 尚 平野 浩彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.175-182, 1999-03-31 (Released:2014-02-26)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
江戸時代の古人骨99個体を資料とし, 壮年者と高齢者の齲蝕の病態にどのような相違があるかを検討した。その結果, 江戸時代においては, 高齢者全体の齲歯率18.8%は壮年者全体の齲歯率7.0%よりも有意に高いこと (P<0.001) 。ほとんど全ての歯種で, 高齢者の齲歯率が壮年者よりも高い傾向があること。前歯部の齲蝕は壮年者にはほとんどみられないが, 高齢者では一定の割合で認められること。壮年者と高齢者の齲歯率の相違の程度は, 下顎歯よりも上顎歯でより顕著であること。齲蝕発症部位として, 高齢者では歯頸部齲蝕・根面齲蝕が全体の66.4%を占あ, 歯頸部齲蝕・根面齲蝕は加齢とともにその割合が増加する一方, 咬合面齲蝕は壮年者よりも減少すること。縄文時代人に多く見られた頬側面齲蝕の減少は, 江戸時代には歯磨きの習慣が広まっており, 歯磨きによって頬側面の衛生がある程度保たれたと考えられること。高齢者では上顎歯の喪失歯率が下顎歯の喪失歯率よりも有意に高く, 歯周疾患がその原因として考えられること, などが確かめられた。高齢社会にあたって, 高齢者の齲蝕病態の歴史的変遷を把握することは, 将来の口腔衛生の指針作りや予防歯科学の領域においても有益と思われるので報告する。
- 著者
- 中田 遼志 河野 浩之 平野 照之
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経超音波学会
- 雑誌
- Neurosonology:神経超音波医学 (ISSN:0917074X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.1-2, 2020 (Released:2020-05-09)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 神経生理学的研究からみた統合失調症の GABA 機能障害
- 著者
- 平野 羊嗣
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.199-203, 2015 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 29
最近の,脳波や脳磁図,光遺伝学といった電気生理学的研究の進歩や,死後脳研究の知見により,皮質の周期的神経活動(neural oscillation)の異常が,精神疾患の病態生理に深くかかわっていることがわかってきた。神経活動の中でも主にγ帯域の周期的皮質活動(γ band oscillation)が,認知や知覚,または意識に関連していることが知られているが,認知機能や知覚処理の障害,自我意識障害を有する統合失調症患者では,特にこのγ band oscillation が障害されていることが明らかになってきた。γ band oscillation の障害は,神経回路内のリズムメーカーとしての機能を担う GABA 作動性の抑制性介在ニューロンの機能低下と,興奮性ニューロンの障害(NMDA 受容体の機能低下)ならびに,この両者のバランス(E/I バランス)が破綻することにより生じるとされている。さらに,これらの現象は種を問わず認められ,統合失調症のモデル動物でも同様の結果が得られるため,統合失調症の新たな病態モデル,治療ターゲットとして注目されている。
- 著者
- 平野 幹雄 鈴木 徹 野口 和人
- 出版者
- 宮城教育大学特別支援教育総合研究センター
- 雑誌
- 宮城教育大学特別支援教育総合研究センター研究紀要
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.22-30, 2010-06
本稿においては、筆者らが高機能自閉症およびアスペルガー症候群の子どもを対象におこなっている社会性発達の支援のための放課後実践について、その概要と開始から1年半の間の子どもの様子について紹介することを目的とした。対象児は、11歳から17歳までの高機能自閉症およびアスペルガー症候群の子ども5名で、あった。筆者らの放課後活支援においては、対象児が鉄道やコンピュータに興味を持っていたことから、両者を組み合わせて子どもがしたいと思う活動として組織した。具体的には、双方向型のブログの運営と定例会の開催、一日旅行を通じて支援をおこなった。学校行事と日程が重なる日以外の対象児の参加状況はほぼ皆勤であった。定例会を重ねることで、対象児から積極的に挨拶をする様子、自らの発言に対する他者の関心の有無に注意を払う等の変化が見られた。これらの変化は、長期的な支援をおこなったこと、筆者らの実践が対象児において主体的に参加できる場として機能したことによると考えられた。また、鉄道という共通の土俵ができあがったこと、リアリティをもって長期間かかわりを続けたことによって、対象児にとって筆者らが親しくもリスペクトされる存在となったことが重要であると考えられた。
- 著者
- 岡田 宏基 平野 大輔 谷口 敬道
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.292-300, 2020-06-15 (Released:2020-06-15)
- 参考文献数
- 32
本研究の目的は,陰性症状の5つの因子である失快楽症,非社会性,意欲の低下,感情鈍麻,言語の貧困と社会機能との関連を検討することである.分析対象者は当院に入院する長期入院統合失調症者51名であった.従属変数を精神障害者社会生活評価尺度下位項目,独立変数をBrief Negative Symptom Scaleの下位項目とし,Spearmanの順位相関係数および重回帰分析にて分析した.結果,日常生活,労働には意欲の低下,対人関係には非社会性,感情鈍麻が有意に寄与していた.自己認識についてはどの因子とも関連していなかった.陰性症状の中でも意欲の低下,非社会性,感情鈍麻の改善に取り組むことが,退院支援に向けて有用であることが示唆された.
2 0 0 0 OA 吻合部におけるシャント音とドップラー超音波を用いた上腕動脈平均血流量,血管抵抗指数の関係
- 著者
- 西浦 庸介 太田 圭祐 小林 利江 倉知 あかね 村瀬 景子 石黒 正崇 平野 ツヤ子 伊藤 友一 井手 敦基 濱野 髙行
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.215-220, 2022 (Released:2022-03-28)
- 参考文献数
- 18
われわれはシャント音を人工知能で音質を数値化し評価できることを報告した.しかし,聴診部位の情報が欠損しており閉塞の予測因子としては不足があった.また,分枝の多いシャントは血流量が低下しにくいため,ドップラー超音波による上腕動脈平均血流量(mFV)や血管抵抗指数(RI)では閉塞を予見しにくいと言われている.しかし,聴診部位が記録しやすい吻合部のみでのシャント音であれば,前述超音波所見との関連を認めるのではないかと考えた.評価項目として,シャント吻合部での音質と超音波によるmFV,RIを用いて比較を行った.その結果,シャント血流量を示すmFVはシャント聴診音の強度と相関した.超音波によるRIは人工知能で判断される断続音と弱い相関を認めた.日々の聴診によりシャント血流量を間接的に評価することが可能であると考えられた.しかし,吻合部のみでなくシャント全長にわたる聴診が狭窄音の評価に重要である.