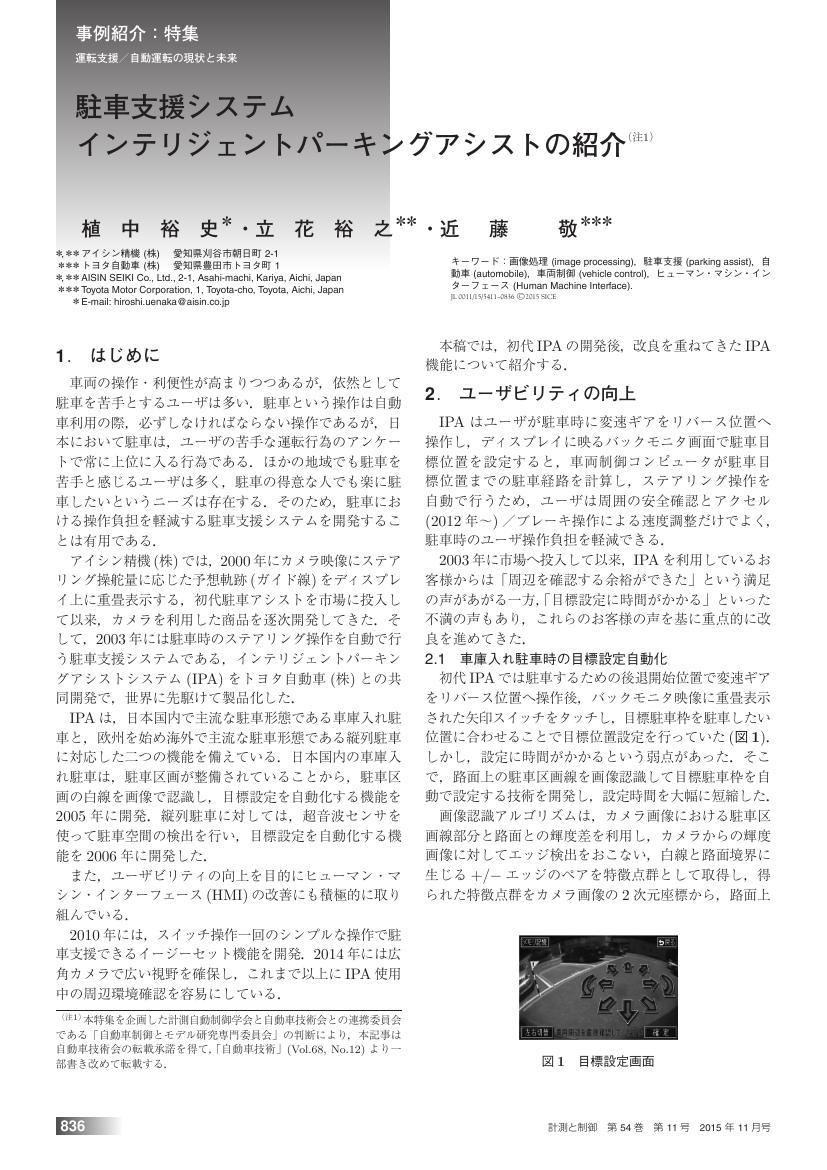1 0 0 0 日本学術会議 第5部報告
1 0 0 0 OA バイオリファイナリーの現状と展望
- 著者
- 蓮沼 誠久 石井 純 荻野 千秋 近藤 昭彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.689-695, 2015-09-20 (Released:2016-09-20)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
持続可能な社会へ向かうためには再生可能エネルギーが中心的な役割を果たすことが求められている.そのなかで,バイオマスから液体燃料やバルクケミカルを経済性良く,高効率で生産する技術の開発が期待されている.バイオマスとしては,安定的な供給が可能で,食糧と競合しないリグノセルロース系バイオマスの利活用が望まれている.本稿ではリグノセルロース系バイオマスからのエタノールの製造プロセスについて研究の課題と最新の知見を紹介するとともに,バイオプロセスによるバルクケミカル生産に関する最近の研究例についても紹介する.
1 0 0 0 脳内身体表現のスローダイナミクスモデル
四肢の欠損した患者や統合失調症の患者は,自分の身体への所有感が低下することや自分の運動に対して主体感が持てなくなり,健常者と比べて脳内身体表現が変容していることが知られている.本年度はこの身体所有感や運動主体感が脳内身体表現の変容に対してどのように影響を与えるのか定量的に評価し,数理モデルの構築を行った.具体的には,健常者に対してラバーバンド錯覚という現象を起こした上で,身体所有感と運動主体感がそれぞれ感じられない条件で,脳内身体表現がどのように変化するか調べた.その結果,被験者が能動的に動くことで,運動主体感は増し,ラバーバンド錯覚で呈示する腕の映像が実際のものと異なる時には,身体所有感が低下することがわかった.次に脳内身体表現の変容に対して,身体所有感と運動主体感が与える影響を定量的にモデル化した結果,対象とする被験者の数回の試行データを用いることで,変容がどの程度進むかを推定することができるようになった.またこのような知見を実際のリハビリテーションに応用可能なプラットフォームとして,バーチャルリアリティ環境の運動介入システムの実装を行った.これは使用者の腕の運動と筋活動を計測し,それをリアルタイムで使用者にフィードバックするシステムである.このシステムを使うことで,実際に使用者が行っている運動とは異なる結果を返したり,あえて運動を過剰に表示することで,運動を誘導することができることが分かった.
1 0 0 0 OA 下肢伸展挙上保持における体幹筋活動
- 著者
- 近藤 裕貴 岩田 学
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.577-581, 2011 (Released:2011-11-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
〔目的〕体幹筋へのアプローチとして,臨床場面でのSLRの活用方法を見出すために下肢伸展挙上(以下,SLR)保持における非挙上側下肢の条件設定によって,下肢・体幹筋活動がどのように変化するか調査した.〔対象〕健常男性21名(年齢20.6±3.7歳)を対象とした.〔方法〕課題動作は,非挙上側下肢を鉛直下方向に押すことを強調したSLR保持:「押す」,押さないことを強調したSLR保持:「押さない」,特別な条件を加えない通常のSLR保持:「通常」,の3条件とした.非挙上側下肢の肢位は股・膝関節伸展位とした.表面筋電図により,脊柱起立筋,腹直筋,内側ハムストリングス,大腿直筋,それぞれ左右両側の計8筋の筋活動を測定した.〔結果〕脊柱起立筋は「押す」,腹直筋は「押さない」において,左右両側とも他の2条件に比べて有意に%MVCが高かった.〔結語〕「押す」,「押さない」の2条件は,脊柱の運動が制限されていても様々な臨床場面で体幹筋活動を促して,体幹機能の賦活化を図ることが可能であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 高齢者における下肢直達牽引の問題点
- 著者
- 秋山 寛治 近藤 司
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.276-278, 1994-03-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 3
We reviewed the complications developing after treatment with wire traction for femoral neck fractures in thirty elderly female patients ranging in age from 69 to 90 years. Eight cases of wire movement, six cases of local infection, and nine cases of psychological symptoms were recorded during traction. Regarding the mobility of knee joint and quadriceps muscle power at four weeks postoperatively, no significant difference was found between traction through the distal part of the femur and the tibial tuberosity.
1 0 0 0 OA ガリレオ・ガリレイと材料力学
- 著者
- 近藤 恭平
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.589, pp.32-41, 2003-02-05 (Released:2019-04-15)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 デュラグルチドの血糖コントロールおよび腎機能への影響
- 著者
- 石郷 友之 近藤 蕗 立石 莉穂 野々山 雅俊 藤居 賢 木明 智子 中田 浩雅 野田 師正 宮本 篤
- 出版者
- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会
- 雑誌
- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.201-209, 2018 (Released:2019-01-29)
- 参考文献数
- 30
糖尿病性腎症は末期腎不全(end-stage renal disease:ESRD)や血液透析の主要な原因の一つである。また、ESRDや血液透析患者では心血管イベントや死亡率の増加が報告されており、腎機能の低下や透析導入を遅らせることは重要な課題である。近年、glucagon-like peptide 1(GLP-1)受容体作動薬であるリラグルチドの腎保護作用が報告されている。しかし、デュラグルチドについては海外でアルブミン尿の減少効果が示されているのみであり、本邦においてデュラグルチドの腎機能への影響についての報告はまだない。その為、我々はデュラグルチドの血糖コントロールおよび腎機能への影響について検討した。2016年9月から2017年9月にデュラグルチドが開始された症例は45例で最終的な解析対象は19例であった。主要評価項目はデュラグルチド開始3ヶ月後の糖化ヘモグロビン(HbA1c)、推算糸球体濾過速度(eGFR)とし、腎機能への影響についてはeGFRの変化量も調査した。平均年齢は57.4歳で男性10例、女性9例であった。HbA1cは、デュラグルチド開始時8.9 ± 0.4%(平均 ± SE)から3ヶ月後8.0 ± 0.4%と有意な低下を認めた(p = 0.019)。また、eGFRは開始時60.2 ± 4.7 mL/min/1.73m2(平均 ± SE)から3ヶ月後65.3 ± 4.9 mL/min/1.73m2と有意な上昇を認めた(p = 0.011)。一方、収縮期血圧は123.6 ± 16.2 mmHgから125.6 ± 16.6 mmHgと変化は見られなかった(p = 0.919)。eGFRの変化量は、デュラグルチド開始前の3ヶ月間では2.1 ± 5.6 mL/min/1.73m2低下したが、開始後の3ヶ月間では5.1 ± 7.9 mL/min/1.73m2上昇した(p = 0.011)。本研究からデュラグルチドにおける2型糖尿病患者の腎障害の進行抑制もしくは腎機能改善効果が示唆される。
1 0 0 0 OA 後頭葉病変による読み書き障害
- 著者
- 近藤 正樹
- 出版者
- 日本神経心理学会
- 雑誌
- 神経心理学 (ISSN:09111085)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.311-321, 2016-12-25 (Released:2017-01-18)
- 参考文献数
- 46
後頭葉病変では純粋失読が主体であり,後頭葉病変による失書の発症は後頭葉と頭頂葉,側頭葉の境界域を含めた病巣の広がりと関係していると考えた.頭頂葉であれば角回への広がり,側頭葉であれば中・下側頭回への広がりにより失読失書が出現し,後頭葉から離れて頭頂葉ないし側頭葉寄りになると純粋失書になることが想定された.境界に関係する部位として,側頭葉では中・下側頭回,頭頂葉では角回への病変の広がりに注目する必要がある.また,純粋失読にまつわる話題として,視覚性語形領域(visual word form area:VWFA)に関する最近の知見,数字読み,逐次読みの病態機序に関する報告を紹介した.
- 著者
- 小田切 陽一 内田 博之 市川 敏美 近藤 直司
- 出版者
- 山梨県立大学
- 雑誌
- 山梨県立大学看護学部紀要 (ISSN:18806783)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-8, 2010
山梨県の自殺率と既存統計を用いた生態学的分析から自殺との関連が示唆される人口学的、社会学的要因の抽出をおこなった。その結果、人口世帯要因では、老年人口割合、単身高齢者割合、死別高齢者割合が正の相関、平均世帯人員が負の相関を示した。産業・経済要因では、管理的職業従事者割合、生活保護率と正の相関、課税対象所得と負の相関を認めた。医療・福祉要因では、腎不全死亡率、老人クラブ加入率と正の相関、精神作用物質による精神・行動の障害による受療率と負の相関を認めた。また神経症障害、ストレス関連障害および身体表現性障害の受療率と正の相関傾向、気分障害 (躁うつ病を含む)、その他の精神および行動の障害による受療率、精神保健福祉相談 (心の健康づくり相談) 件数と負の相関傾向を認めた。本研究の結果、山梨県の自殺率に関連する要因として、人口の高齢化や脆弱な経済基盤、精神障害に関わる相談や受療行動が低いことなどが示唆された。
- 著者
- 近藤 悠希
- 出版者
- 日本薬局学会
- 雑誌
- 薬局薬学 = The journal of community pharmacy and pharmaceutical sciences (ISSN:18843077)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.41-45, 2018
1 0 0 0 IR 綿チップ押しつぶし課題の舌圧測定への応用と嚥下課題教示手段としての効果
- 著者
- 加藤 直志 小島 千枝子 小野 高裕 近藤 重悟
- 雑誌
- リハビリテーション科学ジャーナル = Journal of Rehabilitation Sciences
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.27-38, 2014-03-31
本研究では,"綿チップ押しつぶし" 課題の有用性について検討した.第1実験では,嚥下障害者を含む102 名を対象に"綿チップ押しつぶし" 課題後の綿球のつぶれ具合とJMS 舌圧測定器の最大舌圧の相関分析,回帰分析を行い,綿球のつぶれ具合で舌圧を推測できるかを調べた.第2実験では,健常若年者20 名を対象に,綿チップ押しつぶしを教示に用いた嚥下(MS),Effortful swallow(ES),普通嚥下の舌圧発現様相を比較し,嚥下課題の教示に用いることの有効性を調べた.その結果,第1実験では,舌圧=12.117 + 67.961 ×綿球水分変化量の回帰式が得られ(R2 =0.568),第2実験では,MS はES とほぼ同等に舌圧持続時間と舌圧最大値が高値を示し,さらに,MS では綿チップの押しつぶし課題でターゲットとした部位の舌前方部(Ch1)の舌圧発現が他測定点より有意に早く,Ch1の舌圧持続時間はES より有意に延長した.以上のことから,"綿チップ押しつぶし" 課題は,嚥下訓練において多彩な訓練ツールとして用いることができることが示された.
糖尿病合併症は微小血管障害に起因する臓器の機能不全による. また, 微小血管において慢性炎症を引き起こし,毛細血管を退行させる. 一方, 運動による血流増加は毛細血管の退行を抑制させることができる. また, 経皮的な二酸化炭素の吸収はボーア効果による血流促進効果をもつことが報告されている. そこで本研究では二酸化炭素経皮吸収による筋毛細血管退行の予防効果を検証した.さらに超音波照射による炎症抑制や代謝促進効果についても検証する計画である.平成29年度は二酸化炭素経皮吸収による糖尿病性毛細血管退行の予防効果について検証した.慢性的な高血糖曝露は骨格筋のクエン酸シンターゼ(CS)活性の低下や毛細血管の退行を引き起こした.一方,経皮的二酸化炭素吸収は高血糖曝露によるCS活性低下や毛細血管退行を抑制し,血糖の上昇を抑制した.さらに骨格筋の代謝や血管新生に関するeNOS, PGC-1α, COX Ⅳ, VEGFタンパク質発現量を増加させ,血管新生抑制因子(TSP-1)の低下が認められた.これらの結果から経皮的二酸化炭素吸収は骨格筋の代謝や血管新生に関わる因子を増加させ,血管新生抑制因子を低下させることで高血糖曝露による骨格筋の酸化的リン酸化機能低下や毛細血管退行を抑制することが明らかとなった.また,超音波照射による効果を検証するためにC2C12筋芽細胞を使用して予備検討を実施した.C2C12筋芽細胞の超音波照射ではインテグリン/focal adhesion kinase (FAK)のリン酸化の増加が観察され,P38MAPKリン酸化が減少させ, 炎症モデルにおいてTNFaの発現を超音波照射で軽減させる効果を観察した.
1 0 0 0 OA 駐車支援システムインテリジェントパーキングアシストの紹介
- 著者
- 植中 裕史 立花 裕之 近藤 敬
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.11, pp.836-840, 2015-11-10 (Released:2015-11-20)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 電子顕微鏡像からのイオン伝導度の学習 ~畳み込みニューラルネットワークによる特徴可視化~
本研究では,畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて材料の物性予測に必要な特徴を微視組織から自動的に抽出することを試みた.まず,実験で得られた電子顕微鏡像およびイオン伝導度を訓練データとして用いてCNNを訓練した.次に,訓練後のCNNに電子顕微鏡像を入力した際のGlobal Average Pooling(GAP)レイヤー直後の発火と,与えた電子顕微鏡像の教師データ(イオン伝導度)との相関を調べ,正(負)の相関のあるものを高(低)イオン伝導体に特有の特徴と定義した.それぞれの特徴のGAP適用前の特徴マップを比較したところ,結晶欠陥の少ない領域および径の大きなボイドが高イオン伝導体に特有の特徴であり,径の小さなボイドが低イオン伝導体に特有の特徴であることが分かった.この知見は材料技術者の持つ知識と一致しており,CNNによる特徴の自動抽出が有効であることを示すことができた.
1 0 0 0 OA 登熟期の高温および遮光処理で発生した水稲玄米のリング型乳白粒の層別デンプン特性
- 著者
- 梅本 貴之 岩澤 紀生 近藤 始彦
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会講演会要旨集 第231回日本作物学会講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.446, 2011 (Released:2011-04-05)
1 0 0 0 近藤典生教授 : 東京農業大学教授退職記念文集
- 著者
- 近藤典生先生退職記念会記念文集編集委員会編
- 出版者
- 近藤典生先生退職記念会記念文集編集委員会
- 巻号頁・発行日
- 1986
1 0 0 0 日本語の話しことばに見られる 「代償延長」 について
- 著者
- 近藤 安月子
- 出版者
- 東京外国語大学
- 雑誌
- 東京外国語大学論集 (ISSN:04934342)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.[1]-14, 1992
1 0 0 0 OA 地方都市の中心市街地活性化が地域活性化に果たす役割に関する研究
- 著者
- 城所 哲夫 近藤 早映
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.791-797, 2016-10-25 (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 13
本研究では、日本の地方都市の地域活性化の進め方と中心市街地の役割に関する考え方として、ライフスタイル産業仮説とクリエイティブ・タウン仮説から構成されるイノベーティブ・タウン仮説を提示した。イノベーティブ・タウン仮説の肝は、ライフスタイルを生かした地域の活性化と、そのベースとなるアイデアを喚起し、人と人をつなぐ場としての中心市街地の役割である。中心市街地活性化の好事例としてとり挙げられることの多い地方都市についてイノベーティブ・タウン仮説の適合性を検討したところ、中心市街地活性化事業の展開の仕方(行政主導型、協働型、民間主体型)の違いにより、そのアプローチの違いはみられるものの、全体として、イノベーティブ・タウン仮説に適合したかたちで中心市街地活性化事業が展開していることが確認できた。とくに「民間主体型」において、より直接的にライフスタイル産業の生成に結びつく活動が展開していることが指摘できる。一方、「行政主導型」「協働型」においては、ライフスタイルの彫琢、市民のネットワークの形成、魅力的なパブリックスペースの創出等の中長期的な目標が重視される傾向がある。
1 0 0 0 腱板損傷に対する上腕骨頭の中心化トレーニングの効果
- 著者
- 近藤 正太 井手 裕一朗 井関 康武
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.C3O3068, 2010
【目的】肩の有痛性運動機能障害、特に腱板損傷症例においては関節窩に対し上腕骨頭が腹頭側偏位することは臨床場面で多く経験すると共に文献的にも示されている. このアライメント異常がアウトレットインピンジメントを発生させ運動時痛を伴う機能障害の誘発要因であると考える. 従来、腱板損傷に対するトレーニングはセラバンド等を用いて負荷をかけた回旋運動、アウターマッスルの過活動を誘発するような運動等、上腕骨頭の中心化を考慮しないトレーニングが一般的と思われる. そこで今回、この骨頭の腹頭側偏位を修正し関節窩に対し骨頭の中心化を促すトレーニングが、肩外転時における外転筋の筋発揮能力に改善が見られるか検討したので報告する.【方法】腱板損傷と診断され、視診、触診にて骨頭の腹頭側変位を認めた15例18肩. 男性7例、女性8例、平均年齢62.8歳(31~79歳)を対象とし、上腕骨頭の中心化を促すための治療(中心化トレーニング)を施行し、その前後における外転筋力を測定した. さらに15例18肩の中から、一般的に行われている腱板損傷に対するトレーニング(腱板トレーニング)が施行可能であった13例16肩に対し、腱板トレーニング前後での外転筋力を同様に測定した. トレーニングとして、1.骨頭の中心化トレーニング:まず関節窩に対して骨頭の中心化を促すため、背臥位において骨頭の背側へのモビリゼーションを、Grade2(軟部組織の伸張による制限を感じるところまで)までを用い、中心化が得られるまで断続的に2分~3分間施行した. その後椅子座位で、肩約30°~45°外転位にし上腕骨を肩甲骨面上に保持し、肘をベッドに置き軽度外旋位から骨頭を背側誘導しながら肩甲下筋による内旋運動を、各症例の疲労を考慮し30回~50回行わせた. 2.腱板トレーニング:肩を下垂位、肘90°屈曲位にした椅子座位で肩の内旋、外旋運動をセラバンドにより、筋疲労を起こさない程度の抵抗量でそれぞれ30回、手を顎に当てた状態で90°までの肩屈曲運動をセラバンドで抵抗を加え同様に30回施行した. 外転筋力測定:端坐位にて肩甲骨面上で肩90°外転、手掌を床に向けた肢位を保持させ、最大での等尺性肩外転筋力をhand-held dynamometer(マイクロFETII)を用い前腕遠位に抵抗を加え、中心化トレーニングと腱板トレーニングの施行前後でそれぞれ2回測定し、最大筋力を測定値(単位;ニュートン)として比較した. なお中心化トレーニングと腱板トレーニングは日を変えて行った. 統計学的検討は対応あるt検定を用い、危険率1%未満を有意差ありとした. 【説明と同意】被検者に研究の内容を説明し同意を得た.【結果】腱板損傷15例18肩の平均最大外転筋力は28.41N±8.51であったが、上腕骨頭の中心化トレーニング後では34.57N±10.09と筋力の増加を示し、有意な差を認めた(p<0.005). また平均増加率は24.1%でありトレーニング後、筋力低下を示したのは18肩中1肩だけであった. その中から中心化トレーニングと腱板トレーニング共に施行可能であった13例16肩の中心化トレーニング前後の筋力は、それぞれ29.28N±8.49、35.01N±10.66となり有意な差を認め(p<0.001)、平均増加率は20.8%であったが、腱板トレーニング前後では、トレーニング前30.58N±14.5、トレーニング後は31.93N±15.4であり統計学的有意差を認めず(p<0.12)、平均増加率も5.07%にとどまり、しかも、逆にトレーニング後筋力低下を示したものは16肩中4肩に認められた.【考察】今回、上腕骨頭の中心化トレーニングにより、最大外転筋力が平均28.41Nから34.57Nに向上し、平均24.1%の増加率を示した. また腱板トレーニングも施行可能であった13症例16肩に限定しても中心化トレーニング後は筋発揮能力の改善を見た. つまり、効率的外転運動を行うためには上腕骨頭の回旋軸は外転運動の全般にわたり、関節窩の中心に位置するよう比較的一定していなければならないことを示すものであり、健常人の肩運動時におけるバイオメカニクスの研究と一致する. これを裏付けるものとして、今回骨頭の中心化を考慮しない肩の回旋筋強化を主とした腱板トレーニング前後において、最大外転筋力にあまり変化なく効果は認めなかった. しかも4肩で逆に筋力低下を示した事は、この腱板トレーニングが大胸筋や三角筋後部繊維、小円筋、棘下筋の筋スパズムを複合的に強化し骨頭の腹頭側偏位を助長したためと考えられ、このことからも腱板損傷症例に対する骨頭の中心化は重要であり、トレーニングの有用性を示すものと考える.【理学療法学研究としての意義】腱板損傷に対する理学療法を骨頭の位置異常と言う視点からも捉える事で、より高いレベルでの治療効果の可能性が期待出来る.