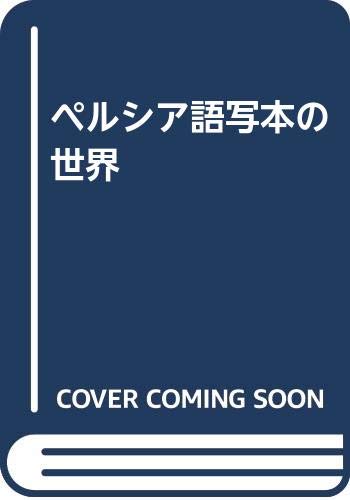- 著者
- 加藤 太郎 板東 杏太 有明 陽佑 勝田 若奈 近藤 夕騎 小笠原 悠 西田 大輔 髙橋 祐二 水野 勝広
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.326-332, 2021-03-18 (Released:2021-07-03)
- 参考文献数
- 18
目的:脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration:SCD)に対する短期集中リハビリテーション治療(SCD短期集中リハビリテーション)の効果が,先行研究により示されている.しかし,SCD短期集中リハビリテーションの効果検証は,Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(SARA)の総得点により報告されており,SARAの下位項目による詳細な検証はなされていない.本研究は,歩行可能なSCD患者の運動失調に対するSCD短期集中リハビリテーションの効果を,SARAの総得点と下位項目得点から検証することを目的とした.方法:対象は,SARAの歩行項目3点以下に該当し,4週間のSCD集中リハビリテーション治療プログラム(SCD集中リハビリテーション)に参加したSCD患者23名(男15名,女8名)とした.評価項目はSARAとし,SCD集中リハビリテーション実施前後に評価を実施した.対象者のSCD集中リハビリテーション実施前後のSARAの総得点および各下位項目得点を,後方視的に解析した.統計はWilcoxonの符号付き順位検定を用いて分析検討し,有意水準は5%とした.結果:SCD集中リハビリテーション実施前後において,総得点および下位項目得点のうち,歩行,立位,踵-すね試験に有意な点数の改善を認めた(p<0.05).一方,下位項目得点で座位,言語障害,指追い試験,鼻-指試験,手の回内・回外運動は有意な点数の改善を認めなかった.結論:本研究の結果は,SCD集中リハビリテーションはSCD患者のSARAにおける総得点と,特に体幹と下肢の運動失調を有意に改善させることを示した.
1 0 0 0 OA 地域在住高齢者の要介護認定のリスク要因の検討 AGES プロジェクト 3 年間の追跡研究
- 著者
- 平井 寛 近藤 克則 尾島 俊之 村田 千代栄
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.501-512, 2009 (Released:2014-06-13)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 15
目的 本研究では,地域在住高齢者9,702人を 3 年間追跡し,要介護認定のリスク要因の検討を行った。方法 2003年10月,東海地方の介護保険者 5 市町の協力を得て,各市町に居住する65歳以上で要介護認定を受けていない高齢者24,374人を対象とした自記式アンケート郵送回収調査を行った。調査回答者は12,031人(回収率49.4%)であった。このうち,性別,年齢を回答していない者(n=1387),歩行,入浴,排泄が自立していないまたは無回答の者(n=905),2003年10月31日までに要介護状態になった者,死亡した者(n=37)を除いた9,702人を分析対象とし2006年10月まで 3 年間追跡した。 目的変数(エンドポイント)は要介護認定とした。説明変数として年齢,家族構成,等価所得,教育年数,治療中の疾病の有無,内服薬数,転倒,咀嚼力,BMI,聴力障害,視力障害,排泄障害,老研式活動能力指標,うつ,主観的健康感,飲酒,喫煙,一日当たりの平均歩行時間,外出頻度,友人との交流,社会的サポート,会参加,就労,家事への従事を用いた。 Cox 比例ハザード回帰分析を用いて,要介護認定についてのハザード比を求めた。分析は男女別に行った。分析にはすべて SPSS 12.0J for Windows の Cox 比例ハザード回帰を用いた。結果 3 年の追跡期間中の死亡は520人,要介護認定838人,重度要介護認定380人であった。転出等による追跡打ち切りが103人であった。男女共通して要支援以上の要介護認定の高いリスクと関連していることが示されたのは,年齢高い,治療中の疾病あり,服薬数多い,一年間の転倒歴あり,咀嚼力低い,排泄障害あり,生活機能低い,主観的健康感よくない,うつ状態,歩行時間30分未満,外出頻度少ない,友人と会う頻度月 1 回未満,自主的会参加なし,仕事していない,家事していないこと,であった。結論 要介護に認定に関連するリスク要因を明らかにした。これらに着目した介護予防プログラムの開発が必要である。
1 0 0 0 OA 肩関節屈曲初期時の代償動作への運動療法と肩甲骨アラインメントの重要性
- 著者
- 加古原 彩 三浦 雄一郎 福島 秀晃 布谷 美樹 田中 伸幸 近藤 克征
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.137-143, 2006 (Released:2007-01-30)
- 参考文献数
- 7
In this article, we describe physical therapy for a case of decline in muscular strength caused by axillary nervous paralysis with a dislocation of the shoulder joint. This case was characterized by difficulty in flexional movement in the scapulothoracic joint in primary flexion of the shoulder joint because of the adduction and lift of the scapula. We defined the alignment on the several phases that the specific movement of scapula appears. We practiced scapula alignment and performed electromyographic assessment. In this case, in addition to a decline of muscular activity in the deltoid muscle, the upper, middle and lower fibers of the trapezius muscle started to move before the anterior fibers of the deltoid muscle. So, we supposed that this phenomenon caused the disorder, the specific movement of the scapula. We observed the start of activity of the deltoid and trapezius muscles and administered a pendular movement as a therapeutic exercise. Improvement in both excursion of flexion and in patterns of muscular activity in the deltoid and trapezius muscles were confirmed. Furthermore, with repetition of kinesiatrics in the sitting position on the edge of a bed following results was acquired; an increase in muscular activation in the anterior fibers of the deltoid muscle and a muscle activation with same order. This lead to improvement of stability of the scapula because of a decrease in adduction and lift of the scapula in the start position. From the above, we suggest that choice of the method of kinesic therapy, paying attention to the posture of patients and paying attention to the stability of scapulothoracic joint is important.
1 0 0 0 ウェル・プリペアド・ピアノ
- 著者
- リチャード・バンガー著 近藤譲 ホアキン M. ベニテズ共訳
- 出版者
- 全音楽譜出版社
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 OA 花部形態の多変量解析に基づく日本産カンアオイ属ウスバサイシン節の形態比較
- 著者
- 山路弘樹 中村輝子 横山潤 近藤健児 諸田隆 竹田秀一 佐々木博 牧雅之
- 出版者
- 植物研究雑誌編集委員会
- 雑誌
- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.57-78, 2007-04-20 (Released:2022-10-20)
日本産カンアオイ属ウスバサイシン節植物の形態変異を明らかにするために,国内の全分布域・既知の分類群,地域集団を含む55集団について野外調査を行った.同節に関する過去の研究はいずれも量的形質の評価が不十分であるため,本研究では今まで用いられてきた形質,新たに採用した形質の評価に加え,花の量的形質に基づく多変量解析を行った.その結果,形態より区別できる8型が認識された.日本の同節はまず萼筒内壁のカラーパターンで2型に分けられ, D 型は全面暗紫色なのに対し, L 型は基底部は暗紫色,中央部は黄緑色ないし淡紫色,萼筒開口部は暗紫色ないし白色だった. D 型はさらに萼筒内壁,萼裂片内面の毛の細胞数,雄蕊・雌蕊の数で D1-D4 の4型に分けられ, L 型は萼筒の形態,萼筒開口部の大きさ,萼裂片の形態,サイズで L1-L4 の4型に分けられた.この8型はほぼ異所的に分布し,それぞれ独立の分類群に値するまとまった地域集団と推定された.
- 著者
- 常深 志子 近藤 健 藤原 香子 中野 美佐
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.250-256, 2023-04-15 (Released:2023-04-15)
- 参考文献数
- 20
急性期病院での認知症ケアチームにおける作業療法実践を検討した.認知機能低下を伴う運動器疾患術後の高齢者16名を調査した結果,認知機能改善はMini Mental State Examination-Japaneseではなく,Functional Independence Measure(以下,FIM)cognitiveに認められた.また,FIM motorに改善を認め,行動・心理症状,せん妄,向精神薬内服,テープ付き紙おむつの使用数,身体拘束使用数は減少した.作業療法士の認知症ケアチームへの関わりは,急性期医療における高齢者ケアに役立つことが示唆された.
1 0 0 0 OA 濃赤色イチゴ新品種 ‘真紅の美鈴’ の果実品質およびアントシアニン色素
- 著者
- 水野 真二 成川 昇 近藤 春美 上吉原 裕亮 立石 亮 窪田 聡 新町 文絵 渡辺 慶一
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.109-115, 2021 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 12
アントシアニン色素を多く含み,果実が濃赤色を呈する促成栽培用イチゴ品種 ‘真紅の美鈴’ を育成した.神奈川県における試験栽培において,本品種は ‘とちおとめ’ より花芽分化がやや遅く,定植適期は9月20日頃以降であると考えられた.果実の硬度は ‘とちおとめ’ 並みに高く,糖酸比は20を超え,還元糖のグルコースとフルクトースを比較的多く含んでいた.果実のアントシアニン色素の含量は新鮮重1 g当たり185 μgであり,母親の ‘ふさの香’ および父親の ‘麗紅’ の約2倍,‘とちおとめ’ の約3倍であった.一方,果汁の抗酸化活性には‘真紅の美鈴’と従来品種で大きな差はみられず,アントシアニンの抗酸化活性への寄与度は低いと推定された.アントシアニンの組成はペラルゴニジン配糖体が80%以上を占めており,検出された5成分の構成比は ‘とちおとめ’ や親品種と概ね同等であった.このことから,‘真紅の美鈴’ が濃赤色を呈するのはアントシアニン組成の影響ではなく,色素の含量が顕著に多いためと考えられた.
- 著者
- 近藤 圭太 山北 喜久 玉井 宏明 岡崎 誉
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.735-740, 2020-12-28 (Released:2020-12-28)
- 参考文献数
- 20
背景・目的:超高齢者が緊急入院すると,廃用症候群に陥りやすく,入院期間も長びき予後も悪くなることが問題となる。これに対し早期リハビリテーションの効果が期待されるなか,当院の現状を調査し検討した。方法:2017年度の1年間で,救急車搬送され入院となり理学療法を施行した超高齢者243人を対象とし,入院後48時間以内にリハビリテーション開始の早期リハ群と,以降の非早期リハ群に分け,早期リハの効果を,退院時転帰,在院日数などにつき検討した。結果:退院時転帰は,退院,転院,死亡で2群間に有意差はなく,平均在院日数が早期リハ群で縮減した(16.9±11.3日vs 21.8±12.6日,p=0.0195)。疾患別にみると,脳血管系と整形外科系で早期リハ群が多かった。結論:緊急入院した超高齢者に早期リハを行うことは,退院時転帰に有意差はなかったが,在院日数を有意に縮減した。在院日数縮減は廃用症候群の予防や病床回転率に寄与し,超高齢社会に向けての1つの対策となり得る。
- 著者
- 近藤 康雄 山口 顕司 坂本 智
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌論文集 (ISSN:13488724)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.1259-1263, 2006-10-05 (Released:2012-01-13)
- 参考文献数
- 9
A bio-chemical treatment system was developed to reutilize the spent water-soluble coolant as a diluent of renewal coolant. The bio-chemical treatment using oil-decomposing microorganisms and a biological activated carbon filtration method showed a high recovery rate of water resource from an emulsion-type coolant. The water-soluble coolant can form the uniform micelle colloid in the recovered water and showed no quality change during the nine months standing at ambient temperature. The processing cost, around 35 yen/L, was equal to or less than current disposal cost. No difference was shown in the chisel and flank wear of machine tool after 100 holes drilling between the water-soluble coolants diluted with recovered water and service water. These facts indicated that the proposed treatment system must be an effective way to reutilize the water-soluble coolant as the diluent of renewal coolant.
1 0 0 0 OA 東北地方太平洋沖地震による浦安市埋立地盤の液状化被害調査
- 著者
- 京川 裕之 清田 隆 近藤 康人 小長井 一男
- 出版者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 雑誌
- 地盤工学ジャーナル (ISSN:18806341)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.265-273, 2012 (Released:2012-03-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 8 3
東北地方太平洋沖地震によって埋立地の大部分が液状化した千葉県浦安市において,著者らは地震発生直後から航空レーザ測量,粒度分析,SWS試験などを行い,液状化による地盤の変動を継続的にかつ定量的に把握してきた。これらの調査より,(1) 浦安市の埋立地では地盤沈下が広範囲に生じており,その沈下量の分布は家屋・ライフラインの被害と対応している。(2) 同時期の埋立地(未改良地区)で,被害程度が大きく異なる場所がある。(3) 広範囲に採取した噴砂の粒度およびSPT試料の粒度は,大量の噴砂と再液状化が確認されているニュージーランド・クライストチャーチのケースと非常に似通っている。(4) 液状化により地盤の貫入抵抗は大きく低下し,その後2ヶ月程度で強度は回復・安定するが依然として低い値を示している。本稿では以上の知見より,同地区の再液状化の可能性についても検討する。
1 0 0 0 OA アメリカの中学生の日常あいさつ言葉について
- 著者
- 近藤 富英
- 出版者
- 信州豊南短期大学
- 雑誌
- 信州豊南短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Junior College (ISSN:1346034X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.1-14, 2009-03-01
1 0 0 0 OA 都道府県がん診療連携拠点病院1施設のがん看護外来における相談内容に関連する要因
- 著者
- 塚越 徳子 角田 明美 渡辺 恵 京田 亜由美 瀬沼 麻衣子 近藤 由香 北田 陽子 廣河原 陽子 一場 慶 金子 結花 関根 宏美 宮澤 純江 橋本 智美
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.95-103, 2023 (Released:2023-04-06)
- 参考文献数
- 34
【目的】群馬大学医学部附属病院のがん看護外来における相談内容に関連する要因を明らかにする.【方法】2019年度の相談1308件から欠損値を除く1084件を対象に後ろ向きに調査した.調査項目は年代,性別,相談者,利用回数,がんの治療状況,相談内容などとした.相談内容と利用者の属性とのχ2検定,二項ロジスティック回帰分析を実施した.【結果】治療に関する内容は,70歳代以上,家族・親族のみ,再発・転移あり,初めての利用,治療前,泌尿器,子宮・卵巣,原発不明と関連した.身体的な内容は,治療中,治療後,再発・転移なし,消化器と関連した.心理的な内容は,30歳代以下,40~60歳代,患者のみ,2回目以上の利用と関連した.社会的な内容は,患者のみ,家族・親族のみ,再発・転移なし,乳房と関連した.【結論】相談内容によって関連要因は異なり,関連要因に応じて相談の準備を整えることに活用することができる.
1 0 0 0 OA プロジェクトエコノミー時代におけるビジネスモデルの変革
- 著者
- 三木 章義 近藤 アンリ
- 出版者
- 一般社団法人 PMI日本支部
- 雑誌
- プロジェクトマネジメント研究報告 (ISSN:24362115)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.68-73, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 22
生き残りをかけたビジネス環境は激しさを増している.企業は競争優位を得るために,自社のリソースや能力を再構築し,ビジネスモデルを変革することに苦心している.日本では,多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に挑戦しているが,成功しているとは言い難い.本研究では,まずダイナミック・ケイパビリティのレビューから始め,企業がビジネスモデルの変革を成功させるための方法について仮説を構築しその一部を検証した.
1 0 0 0 OA 抗リン脂質抗体症候群を合併した肺癌2切除例の検討
- 著者
- 近藤 泰人 玉川 達 園田 大 松井 啓夫 塩見 和 佐藤 之俊
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会
- 雑誌
- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.12-20, 2019-01-15 (Released:2019-01-15)
- 参考文献数
- 26
抗リン脂質抗体症候群(APS)は,動静脈血栓症を伴う自己免疫疾患である.APS合併肺癌は稀で,その意義は明らかでない.【症例1】75歳女性.検診で血小板低値を認め,精査でAPSと診断された.胸部CTで右下葉に103 mm大の腫瘤影と#7リンパ節腫大を認めた.精査で扁平上皮癌(SCC)と診断され,右下葉切除術を行った.入院時に血小板低値を認めた.術前,術中に血小板輸血を行い,合併症なく退院した.【症例2】66歳男性.副甲状腺腺腫精査のMIBGシンチグラフィーで左S6に31 mm大の腫瘤影を認めた.精査でSCCと診断され,左下葉切除術を行った.入院時に血小板低値と凝固時間延長を認めた.既往歴にAPSと心房細動があり,バイアスピリンとワルファリンを内服していた.術前に同薬剤を休薬し,未分画ヘパリンを投与し,合併症なく退院した.APS合併肺癌の外科的治療には慎重な周術期管理を要すると考える.
1 0 0 0 OA 宝塚市水道水フッ素濃度の経年的推移と斑状歯・むし歯のない者の割合の関係
- 著者
- 近藤 武 笠原 香 中根 卓 樋口 壽英 藤垣 佳久
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.144-150, 2004-04-30 (Released:2017-12-22)
- 参考文献数
- 5
わが国の水道水のフッ素基準値は,0.8 mg/l 以下である.しかし,宝塚市は中等度の斑状歯の発生抑制を目的として,国の基準より低い0.4〜0.5 mg/l 以下で給水している.この基準の妥当性は,この濃度の飲料水を出生時から摂取した児童・生徒の,中等度の斑状歯所有率の減少によって証明される.今回,宝塚市水道局から公表されている,水道水中フッ素濃度の経過と,宝塚市教育委員会から公表されている児童生徒の歯科健診結果から調査した.管末のフッ素濃度は昭和55年度(1980)以降平成12年度(2000)まで,年平均濃度は暫定管理基準を超える濃度はみられなかった.昭和56年度(1981)から63年度(1988)の間に出生した児童・生徒について,斑状歯所有率の経過をみると,平成8年度(1996)では5.3%であったが,平成12年度(2000)には2.3%と減少した.むし歯のない者の割合についてみると,経年的に増加がみられたが,全国的にも同様の傾向がみられたことから,その関係ははっきりしなかった.
1 0 0 0 OA 日本の哺乳類相—種の生態,古環境および津軽海峡の影響について
- 著者
- 近藤 憲久
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1and2, pp.1and2_131-143, 1982 (Released:2008-10-01)
1 0 0 0 OA 心拍変数を用いたタクティールタッチ®の有効性の検証 : 成人女性を対象にして
- 著者
- 山本 裕子 梅田 智広 溝口 幸枝 長尾 匡子 近藤 純子 東瀬戸 久子 Yuko Yamamoto Tomohiro Umeda Yukie Mizoguchi Kyoko Nagao Junko Kondo Hisako Higashiseto 千里金蘭大学 看護学部 奈良医科大学 千里金蘭大学 看護学部 千里金蘭大学 看護学部 千里金蘭大学 看護学部 藤井寺市地域包括支援センター
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.141-147,
本研究の目的は、健康な成人女性6名(平均年齢50.2歳±8.7歳)を対象にストレス値からみたタクティールタッチ(スウェーデン発祥の触れるケアの一種である)の有効性を明らかにすることである。対象者の施術前条件の統一を図る目的で数計算100問の解答を課した。タクティールタッチ施術グループ3名とタクティールタッチ施術を受けない安静臥位グループ3名に分け、各対象者の左胸部にヘルスパッチを貼付し、数計算時およびタクティールタッチ施術時(または安静臥位時)その後の安静10分後、20分後、30分後、飲水時のストレス値、心拍数、体温を測定しFFT(高速フーリエ変換)で算出しHRV解析した。HRV解析図およびストレス値と心拍数・体温のHRV解析結果の平均値比較から、タクティールタッチ施術を受けたグループの方がストレス値は大きく低下し心拍数も低下したのみならず持続も認められた。
1 0 0 0 OA 小集会報告「タフォノミーを考える会」
- 著者
- 安藤 寿男 近藤 康生
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.35-38, 1988-12-15 (Released:2017-10-03)
1 0 0 0 ペルシア語写本の世界 = جهان نسخههای خطی فارسی : نمونههائی از دستنوشتههای ایرانی, ماوراء النهری و هندی
- 著者
- 羽田亨一 近藤信彰共編
- 出版者
- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 OA カラマツの化学的研究(第I報)
- 著者
- 近藤 民雄 古沢 亘江
- 出版者
- THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY
- 雑誌
- 日本林学会誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.12, pp.406-409, 1953-12-25 (Released:2011-09-02)
- 参考文献数
- 16
1) From the results of paper partition chromatography it was concluded that katuranin is present in the heartwood of Larix Kaempferi SARG. in very small content, companying with distylin.2) Two semiquantitative methods, applying the procedures of paper partition chromatography were elaborated to detect the most probable content of distylin in the heartwood of Karamatzu.