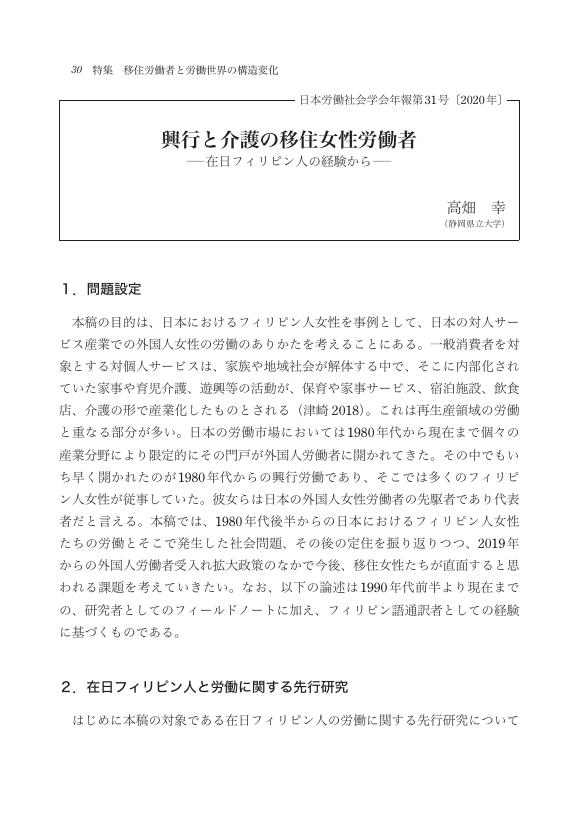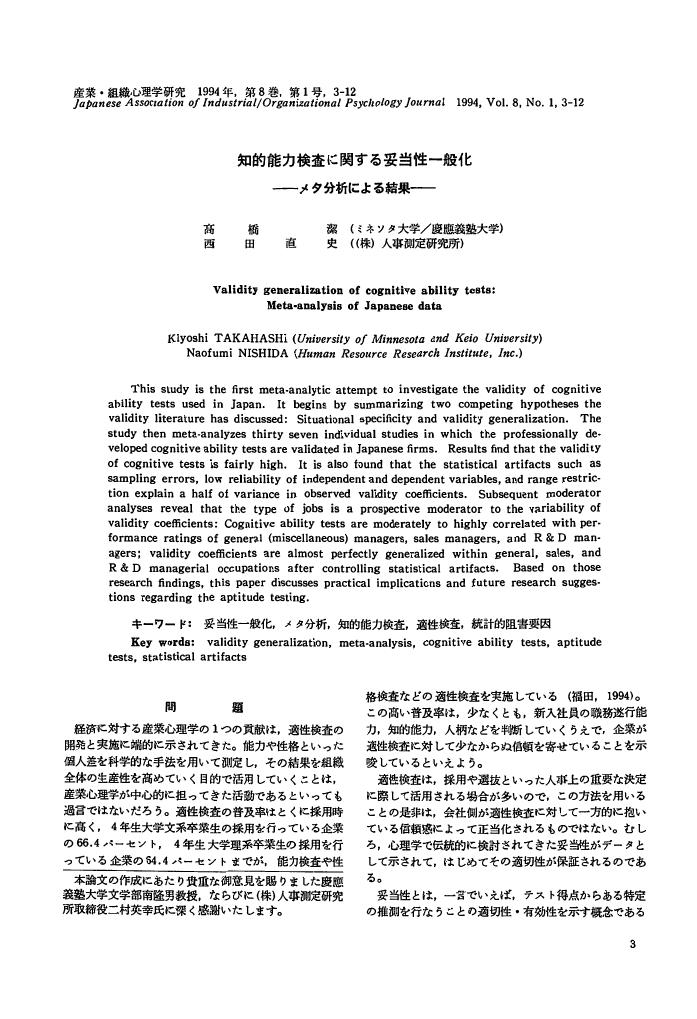- 著者
- Kinuko Kimura Yoshio Nakano Kouji Matsuoka
- 出版者
- The Japanese Biochemical Society
- 雑誌
- The Journal of Biochemistry (ISSN:0021924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.1, pp.84-87, 1989-01-01 (Released:2008-11-18)
- 参考文献数
- 12
The nucleotide ligation site of adenylylated glutamine synthetase, which contains a unique tyrosyl residue linked through a phosphodiester bond to 5'-AMP, was studied by digestion with three hydrolytic enzymes. The products on micrococcal nuclease digestion were adenosine and o-phosphotyrosyl glutamine synthetase. The Km for this macromolecular substrate with the nuclease was 40 μM, at pH 8.9. The glutamine synthetase activity was not affected by deadenosylation with the nuclease, in contrast to SVPDE digestion, with which the glutamine synthetase activity was markedly increased. The Km for the native adenylylated glutamine synthetase with the SVPDE was 36 μM, i. e., similar to that for the nuclease. When the isolated o-phosphotyrosyl enzyme was incubated with alkaline phosphatase at pH 7.2, the glutamine synthetase activity rapidly increased to the same level as that of the SVPDE treated enzyme. Furthermore, kinetic properties of the o-phosphotyrosyl glutamine synthetase were compared with those of the adenylylated enzyme. The optimum pH, apparent Km for each of three substrates, glutamate, ATP, and NH3, and Vmax were in good agreement, as to either Mg2+- or Mn2+-dependent biosynthetic activity. From these results we can conclude that the regulation of glutamine synthetase activitysimply requires the piosphorylation of the tyrosyl residue in each subunit, without recourse to adenylylation.
1 0 0 0 OA 二次性尿崩症をきたしたPTHrP産生肺癌の1例
- 著者
- 田村 和貴 中村 昭博 松尾 聡 伊藤 重彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.209-213, 2002-06-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
背景. 肺癌患者ではしばしば高カルシウム (Ca) 血症を合併し, その原因として副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP) の関与が指摘されている. 今回我々はPTHrP産生により高Ca血症を生じ二次性尿崩症をきたした肺癌の1例を経験した. 症例. 症例は68歳, 男性. 平成11年5月, 咳嗽と胸部異常陰影の精査のため入院し左下葉進行肺癌と診断された. 化学放射線療法施行後の平成12年11月, 全身状態悪化のため再入院となった. 胸部CT上, 腫瘍の再増大と左無気肺を認めたが, 骨や脳転移の所見はなかった. 入院中, 多飲・多尿出現し高Ca血症と血清PTHrP-C端の上昇を認めたことから, humoral hypercalcemia of malignancyによる二次性尿崩症と考えられた. パミドロン酸ニナトリウム30mgにて高Ca血症と多尿は速やかに改善したが, 多発肺転移から呼吸不全を生じ死亡した. 腫瘍組織の免疫組織学的検討では腫瘍細胞の細胞質にPTHrP抗原の発現を認めた. 結論.二次性尿崩症を生じたPTHrP産生肺癌の1例を経験した. 心肺機能低下例での高Ca血症治療においてパミドロン酸ニナトリウムは単剤でも有効であった.
1 0 0 0 OA 西太平洋及びインド洋における熱帯低気圧とMadden-Julian振動との関連
- 著者
- Brant Liebmann Harry H. Hendon John D. Glick
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.401-412, 1994-06-25 (Released:2009-09-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 372 402
当論文においては、西太平洋及びインド洋における熱帯低気圧とMadden-Julian振動(MJO)との関連を記述する。熱帯低気圧は振動の積雲対流活動活発期に生じ易いし、雲塊は下層の低気圧性渦度の周辺に存在し、発散場はMJOに伴う積雲対流活動の西方極側に現れる。熱帯低気圧や台風の絶対数は振動の積雲対流活動活発期に増大するが、弱い熱帯低気圧から転化する熱帯低気圧と台風の比率は、積雲対流活動活発期と乾燥期において同一である。積雲対流活動活発期においてより多くの熱帯低気圧や台風が存在するのは、当時期により多くの弱い熱帯低気圧が存在することによる。当研究の第三の結果は、積雲対流活動活発期の熱帯低気圧の活動度がMJOの活動度に限定されていない点である。事実、我々はMJOと独立かつ無作為に選ばれた積雲対流活動活発期において熱帯低気圧の活動度が同等に増大することを見いだした。結論として、MJOは熱帯低気圧に影響を及ぼす独自の機構を持つと言うより、むしろそれに伴う熱帯の変動度が大きな割合を占めるという点で重要である。
- 著者
- 三輪 律江 仙田 満 矢田 努
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.487-492, 1992-10-25 (Released:2019-12-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
THIS STUDY ATTEMPTS TO DEVELOP POLICY AND PLANNING TOOLS FOR IMPROVING CHILDREN'S PLAY ENVIRONMENTS AND ANIMATING PLAY THROUGH CASE STUDIES IN SIX CITIES, AS PART OF A SERIES OF INTERNATIONAL CASE STUDIES. THREE SCHOOL DISTRICTS WERE CHOSEN FOR INTERVIEWS EMPLOYING A QUESTIONNAIRE AND A MAP. PARALLEL OBSERVATIONS HAVE PROVIDED DATA AS TO WHERE AND HOW CHILDREN ACTUALLY PLAY.
1 0 0 0 OA 日本呼吸療法医学会ECMO事業の歴史と変遷
- 著者
- 竹田 晋浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸療法医学会
- 雑誌
- 人工呼吸 (ISSN:09109927)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.12-16, 2021 (Released:2022-05-30)
- 参考文献数
- 5
本邦の呼吸不全に対するECMO(extracorporeal membrane oxygenation:体外式膜型人工肺)治療は、2009年のH1N1インフルエンザ当時は海外の治療水準に大きく遅れを取っており、その改善を目的として、日本呼吸療法医学会にてECMOプロジェクトが立ち上げられた。このプロジェクトは少しずつではあるが着実に成果を上げ、2016年には本邦のECMO治療の成績は世界のトップレベルにまで至ったことが確認できた。 そして2020年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対して日本COVID-19対策ECMO net(ECMO net、現:NPO法人日本ECMO net)が立ち上げられ、ECMOプロジェクトを創設した当学会が共同で活動を行うこととなった。多くの関係学会からもECMO netの活動に対する賛同と協力を得るに至り、まさに“ALL JAPAN”によるCOVID-19への有事対応となった。 この現象は、本邦の医学史のなかではきわめて異例であり、所属団体を超えた医療者同士の関係構築が、その後のECMO netの活動を強固たるものにしてゆく礎となった。当学会から発展したECMO netは、重篤な新興感染症パンデミックに対して本邦で初めて実働した緊急医療支援団体であり、その活動は今後の医療政策において欠かせぬものとなるであろう。
- 著者
- 齊藤 大樹 開 光太朗
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0920, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】脳性麻痺者では,痙縮による姿勢筋緊張亢進が正常発達を阻害している。神経筋電気刺激(以下:NMES)は,痙縮抑制や筋萎縮予防及び改善を目的として実施される物理療法であり,脳性麻痺患者を対象とした痙縮や筋緊張の変化についての報告はほとんど見当たらない。また,NMESによる筋緊張抑制には,拮抗筋刺激(相反性抑制)を利用したIa-NMESおよび痙縮筋直接刺激(自己抑制)を利用したIb-NMESが知られている。先行研究では,脳性麻痺者の痙縮に対して,Ia-NMESとストレッチを行い,筋緊張抑制に少し効果があったとされているが,健常人においてはIa-NMESとIb-NMESを比較した場合Ib-NMESのほうがストレッチ前処置としては効果が高かったと示されている。今回,通常行っている可動域練習(ROM)と比べ各NMESを与えることで痙縮の改善が得られるのかを検証した。【方法】対象はGMFCSIIIレベルの成人脳性麻痺者1名(19歳)とし,対象筋はヒラメ筋とした。介入期間は1ヶ月半とし,足関節可動域練習,Ib-NMES,Ia-NMESの3つの介入をそれぞれ日を分けて行ない,セッションごとの即時効果を検証した。NMES刺激は総合電気治療器ES-520,刺激電極5cm×9cmの粘着パッド使用し,設定は周波数20Hz,刺激強度12~14mA,刺激時間10分間,立ち上がり2sec,持続4sec,減衰0.5sec,休止4secとし,刺激はIb-NMESはヒラメ筋,Ia-NMESは前脛骨筋に与えた。足関節可動域練習は徒手による持続的伸張を下腿三頭筋に伸張反射が出現しない速度で最終可動域付近まで行い,一回につき20秒,休息2秒,5分間実施した。評価は足関節背屈角度,Modifield Ashwonh Scale(MAS),筋硬度,足関節背屈抵抗トルクの測定を各介入前,介入後に実施し,結果値は3回測定した結果の平均値を採用した。【結果】足関節背屈角度とMASにおいてはROM後は抵抗が少し低下,背屈角度改善し,Ib-NMES後は抵抗増加,背屈角度低下し,Ia-NMES後は抵抗が少し低下したが,角度は大きく変わらなかった。ヒラメ筋の筋硬度はROM後は変化が少なく,Ib-NMES後は増加し,Ia-NMES後は少し低下した。足関節背屈抵抗トルクはROM後はやや低下し,Ib-NMES後は増加,Ia-NMES後は少し低下した。【結論】今回,ヒラメ直接刺激はIb抑制による緊張緩和を期待していたが,反対に電気刺激により緊張している筋を余計に緊張させてしまった。一方,拮抗筋である前脛骨筋刺激はIa相反抑制により,ヒラメ筋の緊張低下に効果があったと考える。しかし,足関節背屈角度は有意な変化が少なかった。この要因としては,痙縮抑制が生じても長年の痙縮持続による筋短縮や関節構成体自体の拘縮が存在しているため,角度変化については限りがあるのだと考える。今回,一例であるが即時効果が得られる可能性が示唆されたため,運動療法の介入前に電気刺激を実施し痙性を抑制させることで,その後の正常な運動パターン学習を行いやすくする可能性が考えられた。
1 0 0 0 OA 「スポーツ観戦者」の熱中症予防のガイドライン作成
暑熱環境における「スポーツ観戦者」の温熱的ストレス指標に及ぼす影響を検討した。その結果、次のことが明らかになった。①観戦者は熱中症に対する危険意識が低い、②口渇感に頼る水分摂取量では十分ではない、③お茶のみの飲水では体内電解質が不足する、④日常的に曝露されている気象・環境が暑熱環境での応答に影響を及ぼす、⑤女性と比較して男性は水分摂取量が少なく,脱水率が高い。以上のことから、暑熱環境下の観戦は,ほぼ安静状態であっても暑熱ストレスの影響を受け,熱中症発症の可能性が高いことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 遺伝子異常と心筋疾患
- 著者
- 木村 彰方
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.438-449, 2018-04-15 (Released:2019-05-09)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 とやまと自然
- 著者
- 富山市科学文化センター建設準備事務局
- 出版者
- 富山市科学文化センター建設準備事務局
- 巻号頁・発行日
- 1978
- 著者
- 野入 直美
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19.20, pp.1-11, 2022 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 95
1 0 0 0 OA 在日フィリピン人社会の現在 結婚移民の高齢化・単身化と日系人の多世代居住
- 著者
- 高畑 幸
- 出版者
- 西日本社会学会
- 雑誌
- 西日本社会学会年報 (ISSN:1348155X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19.20, pp.13-22, 2022 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 23
1 0 0 0 OA 興行と介護の移住女性労働者 在日フィリピン人の経験から
- 著者
- 高畑 幸
- 出版者
- 日本労働社会学会
- 雑誌
- 日本労働社会学会年報 (ISSN:09197990)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.30, 2020 (Released:2021-12-28)
- 参考文献数
- 21
- 著者
- Lixiang Wang Yingping Deng
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.9, pp.893-902, 2020 (Released:2020-09-28)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 7 9
Androgen regulates the function of lacrimal and meibomian glands, and its deficiency is a pathological factor underlying dry eye disease (DED). However, no androgen has been approved for treating DED due to lack of definite evidence regarding its efficacy and safety in clinics. In this systematic review, we have summarized the clinical studies on the safety and efficacy of androgen replacement therapy (ART) for DED. Medline (via Pubmed), Embase, Clinicaltrials.gov, Wanfang and Chinese Clinical Trials Registry Database were searched for the relevant prospective studies, and 7 studies wherein androgen was applied topically via eye drops or systemically via oral or transdermal administration were included. The quality of these studies was assessed with the Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias and methodological index for non-randomized studies. Most studies showed that androgen effectively improved dry eye-related symptoms and increased tear secretion. Furthermore, elderly men and peri-menopausal women with lower levels of circulating androgens responded better to ART. However, one study involving patients with Sjögren’s syndrome showed no improvement in the ART group compared to the placebo control, or to the baseline level. Adverse effects were also common but limited to mild skin problems. In conclusion, androgen is a potential treatment for dry eye disease, especially for people with primary androgen deficiency. Short-term application is relatively safe.
1 0 0 0 OA 日本国内の塗り絵の出版状況と幼児教育への浸透
- 著者
- 小田 久美子
- 出版者
- 日本美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育 (ISSN:13434918)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.277, pp.60-65, 1998-12-01 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA いまさら聞けなかった「エントロピー」と「エンタルピー」
- 著者
- 永田 和宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.282-285, 2022-06-20 (Released:2023-06-01)
物質を構成する原子や分子は温度により多くの原子欠陥を生成する。この欠陥が増大すると固体から液体へ液体から気体に変態する。この物質の乱雑さの尺度がエントロピーである。この欠陥は外部からの熱の出入りにより変化する。この熱がエンタルピーであり,内部エネルギー変化と物質がする仕事に使われる。この熱で物質に流入するエントロピーより物質のエントロピー変化は常に大きい。その差はエントロピー生成といい,常に正で自然に起こる過程は不可逆である。エントロピー生成は熱や成分などの流れが生じると生成し非補償熱として散逸する。安定した定常状態ではエントロピー生成が極小であり,大きくなると他の定常状態に遷移することがある。
1 0 0 0 OA 知的能力検査に関する妥当性一般化 -メタ分析による結果-
- 著者
- 高橋 潔 西田 直史
- 出版者
- 産業・組織心理学会
- 雑誌
- 産業・組織心理学研究 (ISSN:09170391)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.3-12, 1994 (Released:2020-07-27)
1 0 0 0 パパ心配しないで : お嬢さんドイツ留学記
- 著者
- 二宮 理佳 金山 泰子
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- ICU日本語教育研究 (ISSN:18800122)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.39-57, 2007
1 0 0 0 OA へーゲルによる「神の痛み」の思想
- 著者
- 松田 央
- 出版者
- The Japan Society of Christian Studies
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.36, pp.32-54, 1997-08-22 (Released:2010-02-10)
- 参考文献数
- 37
1 0 0 0 OA 教育過程の総合的行動遺伝学研究
児童期と成人期の2コホートによる双生児縦断研究を実施した。児童期は小学5年生(11歳児)約200組に対する質問紙と120組への個別発達調査を行った。読み能力や実行機能の発達的変化に及ぼす遺伝と環境の変化と安定性、リズム行動に及ぼす遺伝と環境の交互作用、きょうだい関係の特殊性などが明らかになった。成人期では社会的達成・心身の健康度などの質問紙調査を実施し約200組から回答を得た。また認知能力の不一致一卵性の安静時脳画像とエピジェネティクスのデータを収集した。下側頭回のネットワークの差が一卵性双生児間のIQ差と関連のあることが示された。向社会性への遺伝的寄与が状況により変化することが示された。