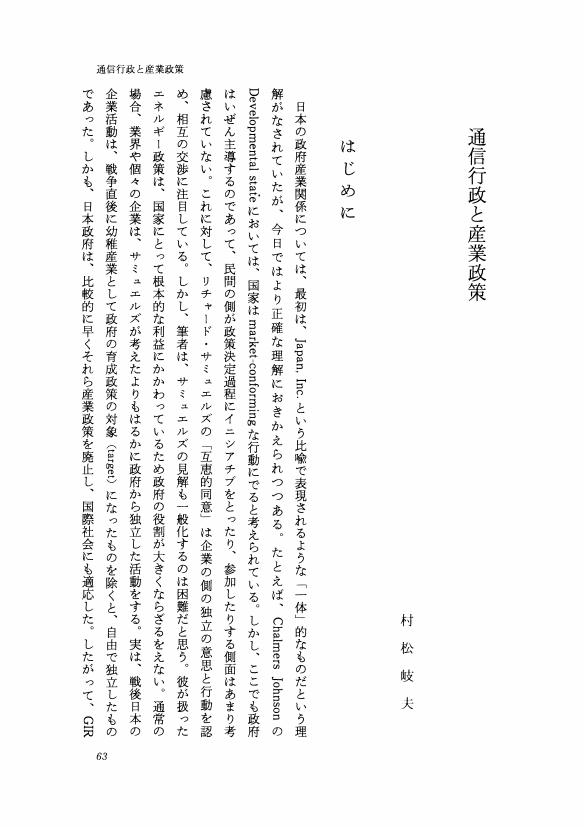43 0 0 0 OA 心理生理学データの分散分析
- 著者
- 入戸野 宏
- 出版者
- 日本生理心理学会
- 雑誌
- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.275-290, 2004-12-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 3 8
反復測定を含む実験計画で得られたデータに分散分析を実施することは, 心理生理学の研究で広く行われている.しかし, 研究者が適切な統計手法を選ぶことは往々にして難しい.本稿は, 心理生理学データに反復測定の分散分析を行うときの, 統計学的に妥当で, 容易に実施できる手続きについて述べたものである.取り上げたのは, 単変量・多変量分散分析の比較, 誤差項の選択, 単純効果と交互作用対比の検定, 多重比較, 効果量といった話題である.典型的な統計検定の流れを数値例を用いて解説する.
43 0 0 0 OA 和文ゴシック体創出の研究経緯
- 著者
- 石川 重遠 後藤 吉郎 山本 政幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第56回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.G02, 2009 (Released:2009-06-16)
この研究は、アメリカのゴシック体に影響を受けた日本のゴシック体の創出について明確にするものである。欧文書体とタイポグラフィの3名の専門の研究者がこの課題解決に取り組んでいる。山本は、ヨーロッパのサンセリフ体がアメリカに渡りゴシック体と呼ばれるようになった研究をしている。また、後藤は、アメリカの印刷技術が日本の近代印刷技術の礎を築いた研究をしている。石川は、日本語のゴシック体の創出に関する研究をしている。この3つの研究をつなげ、「和文ゴシック体創出と欧文書体との関連性研究」としてまとめたい。 今回の発表テーマは、和文ゴシック体の創出である。
43 0 0 0 OA Early SNS-based monitoring system for the COVID-19 outbreak in Japan: a population-level observational study
- 著者
- Daisuke Yoneoka Takayuki Kawashima Yuta Tanoue Shuhei Nomura Keisuke Ejima Shoi Shi Akifumi Eguchi Toshibumi Taniguchi Haruka Sakamoto Hiroyuki Kunishima Stuart Gilmour Hiroshi Nishiura Hiroaki Miyata
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20200150, (Released:2020-05-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 34
BackgroundThe World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak (COVID-19) to be a pandemic on March 11, 2020. Large-scale monitoring for capturing the current epidemiological situation of COVID-19 in Japan would improve preparation for and prevention of a massive outbreak.MethodsA chatbot-based healthcare system named COOPERA (COvid-19: Operation for Personalized Empowerment to Render smart prevention And care seeking) was developed using the LINE app to evaluate the current Japanese epidemiological situation. LINE users could participate in the system either though a QR code page in the prefecture’s website, or a banner at the top of the LINE app screen. COOPERA asked participants questions regarding personal information, preventive actions, and non-specific symptoms related to COVID-19 and their duration. We calculated daily cross correlation functions between the reported number of infected cases confirmed by PCR and the symptom-positive group captured by COOPERA.ResultsWe analyzed 206,218 participants from three prefectures reported between March 5 and 30, 2020. The mean (standard deviation) age of participants was 44.2 (13.2). No symptoms were reported by 96.93% of participants, but there was a significantly positive correlation between the reported number of COVID-19 cases and self-reported fevers, suggesting that massive monitoring of fever might help to estimate the scale of the COVID-19 epidemic in real time.ConclusionsCOOPERA is the first real-time system being used to monitor trends in COVID-19 in Japan, and provides useful insights to assist political decisions to tackle the epidemic.
43 0 0 0 OA 「ウェブらしさ」を改めて考える-2010年代のウェブと社会-
- 著者
- 大向 一輝
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.284-289, 2020-06-01 (Released:2020-06-01)
本稿では,インターネット上でハイパーテキストを実現するための情報システムであるウェブが,人々のコミュニケーションや社会のあり方に対してどのような影響を与えたのかについて議論する。とくに2010年代に普及したスマートフォンやSNSによって,ウェブと人々の関わりが緊密になったことが情報の信頼性を高めると同時に炎上やフェイクニュースの原因となる点について指摘した。また,ウェブの今後の課題について「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の観点から議論する。
- 著者
- Seiji YUKIMOTO Yukimasa ADACHI Masahiro HOSAKA Tomonori SAKAMI Hiromasa YOSHIMURA Mikitoshi HIRABARA Taichu Y. TANAKA Eiki SHINDO Hiroyuki TSUJINO Makoto DEUSHI Ryo MIZUTA Shoukichi YABU Atsushi OBATA Hideyuki NAKANO Tsuyoshi KOSHIRO Tomoaki OSE Akio KITOH
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.90A, pp.23-64, 2012 (Released:2012-06-07)
- 参考文献数
- 157
- 被引用文献数
- 354 624
A new global climate model, MRI-CGCM3, has been developed at the Meteorological Research Institute (MRI). This model is an overall upgrade of MRI’s former climate model MRI-CGCM2 series. MRI-CGCM3 is composed of atmosphere-land, aerosol, and ocean-ice models, and is a subset of the MRI’s earth system model MRI-ESM1. Atmospheric component MRI-AGCM3 is interactively coupled with aerosol model to represent direct and indirect effects of aerosols with a new cloud microphysics scheme. Basic experiments for pre-industrial control, historical and climate sensitivity are performed with MRI-CGCM3. In the pre-industrial control experiment, the model exhibits very stable behavior without climatic drifts, at least in the radiation budget, the temperature near the surface and the major indices of ocean circulations. The sea surface temperature (SST) drift is sufficiently small, while there is a 1 W m-2 heating imbalance at the surface. The model’s climate sensitivity is estimated to be 2.11 K with Gregory’s method. The transient climate response (TCR) to 1 % yr-1 increase of carbon dioxide (CO2) concentration is 1.6 K with doubling of CO2 concentration and 4.1 K with quadrupling of CO2 concentration. The simulated present-day mean climate in the historical experiment is evaluated by comparison with observations, including reanalysis. The model reproduces the overall mean climate, including seasonal variation in various aspects in the atmosphere and the oceans. Variability in the simulated climate is also evaluated and is found to be realistic, including El Niño and Southern Oscillation and the Arctic and Antarctic oscillations. However, some important issues are identified. The simulated SST indicates generally cold bias in the Northern Hemisphere (NH) and warm bias in the Southern Hemisphere (SH), and the simulated sea ice expands excessively in the North Atlantic in winter. A double ITCZ also appears in the tropical Pacific, particularly in the austral summer.
43 0 0 0 OA 釜ヶ崎におけるホームレス伝道の社会学的考察 : もうひとつの野宿者支援
- 著者
- 白波瀬 達也
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.25-49, 2007-06-09 (Released:2017-07-18)
- 被引用文献数
- 2
本稿は野宿者が集住する最下層地域、釜ヶ崎において顕著にみられるキリスト教の「ホームレス伝道」とその受容状況について考察する。日雇労働者の街として知られる釜ヶ崎は、1960年代後半から1990年代初頭にかけて、労働運動が大きな影響力をもっており、キリスト教の直接的な伝道が困難な状況にあった。1990年代中頃に釜ヶ崎は大量の野宿者を生むようになるが、それに伴って労働運動の規制力が弛緩し、1990年代後半にホームレス伝道が急増するようになった。現在、10の教会/団体が食事の提供を伴った「伝道集会」を開催するようになり、多くの野宿者が参加しているが、実際に洗礼を受け、特定の教会にコミットメントをもつようになる者は極めて少ない。宗教と社会階層の関係に着目したこれまでの研究では、社会移動の激しい最下層の人々は特定の宗教シンボルとの関係がランダムあるいは希薄だとする議論が一般的であったが、本稿はこの理論的前提を具体的なフィールドデータから検証し、最下層の人々に特徴的な信仰と所属の様態を把握する。
43 0 0 0 OA 渡良瀬遊水地の洪水調節機能とその課題の考察
- 著者
- 松本 敬司 中井 隆亮 福岡 捷二 須見 徹太郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.I_1477-I_1482, 2014 (Released:2015-05-18)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3
The Watarase retarding basin which is located in the lower Watarase River has an important role on the flood control in the Tone River. The design flood discharge of a period of about 30 years hereafter in the Tone River is 14,000m3/s at the Kurihashi of the Tone River.In this paper, the flood control functions of the Watarase retarding basin are investigated by the flood flow analysis when the peak flood discharge under various discharge hydrographs is about 14,000m3/s at the Kurihashi in the Tone River. It is shown from the calculation that the Watarase retarding basin reduces peak flood discharge and delays the peak occurrence time at the Kurihashi by storing flood discharge flowing back to the Watarase River from the Tone River. Furthermore, some remarks are given for the enhancement of flood control functions of the Watarase retarding basin.
- 著者
- Kosuke Ito Hiroyuki Yamada Munehiko Yamaguchi Tetsuo Nakazawa Norio Nagahama Kensaku Shimizu Tadayasu Ohigashi Taro Shinoda Kazuhisa Tsuboki
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.105-110, 2018 (Released:2018-07-28)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 23
The inner core of Tropical Cyclone Lan was observed on 21-22 October 2017 by GPS dropsondes during the first aircraft missions of the Tropical Cyclones-Pacific Asian Research Campaign for the Improvement of Intensity Estimations/Forecasts (T-PARCII). To evaluate the impact of dropsondes on forecast skill, 12 36-h forecasts were conducted using a Japan Meteorological Agency non-hydrostatic model (JMA-NHM) with a JMA-NHM-based mesoscale four-dimensional data assimilation (DA) system. Track forecast skill improved over all forecast times with the assimilation of the dropsonde data. The improvement rate was 8-16% for 27-36-h forecasts. Minimum sea level pressure (Pmin) forecasts were generally degenerated (improved) for relatively short-term (long-term) forecasts by adding the dropsonde data, and maximum wind speed (Vmax) forecasts were degenerated. Some of the changes in the track and Vmax forecasts were statistically significant at the 95% confidence level. It is notable that the dropsonde-derived estimate of Pmin was closer to the real-time analysis by the Regional Specialized Meteorological Center (RSMC) Tokyo than the RSMC Tokyo best track analysis. The degeneration in intensity forecast skill due to uncertainties in the best track data is discussed.
43 0 0 0 OA 多摩田園都市における生活関連施設の立地経緯について
- 著者
- 石橋 登 谷口 汎邦
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.635, pp.41-50, 2009-01-30 (Released:2009-11-02)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
The Study clarified how neighbourhood amenities are located following their spontaneous emergence in a suburban residential area developed through land readjustment projects. The main findings of the Study are listed below.1) The scope of the development of neighbourhood amenities by a private developer is limited as the emphasis is placed on profit-making amenities.2) In a situation where the locationing of neighbourhood amenities is left to spontaneous emergence, there is a tendency for such amenities to be clustered around a railway station.3) The unit number of neighbourhood amenities shows secular changes while reflecting the characteristics of individual zones.
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:13499092)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20160200, (Released:2017-11-11)
- 被引用文献数
- 36
- 著者
- Eun-Kyung Kim Jin Seop Kim
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.11, pp.3136-3139, 2016 (Released:2016-11-29)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 65
[Purpose] The purpose of the present study is to apply short foot exercises and arch support insoles in order to improve the medial longitudinal arch of flatfoot and compare the results to identify the effects of the foregoing exercises on the dynamic balance of the feet and the lower limbs. [Subjects and Methods] Fourteen university students with flexible flatfoot were selected by conducting navicular drop tests and randomly assigned to a short foot exercise group of seven subjects and an arch support insoles group of seven subjects. The intervention in the experiment was implemented for 30 minutes per time, three times per week for five weeks in total. [Results] In inter-group comparison conducted through navicular drop tests and Y-balance tests, the short foot exercise group showed significant differences. Among intra-group comparisons, in navicular drop tests, the short foot exercise group showed significant decreases. In Y-balance tests, both the short foot exercise group and the arch support insoles group showed significant increases. [Conclusion] In the present study, it could be seen that to improve flatfoot, applying short foot exercises was more effective than applying arch support insoles in terms of medial longitudinal arch improvement and dynamic balance ability.
43 0 0 0 OA 加減速操作位置呈示による列車運転士の運転支援システムに関する研究
- 著者
- 丸茂 喜高 清水 勇介 竹内 亮佑 綱島 均 小島 崇
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.817, pp.TL0280-TL0280, 2014 (Released:2014-09-25)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
This study proposes a driving assistance system to inform the notch operation timing for train drivers. The assistance system indicates visually the notch-off position where the driver releases the accelerator. The notch-off position is calculated by the present vehicle acceleration, velocity and position by assuming the constant acceleration. The assistance system also indicates the brake onset and the predicted stopping positions. Two experiments are conducted by using the train-driving simulator. One experiment examines the effects of the notch-off and brake onset timing on the vehicle velocity and the running time. The assistance system makes it possible to adjust the vehicle velocity and the running time. The other experiment examines the three running patterns by combination of the notch-off and the brake onset positions. With the time recovering pattern, which is combination of the higher notch-off velocity and the later brake onset timing, the assistance system realizes the shorter running time in comparison with the standard running pattern. With the energy saving pattern, which is combination of the lower notch-off velocity and the later brake onset timing, the assistance system prevents the time delay by the later brake timing even if the velocity is lower than the standard running pattern.
43 0 0 0 OA 通信行政と産業政策
- 著者
- 村松 岐夫
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.24, pp.63-89, 1990-05-25 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 21
43 0 0 0 OA 競泳用水着による体幹部圧迫が身体形状および人体生理に及ぼす影響
- 著者
- 諸岡 晴美
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.408-411, 2000-04-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 4
43 0 0 0 OA GISを利用した火砕流の被害予測と避難・救援計画—浅間山南斜面を事例として—
- 著者
- 高阪 宏行
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.483-497_2, 2000-06-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
日本でも多くの活火山に対し火山災害予測図が作成されてきたが,この地図は火山災害の物理的状況を表すだけで,地域社会に与える被害を予測するものではない.火山災害予測図を基礎資料として,人口分布,道路・農地・公共施設などとの位置関係を探ることによって,初めて被害が予測できるのである.本研究は,浅間山の南斜面に発生する火砕流を事例として,GISを利用した防災計画支援システムを構築した.このシステムでは,火山災害予測図をもとに火砕流の流動範囲を噴火後5分以内,5分~10分,10分~15分,15分~30分に色分けして表示するとともに,火砕流のレイヤーと人口分布,道路,鉄道・高速道路,あるいは・学校・病院・ホテルなどのレイヤーとを重ね合わせることで,二っの分布の共通部分から被害予測図を作成した. 被害予測図を用いて被害を予測した結果,被災面積は2,529ha, 人的被害は約3,500人に及ぶことが明らかとなった.また,道路の被災区間は,約1.9kmの国道を含む34.5kmに及び,鉄道や高速道路にも10分~15分で火砕流が到達することが予測された.さらに,防災計画支援システムを利用レて,火砕流が覆う地区をリスク1の地区,その地区周辺で火災が延焼する可能性のある地区を500mバッファのリスク2の地区とし,火砕流に対する緊急計画地域として設定した.また,火砕流からの脱出計画,避難所の設置,避難民の収容計画,救援計画を考察した.
- 著者
- Kazuya Shirato Akinori Azumano Tatsuko Nakao Daisuke Hagihara Manabu Ishida Kanji Tamai Kouji Yamazaki Miyuki Kawase Yoshiharu Okamoto Shigehisa Kawakami Naonori Okada Kazuko Fukushima Kensuke Nakajima Shutoku Matsuyama
- 出版者
- 国立感染症研究所 Japanese Journal of Infectious Diseases 編集委員会
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.256-258, 2015 (Released:2015-05-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 14
42 0 0 0 OA キリスト教における輪廻転生思想 -実存論的神学の立場から
- 著者
- 林 昌子
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.22-30, 2019-07-15 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 40
キリスト教史上において、輪廻転生思想は決して稀ではなかった。むしろ、イエスの時代の信仰に、あるいは福音書に、初期キリスト教時代教父たちの思想やグノーシス的キリスト教の流れのうちに輪廻転生思想は存在する。公会議等によって正統と異端とが峻別されていった歴史は、同時に、異端とされたキリスト教が、中心のローマから東西の辺境に拡散した歴史でもある。辺境世界のキリスト教では、輪廻転生思想が採用されることも珍しくない。多様性と実用性が重んじられる近代においてはなおさら、キリスト教がその教理の内に輪廻転生思想を取り入れる余地がある。本論では、日本のプロテスタント神学である21世紀の実存論的神学において、輪廻転生がどのような理由で受け入れられたのかを考察する。聖書に根拠の乏しい予定説が、後の時代に教理として形成されていった過程を是とするならば、実存論的神学が万有救済説および輪廻転生説を教理として採用することに、神学上の誤謬は生じない。むしろそれらを積極的に採用することが、日本にキリスト教を土着させるための一助となる。
42 0 0 0 OA コミュニケーションにおける曖昧さとその機能
- 著者
- 高橋 英之 岡田 浩之
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.450-463, 2010-08-15 (Released:2010-11-15)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3 3
コミュニケーションは人間の社会性の基盤となるものである.コミュニケーションは情報交換であり,一般的にはそこに曖昧さは必要が無いと考えられる.本論文では,人間のコミュニケーションに含まれる曖昧さが,特に大きな規模の社会集団では非常に重要な機能を持つという仮説を提起し,それを検討するためのシミュレーションと二つの顔表情を題材とした心理実験を行った.本論文ではそれらの研究の詳細を述べるとともに,それらの結果を受け,社会性やコミュニケーションの背後には曖昧さを処理する脳機能が大きな働きをしているのではないかという議論を行った.
42 0 0 0 OA ゴカイ道
- 著者
- 自見 直人
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.1-8, 2023-08-31 (Released:2023-09-08)
- 参考文献数
- 41
Polychaetes represent an immensely diverse taxonomic assemblage, encompassing approximately 12,000 species across 92 families. These organisms have a broad range of habitats, from the Arctic to the Antarctic, and spanning terrestrial environments to the hadal depths of the oceans. Polychaetes are one of the most prevalent taxonomic groups in ecological studies, both in terms of biomass and species richness. Consequently, taxonomic research on polychaetes is pivotal as it forms the foundational basis for various studies. This paper aims to provide an overview of the taxonomy of polychaetes and the research conducted within Japan and to deliberate on the research objectives that warrant further exploration.
42 0 0 0 OA デザイン組織の標準KPIの策定と検証 ― 日本企業における社内デザイン組織を研究対象として ―
- 著者
- 毛 鋭 鷲田 祐一
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングレビュー (ISSN:24350443)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.20-27, 2022-02-28 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 22
本研究の目的は,社内のデザイン組織の活動や成果を共通的な視点で定量的に評価できる手法を開発することを通じて,デザイン経営における「デザイン価値の可視化」問題を明らかにし,デザイン資源の有効活用に寄与することである。そこで,本研究は実務的な視点から,日本大手企業4社のデザイン組織を対象に,プロジェクト単位で合計465名の社内他部門の中間管理層によるデザイン組織へのパフォーマンス評価を求めて,社内デザイン組織は事業へ貢献する主な要素を「商品開発力」・「情報の提供」・「ブランドの一貫性」・「アウトプットの速度」および「コスト」,という五つの要素に抽出することができた。その上,重回帰分析を用いて,それがデザイン組織への満足度に与える影響性を考慮し検証したところ,各社には社内デザイン組織への評価あるいは求めるポイントは異なることがわかった。分析結果を受けて,各企業におけるデザイン組織のパフォーマンスを定量的に評価する指標が策定できることを示唆した。