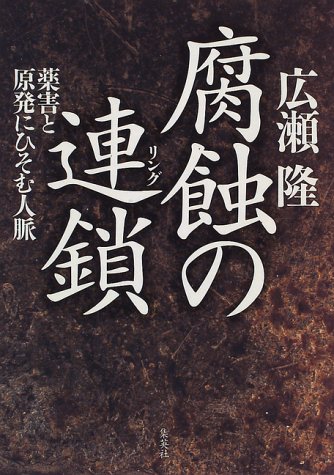1 0 0 0 OA 足関節impingement exostosisに対する鏡視下手術の経験
- 著者
- 鬼木 泰成 中村 英一 水田 博志
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.589-592, 2007 (Released:2007-11-27)
- 参考文献数
- 13
足関節impingement exostosis(以下IE)は脛骨前下縁と距骨背側に発生する骨増殖性変化であり,足関節痛を引き起こす場合がある.今回,IEによる疼痛に対し鏡視下手術を施行した4例を経験したので報告する.【対象】足関節痛にて受診し,単純X線にてIEが確認された4名(男性3名,女性1名),平均年齢15.5歳.【局所所見】軽度の背屈制限と足関節前面に圧痛,運動時痛を認めた.【X線】脛骨前下縁と距骨頸部背側にIEを認め,強制背屈にて衝突像を認めた.足関節不安定性を2名に認めた.【足関節鏡所見】滑膜の増生と軟骨に覆われた骨増殖像を確認し,強制背屈にて衝突を確認した.【手術】鏡視下に骨棘切除術,滑膜切除術を施行した.【経過】疼痛は消失し,スポーツ可能となった.【考察】IEに対する鏡視下手術は低侵襲で,比較的早期のスポーツ復帰が可能であった.問題点としては骨棘の再発についての十分な経過観察が必要であると考えられた.
- 出版者
- 富山大学附属図書館
- 巻号頁・発行日
- 2012
川合文書は、藩政期に砺波郡戸出村(現高岡市戸出)に居住した十村、川合家に伝来した文書であり、藩政期から明治に至るまでの農政の研究に欠かすことのできない貴重な史料を多数含んでいる。
1 0 0 0 OA 白色LEDパルス光がサラダナ生育に及ぼす影響
- 著者
- 森 康裕 高辻 正基 安岡 高志
- 出版者
- 日本生物環境工学会
- 雑誌
- 植物工場学会誌 (ISSN:09186638)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.136-140, 2002-09-01 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 15 18
Lettuce was grown under pulsed white LED light at variation pulse cycles and DT ratios (illuminated period/cycle), and the relative growth rate per unit luminous energy and photosynthetic rate were examined. Both the growth rate and photosynthetic rate were generally increased (except at a pulse cycle of 10ms and a DT ratio of 50%) compared with continuous illumination. Particularly, both the growth rate and photosynthetic rate were increased by 20% or more at a pulse cycle of 400μs and a DT ratio of 50%. A further slight increase in the growth rate was observed when the DT ratio was 33%. These results may be explained by the presence of a period of 200μs duration in which light is unnecessary (period of electron transport) in the light reaction of photosynthesis. This study supports the feasibility of LED plant factories.
1 0 0 0 OA セフトリアキソン投与が原因と考えられる胆砂形成に合併した急性膵炎の1成人例
- 著者
- 佐々木 諭実彦 青木 佐知子 青木 孝太 阿知波 宏一 山 剛基 久保田 稔 石川 大介 水谷 哲也 國井 伸 渡辺 一正 奥村 明彦
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.4, pp.569-575, 2009 (Released:2009-04-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
症例は35歳の女性.大腸憩室炎に対してセフェム系抗菌薬であるセフトリアキソンを投与した後に胆砂が出現し急性膵炎を発症した.約1週間の絶食期間があったこと,セフトリアキソンが長期に投与されたことなどの要因が重なって胆砂が形成されたと考えられた.セフトリアキソン投与が胆泥や胆石の形成を促進する因子であることを十分認識し,腹部症状が出現した際には速やかに精査を行い適切な治療を開始する必要があると考えられる.
1 0 0 0 腐蝕の連鎖(リング) : 薬害と原発にひそむ人脈
1 0 0 0 OA ペットフードで使用される主なカルシウム、リン、マグネシウム源原料(後編)
- 著者
- 迫田 順哉
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.37-48, 2023-04-10 (Released:2023-05-25)
- 参考文献数
- 67
1 0 0 0 OA 商業教育局における社会教育と教養の系譜
- 著者
- 木下 浩一
- 出版者
- Kyoto University
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-23
新制・課程博士
1 0 0 0 OA 「種の多様性と分類学」,両生類の多様性 —生活場所,繁殖,隔離—
- 著者
- 倉本 満
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.39-45, 1997 (Released:2008-07-30)
1 0 0 0 OA 前頭葉の発達とその障害
- 著者
- 青柳 閣郎 相原 正男
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.109, 2013 (Released:2017-04-12)
前頭葉、とくに前頭前野の社会生活における重要性が指摘されている。今回、発達途上の小児と、社会生活の困難さを示すことの多い発達障害児における前頭葉機能の評価を、これまでの我々の研究を中心に紹介する。進化の過程で、前頭前野の大きさはその種の群れの大きさ、すなわち社会の規模に比例しているとされている。また、個体発生は系統発生の過程を再現するといわれている。我々は、ヒトの前頭前野が前頭葉に占める体積の割合が、10歳前頃から急増しはじめ、20歳頃まで増加し続けることを報告した。それはあたかも、家庭から学校、社会へと、人間関係がより複雑になってゆくヒトの社会生活に前頭前野の成長が対応しているかのようである。社会生活に重要な前頭葉機能は、行動抑制、作業記憶、実行機能の順に萌芽してくる。行動抑制とは、将来のより大きな報酬を得るために、目前の刺激に対する反応を抑制する能力である。ヒトは、2 歳頃から行動抑制による動機づけが可能となるが、このとき行動抑制を喚起する生体内信号が情動性自律反応であり、その評価により行動抑制能力の発達や障害の推測が予想できると思われる。我々は、交感神経皮膚反応を用いて健常小児、情動回路損傷症例、発達障害児の情動性自律反応を評価し、健常小児で認めた反応が、情動回路損傷症例や発達障害児で低下していたことを明らかにした。発達障害児における情動性自律反応による行動抑制機能低下の可能性が示唆された。さらに我々は、成人、健常小児、発達障害児、情動回路損傷症例に、強化学習課題遂行中の交感神経皮膚反応を計測し、情動の意思決定への関与を検討した。その結果、健常小児は成人に比し、学習効果が有意に低く、情動反応も未分化であった。また、発達障害児、情動回路損傷症例はともに、学習効果、情動反応が健常小児よりも低かった。これは、情動による意思決定への関与の発達的変化と、発達障害児の情動反応低下による強化学習への影響を示すものと思われた。作業記憶は、必要な情報を必要な間だけ保持し必要なくなったら消去する機能であり、5 歳頃までに獲得し始める。その評価に衝動性眼球運動が有効とされる。我々は、衝動性眼球運動を用いて健常小児、発達障害児を評価し、作業記憶の発達的変化と、干渉制御失敗と衝動性による発達障害児の作業記憶障害を報告した。実行機能は、既に学習された知識・経験、新たに知覚された様々な情報を統合して、目標に向けた思考や行動を組み立てて意思決定する能力であり、7歳頃より芽生える。我々は、前頭葉における実行機能の左右差を評価する神経心理学検査を健常成人、健常小児に施行し、機能的脳画像や脳波周波数解析も交えながら、実行機能に関与する脳部位の時間・空間的変化と、発達的変化を報告した。さらに、発達障害児における実行機能の障害を考察した。
1 0 0 0 OA 特許データを利用した企業価値と研究開発投資の関係分析
- 著者
- Wu Haotian Zhang Chenghuan Han Dongli
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.FIN-030, pp.66-71, 2023-03-04 (Released:2023-03-04)
現代社会においては、科学技術の成果があらゆる場面で活用され、企業に様々な影響を及ぼしている。企業価値と企業における研究開発との関係について従来より研究されてきたが、研究内容まで細かく分析したものが少なかった。特に、中国を初めとした新興国は研究開発の面で大きな進歩を遂げている割には、この点についてはあまり研究されてこなかった。本研究では、中国のハイテク企業であるテンセントとバイドゥの特許データ、市場価値データと決算報告データを利用し、研究開発の内容と企業価値を表すトービンqの関係を分析するための線形回帰モデルを構築した。その結果、技術密集型企業では、研究開発の範囲を限定することによりq値を上げることができるかもしれないことが分かった。
1 0 0 0 OA 温冷水および温食物の摂取による深部体温の変化
- 著者
- 日笠 穣 山本 巌 成川 一郎
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.583-587, 1994-04-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
葛根湯など辛温解表薬の内服の際には, 経験的に温服が重要とされているが, 冷服との効果の差についてはほとんど報告はない。冷温水や温食物が体温に与える影響についても同様である。温服の意義を考察するために, 60℃の温湯180ml, 10℃の冷水180mlを成人10名に飲ませ, 鼓膜温を測定した。さらに70℃の汁400mlを含む天ぷらそばを食べた際の鼓膜温の変化も測定した。温湯の内服では8名に発汗があり, 鼓膜温の変化は一定の傾向は見られなかった。天ぷらそばの摂取では, 鼓膜温が0.73℃上昇した。10℃の冷水では鼓膜温が0.52℃低下した。葛根湯の内服では, 鼓膜温に変化は認められなかった。
1 0 0 0 OA 精神障害者グループホームの地域交流の実態に関する研究
- 著者
- 古山 周太郎 土肥 真人
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.31-36, 2000-10-25 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
This study makes the actual management and conditions of local communication in the Group homes of mental disturbed persons clear. I surveyed these 57 Group homes in Tokyo by hearings and analyzed the surround area of these Group homes with maps. In conclusion, first, we can see they have various operating organizations and principals such as the law for Group homes hopes. And Group homes are the house where mental disturbed persons can live in the local community. Secondly, more than half of all Group homes did the local communication in their own local areas. And the surround area of group homes or the principals of their operating organizations influences the local communications.
- 著者
- 足立 啓 宮本 浩行 赤木 徹也 近藤 隆二郎 日下 正基 本多 友常
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.540, pp.141-147, 2001-02-28 (Released:2017-02-04)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
Based on three case studies of social welfare facilities in proto-typical settings in a farm village, a town, and a city, we investigated how the facilities for persons with intellectual disability had been located and how they had been perceived and accepted by the local community. The following are results achieved by analyzing the diachronically receptive processes in case studies: 1) Employment opportunities which the facilities provided to the local people made it more easily receptive to people in the community. 2) The facilities played an important role of interacting with the local people in the local community. 3) The facilities tried to establish equal partnership with the local community. 4) Small group living was a key to reducing prejudice against persons with intellectual disability, and made people in the community more easily interactive under ordinary circumstances. 5) Reliable back-up supports were found to be essential in assisting independent living with persons with intellectual disability.
1 0 0 0 OA VI.副鼻腔気管支症候群
- 著者
- 金子 猛
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.10, pp.2132-2136, 2020-10-10 (Released:2021-10-10)
- 参考文献数
- 11
副鼻腔気管支症候群は「慢性・反復性の好中球性気道炎症を上気道と下気道に合併した病態」と定義されており,慢性副鼻腔炎に下気道の炎症性疾患である慢性気管支炎,気管支拡張症あるいはびまん性汎細気管支炎が合併した病態である.長引く咳嗽の鑑別診断として重要であり,特に容易に原因が特定できない湿性咳嗽の場合は,第一に考慮すべき病態である.治療の基本は,マクロライド系抗菌薬少量長期療法である.
1 0 0 0 OA 介護予防通所介護を利用する高齢者の軽度認知障害とその関連要因
- 著者
- 佐々木 八千代 野田 さおり 白井 みどり
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.83-90, 2021-04-30 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 35
介護予防通所介護を利用する高齢者を対象としたコホート研究のベースラインデータを用いて軽度認知障害(MCI)とその関連要因について検討した。対象の登録は2017年3月と2018年3月とし,聴力測定,日本版 Montreal Cognitive Assessment(MoCA-J)による認知機能検査,自記式質問紙調査を実施した。MoCA-Jの得点が25点以下をMCI, 26点以上を健常に分類した。ロジスティック回帰分析で多要因の影響を調整し,MCIに関するオッズ比(OR)を算出した。本研究の登録者は296人で,認知機能低下者は217人(73%)であった。登録者のうち,質問紙の回答が得られた272人を解析対象とした。年齢が上がるほど,MCIを有する者が多くなっており(65-79歳に対し80-84歳においてOR=2.18,85歳以上においてOR=6.56),糖尿病の既往があるものでMCIに対するORが上昇していた(OR=3.06)。一方,MCIに対するオッズ比が低下したものは,女性(OR=0.46),脳血管疾患の既往あり(OR=0.30),心疾患の既往あり(OR=0.39)であった。また,老研式活動能力指標の得点が上がるほどMCIを有する者の割合が少なくなっていた(1-9点に対し10-11点においてOR=0.20,12点以上においてOR=0.37)。本研究の結果から,加齢や糖尿病はMCIのリスクである可能性が示唆された。
- 著者
- 岡 京子
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.92-104, 2009-05-23 (Released:2017-09-22)
日本における高齢者介護施設では「全人的介護」という理念の導入、さらに公的介護保険制度開始による市場化の流れによって脱アサイラム化が図られることとなった。新しい介護理念と市場論理という2つの相反する要求の狭間に立たされたケアワーカーの労働は、措置時代の大規模処遇における労働に比べ、大きく変化していることが予測される。今回、高所得者が入居し職員から「VIPユニット」とよばれているユニットケアの場において参与観察を行いA.R.ホックシールドが見出した「感情労働」の観点からケアワーカーの労働を考察した。その結果、利用者の生活においては、かつてみられたようなアサイラム的状況が薄まり、利用者が人として尊重される部分のみならずケアワーカーと利用者のせめぎあいの場面の誕生という側面があるという事実が見出された。そしてケアワーカーの労働においては、利用者個々の自尊心を支え、かつ利用者間の関係を調整するために、またユニットの統制をとるためにも、自己の感情管理と同時に他者の感情管理技能としての「気づかい」が相即的になされている事実が見出された。
1 0 0 0 OA トマス・アクィナス『神学大全』について
- 著者
- 広瀬 京一郎
- 出版者
- 日本基督教学会
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.1967, no.6, pp.70-75, 1967 (Released:2009-09-16)
1 0 0 0 OA うつ病とsuicidality
- 著者
- 中川 敦夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本自殺予防学会
- 雑誌
- 自殺予防と危機介入 (ISSN:18836046)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.81-84, 2019-09-01 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 説明可能な機械学習モデルを用いた豪雨時における住民避難選択行動の要因分析
- 著者
- 塚本 満朗 高木 朗義
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.I_181-I_191, 2022 (Released:2022-05-18)
- 参考文献数
- 21
近年頻発する豪雨災害では様々な要因により人的被害が発生しており,住民避難の促進に関する課題に対して依然として取り組む必要がある.本研究では,機械学習モデルを用いて住民避難選択行動モデルを構築し,eXplainable AI (XAI)という技術を用いて住民避難選択行動の要因を分析した.具体的には,平成30年7月豪雨時の岐阜県と西日本の調査データ,令和元年台風 19 号の東日本の調査データに対して XAI の PI 分析および PD 分析により,避難/非避難および避難場所選択に影響をもたらす要因を明らかにした.
1 0 0 0 OA 研究 心係数の男女差
- 著者
- 新谷 冨士雄 渡辺 真司 稲木 一元 田中 政
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.12, pp.1466-1472, 1982-12-25 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 26
心係数(心拍出量/体表面積)の男女差有無を検討するために,正常な男女349例の安静時心拍出量(二色式虚血法によるイヤピース法)を測定し,次の結論を得た.1)体表面積と心拍出量の関係は女では直線性,男では体表面積の大きい領域を除いて直線性で,両直線は平行し,女の方が約0.4l上方に位置した.2)体表面積とヘマトクリットの関係は体表面積と心拍出量の関係と類似であったが,女の方が男より3-4,%低い位置にあった.3)体表面積と毎分赤血球容積(心拍出量とヘマトクリットの積)の関係は直線性で,男女が完全に重複し,このことから同一体表面積当たりの酸素供給能は男女とも変わらないことが示唆された.以上により女の心係数はヘマトクリットが少ない分だけ男のそれより多いと結論された.