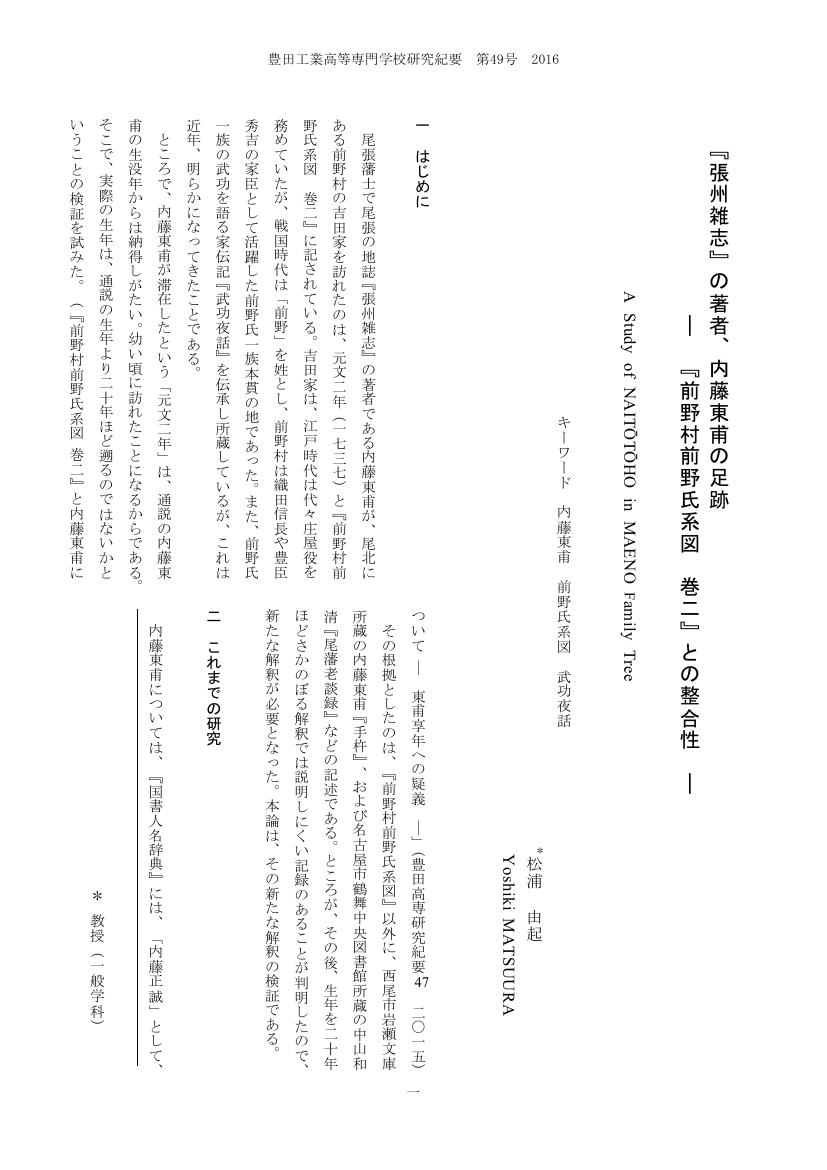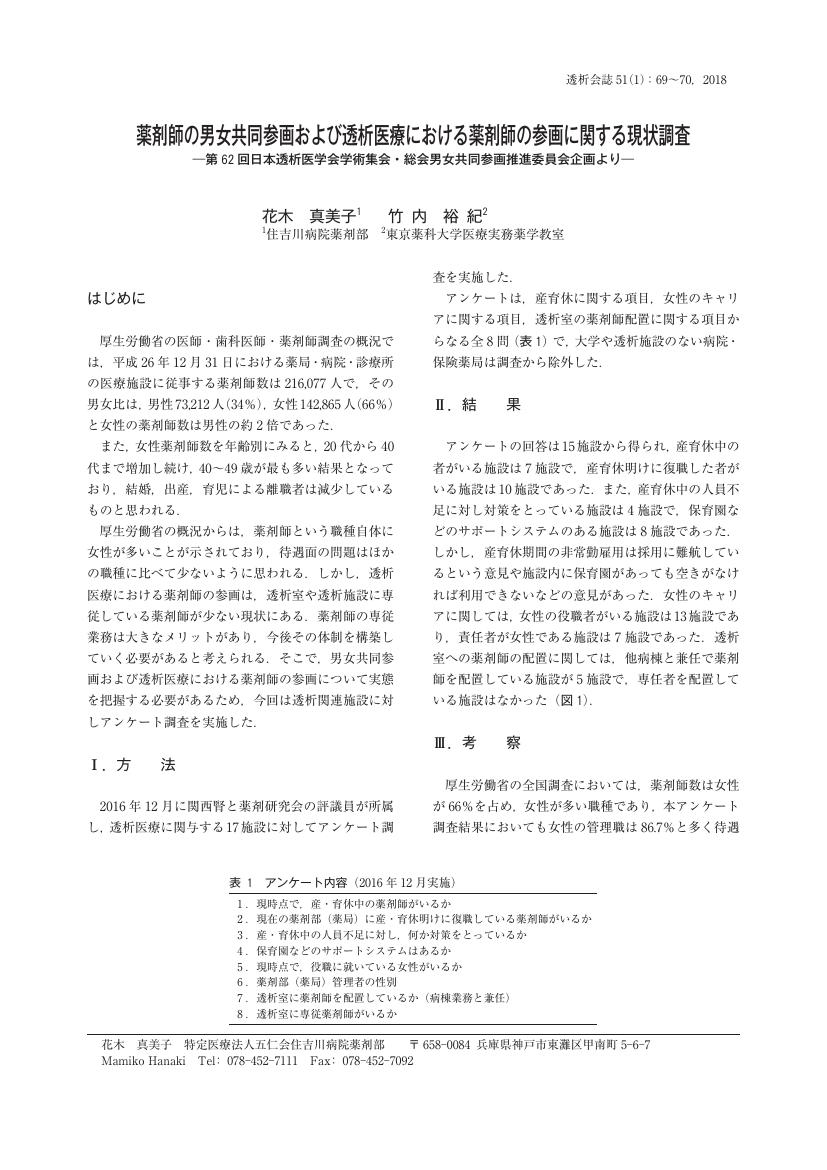3 0 0 0 OA 小麦粉の微生物がその加工食品の品質におよぼす影響
- 著者
- 梶原 景光
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.93-100, 1972-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 OA 小麦粉及び小麦粉加工品中のBacillus属について
- 著者
- 上田 成子 天野 恵里子 門田 ちはる 藤間 基朱 槇野 瑞枝 吉沢 美和子 桑原 祥浩
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.453-455, 1980-09-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
小麦粉及びその製品の微生物汚染状態を検討すると共に,汚染菌叢のうちBacillus属の同定を行なった。(1) 小麦粉の汚染菌数は一般細菌及びカビ・酵母とも全検体104/g以下であった。しかし,パン粉(乾燥及び生製品)については小麦粉と比較して汚染度が高い傾向にあり,とくに生パン粉の汚染度が高かった。(2) 小麦粉,乾燥パン粉及び調味加工小麦粉製品間には菌叢に差異がみられ,とくに調味加工小麦粉製品ではbacilliが多く,生パン粉ではグラム陽性球菌が多く検出された。(3) 各製品から分離されたBacillus spp.の同定を行なった結果, B. licheniformis, B. subtilisが最も普遍的に検出され,その他, B. cereus, B. pumilusも多くの材料から検出されたが,各製品ごとのspeciesの分布にはほとんど差がみられなかった。
3 0 0 0 OA 洞察問題解決の制約緩和における潜在的情報処理
3 0 0 0 OA 我が国における睡眠ポリグラフ検査(PSG)の現状
- 著者
- 八木 朝子
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.1-11, 2016-01-25 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 18
睡眠ポリグラフ検査(PSG)とは,脳波,顎筋電図,眼球運動,気流,呼吸運動,動脈血酸素飽和度,心電図,前脛骨筋筋電図などを終夜にわたり同時に記録する。睡眠と覚醒の区別,睡眠の質と量を評価し,睡眠を妨げる睡眠時無呼吸,周期性四肢運動障害,ナルコレプシー,てんかん発作やレム睡眠行動障害などの同定と重症度評価が可能な検査である。睡眠ポリグラフ検査(PSG)の有用性を活かすためには,映像や音声を同時に記録し,専任の臨床検査技師によるモニタリング(監視)下で行うことが求められる。しかしながら装置や設備コストや人件費がかかり,また技師の教育や技能の習得に時間がかかることもあり,実施できる施設は限られている。睡眠ポリグラフ検査(PSG)の判定結果は,各種睡眠障害の診断に直接的に寄与するため,これらを担う臨床検査技師の職務は重責である。適正かつ安全に実施し,正確に判定する能力が求められる。本稿では,睡眠ポリグラフ検査(PSG)の標準的な測定および判定について,そして我が国における普及状況について述べる。
3 0 0 0 OA 537 元慶2年(878年)相模・武蔵地震と伊勢原断層
- 著者
- 松田 時彦 由井 将雄 松島 義章 今永 勇 平田 大二 東郷 正美 鹿島 薫 松原 彰子 中井 信之 中村 俊夫 松岡 数充
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第96年学術大会(89水戸) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.667, 1989-04-25 (Released:2017-08-25)
3 0 0 0 OA N.I.グロデコフ名称ハバロフスク地方博物館所蔵の永樂通寶の化学分析
- 著者
- 中村 和之 三宅 俊彦 GORSHKOV Maxim Valerievich 小林 淳哉 村串 まどか
- 出版者
- National Institute of Technology, Hakodate College
- 雑誌
- 函館工業高等専門学校紀要 (ISSN:02865491)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.39-47, 2018 (Released:2018-01-31)
- 参考文献数
- 12
This paper reports the result of the chemical analysis of the Chinese coin Yongle Tongbao owned by Khabarovsk Regional Museum named after N.I. Grodekov. It was found that this Yongle Tongbao is the officially minted coin. This coin was excavated in Krasnokurovka burial ground in the Khabarovsk Territory. The burial ground was made under the Pokrovka culture (from the 9 th to the 13 th centuries). However the Yongle Tongbao, which was first minted in 1408, was discovered in the mound No. 30 of Krasnokurovka burial ground. So, it is necessary to reconsider the end period of the Pokrovka culture.
3 0 0 0 OA NFκBデコイオリゴの臨床開発
- 著者
- 和田 和洋 森下 竜一
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.579-589, 2010 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 37
近年,核酸医薬品が次世代の分子標的薬として注目され,様々な疾患の分子レベルでの機構解明を目的とした研究に基づき,その有効性が検証され臨床応用への期待が高まっている.DDSを適用し,目的とする臓器・組織へ送達,標的分子に作用させることにより,治療できる対象疾患が拡大されうるが,核酸医薬品の開発には,安全性および品質の確保という観点で,低分子化学合成品にはない留意点があり克服しなければならない.本稿では,NFκBデコイオリゴヌクレオチドの開発を中心に,核酸医薬品の開発上の課題とDDS技術適用の試みを紹介する.
3 0 0 0 OA バイオ後続品(バイオシミラー)の開発と今後の展望
- 著者
- 高安 義行 塚本 哲治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, no.5, pp.303-309, 2016 (Released:2016-05-13)
- 参考文献数
- 8
バイオ後続品(バイオシミラー)は,品質,安全性および有効性について,先行バイオ医薬品との比較から得られた「同等性/同質性」を示すデータ等に基づき開発される.国内では既に7剤のバイオ後続品が販売されており,バイオ後続品の開発や承認申請に関する企業側の経験も蓄積されてきている.高額な先行バイオ医薬品に比べ,薬価が低く設定されるバイオ後続品は,高騰する国民医療費の抑制策として,また,患者の医療費負担軽減策として大いに期待されており,今後,大型バイオ医薬品の特許が次々と満了することも相まって,この分野の開発競争は激化するものと予想される.一方,医療の現場におけるバイオ後続品の認知度は依然として低く,十分にその価値が発揮されるためには,国の政策に加え,開発・販売する企業がバイオ後続品に関する正しい情報を発信し,医療機関や患者と共有してくことが重要である.
3 0 0 0 OA 會津お薬手帳を用いた薬物医療情報の共有化
- 著者
- 木本 真司 河原 史明 安齊 泰裕 塩川 秀樹 鈴木 涼子 小室 幹男 市橋 淳 西郷 竹次 下山田 博久
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.563-571, 2017-08-31 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 10
目的:とくに救急医療において,地域で形式を統一したお薬手帳による薬物医療情報の共有化が必要であると考える。方法:お薬手帳に関するアンケート調査,病院薬剤師と保険薬局薬剤師が協同した協議会の発足,会津地方で統一した『會津お薬手帳』の構成検討を行った。結果:保険薬局対象のお薬手帳に関するアンケート調査では,お薬手帳のデメリットとして,「持参しない」が90.2%,「医療機関ごとに複数所持している」が85.7%であった。作成した『會津お薬手帳』は,情報共有の同意や病名等を記載する「サマリーページ」,残薬確認,医療スタッフからのメッセージ等を記載する「アセスメントページ」,過去の処方内容や変更が一目でわかる「薬歴ページ」で構成された。考察:救急医療において病名や薬剤服用歴,処方意図を把握することは重要であると考えられ,地域統一型の『會津お薬手帳』を用いての薬物医療情報の共有化が可能となることが示唆された。
3 0 0 0 OA 可換環論の50年
- 著者
- 永田 雅宜
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.157-163, 1984-05-10 (Released:2008-12-25)
3 0 0 0 OA 遺伝性痙性対麻痺の最新情報
- 著者
- 瀧山 嘉久
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.1009-1011, 2014 (Released:2014-12-18)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3
遺伝性痙性対麻痺(hereditary spastic paraplegia; HSP)は下肢の痙縮と筋力低下を呈する神経変性疾患群である.現時点でSPG1~72の遺伝子座と60を超す原因遺伝子が同定されているが,全国多施設共同研究体制であるJapan Spastic Paraplegia Research Consortium(JASPAC)により,本邦HSPの分子疫学が明らかになってきた.さらに,JASPACにより,はじめてC12orf65遺伝子変異やLYST遺伝子変異がHSPの表現型を呈することが判明した.今後,JASPACの活動がHSPの更なる新規原因遺伝子の同定,分子病態の解明,そして根本的治療法の開発へと繋がることが望まれる.
3 0 0 0 OA 『張州雑志』の著者、内藤東甫の足跡 - 『前野村前野氏系図 巻二』との整合性 -
- 著者
- 松浦 由起
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.18, 2017 (Released:2017-03-15)
3 0 0 0 OA 矢澤修次郎・伊藤毅編著『アメリカの研究大学・大学院――大学と社会の社会学的研究』
- 著者
- 宮原 浩二郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.832-833, 2009-03-31 (Released:2010-04-01)
3 0 0 0 OA 南極観測艦 新「しらせ」特集号によせて
- 著者
- 藤谷 克昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.179-179, 2010 (Released:2012-12-06)
- 著者
- Ryosuke Sakai Yoshitaka Hashimoto Emi Ushigome Akane Miki Takuro Okamura Masako Matsugasumi Takuya Fukuda Saori Majima Shinobu Matsumoto Takafumi Senmaru Masahide Hamaguchi Muhei Tanaka Mai Asano Masahiro Yamazaki Yohei Oda Michiaki Fukui
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- pp.EJ17-0414, (Released:2018-01-27)
- 被引用文献数
- 72
Skipping breakfast or irregular breakfast is associated with poor glycemic control. However, a relationship between the timing of dinner and glycemic control in people with type 2 diabetes remains indefinite. Therefore, we investigated the relationship between late-night-dinner and glycemic control in people with type 2 diabetes. We performed questionnaire survey for lifestyle factors in this cross-sectional study. We defined having dinner later than eight pm as late-night-dinner. We examined the differences in clinical and metabolic parameters between those who have late-night-dinner and those who do not have. We also examined the relationship between late-night-dinner and HbA1c, using multiple regression analysis. Ninety-five people (23.2%) had a late-night-dinner, among 409 people with type 2 diabetes. Metabolic parameters (mean (SD) or median (interquartile range)) of people with late-night-dinner were worse than those of without, including body mass index (BMI) (24.4 (4.0) vs. 23.2 (3.4) kg/m2, p = 0.006), triglycerides (1.5 (1.1–2.1) vs. 1.2 (0.8–1.7) mmol/L, p < 0.001), HDL-cholesterol (1.4 (0.4) vs. 1.6 (0.4) mmol/L, p = 0.004) and hemoglobin A1c (58.1 (13.3) vs. 55.2 (10.2) mmol/mol, (7.5 (1.2) vs. 7.2 (0.9) %), p = 0.023)). Late-night-dinner (standardized regression coefficient = 0.13, p = 0.028) was associated with hemoglobin A1c after adjusting for age, BMI, sex, duration of diabetes, smoking, exercise, alcohol, snacking after dinner, nighttime sleep duration, time from dinner to bedtime, skipping breakfast, and medication for diabetes. Late-night-dinner is independently associated with poor glycemic control in people with type 2 diabetes.
3 0 0 0 OA 薬剤師の男女共同参画および透析医療における薬剤師の参画に関する現状調査
- 著者
- 花木 真美子 竹内 裕紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.69-70, 2018 (Released:2018-01-28)
3 0 0 0 OA 記憶改善薬
- 著者
- 赤石 樹泰
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.143, no.5, pp.260-261, 2014 (Released:2014-05-10)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 氷見 徹夫 高野 賢一 山下 恵司 小笠原 徳子 正木 智之 小幡 和史 堤 裕幸 小島 隆 一宮 慎吾 澤田 典均 横田 伸一
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.239-244, 2013 (Released:2014-03-20)
- 参考文献数
- 7
粘膜防御機構は自然免疫の最前線であり,上皮細胞に加えて免疫系細胞などを含む複合的なシステムで構築されている。耳鼻咽喉科領域では扁桃・アデノイドに代表される粘膜関連リンパ装置は,その抗原捕捉機構を駆使して,免疫記憶の形成と特異的抗体産生機構に関与している。一方,上気道の最前線である鼻粘膜もまた抗原捕捉に伴う免疫反応を行っているとともに,ウイルス・細菌感染やアレルギー炎症の場としても重要である。われわれは,扁桃やアデノイド,そして鼻粘膜の上皮についての研究を行い,機械的バリアを含む自然免疫の新しい概念を提唱してきた。ここでは,われわれの研究より得られた知見をもとに,扁桃,鼻粘膜の基本的な免疫臓器としての機能解析と,それぞれの類似性・相違性,自然免疫・獲得免疫での位置づけについて言及する。
3 0 0 0 OA 最新の多発性硬化症治療
- 著者
- 吉良 潤一
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.5, pp.894-904, 2016-05-10 (Released:2017-05-10)
- 参考文献数
- 40
多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)は,若年成人を侵す神経難病では最も多く,中枢神経髄鞘を標的とする自己免疫疾患と考えられているが,証明はできていない.近年,再発や新規病巣の出現を抑制できる疾患修飾薬が次々と開発され,日本でも4種類が臨床応用されるようになった.最初の疾患修飾薬であるインターフェロンベータ(interferon beta:IFNβ)は多面的な作用機序を有し,再発抑制は30%程度に過ぎなかった.しかし,最近では切れ味のよい分子標的薬が開発され,顕著に再発は抑えられるようになった.それでもなお,障害の慢性的な進行を抑制できると証明された疾患修飾薬は開発されておらず,大きな課題として残されている.
- 著者
- 荒井 隆行
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.111-112, 2016-08-30 (Released:2017-07-04)