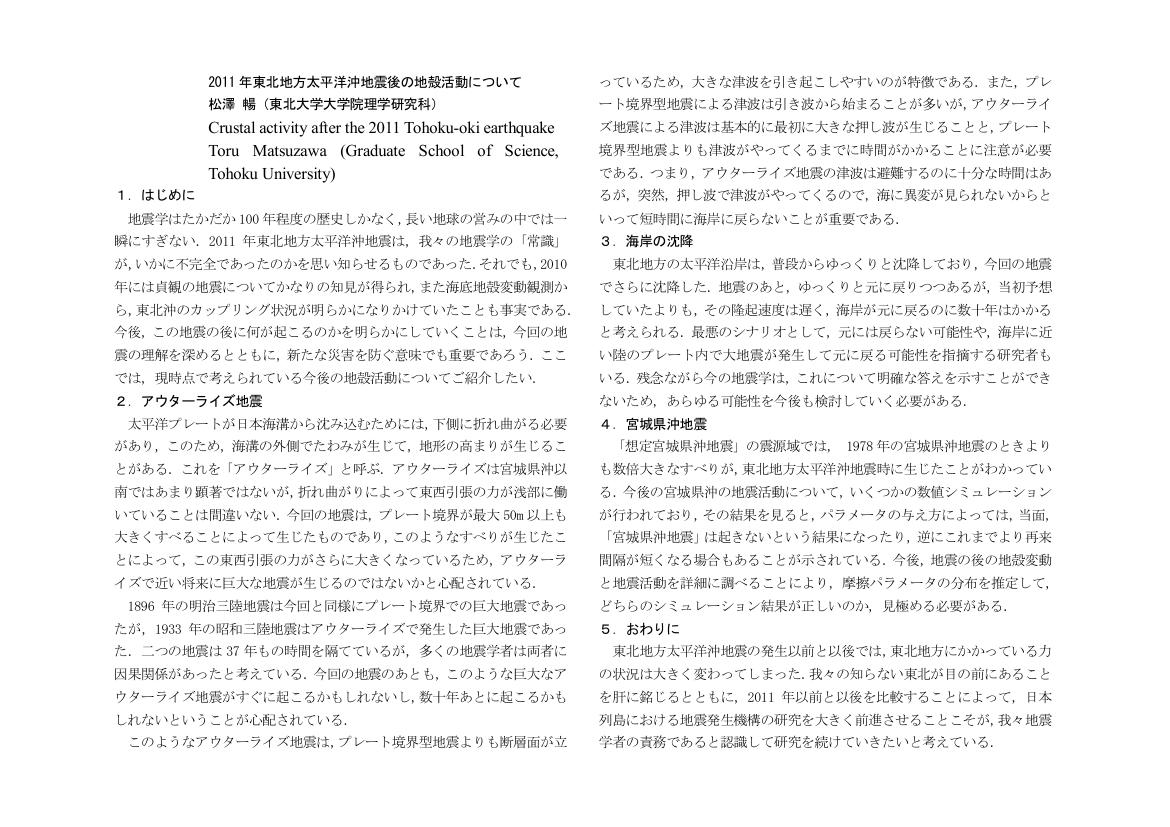1 0 0 0 OA グラフの表現論におけるKacの結果の紹介 (リー環,代数群とその周辺)
- 著者
- 谷崎 俊之
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.394, pp.34-53, 1980-08
1 0 0 0 子宮頚癌発生予防のためのHPVワクチン開発に関する基礎的研究
1.臨床応用の第一歩として・ボランチア13名にこのL2ワクチンを経鼻的に投与する第I/II相試験を行い、VLP抗体および中和抗体の上昇を確認するとともに、安全性を確認した。このL2ワクチンは、最も型共通性でかつウイルスの細胞内エントリーに最も重要な役割を有する領域のペプチドである。pacebo3名、0.1mgが5名、0.5mgが5名にアジュバントなしで経鼻接種され、0.5mgの群の4名においてHPV16とHPV52のL1/L2 VLPに対する中和抗体が誘導され、有害事象はなかった(Vaccine,2003)。2.ワクチン接種の対象者や適応・end pointを決める上でHPV感染からCIN発生、CIN進展に関わる研究を行った。HPV16/52/58のうち複数のVLP抗体を有する場合にCINになりやすく、HPVの1つの型に抗体を有しても他の型の感染やそれに引き続くCIN発生を抑制しないことを示した(J Med Vjrol,2003)。3.HPV16陽性のCINと子宮頸癌において、E6塩基配列のvariationとHLA Class II allelesを検討し、E6 prototypeではDRB1^*1501とDQB1^*0602、D25E(アジア型)ではDRB1^*1502、L83V(ヨーロッパ型)ではDQB1^*03032が有意に高頻度であった(Int J Cancer,2003)。
1 0 0 0 OA 教科教育に心理学はどこまで迫れるか(4)
企画主旨工藤 与志文 本シンポジウムは2011年から始まった同名のシンポジウムの4回目である。また,企画者の一人として,その締めくくりとしての意味合いを持たせたいとも考えている。今回のテーマは「教育目標をどう扱うべきか」である。そもそもこれら一連のシンポジウムは,学習すべき知識の内容や質を等閑視し,コンテントフリーな研究課題しか扱わない教育心理学研究のあり方に対する批判からスタートしたものと理解している。そのような問題意識の行き着く先は「教育目標の扱い」ではないか。これまでのシンポジウムで度々指摘されてきた教育心理学の「教育方法への傾斜」は,自ら教育目標の善し悪しを検討することが少ないという教育心理学研究者の研究姿勢と関連している。教育目標がどうあるべきかという問題は教育学や教科教育学の専門家が取り扱うべきであり,教育心理学はその実現方法を考えていればよいという「分業的姿勢」の是非が問われるべきではないだろうか。本シンポジウムでは,上記の問題意識をふまえ,教育心理学研究は教育目標そのものをどのように俎上にのせうるか,その可能性について議論したい。教科教育に対する心理学的アプローチ:発問をどのように構成するか藤村 宣之 教育目標に対して教育心理学がどのようにアプローチするかに関して,より長期的・教科・単元横断的なマクロな視点と,より短期的なミクロな視点から考えてみたい。 マクロな視点によるアプローチの一つとしては,各学年・教科・単元の目標を,発達課題などとの関わりで教科・単元横断的にあるいは教科や単元を連携させて設定し,それに対応させて構成した学習内容に関する長期的な授業のプロセスと効果を心理学的に評価することが考えられるであろう。その際には,学習内容にテーマ性,日常性を持たせることが教科・単元を関連づけた目標設定を行ううえでも,子どもの多様な既有知識を生かして授業を構成するうえでも重要になると考えられる。 より短期的に実現可能なミクロな視点からの関わりの一つとしては,各単元・授業単位で,どのような発問を設定して,子どもたちに思考を展開させることを考えることで,単元の本質的な内容の理解に迫るというアプローチも考えられる。当該単元の教材研究を子どもの思考や理解の視点から行うことを通じて,どのような力をその単元・時間で子どもに獲得させるか(たとえば当該単元のどのような理解の深まりを一人一人の目標とするか)を考え,それを発問の構成に反映させていくというアプローチである。 ミクロな視点からのアプローチの一つとして,子どもの多様な既有知識を発問の構成に活用し,探究過程とクラス全体の協同過程を組織することで,一人一人の子どもの各単元の概念的理解の深まりを目標とした学習方法(協同的探究学習)のプロセスと効果について,本シンポジウムでは報告を行いたい。発問の構成の方針としては,導入問題の発問としては,当該教科における既習内容に関する知識,他教科の関連する知識,日常的知識など子どもの多様な既有知識を喚起し,個別探究過程,協同探究過程を通じてそれらの知識を関連づけ,さらに,後続する展開(発展)問題の発問としては,それらの関連づけられた知識を活用して単元の本質に迫ることが,個々の学習者の概念的理解を深めるうえでは有効ではないかと考えられる。以上に関する具体的な話題提供と討論を通じて,教科教育の教育目標を対象とする教育心理学研究のあり方について考察を深めたい。知識操作と教育目標工藤 与志文 ここしばらく「知識操作」に関する研究を続けている。知識操作とは,課題解決のために知識表象を変形する心的活動のことを指す。近年,法則的知識(ルール)の学習研究において知識操作の重要性が示されつつある。ところで,同一領域に関する知識といっても,操作しやすい知識と操作しにくい知識があるように思う。西林氏の言葉を借りれば,知識は「課題解決のための武器」であるのだから,どんな武器を与えるかによって戦い方も変わってくるだろうし,すぐれた武器があれば勝算も高まるだろう。筆者は,「操作のしやすさ」をすぐれた武器の要件の1つだと考えている。雑多な知識の中からすぐれた武器となる知識を精選し,学習者がそれらを使えるように援助することは,重要な教育目標となると考えている。このような観点で教科教育を見た場合,わざわざ鈍い武器を与えているのではないかと思われる事例が少なくない。重さの保存性の学習を例に説明してみよう。 極地方式研究会テキスト「重さ」では,「ものの出入りがなければ重さは変わらない」というルールを教えている。このルールは含意命題の形式をとっているため操作が容易であり,ここから直ちに他の3つのルールを導く事ができる。①「重さが変わらないならばものの出入りはない(逆)」②「ものの出入りがあれば重さは変わる(裏)」③「重さが変わるならばものの出入りがある(対偶)」小学生がこれらのルールを駆使することで,一般に困難とされている課題に対して正しい推論と判断が可能になることが教育実践で明らかにされている。たとえば,水と発泡入浴剤の重さを測定し,入浴剤を水に入れた後の質量変化をたずねる課題では,小学3年生が重さの減少と気体の発生を関連づける推論を行うことができた(重さが減ったということは何かが出ていった→においが出ていった→においにも重さがある)。 一方,学習指導要領をみると,小3理科の目標の1つとして「物は形が変わっても重さは変わらない」ことの学習が挙げられている。教科書では,はかりの上の粘土の置き方を変えたり形を変えたりして確かめている。しかし,このルールは命題の帰結項(重さは変わらない)に対応する前提項を欠いており,含意命題の形式をとっていない。したがって,上記のような操作は不可能である。しかもこのルールは,変形して重さが変わる状況では使えない(極地研のルールでは,「重さが変わったんだから何か出入りがあったのだろう」と予想できる)。重さの保存性理解にとって,どちらの知識が武器として有効であるかは明らかではないか。本シンポジウムでは,知識操作という観点から,学習すべき知識の内容や質を問い直すつもりである。ここから,教育目標を対象にした教育心理学研究の1つの可能性を示してみたい。「学習者を異世界へいざなう教科教育の価値とは:分かったつもりから越境的交流へ」田島 充士 「学校で学んだ知識は,社会に出ると役に立たない」との言説は,今も昔も多くの人々にとって,強い説得力を持って受け止められているものだろう。学習者が学校で学ぶ知識(以下「学問知」と呼ぶ)は,実践現場で養成され活用される具体的知識(以下「実践知」と呼ぶ)と乖離する傾向にあると多くの人々によって受け止められているのは事実であり,学習者に対し,学外における実践知学習の場を提供する,インターンシップ等の実践演習型教育プログラムの実施も盛んである。 しかし教育心理学においては,この実践知習得をターゲットとした実践演習等の価値が認められる一方で,肝心の,社会実践に対する学問知教育(教科教育)の貢献可能性については,十分にモデル化されているとはいえない状況にある。本発表では,ヴィゴツキーによる科学的概念を介した発達論を基軸として,学問知が有する実践的価値を実証的に分析する理論モデルを提供することを目指す。 科学的概念とは,教科教育を通し学習される,抽象的な概念体系をともなう学問知の総体である。その特徴は,空間・時間を異にする,個々別々の具体的な文脈に孤立した実践知を,学習者自身がこの抽象体系に関連づけることで特定のカテゴリーとしてまとめ,相互の比較検証を可能にすることにある。以上のように学問知を捉えるならば,教科教育とは,異なる実践文脈を背景とし,異質な実践知を持つ,いわば異世界に属する人々との越境的な相互交流を促進する可能性を有するという点で,広く社会実践に開かれた価値のあるものだともいえる。 その一方で,教科学習においては多くの者が,授業文脈では学んだ知識を運用できるが,学外の人々との相互交流において応用的に利用することができない「分かったつもり」に陥る傾向も指摘される(田島, 2010)。これは本来,越境的交流の中でこそ活かされるべき学問知が,教室内の交流のみに,その使用が閉じられている問題といえる。つまり教科教育の問題とは,学問知そのものが社会実践に閉ざされているという点にではなく,現状では,多くの学習者がそのポテンシャルを十分に活かすことができず,学外の社会実践との関連を見出すことができないという点にあるのだと考えられる。 本発表では,以上の問題に取り組むべく,実践知との関連からみた学問知に関する理論的視座を提供する。さらに学習者を分かったつもりにとどめず,学問知のポテンシャルの活用を促進し得る教育実践の展開可能性についても検証する。その上で,学習者を異世界へいざなうという学問知の強みを活かした教科教育の社会的価値について論じる。
1 0 0 0 OA ニューヨーク近代美術館「日本家屋展」に見るキュレーターの役割
- 著者
- 山崎 泰寛 松隈 洋
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.688, pp.1441-1446, 2013-06-30 (Released:2013-08-30)
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study is to clarify the role of curator through Arthur Drexler's works on exhibition “Japanese Exhibition House” in the Museum of Modern Art, New York. This study focuses on his preparation of the exhibition, relationships to contributors, and requirements to the architect. Through this study, his role as a curator becomes clear in following points: 1. Thorough research based on on-site observation, 2. Persuasive financial management. 3. Respectful discussion with architect.
- 著者
- 大庭 一郎
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 図書館学会年報 (ISSN:00409650)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.p11-39, 1994-03
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 植物由来食成分(フィトケミカル)の乳癌及び大腸癌に対する抗癌作用の機序解析
フィトケミカルの抗癌作用の分子機序を異なったサブタイプの乳癌細胞で解析するとともに、一次予防へ応用可能かどうかをEMS誘導乳癌モデルラットで検討した。用いたフィトケミカルはイソフラボン、クルクミン、リコペン、ノビレチン、レスベラトロールで、すべて乳癌細胞に抗癌作用を示した。その分子機序はフィトケミカルによって異なるが、増殖とアポトーシスに関連する細胞内シグナル蛋白に働き、増殖抑制とアポトーシス誘導により発揮されることが判明した。動物モデルではイソフラボンやリコペンは乳癌発症を抑制することがわかった。フィトケミカルは乳癌の一次予防に効果があるだけでなく、癌の増殖・進展を抑制する可能性がある。
1 0 0 0 OA 2011年東北地方太平洋沖地震後の地殻活動について
- 著者
- 松澤 暢
- 出版者
- The Geological Society of Japan
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.005, 2013 (Released:2014-04-01)
1 0 0 0 撥水フロントガラス上での水滴のリアルタイムアニメーション
- 著者
- 仲田 将之 柿本 正憲 西田 友是
- 雑誌
- 研究報告グラフィクスとCAD(CG)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.5, pp.1-5, 2012-06-15
ウィンドシールド上の水滴の CG アニメーション手法は,レースゲームや自動車のシミュレータでの特殊効果としてすでに使用されている.これまでのアニメーション手法は,親水表面であるガラスを考慮して水滴が流れに沿って濡れ広がることを想定したものだった.一方,自動車分野ではワイパーに加えて撥水フロントガラスを使用してドライバーの視認性を改善する方法が普及してきた.撥水ガラスに付着した水滴の振る舞いは,普通の親水ガラスでのそれとは異なる.本論文では,フロントガラスの撥水性を考慮した水滴のリアルタイムアニメーション手法を提案する.提案法では各水滴を質点として記述し,動的撥水性や重力,空気抵抗などの外力を考慮してシミュレーションを行う.ガラス表面にはそれと同時に霧雨と同程度の粒径を持つ水滴が多数付着しており,しかもこのサイズの水滴は外力の影響を受けにくく静止しているため,一枚の画像として扱う.水滴の移動によって撥水表面が綺麗になる現象 (ロータス効果) も可視化する.本論文では,提案法に基づいて走行する自動車のフロントガラスに付着した水滴のアニメーションが可能なことを示す.Animation of water drops on a windshield is used as a special effect in advanced driving games and simulators. Existing water droplet animation methods trace the trajectories of the droplets on the glass taking into account the hydrophilic or water-attracting nature of the glass material. Meanwhile, in the automobile industry, usage of hydrophobic glass windshields has recently been a common solution for the drivers'clear vision in addition to cleaning the water with wipers. Water drops on a hydrophobic windshield behave differently from those on a hydrophilic one. This paper proposes a real-time animation method for water droplets on a windshield taking account of hydrophobicity. Our method assumes each relatively large droplet as a mass point and simulates its movement using contact angle hysteresis accounting for dynamic hydrophobicity as well as other external forces such as gravity and air resistance. All of a huge number of still, tiny droplets are treated together in a normal map applied to the windshield. We also visualize the Lotus effect, a cleaning action by the moving droplets. Based on the proposed simulation scheme, this paper demonstrates the motion of the virtual water droplets on the windshield of a running vehicle model.
表現の自由と個人の人格権は共に、憲法で保証された基本的人権であり、その対立の調整は極めて慎重でなければならない。刑事事件報道における被疑者・被告人の人権と表現(報道)の自由との衝突に関する事例研究を行った。ケーススタディとして、1981年に逮捕され95年に無罪が確定した大分・みどり荘事件の輿掛良一さんの報道被害、94年6月の松本サリンでの河野義行さんに対する捜査とメディアによる人権侵害、米国アトランタ・五輪公園爆弾事件の第一通報者リチャード・ジュエルさんの事例を取り上げた。日米の犯罪報道を比較研究した。また、神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件、東京電力社員殺人事件などでの被害者のプライバシー侵害問題も調査した。少年事件での実名・顔写真の掲載、文藝春秋の少年供述調書の掲載などが相次いだことで、これらの少年法違反の取材・報道に関して、現場記者、捜査当局者、一般市民などから聞き取り、アンケート調査を実施した。その結果、取材記者は警察情報にほぼ依存しており、捜査当局の監視機能は働いていないことが分かった。報道現場で犯罪報道の構造を改革を求める声が強いことも分かった。人権と報道のテーマは、97年8月末に起きたダイアナ元英皇太子妃の事故死で、世界的な問題となった。ジュエルさんと対メディア訴訟の代理人であるワトソン・ブライアント弁護士が97年10月に来日、二人から詳しく当時の事情を聞いた。さらに北欧、英国など諸外国の事例との比較も検討した。放送界でもNHKと民間放送連盟が97年6月に苦情対応機関、「放送と人権等権利に関する委員会機構(BRO)を設置.BROは98年3月に米サンディエゴ教授妻娘殺人事件報道に関して初の見解書を発表。プレスにおいては新聞協会が協力しないために、新聞労連が独自で98年3月に報道被害相談窓口をスタートさせた。日本に生まれつつあるメディア責任制度の問題点を明らかにして、その解決方法を提示した。
1 0 0 0 OA 人間学としての英語教育 : 30余年の実践をふり返る
- 著者
- 玉城 康雄
- 出版者
- 沖縄国際大学
- 雑誌
- 沖縄国際大学外国語研究 (ISSN:1343070X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.1-13, 2005-03-29
1 0 0 0 OA ホーソン実験の真相 ―リレーアセンブリテストの実際―
- 著者
- 大橋 昭一 Ohashi Shoichi
- 出版者
- 關西大學商學曾
- 巻号頁・発行日
- 2006-08-25
商学部創設100周年 商学会設立50周年 記念特集
- 著者
- 斉藤 豊治
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法の科学 : 民主主義科学者協会法律部会機関誌「年報」 (ISSN:03856267)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.195-197, 2014
1 0 0 0 OA IV.HIV感染症とエイズの診断基準
- 著者
- 味澤 篤
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.11, pp.2767-2773, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 12
HIV感染症は,抗体+抗原による第4世代のスクリーニングキットが使用されるようになって,感染後2~3週間で陽性が判明するようになった.しかしスクリーニング検査では必ず偽陽性が生じるので,確認検査としては,WB法+RT-PCR法が用いられている.WB法は急性感染期には陰性となってしまうために,RT-PCR法でのHIV-RNA量測定が必要となる.一方AIDSは,HIV感染者が,エイズ動向委員会で定められた23の疾患もしくは状態と判定された場合に診断される.
1 0 0 0 OA P-27. 扁桃炎をきっかけに判明したHIV感染症の2症例
- 著者
- 山口 宗太 大木 幹文 大久保 はるか 石井 祥子 櫻井 秀一郎 大越 俊夫
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.137-137, 2008-08-10 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 IR 終末期ケアに関する啓発活動への高齢者の関心と規定要因
- 著者
- 松井 美帆 森山 美知子
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.65-74, 2004-09-17
- 被引用文献数
- 4 5
本研究の目的は、終末期ケアの啓発活動への高齢者の関心とその規定要因を明らかにすることである。対象は中国地方の老人クラブ会員258名で、医療保健専門家による終末期ケアに関する教育講演については58.9%に関心がみられた。関連要因として年齢があり、前期高齢者に関心が高い傾向であった他、終末期ケアに関する家族や医療従事者との話し合いをはじめ、かかりつけ医の有無、家族機能、手術経験などが関連していた。一方、延命治療の意向では医師や家族に判断を任すとした非自己決定群が58.6〜61.1%であり、リビング・ウイルをよく知っているものは12.2%であった。以上のことから、前期高齢者の世代から家族や医療従事者との関係に配慮した上で、自分の意向を事前に周囲と話し合っておくことやアドバンス・ディレクティブについて啓発活動を行なうことの重要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 書評
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.409-412, 1959-03-31 (Released:2010-07-16)
1 0 0 0 学区で取り組む品性教育の研究者による支援と成果・問題点の分析
東京都のA区が取り組み始めた人格の完全を目指した品性・品格教育を、研究者で支援するのが本研究の目的である。本研究の3年間の目的は、(1)品性・品格教育の全国初の実践に向けて、取り組みの理念や教育的意義を、教員や保護者に向けて正確に伝えるため、教育委員会の活動を支援すること、(2)品性に関する教育の成果を、well-beingとの関係を中心にアンケートで調査し、この取り組みをエビデンス・ベースの展開にすること、(3)アメリカで教員達に品性・品格教育を教え、全米で学校を支援しているボストン大学の先生をお招きし、A区の品性・品格教育にコメントしていただき、旧来の教育と違った新しい視点を取り入れることである。本年度はまとめの年なので、(1)、(2)を中心に行った。(1) 地域の保護者向け講演会、校内研修会、教育委員会主催の研修会等で、交通費、講演料なしの講演を行い、全区実施に向けて教員研修等のお手伝いをした。また、教育委員会は、全学区で使用する教師用手引き書を作成したが、これを作成する際、知識提供、翻訳した資料の提供を行った。(2) アンケート調査は、A区が取り組みを始める前の段階から毎年、2月に調査を行っている。今回で4回目のアンケートを実施した。3回目までのまとめは、アンケートに協力してくださった学校と教育委員会にお伝えした。この分析の結果、規範意識は確かにwell-beingと関わっているが、その教育の成果の様相は内容(根気、活力、寛容など)によって多様であることが窺えた。(3) 昨年のボストン大学の教授による講演の逐語録をまとめ、多くの方に配布できるようにした。
1 0 0 0 OA 農地の放射能汚染マップ作成モデル事業による風評対策と損害構造の解明
農地の汚染マップは、避難指示や解除、除染、農業対策などに関して、分野横断的に活用できる政策立案の基礎資料となる。生活圏における放射線量が可視化されたマップは、地域住民が、今の暮らしの中で少しでも外部被ばくを減らす方法を考える判断材料として用いることができる。実態調査を行うにあたっては、①復興庁が総合的な管理を行う、②被害レベルが高い地域から順次作成、③被害レベルに応じて更新頻度を設定、④経費を抑えた簡易な手法を採用し予算確保、⑤実測は行政・研究機関・民間企業・地域住民の持てる力を最大限活用することが重要である。
1 0 0 0 OA ニーズとライフスタイルを踏まえた吃音がある中学・高校生の教育・支援方法の開発
多様な教育・支援ニーズがあり、勉学や部活動などで多忙な吃音のある中学・高校生の実情にあった教育・支援方法について、(a)「吃音のある中高生のつどい」の実施、(b)「吃音スタディーブック中高生版」の開発をした。「吃音のある中高生のつどい」は勉学や部活動などの影響が最小限となる夜間や休日に、2014年度に6回、2015年度に5回実施し、毎回1~7名の参加があった。「吃音スタディーブック中高生版」は、中高生が興味を持って取り組めるように、タブレット端末などを用いるマルチメディア自学教材とし、吃音の基礎知識クイズ、吃音動画クイズ、吃音の中高生へのメッセージ(吃音との付き合い方の提案)で構成された。