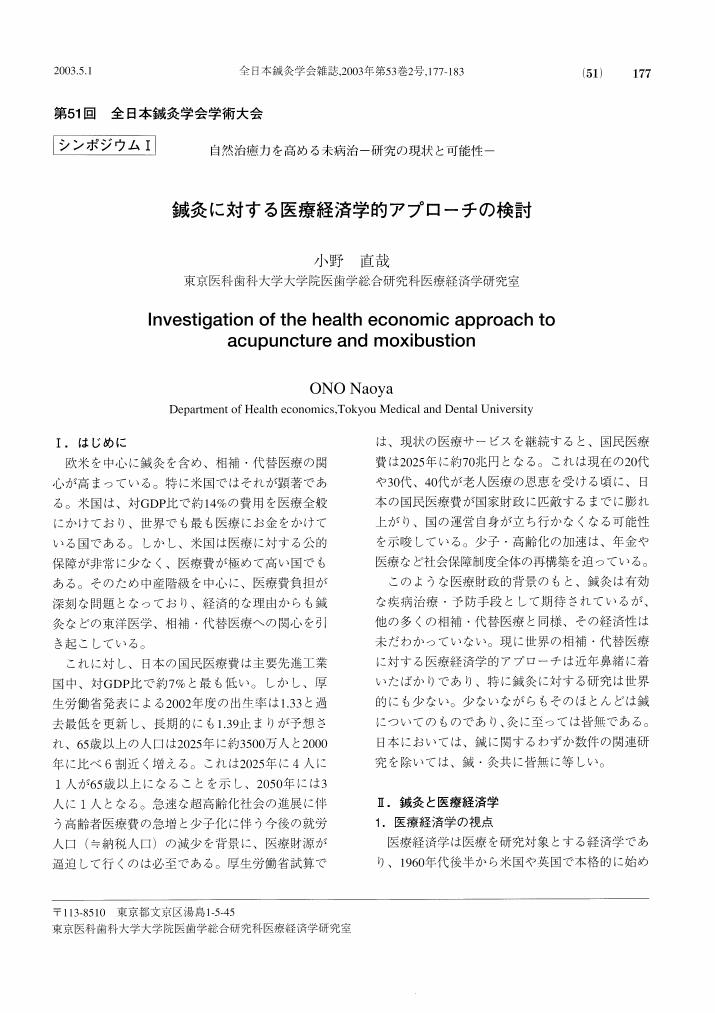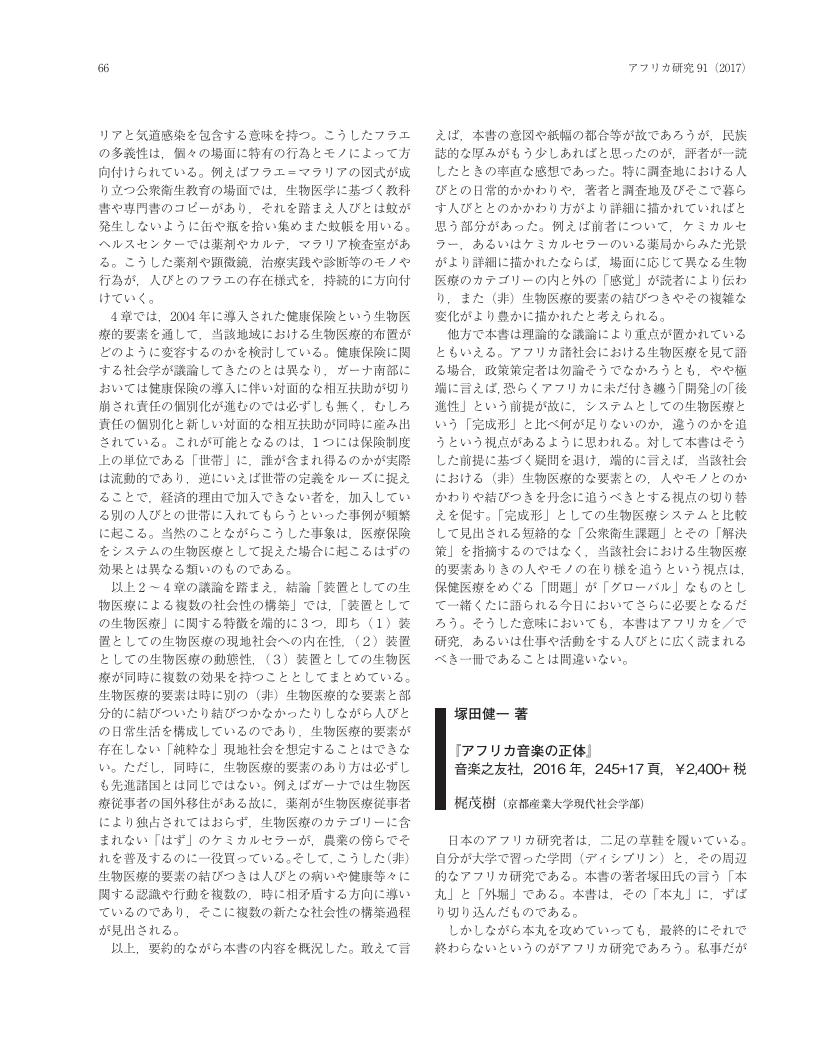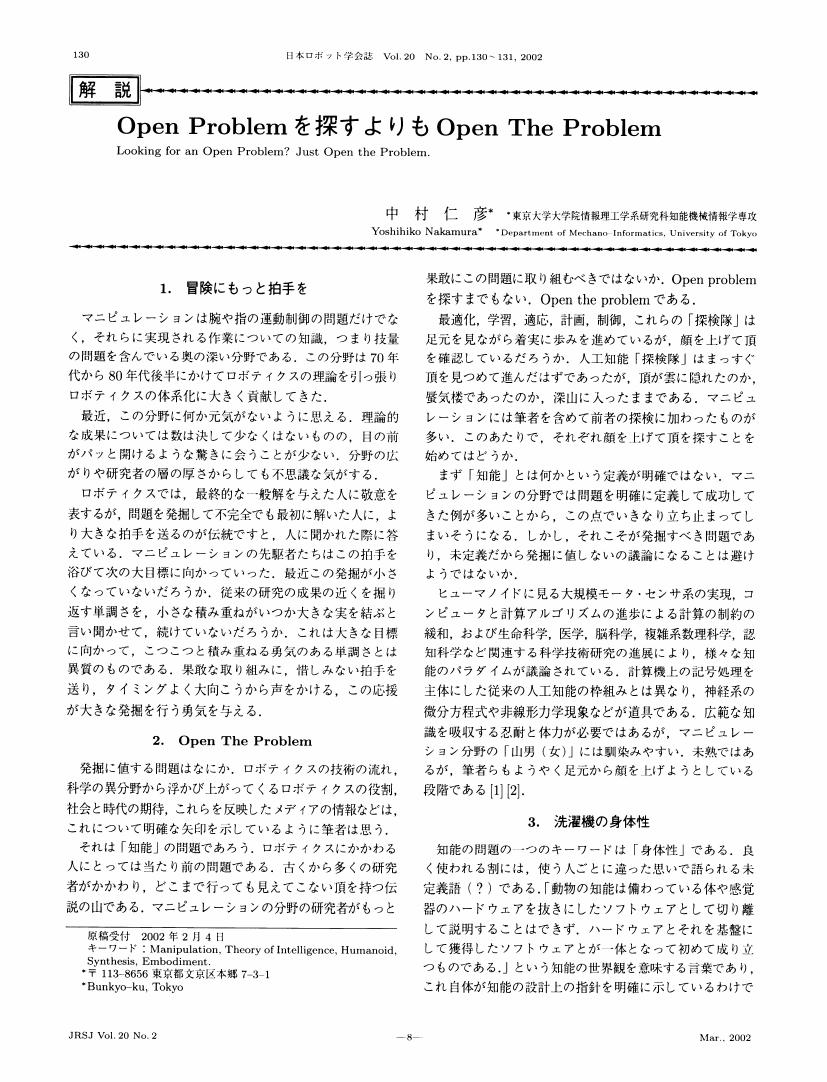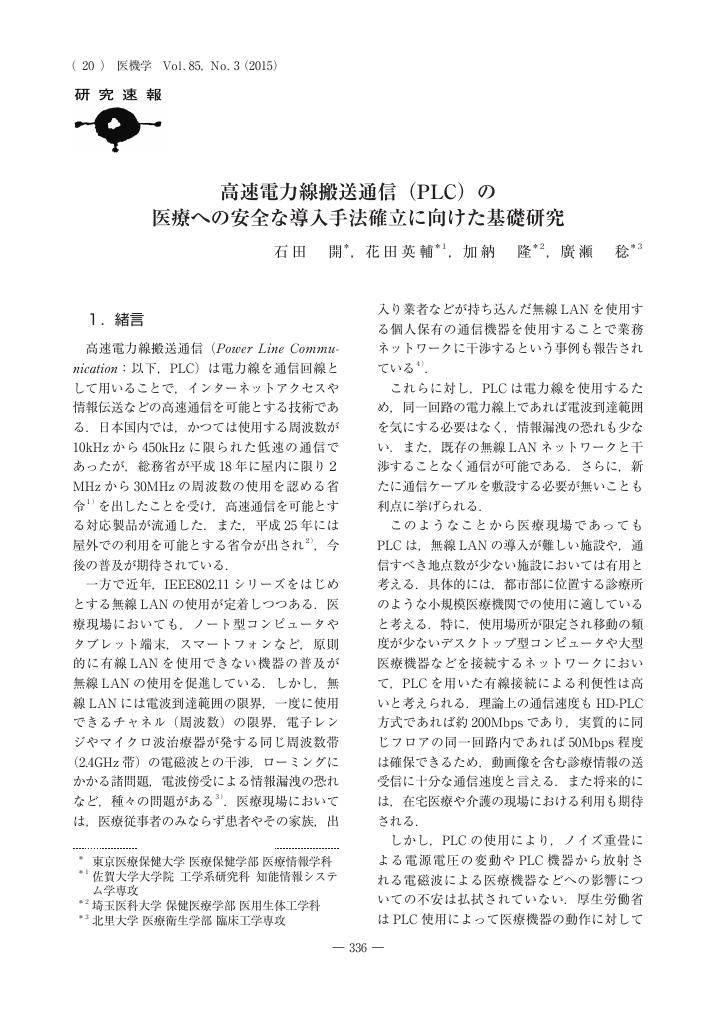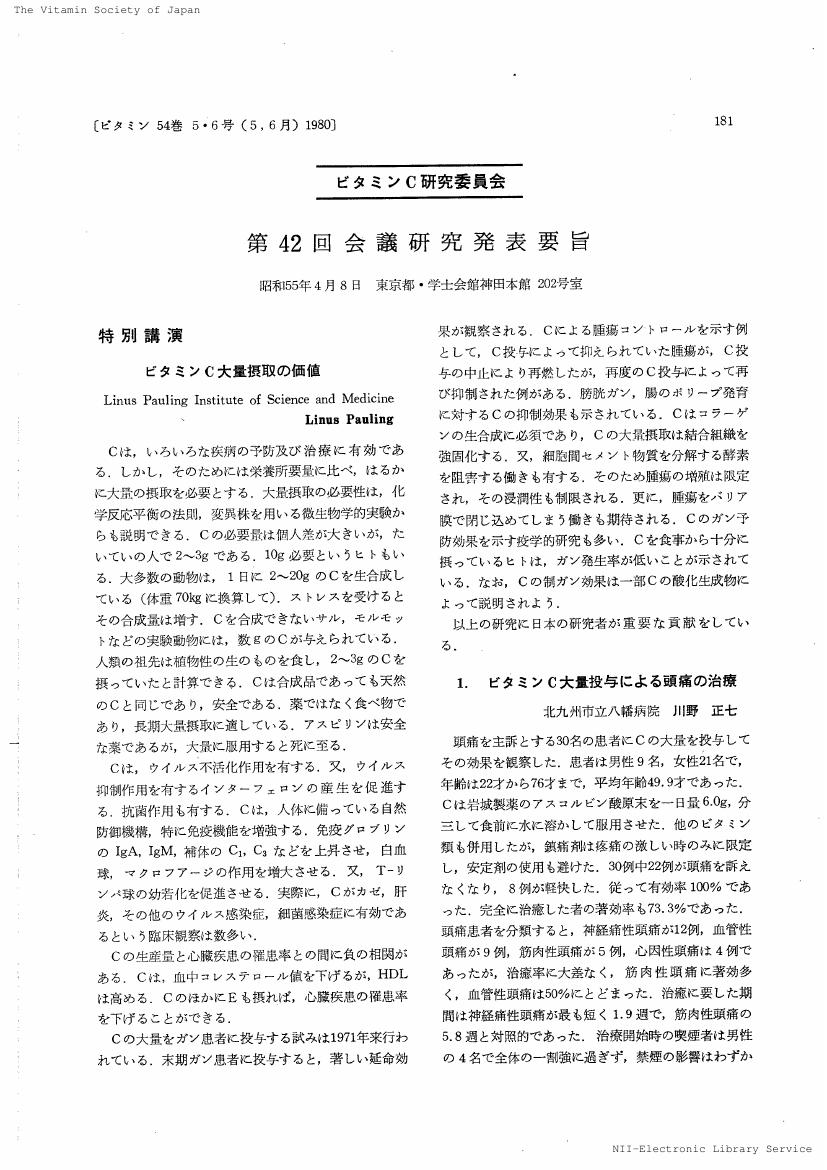2 0 0 0 OA 井川壽子著『イベント意味論と日英語の構文』東京:くろしお出版,2012,x + 202頁
- 著者
- 衣畑 智秀
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, pp.75-79, 2017 (Released:2017-04-12)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 岩橋 勝
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.621-623, 2013-02-25 (Released:2017-06-10)
2 0 0 0 OA 高度情報社会と文化変容
- 著者
- 中野 収
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.308-318,383, 1984-12-31 (Released:2009-11-11)
- 被引用文献数
- 1 1
社会の情報化に伴って、文化の各領域での変容が進行する。しかし、情報化は必ずしも原因ではない。文化の変容によって情報化が進行し、情報化が文化変容を促す。というか、むしろ、情報化と文化変容は、産業社会の変動のふたつの側面なのである。'60年代以降、人々の生活様式の変化が著しい-衣食住の形から社会的移動のパターンまで。特に、テレビの普及にはじまるさまざまなメディアの生活への浸透は、社会や生活の中での人間の条件を変えてしまった。人々は孤立し、メディアを擬人化し、メディアに知識情報を求めなくなった。この現象は、いわゆる価値の多様化と併行して進行した。さまざまな社会的規範が弛緩し、価値の多様化が進み、社会的逸脱が常態化した。その結果、社会的表象を解読するコードが、不安定になり、流動化した。こうした社会的規範の極度に弛緩した時代に、文化創造は、どのような形で、いかにして可能なのだろうか。新しい生活様式は、明らかに文化の創造であった。たしかに、, 60年代は文化的に多産な時期であった。しかし、現在、音楽、絵画、文学、映画、演劇における創造の主要な形態は、引用と模倣と剽窃とパロディにとどまっており、創造の名に値する創造は、極めてマイナーな領域で行われているにすぎない。
2 0 0 0 OA 鍼灸に対する医療経済学的アプローチの検討
- 著者
- 小野 直哉
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.177-183, 2003-05-01 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 ブレスト・アウェアネス 乳房の健康教育
- 著者
- 植松 孝悦 笠原 善郎 鈴木 昭彦 高橋 宏和 角田 博子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本乳癌検診学会
- 雑誌
- 日本乳癌検診学会誌 (ISSN:09180729)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.27-33, 2020 (Released:2020-04-06)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
自覚症状のある乳癌の早期診断は,その乳癌患者の予後と生存率を改善させる。そのためには,乳癌の初期症状を早く自覚して速やかに医師を受診するという乳房の健康教育の普及が重要であり,この正しい保健医療行動が確実に進行乳癌の減少をもたらす。ブレスト・アウェアネスは,乳房を意識した生活習慣を通して,乳房に変化を感じたら(乳癌の初期症状を早く自覚する)速やかに医師を受診するという正しい保健医療行動をとるための健康教育であり,乳がん検診の理解とその受診勧奨を目的とした啓発活動である。ブレスト・アウェアネスを実践することで,マンモグラフィ偽陰性の場合でも,早期に乳癌を発見し速やかに診断と治療が可能となる。つまり,ブレスト・アウェアネスの普及が,対策型乳がん検診の高濃度乳房問題に対する具体的な対応策の一つである。さらにブレスト・アウェアネスの推奨は,若年性乳癌の早期発見のための具体的な方策にもなる。ブレスト・アウェアネスは乳がん教育を実践するための具体的なキーワードであり,これから教育現場で行われるがん教育でも積極的に取り入れられるべき内容と思われる。ブレスト・アウェアネスの普及に器機の整備や購入の必要性はない。よって,その体制を整えることは比較的容易であり,速やかに全国一律で実施することが可能である。ブレスト・アウェアネスは,効率的かつ効果的な乳癌対策であり,乳がん検診と並ぶもう一つの乳癌医療政策の柱として,わが国も積極的に導入すべきである。
2 0 0 0 OA 338絵本における色の三原色混合率の抽出
- 著者
- 伊勢田 知子 松前 祐司 岩崎 晴美 斎藤 兆古 堀井 清之
- 出版者
- 社団法人 可視化情報学会
- 雑誌
- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1Supplement, pp.291-294, 2000-07-01 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 7
The colors on picture books by Dick Bruna have been analyzed by using computer.Fundamental colors including red, blue and green specified by Bruna himself are revealed to be not pure fundamental colors. These picture books have taken reposeful colors that mixed one fundamental color to another fundamental one. The thread of narrative is made a development along the changes of these reposeful colors that increases the charm of picture books by Bruna.
- 著者
- 梶 茂樹
- 出版者
- 日本アフリカ学会
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.91, pp.66-69, 2017-05-31 (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 女性の顔面部皮下脂肪の分布解析
- 著者
- 佐藤 真由美 森 忍 吉塚 直伸 武馬 吉則
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.125-130, 2004-06-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 8
女性の顔の形状に関しての美意識は高く, 形状を形づくるものとしては骨格や筋肉, 皮下脂肪が関わっていると考えられる。そこでわれわれは, MRI法 (核磁気共鳴映像法) を用いて女性の顔面における皮下脂肪を計測し, 皮下脂肪の分布と体型との関係について実態解析を行ったので報告する。健常女性38名を, 痩身体型10名・正常体型18名・肥満体型10名に分け, 頭部MRI撮影を行った。撮影条件は, 脂肪を映すのに適したT1強調で撮影した。MRI画像の顔面皮下脂肪面積は, 肥満体型, 正常体型, 痩身体型の順で多かった。さらに, 顔面45ヵ所の皮下脂肪厚を計測した結果, 頬部の鼻側は体型にかかわらず皮下脂肪量が多い部位であったが, 咬筋部と下顎骨部周辺の皮下脂肪量はBMI (Body Mass Index) が高くなるに伴い増大した。すなわち, 体型にかかわらず皮下脂肪が存在する部位と, BMIの増加に伴い蓄積していく部位があることが示唆された。
2 0 0 0 OA Open Problemを探すよりもOpen The Problem
- 著者
- 中村 仁彦
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.130-131, 2002-03-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 久米 亮一
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.151-158, 2017-07-01 (Released:2018-07-18)
- 参考文献数
- 3
我々は,退院後の装具のメンテナンスや作り替えを専門分野と位置づけ15年に渡り取り組んできた.地域には「歩容の崩れ」,「足部の変形」,「装具の不適合」が多く存在し,今までの知識や技術,考え方では解決できない問題点に気づくことができた.装具について,自宅での未使用などが引き起こす不適合,介護保険非対象者がおかれる状況,老人保健施設における必要性,在宅ケアの実情などの「環境的問題」,および制御力の小さい短下肢装具のリスク,製作の遅れのリスク,装着練習の大切さ,予備の装具の重要性などを整理する.そして現在行っているケアマネジャーやセラピストとの連携や,講演活動によって地域環境に対する直接アプローチを紹介する.
2 0 0 0 OA 高速電力線搬送通信(PLC)の医療への安全な導入手法確立に向けた基礎研究
- 著者
- 石田 開 花田 英輔 加納 隆 廣瀬 稔
- 出版者
- 一般社団法人日本医療機器学会
- 雑誌
- 医療機器学 (ISSN:18824978)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.336-342, 2015 (Released:2015-09-11)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 「人間性心理学研究」の査読についての簡潔な報告
- 著者
- 泉野 淳子
- 出版者
- 心の諸問題考究会
- 雑誌
- 心の諸問題論叢 (ISSN:13496905)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.17-26, 2009 (Released:2009-07-14)
- 参考文献数
- 18
本報告は、約10年前「人間性心理学研究」に投稿して審査を受けた際の体験を一事例としてまとめたものである。その審査のあり方は首を傾げたくなるようなものだった。審査者たちの評価基準は投稿論文審査内規に沿った一貫性あるものとは思われず、一人の審査所見には明白な誤りさえ含まれていた。論文は、戦後日本の教育界や臨床心理学界に多大な影響を与えたC.R.ロジャーズとキリスト教の関係を論じたものであった。その主張はおそらく日本のロジャーリアンの主流の見解に合わないものだったのであろう。ある審査者は内容を理解しかねているようであった。このような過去のことを今になって取り上げる理由の一つは、時間を経たことによって冷静に自分の論文および審査所見を読み、客観的に吟味できるようになったためである。うまく機能しなかった実例を検討することは、審査制度を改善していくためにも大切なことであると考える。
- 著者
- Hiroshi Kadowaki Hiroshi Akazawa Junichi Ishida Issei Komuro
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.9, pp.1446-1453, 2020-08-25 (Released:2020-08-25)
- 参考文献数
- 58
- 被引用文献数
- 10
Improvements in the long-term survival of cancer patients have led to growing awareness of the clinical importance of cancer therapeutics-related cardiac dysfunction (CTRCD), which can have a considerable effect on the prognosis and quality of life of cancer patients and survivors. Under such circumstances, onco-cardiology/cardio-oncology has emerged as a new discipline, with the aim of best managing cardiovascular complications, including CTRCD. Despite the recent accumulation of epidemiological and clinical information regarding CTRCD, the molecular mechanisms underlying the pathogenesis of CTRCD by individual drugs remain to be determined. To achieve the goal of preventing cardiovascular complications in cancer patients and survivors, it is important to elucidate the pathogenic mechanisms and to establish diagnostic strategies with risk prediction and mechanism- and evidence-based therapies against CTRCD.
2 0 0 0 OA 明治初期の勇払基線と苫小牧の発展
- 著者
- 加藤 芳夫
- 出版者
- Japan Cartographers Association
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.11-16, 1978-12-10 (Released:2011-07-19)
本稿は, 第9回国際地図学会議 (53年7月, ワシントンD. Cメリーランド大学) のために, 国際地図情報センターから提出されたThe First Systematie Base-line and Triangulation Survey in Japan-Yufutsu Base-line Survey in Hokkaido in 1873-をもとに, この基線測量からすでに一世紀を経過した苫小牧の変遷を, 国土地理院の5万分の1地形図によって概観し, 特に戦後, 内陸堀込港湾の造成によって急速なテンポで変貌しているこの地域の様相を描いてみたい。本号の添付地図は, 明治8年開拓使による「三角術測量北海道之図」及び「北海道三角術測量有仏基線之図」であり, 同国際会議に提出したものと同様のものである。国際地図情報センターから筆者への要請は, アメリカで開かれる国際会議であるだけに, 日米の国際親善及び国際交流のための橋渡しの一助となればという意図によるものであった。従って, この古地図の複製にあたっても, 古地図としての歴史的な意義を解明することを目的とするものではなく, より一般的に明治初期の開拓使時代における偉大な事業のひとつとして紹介したものである。
2 0 0 0 OA 観光地における新型コロナウイルス(COVID-19)感染予防策
- 著者
- 倉橋 節也 永井 秀幸
- 出版者
- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
- 雑誌
- 横幹連合コンファレンス予稿集 第11回横幹連合コンファレンス
- 巻号頁・発行日
- pp.A-3-4, 2020 (Released:2020-11-21)
This paper implements the infection process of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) in an agent-based model and compares the effectiveness of multiple infection prevention measures for a tourist area. In the model, 3200 virtual residents agents live in nine towns where they commute to office or school and visiting stores. The model simulates an infection process of local residents by tourists who regularly own in. The results of the experiments showed that individual infection prevention measures alone or partially combined them do not produce significant effects.
2 0 0 0 OA 燃料電池の原理と特徴
- 著者
- 津島 将司 平井 秀一郎
- 出版者
- 一般社団法人 スマートプロセス学会 (旧高温学会)
- 雑誌
- 高温学会誌 (ISSN:03871096)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.224-230, 2009-09-20 (Released:2012-10-16)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
Fundamentals of fuel cells including polymer electrolyte fuel cell (PEFC), phosphoric acid fuel cell (PAFC), alkaline fuel cell (AFC), molten carbonate fuel cell (MCFC) and solid oxide fuel cell (SOFC), are presented. Three types of overpotential, activation overpotential, ohmic overpotential and concentration overpotential, are described. Polarization curves in PEFC and SOFC are also presented for better understanding of dominant factors that determine overall cell performance.
2 0 0 0 OA 1.ビタミンC大量投与による頭痛の治療 : ビタミンC研究委員会第42回会議研究発表要旨
- 著者
- 川野 正七
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5-6, pp.181-182, 1980-06-25 (Released:2018-03-07)
2 0 0 0 OA ジャスト イン タイムと経済地理学
- 著者
- 野尻 亘
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.471-492, 2002-10-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 130
- 被引用文献数
- 1 1
Since the mid 1980's, many Western economic geographers, especially in new industrial geography, have shown great interest in the Just-in-Time system (JIT). The core of their interests is not in the problem of logistics, but rather in the definition of the JIT in the Regulation Approach and its spatial implications from the viewpoints of labour control and subcontracting.Regulationists, Lipietz and Leborgne have considered the JIT is a part of the process leading to Post-Fordism, because the JIT is different from Fordism and Taylorism, workers on shop- floors can participate in quality control, partially improve their working conditions, and engage in multiple working process. Accordingly, they say the JIT raises functional flexibility in the firm and effectively orders subcontractors to enhance numerical flexibility. So, they have boldly set forth the hypothesis that the introduction of the JIT will make the region surrounding the assembler an ideal democratic society of Post-Fordism. In that place, regional society consists of consensus and collaboration of workers, managers, various scale corporations, labour unions, and other social institutions for the purpose of administration, education, investigation, and welfare.However, many new industrial geographers have criticized this hypothesis from theoretical perspectives and results based on examplary studies, especially about the case of Japanese automobile factories transplanted in the West. In conclusion, they say the JIT is not Post-Fordism, but has rather strengthened the regime of Fordism and the mass production system. In other words, it can be defined as Neo-Fordism, Neo-Taylorism, ‘structured flexibility’, or quasi-vertical integration which aims to effectively utilize both the merits of in-house production and contracting out to subcontractors.Therefore, many new industrial geographers have debated about the spatial implications of the JIT, namely whether the JIT causes agglomeration of suppliers around the assembler or not.First, the overarching spatial tendency is towards some form of agglomeration through the introduction of the JIT, because of the need for suppliers to be proximate to assemblers to deliver frequently, smoothly exchange information about quality control and development of new products, and reduce their transaction costs.Second, the JIT is not necessarily accompanied by agglomeration because of rapid development of transportation and communication between assemblers and suppliers. The restriction according to the laws of local contents makes the assembler order existing suppliers. In the case of standard parts, the supplier can concentrate production in one factory to pursue scale economics and deliver to each assembler. The suppliers also prefer to locate in rural areas, a little away from large assemblers to avoid the rise of labour costs and reinforcement of the labour movement.In the latter half of the 90's, Boyer, a Regulationist, has insisted that the accumulation regime has not unilinearly evolved from Fordism to Toyotism (JIT) or Volvoism in Sweden. He has allegedly criticized the doctrine of the convergence of a single social system of production. These models are not exclusive alternatives but rather coexisting multiple hybrid models. Therefore, it will be necessary to elucidate how the path-dependency or historical contingency of individual firms, especially Japanese transplants and major first-layer suppliers in the West, and conventions, institutions, and cultural backgrounds in Japan or the West affects the embeddedness of the JIT in the region and the spatial structure of industrial organization.In the results, some economic geographers, for example, Lung or Sadler, have insisted that there are no necessary conditions on spatial form of production owing to the introduction of JIT. It causes the decline of geograpohical studies about the JIT since the latter half of 90's.
2 0 0 0 OA 同位体の発見と分類,その利用について(同位体の化学)
- 著者
- 熊本 卓哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.70-73, 2013-02-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
高校の教科書では,同位体どうしは,原子番号が同じであり,同一元素の属する原子であるので,化学的性質はほぼ同じと紹介されている。しかしながら,核種や利用法によって特徴のある性質を示すものがある。一昨年の原発の事故以来,放射性同位体に関する話題が喧し<,何かと悪者にされる同位体であるが,同位体の分類や性質,エネルギー源として以外の利用法について理解を深めることは重要ではないかと考えられる。本稿では,同位体が見つかった経緯と同位体の種類,最近の同位体を用いた研究例について概説する。
2 0 0 0 OA ダイヤモンド表面:無機結晶・有機分子の境界
- 著者
- 安藤 寿浩 中川 清晴 蒲生西谷 美香
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.1447-1451, 2001-12-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 17
気相合成法によるダイヤモンド薄膜の倉成が行われるようになっZ以来,ダイヤモンド薄膜の応用覇究が盛んになり,また不純物の制御による半導体ダイヤモンド結aeqを利用した実用化研究も注目されZいる1,2).ダイヤモンド半導体はそのバンドギャップの広さゆえ表面伝導性,表面の負性電子親和性などの特異な性質を発現する.QVO法による不純物のh一ピング,ホモ/ヘテQエピタキシー,表面伝導,電子親和性の制御,すべてダイヤモンド表面の関わる重要な研究課題である.また最近Zは電気化学分野での電極応用,DNAの固定などの生体関連材料との融合,触媒担体への応用,カーボンナノチューブとの複合化といった新たな分賢で材料としてダイヤモンドを用いる場合のダイヤモンド表面の重要性が増している.ダイヤモンドはいうまでもなく炭素単体の典型的な結最であり,炭素原子;を中心とする有機化合物の延長でもある.本稿では,ダイヤモンド,特にその表面を無機結晶固体と有機化合物のインターフェースであるとの考えから,ダイヤモンドの結晶成長および表面科学の研究の一部を紹介する.