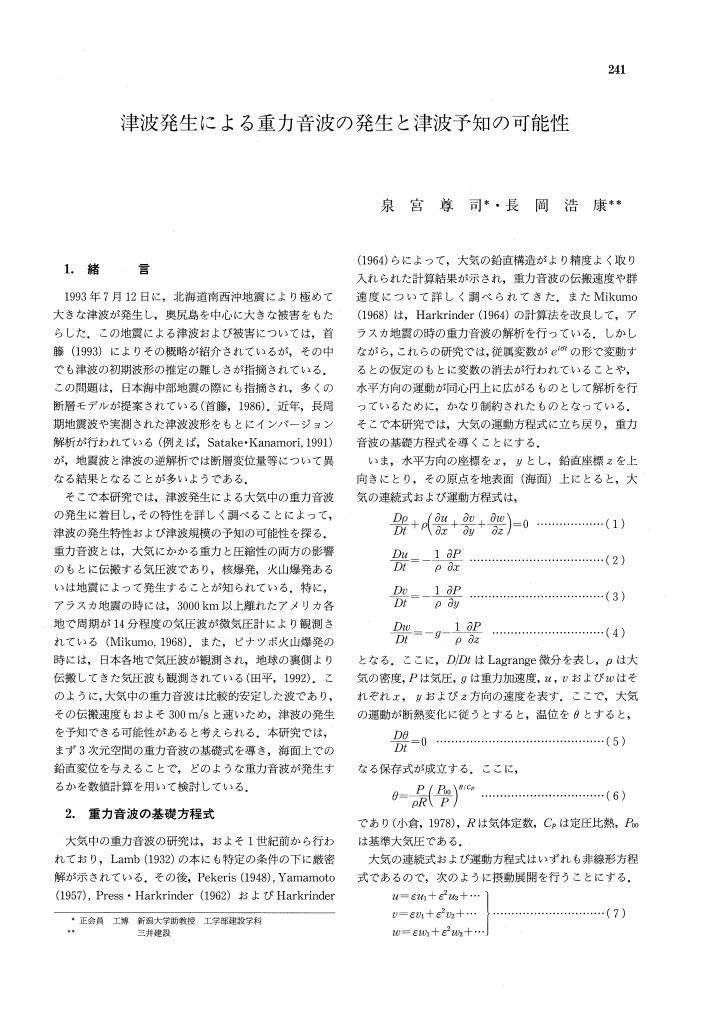4 0 0 0 OA 心尖部肥大型心筋症における巨大陰性T波の成因
- 著者
- 古賀 義則
- 出版者
- Japanese Heart Rhythm Society
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.132-140, 2001-03-25 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
巨大陰性T波 (GNT) は心尖部肥大型心筋症が認識される端緒となった心電図所見で, 心尖部壁厚とGNTの深さが良く相関することから心尖部の限局性肥厚を反映した所見と考えられている.心電学的には心尖部での再分極過程が遅延するために心尖部から心基部 (右上方) へ向かうTベクトルが増大しGNTを形成すると考えられる.この再分極過程の遅延の機序として心尖部への興奮伝播が遅れることが体表面電位図による検討で示されているが, 活動電位持続時間についての電気生理学的検討はない.しかし肥大した心筋細胞や心不全や心筋症による病的心筋細胞では活動電位持続時間が延長すると報告されている.一方BMIPP心筋シンチ像では心尖部は欠損像を示し, 長期観察例ではGNTはR波の減高と共に消失し, 心筋の変性脱落が進行すると考えられる.したがって本症の心尖部心筋細胞は肥大した病的細胞と考えられ活動電位持続時間が延長していることが推測される.この結果心尖部の再分極過程が遅延しGNTが形成されると考えられるが, 今後は細胞レベルの電気生理学的検討やイオンチヤネルの研究を期待したい.
4 0 0 0 OA 耳珠のはたらき
- 著者
- 本田 学
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.5special, pp.789-801, 1985 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 2
The human tragus is bigger than that of other animals, and it overhangs the front of the entrance to the auditory canal. Thus, it is probable that the tragus is related to acoustic function of the external ear. Since no acoustic studies have been reported to date, the author examined the acoustic function of the tragus.The source of sond was a Function Generator (TECTRONICS FG 504), and the response curves were measured in a linear scale (the frequency range was from 0.1k to 10kHz). Sound pressure was measured by a very small condenser microphone (RION EU-22), which could be placed in the auditory canal. The data were averaged and analyzed by an Analyzing Recorder (YEW MODEL 3655).Included in this study were one subject with a tragus defects, ten subjects with normal ears, an external ear replica (KOKEN LM 7#1202), an auditory canal model (Plastic) and a tragus model (clay model).The results were as follows:1. The tragus increased the acoustic length of the auditory canal (by about 3mm), lowering the frequency of the canal resonance (about 200Hz).2. The tragus helped the acoustic function of the pinna, and it raised the acoustic response of 4k to 8kHz up to about 5 to 7dB.3. The tragus forms part of the horn shape of the external ear, and it causes the acoustic response of the horn under 8kHz to be a flat response.Therefore the acoustic function of the tragus in the human is of obvious importance to the function of the external ear.
4 0 0 0 OA 子どもの空想の友達に対する親の態度
- 著者
- 富田 昌平 本藤 沙也香
- 出版者
- 心理科学研究会
- 雑誌
- 心理科学 (ISSN:03883299)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.40-53, 2015-06-25 (Released:2017-09-10)
- 著者
- 宮本 崇 西尾 真由子 全 邦釘
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.J2, pp.152-156, 2021 (Released:2021-11-17)
- 参考文献数
- 13
物理現象の入出力をデータ駆動的に再現するサロゲートモデルは,物理問題の高速な予測を行う代替的な手段としてその利用が進んでいるが,得られた解が物理的な条件を満足する保証がない問題が知られている.これに対して,Physics-Informed Neural Networks(PINNs)は支配方程式による拘束を表現した損失関数を導入することで,支配方程式をデータ駆動的に求解するニューラルネットワークである.本稿では,1次元連続体の自由振動問題に対してPINNsの定式化とコード実装を行う.
4 0 0 0 OA 数理社会学・リベラル・公共社会学 : プロ社会学者は社会のために何が言えるのか?
- 著者
- 太郎丸 博
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.52-59, 2010-05-29 (Released:2017-09-22)
- 被引用文献数
- 1
本稿では、まず日本では数理社会学が不人気である事実を確認し、その理由を説明する仮説として、リベラル仮説と伝統的公共性仮説を検討する。リベラル仮説によると、社会学者の多くはリベラルであるが、マイノリティの生活世界を描くことを通して、抑圧の実態を告発し、受苦への共感を誘う戦略がしばしばとられる。そのため、社会学者の多くは抽象的で単純化された議論を嫌う。そのことが数理社会学の忌避につながる。伝統的公共性仮説によると、日本の社会学では伝統的公共社会学が主流であるが、伝統的公共性の領域では、厳密だが煩雑な論理よりも、多少曖昧でもわかりやすいストーリーが好まれる。それが数理社会学の忌避につながる。このような数理社会学の忌避の原因はプロ社会学の衰退の原因でもあり、プロ社会学の衰退は、リベラルと伝統的公共社会学の基盤をも掘り崩すものである。それゆえ、数理社会学を中心としたプロ社会学の再生こそ日本の社会学の重要な課題なのである。
4 0 0 0 OA 失語 : 書字面
- 著者
- 佐藤 睦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.198-204, 2011-06-30 (Released:2012-07-01)
- 参考文献数
- 5
文字の読み書き機能は口頭言語の獲得と密接に関わっている。そのため,「聴く」・「話す」・「読む」・「書く」のすべての言語様式が何らかの機能低下をきたす失語症の場合,書字の症状には書字機能自体の問題のみならず語想起障害など他の言語様式の困難さが反映されることが少なくない。書字の脳内機構を論じた大槻 (2006) によれば,書字達成には左中前頭回,左頭頂葉 (上頭頂小葉,角回) ,左側頭葉後下部がさまざまなレベルで関与している。これらの領域は失語症をもたらす Broca 野や Wernicke 野に隣接していることから,失語症例で書字障害をきたすのは必然である。本論では,失語症におけるさまざまな書字障害の実例を提示した。
4 0 0 0 OA 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎を合併した2例
- 著者
- 寺谷内 泰 五十嵐 豊 生天目 かおる 平野 瞳子 溝渕 大騎 中江 竜太 横堀 將司
- 出版者
- 日本救急医学会関東地方会
- 雑誌
- 日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.202-206, 2022-12-28 (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 7
抗melanoma differentiation-associated gene (MDA) 5抗体陽性皮膚筋炎は, 予後不良な急速進行性の間質性肺炎を高頻度に合併する。今回, 当施設で経験した2例を報告する。症例1 : 44歳, 男性。呼吸苦を自覚し救急要請した。検査の結果, 重症肺炎と診断し, 人工呼吸器および体外循環管理を開始した。その後, 抗体陽性の判定を受けステロイド, シクロホスファミドによる加療を行ったが, 救命には至らなかった。症例2 : 68歳, 女性。倦怠感を自覚して近医を受診し, 肺炎像があったため入院した。その後, 呼吸不全が増悪し人工呼吸器管理を開始した。抗体陽性の判定を受け, ステロイド, シクロホスファミド, タクロリムスによる加療を行ったが救命には至らなかった。重症呼吸不全で新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を疑うような画像所見を呈する症例では本疾患も鑑別疾患としてあげられる。
4 0 0 0 OA 東南アジアのイヌ肉食習慣における狂犬病感染のリスク調査と対策
- 著者
- 西園 晃 アハメド カムルディン 齊藤 信夫 山田 健太郎 鈴木 基 グエン キューアン パカマッツ カウプロッド エリザベス ミランダ
- 出版者
- 大分大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
東南アジアにはイヌ肉を食する文化があり、感染犬とその食肉の取り扱いに伴う狂犬病感染リスクが想定されるが、実態は全く知られていない。3年間の計画で、ベトナム、フィリピンでのイヌ肉取り扱いによる非定型狂犬病曝露の可能性、リスク因子の解析を行った。その結果、これらの国では動物咬傷に依らずイヌ肉を食するまたはその肉を扱うことで、狂犬病ウイルスに感染する非定型的な感染様式が存在することが明らかになった。特にベトナムのイヌ食肉市場従事者の中には、イヌからの咬傷曝露歴や狂犬病ワクチン接種歴がないにもかかわらず狂犬病ウイルスに対する抗体を有し、微量のウイルスの曝露による不顕性感染が成立したと考えられた。
4 0 0 0 OA 津波発生による重力音波の発生と津波予知の可能性
- 著者
- 泉宮 尊司 長岡 浩康
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.241-245, 1994-10-30 (Released:2010-03-17)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 統合失調症患者の原因帰属および抑うつ・不安が被害妄想的観念の3側面に及ぼす影響
- 著者
- 村上 元 森元 隆文 西山 薫 池田 望
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- pp.27.1.8, (Released:2018-05-18)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
本研究は,被害妄想的観念の頻度,確信度,苦痛度の3側面に対して影響を与える要因を検証することを目的とした。被害妄想的観念への影響要因としては原因帰属,不安,抑うつを想定した。原因帰属は,内在性,安定性,全般性の3次元とし,内在性についてはさらに内的帰属,外的–状況的帰属,外的–人的帰属の3次元に細分化した。研究には統合失調症患者48名が参加した。階層的重回帰分析の結果,被害妄想的観念の頻度には抑うつと全般性が,確信度には抑うつ,外的–人的帰属,および全般性が,苦痛度には抑うつと不安が影響を与えていた。以上のことから,被害妄想的観念の3側面それぞれは,影響をおよぼされる要因が異なることが示された。したがって,被害妄想的観念への介入に際しては,各側面ごとに,感情の統制,もしくは原因帰属の把握が必要であることが示唆された。
4 0 0 0 OA 18世紀前半のいくつかのアイヌ語資料について
- 著者
- 佐藤 知己
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, pp.29-58, 2009-02-25
4 0 0 0 OA 広島の原爆投下を語る戦争アニメにおける変化
- 著者
- アルト ヨアヒム
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.31-41, 2019-03-01 (Released:2021-05-07)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
本稿は、日本国民の第二次世界大戦についての集合的記憶における広島への原爆投下の役割から出発し、原爆投下を扱った「戦争アニメ」を取り上げる。戦争アニメのナラティブの方向を確認するために用意した分析モデルを利用し、主な論点は作品の時空間的な舞台によるのフレーミングに起きた変化である。さらに、各作品のそれ以外の特徴も簡潔に考察する。後者の特徴には例えば各作品の間に起きた「主人公」のキャラクターの変化と物語の中に起きる主人公の成長といった点が含まれている。また、有名ではない作品が広島への原爆投下のメディア的なイメージに与えた影響に対しての学術的な観察の欠如を本稿では批判的に焦点を当てる。最終的には、対象作品の特徴の社会的な背景も触れながら論じる。
4 0 0 0 OA 大都市における震災時の交通対応策に関する研究 阪神淡路大震災の教訓と現状の課題
- 著者
- 中川 大 小林 寛
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.187-206, 2006 (Released:2006-03-30)
- 参考文献数
- 203
- 被引用文献数
- 4 5
阪神淡路大震災後の大規模な渋滞は,大都市の震災対応策に重要な教訓をもたらした.しかしながら,それから10年以上が経過しているにもかわらず,震災緊急時の交通対応の視点は基本的には変わっておらず,その教訓が十分に活かされる状況には至っていない.その原因の一つには,実際に現場でどのような現象が生じていたかが必ずしも明らかになっているとは言えないという点がある.そこで本研究では,最も重要な期間である震災発生後1~2日間における現象をあらためて明らかにするため,当時の状況に関する研究・文献等を調査し,被災地に流入できる全断面の震災直後の状況を把握する.また,これらの分析から,大都市における震災時の交通対応策に対して得られる教訓を整理し,現在の対策の課題を明らかにする.
4 0 0 0 OA フーコーにおける人間の終わりと主体の復権― 近代的主体の死から古代的主体の発掘へ ―
- 著者
- 伊東 輝夫
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.133-136, 2020-12-25 (Released:2021-12-25)
- 著者
- Naoshi KONDO Makoto KURAMOTO Hiroshi SHIMIZU Yuichi OGAWA Mitsutaka KURITA Takahisa NISHIZU Vui Kiong CHONG Kazuya YAMAMOTO
- 出版者
- Asian Agricultural and Biological Engineering Association
- 雑誌
- Engineering in Agriculture, Environment and Food (ISSN:18818366)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.54-59, 2009 (Released:2009-04-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
As basic research to develop a machine vision system to detect rotten mandarin orange, the extraction and identification of fluorescent substances contained in rotten parts of mandarin orange were conducted, and the excitation and fluorescence wavelengths of the substance were determined. Although it has been reported that damaged orange fruit skins are often fluoresced by UV light, it was suggested that fluorescent substances exist not only in the rotten parts of skins but also the normal parts of skins from this research. The fluorescent substances were extracted from 1kg of mandarin peel, and NMR analysis and mass spectrometry were conducted. From this experiment, it was found that the fluorescent substance was quite possibly heptamethylflavone and that the excitation and fluorescent wavelengths of one of the substances were 360 to 375nm and 530 to 550nm, respectively.
4 0 0 0 OA 亀ヶ岡文化を中心としたベンガラ生産の復元
- 著者
- 児玉 大成
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.20, pp.25-45, 2005-10-20 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 113
ベンガラは,褐鉄鉱または赤鉄鉱から得る方法があり,一部は後期旧石器時代より確立された技術として生産された。縄文時代のベンガラ生産は,原料を粉砕,磨り潰されるところまでは理解されているものの,きめ細かく均一的な粒子を得るための調製方法については未解明な部分が多い。北海道南部から東北北部に形成される亀ヶ岡文化の遺跡では,赤鉄鉱の出土が目立ち,宇鉄遺跡においては2,300点,約65kgもの赤鉄鉱とベンガラ付着石器や土器が数多く出土している。小稿では,宇鉄遺跡の赤色顔料関連資料の分析と顔料の製造実験を通して実証的なベンガラ生産の復元を試みた。その結果,赤鉄鉱を叩き割りして頁岩部分とコークス状部分とを分離させ,次にコークス状の赤鉄鉱のみを粉砕し,さらに磨り潰したものを水簸による比重選鉱を行い,赤色の懸濁液を土器で煮沸製粉していたことが明らかとなった。このような煮沸製粉法によるベンガラ生産では,均一的な微粒子粉末を得ることができ,より多量な生産を容易に可能とする。こうした技術を必要とした背景には,亀ヶ岡文化が多様な赤彩遺物を増大させたことと密接に関係するものと考えられる。
- 著者
- Shin Taketa June-Sik Kim Hidekazu Takahashi Shunsuke Yajima Yuichi Koshiishi Toshinori Sotome Tsuneo Kato Keiichi Mochida
- 出版者
- Japanese Society of Breeding
- 雑誌
- Breeding Science (ISSN:13447610)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.435-444, 2023 (Released:2023-12-21)
- 参考文献数
- 52
Two modern high-quality Japanese malting barley cultivars, ‘Sukai Golden’ and ‘Sachiho Golden’, were subjected to RNA-sequencing of transcripts extracted from 20-day-old immature seeds. Despite their close relation, 2,419 Sukai Golden-specific and 3,058 Sachiho Golden-specific SNPs were detected in comparison to the genome sequences of two reference cultivars: ‘Morex’ and ‘Haruna Nijo’. Two single nucleotide polymorphism (SNP) clusters respectively showing the incorporation of (1) the barley yellow mosaic virus (BaYMV) resistance gene rym5 from six-row non-malting Chinese landrace Mokusekko 3 on the long arm of 3H, and (2) the anthocyanin-less ant2 gene from a two-row Dutch cultivar on the long arm of 2H were detected specifically in ‘Sukai Golden’. Using 221 recombinant inbred lines of a cross between ‘Ishukushirazu’ and ‘Nishinochikara’, another BaYMV resistance rym3 gene derived from six-row non-malting Japanese cultivar ‘Haganemugi’ was mapped to a 0.4-cM interval on the proximal region of 5H. Haplotype analysis of progenitor accessions of the two modern malting cultivars revealed that rym3 of ‘Haganemugi’ was independently introduced into ‘Sukai Golden’ and ‘Sachiho Golden’. Residual chromosome 5H segments of ‘Haganemugi’ surrounding rym3 were larger in ‘Sukai Golden’. Available results suggest possibilities for malting quality improvement by minimizing residual segments surrounding rym3.
- 著者
- Yoshinao Yazaki Kazuhiro Satomi Taishiro Chikamori
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.11, pp.1645-1651, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
Objective The Lewis lead configuration is an alternative bipolar chest lead and it can help detect atrial activity. The utility of the Lewis lead to distinguish orthodromic atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT) from typical atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) by visualizing the apparent retrogradely conducted P waves was investigated. Methods Forty-four patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were included in this study. All patients had PSVT documented by an electrocardiogram (ECG) and underwent an electrophysiological study (EPS). During tachycardia, an ECG recording was performed using a Lewis lead with the electrode on the right aspect of the sternum at the second intercostal space instead of the right arm and the electrode on the fourth intercostal space instead of the left arm. The ECG parameters during tachycardia were compared between AVRT and AVNRT. Results Fourteen patients were diagnosed with AVRTs and 30 with typical AVNRTs on EPS. The positive P wave could be seen in the Lewis lead configuration in 9 of 14 patients with AVRTs and 21 of 30 patients with AVNRTs. P waves were more often visible in the Lewis lead configuration than in the standard leads (66% vs. 45%). The RP interval was significantly longer for AVRTs than for AVNRTs (88±17 vs. 154±34 ms, p<0.001), which yields 89% sensitivity and 71% specificity for distinguishing these 2 tachyarrhythmias with a cut-off point of 100 ms. Conclusion A Lewis lead configuration may help to make an accurate diagnosis among the reentrant supraventricular tachycardias prior to procedures, owing to its ability to locate P waves.
4 0 0 0 OA 都市計画における移動の自由の制限の再考 東日本大震災後の状況を素材として
- 著者
- 窪田 亜矢
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.1358-1364, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 38
東日本大震災後に都市計画が適用された状況をふまえれば、都市計画において合理的な目標像を設定できたとはいえない。都市計画の再考が必要である。都市計画は、特定の都市や地域を対象に、今よりも良い状態が存在し、それを合理的な目標像として描き、規制と事業によって実現できるという信念に基づいている。現状からの変化を前提としているので、個人の移動の自由を制限することを原理的に包含している。しかし、個人の移動の自由とは、現状保障を基本とする居住や事業を営む場所に関するもので、個人の命や生活に関わる重大な自由である。そこで、現状の都市計画に、個人の移動の自由を尊重する規範を並立させる必要がある。