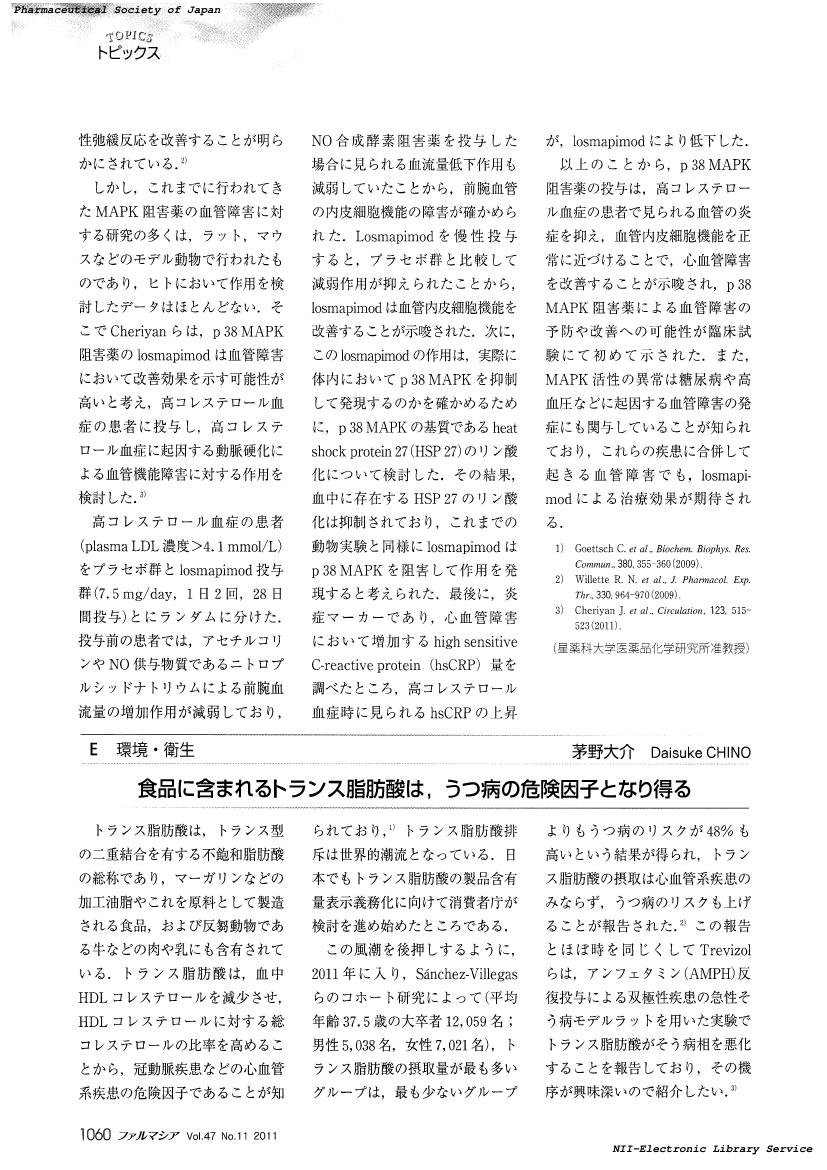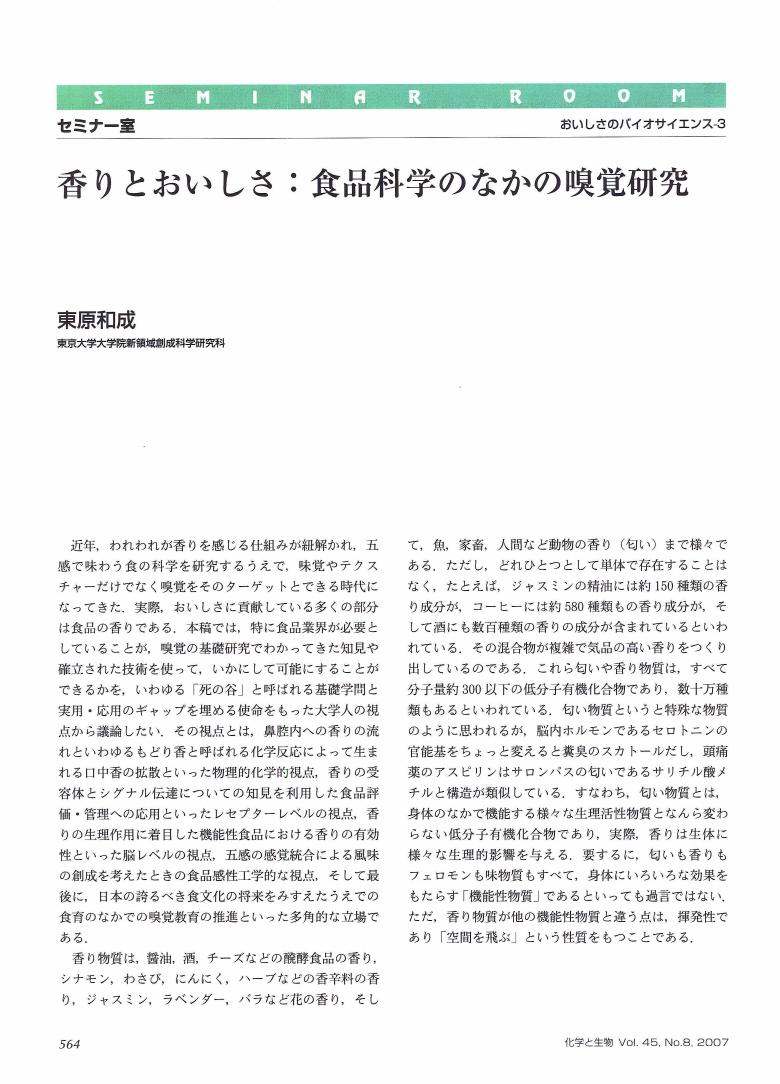4 0 0 0 OA 国内初発見!サシバエの寄生蜂
- 著者
- 松尾 和典
- 出版者
- 公益社団法人 畜産技術協会
- 雑誌
- 畜産技術 (ISSN:03891348)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.786-Nov., pp.2-6, 2020-11-01 (Released:2023-05-05)
4 0 0 0 OA 小山内薫『息子』の時代
- 著者
- 大橋 裕美
- 出版者
- 西洋比較演劇研究会
- 雑誌
- 西洋比較演劇研究 (ISSN:13472720)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.149-161, 2013-03-15 (Released:2013-03-15)
- 参考文献数
- 28
MUSUKO (The Son) is one of Osanai Kaoru’s most famous plays, and a typical example of Shin-Kabuki (New Kabuki) works. It was first published in magazine form in 1922. MUSUKO is a tale about a night watchman and a wanted young man named Kinjirô. He, it turns out, is the watchman’s son, who disappeared nine years ago. Kinjirô meets his father again, but the watchman does not recognize his son because he has changed so much. Kinjirô keeps his secret to himself, and says good-bye to the watchman. Thus, Osanai describes an unusual relationship between a son and his father. The play was first staged in March 1923 at Teikoku Gekijyô. The actors Onoe Kikugorô VI (1885-1949), Onoe Matsusuke IV (1843-1928), and Morita Kanya XIII (1885-1932) all performed in the play, drawing a large audience. In this paper, I focus on two important aspects of MUSUKO as a modern Japanese play. Firstly, it is an adaptation of Augustus in Search of a Father by Harold Chapin (1886-1915). Generally, dramatic adaptations in modern Japan include concepts from the original sources, as in the play Hernani by Matsui Syôyô (1870-1933), and Suisu-Giminden (Wilhelm Tell) by Iwaya Sazanami (1870-1933). Both of these authors considered the original stories very carefully. In contrast, Osanai’s theory of adaptation is unique. He cut a lot of the dialogue and scenes from Chapin’s play, and changed the nature of the father’s character: the father in MUSUKO is as stubborn as a mule. Secondly, MUSUKO is a new and interesting drama about a father and his son. Needless to say, plays depicting parents and children are often warm-hearted, and emotional. Augustus in Search of a Father is a sentimental play as well. Yet, in MUSUKO, Osanai depicts the father and his son without tearful affection. It is noteworthy that the dramaturgy of MUSUKO is of a very rare type in Japan. MUSUKO was a well-received play during the Taisyô Era. The audience and critics spoke highly of its stage atmosphere. The set, designed by Tanaka Ryo (1884-1974), left an elegant impression on many people. During the Taisyô Era, the “kibun”(atmosphere or mood) was an important idea for the audience. They praised MUSUKO for its refined sense. MUSUKO was received as an enchanting play at its first performance in 1923.
4 0 0 0 OA 今 敏のつながり合う創造的世界:自己探求の連鎖
- 著者
- 藤原 正仁
- 出版者
- 日本アニメーション学会
- 雑誌
- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.15-32, 2016-09-07 (Released:2023-02-18)
- 参考文献数
- 76
本研究の目的は、今 敏のライフストーリーの観点から、今 敏監督の人間像、今 敏監督作品の創造過程、そして、今 敏監督と今 敏監督作品との連関について明らかにすることである。本研究では、アニメーション作品、絵コンテ、日記、ブログ、ウェブサイト、エッセイ、音声解説、記事などの資料調査に基づく質的研究の方法論を採用した。その結果、今 敏は、仕事と仲間とともに、アニメーション監督という職業を通して、アイデンティティを確立させながら、自らを表現しようとしていることが明らかにされた。今 敏監督は、絵を描くことによって、想像力を拡張し、創造性に富んだ新しいアニメーションの表現に挑戦し続けた。彼のアイディアは、現実と対峙し、予期しない出来事や偶然の出会いが源泉となっている。とくに、平沢進の音楽と筒井康隆の小説の影響を受けており、これらの世界観は、今 敏監督のアニメーション作品に活かされている。さらに、今 敏監督は、日常生活の中での想像力を作品に反映している。本研究の結論として、今 敏は、自らの人生の意味を探求しながら、アニメーション作品の中に、彼自身の人生のテーマを表現し続けたことが明らかにされた。
4 0 0 0 OA <研究資料>法然六五〇年の御忌 : 『蕐頂山大法會圖録全』『勅會御式略圖全』の翻刻
- 著者
- 姜 鶯燕 平松 隆円
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.301-335, 2012-03-30
平安末期の僧である法然は、比叡山で天台を学び、安元元(一一七五)年に称名念仏に専念する立場を確立し、浄土宗を開いた。庶民だけではなく関白九条兼実など、社会的地位に関係なく多くの者たちが法然の称名念仏に帰依した。建暦二(一二一二)年に亡くなったあとも、法然の説いた教えは浄土宗という一派だけではなく、日本仏教や思想に影響を与えた。入滅から四八六年が経った元禄一〇(一六九七)年には、最初の大師号が加諡された。法然の年忌法要が特別に天皇の年忌法要と同じく御忌とよばれているが、正徳元(一七一一)年の滅後五〇〇年の御忌以降、今日に至るまで五〇年ごとに大師号が加諡されており、明治になるまでは勅使を招いての法要もおこなわれていた。本稿は、法然の御忌における法要が確立した徳川時代のなかで、六五〇年の御忌の様子を記録した 『蕐頂山大法會圖録全』『勅會御式略圖全』の翻刻を通じて、徳川時代における御忌のあり方を浮かび上がらせることを目的とした。
4 0 0 0 大規模災害からの復興の地域的最適解に関する総合的研究
- 著者
- 浦野 正樹 松薗 祐子 長谷川 公一 宍戸 邦章 野坂 真 室井 研二 黒田 由彦 高木 竜輔 浅川 達人 田中 重好 川副 早央里 池田 恵子 大矢根 淳 岩井 紀子 吉野 英岐
- 出版者
- 早稲田大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
本研究では、東日本大震災を対象として発災以来社会学が蓄積してきた社会調査の成果に基づき、災害復興には地域的最適解があるという仮説命題を実証的な調査研究によって検証し、また地域的最適解の科学的解明に基づいて得られた知見に基づいて、南海トラフ巨大地震、首都直下地震など次に予想される大規模災害に備えて、大規模災害からの復興をどのように進めるべきか、どのような制度設計を行うべきかなど、復興の制度設計、復興の具体的政策および復興手法、被災地側での復興への取り組みの支援の3つの次元での、災害復興に関する政策提言を行う。また、研究の遂行と並行して、研究成果の社会への還元とグローバルな発信を重視する。
4 0 0 0 研究支援業務を担う大学経営人材のキャリアと育成
- 著者
- 木村 弘志
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.28-33, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)
本稿では,特に研究支援の分野において,大学経営人材が担うことが期待されている業務と,そのキャリア・育成について考察した。大学経営人材が担う研究支援業務の範囲は,URAの中核業務以外にもわたり,より幅広くなっている。そのような業務を遂行するうえでは,「多様な専門性が必要となる業務を遂行する能力」「研究そのものや,研究に関連する諸活動の理解」が必要となる。そして,そのような能力を身につけるためのキャリア・育成について,事務職員出身者と教育職員出身者という出自の異なる2つのルートに分けて考察し,それぞれがキャリア内で身につけうる能力と,各種教育プログラムで補うべき能力について論じた。
4 0 0 0 OA 産業医マインドを持つプライマリ・ケア医育成のための活動報告
- 著者
- 安藤 明美 今井 鉄平 田中 千恵美 富田 さつき 鈴木 富雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.162-164, 2023-12-20 (Released:2023-12-27)
- 参考文献数
- 5
日本では産業保健へのアクセスが困難な人たちへの産業保健の提供は不十分だが,健康問題の最初の相談先となり得るプライマリ・ケア医から産業保健サービスが提供されることは,解決策の一つとして期待される.しかし,プライマリ・ケア医の産業保健に対する意識は十分とはいえない.このため,我々は各種教育・啓発活動を2021年4月より行ってきた.今回の報告でプライマリ・ケア医の産業保健への意識が高まることを願っている.
4 0 0 0 OA 食品に含まれるトランス脂肪酸は,うつ病の危険因子となり得る
- 著者
- 茅野 大介
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.11, pp.1060-1061, 2011-11-01 (Released:2018-08-23)
4 0 0 0 OA 学校の勉強なんかしない : 男の特権?
- 著者
- 高田 里惠子
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター
- 雑誌
- 応用倫理 (ISSN:18830110)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.Suppl, pp.14-23, 2018-03-31
4 0 0 0 OA 和歌山県椿山ダム建設にともなう水没移転者の人口移動研究
- 著者
- 佐々木 敏光
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.3, pp.131-151, 2021-05-01 (Released:2023-02-19)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4
本稿では,和歌山県椿山ダムの建設により水没移転を余儀なくされた人々が移転先をどのように決定したかを,属性,およびそれ以外の要因にも焦点を当てながら解明することを目的とする.ダム建設計画が発表されると,水没予定地区の住民は反対運動を起こしたが,すぐに条件闘争に切り替えた.補償交渉の過程での意見対立は人間関係の悪化を招き,地元ダム対策組織が分裂と再編成を繰り返す事例が見られ,移転先の意思決定に大きな影響を与えた.水没移転者のほとんどは,住み慣れた地域の近くに移転した.新たに仕事を見つけるには高齢で,そのため,移転前と同じ仕事に従事することを望んだことによる.林業経営者も,事業継続のため近隣地域に移転した.水没移転を人口移動の一つとしてとらえ,水没移転者の属性,人間関係等のファクターに注目しながら移転先の意思決定に至るプロセスの分析を行った結果,複数の移転パターンが明らかになった.
4 0 0 0 OA 間葉系幹細胞の新しい機能 ─免疫調節細胞としての間葉系幹細胞─
- 著者
- 秋山 謙太郎 古味 佳子 窪木 拓男
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.346-353, 2016 (Released:2016-11-09)
- 参考文献数
- 69
間葉系幹細胞は,様々な体細胞に分化できる多分化能を有している事が知られており,その性質を応用した組織再生療法が長年に渡り,研究・臨床応用されて来た.一方,間葉系幹細胞の持つ免疫調節機能が着目されるようになり,様々な全身性免疫疾患に対する間葉系幹細胞移植療法の治療効果が報告されるようになった.このように間葉系幹細胞の機能は多岐に渡るが,その機能自体や制御メカニズムは未だ不明な点が多く,治療効果が不確実な場合もある.本稿では間葉系幹細胞の持つ機能のうち,とりわけ免疫調節機能の発現と治療効果が得られるメカニズムについて我々の研究データとともに紹介する.
- 著者
- 諸岡 雄也 古野 憲司 菊野 里絵 川向 永記 加野 善平 空閑 典子 鳥尾 倫子 安部 朋子 水野 由美 吉良 龍太郎
- 出版者
- 日本神経感染症学会
- 雑誌
- NEUROINFECTION (ISSN:13482718)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.131, 2022 (Released:2022-05-12)
- 参考文献数
- 19
【要旨】新生児、早期乳児の無菌性髄膜炎における FilmArrayⓇ髄膜炎・脳炎パネルの有用性を検討した。発熱で受診した生後3 ヵ月未満の 152 例に髄液検査を施行し、細胞数増多 27 例、正常 125 例であった。細胞数増多 27 例中 15 例が無菌性髄膜炎と診断された。10 例は病原体陽性(全例 enterovirus:EV)、5 例は陰性であった。陽性群の抗菌薬投与日数は平均 2.4 日で、陰性群 4.8 日とくらべて有意に短かった(P<0.04)。細胞数正常 125 例中 15 例に本検査を実施し、EV1 例、human parechovirus2 例を検出した。本検査により不要な抗微生物薬を安全に減らせる可能性がある。
4 0 0 0 OA 犯罪プロファイリングは法廷で証拠となるか
- 著者
- 重田 園江
- 出版者
- 明治大学社会科学研究所
- 雑誌
- 明治大学社会科学研究所紀要 (ISSN:03895971)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.1-9, 2008-03-10
4 0 0 0 OA 石川県にみられる民家型に関する基礎研究
- 著者
- 村田 一也
- 出版者
- 独立行政法人 石川工業高等専門学校
- 雑誌
- 石川工業高等専門学校紀要 (ISSN:02866110)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.43-52, 2014 (Released:2017-10-01)
Generally speaking, “Minka” means an old Japanese (private) houses. Studies of Minka to date have focused on the associated life style and culture, as well as the environments and societies that they were located in. Minka have characteristic madori (floor plans) depending on the region in which they are situated. That is, there are regional types in its MADORI = PLAN. In this paper, I dealt with Minka-Types as a result of research studies for Minka, then I tried to analyze some Minka-Types in Ishikawa prefecture found by previous researches. I analyzed the contents and models regarding Minka types in Ishikawa prefecture of three previous studies. I then unified the classification of Minka Types in Ishikawa prefecture. This paper is fandamental study in that mean. Ishikawa prefecture is divided into the Kaga region and Noto region, which differ both geographically and culturally. A distinction was made between Kaga type and Noto type madori. Furthermore the Minkas of Ishikawa prefecture were classified into five types: which were Kaga I type, Kaga II type, Noto I type, Noto II type and Noto III type. I clarified the areas of distribution in Ishikawa prefecture and the characteristics of the five Minka Types. The relationship between the findings of the three previous studies is discussed. Unified diagrams and a distribution map will be shown in another paper.
4 0 0 0 OA 4)IgG4関連呼吸器疾患
- 著者
- 久保 惠嗣 松井 祥子 山本 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.9, pp.1848-1852, 2015-09-10 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 10
4 0 0 0 OA 日本漢方諸学派の流れ
- 著者
- 安井 廣迪
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.177-202, 2007-03-20 (Released:2008-09-12)
- 被引用文献数
- 8 5
現在の日本の漢方医学の形は, 過去における諸学派の理論や方法の影響を受けて形成された。この医学は, 当初は中国医学の模倣であったが, 徐々に日本独特の形を獲得, 16世紀に至り, 曲直瀬道三らの努力によって当時の明の医学システムを全面的に導入することに成功し, 一大学派を形成した。17世紀後半に入ると, 中国の『傷寒論』研究ブームの影響が日本に及び, この古典に基づいた医学体系を構築する学派が出現した。とりわけ吉益東洞は徹底して『傷寒論』処方の研究を行い, 処方を特定の症候に対応させて運用する方証相対システムを考案した。そのあと後世派と古方派の医術を臨床的に折衷する学派が出現した。折衷の形はさまざまであり, この学派に属する多くの医師によって, 個性溢れる治療が行われた。1868年の明治維新後, 漢方医学は正統の地位を外れたが間もなく復興し始め, 少数ながら精鋭の漢方専門医によって『漢方診療の実際』 (1941) が出版されて, 現在の漢方医学の基礎を作った。その後の漢方医学は, 現代医学的な研究を多く取り入れ, 学派も以前とは異なった形で存続している。
4 0 0 0 OA 中性子核変換による金生成技術の検討
- 著者
- 岩橋 大希 高木 直行
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集 2012年春の年会
- 巻号頁・発行日
- pp.231, 2012 (Released:2012-03-27)
原子炉の中性子を利用して水銀から金を製造する核変換技術(原子炉錬金術)の検討に着手した。原子炉内に水銀を被覆管に封入した状態で装荷する事による反応度影響と金の製造量の評価を行い、水銀装荷量を増やすと金の生成量が増加したが、生成効率が下がるという知見を得た。
4 0 0 0 OA 大規模自然災害がカップ麺の需要に与えた影響 —2016 年熊本地震の事例分析—
- 著者
- 松田 敏信
- 出版者
- 農業生産技術管理学会
- 雑誌
- 農業生産技術管理学会誌 (ISSN:13410156)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.107-114, 2022 (Released:2024-01-09)
4 0 0 0 OA 人工地震発生装置および地震時土圧測定装置について
- 著者
- 市原 松平 丹羽 新
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:00471798)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.38, pp.43-48, 1956-10-31 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 5
岸壁に作用する地震時土圧の諸性質, 並びに地震時における壁体の運動を明らかにするために, 著者らは人工地震発生装置を築造し, 同時に地震時土圧測定に関する一連の測定器を完成した。以下これらの実験装置の概略について述べる。
4 0 0 0 OA 香りとおいしさ
- 著者
- 東原 和成
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.8, pp.564-569, 2007-08-01 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 3