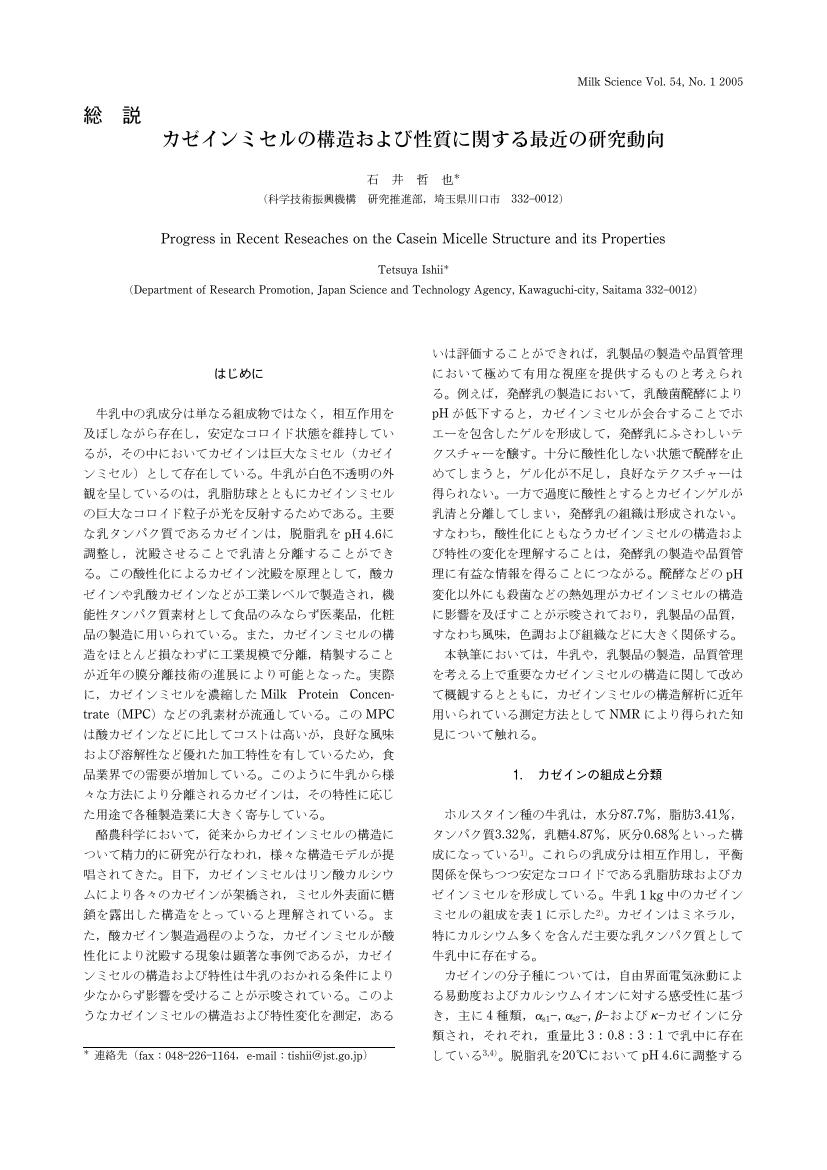4 0 0 0 OA 緑茶用新登録品種「おくむさし」について
- 著者
- 松本 武夫 淵之上 康元 米丸 忠 田中 万吉
- 出版者
- Japanese Society of Tea Science and Technology
- 雑誌
- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.19, pp.6-9, 1962-11-15 (Released:2009-07-31)
- 被引用文献数
- 1 2
"Oku-Musahi" is a new variety for green tea. This was developed by the Tea Breeding Laboratory, M. A. F.-designated, Saitama-Ken Tea Exp. Stat., and the registration of this variety was made in 1962. "Oku-Musashi" was selected from the hybrids between "Saya-mamidori" and "Yamatomidori".The superior points of this variety are as follows;1. It grows vigorusly, and produces high yield and, especially, is cold resistant. It is, adapted to the northern zone of green tea production in Japan as Saitama Ken.2. It grows leaves of superior qualities for green tea. And, therefore, the tea has good characters, especiaially, in aroma and taste.3. "Oku-Musashi" is a late variety, that is, the plucking time is a few days later than "Sayamamidori" and 7 to 10 days later than "Yabukita, " both are main varietys cultivated in Saitama district. Therefore, the tea growers can control the labour of tea leaf plucking.
4 0 0 0 OA 平成28年熊本地震後初期の建設会社の応急復旧対応に関する調査結果
- 著者
- 柳原 純夫 仲村 成貴 後藤 洋三 山本 幸 柿本 竜治
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集A1(構造・地震工学) (ISSN:21854653)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.I_564-I_574, 2021 (Released:2021-07-22)
- 参考文献数
- 4
熊本地震直後の社会基盤設備の応急復旧での地元建設会社の初動対応の実態把握と課題抽出を目的とし,ヒアリング及びアンケート調査を実施した.調査結果と課題は次の通り.(1) 地震後の初動対応に遅れや混乱が発生した.協定内容の改善が必要である.(2) 対応工事の必要資源の不足が発生した.防災計画等での考慮が必要である.(3) 建設会社が実施した応急復旧工事における,費用清算面の問題はなかったが,施工数量の確定や支払処理の円滑化が課題として残った.(4) 応急復旧作業時は作業安全レベルが低下していた.地震後の工事を対象とした安全教育システムの確立が急務である.(5) 事故発生時には「公務災害補償」と同等の補償の適用を望む回答が大半を占めた.法律面を含めた補償制度面の対応が必要である.
4 0 0 0 OA 脳活動の情報量解析による分離脳のメカニズムの解明
左脳と右脳をつなぐ脳梁がてんかんの治療のために切断された脳は「分離脳」と呼ばれ、患者はあたかも左脳と右脳に2つの独立した意識が生じているかのような行動をとる。分離脳を理解することは、我々がなぜ左脳と右脳とで統合された1つの意識を持ち得るのかということを理解する上で重要である。本研究では、この分離脳の神経メカニズムの理解を目標として、サルのECoGデータの記録及び、神経活動データから神経ネットワークの構造を抽出するアルゴリズムの開発を行った。このアルゴリズムは情報の統合が最大となるサブネットワークを効率的に探索することが可能で、これによって脳活動からネットワークの分離を判定することが可能となる。
4 0 0 0 バイラテラル制御における周波数修正法の有効性検証
- 著者
- 椿 崇裕 小林 聖人 上田 好寛 元井 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, no.1, pp.28-34, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)
- 参考文献数
- 25
For operability improvement, this paper proposes a frequency modification method using fast Fourier transform (FFT) in a bilateral control. A bilateral control is one of the remote control methods with tactile sensation. The bilateral control system consists of the leader and follower systems. By using FFT, the position response and estimated force in the leader and follower systems are converted from the time domain to the frequency domain. In the frequency domain, frequency modification is conducted. After the frequency modification, the frequency domain data is reconverted to the time domain by using inverse FFT. Therefore, the proposed method enables frequency modification that is easy for the operator to manipuate in the bilateral control. For the confirmation of the validity of the proposed method, the experiments that imitate drilling tasks were conducted.
4 0 0 0 OA ペットロスに伴う死別反応から医師の介入を要する精神疾患を生じる飼主の割合
- 著者
- 木村 祐哉 金井 一享 伊藤 直之 近澤 征史朗 堀 泰智 星 史雄 川畑 秀伸 前沢 政次
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.59-65, 2016-07-20 (Released:2017-01-24)
- 参考文献数
- 17
ペット喪失に伴う深刻な心身の症状が2カ月を超えて持続する場合には,医師による対応が必要である可能性が高いと考えられる。東京および愛知の動物火葬施設で利用者に対して精神健康調査票(GHQ28)による追跡調査を実施したところ,死別直後で22/37名(59.5%),2カ月後で17/30名(56.7%),4カ月後で11/27名(40.7%)の遺族がリスク群と判定された。また,心身の症状に影響のある要因として,遺族の年齢,動物との関わり方,家族機能が挙げられた。ペット喪失後の問題を減らすためには,こうした要因をもつ飼育者に獣医療従事者が事前に気づき,予防的な対応をとることが重要と考えられる。
4 0 0 0 OA 生理用品の性能と使用実態
- 著者
- 小川 育子 菅 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.11, pp.618-625, 1994-11-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- EVA PETREJCÍKOVÁ MIROSLAV SOTÁK JARMILA BERNASOVSKÁ IVAN BERNASOVSKÝ ADRIANA SOVICOVÁ ALEXANDRA BÔZIKOVÁ IVETA BORONOVÁ PETRA ŠVÍCKOVÁ DANA GABRIKOVÁ SONA MACEKOVÁ
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.2, pp.89-94, 2009 (Released:2009-07-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 4 4
European ‘gypsies’, commonly referred to as Romanies, are represented by a large number of groups spread across many countries. We performed a population genetic study on 200 unrelated Romany males to reveal the genetic origin of the Slovak Romany population. On the basis of Y-chromosome haplotypes, we determined the corresponding Y-haplogroups using Whit Athey’s Haplogroup Predictor. The obtained distribution of haplogroups provided strong evidence of Asian origins, especially Indian. The Indian Y-haplogroup H was the most prevalent and represented 40% of all the samples. The distribution of haplogroups was: E1b1b, 21%; J2, 16.5%; I1a, 14%. Haplogroups R1a, R1b, I2a, and N1 were observed in small frequencies. The obtained genetic structure indicated that the endogamous Romany population has been shaped by a genetic drift and differential admixture, and correlates with the migratory history of the Romanies in Europe.
4 0 0 0 OA 小学校の普通教室における掲示物の実態と児童の意識に関する事例研究
- 著者
- 山岸 明浩 奥原 由真
- 出版者
- 人間-生活環境系学会
- 雑誌
- 人間と生活環境 (ISSN:13407694)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.49-57, 2016 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3
本研究では,松本市内の小学校を対象に,教室内の掲示物の実態と掲示物に対する児童の意識について検討した。調査の結果,1教室当たりの平均で38件の掲示がなされており,掲示の種類については生活面の掲示物が71%と多くなっていた。掲示位置と掲示内容の関係については,生活面の掲示では教室の前側には「目標」や「決まり事」の掲示が多く,教室の後側には,「取り組み」や「メッセージ」の掲示が多くなっていた。学習面の掲示では,教室の前側には「学習の心がけ」,後側には「学習の作品」,窓側・廊下側には「学習の振り返り」が多く掲示されていた。学年による違いについては,掲示物の件数は低学年で多い傾向となり,内容は高学年になると生活面の掲示物の割合が多くなった。掲示物と児童の意識の関係については,掲示物の種類が児童の意識に強く影響しており,「予定」や「取り組み」,「学習の作品」の認知の度合いが高い結果となった。
- 著者
- 小口 悠紀子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.174, pp.56-70, 2019-12-25 (Released:2021-12-26)
- 参考文献数
- 17
本稿は,初級日本語学習者を対象に,構造シラバスの中で教師がTBLTの理念を取り入れることの可能性とタスクの効果を検討した実践報告である。本稿では全9回 (27時間) に及ぶTBLT実践を行い,(1) 学習者はTBLTアプローチをどう受け止めていたか,(2) 学習者はタスクを楽しみ,有効性を実感していたか,(3) 学習者のタスクに対する反応は,教師が想定するものであったか,という点について検証した。その結果,学習者はTBLTによる日本語授業に概ね肯定的な反応を示したものの,学習者の持つビリーフスやコースの評価方法がTBLTに沿わない場合,不安や戸惑いを感じることが分かった。また,マイクロ評価の結果,タスクが持つ真正性の高さが学習者の動機付けを高め,教師の狙い通り能動的な授業参加や内容中心のコミュニケーションを促す一方で,言語形式への焦点化は,教師に頼らず学習者間で適宜行われていることが明らかになった。
4 0 0 0 OA カゼインミセルの構造および性質に関する最近の研究動向
- 著者
- 石井 哲也
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.1-8, 2005 (Released:2014-03-15)
- 参考文献数
- 37
ここ数十年で乳がんの年齢調整罹患率は著しく増加してきたが、乳がんの原因はその既知の危険因子だけでは半分程度しか説明できないとされている。一方、新規な環境汚染物質である有機フッ素化合物への曝露が乳がん発生に関与している可能性が注目されている。しかしながら世界的にもデータが乏しく、国際機関が発がん性を評価していない有機フッ素化合物も多い。既存の疫学研究では異性体別に研究しておらず、南半球での研究例もまだない。これまで日本人女性において有機フッ素化合物が乳がんの発生に及ぼす影響の解明を進めてきたが、これに加え、本研究ではブラジル人女性における症例対照研究を行い、国際比較と統合解析を行う。
4 0 0 0 慢性疼痛の漢方治療-痛み・冷え・気に対する処方-
- 著者
- 光畑 裕正
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.403-408, 2012
- 被引用文献数
- 4
慢性疼痛は複雑な病態を呈し, 治療に難渋することがしばしば見受けられる. 西洋医学的治療で鎮痛が得られない症例で漢方薬が有効なことがある. 抑肝散は抗アロディニア作用があり, 神経障害性疼痛を含む慢性痛に効果がある. 抑肝散は絞扼性神経損傷ラットモデルで抗アロディニア作用を示し, その機序の一つはグルタミン酸トランスポーター活性化によりグルタミン酸濃度を低下させることを筆者らは明らかにした. また慢性痛は冷えを伴うことが多く, 当帰芍薬散, 苓姜朮甘湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 真武湯, 八味地黄丸など冷えを改善する方剤が効果を示す. また慢性痛では気の異常 (気鬱, 気逆, 気虚) を伴うことが多く, 半夏厚朴湯や四逆散, 柴胡疏肝湯など気剤が著効することがある. 慢性疼痛治療の一つの選択肢として漢方は有用である.
4 0 0 0 OA 長時間保湿作用を有する保湿剤塗布による妊娠線出現予防効果の検証
4 0 0 0 IR 中小企業における女性への事業承継の障壁要因と承継後の事業成長要因に関する研究
- 著者
- 黒澤 佳子
- 出版者
- 法政大学 (Hosei University)
- 巻号頁・発行日
- 2023
type:Thesis
4 0 0 0 OA ERCP後膵炎予防の現状と展望
- 著者
- 峯 徹哉 川口 義明 小川 真実 川嶌 洋平
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.9, pp.2393-2402, 2017 (Released:2017-09-20)
- 参考文献数
- 54
従来の診断基準は日本消化器内視鏡学会で作成されたが,国内でも十分に活用されているとはいいがたい.外国でも診断基準は作られているが長い間改正されないので,現実的ではなくなっていると思われる.われわれの作成したガイドラインはEBMに基づいたものであり,世界を見回してもEBMに基づくERCP後膵炎ガイドラインは見あたらないと思われる.われわれは将来的にERCP後膵炎の診断基準を見直し,より早く治療を行い救命すると同時に如何に重症のERCP後膵炎を生じさせないかその予防法を検討する必要がある.
4 0 0 0 OA 庚申信仰と北斗信仰
- 著者
- 窪 徳忠
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.141-147, 1957-08-25 (Released:2018-03-27)
4 0 0 0 OA Z世代と「テレビ」 NHK文研フォーラム2023
- 著者
- 保髙 隆之 舟越 雅
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.12, pp.2-19, 2023-12-01 (Released:2023-12-20)
今後のメディア動向を占うデジタルネイティブの先駆けとして注目される「Z世代」。文研はZ世代とテレビの今のリアルな距離感とこれからの関係を探ることをめざし、文研フォーラム2023で「Z世代とテレビ」と題したシンポジウムを行った。 登場した大学生たちの発言からは、従来の据え置き型テレビでリアルタイム視聴することがいまの学生の生活に合わないこと、情報源を目的に応じて使い分けていることが分かった。Z世代の多彩な情報源の中でも存在感があったのがSNSで、中でも10代後半を中心に利用率が高かったのがTikTokだった。政治系の動画も視聴されていたが、専門家からはショート動画ならではのミスリードやフェイクニュースの危険性の指摘も出た。 またZ世代の特徴とされがちな「タイパ(タイムパフォーマンス)」について、学生へのインタビューと文研の調査で実態に迫った。倍速視聴はすべてのコンテンツではなく、内容によって行われること、切り抜き動画の視聴については時間短縮だけが目的ではなく、編集した人の「面白いものを見せたい」という思いへの信頼も背景にあった。 最後に、学生たちから「これからのテレビ」に向けて提言があった。「テレビはストレスフリーになって」「テレビは謙虚になって」など、Z世代の合理的なメディア選択の対象に入るためのテレビへの期待と不満が明らかになった。
4 0 0 0 IR 「演歌・歌謡曲」にみる日本ポピュラー・ソング文化に関する考察 : ジャンル変遷史を中心に
- 著者
- 黄 逸雋
- 出版者
- 法政大学 (Hosei University)
- 巻号頁・発行日
- 2023
type:Thesis
4 0 0 0 OA The Kumamoto Dialect in Selected Mangas
- 著者
- Jana Sedlackova
- 出版者
- 学習院女子大学
- 雑誌
- The Gakushuin Journal of International Studies (ISSN:21884927)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.13-26, 2023-03
The period of “reinvention of the Japanese dialect” began toward the end of the 1970s; however, the changing attitude of the Japanese society toward dialects and its speakers became more visible in pop culture in the twenty-first century. I analyzed mangas where the characters use the Kumamoto dialect, and sought to answer three questions: what is the typical role of the dialect-speaking character?; how is the dialect used?; and how does it appear? I identified that the typical dialect-user is a school-age character who is young, with traits such as friendliness, eagerness, and the culture/tradition promoting function. Moreover, dialect is mostly used—publicly and privately—with hierarchically lower or equal classes. Finally, as the dialect is represented the most by grammatical and phonetic expressions, it is simplified for intelligibility.
4 0 0 0 OA 橋本遊廓の遊客と娼妓 : 遊客帳の分析から
- 著者
- 竹中 友里代
- 出版者
- 京都府立大学
- 雑誌
- 京都府立大学学術報告. 人文 (ISSN:18841732)
- 巻号頁・発行日
- no.73, pp.97-119, 2021-12-25