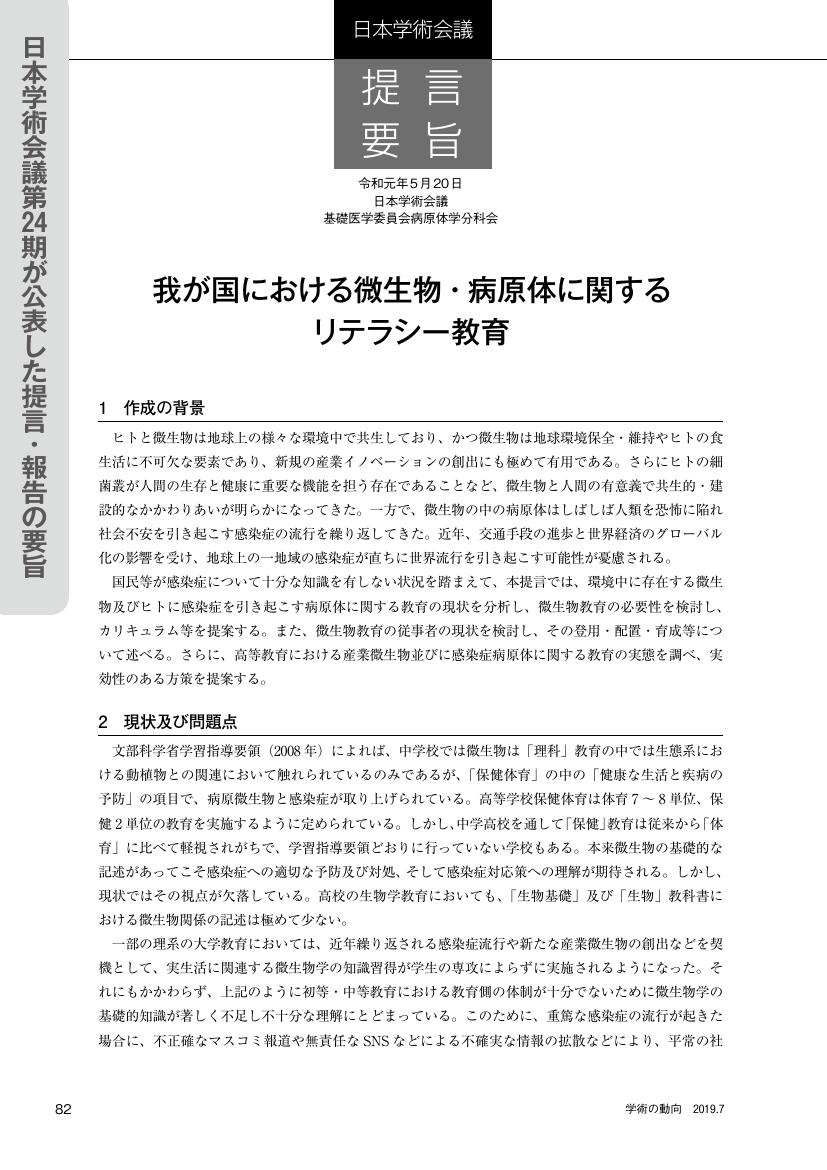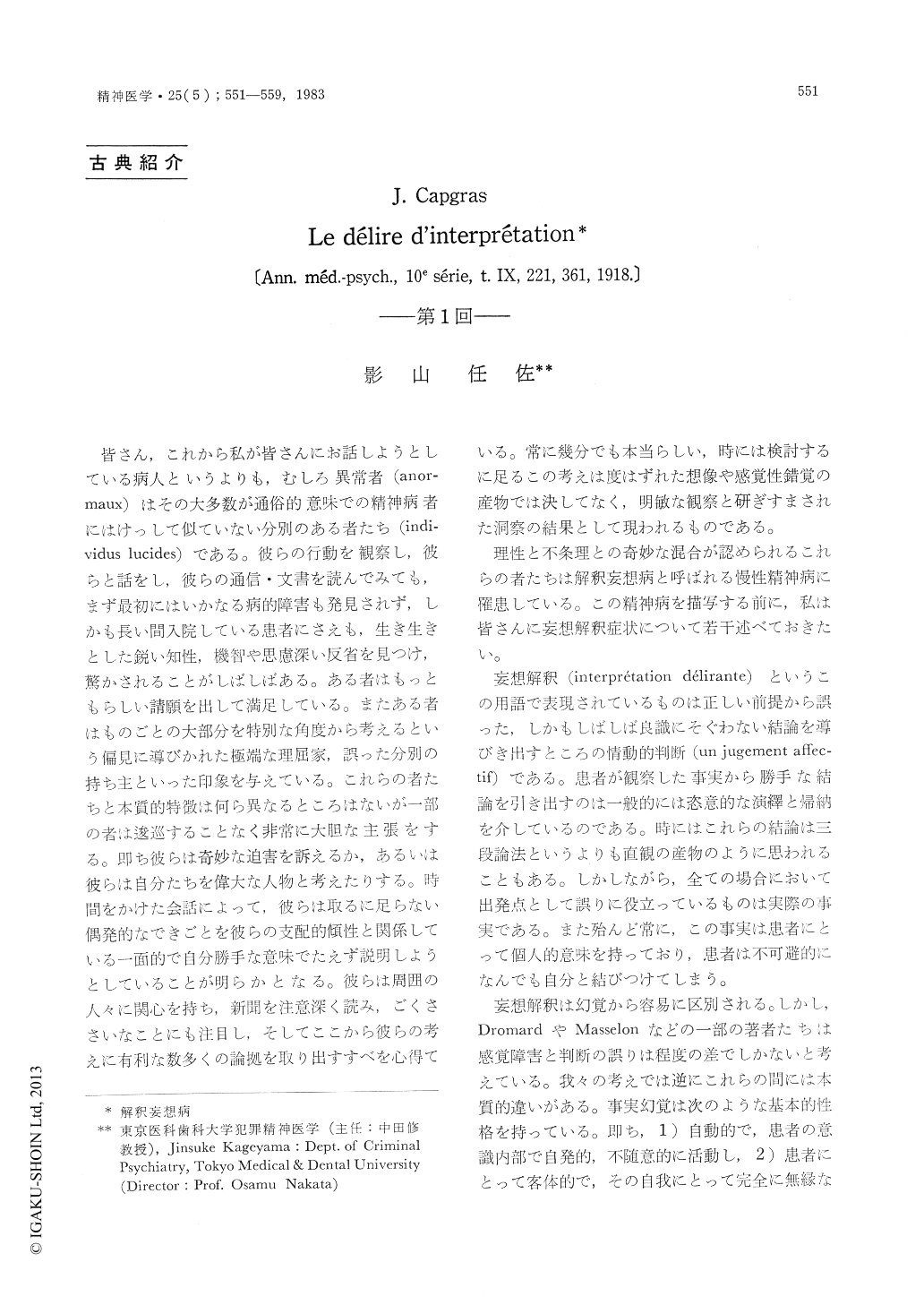4 0 0 0 OA 教育辞林
- 著者
- ヘンレ・キッドル, アレキサンドル・ジェー・スケーム 編
- 出版者
- 文部省編輯局
- 巻号頁・発行日
- vol.第11冊-21冊, 1885
4 0 0 0 OA MMX搭載火星周辺ダストモニターによる火星周辺のダスト環境計測
- 著者
- 小林 正規 奥平 修 千秋 博紀 和田 浩二 木村 宏 佐々木 晶 KOBAYASHI Masanori OKUDAIRA Osamu SENSHU Hiroki WADA Koji KIMURA Hiroshi SASAKI Sho
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構特別資料: 第17回「宇宙環境シンポジウム」講演論文集 = JAXA Special Publication: Proceedings of the 17th Spacecraft Environment Symposium (ISSN:24332232)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-SP-20-007, pp.35-46, 2021-01-29
第17回宇宙環境シンポジウム (2020年10月7日-8日. 宇宙航空研究開発機構(JAXA)オンライン会議)
4 0 0 0 OA コロナ問題をめぐる哲学と心理学の対話
- 著者
- 阿部 恒之 北村 英哉 原 塑
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- エモーション・スタディーズ (ISSN:21897425)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.Si, pp.31-41, 2021-03-22 (Released:2021-03-25)
- 参考文献数
- 8
This article is a modified record of “Philosophy and Psychology III: Contrastive approaches to the COVID-19 problems,” a public symposium held at the 84th annual convention of the Japanese Psychological Association on September 9, 2020 via webinar. Before this symposium, philosophers and psychologists joined and discussed emotions (2018) and justice (2019) to stimulate psychologists to have greater interest in and to devote more attention to philosophy. It had been noted that psychologists tend to be quite indifferent to philosophy despite the fact that historical origins of psychology as an established discipline can be traced back to philosophy and physiology. In the last symposium, we, two psychologists and a philosopher, discussed COVID-19 as a problem, particularly addressing topics of “freedom and publicness” and “the future of embodiment.” Through that discussion, results showed that philosophy and psychology can be complementary and productive for both.
4 0 0 0 OA 深層学習を用いたアボカドの追熟段階分類手法の提案
- 著者
- 杉本 隼斗 久野 文菜 谷口 航平 濱川 礼
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.1F3OS2a01, 2020 (Released:2020-06-19)
本研究では、アボカドの食べ頃判断支援を目的とした深層学習によるアボカドの追熟段階分類手法を提案する。アボカドは収穫後、追熟を経て食べ頃を迎える果物であり、一般消費者に食べ頃の見極めが要求される。アボカドの食べ頃を見極めるには、主に果皮の色や質感、硬度などが指標とされる。しかし、これらの指標は曖昧であり、熟練者でなければ正確な判断は困難である。 このような問題に対し、様々な追熟段階分類手法が提案されているが、特殊デバイスが必要とされる手法が多く、一般消費者が手軽に利用可能な手法は少ない。また、深層学習の画像認識による手法は提案されていない。深層学習は高精度な分類が期待され、一度データを学習させたモデルを利用すれば、ユーザは画像入力のみで出力結果を得ることが可能であるため、アボカドの追熟段階分類においても有効であると考えた。 そこで本研究では、深層学習を用いたアプローチによってアボカドの追熟段階分類を行った。深層学習はアボカドの果実検出にYOLOv3、追熟段階分類にVGG19を使用した。評価の結果、果実検出では高精度な検出が可能となったが、追熟段階分類では多くの改良点が残る結果となった。
4 0 0 0 OA 何が人を幸せにするか?経済的・社会的諸要因そして倫理の役割復活
- 著者
- 岡部 光明
- 出版者
- 明治学院大学国際学部
- 雑誌
- 明治学院大学国際学研究 = Meiji Gakuin review International & regional studies (ISSN:0918984X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.91-109, 2015-10-31
豊かさを測るため,これまで経済的尺度(経済成長率や一人あたりGDP)が重視されたが,近年その不十分さが強く意識されるに伴って「幸福」についての関心が上昇し,関連研究も増加している。本稿は,経済学的視点のほか,思想史,倫理学,心理学,脳科学などの知見も取り入れながら考察した試論であり,概略次の主張をしている:(1)幸福を考える場合,その深さや継続性に着目しつつ(a)気持ち良い生活(pleasant life),(b)良い生活(good life),(c)意義深い人生(meaningful life; eudaimonia)の3つに区分するのが適当である。(2)このうち(c)を支える要素として自律性,自信,積極性,人間の絆,人生の目的意識が重要であり,これらは徳倫理(virtue ethics)に相当程度関連している。(3)今後の公共政策運営においては,上記(a)にとどまらず(b)や(c)に関連する要素も考慮に入れる必要性と余地がある一方,人間のこれらの側面を高めようとする一つの新しい思想もみられ最近注目されている。(4)幸福とは何かについての探求は,幅広い学際的研究が不可欠であり今後その展開が期待される。
4 0 0 0 数学の自動化を推進するための機械学習を用いた定理自動証明手法
数学における証明のを計算機を用いて一部自動化することを目指します.本申請課題は,この最終目標に対する探索研究として,自然数に関する命題の証明の一部自動化を目指します.本申請課題では,証明が二者ゲームとして定式化でき,したがってゲーム AI の学習手法を証明ゲームに適用することで有能な自動証明アルゴリズムを錬成できるのではないか,というアイデアに基づいて研究を進めます.自動証明は様々なシステムが意図通りに動作することを保証するための要素技術として用いられており,その点で将来的に産業的なインパクト・貢献の可能性が期待できると考えています.
4 0 0 0 OA フェイクニュース伝播ネットワークの構造的異質性
- 著者
- 佐野 幸恵 Orr Levy 高安 秀樹 Shlomo Havlin 高安 美佐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 73.2 (ISSN:21890803)
- 巻号頁・発行日
- pp.2160, 2018 (Released:2019-10-28)
4 0 0 0 OA 背教者・不干斎ファビアンの生涯(補説)
- 著者
- 井手 勝美
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.23-31, 1978
本稿は若干の史料を補足して、旧稿「背教者・不千斎ファビアンの生涯」(広島工業大学研究紀要七-二)で解明できなかった彼の事蹟を明らかにしたものである。
4 0 0 0 OA 我が国における微生物・病原体に関するリテラシー教育
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.7, pp.7_82-7_83, 2019-07-01 (Released:2019-11-22)
4 0 0 0 —J. Capgras—解釈妄想病—第1回
皆さん,これから私が皆さんにお話しようとしている病人というよりも,むしろ異常者(anormaux)はその大多数が通俗的意味での精神病者にはけっして似ていない分別のある者たち(individus Iucides)である。彼らの行動を観察し,彼らと話をし,彼らの通信・文書を読んでみても,まず最初にはいかなる病的障害も発見されず,しかも長い間入院している患者にさえも,生き生きとした鋭い知性,機智や思慮深い反省を見つけ,驚かされることがしばしばある。ある者はもっともらしい請願を出して満足している。またある者はものごとの大部分を特別な角度から考えるという偏見に導びかれた極端な理屈家,誤った分別の持ち主といった印象を与えている。これらの者たちと本質的特徴は何ら異なるところはないが一部の者は逡巡することなく非常に大胆な主張をする。則ち彼らは奇妙な迫害を訴えるか,あるいは彼らは自分たちを偉大な人物と考えたりする。時間をかけた会話によって,彼らは取るに足らない偶発的なできごとを彼らの支配的傾性と関係している一面的で自分勝手な意味でたえず説明しようとしていることが明らかとなる。彼らは周囲の人々に関心を持ち,新聞を注意深く読み,ごくささいなことにも注目し,そしてここから彼らの考えに有利な数多くの論拠を取り出すすべを心得ている。常に幾分でも本当らしい,時には検討するに足るこの考えは度はずれた想像や感覚性錯覚の産物では決してなく,明敏な観察と研ぎすまされた洞察の結果として現われるものである。 理性と不条理との奇妙な混合が認められるこれらの者たちは解釈妄想病と呼ばれる慢性精神病に罹患している。この精神病を描写する前に,私は皆さんに妄想解釈症状について若干述べておきたい。
4 0 0 0 OA Cloningerの気質・性格モデルとBig Fiveモデルとの関連性
- 著者
- 国里 愛彦 山口 陽弘 鈴木 伸一
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.324-334, 2008-03-31
- 被引用文献数
- 3
現在盛んに研究がなされているパーソナリティモデルにCloningerの気質・性格モデルとBig Fiveモデルの2つのモデルがある。しかし,2つのモデル間の関連性についての研究は少ない。そこで,本研究は,気質・性格モデルとBig Fiveモデルとの関連を検討することを目的とした。大学生457名を対象にTemperament and Character lnventory(TCI)とBig Five尺度を実施した。その結果,TCIとBig Five尺度は強い関連を示し,気質・性格モデルはBig Fiveモデルの説明を行うことが可能であることが示唆された。また,外向性を除くBig Fiveモデルの各因子の説明には,気質だけでなく性格が必要であることが示唆された。最後に,気質・性格モデルの観点からBig Fiveモデルの各因子の特徴について論議された。
4 0 0 0 OA 〈実験社会心理学研究〉に関する研究
- 著者
- 矢守 克也
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.63-81, 2021 (Released:2021-03-04)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
本論文は,社会心理学における実験的研究について検討した展望論文である。特に,実験の概念をより広義なものへと拡張し,実験という手法が本来有する豊かなポテンシャルをより大きく引き出す方向で,実験社会心理学の領域を再構築することをねらいとした。一般に,典型的な実験室実験と文化・歴史的な視点を重視する現場研究との距離は非常に大きいと見なされている。しかし,中間部に,「アイヒマン実験」や「実験の史学」などを配置すると,両者の連続性を確認できる。その上で,実験社会心理学研究の拡張を2つの方向から構想した。第1は,草創期のグループ・ダイナミックスにおける実験研究がそうであったように,実験室ならではの生態学的特性を活かしつつ,人間の実存性や社会のリアルな生態に接近するための回路を設け,実験室実験に現場研究の長所を取り込む方向性である。第2は,「実験の史学」のように,現実社会を対象とした研究に,実験操作に匹敵する比較条件を設定するための仕組みを導入し,現場研究に実験室実験の美点を取り込む方向性である。こうした志向性を有する具体的な事例を社会心理学,歴史学,防災・減災研究の領域から紹介し,新たな実験社会心理学研究の構想を提示した。
4 0 0 0 IR 医療ソーシャルワーク業務と地域医療連携業務について:ソーシャルワーク属性による分析
- 著者
- 真嶋 智彦
- 出版者
- 東北福祉大学
- 雑誌
- 東北福祉大学研究紀要 = Bulletin of Tohoku Fukushi University
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.69-85, 2021-03-18
昨今,医療環境の変化に伴い,医療ソーシャルワーク業務は多様化し,医療ソーシャルワーカーの配属部門が,従来の医療福祉部門から地域医療連携部門へと変化してきているとされる。本研究では,病院の地域医療連携部門の業務と医療ソーシャルワーク業務の関係について,先行研究をもとに検討を行った。その結果,以下のことが明らかとなった。地域医療連携業務はその成立過程で,医療ソーシャルワーク業務と共通部門が複数あったため,医療ソーシャルワークの一部は地域医療連携業務に統合された。その後,医療状況の変化や地域医療連携業務多様化の影響を受け,医療ソーシャルワーカー業務内の比重に変化が窺われる。また,医療ソーシャルワーカーに対する,間接援助及びメゾレベル以上での活躍に社会的期待が高まっている。
4 0 0 0 OA 薬局薬剤師における薬学的疑義照会の意識調査
- 著者
- 鹿村 恵明 高橋 淳一 大山 明子 根岸 健一 伊集院 一成 上村 直樹 青山 隆夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.10, pp.1509-1518, 2011 (Released:2011-10-01)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 4
Community pharmacists can provide effective pharmaceutical care by questioning the physicians about their prescriptions. The regulatory authority (Ministry of Health, Labour and Welfare or the like) has been issuing instructions/advice to health insurance-covered pharmacies about the nature of questions to be asked to physicians under the national health insurance system. However, this practice has been facing similar kind of problems almost every year. To identify the reasons for repetition of the problems and facilitate proper application of drug therapy at hospitals, we recently examined the nature of questions asked to physicians by conducting a survey of 165 health insurance-covered pharmacies belonging to 8 district branches of the Japan Pharmaceutical Association. When the pharmacists were asked to express their view whether each of the 18 sample questions included in the past surveys was actually necessary, the most frequent answer from the respondents (n=1980) was “neutral” (42.9%), followed by “unnecessary” (29.0%) and “necessary” (26.6%). Further, 55.5% respondents answered that it is necessary to refer to publications of the concerned fields (guidelines, etc.) when questioning the prescriptions. However, the responses about the possible reasons for judging the necessity of the questions suggested that sometimes the pharmacists failed to understand the details of such publications. The results from this study suggest that a high percentage of community pharmacists believed that there was little need to ask questions about prescriptions if the suggestions made by the regulatory authority about the relevant questions were taken into account. Further, our study findings suggested that pharmacists working at clinics cannot present a clear-cut rationale for their judgment about the necessity of asking questions about prescriptions under the current circumstances where sufficient information collection and the evaluation of need for asking questions about prescriptions are not possible.
4 0 0 0 OA 計量的アプローチによる役割語の分類と抽出の試み テレビゲーム『ドラゴンクエスト3』を例に
- 著者
- 麻 子軒
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.103-116, 2019-06-20 (Released:2020-09-20)
- 参考文献数
- 15
役割語をテレビゲームという新しい言語資料を用いて,計量的アプローチで分類・抽出した.『ドラゴンクエスト3』のキャラクターの発話における代名詞や助詞などの特徴量をクラスター分析と特化係数で解析した結果,①格助詞「が/を」,副助詞「は」があまり用いられない「異人ことば」,②代名詞「あたし」,助動詞「ちゃう」,副助詞「ったら/なんて」,接続助詞「けれど」,終助詞「かしら/もの/わ/の/ね」,感動詞「きゃー/まあ/あら」が多用された「女ことば」,③特徴語が観察されない「中立ことば」,④代名詞「そなた/わし」,助動詞「じゃ/とる/である/まい」,副助詞「なぞ」,終助詞「のう/ぞい/ぞ」,感動詞「やれやれ」が多く見られる「老人ことば」,⑤代名詞「おめえ/オレ/あんた」,助動詞「やがる/ちまう/てやる」,副助詞「なんか」,終助詞「ぜ/い/さ」,感動詞「へい/おい」が特徴的な「男ことば」,⑥代名詞「ボク」,終助詞「よう/さ/や/なあ」,準体助詞「ん」,感動詞「わーい/ねえ」が多用された「少年ことば」の6つの分類を得た上,従来では注目されていない副助詞と接続助詞も役割語的要素である可能性を示した.
- 著者
- 田端 真弓
- 出版者
- 大分大学教育福祉科学部
- 雑誌
- 大分大学教育福祉科学部研究紀要 (ISSN:13450875)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.225-240, 2015-10
体育・保健体育科における「集団行動」は,戦前を起点とすることが指摘され,これまでにも体育授業で取り扱うことは妥当でないと批判されてきた。しかし,現行の学習指導要領にもその行動様式が含まれ,それらを補完するように文部科学省の手引きが発行されている。また,運動の特性を踏まえることなく行動様式を美化した授業展開が提案されることもある。本稿では戦後の体育関係者によって展開された「集団行動」をめぐる議論について明らかにし,「集団行動」が指導の対象とされる理由を検討する。これを受けて体育授業のあり方と収斂した。内容は以下のように集約される。「集団行動」の導入にはアメリカ進駐軍の指導とそれによる文部省の通達,教師たちの混乱,児童生徒のモラルのなさが関わっていた。当時の体育教師たちは戦前の教育の影響とそれによる戦後の衝撃から新しい指導法を生み出すことよりも,戦前の秩序運動や教練をモデルとする「集団行動」の指導に回帰することを要望した。これらは能率,安全,秩序など一定の論理により成り立っていた。一方で,歴史的反省,体育授業の本質,教師の快感や美意識に着目し,「集団行動」を批判,危倶する声もあった。これまでにこのような議論を経てきたが,学習指導要領とそれを補完する手引きによる指導の構造は現存している。体育授業は現在,「指導と評価の一体化」の域に到達している。それをめざした体育授業を展開させようとするならば,「集団行動」に費やす時間はないと考えられる。
4 0 0 0 OA 外務省設置の経緯-わが国外政機構の歴史的研究 (1)-
- 著者
- 三上 昭美
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1964, no.26, pp.1-21, 1964-07-01 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 91
- 著者
- 臼杵 陽
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:13412361)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.73-93, 2009-03-15
4 0 0 0 IR 「異類女房」としての綾波レイ(『新世紀エヴァンゲリオン』)とサン(『もののけ姫』)
- 著者
- 秋田 巌 Iwao AKITA 京都文教大学人間学部 KYOTO BUNKYO UNIVERSITY Department of Human Studies
- 雑誌
- 人間・文化・心 : 京都文教大学人間学部研究報告 = Reports from the Faculty of Human Studies, Kyoto Bunkyo University
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.39-48, 1998-07-20
Great success of "Neon Genesis Evangelion" and "The Princess Mononoke" in 1997 are fresh in our memories. I found these simultaneous great hits more than a mere accident, and have submitted to the viewpoint of looking upon these heroines as "Non-human Wives"; Rei Ayanami as a "Disappearing Anima" and San as an "Animal Wife." The slender, delicate and frail looking image of this beautiful girl Rei is a historically important image for the Japanese; as the inner female image held by Japanese men, and as the soul or the God image of both men and women. And, this image goes back to Princess Kaguya in Taketori Monogatari. We have a long history of "The Disappearing Anima" repressing "Animal Wives," just as demons and devils have been repressed by the Christian God. Interestingly enough, we have "Animal-possession" such as fox-possession, snake-possession and dog (god) -possession rather than demonomania in the West. One of the features of modem Japan may be the over exclusion of "E" ‒uncleanliness, impurity or defilement‒ and this is expressed as the flood of goods for the removal of odors and the antibacterial products. "The Disappearing Anima" always exists on a pedestal. The divinity being enshrined. Whereas the "Animal Wives" have been looked down upon and exist in a low place. The relationship of these two different "Non-human Wives" may be thought to represent the mentality of excluding "E."