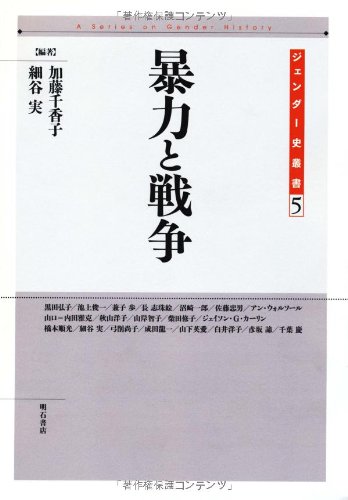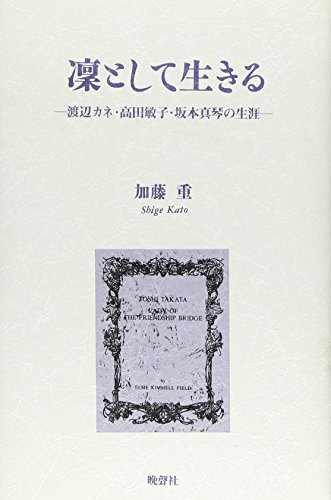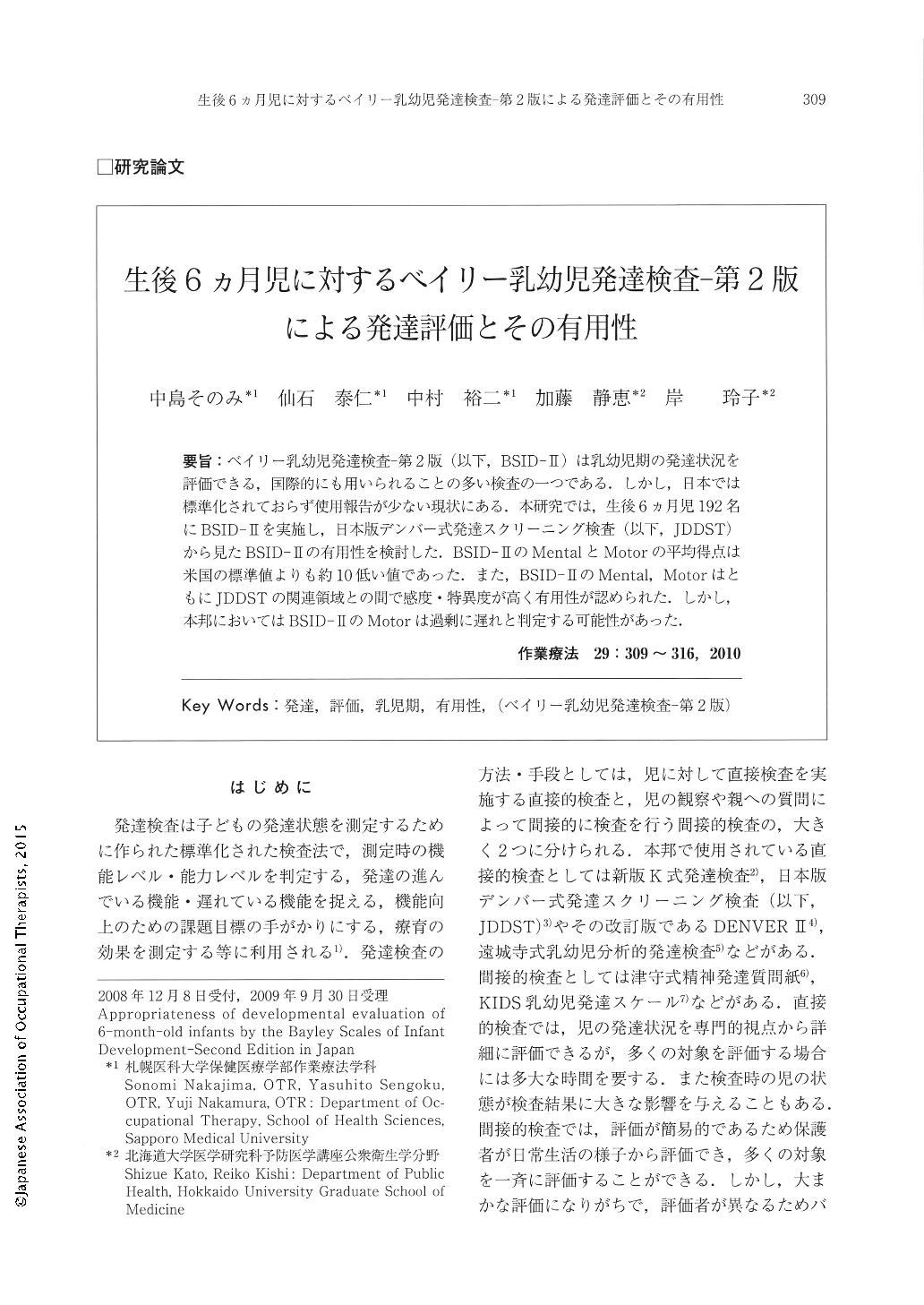1 0 0 0 OA チンパンジー4頭の脳形態の発達
- 著者
- 三上 章允 西村 剛 三輪 隆子 松井 三枝 田中 正之 友永 雅己 松沢 哲郎 鈴木 樹里 加藤 朗野 松林 清明 後藤 俊二 橋本 ちひろ
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第22回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.90, 2006 (Released:2007-02-14)
大人のチンパンジーの脳容量はヒトの3分の1に達しないが、300万年前の人類とほぼ同じサイズである。また、脳形態とその基本構造もチンパンジーとヒトで良く似ている。そこでチンパンジー脳の発達変化をMRI計測し検討した。[方法] 霊長類研究所において2000年に出生したアユム、クレオ、パルの3頭と2003年に出生したピコ、計4頭のチンパンジーを用いた。測定装置はGE製 Profile 0.2Tを用い、3Dグラディエントエコー法で計測した。データ解析にはDr_View(旭化成情報システム製)を用いた。[結果] (1)脳容量の増加は生後1年以内に急速に進行し、その後増加のスピードは鈍化した。(2)大脳を前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けて容量変化を見ると前頭葉の増加が最も著明であった。(3)MRIで高輝度の領域の大脳全体に占める比率は年齢とともにゆっくりと増加した。[考察] チンパンジーとヒトの大人の脳容量の差を用いてチンパンジーのデータを補正して比較すると、5歳までのチンパンジーの脳容量の増加曲線、高輝度領域に相当すると考えられる白質の増加曲線は、ヒトと良く似ていた。今回の計測結果はチンパンジーの大脳における髄鞘形成がゆっくりと進行することを示しており、大脳のゆっくりとした発達はチンパンジーの高次脳機能の発達に対応するものと考えられる。
- 著者
- 平山 昌男 加藤 順一 村上 雅仁 永田 安雄 傳 秋光
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, 2003-04-20
- 著者
- 加藤 はる 加藤 直樹 渡辺 邦友 上野 一惠 坂田 葉子 藤田 晃三
- 出版者
- 日本環境感染学会
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.12-17, 1995-10-20
- 参考文献数
- 14
3回の再発が認められた11歳の<I>Clostridium difficile</I>性腸炎例の計4回のエピソードにおける<I>C.difficile</I>分離株について, ウェスタンプロッティング (WB), パルスフィールドゲル電気泳動 (PFGE), およびpolymerase chain reaction (PCR) によるタイピングを用いて検討した.エピソード2の際の分離株はどの3つのタイピング法を用いてもエピソード1の際の分離株と同じタイプであり, エピソード2はエピソード1と同じ株による再燃と考えられた.しかし, エピソード3の際の分離株は3つのタイピング法でエピソード1および2の分離株と異なるタイプを示したことから, 新しい菌株による再感染であると考えられた.エピソード4の際に分離された菌株はWBタイピングではエピソード1と2の際に分離された菌株と異なり, さらにエピソード3からの分離株とも異なるタイプであった.しかし, エピソード4からの菌株はPFGEタイピングでは細菌のDNAが抽出過程で破壊されタイピングができず, PCRタイピングではエピソード1および2からの分離株とはminor bandに違いが認められたのみで, エピソード1と2の分離株と同じタイプに分類された.これらのことからエピソード4はさらに新しい菌株による感染と考えられた.Cd顔ae起因性腸炎では治療にいったん反応しても, 再発が多いことが治療上大きな問題となっている.タイピング法は, このような再発が同じ菌株による再燃なのか, 新しい菌株による再感染なのかの検討を可能にし, <I>C.difficile</I>感染の治療や予防を行ううえで非常に有用であると考えられた.
1 0 0 0 400m走後半の支持期における下肢関節のキネティクス的特徴
- 著者
- 平野 達也 加藤 彰浩 筒井 清次郎 木越 清信
- 出版者
- 日本学生陸上競技連合
- 雑誌
- 陸上競技研究 (ISSN:09199918)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.1, pp.26-35, 2016-03
1 0 0 0 OA 超音波と塩化カルシウムを用いたモノエタノールアミン溶液からの二酸化炭素の脱離
- 著者
- 藤原 達央 大川 浩一 加藤 貴宏 菅原 勝康
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.1, pp.1-7, 2019-01-31 (Released:2019-01-31)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 4
This study investigated an effective method to desorb CO2 from low-concentration (0.2 mol/L) monoethanolamine (MEA) solutions using calcium chloride (CaCl2) and ultrasound irradiation at 25 ºC. The pH value of the solution had a large influence on the desorption ratio of CO2 from MEA solution under ultrasound irradiation. CO2 was successfully desorbed up to pH8.2, and it was impossible to desorb CO2 at pH over 8.2. It was clarified that CO2 desorption by ultrasound irradiation is useful for the concentration of MEA solution of up to 2.0 mol/L, because the pH rises above 8.2 when the concentration of MEA solution is increased to above 2.0 mol/L. It also became evident that the addition of small amount of CaCl2 further increases the amount of CO2 desorbed during ultrasound irradiation.
- 著者
- 加藤 大智 Jochim Ryan 佐古田 良 岩田 祐之 Gomez Eduardo Valenzuela Jesus 橋口 義久
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.26, 2009
吸血性節足動物の唾液は、抗凝固、血管拡張、発痛抑制、抗炎症などの作用をもつ"生理活性物質のカクテル"で、これを宿主に注入することにより効率よく吸血行為を行っている。本研究では、中米から南米北部におけるシャーガス病の主要なベクターであるサシガメ<I>Triatoma (T.) dimidiata</I>の唾液腺遺伝子転写産物の網羅的解析により、新規生理活性物質の探索を行った。<I>T. dimidiata</I>唾液腺からmRNAを抽出、それを鋳型にcDNAライブラリーを作製し、無作為に464クローンの遺伝子転写産物の塩基配列を決定した。その結果、361クローン(77.8 %)が分泌タンパクをコードしており、このうち、89.2 %が低分子輸送タンパクであるリポカリンのファミリーに属するタンパクをコードしていた。特徴的なことに、分泌タンパクのうち、52.1 %が<I>T. protracta</I>唾液の主要なアレルゲンとして同定されているprocalinに相同性を示しており、このタンパクが吸血の際に重要な役割を果たしていることが示唆された。この他に、<I>T. dimidiata</I>の主な唾液成分として、コラーゲンおよびADP誘発性の血小板凝集阻害物質、トロンビン活性阻害物質、カリクレイン・キニン系の阻害物質、セリンプロテアーゼ阻害物質などと相同性を持つタンパクを同定することができた。本研究で得られた結果は、吸血性節足動物のユニークな吸血戦略を理解する上で有用な知見をもたらすものと考えられた。また、得られた遺伝子クローンから作製することができる組換えタンパクは、研究・検査試薬および新薬の素材分子として活用できるものと考えられた。
1 0 0 0 漂着ごみから推定される日本から流出する海洋浮遊ごみ
- 著者
- 岡野 多門 加藤 郁美
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会論文誌 (ISSN:18835856)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.25-37, 2015
海に流出した浮遊ごみの一部は海岸に漂着するため,漂着量は各国での固形廃棄物の管理体制の指標となる。ここでは日本からのごみの流出抑制を目的として,鳥取県の8海岸の延べ4 km区間で,8年間半の毎月の漂着ごみ量を測定した。その結果,漁業ごみが最も多く,ロープ,フロート,20 Lプラスチック容器の3種の年間平均漂着重量は約65 kg/(hm・y) であった。日本製漁具は少なかったが,飲料や洗剤,調味料容器,耐圧缶,およびライターの民生ごみの年間平均漂着重量は約28 kg/(hm・y) で,その約半分が日本のごみであった。最も深刻な日本ごみは小型のペットボトルで,近くの河川流域と海浜周辺で投棄されていた。この2つの投棄地からの漂着数の比は大型ペットボトルとタブ型飲料缶を説明変数とする重回帰分析で推定できる。これは漂着数と海浜での投棄数を推定するための初めての方法で,実効性のある排出防止対策の実施に利用できる。
1 0 0 0 IR <原著>BSRI日本語版による性役割タイプの分類
- 著者
- 加藤 知可子
- 出版者
- 県立広島大学
- 雑誌
- 広島県立保健福祉短期大学紀要 (ISSN:13420070)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.7-11, 1999-03
本研究では, BSRI日本語版を用いて被験者を女性型, 男性型, 両性具有型, 未分化型の性役割タイプに分類し生物的な性差(性別)との関係を検討した。調査対象は, 大学生, 専門学校生, 大学院生の男性95名, 女性100名, 合計195名である。調査では, BSRI日本語版による男性性得点と女性性得点の中央値分割にて性役割タイプに分類した。その結果, 性役割タイプの出現率では性差は認められなかった。つまり, 男性および女性の中性化が進んでいると推測する。
1 0 0 0 死亡個票から見た熊本県の胃癌死亡者の分析
- 著者
- 清元 晃 加藤 哲夫 大塚 宗臣 並川 和男 中村 弘 由布 雅夫 松本 孝一 光野 利英 大島 和海 仲村 保広
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.654-658, 1978
昭和45年から48年までの4年間の熊本県の胃癌死亡者の死亡個票を調査した.<br>総数2783名, 各年度ほぼ700名前後, 男女比は1.4:1と低く, 最多罹患年令層は70才台前半であつた. 官公立病院における死亡は約25%, 診療所では約20%, 自宅死亡者は漸減していたが約45%と半数近かつた. 期間不明を除いた2282名の80%弱の1794名が1年以内に死亡し, 5年以上生存したものは24名であつた. 死亡診断書記入医師の所属は官公立病院においては内科外科のみであり, 外科からの比率がふえていたが, 診療所及び自宅においては外科からの診断書(25%)より内科からの診断書(50%)が多く, その他の診療科からのものも10%前後認められた. 熊本県の胃癌死亡者には進行癌が多く見られ, この原因究明のための逆視的追求の必要性について論じた.
1 0 0 0 OA 橋爪大三郎著『性愛論』
- 著者
- 加藤 秀一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.361-370, 1997-12-30 (Released:2010-04-23)
踏み込んだ検討に移る前に, まず本書の内容を概観しておこう。『性愛論』は, 先にその一部を引用した短い序章を別とすれば, 全部で6つの章から成っている (以下, 「」内の部分は基本的に引用であり, 〈 〉の部分は, 著者の主張を評者の解釈を経て要約したことを示す。短い引用箇所については, あまりにも煩瑣になることを避けるため, 当該ページの挙示は省略する) 。第1章「猥褻論」と第3章「性関係論」は, もともとひとつながりの論文として書かれたものであり, 内容的に連続している。ここでは〈社会空間は性愛現象と非性愛現象とに分離している〉という社会存立の「公理」が解説されている。中にはさまれた第2章「性別論」では, 「規範としての性別」の成り立ちが原理的に説明されている。以上3つの章は, 性愛という現象に関する著者の見方の最も基礎的な部分を述べた, 原理論的な部分である。これに対し, 第4章「性愛倫理」ではキリスト教における性愛観の変遷が簡単に跡づけられ, 第5章「性愛倫理の模造」は, 戦後日本における性愛関係書のベストセラーの内容分析にあてられている。これら二つの章は前半で示された原理論的視点から歴史的事象を分析する応用編といえるだろう。さらに一書の締めくくりとして, 「性愛世界の彼岸」と名づけられた終章が置かれている。これら全編にわたって評者が疑問としたい点は多いが, 紙数の制約から, 本稿では本書の前半部分で展開された原理論的内容に視野を限定して, その中心線をたどりなおしてみることにしたい。上に記したように, 著者が提示する最も基本的な認識枠は, 〈性愛領域/非性愛領域〉という対である。これが「人間社会」に普遍的に妥当する分析枠として提示される。他方, 「性愛」の領域が限局されると同時に, その外部では, 「言語と権力」という他の媒介の流通性が高まる, とされる。次の箇所は, 本書のこのような理論的要諦を示しているだろう。「血縁に基づく親族秩序は, 事実としての性交渉や性愛関係の広がりを, ある一定の正当化手続によって婚姻とみなされるようになった配偶関係のなかに封じこめる。そしてまた逆に, そうした婚姻を間に挟んで水平に拡がる人びとの相互関係を, 性愛への志向を脱色され言語的・権力的な作用へと純化されたものとする。こうして社会空間は, 全域的な一種の透明性を獲得する。この透明性は, より遠隔に対してはたらく普遍的な作用力, すなわち言語や権力のはたらきを, 当該空間の端から端にまで容易に到達できるようなものとする (111頁) 。ここから直ちに二つの問題が生じる。第一に「性愛領域」の内容 (「非性愛領域」の内容に比重が置かれないのは, 本書のテーマからして当然であるから, 本稿では問わない), 第二にそれと非性愛領域との関係づけである。大まかに言って著者は, 第一の問題に対してはLévi-Straussの提示した概念法を再構成することで答え, 第二の問題に対しては独自の分析を展開している。こうした意味で, 本書は Lévi-Straussの親族構造論における方法と理論を拡張して, 性現象一般の普遍的構造の記述をめざす企てである, と言えるだろう。本書そのもののなかにはその通りの表現はみられないが, その中心的なアイデアをより厳密に展開したといえる別の論考 (「親族・家族・社会シスデム-人類学的交換理論の論理とその拡張」, 『橋爪大三郎コレクションII 性空間論』勁草書房) がその傍証となるだろう。評者の疑問は, 先の二つの問題-相互に切り離せるものではないから, 二重の, とするべきか-の全域に関わっている。第一に, 「性愛領域」に直接的な身体関係としての「性交渉」から, 「家族~親族」といった社会制度までが含まれているが, それを「性愛」の名の下に一括りにすることへの疑問。評者の見解では, ここでは橋爪氏は, Lévi-Straussの誤謬を拡大再生産してしまっていると思う。これと関連して第二に, 橋爪氏は, 「性愛領域」に含まれた諸制度にすでに流通している権力作用をうまく理論に織り込むことができなくなってしまった。以下, これらの問題について検討していく。
1 0 0 0 OA 子宮内膜細胞診, 組織診が診断の契機となった子宮内膜間質肉腫の 1 例
- 著者
- 牛島 倫世 山川 義寛 高越 優子 加藤 潔 岡田 英吉
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.280-284, 2009 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 12
背景 : 子宮内膜間質肉腫はまれな疾患で予後不良であり, 術前診断は困難である. 子宮内膜細胞診・組織診が診断の契機となった 1 例を報告する.症例 : 52 歳, 4 回経妊 2 回経産, 50 歳閉経. 主訴は不正性器出血. 経腟超音波で子宮体部に径 5.5 cm の腫瘤を認めた. 子宮内膜吸引細胞診陽性であり, 内膜生検にて間質細胞に著明な核異型と核分裂像を認め, 子宮内膜間質肉腫が疑われた. CT で腫瘤は辺縁が不均一に造影され, MRI では T2 強調像できわめて不均一であり, 出血性壊死を疑わせる所見であった. 病変は子宮内に限局しており, 腹式単純子宮全摘術・両側付属器摘出術を施行した. 病理所見では, 子宮内腔に広茎性ポリープ状腫瘤を認め, 多くの核分裂像を伴った多形性の腫瘍細胞からなっており, 脈管侵襲を認めた. 免疫染色では CD10, vimentin に陽性, cytokeratinAE1/AE3, SMA, S-100, ER に陰性であり, high-grade endometrial stromal sarcoma と診断された.結論 : 本症例では免疫染色を含む細胞診, 組織診が子宮内膜間質肉腫の診断に有用であった.
1 0 0 0 ふたつの文化のはざまから : 大正デモクラシーを生きた女
1 0 0 0 ふたつの文化のはざまから : 大正デモクラシーを生きた女
1 0 0 0 第3回マイコトキシン研究会一般講演要約
1 0 0 0 暴力と戦争
- 著者
- 加藤千香子 細谷実編著
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 凛として生きる : 渡辺カネ・高田敏子・坂本真琴の生涯
1 0 0 0 凛として生きる : 渡辺カネ・高田姉妹の生涯
- 著者
- 中島 そのみ 仙石 泰仁 中村 裕二 加藤 静恵 岸 玲子
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.309-316, 2010-06-15
要旨:ベイリー乳幼児発達検査一第2版(以下,BSID-Ⅱ)は乳幼児期の発達状況を評価できる,国際的にも用いられることの多い検査の一つである.しかし,日本では標準化されておらず使用報告が少ない現状にある.本研究では,生後6ヵ月児192名にBSID-Ⅱを実施し,日本版デンバー式発達スクリーニング検査(以下,JDDST)から見たBSID-Ⅱの有用性を検討した.BSID-ⅡのMentalとMotorの平均得点は米国の標準値よりも約10低い値であった.また,BSID-ⅡのMental,MotorはともにJDDSTの関連領域との間で感度・特異度が高く有用性が認められた.しかし,本邦においてはBSID-ⅡのMotorは過剰に遅れと判定する可能性があった.
- 著者
- X. イリヤル 山本 豊 加藤 治文 荒明 美奈子 黒岩 ゆかり 會沢 勝夫
- 出版者
- 日レ医誌
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.281-284, 1996
The cytotoxicity of PDT with ME2906 and Laser to P388 cells was examined. Cell viability was assayed by the MTT method. When the laser irradiated at 10J/cm<SUP>2</SUP> after incubation for 4 hours with 10μg/ml of ME2906, cell viability was not decreased but with 20 and 30μg/ml of ME2906, cell viabilities were 9 and 1.4% respectively. When the laser irradiated at 10J/cm<SUP>2</SUP> after incubation for 24 hours, cell viabilities were almost same as those of 4 hours incubation. ME2906 contents at 24 hours after drug administration at concentration of 10μg/ml measured 2.8×10<SUP>-9</SUP>μg/cell, and at 4 hours after drug administration at 20μg/ml measured 5.5×10<SUP>-9</SUP>μg/cell. These data showed that the cytotoxicity of PDT to P388 cells was dependent on the ME2906 intracellular accumulated contents but independent on laser doses.