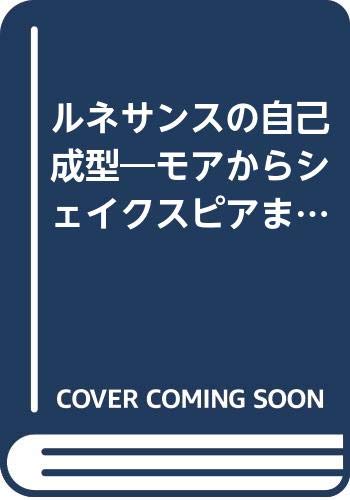1 0 0 0 OA 咀嚼が糖代謝に及ぼす影響
- 著者
- 橋本 和佳 百合 草誠 松田 秀人 高田 和夫 犬飼 敏博 土屋 智昭 吉田 真琴 清水 武藤
- 出版者
- Japanese Society for Mastication Science and Health Promotion
- 雑誌
- 日本咀嚼学会雑誌 (ISSN:09178090)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.52-59, 2007-05-31 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
今回著者らは, 日常のさまざまな咀嚼習慣のなかでの食物性状の選択という問題が生活習慣病発症に及ぼす影響を明らかにする目的で, ラットを用いて, 異なった性状の飼料での飼育時の糖代謝の違いを検討した.Wistar系ラットを4週齢時より, 成分は同一で固形状または粉末状と性状の異なる飼料のみで飼育し, 絶食後にグルコースを経口投与し, 血糖値の推移を検討した.その結果, グルコース投与後の血糖値は, 42週齢以前では両群間に有意差がなかったが, 45, 48, 51週齢時には有意差が認められ, すべて粉食群は固形食群より大きな値を示した.また, 血糖値の最大値は3つの週齢時とも粉食群は固形食群に比較して遅延して発現するとともに, 粉食群は血糖値の高い状態が持続した.また, 糖代謝に差異の認められた週齢時には, 両群間の体重にも差異が認められ, 粉食群が固形食群より大きな値を示した.これらのことより, 育成時における飼料の性状に伴う咀嚼機能の促進が成長後 (45週齢以降) の糖代謝の充進に寄与することが明らかとなった.また, 咀嚼習慣や食習慣に関する指導が生活習慣病予防や治療の一つとなる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 知的労働生産性向上のためのウェアラブル頭頸部冷却システムによる基幹脳活性法の研究
ストレスによる知的労働生産性低下の防止を狙いに、深部脳活動の減弱が暑熱環境暴露や高負荷印加状態でいかに注意機能を低下させるかについて神経生理学的方法に基づき調べ、頭頸部冷却刺激を中心とする深部脳賦活法を検討した。結果、注意機能維持に深部脳の高い定常的活動度と抑制・賦活パターンを呈する同期的活動が重要であり、頭頸部冷刺激はこの深部脳活動増強に寄与することを明らかにした。さらに、深部脳活動が最大となる条件を心理学的指標との相関において明らかにした。
1 0 0 0 OA Nissenのfundoplication術後患者に発症した成人特発性胃破裂の1例
- 著者
- 土居 幸司 荻原 菜緒 永縄 俊博 高田 英輝 中塩 達明 佐藤 榮作 山内 晶司
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.369-372, 2003-05-01
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
Nissenのfundoplicationは,逆流性食道炎を伴う食道裂孔ヘルニアなどに対し広く行われてきた手術法であるが,その後に胃破裂を来したという報告は少ない.今回我々はNissenのfundoplication術後に胃破裂を来した症例を経験したので報告する.症例は60歳の男性,約3年前に食道裂孔ヘルニアに対しNissenのfundoplicationを受けている.腹痛と腹部膨満感にて当院受診.来院時の腹部X線検査にて胃の著明な拡張を認めたが,処置中に突然,腹部の激痛を訴え,再度のX線検査にて多量のfree airを認めたため胃破裂と診断.緊急開腹手術を行ったところ,胃小彎側が破裂しており,腹腔内には食物残渣とともに可燃性のガスが貯留していた.何らかの原因により胃腸の通過障害が起こり,停滞した食物残渣からガスが発生したが,fundoplicationの逆流防止機構により内圧が上昇し,胃破裂に至ったと考えられた.
- 著者
- 佐藤 達雄 塩原 由紀江 大森 明文 芳野 未央子 久芳 慶子 高田 圭太 池田 由紀 元木 悟 小倉 秀一 工藤 光夫
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.303-307, 2009-07-15
- 参考文献数
- 13
黒色の液状マルチ資材が地温ならびにコマツナの生育,収量に及ぼす影響を明らかにするため,処理量を1,0.5,0.25 L・m<sup>−2</sup>区および無処理区の4水準3反復,播種日を2007年9月21日,10月5日,10月20日および2008年1月22日の4水準として組み合わせ,栽培試験を行った.その結果,液状マルチ資材は,散布量に関わらず無処理に比較して増収することが明らかになった.地下5 cmの温度を解析したところ,液状マルチ散布により最高地温は上昇するが,9月21日播種を除き最低地温は低下した.この現象はコマツナの生育初期に顕著であったが,生育に伴って,その差は小さくなった.播種後10日間の毎正時積算地温に有意な差は認められなかった.地温の日較差の増大はコマツナの増収に寄与した可能性が考えられた.<br>
1 0 0 0 OA グローバル化と地域景観・地域環境の変容・保全-紀伊半島の近現代に着目して
本研究では,グローバル化と地域景観・地域環境の変容について、特に紀伊半島における近現代を中心に検討した。その結果以下の諸点があきらかとなった。(1)1960年代後半からの外材供給の増大にともなう国内材供給量の低下は、十津川流域における植林地の変化に大きな影響を及ぼし、植林地伐採後の落葉広葉二次林景観の出現をもたらしている。(2)生活基盤が脆弱な紀伊半島和歌山県沿岸部では、近代を通じてグローバル化の2度の波があることが明らかとなった.このうち2度目は最近10年ほどの動きであり,明治期以降第2次大戦前までの1度目のグローバル化を基盤とした歴史的な地域性を引き継いでいる。(3)経済的な面でグローバル化の進行が顕著な日本社会ではあるが、高齢者個々の「生きられた世界」の構築には、地理的要素や地域の特殊性といった地域間の差異が大きく影響している。
本研究は、QuickBird, Coronaなどの高解像度衛星画像をベースとして,地理学・歴史学・考古学・第四紀学などが連携した文理融合的研究を通して,点から線さらに面への空間的視点,および,過去から現在あるいは現在から過去への時間的視点の両側面から,囲郭・集落(居住拠点跡),耕地・耕地跡(生産活動),水利用(灌漑水路跡),それらの空間的関係(施設配置,シルクロード,交通路),さらに放棄後の景観変化などを例として,中央アジアから中国,モンゴルにかけての乾燥・半乾燥地域を主な対象として,遺跡立地と景観復元に関わる方法論,衛星考古地理学的研究法を確立することを目的とした.2012年度は、2011年度に引き続き,モンゴル南部オムノゴビ県のサイリン・バルガスン遺跡および周辺地域において,モンゴル科学アカデミー考古研究所の協力を得て,研究分担者の白石を中心として、囲郭の詳細,灌漑水路跡の有無確認などの現地調査を8月に実施した.また、6月には、研究分担者の小方が「1960年代に撮影された偵察衛星写真の遺跡探査・歴史的景観復原における有用性」のタイトルで、京都大学で開催された日本文化財科学会第29回大会で、成果の一部を発表した。しかしながら、研究代表者相馬の予期せぬ急逝により当該研究の遂行が不可能となったため、残念ながら本研究課題は、8月11日をもって終了することとなった。
1 0 0 0 OA 屋号としての『満蒙』と満洲(1)への理解度
- 著者
- 高田 智之
- 出版者
- 共栄大学
- 雑誌
- 共栄大学研究論集 (ISSN:13480596)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.67-74, 2013-03-31
『満蒙』という76 年の歴史を持つ筆者の実家の老舗鮮魚店の屋号と、実家に保管されていた戦前の写真グラフなどを通して、内地の日本人として祖父と父が満洲(現・中国東北部)に対してどのような理解を得ていたかを考察した。一方、実家の店以外にも満洲にちなんだ屋号を持つ商店や旅館があることが分かり、それらの屋号の由来について経営者に聞いた。その結果、筆者の祖父や父を含め、彼らが満洲に対して繁栄、希望、懐古といったシンプルかつ独善的なイメージを抱いていたことが確認された。そのようなイメージは日本の傀儡国家・満洲国に代表される当時の満洲の実態とはかけ離れたものであるが、今日の尖閣諸島問題のような日中間の歴史認識の隔たりを理解する手掛かりを提供してくれる。
1 0 0 0 OA 高対話型おとりシステムの運用経験に関する考察
- 著者
- 澁谷 芳洋 小池 英樹 高田 哲司 安村 通晃 石井 威望
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.8, pp.1921-1930, 2004-08-15
インターネット利用人口は拡大しており,今日では個人,組織の双方においてネットワークの使用は欠かせないものとなりつつある.インターネットは多種多様なサービスを提供し,なくてはならないものになっているが,その半面,不正アクセスの問題も急増している.しかし実際の侵入がどのようなものであるかを認知する機会が少なく,見えない世界でのセキュリティに対する認識が難しい.そこで本論文では不正侵入対策の手段の1つとなっているおとりシステムに着目し,Honeynet Projectが提唱している高対話型として構築した.高対話型おとりシステムの特徴として,OSレベルでおとりを実現し,不正アクセス者に制限なく自由に行動させ,不正アクセス者に気づかれないように行動記録を取得,分析することにより,既知の攻撃方法のみならず,未知の脆弱性や行動を記録することが期待されている.しかし高対話型おとりシステムは概念が新しく,主としてその概念ばかり公開されており,具体的なシステム構築例および,運用結果,問題点についての公開情報が少ない.したがって本論文では高対話型おとりシステムを公開されている情報を参考に実際に構築,運用し,不足する機能を追加したうえでさらに運用を行った.その結果得られたデータおよび知見をもとにおとりシステムの持つ問題点および運用方法の提案を含め今後の課題について述べる.
1 0 0 0 ルネサンスの自己成型 : モアからシェイクスピアまで
- 著者
- S. グリーンブラット[著] 高田茂樹訳
- 出版者
- みすず書房
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 OA 無機ヒ素の無毒化処理技術を用いた慢性ヒ素中毒の予防と改善の研究
現在、無機ヒ素(iAs)の飲料水や土壌汚染からの大規模な慢性ヒ素中毒がアジア諸国で発生している。中毒の原因であるiAsの無毒化は、慢性ヒ素中毒の予防や根絶に寄与すると推測している。社会普及に繋がるiAsの無毒化技術を検討した。本研究から、酸化チタン光触媒、酢酸の存在下、光照射により、iAsは無毒化ヒ素であるアルセノベタイン(AsB)に変換された。この手法はヒ素汚染土壌や水の浄化に応用が期待される。海洋投棄モデルとしてAsBの海水中での挙動を検討した結果、短時間で海水中ヒ素濃度(2ppb)に安定的に到達し、この結果は究極の低コストプロセスとしてのAsBの海洋投棄の可能を示唆するものである。
1 0 0 0 OA 廃棄物を利用した生物易付着性コンクリートの開発と藻礁への応用
- 著者
- 佐藤 利夫 野中 資博 山本 廣基 高田 竜一 福田 康伴
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.469-480, 2003 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 41
2030年頃に予測されている世界食料危機に対応するためには, 日本は海産資源に頼らざるを得ない. 特に生産力が高い沿岸浅海域の増殖環境の整備が不可欠である. しかし, 日本の沿岸浅海域では環境破壊や水質汚濁等により水産資源の増殖に重要な藻場の消失が進行している. よって沿岸浅海域の環境保全と藻場の回復を行う技術開発が極めて重要である.沿岸環境を劣化させている一因として, 火力発電所から排出されるフライアッシュ (FA), クリンカーアッシュ (CL) の沿岸域への投棄, および, コンクリートの基本材料となる骨材 (砂利および砂) の沿岸域からの過量な採取がある.本研究の目的はFAおよびCLをコンクリートに混合して再利用し, さらに地場産業からの廃棄物である低品質ゼオライトおよび鉄分含量が多い鋳物廃砂 (鉄分) も混合して, 生物易付着性を付与した廃棄物利用コンクリートを開発し, これを人工藻礁として活用することである. これが成功すれば, 浅海生産環境の保全・修復および廃棄物の再資源化を同時に解決することが可能となる.まず, 配合材料が異なるPlain (通常のモルタル), FA & CL FA & CL+ゼオライト, FA & CL+鋳物廃砂, FA & CL+ゼオライト+鋳物廃砂モルタル供試体の5種類を作製し, 人工藻礁としての利用性を検討するため, 耐久性・強度を評価した・次にFA & CLモルタル供試体について有害物質の溶出試験を行い, 海洋環境や生物に対する安全性を評価した. 次いで各モルタル供試体を海水に浸漬し, 表面に形成された生物膜のバイオマスをATP量, クロロフィルa量およびFDA分解活性を測定することにより評価した.強度試験の結果, FA・CLおよび鋳物廃砂やゼオライトを混合した廃棄物利用コンクリートは, 人工藻礁として十分な強度を有することが明らかとなった. また溶出試験を行った結果, FAとCLを混合したモルタル供試体から重金属類および有機リンの溶出はほとんど認められず, 廃棄物利用コンクリートを藻礁として利用する上で安全性を確認する第一歩を踏み出すことができた.生物易付着性試験を行った結果, ゼオライトと鋳物廃砂 (鉄分) を配合した3系 (FA & CL+ゼオライト, EA & CL+鋳物廃砂, FA & CL+ゼオライト+鋳物廃砂) のATP量は, Plainと同等か多かった. クロロフィルa量は, FA & CL+鋳物廃砂>FA & CL+ゼオライト>FA & CL+ゼオライト+鋳物廃砂=FAamp;CL>Plainの順に多かった. FDA分解活性はPlainと各系に有意な差は見られなかった. 以上の結果から, FA・CLおよび鋳物廃砂 (鉄分) やゼオライトを混合した廃棄物利用コンクリートは, 生物の付着性も良好であり, 特に藻類の著しい増加が見られ, 人工藻礁として利用できる可能性が高いことが示された.
- 著者
- 高田
- 出版者
- 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, 1966-08-25
1 0 0 0 OA 日本と途上国の看護技術の差異(中国)
- 著者
- 辻村 弘美 森 淑江 高田 恵子 宮越 幸代
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.51-58, 2009-02-01 (Released:2009-03-13)
- 参考文献数
- 13
【背景・目的】 看護は各国の様々な背景や状態により異なると考えられる. 中国で活動した青年海外協力隊員の面接調査と国際協力機構への報告書を分析し, その差異を明らかにすることで, 国際看護協力における示唆を得る. 【対象と方法】 看護師隊員4名の報告書計20冊と本人への面接結果を対象とし, 日本の看護と異なる点を抽出した. 【結 果】 「臨地実習において学生が行う基本的な看護技術」の80項目中, 日本と異なる看護に関する記述は41項目で, 対象者全員が差異があると述べた看護は, 「創傷管理技術」, 「与薬の技術」, 「身の回りの援助は家族が行う」, 「看護記録」であった. 4名中3名が差異があると述べた看護は, 「膀胱内留置カテーテル法」, 「点滴静脈内注射・中心静脈栄養管理」, 「手洗い」などであった. 【結 論】 日本と中国の違いが示唆されたので, 中国での看護技術の教育や臨床での状況について把握していく.
1 0 0 0 OA 高齢期在宅ケアを支える地域福祉システム構築に関する基礎的研究と市民学習への参画
- 著者
- 高田 知恵子 高田 利武
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.378-379, 1986-08-20
- 著者
- 鈴木 茂忠 宮尾 嶽雄 西沢 寿晃 高田 靖司
- 出版者
- 信州大学農学部
- 雑誌
- 信州大学農学部紀要 (ISSN:05830621)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.p147-177, 1977-12
- 被引用文献数
- 4
Investigation is running on since April 1975 in order to make clear the food habit of the Japanese marten, Martes melampus melampus on the eastern slope of the Mt. Kiso-Komagatake. In view of the results so far achieved, the authors attempted to make clear the food habit to examine scat samples, which were collected in the upper part of low mountaineous zone (1,200-1,600m above the sea level : we called "the A zone") and the sub-alpine zone (1,700-2,600m above the sea level : we called "the B zone") on the eastern slope of the Mt. Kiso-Komagatake from the end of March 1976 to the end of January 1977. In the present paper, especially the authors will be discussed on the following several points : i) change of food habit from autumn to winter in each year of 1975 and 1976 in the A zone. , ii) the change throughout the year in the A zone, and iii) difference of food habit between the A and B zones. The results obtained were summarized as follows 1) The number of scats collected in the A zone was less amount since August and thereafter its number suddenly increased from September. However, the authors could not be clear what had caused the results. 2) In the A zone, food habit from March to June seemed to be dependent on animal diet, while at the time from September to January of succeeding year, it may be dependent essentially on vegetable diet rather than animal. And both animal and vegetable were eaten in July and August. In the B zone, on the other hand, there was scarcely any scat which contained only animal component and scat containning vegetable component or vegetable and animal were commonly found from September to December. 3) Food habit was dependent on animal diet, namely, Lepus brachyurus from March to June in the A zone. 4) There was scarcely any scat which contained only animal and that containning vegetable component or vegetable and animal component were commonly found from September to December in the A zone. Food component in scat from July to August would be intermediate before June and after September within a year. 5) Kinds of vegetable diet eaten by the Japanese marten were Rubus, Pari-etales (Actinidia) and Sorbus in July and August, in September and October, and in November and January, respectively. 6) Sorbus was mainly eaten from November to January in 1976 as a vegetable diet, which had not been found at all in the previous report of 1976 (SUZUKI, MIYAO et al) in the A zone. It seemed to be considered that the lower temperature during June to September might cause the difference of kinds in vegetable diet among 1975 and 1976. 7) Lepus brachyurus and murine rodents were the most important as an animal diet in the A zone and the mutual compensatory relation as a companion diet would be recognized among two kinds of animals, that is, the higher the frequency of appearance of the murine rodents, the lower the L. brachyurus occurred and the frequency relation was vice versa. These tendencies may suggest that the Japanese marten may attack the animal as a density-dependent factor and the Japanese marten may be used to eat the animal which increased the population density. 8) Frequency of scat which contained animal component (L. brachyurus or Coleopterous insect) became higher in July and August and the component changed to both animal and vegetable in September and then it reached about 50% for vegetable diet (Sorbus) in the B zone. 9) Animal diet was much weight rather than vegetable in the B zone compar-ing with the diet in the A zone. 10) Main animal diet was L. brachyurus in the B zone.
- 著者
- 鈴木 茂忠 宮尾 嶽雄 西沢 寿晃 高田 靖司
- 出版者
- 信州大学農学部
- 雑誌
- 信州大学農学部紀要 (ISSN:05830621)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.p47-79, 1978-07
Investigation has been made from May 1975 to January 1977 in order to make clear the food habit of the Japanese serow, Capricornis crispus on eastern slope of the Mt. Kiso-Komagatake, where the University Forest in the Faculty of Agriculture, Shinshu University expands. The investigating area is a low temperate zone and is enveloped in natural forest in upper part of low mountaineous zone (1,200-1,600m above the sea level). Seasonal change of food plants was clear up by analyzing the plant traces eaten by the Japanese serow. This analysis didn't express quantitative estimation of plant eaten by the animal, but identification of plant, namely, qualitative list of plant species. Further, there was less data obtained from March to April and we were obliged to omit it. The results obtained were summarized as follows (1) The Japanese serow was used to bite tip of herbs, young trees and shrubs off and the animal seems not to be grazing herbivore, but browsing herbivore or snip feeder. (2) Total 189 plant species were listed up as the food of the Japanese serow, among them, 94 species (27 families) for herb ; 85 species (29 families) for broadleaf tree ; 7 species (2 families) for coniferous tree ; and 3 species (1 family) for bamboo grass, respectively. The number of species eaten by the Japanese serow reached to maximum in July (106 species) and thereafter down to minimum in November. (3) Number of plant species of herb and broad-leaf tree was divided into a half in each from May to November and the two plant groups should become themain food enough to feed at this time. While, ever-green coniferous tree and bamboo grass might be added to the two plant groups during winter from December to February. Number of herb species decreased suddenly and broad-leaf tree, therfore, might act an important role on food and percentage utility of broad-leaf reached on 83.1% at the time of February. On the other hand, the ever-green coniferous tree was down to 5% and 2% for bamboo grass. In the investigating area, there was so small amount of biomass for ever-green coniferous tree that the tree seemed to be a secondary food. (4) Plants feeded on each month throughout a year (but March and April could not be observed yet) were as follows : Hydrangea paniculata, H. cuspidata, H. macrophylla, Rubus kinashii, R. rnorifolius, Euonymus sieboldiana, Helwingia japonica, Clethra barbinervis, Sambucus sieboldiana and Viburnum furcatam. Above 10 species were all deciduous broad-leaf tree and the Japanese serow were used to feed on twings and leaf during spring to autumn and on twigs with winter bud. Moreover, plants feeded for the most part within a year were as follows Polygonum reynoutria, Clematis stans, Cirsium tanakae, Artemisia vulgaris, and Vitis coignetiae. It may be considered that these two sorts of plant species shall become a fundamental food resource for the Japanese serow in the area. (5) Petasites japonicus, Trillium tschonoskii, T. apetalon and Paris tetraphylla, which expand new green leaves to be the first to do other plants at the time of early spring may play a compensatory role upon many species of food plants feeded throughout a year. (6) Various species of herb and broad-leaf tree were feeded during summer, such as the plants mentioned (4) and Heracleum lanatum, Angelica multisecta, Cacaria hastata, Ainsliaea acerifolia, Eupatrium sachalinense, Elatostemma involuc-ratum and Boehmeria tricuspis as well. (7) Leaf of Petasites japonicus, fall down leaves of broad-leaf tree, dried herbs and nuts of Quercus crispula which were feeded during the late autumn must become a major food at the only short time of pass through autumn to winter. (8) Twigs and leaves of ever-green coniferous tree and bamboo grass which were feeded during only winter season (December to February), will supply for food in winter. In this period, the Japanese serow would usually not to be enough to feed the plant mentioned (4) and ever-green coniferous tree and bamboo grass seemed to be a suitable food for keeping hunger away. (9) Some poisonous plants were rearely feeded such as Scapolia japonica, Aco-nitum japonicum, Aquilegia buergeriana, Veratrum stamineum, Pieris elliptica, Aesculus turbinata and Buddleja insignis.(10) Plant species which did not remain traces eaten by the Japanese serow in the investigating area were as follows : Rhododendron degronianum, R. japonicum, Macleya cordata, Convallaria majalis, Shortia soldanelloides, Arisaema, Matteuccia struthiopteris, Blechnum niponicum etc.
- 著者
- 蔵口 雅彦 湯元 美樹 高田 賢治 津田 邦男
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ED, 電子デバイス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.81, pp.37-40, 2009-06-04
- 参考文献数
- 8
GaN系電子デバイスにおいて特性向上を図るため、ゲートリセス構造が有望である。窒化物半導体ではウエットエッチングによる精密なエッチングが難しいため、リセス構造形成のためには低ダメージなドライエッチング技術が求められる。本研究では、BCl_3とCl_2の混合ガスを用いたICP-RIEにより、エッチングの低ダメージ化を検討した。その結果、BCl_3とCl_2の混合ガスにより低バイアスパワーで表面モフォロジーが維持できることが分かった。また、表面モフォロジーが維持できる範囲内では、Cl_2/BCl_3比を高くすることでAlGaNを効率よくエッチングができ、BとClの半導体層への侵入量を抑制できることが分かった。
1 0 0 0 OA 高齢者の口腔機能の評価と管理のシステム化に関する研究
- 著者
- 武井 典子 藤本 篤士 木本 恵美子 竹中 彰治 福島 正義 奥瀬 敏之 岩久 正明 石川 正夫 高田 康二
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.384-396, 2009-03-31 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
近年, 軽度の要介護高齢者の増加が厚生労働省より指摘され, 平成18年度の介護保険制度の改正では, 介護予防として口腔機能の向上が位置づけられた。また, 平成20年度の「後期高齢者医療制度」では, 食べる・話す・笑う機能を低下させないために「口腔機能の評価と管理」が位置づけられた。しかし, どちらも総合的な評価法や具体的な管理方法は, 社会科学的施策として確立されていない。このような現状から, 著者らは, 自立から要介護までのすべての高齢者のための介護状態の予防・軽減, QOLの向上などを目指した安全で有効な口腔機能の評価と管理のシステムの開発を試行し, 広く社会科学的に合理的な施策として実現すべく検討を試みてきた。今回はその第1報として, 自立高齢者を対象に, 口腔機能の総合的な検査法, その結果に基づいた改善法, その実施の有効性についての評価法を試行検討した。対象者は, 札幌市の某ケアハウスに入所している自立高齢者91名である。口腔機能を総合的に評価するために, 口腔の周り, 口腔の入り口 (咀嚼), 口腔の奥 (嚥下), 口腔の清潔度の4つのカテゴリーに分けて行った。その結果を活用して改善法を提案・実施・評価を行った。その結果, 咀嚼力の判定, 唾液湿潤度検査, 反復唾液嚥下テスト, オーラルデイアドコキネシス, カンジダ検査が有意に改善したことにより, 今回試作したシステムは, 自立高齢者の口腔機能の評価と向上に役立つ可能性が示唆された。