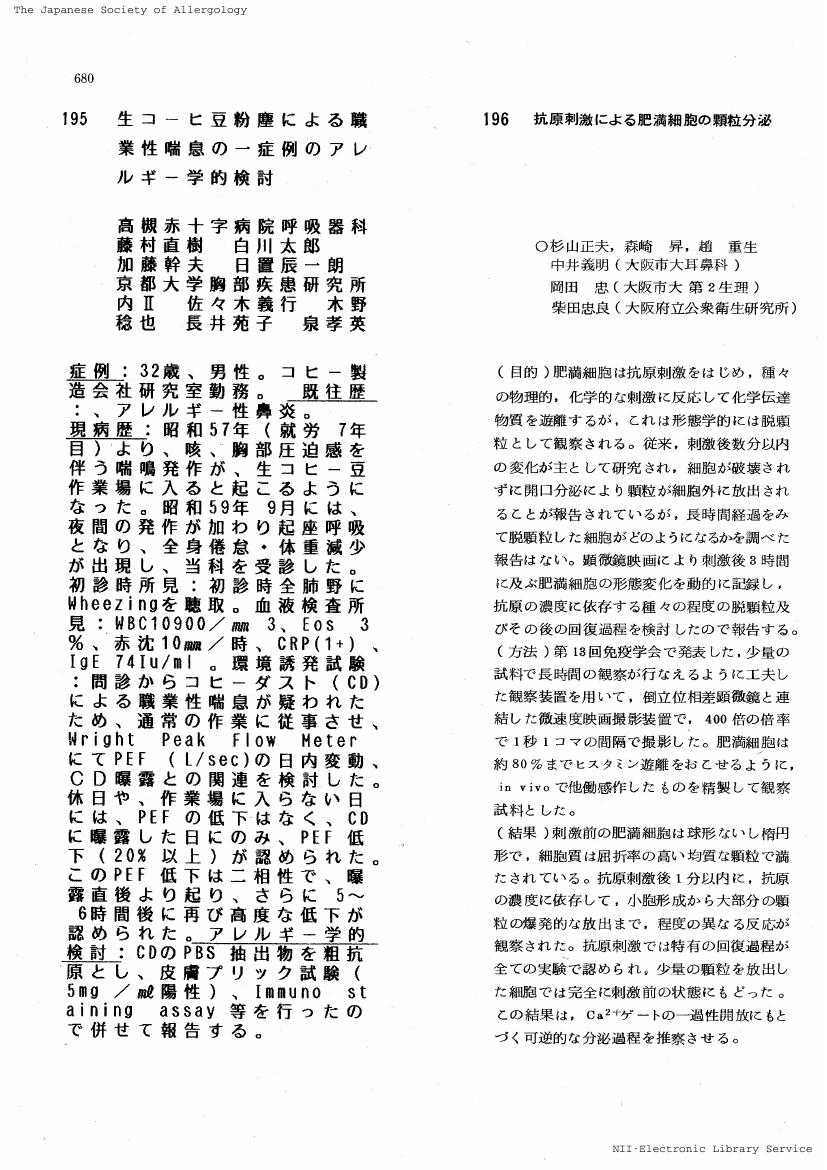- 著者
- Daisaku Nishimoto Rie Ibusuki Ippei Shimoshikiryo Kenichi Shibuya Shiroh Tanoue Chihaya Koriyama Toshiro Takezaki Isao Oze Hidemi Ito Asahi Hishida Takashi Tamura Yasufumi Kato Yudai Tamada Yuichiro Nishida Chisato Shimanoe Sadao Suzuki Takeshi Nishiyama Etsuko Ozaki Satomi Tomida Kiyonori Kuriki Naoko Miyagawa Keiko Kondo Kokichi Arisawa Takeshi Watanabe Hiroaki Ikezaki Jun Otonari Kenji Wakai Keitaro Matsuo
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20220354, (Released:2023-11-04)
- 参考文献数
- 35
Background: Improving diets requires an awareness of the need to limit foods for which excessive consumption is a health problem. Since there are limited reports on the link between this awareness and mortality risk, we examined the association between awareness of limiting food intake (energy, fat, and sweets) and all-cause mortality in a Japanese cohort study.Methods: Participants comprised 58,772 residents (27,294 men; 31,478 women) aged 35–69 years who completed baseline surveys of the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study from 2004 to 2014. Hazard ratios (HRs) for all-cause mortality and 95% confidence intervals (CIs) were estimated by sex using a Cox proportional hazard model, with adjustment for related factors. Mediation analysis with fat intake as a mediator was also conducted.Results: The mean follow-up period was 11 years and 2,516 people died. Estimated energy and fat intakes according to the Food Frequency Questionnaire were lower in those with awareness of limiting food intake than in those without this awareness. Women with awareness of limiting fat intake showed a significant decrease in mortality risk (HR=0.73; 95% CI, 0.55 to 0.94). Mediation analysis revealed that this association was due to the direct effect of the awareness of limiting fat intake and that the total effect was not mediated by actual fat intake. Awareness of limiting energy or sweets intake was not related to mortality risk reduction.Conclusion: Awareness of limiting food intake had a limited effect on reducing all-cause mortality risk.
- 著者
- 鈴木 克哉
- 出版者
- 環境社会学会
- 雑誌
- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.55-69, 2008-11-15 (Released:2018-12-18)
- 被引用文献数
- 6
近年,野生動物と人間活動との軋礫が世界各地で問題になっている。しかし日本では,加害動物による人間活動への影響量の軽減手法に関する技術的側面やその普及論が注目されがちであり,被害を受ける側である地域住民の「被害認識」が管理政策に取り入れられることはほとんどなかった。一方,この分野で先進的な欧米では,野生動物と人の軋礫問題において,さまざまな利害関係者間の相互関係をも調整対象とする軋礫管理(wildlife conflict management)の視点が注目されている。そこで本稿では,下北半島のニホンザルによる農作物被害問題を事例に,「被害認識」の形成要因として対人関係に着目した。その結果,被害農家は日常レベルにおいて許容を伴う複雑な「被害認識」を持っているが,被害経験を共有しない他者と対峙する場面では,サルに対する否定的価値観だけが表出されやすいこと,またそのような否定的価値観は地域社会において先鋭化され,捕獲をめぐる意見に収斂されやすいことが明らかになった。しかし,ニホンザルの農作物被害軽減に向けては,捕獲が必ずしも有効な手法ではなく,このような場合,施策をめぐって異なる価値観を持つ利害関係者間で意見の対立が生じ,獣害が社会問題化しやすい状況にある。今後,さまざまな獣害問題を解消するためには,従来の生物学的なアプローチに,それぞれの利害関係者の認識構造の把握や異なる価値観の調整手法に関する社会科学的なアプローチを融合させる方法がある。
1 0 0 0 OA 日本における国家計量標準とその供給体制:質量及びその関連量―力学量―
- 著者
- 大岩 彰
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.313-320, 2009-04-10 (Released:2022-05-27)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA オールセラミックカンチレバーブリッジの生存率と合併症:文献的レビュー
- 著者
- 矢谷 博文
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.209-224, 2020 (Released:2020-08-13)
- 参考文献数
- 56
目的:オールセラミックカンチレバーブリッジの生存率,成功率と合併症に関する系統的文献レビューを行い,評価すること.方法:オールセラミックカンチレバーブリッジの生存率,成功率,失敗のリスクファクターならびに合併症について記載された文献について,適切なMeSHの選択と包含基準の設定を行ったうえで,PubMedからコンピュータオンライン検索を行った.検索された文献の抄録を精読してさらに文献を絞り込み,最終的に15論文を選択し,レビューを行った.結果:得られた結果は以下のとおりである:1)生存率と成功率の考察は,異なる10のコホートの患者302人,ブリッジ381個の臨床成績を対象とした,2)MIを具現化する少数歯欠損補綴法としてのカンチレバーブリッジ,特に接着カンチレバーブリッジの生存率,成功率は高く,2リテーナー型の接着ブリッジよりも優れた臨床成績が得られている,3)症例選択はカンチレバーブリッジ成功の重要な要素であり,欠損部位としては,上顎側切歯,上顎中切歯,下顎切歯,上下顎小臼歯が適しており,欠損歯数は1歯で支台歯は生活歯であることが望ましい,4)使用材料としては,最近はガラスセラミックスに代わって高密度焼結型ジルコニアが用いられるようになっており,材料として最も適切と考えられる,5)合併症の出現率は総じて低く,特に生物学的合併症の出現頻度はきわめて低く,ほとんどが脱離をはじめとする技術的合併症である,6)接着カンチレバーブリッジを成功に導くためには,2リテーナー型接着ブリッジにおいて確立された接着技法を遵守することが重要であり,装着にはMDP含有の歯科用接着材が適している.結論:オールセラミックカンチレバーブリッジ,特に接着カンチレバーブリッジの生存率,成功率は高く,また従来型2リテーナー型ブリッジを上回る利点を多く有し,メタルフレームを用いたカンチレバーブリッジとともに少数歯欠損補綴法の1オプションに加えられるべきである.
1 0 0 0 OA 195 生コーヒー豆粉塵による職業性喘息の一症例のアレルギー学的検討
1 0 0 0 OA Collagen Content and Collagen Fiber Architecture in the Skin of Shamo Chicken, a Japanese Game Fowl
- 著者
- Shotaro Nishimura Sayaka Arai Yoshinao Z Hosaka
- 出版者
- Japan Poultry Science Association
- 雑誌
- The Journal of Poultry Science (ISSN:13467395)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.2023026, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 13
Collagen content and collagen fiber architecture in the skin of Shamo chickens were compared between sexes and body parts. Cervical, thoracic, dorsal, femoral, and crural skin samples were collected and their collagen content was analyzed. Collagen fiber specimens were prepared for scanning electron microscopy using the cell maceration method with a NaOH solution. Sex differences in collagen content were only observed in the femoral skin of mature chickens, but not in 10-week-old chicks. The difference in collagen content between body parts was obvious; femoral and crural skin had higher collagen content than those of other parts in both sexes. Scanning electron microscopy indicated that the collagen fiber architecture was quite different between the superficial and deep layers in the dermis, with the former consisting of loosely tangled band-like collagen fibers, and the latter composed of thick and dense layers of collagen bundles in a parallel arrangement. The width of collagen fibers in the superficial layer of the dermis differed between sexes in the dorsal, femoral, and crural skin. From these results, it is likely that the difference in collagen content in the femoral skin is not due to sex hormones but other factors, such as mechanical stimulation in daily activity. Additionally, collagen fiber width in the superficial layer is likely related to the difference in collagen content between sexes and between body parts.
- 著者
- 田井 郁久雄
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.56-75, 2001-07-01 (Released:2017-05-24)
岡山市の中心地域に位置する地区図書館である岡山市立幸町図書館では,2000年4月から,火曜日〜金曜日の開館時間を2時間延長した。本稿では,1999年度と2000年度の利用統計を比較して,開館時間延長のサービス効果を検証した。開館時間は長ければよいというものではない。延長に見合うだけの一定の効果がなければ成功したとはいえない。幸町図書館の場合はどうだったか,期待したほどの効果がなかったとすれば何が問題なのか,サービスの向上のための方策として開館時間の延長の優先度をどう考えるべきか等の問題について考察した。
1 0 0 0 OA 性教育のポリティクス 公私二元論問題と性教育論争
- 著者
- 広瀬 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.4, pp.526-538, 2022 (Released:2023-04-25)
- 参考文献数
- 36
少数派の親の意思をどのように位置づけるかという公私二元論問題抜きに性教育論争を理解することはできない。宗教が扱ってきた「性」、また近代社会が私的なことがらとした「性」を、公教育で積極的に扱うのが性教育だからだ。教育内容のみならず性教育の実施そのものに同意できない宗教関係者などからの批判が登場して性教育論争となる。本稿では、イギリス、アメリカおよび日本の性教育論争の特徴とこの論点への対処方法を整理した。
- 著者
- Karumuri ASHOK Zhaoyong GUAN Toshio YAMAGATA
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.41-56, 2003 (Released:2003-03-18)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 187 214
Using observed sea surface temperature data from 1871-1998, and observed wind data from 1958-1998, it is confirmed that the recently discovered Indian Ocean Dipole (IOD) is a physical entity. Many IOD events are shown to occur independently of the El Niño. By estimating the contribution from an appropriate El Niño index based on sea surface temperature anomaly in the eastern Pacific, it is shown that the major fraction of the IOD Mode Index is due to the regional processes within the Indian Ocean. Our circulation analysis shows that the Walker circulation during the pure IOD events over the Indian/ Pacific Ocean is distinctly different from that during the El Niño events. Our power spectrum analysis, and wavelet power spectrum analysis show that the periodicities of El Niño and IOD events are different. The results from the wavelet coherence analysis show that, during the periods when strong and frequent IOD events occurred, the Indian Ocean Dipole Mode Index is significantly coherent with the equatorial zonal winds in the central Indian Ocean, suggesting that these events are well coupled. During the periods when there seems to be some relationship between the equatorial zonal winds in the central Indian Ocean and ENSO index, no significant coherence is seen between the Indian Ocean Dipole Mode Index and the equatorial zonal winds in the central Indian Ocean, except after 1995, suggesting that most of the IOD events are not related to ENSO.
1 0 0 0 OA 大洗磯浜海岸の侵食と大洗水族館の護岸空洞化
- 著者
- 宇多 高明 松浦 健郎 大崎 康弘 大木 康弘 三波 俊郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.I_643-I_648, 2016 (Released:2016-11-15)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2 2
茨城県の大洗磯浜海岸にある大洗水族館前には,1961年頃までは幅130 mもの砂浜が広がっていたが,急速に侵食が進み,護岸が波に曝される状態となった.2015年10月には階段護岸の空洞化が始まって陥没の危険性が高まり,2015年11月18日には階段護岸を強制的に崩落させねばならない事態となった.本研究では,最終的に破壊に至った大洗水族館の護岸を実例として,護岸の被災原因について考察した.空中写真とWorldView-2衛星画像を用いて大洗磯浜海岸の長期的な汀線後退状況を把握した上で,数回の現地踏査とドローンによる低空(150 m)からの空中写真撮影により護岸の被災原因について考察した.
1 0 0 0 OA 機能回復型凍結抑制舗装の開発と効果
- 著者
- 小島 逸平 佐沢 昌樹
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 舗装工学論文集 (ISSN:18848176)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.39-46, 2001 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 9
特殊な高吸水性ポリマーを舗装体に固定することによって、凍結防止剤を舗装体内に貯留でき、この貯留した凍結防止剤が滲み出てることによって路面凍結を抑制し、凍結防止剤が次第に流出して凍結抑制機能が低下した時には、凍結防止剤を路面に再散布することによって、再び凍結抑制機能を回復することができる、機能回復型凍結抑制舗装を、平成10年から実路に適用してきた。本報告は、その特徴と3年間の追跡調査から判ってきた効果や問題点と、更に改良技術について報告する。
1 0 0 0 OA T波の多様な形状
- 著者
- 村田 広茂 清水 渉
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.170-175, 2023-10-31 (Released:2023-11-03)
- 参考文献数
- 6
心電図のT波は,P波―QRS波に続く第三の主要な波であり,心臓の電気的興奮からの回復(再分極)過程を表す波形である.T波を評価する際には,まず正常なT波の極性や振幅の基準値を理解しておく必要がある.次に,異常T波の形状を大まかに3パターンに分けて,つまり,高いT波,平低T波,陰性T波と,それぞれ心電図診断をする.さらに,二相性,二峰性(ノッチ型)などの幅の形態変化を考慮して,それぞれ特徴的な病態や疾患との関わりを理解し,鑑別診断することが大切である.高いT波として重要なのは,高カリウム血症に特徴的なテント状T波と,心筋梗塞超急性期のみに出現する超急性期T波(Hyper acute T wave)である.陰性T波のうち虚血性心疾患に関与するものが重要であり,心筋梗塞の亜急性期から再灌流後に出現する冠性T波(Coronary T wave),一過性の心筋虚血を反映し重度冠動脈疾患を示唆する陰性もしくは二相性T波(Wellens症候群)などがある.心肥大を示唆する,ストレイン型ST-T変化や心尖部肥大型心筋症などに見られる巨大陰性T波(Giant negative T wave)など,各疾患に特徴的なT波も報告されている.また,先天性QT延長症候群の遺伝子型ごとに特徴的なT波や,Brugada症候群のJ点(ST)上昇から引き続く陰性T波など,診断に直結する重要なT波もある.このように,正常なT波の形状とその成因を理解したうえで,臨床上重要な病態・疾患を中心にT波の異常との関係を総合的に理解することが重要である.
1 0 0 0 OA 5. 各論 3) Wide QRS頻拍の鑑別診断と治療
- 著者
- 西崎 光弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.2, pp.305-313, 2006-02-10 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
Wide QRS頻拍は心室頻拍の頻度が高いため, 機序が上室性か心室性によるものか, 早急に鑑別診断することが治療上, 極めて重要である. 心室頻拍と変行伝導を伴った上室頻拍は (1) 房室解離 (2) QRS幅 (3) QRS電気軸 (4) 頻拍中のQRS波形 (5) 洞調律時心電図 (6) 基礎心疾患を指標として鑑別され, 特に, 頻拍中のQRS波形はV1, V6誘導の波形に注目する必要がある. 治療は両者の鑑別と基礎心疾患や心機能の程度によって決定される.
1 0 0 0 OA COVID-19感染流行下における起立性調節障害患者の問題点と当院での取り組み
- 著者
- 大川 優子 安部 義一 鈴木 正義
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.22-30, 2022 (Released:2022-06-23)
- 参考文献数
- 6
起立性調節障害(OD:orthostatic dysregulation)は,自律神経系による循環調節不全が主要原因であり,心身症としての側面も強く不登校を伴うこともある。今回我々は,心身症としてのOD診断チェックリスト陽性OD患者のうち,不登校の原因とコロナ禍での問題点を調査した。期間は2020年4月1日から2021年10月31日に当院小児科外来を受診したOD患者67例を検討した。対象は平均年齢13.7±2.4歳,男20例:女47例であった。ODの各サブタイプの内訳は体位性頻脈症候群43例,遷延性起立性低血圧15例,起立直後性低血圧1例,起立直後性低血圧を伴う血管迷走神経性失神1例,他に従来の診断基準で陽性が7例あった。患者67例のうち,心身症としてのチェックリスト陽性が37例,不登校が22例であった。COVID-19(Coronavirus disease 2019)流行に伴い子供達の生活環境も一変し,変化に適応出来ず不登校になった症例や,体調不良を訴えると感染を疑われ,保健室で休養出来ず早退させられた症例もあった。また外出自粛による生活リズムの乱れや,運動不足も症状悪化の原因と考えられた。当院では自律神経調節機構の病態の説明や生活指導を患者本人や家族へ行ない,不登校の期間や心身状態の程度に応じて環境調整など学校と連携を取り,他医療機関の精神科と連携し心理療法を行なった。コロナ禍におけるOD患者を診察する上での問題点を考察した。
1 0 0 0 OA フィールドのリアル社会学 ―福島原発事故とふるさと剥奪―
- 著者
- 関 礼子
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.70-82, 2020 (Released:2021-05-29)
- 参考文献数
- 15
福島原発事故による避難者が「ふるさと」に帰還しはじめた。社会学はこの状況をどのように捉えるのだろうか。本稿は、避難者が帰還しても戻らない「ふるさと剥奪」被害を論じる。「ふるさと」とは、人と自然がかかわり、人と人とがつながり、それらが持続的である場所のことである。だが、帰還後も人々は「ふるさと」を奪われたままで、復興事業はショック・ドクトリンをもたらすばかりである。本稿は、福島県の中山間地の集落を例に、避難を終えても終わらない被害を共同性の解体という点から捉え、「ふるさと剥奪」の不可逆な被害を論じたい。
1 0 0 0 OA ホームレスの健康調査とアルコール問題 文献検討
- 著者
- 松井 達也
- 出版者
- 学校法人 天満学園 太成学院大学
- 雑誌
- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.127-136, 2013 (Released:2017-05-10)
本研究の目的は近年の国内におけるホームレスの健康調査とアルコール問題に関する文献検討を行い,その現状を明らかにすることである。ホームレスに関連する調査資料を含む国内文献31編の文献検討を行った結果,全国調査10編,大阪市内の調査9編,他の地域の調査6編,支援報告6編であった。ホームレスの全国調査において路上生活者はこの10年間で1万5千人ほど減少している一方で,路上生活を脱した,脱ホームレスのうち精神障がいの疑いがある者15.2%,アルコール依存症の疑いがある者14.1%となっており,孤立を解消するための伴走型の支援が求められていた。大阪のあいりん地区や東京の山谷地区では高齢化が進み,ほぼ全員が単身男性,家族との関係が絶縁または希薄,若年発症と思われる人が多く,生活障害が顕著であるため,服薬や金銭管理などきめ細やかな関わりが求められていた。アルコール症患者に対しては毎日の生活リズムを重視したハードな治療プログラムが必要であったが,治療導入においては信頼関係をいかに築くかが重要であり,受容的に人間としての患者の尊厳に気を配ることが何よりも大切であった。
- 著者
- Akio MATSUMOTO Yasuo NONAKA
- 出版者
- JAPAN SECTION OF THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION INTERNATIONAL
- 雑誌
- 地域学研究 (ISSN:02876256)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.1-16, 2005 (Released:2007-06-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 1
This study investigates an economic implication of chaotic fluctuations that are observed in a nonlinear economic dynamic model. To this end, it constructs a nonlinear discrete time Cournot duopoly model in which firms have U-shaped or inverted U-shaped reaction functions due to production externality and shows that chaotic output fluctuations can arise for strong nonlinearities. Two main results of this study are: (i) it is theoretically as well as numerically confirmed that one of the duopolists can benefit in the sense that the long-run average profit taken along a chaotic trajectory is higher than the profit taken at an equilibrium point while the other is disadvantaged if both duopolists are homogeneous; (ii) it is verified with numerical simulations that both duopolists can benefit from chaotic trajectories if they are heterogenous.
1 0 0 0 OA 道なき道を彷徨う覚悟
- 著者
- 鹿野 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.75-78, 2022-07-15 (Released:2022-08-15)
- 参考文献数
- 25
1.はじめに教えるとは 希望を語ること学ぶとは 誠実を胸にきざむことという言葉は,フランスの詩人ルイ・アラゴン「ストラスブール大学の歌」1)の一節である.私は