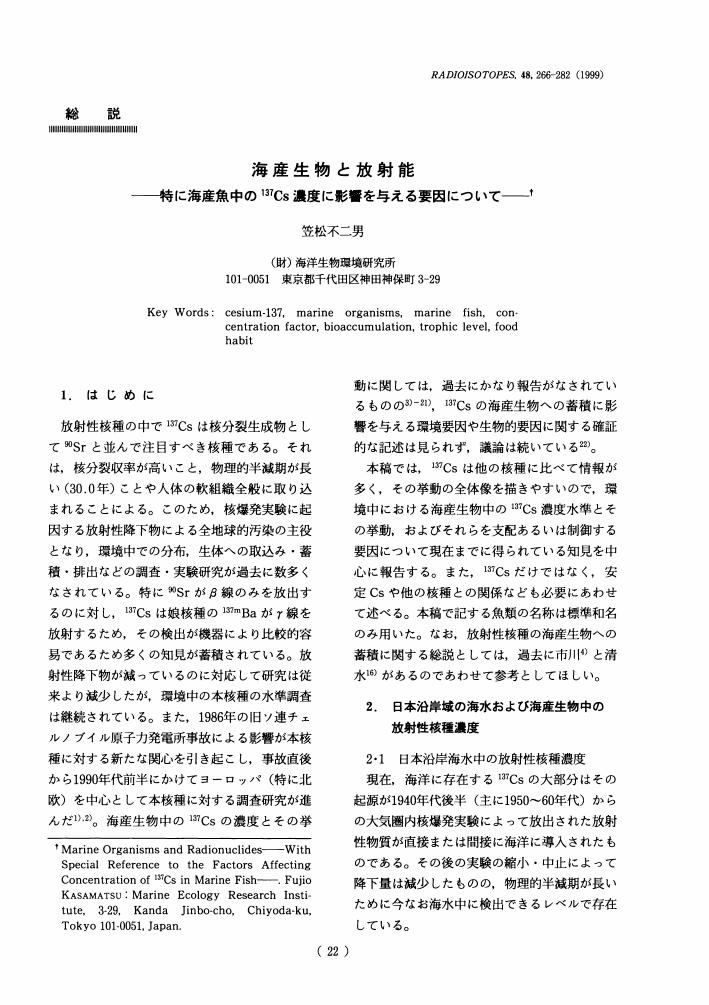36 0 0 0 OA 軽微な事故で横転する軽ハイトワゴンの危険性
- 著者
- 本宮 嘉弘 高塚 尚和
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.34-41, 2018 (Released:2019-03-28)
- 参考文献数
- 6
わが国では近年、軽ハイトワゴンと呼ばれる車高の高い軽乗用車が流行しているが、このような車種は重心が高いため、交差点等で低速度で衝突しただけでも容易に横転する。車両が横転した場合、乗員が車室内に強く二次衝突したり、割れた窓部から車外放出されるなどして死傷することが多い。筆者らが実際に調査した横転死亡事故をもとに、実車を用いた衝突実験やコンピューターシミュレーション解析により事故時に軽ハイトワゴンが横転するメカニズムを解明した。その結果、横転には衝突後のヨー回転速度やローリング共振周波数等が影響することが判明し、さらに走行速度が低いほど横転し易い可能性も示された。このため、軽ハイトワゴンが横転し易い車両であることを周知させるとともに、横転に備えてカーテンシールドエアバッグの装着を義務付ける等の方策が必要であろう。
36 0 0 0 OA 子どもの急変に先立つ過程における看護師の経験
- 著者
- 海老名 泉紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.340-348, 2020 (Released:2021-01-22)
- 参考文献数
- 18
目的:子どもが急変を起こす以前に看護師がどのような経験をしているのか,一連の過程を把握すること.方法:子どもの急変経験がある看護師9名に非構造化面接調査を行い,グラウンデッド・セオリーを用いて分析した.結果:看護師は何が起こるかわからない《不確かな状況》において,危機を回避するために《子どもの声を届ける》という過程がある一方,回避するための思うような対応が得られず《引っかかりを残す》という,異なる帰結に至る過程が把握された.これら帰結を導くプロセスは,《アンテナを張る》《何かが起こる予感》《医師との共有化のハードル》《声にならない声を届ける使命感》《周囲を巻き込む》で構成され,子どもの状態を医師と共有できるかが道筋を分ける分岐点となった.結論:子どもの急変においてはこの共有化のハードルをいかに下げ,一人の看護師の感覚を医療チーム全体の問題意識にしていくことの重要性が示唆された.
36 0 0 0 OA 顎変形症の標準手術 - Le Fort I 型骨切り術-
- 著者
- 中嶋 正博
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8, pp.473-479, 2012-08-20 (Released:2014-11-14)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 4
Othognathic surgery for jaw deformities are most frequently performed in Japan. Regarding those procedures, Le Fort I osteotomy and anterior maxillary alveolar osteotomy in the maxilla, and sagittal split ramus osteotomy, intraoral vertical ramus osteotomy, anterior mandibular alveolar osteotomy, and genioplasty in the mandibule are selected singly or combined based on cases. Among these orthgnathic surgeries, Le Fort I osteotomy is a typical surgical procedure, as well as sagittal split ramus osteotomy. Although the designing of osteotomy lines in Le Fort I osteotomy is simple, this surgical procedure is apt to be regarded as difficult, due to other risk factors in comparison with mandibular osteotomy, such as difficulty in the repositioning of bone segment, complexity of the maxillary bone structure, bleeding, surgical invasion of the nasal cavity and paranasal sinus, and postoperative changes in the nasal base morphology. However, regarding surgical treatment for jaw deformities, Le Fort I osteotomy is considered to be a surgical procedure which we should master, as well as sagittal split ramus osteotomy.Basically, orthognathic surgeries involve subperiosteal surgical manipulation, and it is simply summarized that Le Fort I osteotomy should also be carefully performed without injuring the periosteum. In order to achieve this, it is necessary to accumulate experience, sufficiently understanding the basic factors to safely perform Le Fort I osteotomy. This manuscript outlines the major points in the surgical procedure of Le Fort I osteotomy.
36 0 0 0 OA 異投射・虚投射の発生と共有: 腐女子の妄想と二次創作を通じて
- 著者
- 久保(川合) 南海子
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.40-51, 2019-03-01 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 44
Humans have repeatedly reproduced original stories by interpreting them via new works of art (novels and paintings) through the ages. The motivation behind such reproductions seem to be related to “misprojection” and “fictional projection”. According to Suzuki (2016), who used the term “projection science,” misprojection refers to situations in which internal representations of the real world are projected onto a wrong target, like in a ventriloquism effect, whereas fictional projection refers to situations in which internal representations are projected onto something in the real world despite the absence of actual visual input (e.g., ghost). Women who create fan fiction in which an existing story of friendship or rivalry between two men is changed into a love story between men, and who prefer love stories about homosexual men (referred to in Japanese as “Fujoshi”) are considered to be converting the original work into a reproduction through misprojection and fictional projection. We discuss the similarities between fan fictions by Fujoshi and academic activities, because both fan fictions and scientific hypotheses describe things that do not exist in reality, yet are shared by many people if they are convincing enough. Products of misprojection and fictional projection shared by the community are overwritten and more refined. Previous literatures on “projection science” have focused on each individual, and barely address the dynamics of sharing and the propagation of new works reproduced through misprojection and fictional projection. This review paper analyzes the sharing of misprojection and fictional projection common to art, religion, and academic activities, and proposes that the sharing of those projections is an important function related to various human cognitive activities.
36 0 0 0 OA アイヌの定住期間からみた集団の空間的流動性— 1856∼1869年の東蝦夷地三石場所を例に —
- 著者
- 遠藤 匡俊
- 出版者
- 東北地理学会
- 雑誌
- 季刊地理学 (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.19-37, 2009 (Released:2011-12-08)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 2 1
集団の空間的流動性は,おもに移動性の高い狩猟採集社会で確認されてきたが,移動性の程度と集団の空間的流動性の程度の関係が必ずしも明確ではなかった。本研究では,定住性が高いアイヌを事例に,定住性の程度と流動性の程度の関係を分析した。1856∼1869年の東蝦夷地三石場所におけるアイヌの27集落を対象として集落の存続期間を求めた結果,最低1年間,最高14年間,平均4.4年間であった。全期間中に消滅した集落は18,新たに形成された集落は14,そして14年間ずっと存続し続けた集落は3であった。分裂の流動性が高い集落(S<0.82)および結合の流動性が高い集落(J<0.79)は,いずれも集落の存続期間の長さには関わりなく多くみられた。このように,集落の空間的流動性の程度は集落の存続期間の長さとは関係しなかった。消滅した集落の分裂の流動性は存続し続けた集落よりも低く,新たに形成された集落の結合の流動性も存続し続けた集落よりも流動性が高いという傾向はとくに認められなかった。この結果は,アイヌのように移動性の低い狩猟採集社会だけでなく,移動性の高い狩猟採集社会においても,移動性の程度と流動性の程度はあまり関係がなかったことを示唆する。
36 0 0 0 OA 学童の食事中における会話の有無と健康及び食生活との関連
- 著者
- 岸田 典子 上村 芳枝
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.23-30, 1993 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 9 8
学童376人に, 食事中の家族との会話の有無 (以下, “有り”を会話群, “無し”を非会話群とする) と健康・生活の規則性・食生活との関連について, 質問紙法により調査を行い, 次のような結果が得られた。1) 健康についてみると, 会話群は非会話群に比べ, 食欲がある, 朝の目覚め良好, だるいことはない, 夜よく眠れる, 風邪をひきにくい, イライラしない, 非常に健康なほう, 健康良好, 起立性調節障害症状無しなどの割合が高く, 食事中の家族との会話と健康との関連がみられた。2) 生活の規則性に関して, 起床・就寝・排便・間食時刻などが規則的で, 朝食を毎日食べる, 運動を毎日するなど, いずれも会話群のほうに割合が高かった。3) 食生活では, 料理や6つの基礎食品群の組み合わせがよい, 野菜をよく食べる, 給食外で牛乳を飲む, 食べ物の好き嫌いがない, 間食量を決めている, 清涼飲料水を飲まないなどについて, 会話群のほうに割合が高かった。
36 0 0 0 OA 戸田格子の誕生(<小特集>戸田盛和―その物理と人間の魅力―)
- 著者
- 和達 三樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.688-691, 2011-09-05 (Released:2019-10-22)
- 参考文献数
- 13
戸田盛和教授(東京教育大学名誉教授)の業績を振り返る.特に,1次元非線形格子力学の研究において,どのように指数関数形ポテンシャルが導入されたか,を原論文に基づいて説明する.指数関数ポテンシャルで結ばれた1次元格子は,現在「戸田格子」とよばれている.戸田格子の発見はソリトン概念の確立に寄与し,また,ソリトン理論を発展させた.我国の基礎科学研究が世界に誇る大きな業績の一例である.
36 0 0 0 OA 二酸化炭素と人体
- 著者
- 高橋 正好
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.352-357, 1998-10-15 (Released:2017-04-30)
二酸化炭素は人体において代謝活動の結果生産される物質であり,また酸塩基平衡の維持などの重要な役割を担っている.しかし,過剰に存在した場合にはさまざまな悪影響を及ぼす.本資料においては,人体内における二酸化炭素の役割や,危険性などについて整理した.
36 0 0 0 OA 海産生物と放射能 ―特に海産魚中の137Cs濃度に影響を与える要因について―
- 著者
- 笠松 不二男
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.266-282, 1999-04-15 (Released:2011-03-10)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 32
36 0 0 0 OA 2017年度時限研究会「脳の理論から身体・世界へ:行動と認識への再挑戦」実施報告
36 0 0 0 OA ブラジャーの官能評価に基づく判定者の類型化 ―若年女子について―
- 著者
- 岡部 和代 黒川 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11, pp.743-751, 2006 (Released:2007-10-12)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
ブラジャーは女子の肌に密着するファンデーションとして, 消費者の感性的ニーズをデザインに反映させる必要がある. 消費者の好みや感性をデザインに活かすには, 評価した人の特性を評価し, 類型化することが必要となる.そこで, 本研究では日本人若年女子193名にタイプの異なるブラジャー5種を対象として官能評価を行わせ, ブラジャーの特性を明らかにした上で, 判定者の類型化を行った. ブラジャーに共通した因子として, ズレ感, 揺れ感, 圧迫感, 整容感, 背面・脇押え感を抽出した. 特にズレ感や揺れ感の因子は寄与率が高く, また総合的な着心地との相関が高かった. タイプ別に導出した判定者の因子スコアを原データとしてクラスタ分析を行い, 判定者を4クラスタにパターン分類した. クラスタごとに官能評価結果を分析することにより, 評価の深層を浮かび上がらせることが可能になるということが示唆された. さらに評価結果は, 判定者がブラジャーについてどのような感覚が強いか, ひいてはブラジャーに何を要求しているかを表すものと考えることができる. 判定者が多ければ, 判定者のクラスタはそのまま消費者のクラスタと考えられ, 官能評価分析の結果をニーズに基づく商品設計に応用できるはずである. しかし, 官能評価の判定者の反応が多様であることから, 官能評価の方法や商品設計について考えさせられる点が多かった. 本研究では4クラスタに分類したが, ほとんどの項目に中間の評価をするクラスタ1の判定者が多く含まれる官能評価では明瞭な結果が得られない可能性が高くなるし, クラスタ2とクラスタ3のように反応差が大きい判定者が混じっている場合も平均化されて曖昧な結果に終わることが考えられる. 消費者の感性を商品に反映し, 質の向上を図るためにはクラスタごとに官能評価結果を分析して深層を浮かび上がらせることの重要性が示唆された.
- 著者
- Ryuichiro Hayashi Shigeki Yamaguchi
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.2339-23, (Released:2023-08-02)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
A 33-year-old woman developed paresthesia in her right thumb approximately 30 minutes after receiving the BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccine. The paresthesia gradually spread to her right-side limbs and trunk, and cervical magnetic resonance imaging (MRI) revealed a localized lesion in the right dorsal column. After glucocorticoid therapy, her symptoms and MRI findings improved. Although disease developing less than 24 h after vaccination is considered an unlikely cause of immuno-associated adverse events following vaccination, we discuss the possible mechanisms involved in early-onset central nervous system inflammation after vaccination in view of preexisting immunopathological susceptibility.
36 0 0 0 OA 爬虫類の分類学・系統学・生物地理学―分岐分類学の問題点
- 著者
- 疋田 努
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.1-9, 2019-08-31 (Released:2019-09-12)
- 参考文献数
- 30
In the studies of reptiles, I started the study of phylogeny and biogeography of the scincid genus, Plestiodon (formerly Eumeces) in the East Asian Islands by cladistic analysis and neighbor joining method based on morphological data. Then our laboratory has continued to study this group genetically using allozymes and DNA data. We revealed the process of the speciation of the genus in Japanese and Ryukyu Archipelagos. During the studying this group, we described five cryptic species. While studying the taxonomy and phylogeny of reptiles, I found that the cladistic taxonomy has several problems. I proposed the gradistic classification system showing cladistic relationship by putting a tag of the descendant grade within the ancestral grade.
36 0 0 0 OA 政治的態度の母集団分布の形状を推定する: 統計モデリングアプローチ
- 著者
- 清水 裕士 稲増 一憲
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.113-130, 2019 (Released:2020-06-25)
- 参考文献数
- 37
本研究の目的は,保守‐革新についての政治的態度の母集団分布の形状を推定することである.これまで単項目の政治的イデオロギー尺度によって分布の形状が分析されてきたが,回答の難しさと反応バイアスの影響を強く受けることが指摘されてきた.そこで本研究ではSGEDを態度の事前分布とした一般化段階展開法による項目反応モデルを用いて,反応バイアスを補正する統計モデリングを活用し,母集団分布の形状を推定した.また同時に,政治的知識の程度によって形状がどのように変わるのかを検討した.分析の結果,反応バイアスを除去する前の分布はラプラス分布に似た中に収斂した分布となり,バイアスを補正したのちには正規分布に近づいたが,依然尖度が高い分布となった.また政治的態度による違いが大きく,政治的知識が少ない回答者の分布は中に収斂する一方,多い回答者の分散が大きく,正規分布に比べて尖度が小さい一様分布に近い分布となった.このことから,政治的知識の程度に応じて,周りから受ける影響が異なる態度形成メカニズムが推論できる.
36 0 0 0 OA ゲージ理論を行列模型を用いて調べる――ラージN 極限への挑戦
- 著者
- 大川 正典
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.264-273, 2020-05-05 (Released:2020-10-14)
- 参考文献数
- 16
素粒子の標準モデルは,その基礎をゲージ理論においている.実際,電磁相互作用を媒介する光子はU(1)ゲージ理論により記述されており,また強い相互作用を作り出すグルーオンはSU(3)ゲージ理論に支配されている.光子は電荷を持たないので自己相互作用をしないが,グルーオンは自分自身で電荷(色電荷と呼ばれる)を持ち自己相互作用をし,その結果として強い力が作り出される.両者の違いは数学的には,U(1)群が可換なのに対して,SU(3)群が非可換であることからくる.一般にSU(N)非可換ゲージ理論は非常に複雑な構造を持っているが,1974年,’t HooftはSU(N)群の次元Nを大きくした時,摂動論の各次数でプラナーダイアグラムと呼ばれる特定のダイアグラムからの寄与しかなく,理論が簡単になることを発見した.ただし強い力が作り出されるのは非摂動論的効果であり,相互作用の大きさのべき展開で定義される摂動論では解析できない.非摂動論的効果の研究をするには,時空を離散化し4次元格子上に理論を定義し,自由度を有限にして数値シミュレーションを行うのが常套手段である.しかしNが大きいとき,SU(N)ゲージ理論を格子上で調べるのは現実的ではない.その理由は以下の通りである.一辺がLの4次元正方格子を考える.各格子点には4つのSU(N)行列を置くので,全体の自由度は4(N 2-1)L4となる.スーパーコンピューターで計算可能な自由度の数には限界があり,例えばL=30とすると,Nが10を大きく超える計算はできない.1982年江口と川合は,Nを無限にしたとき格子上で定義されたSU(N)ゲージ理論は,4つのSU(N)行列のみを持つ行列模型(江口・川合モデル,EKモデル)と等価である可能性を示した.以下で,Nを大きくとる極限をラージN極限と呼ぶ.EKモデルの自由度は4(N 2-1)なので,数値シミュレーションでNは数千の値を持つことができ,実質的にラージN極限が取れてしまう.残念ながら,EK模型は非摂動論的研究に重要な中間結合領域で破綻してしまう.この欠点を解決するために種々の改良が試みられ,2010年最終的に,González-Arroyoと筆者は,理論にある種のツイスト境界条件を課すことにより,中間結合領域でも有効な行列模型(TEKモデル)を構築した.現在ではTEKモデルを用いて,SU(N)ゲージ理論のラージN極限でのクォーク間ポテンシャルや中間子質量が非摂動論的に計算されている.近年,アジョイント表現に属するスカラー場やフェルミオン場を伴ったSU(N)ゲージ理論が大きな関心を呼んでいる.その理由のひとつに,AdS/CFT対応がある.これによると,Anti de Sitter時空を背景に持つ超重力理論と,ラージN極限でのゲージ理論との間に対応がある.SU(N)群のアジョイント表現にあるスカラー場やフェルミオン場のラージN理論も,行列模型を用いて調べることができる.行列模型による非摂動論的効果の研究は始まったばかりであり,今後の発展が強く望まれる分野である.
36 0 0 0 OA 日本占領をジェンダー視点で問い直す ──日米合作の性政策と女性の分断──
- 著者
- 平井 和子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.5-16, 2014-10-20 (Released:2015-12-29)
- 参考文献数
- 4
2001 年の「9.11 事件」に端を発する、対イラク戦争開始に当たって、ジョージ・W・ブッシュ大統領は、過去の数ある占領の中から、民主化の成功例として「日本モデル」を取り出して、占領を正当化しようとした。攻撃に際しては、「女性解放のため」という理由が付け加えられた。これを、わたしは日本の女性史研究が大きく問われていると受け止めた。アメリカによる日本占領をひとたび、敗者‐勝者の男性間で取引された女性たち(占領軍兵士へ「慰安」の提供をさせられた売春女性たち)の体験から見直せば、軍事占領と女性解放を安直につなげることの矛盾は明らかである。具体的にいえば、敗戦直後、日本政府によってつくられたRAA(Recreation and Amusement Association)などの占領軍「慰安所」や、冷戦期に激化した基地売春下で、女性たちが強いられた性管理の実態は、日米合作による軍隊維持のための組織的性暴力であった。さらに、売春禁止運動を担った廃娼運動家や女性国会議員・地域婦人会の女性たちと、売春女性たちの間には大きな分断があり、これが米兵の買春行為と矛盾しない売春防止法を生み出す要因の一つとなった。つまり、二分化された女性たちの対立と反目が、結果として軍事化(日米安保体制・軍事基地)を支えることにつながった。ここに、女性を、「護られる女性=『良家の子女』」と、売春女性(「転落女性」「特殊婦人」)に二分化する男性中心的な「策略」の罠がある。米兵の買春行為の激しさは、朝鮮戦争勃発とリンクする。そのため、軍事組織は売春女性を「活用」して、兵士の性をこそコントロールする必要があったのである。
36 0 0 0 OA “頭の良い人”の概念
- 著者
- 東 洋 柏木 恵子
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- Japanese Psychological Research (ISSN:00215368)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.17-26, 1987-02-25 (Released:2009-02-24)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 65
The purpose of this study was to examine the concept of intelligence among Japanese. Male and female college students, and mothers of female students were asked to think of an intelligent person, and to rate each of 67 descriptors according to whether it fits that person or not. It was found out that some of the descriptors were highly general regardless of the background of the person to be described, and that some were specific to the sex and other backgrounds of the person. As compared to the results of studies in the U.S., descriptors related to the receptive social competence tended to be associated with high intelligence, especially when the person to be described was a woman. The factor structure found in Japanese subjects which showed the predominant factor of social competence differed from that for Americans reported by Sternberg. Sex stereotyping in the concept of intelligence was also observed: Descriptors for a female target, compared those of a male target, were distributed more heavily in the domain of social competence and the reading and writing. Sex-role differentiation in concept was more pronounced in the responses of male students as compared to those of female subjects.
- 著者
- 岩橋 清美 北井 礼三郎 玉澤 春史
- 出版者
- 兵庫県立大学自然・環境科学研究所天文科学センター
- 雑誌
- Stars and Galaxies (ISSN:2434270X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.7, 2022 (Released:2023-02-10)
- 参考文献数
- 24
安政五(1858)年に出現したドナティ彗星は、我が国では京都土御門家、江戸幕府天文方および大坂間家 において観測され、その観測記録が残されている。これらの史料は、いずれも西洋天文学に基づく観測記 録であり、高度・方位が数値として記されている。管見の限りでは、19世紀前半の彗星観測記録において、 京都土御門家・江戸幕府天文方・大坂間家の記録がそろっている事例はドナティ彗星のみである。これらの 観測記録から、彗星の日々の赤経・赤緯値を導出して、観測精度の相互比較を行った結果、(1)西欧の近代 的な観測精度に比して我が国観測所の観測精度は一段落ちるものの、(2)彗星の軌道を赤道座標値で±2度 の精度ではあるが、軌道の全貌を概ね把握できていたこと、(3)3観測所の中では土御門観測が一番優れて いたこと、(4)天文方、間の観測は期間が短く断定は難しいが、観測値にオフセットがあることが分った。 また、三観測所での測量の比較から、測量の基本的な考え方は相互に共通しており、時刻測定の方法 も共通の機器が使われているので、天体位置測量の精度の違いは、儀器の設置精度および堅牢性、眼視観 測者の熟練度によるところが大きいという結論を得た。
36 0 0 0 OA ドイツ・ミュンヘン市域における保育施設の音環境設計に関する視察調査
- 著者
- 川井 敬二 佐藤 将之 野口 紗生 船場 ひさお
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.58, pp.1083-1086, 2018-10-20 (Released:2018-10-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 1
This report describes the results of site inspection of child daycare facilities and interview with the related persons regarding with acoustic design, which were carried out in Munich city region, Germany, where regulations of acoustic design for daycare facilities exist. The purpose of this attempt is to find the situation of acoustic design in daycare facilities in contrast to those in Japan without any standards or regulations. The result revealed that all the rooms in the inspected facilities were equipped with sound absorptive material and personnel were more or less aware of the benefit of good acoustics.
36 0 0 0 OA p値を使って学術論文を書くのは止めよう
- 著者
- 豊田 秀樹
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.379-390, 2017 (Released:2019-03-22)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
A p-value can be simply defined as the probability that under a specified statistical model a statistical summary of the data (e.g., the mean difference between two groups) would be equal to or more extreme than its observed value. p-values do not measure the probability that the studied hypothesis was true, or the probability that the data were produced by random chance alone (Wasserstein & Lazar, 2016). What researchers usually want is p(HjD), the probability that a research hypothesis was true, given the data. Three examples were shown that analyzed using the probability that a hypothesis was true, instead of p-values. A peer-reviewed policy using a new standard for publishing useful papers for society was proposed.